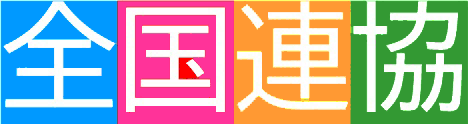改訂 テキスト学童保育指導員の仕事【増補版】
 在庫
在庫
『テキスト学童保育指導員の仕事』は1999年の発刊以降、何回か改訂を行ってきました。今回、安全対策や危機管理の充実を求める声が高まっていること、各地で地震や風水害などの自然災害が起きていることをふまえてまとめた『学童保育の安全対策・危機管理~「安全対策・危機管理の指針」づくりの手引き~』と、「学童保育指導員の倫理綱領(案)」を収録しました。ぜひ、日々の学びにご活用ください。
- A4判220頁 頒価1000円(税込み)
- 一般書店では取り扱っておりません。ご購入は、直接、全国学童保育連絡協議会へお申し込みください。
はじめに
第1課 学童保育の目的と役割
1.働く保護者の願いと学童保育の役割
- (1)働く保護者の願いと学童保育の役割
- (2)学童保育の対象としている「放課後」とは
- (3)学童保育の対象となる子ども
2.学童保育の基本
- (1)子どもの人権を守る
- (2)子どもとしての権利を守る
- (3)安全・安心な生活を保障する
- (4)生活を保障することを通して成長・発達を促す
- (5)保護者と指導員が共に子育てをする
3.指導員の役割と仕事
4.学童保育の歴史・制度の変遷と内容
- (1)学童保育の始まり
- (2)法制化された学童保育
- (3)「子ども・子育て支援新制度」と学童保育
第2課 子ども理解と働きかけの基本的な視点
1.子どもの人権・権利について
2.学童期の子どもの発達と生活
- (1)学童期の子どもの成長と発達の特徴
- (2)学童保育の子どもたちは
- (3)子どもの心と身体の健康
3.個別の支援を必要とする子ども
- (1)障害のある子どもたち
- (2)個別の支援を必要とする子ども
第3課 生活づくりとは何か
1.学童保育の生活づくりの特徴
- (1)「生活の場」である学童保育
- (2)生活づくりとは何か
- (3)学童保育の生活の特徴
- (4)一日の生活の見通しと流れ
- (5)長期休みの生活
2.指導員の意図的な働きかけ
- (1)子どもを理解する視点
- (2)意図的な働きかけとその留意点
- (3)高学年の子どもたちの生活づくり
- (4)障害のある子どもを含めた生活づくり
- (5)個別の支援を必要とする子どもへの対応
第4課 学童保育の生活で保障すべき内容
1.子どもの安定した生活
2.遊びを主とした日常の生活と行事・活動
- (1)遊びを主とした日常の生活
- (2)行事や活動について
- (3)宿題と塾・習い事について
3.おやつ
4.施設外保育
- (1)日常の生活や行事としての施設外保育
- (2)学童保育からの外出
第5課 子どもの安定した生活の保障
1.「安全と健康を守る」という意味
2.安全を管理する
- (1)保育にあたって
- (2)施設の維持管理と環境整備
3.衛生管理
4.「健康」を管理する
- (1)子どもの健康状態を知る
- (2)アレルギーの対応
- (3)ケガ・病気の対応
5.安全対策・危機管理
- (1)子どもの安全対策・危機管理の基本
- (2)自然災害などへの対応
6.事故・保険
- (1)事故やケガの際の保護者への連絡やその後の対応
- (2)学童保育と保険
第6課 日々の実務の内容
1.出欠席の確認
2.保育の打ち合わせ
3.保育の記録
4.保護者との連携
5.学校・関係機関との連携
- (1)学校との必要に応じた連絡
- (2)地域の関係機関との連携
6.施設の整備・運営・管理
- (1)施設の維持管理と環境整備
- (2)業務にかかわる日誌、運営に関する記録
- (3)金銭管理 (おやつ代・傷害保険・賠償責任保険などの管理)
第7課 記録・保育計画・職員会議
1.子ども理解と記録
- (1)保育の記録
- (2)記録はなぜ必要か
- (3)日々の実践のなかからなにを記録するか、その方法は
2.保育計画と振り返り・まとめ
- (1)保育計画(見通し)の作成
- (2)振り返り・まとめ
3.日々の打ち合わせ・職員会議
第8課 保護者の子育てを支える
1.保護者に子どもの生活を伝える
- (1)保護者の子育てを励まし、共に育てる
- (2)保護者との信頼関係を築く
- (3)保護者と情報を共有する
- (4)保護者に子どもの生活の様子を伝えるための方法や工夫
2.父母会(保護者会)との連携を図る
- (1)父母会(保護者会)の必要性
- (2)父母会(保護者会)との連携
第9課 関係機関との連携
1.学校との連携
2.保育所および幼稚園などとの連携
3.地域、自治体との連絡・連携
- (1)地域との連絡
- (2)自治体(行政)との連携
4.福祉事務所・児童相談所など関係機関・施設との連携
5.児童虐待防止のための関係機関との対応
第10課 指導員の専門性を高めるために
1.指導員の専門性とは何か
- (1)指導員の仕事と求められる専門性
- (2)専門的な知識、技能について
- (3)指導員の仕事の公務性
- (4)専門性を高めることと労働条件の向上との関係
2.専任・常勤・複数体制の確立
- (1)専任体制はなぜ必要か
- (2)児童館併設や「放課後子ども総合プラン」内の学童保育の専任体制
- (3)常勤体制はなぜ必要か
- (4)常時複数体制はなぜ必要か
3.学習の必要性、方法、内容
- (1)学ぶことの必要性
- (2)学ぶべき内容
- (3)自主的な学習を活発に
- (4)研修に対する行政の責任と役割
4.実践記録および実践記録の検討
- (1)実践記録を書くこと
- (2)実践記録の検討
第11課 指導員に求められる職業倫理と職場の確立
1.指導員に求められる職業倫理
- (1)大切な役割を担っている指導員という仕事
- (2)求められる専門職としての職業意識
- (3)求められる専門職としての職業倫理
2.専門職としての指導員集団づくりとその確立
- (1)専門職としての指導員集団づくりをすすめるうえで大切にしたいこと
- (2)専門職としての指導員集団の確立
第12課 施設の運営管理・事業内容の向上
1.施設の運営管理・情報公開
2.労働環境整備
3.事業内容の向上、苦情への対応
4.学童保育をよりよくしていく
学童保育の安全対策・危機管理 ~「安全対策・危機管理の指針」づくりの手引き~(2018年5月改訂)
「学童保育指導員の倫理綱領(案)」の提案にあたって
[資料]
- ◇児童福祉法等の学童保育に関係する法規
- ◇提言「学童保育の保育指針(案)」2012年12月改訂 全国学童保育連絡協議会
- ◇提言「私たちが求める学童保育の設置・運営基準」2012年9月改訂 全国学童保育連絡協議会
- ◇放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)
- ◇放課後児童クラブ運営指針
- ◇放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修の項目・科目と研修時間数
- ◇学童保育数と国の補助金と施策の推移
- 「放課後児童クラブ運営指針」『テキスト学童保育指導員の仕事』対照表
- ◇全国学童保育連絡協議会の紹介