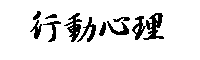
2016/12/18:renewal
/back/人間行動
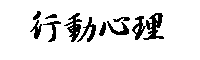 2016/12/18:renewal /back/人間行動 |
|
行動と責任 ◆人間とは何か 「人間」というと、われわれはいつも二つのことを考えます。その一つは、動物の一種として の人間であり、もう一つは考えることを主体とした人間です。 これは、簡単に「肉体と精神」とか、「体と心」というような言い方をしていますが、実 はこの二つはなかなか分けがたいものでして、更にこのような二元的に考えることに意味 があるかどうかさえ大きな疑問が残ります。 人間の感覚には各種の錯覚があることでよく知られています。たとえば、我々の日常の生 活の中でも思い違いということは決して少なくありません。 ある書類の中の大切な文句を確かに見たと思っていても、それが間違いであったりしま す。あるいはまた、その当時の情景がまざまざと目の前に見えるほど深い印象を持ってい る経験が、後からよく調べてみると、そんなことは全くあり得ないということがわかった りすることもあります。 これらは人間の記憶というものは年月がたつと少しずつ変わったり、他の記憶と混じり合 うという理由によることもありますが、実際にはほんのちょっと前のことでも思い違いし ていることはあるのです。
人はものを判断する場合に、自分の過去の経験からできたあるパターンにあわせてみよう
とする傾向が強いので、ともするとこのような錯覚に陥るのでしょう。 たとえば、図1を見てみると、この二本の線分は全く同じ長さなのに、一方は長く一方は 短く見えます。
さらに、本質的に考えると、人間が”知っている”と思っている外部の「世界」は、実は 感覚器を通して自分の意識の中につくられた世界にすぎないことがわかってきます。これ は「意識内容」といわれているものです。 そこで、この「意識内容」と「外界の真相」とは必ずしも一致しているとはいえないこと が認識できることになります。 たとえば、普通の人には赤外線や紫外線は見えないし、二万五千ヘルツ程度より高い音 は聞こえません。ところが、ある種の動物はこれらを関知できることが知られています。 もし、そのような感覚を持つ人間がいれば、その人の意識内容は普通の人と同じとは考え られません。 また、全く同じように色盲の人の意識内容は普通の人とのそれとは異なるでしょうし、ま た一時的に感覚器官に異常が生じたときは、その人の意識内容は変わってくるはずです。 要するに、われわれは、自分の周りのすべてのことに対し、完全に実在の真相を知ってい るとは信じられないことになります。このことを進めて考えると、すべては錯覚かもしれ ないことにもなります。
いまの自分というものは、他の本当の自分が見ている夢の中の自分なのかもしれないと極
言できないことでもありません。 そんなところまで延長して考える訳にはいきませんが、少なくとも自分が夢の中で他の人 間になったり、あるいは他の動物になっていろいろと迷ったり苦しんだりする夢を見るこ とは決してないことではないのです。 こう考えてくると、自分が知っていると思っている外界は、実はすべて自分の心の中にあ る意識内容にすぎないのです。そこで、真に存在するものは何かということを追求する と、絶対的に確かな存在をとらえることはなかなか困難になってくるでしょう。しかも、 人間の感覚は決して正確なものでないこともわかっているのです。 そうなると、我々が確かに見たと思っていたことが幻覚かもしれないし、あると思ってる ものが果たして真に存在するかどうか疑わしくなってきます。デカルトはこれに対し、 「我思う故に我あり」を出発点にしました。 つまり、こんなことを考えている「我」は少なくとも存在するということだけは確かであ ると考えたのでしょう。この場合の「我」とは、いうまでもなく肉体的な意味の人間では ありません。それは考えることの主体であって、むしろいわゆる「人格」あるいは「責任 主体としての人間」に近いものを意味しているのだと思います。 そこで、ここでは特にこのような人間つまり、デカルトのいう「我」、法律上の責任者と しての人間のことを「人間」ということにし、動物の一種である人間をさす場合には特に 説明をつけることにします。 つまり、ここでいうところの「人間」とは、動物の一種としての人間ではなく、社会に対 し、あるいは他の人々に対して自分の責任の下に行動する人間をさします。なお、この意 味での「人間」には、自分の行動を自分の自主的な考えで決定することができるのだとい う基本的な考えが裏付けとしてあることを指摘しておきます。 それは、つまり、社会に背く行動をしたり、他人に害を与えたりした場合には刑罰を受け る資格があることを意味します。
|
|
◆ 魂を持った責任者 ところで、デカルトの考えのような「我」、つまり人間は生まれてから死ぬまでの間色々変 わるかもしれませんが、一生を通して自覚し、心の中に画然として存在すると思われる「自 分」、世間一般から「何某」としていつも認められる「人格」は果たして何なんでしょうか。 これについての議論にはあまり深入りしないことにしますが、「我」と考えられるもの は、一口にいえば我々の肉体の持っている性質から生まれたものであることは確かです。 そのため、人生の途中で大きい精神障害にあった人、大脳に重大な傷を受けた人たちは事 実上全く変わった人格になってしまいます。つまり、魂論的にいえば、他の魂と入れ替 わったのだともいうような現象が起こります。 そこで考えられることは、魂というような別のものを考えないで、「我」という自覚は人 間の神経系の持つ性質の中で永続性の高いものの現れではないかということです。人間の 体の中で神経細胞のみは生まれてから死ぬまで一生変わらないし、その中のつながりもそ の形は死ぬまであまり変わらず、長く続いてくことはよく知られています。 そこで、人間における「我」とは、それぞれの神経系のパターンによる性質と考えたとこ ろで大きな矛盾はないようにも思えるのです。 そして、大脳などの中での一生の間にあまり変わらない性質の抽象されたものが、前述の 「人間」だと考えると、多くの人々が魂的なものを自分の中に自覚することはそう不思議 なことではありません。 つまり、人間は一生の間「我」があるという考えを持ち続けることは当然です。そういう わけで、人間に魂があるかどうかを論じないでも、魂を持つという考えは、その人間の生 きている間中だけについてのことならば何の差し支えもないことになります。 要するに、魂は少なくとも人間が生きている間は存在すると考えても支障はありません。 さらに進んで、この魂がその人間の社会の中での諸行動の真の指令社なのだと考えれば、 その魂を持つ人間こそ社会に対する責任の主体と考えて差は使えない(「我」を大脳の性 質としてもこの考え方はあまりおかしくありません)。こう考えて、ここでは人間を以上 のように魂を持った責任者として理解していくことにします。 この議論はいうまでもなく舌足らずでありますが、これのより深い説明は浅学のためお許 しを戴いて、ここではこの意味で人間を理解していくことにします。 こう考えると人間は自由意志を持ち、自分の行動を自分で決定でき、かつその結果につい ては責任を持つ魂を持っているものだということになります。しかしまた、それと同時に 逆に考えて、他人の命令に全く無考えで機械的に従う人間、無あるいは他人の行動や思想 をただ真似するだけの自主性のない人間は、真の意味での「人間」ではなく、魂のなく なった抜け殻的な人間なのだということがわかります。 自主性を中心に考えると、単に人真似や他人に追随する事だけで世に生きていくことな どは人間性の放棄です。それぞれの人がそれぞれの能力と責任に応じた創造性を発揮し、 自己独自のものを打ち出して、社会に貢献することこそ「人間」である証であるというこ とができます。
|
|
◆ 組織と個人の関わり つぎに、会社のような組織を考えるときに生ずる問題は、組織の一員であっても、人間は蜂 のような昆虫と違って自由意志を持っている点です。つまり、組織の中の人間は、単純に一つ の組織の中に組み込まれ、何の疑いもなくその組織の目的に奉仕することは不可能です。 組織の目的に奉仕し、組織の健康を維持しその成長発展を目指して、自分に与えられた役 割を推進するのは、ミツバチなら生まれながらに持っている本能です。つまり、それは遺 伝的に作りつけられたものです。しかし、人間は違います。人間の本能には、そんな融通 性のない、作りつけられる遺伝のようなものは、ほとんど見あたりません。 人間の行動は、前にも述べたように本能によってのみ起こるものでなく、むしろ後天的に 形成された、条件反射によって生じた二次本能の方が遙かに大きいものです。 成人した人がある何かが好きでしょうがないなどというときは、ほとんど多くの場合、生 まれてから後の何かの事件で作り上げられた条件反射によるものです。 しかしこれらは、生まれながらの本能のように自覚されていることが、実は多いのです。 しかも、それが多くの場合、過去に多くのにがい経験などによって歪められるので、直截 的には現れず、いろいろの屈折した形で現れるのがふつうです。極端な場合は、苦痛を喜 びとすることさえあることが知られています。 ですから、組織の中での自分の役割の理解、組織の目的への献身、あるいは奉仕などの組 織化としての筋の通った考えは、本能的あるいは二次本能的なものとして考えられませ ん。言葉を中心とした理性的なものとして捉えられなければならないのは当然です。 もちろん、この場合、理性的なものといっても、その奥の衝動力(モーティブ・フォー ス)としては、最終的に本能的要素とつながるものには違いありません。誰でも、いやで いやでしょうがないことをいつまでも続けようとはしないように、大好きなことをしない ですますこともなかなか難しいものです。 しかし、われわれは組織の中での役割の遂行を、単にむき出しの本能、あるいは二次本能 に、身を任せるんだと割り切ったのでは、社会生活ができず、社会の落伍者になり果てる に違いないことを知っています。 社会水準以上の社会生活をしていくためには、理性的判断とそれに従った行動が絶対に必 要なことはいうまでもないでしょう。 このように考えると、いままでに、できてしまった二次本能は、ある程度仕方がないとし ても、これから先については、条件反射を自分の理性的判断に沿うように、コントロール することが重要だということが理解されます。
これは、古くは修養とか克己とかいわれたことであり、自己啓発とか管理者訓練といわれ
るものです。これについては、すでにできあがってしまった二次本能を何とか直していこ
う、とする考えも含まれていることは非常に重要なことです。 |
|
|