
真冬の夜(マローズ)を越えるとき
〜はたはたVer.〜

真冬の夜(マローズ)を越えるとき
〜はたはたVer.〜
『‥‥戦乙女の涙は癒しの涙。
人を治す為に泣き続けて、私はもう泣けなくなった。
命を粗末にしすぎたから、大事な時に泣けなくなった。』
舞台から流れてくるのは、悲しき戦乙女の歌声。そして、次の瞬間。空間を切り裂き舞台上に大鎌を構えた死神が現れ、観客席が歓声に包まれる。
『‥‥死神は答えた、
「夜の闇に包まれて、命の火は消えてしまった‥‥。
さあ、貴方の息吹きを分けておくれ」』
戦乙女に手を伸ばしつつ、本物の死神が大鎌を振りあげた!
|
マローズの檻「これでリサーチフェイズが一回りしたわけだが‥‥」 |
| >> Scene13 『二つの決意(十年前のシーン・2)』 |
夜陰に紛れ、幾重もの包囲網を潜り抜け可能な限り遠くまで逃げてきた。真冬の夜の中、降り続く吹雪でもう追跡もできないだろう。もっとも、自分達が生きて帰れるかについても相当の疑問符が付く状態だ‥‥。
真冬の夜に吹き荒れる吹雪が容赦なく俺達に吹きつける。まだ腕の中で気絶しているソーファを庇いながら、雪の中を進み続けた。
「ここまでくれば、しばらくは大丈夫だろう‥‥」
何とか風除けになりそうな所を見つけ、暖を取り冷え切った体を温める事にする。
「う‥‥ん‥‥」
火の灯かりのせいで、目を覚ましたソーファがゆっくりと目を開く。しばし、ぼーっとした目で、目をしばたたかせ、辺りを見回す。
「‥‥気が付いたのか?」
「お、お母さん!!姉さん!!」
突然大きな声を上げる、意識が混濁しているのだろう。
「‥‥ソーファ‥‥、ここがどこか分かるか‥‥?」
「こ・こ‥‥?‥‥分からない‥‥、分からない‥‥。‥‥ねえ、姉さんは?‥‥お母さんは?私は‥‥ひとり?」
青い大きな瞳に涙を浮かべ、俺の方を見上げながらそう聞いてくる。
「ソーファ‥‥、お前はどこまで憶えている‥‥?」
「憶えてない!‥‥憶えてない!!」
母親の死を目撃し、ここにフレデリカはいない。幼いが聡明な少女はすぐに悟ったのだろう、両耳に手を当て必死に首を振る。まるで、全てを無かった事にしたいかのように。
「‥‥・もう全部分かっていると思うけど、とりあえず言っておく‥‥」
あらためてソーファに事実を伝える事は残酷な事かもしれない。だが全て知っているのなら、憶えているのだったら、現実に向き合わなければこれからは生きていけない。だから俺は全て話すことにした。
「ヴァイオレットはロシア軍兵士に撃たれて死んだ‥‥。‥‥フレデリカも、もういない‥‥」
小さな少女にとって、それはあまりにも残酷な現実。
「どうすれば‥‥・、私はどうすればいいんですか‥‥?」
ソーファは両目に浮かんだ涙を必死にこらえていた。
「‥‥お前はどうしたい‥‥?俺は‥‥、任務のままお前をここまで連れて来た。‥‥いや、そうじゃないな。フレデリカに頼まれてここまで連れて来た。お前はこれからどうしたい‥‥?」
二人を護れなかった俺にできる事は、フレデリカとの約束を護る事。
「フレデリカ姉さんは、クロノスさんに何て言ってましたか‥‥?」
「‥‥お前を護るよう‥‥そう言っていた。この蒼い宝石を俺に渡して」
それは、フレデリカがいつも身につけていた蒼い小さな宝石。
「それが姉さんの望み‥‥。願いだったのなら、私は生きなきゃいけない‥‥」
両目に強い決意を込めて、ソーファは涙を拭う。
「姉さんとの約束だから‥‥、どんな事があっても私は歌を止めません。私は歌を歌って幸せになります」
いつも笑顔で歌を歌っていた少女は、胸に手を当て笑顔でそう誓いを立てる。
「‥‥分かった。だったら俺は、お前がそう出来るように、笑顔で歌を歌えるようになるまで護ってやる」
部隊を‥‥いや、全てを失った今の俺に出来る事。それはこの少女の笑顔を護る事。ただそれだけだった。
「‥‥俺はフレデリカに頼まれたのに、ちゃんと銃を教えてやる事が出来なかった」
フレデリカに貸した銃と同じ“MP10”を取り出すと、ソーファの小さい両手に握らせる。
「え‥‥?あの、これは‥‥?」
「‥‥だけど、お前のその強さがあれば十分に使う事が出来るはずだ」
6歳の少女の小さな手には、まだ余る大きさの銃。
「‥‥お前が笑顔で歌えるようになったら、俺の役目も終わりだ。その時はそれで自分の身を護るんだ」
「あ、は、はい‥‥。分かりました。‥‥有り難うございます」
ソーファは自分の両手に余る銃を大事そうに持ち優しく微笑むと、精一杯背伸びをして俺の頬に軽く唇を触れさせた。小さな少女の小さいけれど精一杯の気持を込めて。

| >> Scene14 『遠い遠い、昔の話』 |
夜のサンクト・ペテルスブルク、バー『トラザルディー』。アンダーグラウンドな情報を求めて、モーガンは“耳が早いと噂の”ラットという情報屋に話を聞きに来ていた。
“エリューナの双珠”の捜索に動いている二つの組織。ロシアンマフィア“リューリク”と、ロシア対内防諜局・通称“クリムゾンブレイド”。両組織は共闘状態にあるとはいえ、現在は別々に動いており。特にロシア対内防諜局は、“マローズの檻”の名でロシアの裏社会に知られる人物の指揮の下、本格的に“エリューナの双珠”の獲得に乗り出しているようだ。
“白きフェンリス”が“エリューナの蒼玉”捜索に、“邪眼使い”が“エリューナの紅玉”捜索に当たっているのだと言う。
だが気になるのは、“白きフェンリス”の行動であった。必ずしも軍の利益の為に動いているようには思えない。モーガンのフェイトとしての勘がそう告げた。
「ま、調べられるのはこれくらいだ。これ以上は俺の首が飛びかねんから、勘弁してくれ」
噂通り耳が早かった男ラットは苦笑いをしつつ、モーガンのおごりのウォッカを飲み干し、机の上の1ゴールドをしまう。
「ありがとうよ。せいぜい気を付けるさ、じゃあな」
自前で頼んだバーボンを一気に飲み干すと、モーガンは“かなり高級な休憩室”を後にした。
「しゃあねえな‥‥、とりあえず報告に戻るか。‥‥ん?」
休憩室の小さな扉を窮屈そうにくぐったモーガンは、カウンターの客の一人に目が止まる。頼んだまま手付かずのカクテルを前に、一人物思いに耽っている女性‥‥“白きフェンリス”フレデリカである。
「っと‥‥」
ギシギシとスツールを軋ませながらフレデリカの隣に座り、改めてバーボンを注文する。一見すると赤の他人のような素振りだ。
「あ‥‥、しばらくぶりです。調査の方、何か分かりましたか‥‥?」
フレデリカの方はスツールに腰を掛け直し、モーガンに隣の席を勧める。
「まあ、そこそこな」
バーボンを一口煽りながらそう答える。
「そうですか‥‥」
「だけど、本当の所、何が目的なんだ?話は聞いていたよりでかいじゃねえか」
「え‥‥・」
世間話でもするような口調で核心に触れられたせいか、一瞬言葉に詰る。
「知っている分には黙っててやるが、知らずに動かされるのは御免だ」
モーガンがここにいる事はあらかじめ知っていた事‥‥。当然予想されるべき質問であり、受け流す心積も出来ていたはずだった。だけど、サングラスの奥の瞳を見てしまった彼女には、それは出来なかった。
「‥‥今の私には何も有りません。だけど、あの子‥‥ソーファは私の希望だった。あの子が幸せになる事が私の幸せだった。例え遠く離れていたとしても、あの子が幸せであるようにそう願っています‥‥」
「‥‥‥‥」
「昔の話をしませんか。十年も昔から続く物語‥‥遠い遠い、昔の話です」

| >> Scene15 『赤き天使と黒き悪魔』 |
場面は光り輝く金色のストリーム。一転、脳内に焼けるような匂いが立ち込める。進入対象、マット・マックス・モーガンのデータを2秒でブレイク。相手のデータを抜き出す。
「‥‥なるほど、面白い魚が網に掛かった。調べよう‥‥、それすらも予定のうちだ」
赤い天使の写ったモニターの前で、そう呟きながら女性はジャックを外す。
ロシア軍対内防諜局。裏世界の住人に“クリムゾン・ブレイド”の名で恐れられる非公式活動専門のセクション。モニターの前にいるのは年齢不詳のくすんだ金髪の女性。裏世界の全ての勢力が畏怖をもってその名を語る伝説のフィクサー“マローズの檻”。ロシアの裏社会の真の支配者。
衛星軌道上から撃ち下ろされる雷の槍――ミョルニルの雷――をもって敵対する全てを焼き払う力すら持っている。
だが彼女は代行者に過ぎない。“マローズの檻”の実体は災厄前に作られた衛星軌道上の情報網「ミールシステム」であるのだ。
“マローズの檻”はゆっくりと顔を上げる。その隣にはペルソナ・ハイランダーの少年。
「お目覚めかい?何か楽しいことでもあったみたいだね」
「予定通り網に掛かった。フール・フール、君に頼みたいことがある」
ディスプレイにはフェイトの男性、マット・マックス・モーガンの顔が表示される。
「ふうん‥‥彼を殺せばいいんだね。行って来るよ」
フール・フールと呼ばれた少年は、身の毛もよだつような笑みを浮かべその場から消える。
フール・フール‥‥その名はソロモン72柱の悪魔の内の一体に刻まれている。気まぐれのみで“マローズの檻”に手を貸している彼は、齢2000歳を越える本物の悪魔。
彼女は再び目を閉じる。浮かんでくるのはかつての光景。血に彩られた数十年前の記憶。災厄直後の、赤い太陽の下の記憶。
『天地がひっくり返った年。赤い空の街。暗い部屋にうずくまる私。
見下ろせば半分に欠けた母の顔、暖炉で燃えてる父の腕。
扉をこじ開ける音が聞こえる。
‥‥思い出せるのは軍人達の下卑た表情と、拳銃を持って血溜りに佇む、私だけだ‥‥』
「もう少しだ‥‥。信じられない額のあの遺産を入手できれば、真冬の夜(マローズ)、雪に閉ざされた祖国ロシアを変えることができる」
再び“マローズの檻”は光り輝く無限のグリッドの中に意識を戻す。
「私はこの世界がどれほど愚かなものかを知っている。
だから、――――負けるわけにはいかない」
赤い服を着た天使のアイコンがグリッドの中を駆け巡る。
| >> Scene16 『カーチェイス!』 |
「アイツは――――、“デスサイズ”!千の死をもたらしたっていう伝説の殺し屋だ。連中、本気になったな。おい、ケツに火が点く前に俺達もいくぞ!車を回せ」
賓客席から第三幕を眺めていたレッガー、イェレミーヤ・ゲールマンは、舞台上から伝わる並々ならぬ殺気に腰を上げ、階下に視線を向ける。
「アルサノフの子倅ども、俺はここにいる。早く上がってこい」
射抜くような目で“グッドイアイズ”に言い放ち、『アルタイル』を後にする。
「おい!奴が車が車で逃げるぞ。車をそっちに回す、すぐに追うぞ!」
『アルタイル』の前でイェレミーヤの部下を張っていたミハイルから連絡が入る。
「面白くなって来たようだな‥‥」
舞台の方から流れてくる殺気と、自らに向けられたイェレミーヤの視線、両方を受け止めつつ鮫のように笑うと“グッドアイズ”も『アルタイル』を後にした。
「おい、“グッドアイズ”こっちだ、早く乗れ!」
『アルタイル』の前でグッドアイズを出迎えたのは、ミハエルの部下が回した車ではなく、モーガンのドンキーミニ。“グッドアイズ”は即座の飛び乗る。
「モーガンか‥‥、早いな」
「ああ、猫野郎の事だ、こんな事になっていると思ってな。それよりも、アイツらを追えばいいんだな」
前方には、走り去る3台のリムジン。先頭の一台にはゲールマンの姿。モーガンは、中古車のアクセルを全開に吹かし、タイヤを軋ませながら急発進をする。
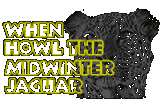
3台のリムジンは躊躇する事無く、屋台を蹴散らしながら市場を走り抜け、テーブルとスロットマシーンを破壊しながらカジノを突っ切り、料金所を無視してハイウェイへと入っていく。遅れじとそれに続くモーガンのドンキーミニ。
「ち‥‥!全く無茶しやがるぜ‥‥」
悪態を吐きながらも、モーガンは楽しげな表情でカーチェイスを繰り広げる。ハイウェイに出た所で、一気にリムジンとの間合いを詰める。
ゲールマンの乗るリムジンを庇うかのように、2台のリムジンがドンキーミニの前をふさぎ、合計20丁のトンプソンSMGが窓から生える。雨のようにばら撒かれる銃弾。それらを避けながらモーガンが車をリムジンに肉薄させると、“グッドアイズ”の獣の爪が1台のリムジンを紙の如く引き裂き、火屑へと変える。
「ヒュー!なかなかやるな、猫野郎」
「もう1台の方は任せたぞ‥‥」
「ああ、任せておけ。よっと‥‥これでも、食らいやがれ!」
アクセルを全開に踏み込むと、一気にもう1台のリムジンを抜き去る。と同時に、抜き去りざま懐から“ハードラックグレネード”を取出すと、リムジンの中に投げ込む。爆発と同時に操縦不能となった車は、激しくスピン、勢いを殺せぬまま街灯に突っ込んでいった。
「よし、一気に追いつくぞ‥‥んん?」
あらためて、前方のイェレミーヤの車を探すと、リムジンはハイウェイを降りて行った。道路標示には『ドリームパーク』建設予定地と有る。
「そう言う事か‥‥、奴め‥‥」
レオニード・アルサノフが殺された場所。イェレミーヤはそこで決着を付けるつもりらしい。
人気の無い、廃棄された遊園地跡『ドリームパーク』。乗り捨てられたリムジンの先にそびえるのは、夕暮れの光を受けて痛々しいほどに真っ赤に染まった塔。
そしてその下に見えるのは、塔からの反射光を浴び妖しい光を放つ打ち捨てられたピエロと、遊園地のマスコットキャラクターたち。
「ここは相当ヤバイな。用意は出来ているか“グッドアイズ”?」
バサラとしての直感がモーガンに告げる、ここは何者かの“領域”だと。
「ああ、あの日から準備は出来ている‥‥」
“グッドアイズ”は抜き身の剣を右手にそう答える。
闇の衣をまとった男、マット・マックス・モーガン。獣の本性を持つ男、“グッドアイズ”。二人は燐光煌く遊園地『ドリームパーク』へゆっくり入っていった。

| >> Scene17 『死神の鎌と騎士の剣』 |
舞台は漆黒の闇に包まれていた。
『‥‥戦乙女の涙は癒しの涙。
人を治す為に泣き続けて、私はもう泣けなくなった。
命を粗末にしすぎたから、大事な時に泣けなくなった。』
悲しみを歌う戦乙女の声。その悲しき歌声が『アルタイル』を包み込む。
『‥‥死神は答えた。
「夜の闇に包まれて、命の火は消えてしまった‥‥。
さあ、貴方の息吹きを分けておくれ」 』
答えるのは、死を告げる大鎌クロゥ・クルーアッハ。今まさに、白きフェンリスの、いやソーファ・ユーリィ・パヴロヴァの命を奪わんと大鎌が振り下ろされた!
だがその時、戦乙女の目の前で大鎌と騎士剣が交錯し火花が散る。死を告げる大鎌から戦乙女の身を護ったのは、フィアナ騎士団の騎士フィンマックール。突如として舞台上で繰り広げられた本物の剣劇の迫力に、観客席に歓声と共にどよめきが上がる。
『たとえ夜の闇に包まれたとしても、月の明かりと我が剣が命を照らす明かりとなる』
突如、頭上に現れた月の明かりの元、騎士フィンマックールが死神の前に立ちはだかる。
「なるほど、紅玉を護る騎士か‥‥面白い。名は、何と言う?」
「貴様に改めて名乗る名前など無い!何故なら‥‥、戦乙女を護る騎士フィン・マックール、それが私の名前だからだ!」
騎士剣を正眼に構え、正面から死神を見据える。
「ほう、ならばまずは貴様の命‥‥、この炎のように消してくれよう」
死神は掌に浮かべた炎を握り潰しながら、鮫のように笑みを浮かべる。
「だが、勇ましきは貴様のその心。今決着を付けてしまうのはあまりにも惜しい‥‥。エリューナの紅玉を護る騎士よ、決着の舞台は先にある。次を楽しみにしているぞ」
そう言うと、死神は大鎌を振り払い観客に一礼し、闇と共に舞台から掻き消えていった。
舞台で繰り広げられた大立ち回りに、観客は雨のような喝采を送る。
「戦乙女“白きフェンリス”。今再び、私の剣を貴方に捧げることを誓いましょう‥‥」
ゆっくりと地面に剣を置き、白きフェンリスの前に傅く。だが、凪月演じる騎士フィンマックールの足が小刻みに震えていたのに気付いた観客は誰一人としていなかった。

騎士フィンマックールが入れ代わるという事態が合ったものの、舞台は滞りなく進み終幕を迎える。観客で賑わっていた『アルタイル』を静寂が包み、道具が片された舞台には暗い明かりが灯っている。
「よかったら私の話を聞いて貰えませんか‥‥?少し長くなってしまいますが‥‥」
「ああ、いいぜ」
戦乙女の衣装から普段着に着替えたソーファは、真剣な表情で語り出した。
「聞いて欲しい事は沢山有ります‥‥。10年前のクリスマス、かつてクラスヤノスクで起こったこと、フレデリカ姉さんのこと、クロノスさんのこと、そして‥‥」
| >> Scene18 『悪魔との取り引き(十年前のシーン・3)』 |
ロシア軍の追手を逃れ、俺達は続く真冬の夜を歩き続けた。クラスヤノスクから一番近くの街には既にロシア軍の手配が回っていたし、真冬の夜を歩くのは少女には辛いものだった。だがそれでもソーファは泣き言一つ言わず懸命に歩き続けた。
やっとの事で国境近くの街にたどり着いた俺達は、国外に脱出すべくロシアンマフィア“リューリク”の幹部、イェレミーヤ・ゲールマンと接触を取る事にした。野心家で残忍な性格だが一度交した約束は違えぬ人物、それがこの男の評判だった。
「パスポートは用意してやってもいい。だが、高いぜ。アンタにゃ用意できない額だ」
「‥‥俺の分はいい、ソーファ一人の分だけでもなんとかなら無いのか‥‥?」
「それだったら、一人5プラチナムだな。だが、例えあんたが賞金首になっても、たらねぇな‥‥」
「‥‥くそっ‥‥!」
目の前のこの男を人質に取り、仲間を脅迫する事は出来たかもしれない。ただ、ソーファがいるこの状況では無理は出来かった。
「まあ、俺だってそんな子が死ぬのは見たくないからなあ‥‥、少しは、まけてやってもいいが」
灰色のトレンチコートを着込んだ赤い髪のレッガーは、くつくつと鮫のような笑みを浮かべる。
「‥‥もちあわせなんてない‥‥。今あるのは‥‥、これだけだ」
フレデリカから渡されたペンダントを取り出す。燃え盛る屋敷の中でフレデリカがすべてを託した蒼い宝玉。これの他に値打ちが有りそうな物はなかった。
「あ、あの‥‥、クロノスさん」
フレデリカがいつも身につけていた蒼い宝玉。それが他人の手に渡って欲しくなかったのだろう。旅の途中で7歳になった少女は、大きな瞳に涙を浮かべ俺の方を見つめた。
「‥‥ソーファ。フレデリカはお前を助ける為にこれを俺に渡した‥‥。こいつにこれを渡すのもお前を助ける為。納得できないのは分かる‥‥、でも分かってくれ‥‥」
「はい‥‥」
俺にはこんな事しか言う事が出来なかった。だけど、それでもソーファは分かってくれた。
「‥‥これで足りるな。少なくとも俺の命よりは高いはずだ‥‥」
俺達のやり取りを楽しそうに見ていたイェレミーヤの机の上に宝玉を置く。
「ほう、こいつはなかなか‥‥。ん?だが傷が‥‥」
宝石を照明にかざし、値踏みをしていたイェレミーヤの表情が真剣な物へと変わる。
「もしかして、エリューナの?!」
「‥‥どうした‥‥?」
「いや、なんでもない‥‥。かなりの値打ちもんだなこれは」
イェレミーヤは何かお宝をでも見つけたような表情でニヤリと笑うと、即座に蒼い宝石をポケットにしまう。
「‥‥それにどれほどの価値があろうとも、ソーファの命には変えられない‥‥」
「大事なようだな。だがその子を連れてこの国を出るのは無理だ、リスクが大きすぎる」
指を鳴らし、二人部下を呼び寄せる。
「だから彼女とはここでお別れだ。彼女の戸籍も用意してやる、誰にも分からないようなものをな。それと、あんたはこれから国境破りをするんだ、その為の算段は整えてやる」
「‥‥分かった、それでいい。その子の事は後は頼む‥‥」
「じゃあ、ここまでだな」
イェレミーヤの指示で、ソーファが黒服の部下二人に連れて行かれようとした時、ソーファが俺の袖をぎゅっと掴んだ。
「‥‥これから、私はひとりなんですか‥‥?」
これから独りで生きて行く事への不安。少女は再び目に涙を浮かべそう聞いてきた。
「‥‥本当は、この後もお前が元気に歌える姿を見れるまでついていてやりたい。だけど、今それを望む事はそれが出来なくなってしまうことなんだ」
もう少しだけでもソーファについていてやりたかった、だがそれは出来ない事だというのは分かっていた。だから、俺はそう答えるしかなかった。
「‥‥だったら、私はいつまでも歌い続けます、姉さんと貴方との約束の為に。もう一度貴方と会える時まで、私はいつまでも歌い続けます」
小さな少女の、誰にも負けない強い意志。ソーファは決意を込めた瞳で頷く。
「ソーファ、お前はもう銃の使い方は分かるな?」
俺がソーファに渡した“MP10”は小さな少女の手にはまだ大き過ぎる物で、使い方が分かっているわけはなかった。だが、敢えて俺はそう聞いた。
「え‥‥?あ、は、はい‥‥」
「その銃は別に使えとかそういう意味で渡したんじゃない。何かがあったらためらわず決断しろ、そういう意味で渡したんだ。いいな」
「はい、分かりました。ほんとうに‥‥、ほんとうに今までありがとうございました」
そして、俺達二人は別れを告げた。
十年の歳月が流れ、俺は再びロシアを訪れていた。部隊を全滅させた男、“邪眼の使い”アークがこの街、サンクト・ペテルスブルグに来ているという情報を聞いて。
ウォッカを飲み干し、静かに代金を置く。
「どうしても行くのか?」
カウンターの反対側、暗闇の中に佇む男がそう聞いて来た。もう一人の部隊の生き残りであり、すでにその半身は義体となってしまった男。
「‥‥知ってしまったからには、行かなければならない。知らなかったのなら、俺はここにただ歌を聴きに来ていただけだったはずだ。‥‥でも知ってしまったのなら、決着はつけなければいけない」
「そうか‥‥、ならこれを持っていけ」
男から投げて渡されたのは、一枚のシルバー。
「これが俺の命だ。傭兵はいつだって、一枚のチップに命を懸けてきた‥‥。頑張れ」
「ああ、じゃあな‥‥」

| >> Scene19 『十年後の再会』 |
「‥‥こんな事があったんです。あの時は私は、クロノスさんと姉さんに助けられて、今は凪月さん、あなたに助けられて、こうして生きているんです。‥‥姉さんも、クロノスさんも行ってしまったから、もう私は一人なんでしょうけど‥‥」
そう言ってソーファは悲しそうな微笑みを浮かべる。
「一人?そうじゃないだろ?今は劇団の皆だっているし、それに‥‥おい、いるんだろ?」
舞台袖のちょうど影になっている辺りに、凪月は声をかける。どうやら、見つかってしまったようだ。
「‥‥ああ、久しぶりだな」
死神の一撃を止めただけの事はある、と言った所だろうか。凪月とは以前ST☆Rで仕事をして以来の縁だ。
「‥‥ソーファ、約束通り素晴らしい歌だったよ」
十年ぶりに聞いたソーファの歌は、評判通り、いや評判以上に素晴らしい歌声だった。フレデリカと一緒に 歌っていた小さな少女の頃には無かった、力強さと儚さと悲しさ、その全てがこもっていた。
「お待ちしていました、十年の間」
十年の歳月は小さな少女を、強い意志を持った女性へと変えていた。変わっていないのは多分俺だけなのだろう。
「‥‥花を贈るなんて、柄じゃないけどな‥‥」
俺は苦笑しながらも、一輪の小さな白い花をソーファに差し出す。シロツメクサ、花言葉は“約束”。
「そんなことないですよ、とっても嬉しいです」
ソーファはそう微笑み、王から剣を受け取る騎士のように恭しく花を受け取る。
「十年前から続いた物語があるとしたら、今はちょうど第二幕の終わりあたりですね。本当に有り難うございます」
「‥‥ああ、だからまだ話は終わっていないし、物語に終わりなんて無いんだ。‥‥いつまでも歌い続ける、それが約束だろう」
今も続く約束、十年前からの約束。
「はい。私は、いつまでも歌い続けます。姉さんの分も‥‥」
「コホン‥‥あ〜〜、二人の水を差すようで悪いんだけど、大体話しは終わったのかのか?」
いつのまにか俺達の傍から離れ様子を見ていた、凪月が話し掛けて来た。
「‥‥ああ、大体終わったよ‥‥」
水を差されたのには違いないので、苦笑しつつそう答える事にする。
「ったく、いい雰囲気になりやがって。それよりもなあ、何なんだよあの死神。見てたんだったら助けろよ!」
そう言って凪月は俺の肩を掴むと、大きく前後に揺すってきた。あの場は凪月一人で大丈夫だと思ったので様子を見ていたのだが、それが気に食わなかったらしい。
「‥‥それは災難だったな、済まない」
とりあえず話しずらいので、凪月には謝り肩から手をどかせることにする。
「災難なんてものじゃなかったんだぞ、死ぬかと思ったんだぞ!」
「そんな、私の事護ってくれたじゃないですか。凪月さんが護ってくれたお陰で、無事だったんですから」
「仕事だからな」
ソーファのその言葉にさらりと答える。これも凪月なりの照れ隠しなのだろう。
「まあいい、お前の口からも何があったか聞かせてもらうからな」
「‥‥別にいいさ、だけど大体は聞いているんだろう?」
十年前の事件とアークに付いてのこと。そして、ロシア対内防諜局が“ロマノフの遺産”を求めて“エリューナの双珠”捜索に動いている事など、ロシアで調べて分かった事を二人に話した。
「‥‥あの時俺がイェレミーアに渡した蒼い宝玉、あれが“エリューナの蒼玉”だったんだな‥‥?」
「はい、あれは十年前のクリスマスに母さんに貰った物なんです。私の紅い宝石と一緒に‥‥」
「‥‥やっぱりな。そうだ、ちょっと見せてもらっていいか‥‥?」
ソーファの胸に付けられていた紅玉を受け取り、照明にかざしてみる。確かによく見てみないと分からないが、隠し彫りによる6桁の数字を見つける事が出来た。これが“ロマノフの遺産”の鍵なのだろう。
「この紅玉の為に、ソーファが死神に襲われたんだな」
「‥‥そうだ。凪月、ソーファの事は任せた。俺はそろそろ行かなければならない」
「おい、それはどういう事だよ!」
「‥‥ソーファを護るという俺の任務は十年前に既に終わっている。それに、ソーファの姿を見る事も出来た。だから、俺は奴を、アークを追わなければならない‥‥」
「だからって‥‥!」
「‥‥死神の奴も言っていただろう、お前の力を認めていると。だからお前一人の力でも大丈夫だ」
「‥‥・分かったよ。勝手にしろ」
ソーファの事は気になるし、傍にいて護ってやりたかった。だけど、‥‥俺にはまだやるべき事が有った。
「ソーファ‥‥、お前はもう一人で生きて行けはずだ。それに、今は凪月だっている‥‥」
「‥‥ごめんなさい。狙われているのは私なのに、いつも私以外の人に護られ、私以外の人が傷付いてしまう。クロノスさん、私は大丈夫ですから。ほんとうに、有り難うございます」
ソーファは真摯な表情で謝ると、力強く微笑んだ。
「‥‥じゃあな、二人とも‥‥」
そう言って俺はその場を後にした、全ての決着を付ける為に‥‥。
舞台の上に残ったのは、凪月とソーファの二人。
「もしかしたら‥‥、クラスヤノスクに行けば何か分かるかもしれません。母さんの教えてくれた秘密の場所が有るんです」
胸に付けた紅い宝玉。それを強く握りながら少女は話し出す。
「そこまで私を護ってくれませんか?お礼は出来る限りいたします。」
クラスヤノスク、十年前の惨劇で廃虚となった街。凍れる大地を走る大陸横断鉄道の駅だけが、まだそこに残っているのだという。
「切符はロズモンドさんの方で手配してくれるそうです。一緒に行って頂けませんか?」
「ったく、支配人もお人好しなんだな。わかったよ、戦乙女に剣を捧げると言ったことだしな」

|
フール・フール「“グッドアイズ”とモーガンはカーチェイス。凪月は死神との舞台上での剣劇だね」 |
| >> Scene20 『赤き刃、二人』 |
塵一つ無いロシア対内防諜局の廊下。二人の将校がすれ違う。一人はプラチナブロンドの髪に左右色の違う瞳をした女性、“白きフェンリス”フレデリカ。そして、もう一人は黒髪に真っ赤な瞳を持つ男性、“邪眼使い”アーク。
「‥‥行くわ。私はあの子を助けにいく」
「彼らの目的地はクラスヤノスクだ。だが“フェンリス”、これでもう敵同士だ。容赦はしない」
短く言葉を交し、二人はそれぞれの方向へと歩いていく。
舞台は変わって局長室。デスクに備え付けられたモニターを眺めながら、一人思案をする年齢不詳の女性、“マローズの檻”。
「―――かくて、白きフェンリスは放たれた。 劇中で彼女は死んだ。涙で人を癒す戦乙女も、自分の傷は癒せなかった。彼女を癒すものは人の涙でしかなかったのに、人は誰も彼女の為に泣かなかったのだ」
そう言って、デスクから静かに立ちあがる。
「‥‥たった一発の銃弾が全ての決着をつける。最後に勝つのは我々だ」
自ら全ての決着をつけんと、“マローズの檻”が狙撃用のライフルに手を伸ばす。
| >> Scene21 『夢の跡地』 |
燐光揺らめく打ち捨てられたドロイド、夕焼けの光を受けて不気味な表情を見せるピエロの人形、ドリームパーク跡地は燐と張り詰めた妖気で満ちている。
園内の広場にあるゴミの小山、その上にはイェレミーヤ・ゲールマン。そして隣には、無邪気なそれでいて凍り付くような微笑み浮かべた少年、フール・フール。
「あ、どうやら来たみたいだね」
『ドリームパーク』ゲートをくぐる二人の人影に向かって、少年は顔を向ける。
「なに、レオニードの時と同じさ。また、殺してやるだけだ、フール・フール」
咥えていた煙草を吐き捨て、静かに立ちあがるイェレミーヤ。
「でもおかしいな、イェレミーヤ。君の顔に死相が見えよ」
くすくすと楽しそうにフール・フールは呟く。
「死神ごと、返り討ちにしてやるさ。来たな‥‥」
妖気漂う『ドリームパーク』。二人の人影、マット・マックス・モーガンと“グッドアイズ”、それぞれの歩みに合わせ次々と空中に火が灯る。辺りには世界中の遊園地から集められたゴミの山が広がっている。 そのゴミの山によって作られた広場。そこでイェレミーヤとフール・フールは静かに二人を出迎えた。
「はじめまして、僕の名はフール・フール。ドリームセメタリーへようこそ。ここは夢の終わるところ。―――君たちの夢が終わるところさ」
どこか芝居じみた仕種で深く礼をすると、静かに空中へと浮かび上がるフール・フール。
「良く来たな、レオニードの子倅。そしてさよならだ」
地面に転がる無数の日本刀の束から無造作に二本を選び、抜き放つイェレミーヤ。
「おいおい、これから何かの劇でも始まるみたいだな。お代は俺達の命ってか?」
いつもと変わらぬ調子でそう言うと、まじないの言葉を唱え闇をまとうモーガン。
「父の仇だ‥‥。死ね」
一言だけそう呟き、だらりと下げた手に抜き身の剣を構える“グッドアイズ”。
辺りを取り囲むのは物言わぬ観客達。“グッドアイズ”とイェレミーヤ、二人の放つ銀光が劇の開始を告げた。
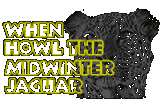
| >> Scene22 -『To Arms in Dixie!』 |
落ちついた雰囲気の内装、談笑する乗客。走る国が変わっても、大陸鉄道の車両には変わらずとゆったりとした時間が流れている。『グランド×クロス』の時ほど客が賑わっているわけではないが、サービスの良さは相変わらずだ。
あたりに物珍しそうな視線を向けているソーファは、どこか楽しんでいる雰囲気すらある。
反面凪月の方は、ソーファとの会話に相づちを打ちつつ油断無く車内を見回している。カブトとしての勘が何か告げるのだろう。
出発して小一時間が過ぎた時に異常は起きた。突然降り止む雪、二人を残しいつのまにかに消えた乗客、そして‥‥車内に満ちる獅子の殺気。瞬間、停電が起き車内が闇に包まれる。
「っ!!来やがったな‥‥!」
いち早く変化に気付いた凪月は、警戒し身構える。
「あ、あの‥‥凪月さん‥‥?!」
「いいから、ソーファはじっとしているんだ!」
突然、向かいの席に現れる気配。この世に二つと無い威圧感。
「やれやれ、そろそろ会えると思っていたぜ」
「‥‥・」
向かいの席に座る死神は何も答えず、煙草を咥え立ち上がると、その手を一閃。手の中に大鎌が現れる。
「そうだ、ちょうど俺も吸いたいと思っていた所なんだ。火、貸してもらえるか?」
死神は無言で空いている方の手をかざすと、凪月の煙草にも火を付ける。
「それで、やっぱり狙いはソーファの紅玉なのか?」
「死神が答える事ではないな‥‥」
油断無く身構える凪月にそう答えると、死神は何事か呟く。死神の唱える死の呪言。一瞬の耳鳴りとともにソーファが突然意識を失い、彫像のように凍り付く。
「っ!?お前、ソーファに何をした!」
「人間が息を止めていられる時間は短い。お前に彼女を救う事は出来るかな」
「だったら、今すぐお前を倒すまでだ」
倒れたソーファを庇うように死神に相対する凪月。だが、その後頭部に大型拳銃が突きつけられる。
「出来るものならばな。凪月 扇、話しには聞いている。幸運の星を味方に付けたカブトだったな」
後部車両から現れたのは、ロシア軍の軍服に身を包んだ赤い目の男、“邪眼使い”アーク。ゆっくりと凪月の背中に狙いを定め、引き金に親指をかける。
「だがこれで二対一、勝ち目はない。До свидания(ダ・スビンダーニャ)、さよならだ」
「‥‥二対一。アーク、冗談もその辺にしておくんだな‥‥」
アークが“エリューナの双珠”のうち“紅玉”捜索に動いている事を知り、俺は急いで『アルタイル』へ引き返す。そこで二人がクラスヤノスクに向かった事を聞き、運び屋に運んでもらいようやく追いついた。 凪月に銃を向けるアークの背後に“LP9”レーザーピストルを突き付ける。
「クロノスか‥‥。そいつの言葉じゃないが、そろそろ来る頃だと思っていた」
アークはそう言うと顔色一つ変えずこちらを振り向く。その口調はまるで、十年ぶりの再会を懐かしんでいるようにも聞こえた。

| >> Scene23 『復讐の獣』 |
両手に刀を構え、イェレミーヤが一気にゴミの山を駆け下る。一瞬の内に間合いを詰め、上下左右、変幻自在の太刀を繰り出す。肩を、胸を、首を狙い次々と繰り出される斬撃に、“グッドアイズ”はまったく身動きが取れない。
「なんだか、あっちの方はすぐに勝負が付きそうだね」
“グッドアイズ”とイェレミーヤの戦いを横目で見ながら、フール・フールはモーガンの前に降り立つ。
「行き場を無くした夢達‥‥。さあ、君達の夢を取り戻すんだ」
フール・フールの吹く笛の音に応え、ピエロの残がい達が動き出す。
「君の相手は、彼らだよ。探偵さん」
緩慢だがしっかりとした足つきで、獲物を求め掴み掛かってくる。動力などないはずなのにその力は侮れない。すんでの所で攻撃を躱したモーガンの背後で、ベンチが鈍い音とともにひしゃげた。
「ったく‥‥、きりがねぇな!」
幼い頃に修得したという闇の力を行使し、ピエロを一体ずつ引き裂いていく。だが、痛みを知らぬピエロ達は怯む事無くモーガンに迫ってくる。それに加え、辺りに響くフール・フールの魔笛の音色が五感を狂わせ動きを鈍らせる。

「どうした、レオニードの子倅。父を殺された恨みはその程度か!!」
防戦一方の“グッドアイズ”の右腕を容赦の無いイェレミーヤの一撃が切り裂く。剣を掴んだ右腕が付け根ごと地面に落ちる。だがその目には、腕を切り落とされた痛みはなく、父を殺した者への恨みだけが灯っていた。
「ああ、さよならだ‥‥」
だらりと、まるで勘弁したかのように“グッドアイズ”は頭を垂らす。
「観念したか。ならば、ここまでだな。」
イェレミーアの必殺の二刀が“グッドアイズ”の心臓と首を貫き、血に染まった刃が背中で交錯する。
「舐めるなよ、人間(ヒューマン)‥‥!!」
“グッドアイズ”の喉から獣の咆哮が鳴り響き、一瞬の内に辺りの空気が凍り付く。切り落された右腕が生え変わり、全ての傷が塞がると同時に異形へと変化を遂げる。太古の、獣の一族の血を引く力が解放されたのだ。
「なっ、貴様?!」
突如として目の前に現れた絶大な力にイェレミーヤの表情が驚愕へと変わる。
「苦しんで死ね‥‥」
“グッドアイズ”の二つ名であるジャガーへと変貌を遂げた頭部が、イェレミーヤの肩に、胸に、首に食らいつく。そして最後に、両腕の鉤爪が深々とその胸を刺し貫いた。
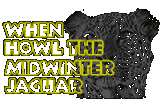
| >> Scene24 『対峙する4人』 |
「‥‥十年前の事は、今更聞きはしない‥‥」
左手の“LP9”を下ろし、瞬時に“EDGE”ナイフを構える。それと同時に、対峙していた4人が動き出す。死神の目の前には、ソーファを庇うように凪月が立ちはだかる。
「だが、弟が死んだ今もどうして軍の為に動いている‥‥!」
俺の言葉を遮るかのように至近距離でアークが銃弾を放ち、答える。
「一度戦いが始まったら、筋を曲げずに立場を貫くもの。善悪の基準は立場が決める。お前の知っているアークはもういない」
まるで観念したかのような緩慢なアークの動き。俺はその死角を付き、一気に間合いを詰める。
「‥‥いや違う。お前は俺の知っているアークだ」
右手の中の刃が深々とアークの胸に突き刺さる。呆気ない幕切れ‥‥、いや、あまりにも手応えが無さ過ぎる。そう思った時、アークの姿が闇の霧の中に消えいく。
「クロノス‥‥、全ての決着はクラスヤノスクでだ」
アークに流れるアヤカシの血。その力がアークの身体をかき消していく。
「ああ、待っていろ決着を付けてやる」
アークの軍服の切れ端だけが床に落ちる。その時にはすでにその姿は車内には無かった。
「さて、歌姫は眠りに付いた。『アルタイル』での決着を付けよう、勇ましき騎士よ」
インフェルナスの燃え盛る大鎌が振るわれる。ただ一度、ただ一度の斬撃だけで、車両じゅうの座席が切り裂かれていく。
「おいおい、ここは電車の中だろ。それに、俺は騎士なんかじゃないぜ」
すんでの所で一撃を躱し、凪月は一瞬だけ目を瞑る。同時没入(フリップ・フロップ)、現実世界を知覚しながらのイントロン。ニューロでもある凪月の得意技だ。車外に流れる風景が、ウェブのストリームと重なる。
「お前みたいなのとまともに戦っても、勝ち目が無いのは分かってる。だから、俺のやり方で行かせてもらうぜ」
ナノマシンを介した敵IANUSへの強制ハック。黒き頭脳に幾万もの糸が紡がれ、インフェルナスの全身に電撃が走る。
「ほう、面白い技を使う‥‥。それでこそだ」
死神は首筋から火花を散らし、一瞬だけうずくまる。
「クラスヤノスクこそ、最後の舞台。次こそ決着を付けよう」
列車の窓という窓から、何百羽という数の鴉が車内に飛び込んで来た。辺り一面が漆黒に闇に覆い尽くされる。そして、次の瞬間、車内は乗客たちの喧燥に包まれていた。まるで何事も無かったかのように。

|
マローズの檻「というわけで一回目のカット進行なのだが‥‥」 |
| >> Scene25 『レオニードの手紙』 |
胸を深く刺し貫かれ、ゆっくりと地面に倒れこむイェレミーヤ。その手からゆっくりと刀が落ちる。だが、それと同時に乾いた音が辺りに響く。少年の手から放たれた銃弾もまたイェレミーヤの胸を貫いていたのだ。
「ほぅらね、僕の言った通りになったよ。彼はこれからの舞台に相応しくなかったんだ」
その手に硝煙の立ち上がる拳銃を持ち、古代バビロニアの悪魔はにこにこと笑うと空中に浮かび上がる。
「ためらわず殺したな‥‥」
ゆらりと立ち上がった“グッドアイズ”がそう呟く。
「フフッ、その言葉はそっくりそのまま返すよ。さて、君たちの絶望はまだ続く。どんな終わり方になるのか楽しみだ。絶望に震える君たちがどんな顔をするのか」
フール・フールの姿はそのまま消えていった。同時にピエロの残骸たちが動くのをやめ、セメタリーに満ちていた陰気な燐光が消えていった。
戦いが終わり、辺りを夜空が包む。夜空に浮かぶのは満天の星々と満月。
「綺麗な月だな―――フフ‥‥、だがもうよく見えやしねえ‥‥」
仰向けに倒れ、息も絶え絶えになりながらも煙草を咥えるイェレミーヤ。“グッドアイズは”それをゆっくりと見下ろす。
「お前にとっての月はもう無い。俺にとっての月はあるがな‥‥」
「‥‥そうかもな。だが、金と権力。男なら誰だって望む物だ。そいつを求めてなにが悪い」
そう言うと、ロシアンマフィア“リューリク”の幹部は鮫のような笑みを浮かべた。
「お前の言っている事は分かる。だが、許さん‥‥」
「へっ‥‥、だろうな」
その口から煙草が地面に落ちる。それが、偉大なる“父”を殺した男の最後だった。
「ん?コイツは‥‥」
満天の星空の下、イェレミーヤの首下から落ちた何かが小さく光る。それを静かに拾い上げるモーガン。
「やっぱりな、“エリューナの蒼玉”か。あんたに恨みはねぇがこいつは貰っていくぜ」
しばらくその場に立ち尽くしていた“グッドアイズ”に確認しつつ、蒼い宝石をコートの下に仕舞う。
「さてと、葬儀場まで送っていくぜ。乗るだろ?」
モーガンのその言葉に“グッドアイズ”は無言で頷く。そして、二人の男は『ドリームパーク』を後にした。

“グッドアイズ”達が再び葬儀場に戻った時、一通の封筒が“グッドアイズ”宛に届いていた。差出人はレオニード・アルサノフ。消印は十日前。レオニードの命日である。
封筒に入っているのは三枚の写真と、一通の手紙。一つは、少し前のフレデリカの写真。一つは、同じく少し前のソーファの写真。そして、もう一つは幸せそうに笑う二人の少女と、それを温かく見守っている母ヴァイオレットの姿が写されている。
姉がヴァイオリンを弾き、妹がそれに合わせ歌い、その様子を母親が温かく見守っている。ここに写ってはいないが、きっと父親も和やかな表情で見守っている事だろう。この写真だけは、日付が2062.12.24と刻まれていた。
『突然の手紙をすまない。お前は元気にしているだろうか。
こんな形になってしまってすまないが、お前に頼みがあるんだ』
こういう書き出しで始まった手紙には、今まで語られる事の無かったレオニードの過去の話しが書かれていた。
レオニードがまだ若かった頃、ロシアの上流階級の令嬢ヴァイオレットと恋に落ち、ソーファとフレデリカ、二人の姉妹が生まれた。しかし、生粋のマフィオーソだったレオニードは、二人の娘の前にほとんど姿を現すことも、父と名乗ることもできずなかった。父らしい事が何も出来なかった事をずっと悔やんでいたのだ。
だが、それでもレオニードは静かに二人の娘を見守り続けたし、クラスヤノスクの惨劇を二人の娘が共に生き延びたと知ったときは多いに喜んだ。
そして、手紙は最後に次のように結ばれていた。
『これから俺は、連中と話を付けに行くつもりだ。
これが父らしいことを何一つできなかった男の、少しでも罪滅ぼしになれば良いと思っている。
‥‥この手紙が届く頃には、俺はこの世にいないかもしれない。
そのときは、俺の代わりに伝えてほしい。“扉を開く鍵は一番大切な思い出の中にある”のだと。
最後に、いつもいつも厄介ごとを押し付けてしまってすまない。
レオニードの過去に何らかの秘密が有った事は、“グッドアイズ”も気が付いていた。ただ、それを知る必要は彼には無かった。だが、知ってしまったからには動かなければならない。それが偉大なる父の意志ならば。
「クラスヤノスクだな。“グッドアイズ”、行くぞ」
“エリューナの蒼玉”を眺めていたモーガンが、“グッドアイズ”の背中に声をかける。レオニードからの手紙の内容。蒼玉に刻まれた6桁のナンバー。そして、フレデリカの言葉。全ての糸が繋がった。
「ああ‥‥」
手紙を読み終え、偉大なる父の息子“グッドアイズ”は最後に黙とうを捧げた。
「明日の午後1時ちょうど、駅で会おう」
そう言い残し、マット・マックス・モーガンは雪降る葬儀場を後にした。
「親父さんは何て言っていたんだ?」
肩に雪を積もらせたままの“グッドアイズ”に、レオニードの腹心ミハエル・フラトコフが声をかける。“グッドアイズ”はそれに対しては何も返さず、無言で父からの手紙を渡す。
「‥‥。で、お前はどうするんだ、“グッドアイズ”?」
手紙を読み終え静かに頷くと、ミハエルはそう問い掛けた。
「親父の頼みを果たすだけだ‥‥」
「行くのか?」
「獣はその親に対し、命を捧げるものだ‥‥」
「そうか‥‥。じゃあ、ここでお別れだな。俺はここで親父さんのもう一つの家族を護らなければならない、俺達のファミリーを」
“グッドアイズ”の言葉を聞いたミハエルは、ニッと笑うとその右手を差し出し硬く握手を結ぶ。
「オー・ヴォワー(さようなら)‥‥」
そして、二人は再びそれぞれの道を歩き始めた。偉大な父の遺志を継ぐ為に。
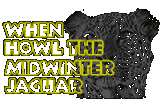
![]()
RI-Foundation > Access 100K > Hata-Maro 2 10万Hit記念ページへ
10万Hit記念ページへ |