
真冬の夜(マローズ)を越えるとき
〜はたはたVer.〜

真冬の夜(マローズ)を越えるとき
〜はたはたVer.〜
| >> Scene26 『クラスヤノスク、再び』 |
まるで何事も無かったかのように大陸鉄道は進み、トンネルをくぐり抜けクラスヤノスクへ到着しようとしていた。死神の呪縛が解かれ、静かに息を整えるソーファのみが先程戦いが有った事を証明していた。
「そんじゃ、俺は他に怪しい奴がいないかどうかちょっと見回りしてくるよ。」
凪月はそう言うと、俺達のいる車両を後にした。
「‥‥ソーファ‥‥。もう、大丈夫か?」
「あ、はい。大丈夫です‥‥」
まだ少し荒い息を吐きながらも、ソーファはにっこりと微笑む。
「二人にまた助けられて‥‥。でも、本当に嬉しいです」
「‥‥言った通り凪月は、ソーファの事を護ってくれたしな。‥‥アークの方は、俺が倒す‥‥」
アークの裏切りによって、傭兵部隊だけでなく、ソーファ達クラスヤノスクの住人達全ての命もまた失われてしまった。たとえどんな理由が有ったとしても、許す事は出来ない。
「アークって、あのアークさんなんですよね‥‥」
「ああ‥‥」
アークの事はソーファも良く知っていた。俺達が親友同士で、よく『エスメラルダ』で酒を飲んでいた事も。
「‥‥奴は変わってしまった。‥‥いや、もしかしたら奴は何も変わっていないのかもしれない、俺と同じように。結局の所、過去に縛られているという意味でも‥‥」
今の俺達にはきっと立場の違い以外、存在しないのだろう。過去に縛られ生きて行く事しか出来ない、俺達には‥‥。
「『例え、どれほどの時が経ったとしても、変わらない想いはある。
過去に縛られることがどれほど愚かに見えたとしても、
過去を捨てて生きていけるほど人間は強くないのだ。』
これは、私の演じていたあの劇の、“白きフェンリス”の言葉です。いいんですよ、それで。私達はそうやって生きているんですから」
俺の眼を見つめ、静かに微笑むソーファ。
「それに、過去は変えれないかもしれないですけど。これから先、運命はいくらでも変えれると思いますから」
確かにそうなのかもしれない。たとえ過去に縛られていたとしても、前に進む事は出来るのだから。
「‥‥アークはあの時、運命は変えれるのものなのか、そう俺に聞いて来た。その時俺は、答える事が出来なかった。だけど、今は答えられる気がする。運命は変える気が有るのならば、あがく事を止めなければ、変える事は出来ると。諦めさえしなければ何かが変わるはずだ。だけど、アークはそれを止めてしまったんだな‥‥」
「クロノスさん‥‥」
「ありがとう、ソーファ。俺は、これからも過去に縛られ続けるかもしれない。だけど、それでもいいんだよな」
俺はそう言って、ソーファに微笑み掛けた。
「はい、私もそう思います」
誰もが捨てる事の出来ない過去を背負って生きている。でもだからこそ、過去に向き合い今を生きて行かなければならないのだろう。
「さてと、お二人さん。そろそろ着くみたいだぜ」
ちょうど俺達の話しが終わった所で凪月がこちらに戻って来た。凪月の事だ、妙な気を回していたのだろう。俺は少し苦笑いをした後、窓の外、未だ雪の降りつつけるロシアの景色に目をむけた。

| >> Scene27 『“白きフェンリス”』 |
昼から降り続いた雪は収まり、透き通った夜空には真っ白な月が輝いていた。フレデリカは屋敷のテラスから、もの憂げな表情で外を眺めていており。以前のように、ヴァイオリンの音色がモーガンを出迎えることはなかった。
「大変だったみたいですね‥‥」
『ドリームパーク』での戦いのおり傷を負ったモーガンは、フレデリカから治療を受けていた。背中と右腕にしっかりと包帯が巻かれる。
「いや、たいした事はないさ。それよりも、約束のものだ。」
コートの内ポケットから、“エリューナの蒼玉”を取り出し、フレデリカの首に掛けてやる。
「あ‥‥、有り難うございます」
大切そうに両手で蒼玉を包み込むように持つと、彼女は静かに微笑みを浮かべた。その表情は、ロシア中の裏の勢力に恐れられている対内防諜局の一員のものではなく。一人の、ただ昔の思いを大切にする女性の、優しい微笑みだった。
「行くのか?クラスヤノスクに」
「はい‥‥」
フレデリカが“エリューナの蒼玉”の捜索を頼んだ理由。ロシア軍人“白きフェンリス”として今まで動いていた理由。その二つを知ったモーガンには、今のフレデリカが気持ちが理解できた。
「‥‥昔の話をしましたね。軍に入ったときには、私は一人になったと思っていました。“ロマノフの遺産”を得ることがこの国が『真冬の夜(マローズ)』から抜け出すために必要なことなら、何が起こっても構わないと思っていました。私には何もなかったのだから。だけど、あの子は生きていた。軍に追われて、自分として生きられなくなっても、好きな歌を歌い、仲間たちと笑って。‥‥会って何ができるかは分かりません。だけど、私はソーファを助けたい。あの子が、笑って生けるように」
クラスヤノスクに向かい、妹のソーファを助けること、ただそれだけがフレデリカの望みだった。
「だから、私はクラスヤノスクに行こうと思います」
「あそこが、“マローズの檻”の中でもか?」
「承知の上です‥‥」
戦乙女“白きフェンリス”のように美しい白金色の髪を持った女性は、固い決意の込もった瞳でモーガンの方を見つめた。
「ボディガードが要るんだったら、雇われてやってもいいぜ。
昔のよしみだ、特別に前金なしの全額後払いで受けてやる」
「モーガン‥‥。ありがとうございます。期待して、いますね」
そう言うとフレデリカは静かに右手を差し出す。しかし、モーガンはその握手を受けず、フレデリカに屋敷に入るよう促す。
「後できっちり払ってもらうぜ」
軍の輸送機の中。高性能なパワーアシストアーマーに弥勒サングラスを装備した冷たい雰囲気を放つ男達がインカムで会話している。
『了解しました、作戦に移ります。‥‥もう生かしておく必要が無くなった。ゼロ・アルファ。後続の歩兵部隊に先だって作戦を開始する』
彼らは、ロシア軍最新鋭パワーアシストアーマー“SV2015-Type13th”を身に纏った降下部隊、《ノクトフライヤー》。輸送機のハッチを解放し、フレデリカの屋敷を目測で捕らえる。
『《オペレーション・ノクトウィング》開始だ。最強の野戦部隊は俺たちだと証明してやれっ!』
背中の滑空翼を広げ、闇の狩人達は次々と降下していった。
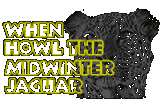
MG20機関砲の一斉射撃。天井に、窓に、床に次々と穴が穿たれていく。パワーアシストアーマーに身を包んだ闇の狩人達は、フレデリカの屋敷を取り囲むと一斉に侵入を開始した。
思いがけず屋敷内は漆黒の静寂に包まれていた。屋敷内に入った瞬間、目隠しをされたような感覚に襲われる。即座に、弥勒を赤外線モードに変更。おぼろげに屋敷内が映し出される。
「そこか!!」
ふいに目の前を白金色の髪の女性が横切る。機関砲の一斉射撃。狙い違わず、銃弾が女性の身体へと吸い込まれていく。
任務完了を確認する為に、隊員の一人が駆け寄る。だが、その表情は驚愕に凍り付く。血の海に横たわるのは一体のパワーアシストアーマー。そして再び屋敷は闇に包まれた。
錯乱した隊員の放った一発の銃弾が、最強の野戦部隊の運命を決めた。屋敷中で繰り広げられる、凄惨な同士討ち。止む事の無い悲鳴と銃声。再び屋敷が静寂に包まれた時、動くものは誰もいなかった。
絶え間なく響く銃声を尻目に、屋敷を走り去る1台のボロ車、中古のドンキーミニ。
「こいつは護衛の初仕事だ」
してやったりの表情でフレデリカに笑い掛けるモーガン。そう、全ては彼の操る闇のまじないによるものだったのだ。“心に露をかける”。幼い頃の彼に、闇のまじないを教えた老婆の極意の一つである。
「ま、帰ってきたら大掃除だな」
サンクト・ペテルスブルグ大陸横断鉄道駅に向かい、車のアクセルを踏み込む。

| >> Scene28 『ヴァイオレットの物置』 |
クラスヤノスク、“惨劇”の傷を色濃く残した街。当時の戦闘の傷が今でも残るこの街には、住民の姿はほとんど無く、駅周辺だけがかろうじて整備されていた。
十年前の“惨劇の夜”、ヴァイオレットが命を落し、ソーファとフレデリカが生き別れた屋敷跡。その館の前に俺達は来ていた。
館の中の焦げ目の入ったアナスタシアの肖像画。ソーファがその裏に隠されたディスプレイにパスコード――2036.09.12、レオニードの誕生日――を入力すると、壁がスライドし、隠し部屋が現れた。
だが、ここにも軍部の手が入っていたのだろう、中は捜索の跡が見て取れた。資料の類は一切持ち出されているようだ。残っていたのは壁際の棚に置かれた小さなオルゴールだけだった。赤と蒼のガラス玉をはめ込まれた小さなオルゴール。
そのオルゴールを手に取ろうと、ソーファが棚に近づく。するとソーファの紅玉に反応し赤いガラス玉が外れ、穏やかなオルゴールの音色が流れ出した。どこか懐かしく、それでいて悲しい感じのする音色が部屋の中に響く。
オルゴールの蓋の裏には若い頃のヴァイオレットとレオニードの写真が貼ってあった。若き日のその微笑みは、今のソーファにとても良く似ていた。
ソーファの手から、オルゴールに付いていた赤いガラス玉が転がり落ちる。その中には一枚のデータチップが隠されていた。データの中身は、ヴァイオレットからの伝言。
『 私には道を残しておくことしかできないけれど、
いつだって貴方たちの事を見守っています。
私の愛しい子供たち、貴方たちのことを愛しています。
簡単なソフトウェアが一つ、伝言の最後に入っていた。“エリューナの紅玉の6”桁、“エリューナの蒼玉”の6桁、そして一番大事な思い出の中にある8桁、合計20桁。このパスワードで、今はスイス銀行に保管されている莫大な“ロマノフの遺産”を手にすることができる。
一定法則に従ってパスワードを周期的に変更するこのソフトを走らせてしまえば、20個もの数字が偶然揃うことは永遠になくなる。世界に必要ない力を、永遠に眠らせることができるのだ。

| >> Scene29 『死を運ぶ風』 |
時刻は午後一時ちょうど。モーガンは車のクラクションを鳴らし、駅前広場で待つ“グッドアイズ”に到着を告げる。車の助手席には、フレデリカの姿。
「よう、待たせたな」
「なに、時間ちょうどだ‥‥」
午後になり小降の雪がちらつく駅前広場。そこは買い物に出る人々でごった返し、さまざまな露天商が立ち並んでいた。
アクセサリーを扱っていた露天商からオルゴールの音色が響く。『アルタイル』で歌姫が奏でた音色と同じ、“真冬の夜を超える日”の一節。
サンクトペテルスブルク大陸鉄道駅そば、高層ビルの上。狙撃用のスナイパーライフル“ドラグノフ”を抱えた女性、“マローズの檻”がゆっくりと顔を上げる。
「私だ。泳がせていた鯛を始末してから帰到する。部隊をクラスヤノスク跡に展開しろ。決着はそこでつける。‥‥ああ、まかせた」
ビル風に煽られ、グレイがかった金髪がゆっくりと宙に舞う。射線の向く先、標的はちょうど真下。車の助手席から降りようとしている白金色の髪の女性に、ターゲッティング。吹き荒れていたビル風が止む。引き金に掛けた指が引かれ、死を運ぶ風が放たれた!
「ん‥‥?」
一瞬、モーガン達の頭上で何かが光る。異変に気づいたモーガンが頭上を見上げると、ビルの屋上からスナイパーライフルのスコープがその身を覗かせていた。
「っ、間に合え‥‥!!」
“マローズの檻”から放たれた一発の弾丸が、吸い込まれるようにしてフレデリカに迫る。フレデリカを左腕で庇うと、モーガンは頭上に突き出した右手に意識を集中させた。手のひらに収束した“力”を一気に開放。急速に銃弾のスピードが失われていく。そして、目前まで迫った銃弾はその動きを完全にストップさせた。

“マローズの檻”は静かに銃を下ろし、その場後にする。狙撃が失敗した事を気にする様子も見せず、その表情からは感情を読み取る事は出来ない。
「今に知るがいい、圧倒的な戦力差を。君たちは吹雪におびえる籠の中の鳥のようなものだ。マローズに怯えるロシアと一緒だよ。自らの力では抜け出すこともできないのだからな‥‥」
|
フール・フール「しかし、この辺りのシーンはほとんどモーガンの独壇場だね(笑)。フレデリカの方も終始モーガンのペースだったし」 |
| >> Scene30 『十年後の再会』 |
嵐の前の静けさのような静寂の中、ただ静かに時間だけが進む。辺りには小ぶりの雪がちらつき、今はただ街の静寂が耳に痛い。
一刻も早く“ロマノフの遺産”を封印してしまいたかった。だが、俺達が知っているのはソーファの持つ“エリューナの紅玉”に刻まれた6桁のナンバーだけだったし、“エリューナの蒼玉”の6桁も残りの8桁のナンバーも全く見当が付かなかった。
頼みの綱は、サンクトペテルブルグで一度だけ顔を合わせた探偵、マット・マックス・モーガンだけだった。モーガンとは、かつて北米にいた頃、仕事を共にした事もあり。何度なくその機転と闇の力に助けられたものだ。
モーガンは、個人的な知り合いでもある“白きフェンリス”というロシア軍仕官に頼まれ、“エリューナの蒼玉”を探しているのだという。そして、俺の考えが間違っていなければ、“白きフェンリス”とは、惨劇の夜、ソーファと生き別れになったフレデリカの事であり。そうだとしたら、俺達と同じように彼らもいずれここに来るはずだ。
凪月のポケットロンからオルゴールの音色が鳴り響く。俺達は静かに待ち続けた‥‥。
ゆっくりと雪を踏みしだく音が、夜の静寂を破る。三つの人影が月夜に照らされ近づいて来た。
「思ってた通りだな。やっぱりここだったか」
2m近い巨漢にスキンヘッドの男、マット・マックス・モーガン。
「懐かしい音色だ‥‥」
シックなスーツに身を包みどこか獣じみた印象の与える男、“グッドアイズ”。
「ソーファ‥‥」
そして二人の後ろには、ソーファの姿を認めて立ち止まる白金色の髪の女性、“白きフェンリス”フレデリカ。
ロシアの大地を踏んだ男達の物語と、十年前から続く姉妹の物語。バラバラだった全ての物語が交わり、一つの運命を紡ごうとしていた。
「姉さん、フレデリカ姉さん!」
フレデリカに駆け寄り抱き着くソーファ。感極まったように目を閉じ、ソーファを抱きしめるフレデリカ。十年の時を経て、再会を果たした二人の姉妹。
フレデリカから少し離れ、姉妹の様子を見ていたモーガンが俺の方に近づいて来た。
「よう、また会うとは縁が有るな」
「‥‥ああ、遅かったな‥‥」
「まあな」
フレデリカの胸元には“エリューナの蒼玉”が輝きを放っていた。モーガンの方は無事に仕事が済んだのだろう。お互いに今までの経緯を話す。
「‥‥その様子だと、仕事の方は終わったみたいだな」
「まだまだ、これからだろ?」
そう、俺達にはまだやるべき仕事が有った。“ロマノフの遺産”を封印するという最後の仕事が。
惨劇の夜から十年の年月が流れていた。フレデリカが俺にソーファを託したヴァイオレットの屋敷。ちょうどその前で俺達もまた再会を果たしていた。
「‥‥フレデリカ‥‥。十年経ってようやく会えたな‥‥」
十年前、あの時俺はフレデリカを助けることは出来なかった。だけど、十年経ってようやく再会する事ができた。
「はい、私はこのとおり大丈夫でしたから。それよりも、本当にありがとうございます。約束通りソーファを護っていただいて」
ソーファと俺の顔を交互に眺めつつ、フレデリカは優しく微笑む。まるで、十年のときを懐かしんでいるように。
「でもそういえば、貴方は変わっていないんですね。まるで、時が止まってしまったみたいに‥‥」
「‥‥それは‥‥。俺は、あの時すべてを失ってしまったから‥‥」
部隊も‥‥、仲間も‥‥、友も‥‥。すべてあの惨劇でなくしてしまった。
「‥‥でも、俺はそれを認めることが出来なかった‥‥。だから、お前やソーファを護ることだけ考えた。任務のことだけ考えたんだ‥‥」
しかし、それも途中で終わりを告げた。
「そして、それが終わったとき。本当に何もなくなってしまったんだ。その時から変わっていない‥‥。十年前のあの時に、時間の神に見放されたんだよ」
本当は単に、極度にサイバーアップされたこの体が原因なのかもしれない。ロシア軍の軍事技術の被検体として、幾度となく体を改造されもした。だけど、そんな事はどうでも良かった、今更何も変わりはしないのだから‥‥。
「クロノスさん‥‥」
自嘲気味の俺の言葉に、フレデリカとソーファは表情を曇らせる。心優しい姉妹は、こんな俺のことでも心配してくれてるのだろう。
「でも、まだこれからがあるじゃないですか。たとえやり直せなくっても、未来は決まっていないんですから」
フレデリカのその言葉は、大陸鉄道の中でソーファが俺に言った言葉と同じだった。たとえ過去に縛られていても、進む事は出来ると。決して捨てる事の出来ぬ過去を背負いながら、それでもなお強く生きて行こうとする二人の姉妹。その二人の言葉が心に響く。
「‥‥そうだな。ありがとう‥‥」
フレデリカのその言葉に静かにうなずく。そう、俺達にはまだやるべき事が有るのだから。
-
Climax Faze -
| >> Scene31 『天使の怖れ』 |
“ロマノフの遺産”の最後のナンバーは、モーガンの推理した通りだった。“グッドアイズ”がレオニードから受け取った写真に記されていた数字、2062.12.24。パヴロヴァ家の家族だけのクリスマス。家族だけの一番大切な思い出の日付。それこそが最後の鍵。
フレデリカのタップを使い、ソーファが“遺産”のページにアクセス。暗証番号の場面が現れ、20桁のナンバーを要求する。
「‥‥ソーファ、フレデリカ。いいな‥‥」
俺が“遺産”のナンバーを読み上げ、それを二人が一つずつ入力していく。これで、十年前からの事件が終わる。きっと元どおりの、幸せな日々が戻る。
だが、最後のナンバーを入力しパスワードの変更を選ぼうとした瞬間、画面に異変が起きた。赤い衣を着た天使のアイコンが画面上に現れ、突然システムがダウン。画面は赤い檻を写したままピクリとも動かなくなる。
直後、爆音とともに数機のワイズマン戦闘ヘリが背後に現れ、「マーチ!」という掛け声と共に完全武装の二個分隊が周囲を取り囲む。
人壁を割るようにして現れたのは、グレイがかった金髪に軍服を身にまとった女性。ロシア対内防諜局・局長“マローズの檻”。
「ここまでご苦労だったな。姉妹が邂逅を果たせて君たちも満足だろう」
その脇には、緑と黒の軍服に身を包んだアーク、死を告げる大鎌と闇色のローブのインフェルナス、宙に浮かび微笑を浮かべるフールフール、それぞれが控えていた。
「さぁ、ナンバーを渡してもらおうか。ロシアの再建のためには、あれが必要なのだ」
「フレデリカ、下がっていろ!」
モーガンがフレデリカを庇う位置に立ち、ソーファを連れて下がるよう指示する。その言葉と同時に、夜空から切り出された闇がワイズマンを取り込み、姿をかき消していく。
「ほう、面白い闇を使うな、君は。だが、君の力がどれほどのものだとしても‥‥」
ゆっくりと俺達の方を見回しながら、“マローズの檻”は続ける。
「見たまえ、この圧倒的な戦力差を。君たちは吹雪におびえる籠の中の鳥のようなものだ。マローズに怯えるロシアと一緒だよ。自らの力では抜け出すこともできない」
モーガンの闇の力でワイズマンが消え去ったといっても、完全武装二個分隊。それにアーク達に囲まれたこの状況は、確かに圧倒的だった。
「さぁ、ナンバーを渡して貰おうか?あれは君たちには過ぎたものだ」
「‥‥確かに、俺達には過ぎたものかもしれない。だが、おまえ達にはもっと過ぎたものだ。そんな物をこの世の中にあっていいはずがない‥‥。あれは俺達が封印する。二度と惨劇は繰り返させない」
人の手には有り余るほどの“遺産”。世界大戦の火種にしかなり得ないようなものならば、どんな理由があっても封印しなければならない。悲劇を乗り越えなければいけない未来など、あっていいはずがない。再び、過去の惨劇を繰り返さないためにも。
「ならば、我々に凍りついた大地とともに凍え死ねというのか。我々には他に道は残されていない。これは生存のための闘争なのだ。‥‥私はロシアを守る盾と剣だ。絶対に引くことはできない」
「交渉決裂だな‥‥」
“グッドアイズ”のその言葉に全員が身構える。決着の時は訪れた。
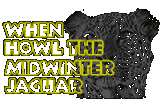
|
フール・フール「さぁ〜って、ラストはトループ&ゲストが総登場で、一気に場面が派手になるね♪」 |
| >> Scene32 『真冬の夜の終わり』 |
二個分隊からの一斉射撃。すばやく身をかわし、俺達は辛うじて致命傷を逃れた。
負傷した眉間を押さえつつ、モーガンは“マローズの檻”に向き合う。その前方にはふわりと宙に浮かぶフール・フール。“ドリームパーク”で会ったときと同じように、心底楽しそうな表情で微笑みながらこちらを見ている。
「よう、遊ぼうぜ子悪魔。これでもくらいな‥‥!」
夜空から切り出した闇の力を再び収束させ、フール・フールに叩き付ける。戦闘ヘリすら消し去った闇の力。衝撃波となったそれが、フール・フールを直撃する。
だが、齢二千年を越えるアヤカシの少年は眉一つ動かさず力を受け止める。
「さてと、今度は僕の番だよね」
マルンバの魔笛に口を当て、その音色をかき鳴らす。虚空に現れた時計の針が左に回り出し、六芒星を形取った炎が散っていく。鉛に変わった空気の中を緩慢に泳いでいるような、時間が逆に回っていくような感覚が俺達を襲う。

だらりと下げた右手に大鎌を持ち、闇色のローブをはためかせながら死神が近づいてくる。大地を覆う雪が静かに舞いあがる。
「このひり付くような感触、たまらんよ‥‥」
イントロン中の凪月の周りには、既にナノマシンの網が張り巡らされていた。その結界のさ中に、一見無防備にも思える動きで死神が侵入してくる。死神の黒い頭脳に向かって糸が紡がれ、電流が走る。
「‥‥遅いな」
だが、それよりも早く大鎌が振り下ろされた。大鎌の一撃が左脚をかすめ、大きく地面を抉り取る。かすめただけの大鎌の一撃。ただそれだけで、左脚が使い物にならなくなる。
「っく‥‥!同時に相手出来る相手じゃないぜ、まったく!」
迫り来る死神の攻撃を避けながらの、システムの復旧作業。凪月の表情にいつもの余裕は無かった。

雪の大地の上で再びアークと相対する。アークの実力は知っていたが、本気で戦ったことは今まで無かった。これが最初で‥‥、そして最後の戦いになるのだろう。
両腕のナノマシンを限界まで作動。戦闘モードを索敵攻撃から殲滅戦へと書換える。
「‥‥プログラム・アルテミス、インストール。自律射撃開始」
左手のナノマシンから射撃データをインストール。二個分隊にレーザーピストルの掃射を浴びせ、沈黙させる。
「‥‥プログラムを限界まで作動させる。これで全ての決着を付けてやる」
左手に“LP9”。右手に“EDGE”ナイフ。それぞれを構える。
「それでもお前は俺には勝てない。お前ではな」
アークの右手には、ガンブレードが握られている。アークがもっとも得意とした得物だ。腰を落とし、お互い油断無く構える。
右手のナノマシンから戦闘データをインストール。近接戦モードに移行。
「‥‥プログラム・アレス、インストール。反応速度、筋力ともに5倍に設定」
一気に間合いを詰め、高振動ナイフの一撃を繰り出す。アークのガンブレードと刃がぶつかり、火花が散る。
渾身の力を込めた一撃。アークの利き腕を狙い一気に振り下ろす。しかし、その攻撃は僅かにアークの軍服を掠めただけで空を切る。ガンブレードの銃口が目前に迫る。
「その動きは予測済みだ。終わりだな‥‥」
迫撃砲の一撃にも勝る元力弾の零距離射撃。骨すら溶かす灼熱の炎が銃口から吐き出される。
「‥‥アーク、お前のその動きもだ」
プログラム・クロノス、インストール。反応速度を5倍から20倍に設定。残像が弾け飛ぶと同時に、地面の雪が蒸発。小型のクレーターが出来上がる。
「ほんの挨拶代わりだ、次はない」
ナイフとブレードが交錯し、一旦間合いが離れる。
その時、夜空を切り裂く光に気づき、全員の動きが一瞬止まる。
“マローズの檻”のサイバーアイに数式が浮かぶ。座表計算、エネルギー充填、軌道修正。0.2秒で計算が終了する。
「天上からの雷の前に、焼き払われるがいい」
衛星軌道上の“マローズの檻”本体が、『ミョルニルの雷』をクラスヤノスクへと振り下ろす。天上からのレーザー掃射。正確無比な掃射に俺達に降り注ぐ。
だが、天上からの雷は全て雪の大地へと吸い込まれていった。辺りに穴が穿たれる。
「ふう。0.01秒ばかし、計算が遅かったみたいだな」
システムからの逆侵入。一瞬早く、凪月の流したプログラムが『ミュルニルの雷』の軌道をそらす。
「ほう、ミールシステムにまで侵入を果たすとは。惜しい人材だな、君は‥‥」
金色のストリーム上では、赤い衣の天使と鎧の騎士が剣戟を繰り広げていた。
フール・フールの吹く魔笛の音色が時間の流れを狂わせ、俺達の動きを鈍らせる。
モーガンの援護に“グッドアイズ”が加わるが、それでも苦戦を強いられていた。モーガンの放つ闇の力はことごとく弾かれ、“グッドアイズ”の振るう降魔剣も完全に捉え切れない。
「くすくす、こっけいだね君達は。まるで、人形劇みたいだ。‥‥・でも、それももう見飽きたな」
天使と見紛う微笑みを浮かべていた少年の顔が、残酷なアヤカシのものへと変わる。全てを溶かす大地の魔力がその小さな体に集束していく。
「これでもう、終幕だよ。‥‥・って、あれ?」
「‥‥黙れ」
アルテミス・プログラムの自動攻撃。アークと対峙したまま、俺は左手だけで“LP9”をフール・フールにポイント。魔力を放とうとしたフール・フールの首を吹き飛ばす。体を空中に残し、頭だけが地面に落ちる。
「あはははは、この僕がやられるなんてね。ほんと楽しいよ」
首だけになってもなお、アヤカシの少年は喋り出す。
「百年後、二百年後。また君達と会うことがあったら、遊んであげるよ」
そういい残すと、フール・フールの首はいつのまにか白い霧となり、掻き消えていく。その笑い声だけが耳に付く。
「お前は同族として許してはおけない‥‥」
『ドリームパーク』の時と同様、“グッドアイズ”の体が獣毛に覆われ、獣のものへと異形化を遂げる。
「ここで消えろ‥‥」
同時に霧へと変じた腕を虚空へと繰り出す。確かな手応え。
「な、なんだお前!?」
フール・フールの声が鈍い音にかき消され、“グッドアイズ”の豹の牙が真紅に染まる。
「‥‥‥‥・不味いな」
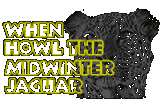
現実世界では死神と、金色のストリームでは赤き天使と、凪月はそれぞれの戦いで苦戦を強いられていた。
「いつまで、“それ”が続けられるかな」
『ミョルニルの雷』の狙いを逸らす為に注意がそれた凪月に死神は容赦なく襲い掛かる。灰色の大地を抉り取りながら、再び死の大鎌が振るわれる。片足を負傷していた凪月には避けれようも無い一撃。
しかし、その一撃を“グッドアイズ”の降魔剣が受け止める。
「死神か‥‥。ならば、まず俺を刈ってみろ」
“グッドアイズ”の降魔剣が一閃され、死神の腹を深々と切り裂いた。
「ふん、良いだろう。それなら、まず貴様を地獄の獣と対面させてくれよう」
燃え盛る大鎌と獣の剣。打ち鳴らされた二つの武器が雪夜に響く。
再び『ミョルニルの雷』が夜空を切り裂く。
「君の演算速度と、私の演算速度。どちらが早いかな」
赤き天使から放たれた必殺の槍。辛うじて凪月の計算が間に合い、狙いがそれる。
「驚いたよ。どうやら君の事を少々侮りすぎていたようだな」
賞賛の表情で“マローズの檻”は凪月を見下ろす。
「いや、それは買いかぶり過ぎだっての」
「しかし、これでチェックメイトだな」
駆風ピストルが凪月の顔面に突き付けられ、“マローズの檻”が銃弾を放つ。慌てて後ろに身を躱そうとするが、銃弾は正確に凪月を撃ち抜こうとしていた。
だが、その時再び『ミョルニルの雷』が凪月の目前に降り注ぐ。放たれた銃弾が一瞬の内に蒸発する。
「なに‥‥?!」
「お、おいおい、マジかよ!?あ、い、いや、狙いどうりだ。ふう、危なかったぜ‥‥」
冷や汗を流しながら凪月は間合いを離す。恐らく偶然流れたプログラムが、『ミョルニルの雷』を降らせたのだろう。凪月の前髪の先端が黒く焦げていた。

高振動ナイフとガンブレードが幾度となく火花を散らす。俺達の表情には、必殺の殺気と十年ぶりの懐かしさ、その両方が浮かんでいた。
ナイフの攻撃をかいくぐり、ガンブレードから灼熱の炎が吐き出される。
リミッター解除。反応速度を50倍に設定。全身の骨が軋み、細胞が声無き悲鳴を上げる。右手の刃を一気にアークの心臓めがけ繰り出す。
「まだだ‥‥。まだ、それでは俺は倒せない」
即死のはずの一撃がそらされ、アークの脇腹をかすめる。右腕が後ろに流れ、体勢が崩れた所に反撃の一撃が繰り出されようとしていた。引き金にかかったアークの指に力が入る。
「‥‥それは、分かってる。だから‥‥、これで終わりだ!」
後ろに流れた腕を折り曲げ背中に振り下ろす。それと同時に空いている左手でアークの体を固定する。鈍い音ともに、アークの右胸からナイフの刃が生えた。
「っぐ!!」
「‥‥アーク‥‥」
「クロノス‥‥。強く、なったな‥‥」
ゆっくりと崩れ落ちていくアーク。その表情はどこか穏やかで、微笑みを浮かべているようにも見えた。

「よし、出来たぜ!!」
並列で作業をしていた凪月が声を上げる。“マローズの檻”によってダウンさせられていたシステムの復旧。天使の赤い檻が全て破壊されていく。
「なるほど。並列でこれを進めていたとはな。負けたよ‥‥」
“マローズの檻”はインカムで部隊に戦闘終了を合図、インフェルナスに退却命令を伝えた。
「ここまでだな‥‥。今回は我々の負けだ、撤退する」
その声に応え、一機のワイズマン戦闘ヘリが頭上に現れる。
「君達の力を侮っていたよ。これで、ロシアの再建がまた10年遅れるだろう‥‥。だが、まだ10年だ。いずれ我々は、再び日の当たる国へと再生を果たすのだ。必ずな」
ゆっくりと身を翻し、“マローズの檻”はヘリに乗り込む。
「‥‥十年か。もしお前達が同じ事を考えているのなら、俺もまた同じ事をするだけだ」
“マローズの檻”が再び悲劇を繰り返すつもりならば、その前に何度だって立ちはだかってやる。俺はそう決意した。
独特のローター音を響かせ、ヘリは夜明け前の空へと飛び去っていった。
気が付くと雪はとうに止んでいて、空は白みかけていた。朝日とともに夜の時間は終わりを告げる。朝日が戦いの後を、雪の戦場を照らす。
その温かな日差しを浴びた時、真冬の夜(マローズ)など既に終わっているのではないか、俺達は皆そう思った。
朝日に照らされる雪の大地を眺めながら、“マローズの檻”は呟くように語る。
「‥‥圧倒的な戦力差をもってしても、どれだけ絶望的な状況でも、彼らは私に勝ったのだ。
我々が“真冬の夜”と思っていたものも、実は温かな日差しだったのかもしれない‥‥」
影の中の彼女の表情は、いまだよめない。その表情に浮かぶのは、喜びか、それとも‥‥
|
フール・フール「むぎゅう‥‥死んじゃったよう(T_T ≪霧散≫でおさらばしようと思ったのに‥‥」 |
-
Ending Faze -
| >> Scene33 『照らされる大地』 |
ゆっくりと昇る朝日が目に眩しい。吐き出される息は白く、ロシアの大地はまだまだ寒かった。
戦場から離れていたソーファとフレデリカの二人が戻って来た。それぞれの右手には拳銃が握られており、二人もまた自らを護る為に戦っていたのだろう。
「‥‥俺の渡した銃は、少しは役に立ったのかな‥‥」
ソーファとフレデリカ、それぞれが握っていたのは、俺が十年前に渡した“MP10”ピストル。
「はい、本当に役に立ちました。結局、姉さんみたいに上手くは撃てなかったんですけどね」
ソーファはそう微笑むと、ぎこちない手つきで銃をしまう。
「それで、いいんだよ‥‥」
何かを護る為には確かに力が必要だ。だけど、何かを護りたい、護る為に何かをしたい。ソーファやフレデリカのように、そう強く思う事はもっと必要なのだろう。
「そうですよね。私もソーファも貴方から教えて頂きましたから。どんな事があっても負けない心。負けない強い心を、銃と一緒に教えてもらいましたから」
フレデリカはそう微笑み、ゆっくりと銃をしまう。
人間の姿に戻り、ゆっくりと近づいて来た“グッドアイズ”がフレデリカに何かを手渡す。
「何にせよ、二人で生きていくなら必要になるだろう。持って行くんだな‥‥」
一通の大きな封筒。それを渡し、“グッドアイズ”は背を向ける。
「生き様を見せてみろ。そこまでして、護りたいもののな」
封筒の中身は、サンクトペテルブルグのとある屋敷の住所だった。レオニードが生前使っていた、誰も知らない町外れの屋敷。封筒の中身を確認し、戸惑うフレデリカ。
「あの、これは?‥‥どうして」
去り行く“グッドアイズ”の背中に、フレデリカはそうたずねる。
「気まぐれだ‥‥」
そう呟くと、“グッドアイズ”はゆっくりと歩き去って行った。
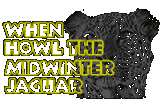
「今、金はいくら持っている?」
戦闘で穴の空いたコートのまま、モーガンはいつもの調子でフレデリカに話し掛けた。良くみると体のあちこちにも怪我を負っている。
「あ、済みません。お金まで持って出てくる時間が無かったもので‥‥」
予想外のモーガンの言葉に戸惑いつつ、表情を落すフレデリカ。屋敷が破壊され、残ったのはほんのわずかのシルバーのみ。モーガンに払う報酬には足りそうもない。
「それじゃたらねえな。出世したら、N◎VAに来て払いな」
そう言い残すと、モーガンは後ろ手に挨拶をし、ゆっくりと去って行った。

「ソーファはこれから、どうするんだ?」
ゆっくりと昇る朝日を眺めていたソーファに、凪月が声をかける。
「えっと、とりあえず『アルタイル』に戻って。あとは‥‥、まだちょっと分かりませんね」
ソーファは微苦笑しつつ、どこか楽しそうな様子で凪月の質問に答える。
「でも、凪月さん。本当にありがとうございました」
「いや、俺は何もしてないぞ。今回はたまたま運が良かっただけだ。それに、あんまり誉められるとかえって虫の居所が悪い」
いつものように素っ気無い凪月の言葉は、凪月なりの照れ隠しのつもりなのだろう。ちょっとムキになったソーファが答える。
「そんなこと、そんなことないですよ」
ソーファの真剣な言葉に、凪月は頬を掻きながら顔を背ける。まんざら悪い気もしないのだろう。その表情はどこか誇らしげだった。
「じゃ、またな」
「あ、凪月さん。是非もう一度、『アルタイル』に来てください。一番良い席を用意しておきますから」
歩き去ろうとした凪月の背中に、ソーファが声をかける。
「いや、一番安い席で良い。そんな良い席は落ち着かないからな」
そう答える凪月の言葉は、いつも通りのものだった。

雪に半分埋まったアークの体を土で埋め、ナイフで墓標を立てる。
アークの死顔はとても穏やかな表情だった。その表情には笑顔すら見て取れた。もしかしたらそれは、弟のもとへ行けた事を望んでいたからなのかもしれない。
十年前、俺はアークの弟とほとんど同じ年齢だったせいもあり、本当の弟のようにアークに可愛がられていた。報酬の出た日、酒場で弟の話しをするアークの表情は今でも心に残っている。
十年前の事件の後。弟が死んでからもアークが軍を辞めなかったのは、俺に殺される為‥‥だったのかもしれない。
再び降り出した雪が、ゆっくりと地面をおおっていく。ナイフの柄だけが射し込む朝の光に反射していた。

| >> Scene34 『4人と2人、それぞれ‥‥』 |
サンクト・ペテルスブルグにある落ち着いた雰囲気のレストラン。オペラ座『アルタイル』が見下ろせる位置にある窓際の席。
日付は、2072年12月28日。数日間、N◎VA行きの航空便を待っていたマット・マックス・モーガンは、ちょうど誕生日を迎えていた。
モーガンは毎年誕生日には1人で豪勢な食事をすることに決めている。
今回は飛行機の都合で夕食を諦めなくてはならないのだが、この店の味はそれを充分補えるだけのものだった。黙々と食事を続けるモーガンの前に何時の間にかペルソナ・ミストレスの女性、フレデリカが立っていた。
「相席、よろしいですか?」
「ん‥‥、ああ」
ちらっとだけフレデリカに目を向けると、モーガンは再び昼食を食べ始めた。いつも通りのモーガンの態度に安心したのか、フレデリカは「失礼します」と微笑み、静かに席に付く。その手には小さな花束が握られていた。
「有り難うございました、本当に」
「まあ、出世払いで待ってやるから、急がなくていいぞ」
昼食を食べ終えてそう答えるモーガンの言葉には、素っ気無さの中にも温かさがあった。
ふと、モーガンが視線を窓の外の『アルタイル』へと向ける。開演時間前の『アルタイル』は、公演を見に来た多くの人で賑わっていた。
「お前の妹も、ずいぶん人気だな」
机に置かれたフレデリカの花束に目線を戻すモーガン。その向こうには静かに微笑むフレデリカの笑顔。レストランに流れる音楽が、二人の時間を静かに彩っていた。

事件の後しばらくの時間が過ぎ。何事も無かったかのように『アルタイル』ではオペラが再開していた。“真冬の夜”の夜明けを歌う天使の歌声が、『アルタイル』を包み込む。
観客席の最上段から舞台の様子を眺めていた凪月は、ゆっくりと扉を閉めて入って来た俺に気付き、視線を向ける。
「‥‥どうしたんだ‥‥?こんな所に突っ立って」
オペラを聞きに来たにしては、凪月の様子は少しおかしかった。どこか苛立っているようで、それでいて吹っ切れたような、そんな表情をしていた。俺の質問には答えず、凪月が逆に聞いていた。
「さて、ここで問題。オペラにつきものといえばなんだと思う? 1.銃、2.酒、3.花束」
おかしなことを聞いて来た、3以外にどう答えろと言うのだろうか。
「‥‥3、かな‥‥。でも、残念ながら俺は、花束なんか持って来てないよ」
「だろう?オペラには花束がつきものだ。持って行ってやれ!」
どこから取り出したのか、凪月の手には花束が握られていた。俺の手に強引にそれを持たせる。
「‥‥‥‥わかった」
2秒。実際に、2秒考えてから俺は答えた。
「俺は行くぞ。じゃあな!」
凪月はそう言うと、門をくぐり『アルタイル』を出て行った。
「ったく、可愛かったよなー!いい子だったよなー!何であいつばっかり!しっかも、俺の相手は死神だし、ったく‥‥!!」
悪態を吐きながらも、凪月の表情はどこか吹っ切れた晴れ晴れとしたものだった。頭上にある、ロシアの青空のように。

凪月に花束を手渡されたまま、俺は観客席の最上階から公演を眺めていた。今日が最終公演日という事もあり、座席は全て観客で埋まっていた。
歌姫への花束贈呈、どうやらそれが俺の最後の役割らしい。公演が終了し、観客の拍手で包まれる中をゆっくりと階段を下りて行く。
前方の座席から一人の男が立ちあがり、階段を上りこちら側へと近づいてくる。スーツに身を包んだ長身痩躯のレッガー、“グッドアイズ”。知り合いのフェイト、モーガンとは親友同士であり。ソーファやフレデリカとは、ファミリーにあたる人物。
どちらが道を譲るでもなく、俺達は自然に階段をすれ違おうとしていた。
「ファミリーを助けてくれて礼を言う。俺はこれ以上、家族を失いたくない‥‥」
「‥‥俺の方こそ、ありがとう‥‥」
すれ違いざまに短く言葉を交し、再び階段を下りて行く。
観客達の鳴り止まぬ拍手の中、ゆっくりと舞台の上へとあがる。舞台には、ソーファと『アルタイル』の劇団員達。
右手には、凪月から渡されたゼラニウムの花束。花言葉は‥‥一体何だったろうか。戦乙女の衣装のソーファに花束を手渡す。今更ながら、自分の場違いな雰囲気に少し溜め息を付く。
「‥‥なんだか知らないけれど、俺がこんな物を渡す事になったよ‥‥」
「でも、私は貴方から頂くのが一番嬉しいんです」
恭しく花束を受け取った歌姫は、にっこりと微笑んだ。慣れない周りの状況に、俺はただ苦笑するばかり。
「ふう‥‥、俺にはこんなのは似合わないな。こういうのは、これっきりにして欲しい」
「そうなんですか‥‥?でも嬉しいのは本当なんですよ‥‥」
そう言って、ソーファは正面に立つとそっと俺の頬に口付けをした。一瞬だけ、胸の鼓動が早くなるのを感じる。凍っていた時間が動き出したようなそんな感覚に。
「ソーファ‥‥。悪いけど、もう少しだけ世界を回ってくる。まだ、ほんの少しだけやるべき事がある、そんな気がするんだ」
アークとの決着がつき、“ロマノフの遺産”が封印された今。十年前からの物語は全て終わりを告げた。だけど、いやだからこそ、もう少しだけ世界を回ってみたかった。物語にはまだ続きがあるのだから。
「クロノスさん、でも‥‥」
「ああ、もちろん。また‥‥、戻ってくるよ」
ソーファの瞳を見つめながら俺は答えた。一際、観客の拍手が大きくなる。俺は観客席に向き直り、ゆっくりと芝居じみた一礼をする。
「‥‥これにて物語は終了。再び運命の糸が紡がれる時まで‥‥」
その言葉だけを残して、影に溶け込み舞台から退場する。
舞台に残ったのは、観客達の拍手と微笑むソーファの笑顔。その二つとともに、舞台を照らす照明が“真冬の夜”の夜明けを象徴していた。

いつかは分からない時、場所は落ち着いた雰囲気のバー。店の中には“グッドアイズ”と店のマスターのみ。二人はカウンターに差し向かいに座り、“グッドアイズ”が話をしている。
“グッドアイズ”の前には、バーボンが並々と注がれたオンザロック。偉大なる父、レオニード・アルサノフが好きだった銘柄。カラン、と氷が解けた音が話を締めくくる。
「‥‥と、こんな話が有ったのさ‥‥」
「あんたも、凄い経験をしたんだな」
偉大な男の仇討ちの話。決して世に出る事の無い遺産の話。そして、十年前から続いた二人の姉妹の物語
。それぞれの話に店のマスターは相づちを打ちながら、ただ頷く。
店の中には、静かなオルゴールの音色が流れていた。レオニードが持っていた悲しい音色のオルゴール。それでいて、どこか懐かしく心を落ち着かせるオルゴールが。
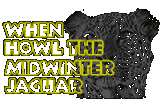
オルゴールの音色が流れるまま、場面だけが切り替わる。
場所は、ロシア連邦サンクト・ペテルスブルグ。訪れる者もほとんど居ない閑静な墓地。そこに、偉大なる男、レオニードの墓はあった。
墓標の前に一枚の写真が置かれている。色褪せてセピア色になってしまった、家族の肖像。
姉の弾くヴァイオリンの音色に合わせて歌う妹。そして、それを眺める父と母。そこにあるのは、幸せな家族の笑顔。ただそれだけだった。
|
フール・フール「ふう、しっかしなが〜いレポートもやっとエンディング。ここまで読んでくれて、読者の皆さんご苦労様って奴だね」 |
| >> Scene35 『十年先のクリスマス』 |
一枚の写真。写っているのは『アルタイル』の貸し切りの上演会。荘厳な大ホールに、たった四人だけの観客。
舞台の上には、二人の姉妹と劇団員達。バイオリンを演奏する姉フレデリカと、春を歌う妹ソーファ。曲目はもちろん、“真冬の夜を越える日”。
その様子を、思い思いの表情で眺めている四人の男達。最前列の席で熱心に曲に聞き入る少年。窮屈そうに座席に体を埋める巨体の男。その横を静かに通り過ぎて目線だけを交す長身痩躯の男。そして、最後尾の座席で静かに壇上を眺める青年。
そんな面々を前に、壇上ではロシアの星が歌っていた。響き渡るは天使の声、歌に語るは春の兆し。アルタイルの歌姫の胸には、変わらずの真紅の涙が、その主の内なる光りを宿して輝いていた。
A
story was finished with this.
Until the thread of the destiny is spun again.

Spesial thanks to:
HATA HATA
for
Ur Another Story of Midwinter Nite!
![]()
RI-Foundation > Access 100K > Hata-Maro 3 10万Hit記念ページへ
10万Hit記念ページへ |