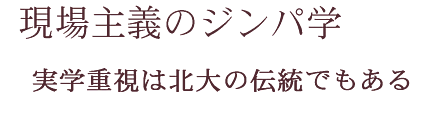丂慜夞偼杒嫗偵偁偭偨惓梲極偵傑偮傢傞巚偄弌傪徯夘偟傑偟偨偑丄僕儞僊僗僇儞椏棟偙偲僇僆儎儞儘乕偺杮応偱偡偐傜偹丄壆戜傕偨偔偝傫偁偭偨偺偱偡丅戝偒側撶傪埻傒丄曅懌忋偘偰從偐偣傞揦偽偐傝偱側偔偰偹丄僐僢僋偑從偄偰嶮偵惙偭偰弌偡椏棟揦傕娷傔傞偲丄嶥杫偵偍偗傞儔乕儊儞揦偺晛媦棪偵嬤偄偖傜偄僇僆儎儞儘乕揦偑偁偭偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
丂徍榓侾係擭偵杒嫗擔杮彜岺夛媍強偑弌偟偨乽杒嫗彜岺柤娪徍榓廫巐擭斉乿偵杒嫗斞憫摨嬈岞夛偲偄偆抍懱偺夛堳柤曤偑嵹偭偰偄傑偡丅扨側傞柤曤偱寢惉偺栚揑側偳偑彂偐傟偰偄側偄偺偱傢偐傝傑偣傫偑丄拞崙恖宱塩偺椏棟揦慻崌偺傛偆側傫偱偡丅揦柤偲偍偍傑偐側廧強偲宱塩幰偺柤慜偟偐彂偄偰偄側偄偗傟偳偹丄悢偊傞偲俀侽俆揦偁傞丅慜夞榖偟偨惓梲極丄偒傚偆庢傝忋偘傞搶棃弴偼偪傖傫偲擖偭偰偄傞偟丄慡晹偱偼側偄傛偆偩偑丄惓摑攈偺桳柤揦傕壛柨偟偰偄傑偡丅(1)偦偺儕僗僩偼丄偄傑昁梫偲偟側偄偺偱攝傝傑偣傫偑丄嶲峫帒椏偲偟偰巹偺島媊榐偺儂乕儉儁乕僕偺曽偱尒傜傟傞傛偆偵偟偰偍偒傑偡丅亙島媊榐傪尒偰偄傞恖偼偙偙傪僋儕僢僋偟側偝偄丅亜
丂斞憫偲偄偆偺偼戝偒側椏棟揦傪巜偡偺偩偐傜丄拞彫楇嵶偺椏棟揦偼擖偭偰偄側偄偼偢偱丄傑偟偰傗丄偦偺拞偺僕儞僊僗僇儞傪弌偡揦偲側傟偽墝偺拞丄尒偊偵偔偄丅拞崙岅偺杮偵傕懡暘彂偄偨傕偺偼側偄偱偟傚偆丅
丂崅栘寬晇偼乽烤梤擏偼惓梲極偲搶棃弴偲惣棃弴偩偗偩偲巚偭偨傜戝傑偪偑偄偱丄傑偩傑偩業揦偱傕偆傑偄偲偙傠偑偁傞丅(2)乿偲偄偭偰偄傑偡偑丄杒嫗傪朘傟偨擔杮恖偺懡偔偼丄偦偆偟偨摴偽偨偱僕儏乕僕儏乕從偄偰偄傞揦側傜埨偔忋偑傞偲偼抦傝偮偮傕丄偩傟偐偐傜嫵傢偭偨偪傖傫偲偟偨揦峔偊偺椏棟揦傊擖偭偨傛偆偱丄惓梲極埲奜偱偼丄搶樢弴偲偄偆椏棟揦偵偮偄偰偺巚偄弌偑懡偄丅偳偪傜偐偲偄偊偽 梤擏偺曽偑懡偄傛偆偱偡偑偹丅偝傜偵攕愴慜丄偮傑傝徍榓俀侽擭埲慜偵杒嫗傪朘傟偰丄揦偺柤慜偼柧婰偟偰偄側偄偗傟偳傕丄僕儞僊僗僇儞傪怘傋偨巚偄弌偑傑偩傑偩偁傞偺偱丄偒傚偆偼偦偆偟偨巚偄弌傕壛偊偰榖偟傑偟傚偆丅 梤擏偺曽偑懡偄傛偆偱偡偑偹丅偝傜偵攕愴慜丄偮傑傝徍榓俀侽擭埲慜偵杒嫗傪朘傟偰丄揦偺柤慜偼柧婰偟偰偄側偄偗傟偳傕丄僕儞僊僗僇儞傪怘傋偨巚偄弌偑傑偩傑偩偁傞偺偱丄偒傚偆偼偦偆偟偨巚偄弌傕壛偊偰榖偟傑偟傚偆丅
丂偙傟偼丄庢傝傕捈偝偢僕儞僊僗僇儞椏棟偲偄偆婏柇側柤慜偼丄杒嫗偐傜峀傑偭偨偲偄偆杒嫗敪徦愢傪曗嫮偡傞傕偺偱偁傝丄僕儞僷妛偲偟偰偼枮廎敪徦愢偲斾妑専摙偡傞偨傔偵傕丄偦偺廂廤偵搘傔偰偍傞偲偙傠偱偁傝傑偡丄側乕傫偰丄偦偙傜偺摉嬊摎曎傒偨偄偩偹丅
丂偦偙偱偩丄惓梲極偲摨偠傛偆偵擭戙弴偵榖偦偆偲峫偊偨偑丄搶棃弴偺偼惓梲極偲堘偭偰丄徍榓侾侽擭戙偵廤拞偟偰偄偰柧帯丄戝惓偺夞憐偑側偄丄偄傗尒偮偐偭偄側偄傫偱偡丅偦傟偱揦偺惗偄棫偪偐傜巒傔傞偙偲偵偟傑偡丅偦偺慜偵丄帒椏傪攝傝傑偡偐傜偹丄偪傚偭偲懸偭偨丅偼偄丄峴偒搉傝傑偟偨偹丅偍傎傫丄偙傑偛傑偨偔偝傫偁傞偱偟傚偆丅
丂惓梲極偱傕堷梡偟偨懞忋抦峴偼搶棃弴偑偍婥偵擖傝偩偭偨傛偆偱丄挊彂乽杒嫗嵨帪婰乿奐揦偵傑偮傢傞堩榖傪徻偟偔彂偄偰偄傑偡丅恖惗孭偲偟偰傕撉傔傞傕偺偱偁傝丄帒椏偦偺侾偵搑拞傪徣棯偣偢偵堷梡偟偨偺偱丄挿偔側傝傑偟偨偑丄挊嶌尃宲彸幰偺曽偺偛椆彸傪偍婅偄偟偰偍偒傑偡丅
帒椏偦偺侾
丂橎偰巹偼崯檤偱丄搶樢弴偵偮偄偰堦尵偟傛偆丅
丂巹偼崱枠丄擔杮偐傜偺媞傪悘暘偦偙偵桿偮偨偑丄扤堦恖偲偟偰揦偺戝偒偄偺偲丄媞偺崿嶨偵嬃偐偸恖偼側偐偮偨丅庩偵斢斞帪偺嶨椐偵帄偮偰偼丄巐奒寶偰偺揦慡懱偑丄婔昐恖偐偺媞偱丄朓偺憙偺傗偆偵噏乆歑偮偰傤傞丅
亀堦懱丄崯偺揦偵偼壗恖儃乕僀偑傤傞偺偐丠亁
丂巹偼偁傞帪丄儃乕僀偺堦恖偵巣偆暦偄偰傒偨丅
亀昐嶰廫屲恖傤傑偡傛丅巹側傫偞傕偆崯偺揦偵嶰廫擭娫嬑傔偰傤傑偝傾丅亁
丂摎偼巣偆偩偮偨丅崯偺昐嶰廫屲恖偲偄傆偺偼丄椏棟恖偩偺挔応偩偺丄偦偺懠偺巊梡恖傪彍偄偨悢偱丄偟偐傕擔杮偺僇僼僄乕偺彈媼偺傗偆偵柍梡偺懚嵼偱偼側偄偺偩丅壖偵堦恖偱屲恖偺媞乮帠泬偼偦傟埲忋偩傜偆乯傪埖傆偲偟偰傕丄堦帪偵榋昐恖埲忋偺媞偵墳愙偡傞偙偲偑弌樢傞姩掕偩偐傜丄挬偐傜斢傑偱偵弌擖傝偡傞媞悢偼戝偟偨傕偺偵堘傂側偄丅
丂揦偺庡恖偼挌巕惵偲偄傆丅斵偼夞嫵搆偱丄偦傕乛乢偼恎偵懏偡傞堦暔傕側偄嬯椡偩偮偨丅寣偲娋偲丄扅偩偦傟偩偗傪帒杮偲偟偰偺婔擭偐偺嬯摤偺屻丄傗偮偲彫嬥傪挋傔摼偨斵偼丄崱偦偺嫄戝側揦傪奐偄偰傤傞摨偠搶埨巗応偺曅嬿偵丄宍偽偐傝偺業揦傪挘偮偰査乮擔杮偺偆偳傫傒偨偄側傕偺乯傪攧傞偙偲偵偟偨丅偦傟偑崱偐傜擇嶰廫擭慜偩丅
丂偁傞擔偺偙偲丄斵偺揦偵棫婑偮偨堦恖偺榁恖偑偁傞丅偦偺榁恖偑棫嫀偮偨偁偲丄晄恾尒傞偲懘檤偵姄偑抲偒朰傟偰偁偮偨丅
丂斵偼憗懍偦傟傪書傊偰榁恖偺峴塹傪捛偮偨丅恖崿傒偺巗応偺拞傪巄偟塈業乆乆偟偰傒偨偑悑偵憑偟弌偣側偄丅帋傒偵姄傪奐偗偰傒傞偲丄嶥懇偑堦攖偩偮偨丅
亀庛偮偨側両亁偲斵偼欔偄偨丅亀曉偟偰傗傝偨偔偰傕憡庤偼壗檤偺扤偲傕暘傜側偄偍媞偩丅憗偔庢傝樢偰偔傟乀偽岲偄偑両丂偳偆偣婞偰乀抲偔栿偼側偄丅洣搙庢栠偟偵偼樢傞偩傜偆丅偑丄偦傟偵偟偰傕丄壌偼傒偡傏傜偟偄業揦彜恖偩丅崱枠偍栚偵偐乀偮偨偙偲傕側偄崯偺戝嬥傪梐偮偰丄傂傛偮偲搻傑傟偱傕偟偨傜偳偆偟傛偆偐両亁
丂斵偼尵棄捠傝偵庛傝愗偮偨丅彜攧傕犸偵庤偵偮偐側偐偮偨丅
丂榁恖偼槵婜偵斀偟丄梻擔傕丄傑偨偦偺梻擔傕巔傪尒偣偢丄搆傜偵斵偺婥傪潌傑偣傞偽偐傝偱偁偮偨偑丄巐屲擔宱偮偰朘偹偰樢偨丅
亀庒偟傗乨乨亁
丂榁恖偼巣偆栤傂偐偗偨丅慠偟奆傑偱栤傆昁梫偼側偐偮偨丅斵偺曽偱桇傝偁偑傞掱婌傃側偑傜丄
亀偙傟偱偛偞偄傑偣偆丠亁
丂偲姄傪嵎弌偟偨偺偱偁傞丅
丂榁恖偼偦偺婔擔偐偺娫丄怱忢傝偺彅乆曽乆傪恞偹曕偄偨偺偱偁傞偑丄嵟屻偵晄恾巚傂弌偟偨偺偑丄査傪嬺偮偨業揦偺偙偲偱偁傞丅偟偐偟乨乨偲榁恖偼峫傊偨丅傛偟傫偽偁偦偙偵抲偒朰傟偰傤偨偵偣傛丄憡庤偼業揦彜恖偱偁傞丅錟偟偰丄抦傜偸偲尵傊偽偦傟傑偱乁偼側偄偐両丂巣偆巚偮偰寢嬊掹傔偨偑丄偦傟偱傕擮偺偨傔棫婑偮偰尒偨偺偩偮偨丅
亀傎傫偲偵丄傛偔樢偰壓偡偮偨丅樢傞擔傕乛乢壌偼崯傟傪書傊偰丄偳傫側偵怱攝偟偨偱偣偆丅亁
丂巣偆尵傂側偑傜丄姄傪栠偡斵偺巔偑丄榁恖偺娽偵偼偝側偑傜亀婏愔亁偦偺傕偺偩偮偨丅偦偺屻榁恖偼斵偵丄偝乀傗偐側揦傪堦尙寶偰乀傗偮偨丅偦傟偑崱擔偺搶樢弴偺夎惗偊偩偮偨偺偱偁傞丅
丂崯偺儘儅儞僗偼丄杒嫗偱曊偔抦傜傟丄恖乆偼挌巕惵偺惉岟傪丄惓捈偺摽偵晈偟偰傤傞偑丄巹偼擩傠丄嬼慠庤拞偵棊偪偨戝嬥偵埶棅偟傛偆偲偟側偐偮偨丄壥姼側傞斵偺撈棫怱偲搘椡偲偵婣偡傋偓偰側偐傜偆偐偲巚偮偰傤傞丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮侾乯偺弌揟偼捤杮 惓屓曇乽徍榓廫巐擭杒嫗彜岺柤娪乿係侽俆儁乕僕丄徍榓侾係擭侾侽寧丄杒嫗擔杮彜岺夛媍強亖尨杮丄
乮俀乯偼崅栘寬晇挊乽杒嫗斏惙婰乿侾俁俉儁乕僕丄徍榓俁俈擭俋寧丄愥壺幮亖尨杮丄
帒椏偦偺侾偼懞忋抦峴挊乽杒嫗嵨帪婰乿俀俆俈儁乕僕丄徍榓侾俆擭俇寧丄搶嫗彂朳亖尨杮
|
丂拞栰尓擇偼乽涮梤擏偼惔偺欦朙巐擭乮堦敧屲屲擭乯偵奐揦偟偨慜栧奜偺惓梲極偑嵟傕楌巎屆偔桳柤偩偭偨偑丄堦嬨巐擇擭惿偟偔傕攑嬈偟偨丅尰懚偡傞偺偱偼搶晽巗応偺搶棃弴乮堦嬨乑嶰擭奐嬈乯偑傛偔抦傜傟丄崈昽極傕搤偺偆偪側傜傗偭偰偔傟傞丅(3)乿偲乽怴杒嫗嵨帪婰乿乮俀俆俀儁乕僕丄徍榓俆俇擭俆寧丄搶曽彂揦亖尨杮丄乯偵彂偄偰偄傞偺偱丄奐揦偼柧帯俁俇擭側偺偱偡偹丅偙偺擭偼儔僀僩孼掜偑儔僀僩僼儔僀儎乕偱旘峴偵惉岟偟偨擭偱偁傝丄搶棃弴傕傑傞偱旘峴婡傒偨偄偵敪揥偟偰丄惓梲極偲暲傇榁曑偵側偭偨偺偱偡側偁丅戝捤椷嶰偼乽惓梲極丒惣樢弴丒搶樢弴偼梤擏傪埲偰柭傞丅(4)乿偲彂偔偺偼摉傝慜偩偭偨偺偱偡丅
丂抾撪岲偼丄偡偽傝乽搶棃弴乿偲偄偆曬崘傪彂偄偰偄傑偡丅乽抾撪岲慡廤乿侾係姫偵廂傔傜傟偰偍傝丄斞憅徠暯巵偺夝戣偵傛傟偽丄徍榓侾俈擭偵弌偨乽夞嫵寳乿偲偄偆嶨帍偵宖嵹偝傟偨(5)傕偺偩偦偆偱偡偑丄斵偺擔婰偵傕壗搙傕搶棃弴偑弌偰偔傞偙偲偐傜傒偰丄抾撪偼懞忋偲摨偠傛偆偵搶棃弴僼傽儞偩偭偨偲巚傢傟傑偡丅
丂傎傏摨偠帪婜偵彂偄偨偲傒傜傟傞偺偵揦庡偺柤慜偑懞忋偲堘偭偰偄傑偡丅巕惵偼憂嬈幰偱摽婱偲偄偆偺偼丄巕嫙偐懛偱偼側偄偐側丅偄偢傟偵偟偰傕夞嫵搆偺挌偲偄偆堦壠偑宱塩偟偰偄偨偺偱偟傚偆丅愴慜偺搶棃弴偺奣梫傪抦傞傛偄堦暥偲偟偰帒椏偦偺俀偵堷梡偝偣偰傕傜偄傑偟偨丅
帒椏偦偺俀
丂丂丂搶棃弴
丂杒嫗偺搶埨巗応偲偄偊偽丄惣扨彜応偲暲傫偱丄擔杮恖偵傕桳柤側彜揦奨偱偁傞丅彜揦奨偲偄偆傛傝傕丄堦庬偺僶僓乕偱偁傞丅堦奻偺拞偵丄悢昐尙偺彜揦偑枾廤偟偰偄傞丅杒嫗偺柤強偺堦偮偱偁傞丅偦偺拞偵椏棟揦偺僽儘僢僋偑偁偭偰丄偦偺拞偺堦偮偵搶棃弴偲偄偆偺偑偁傞丅搶棃弴偼夞嫵搆偺宱塩偡傞椏棟揦偱偁傞丅擔杮恖偵偼丄夞嫵偲偄偆傛傝僕儞僊僗僇儞椏棟偲偟偰抦傜傟偰偄傞丅僕儞僊僗僇儞椏棟偺杮摉偺柤偼丄烤梤擏偲偄偆丅梤偺擏傪巻偺傛偆偵敄偔愗偭偰丄擪側偳偺栻枴傪揧偊丄忀桘偵傂偨偟偰丄摿庩側揝斅偺忋偱從偒側偑傜怘偆偺偱偁傞丅揝斅傪擬偡傞偵偼摿庩側恉偑巊傢傟傞丅堦偮偺揝斅傪悢恖偑埻傒丄棫偪側偑傜丄曅懌傪斅偺戜偵抲偄偰丄栰揤偱徿枴偡傞丅庰偼丄岮傪從偔崅怆庰偑揔偆丅崌娫偵寴偔從偄偨僷儞偵帡偨從栞傪姎傞丅搤偑婫愡偲偝傟傞丅栰庯偑偁偭偰丄偆傑偔偰楑偔丄擔杮恖偵傕愄偐傜婌偽傟偰偄傞丅烤梤擏偼丄杒嫗偱偼丄偙偺揦偲傕偆堦尙惓梲極偲偑桳柤偱偁傞丅
丂烤梤擏偺傎偐偵丄涮梤擏乮壩撶巕乯偲偄偆偺傕偁傞丅偙傟偼摨條偺擏偺悈暟偒偱偁傞丅摿壱偺撶傪梡偄丄摿姅偺栻枴傪挷崌偟偨廯偵偮偗偰怘偆丅偝偭傁傝偟偰丄偆傑偄傕偺偱偁傞丅搶棃弴偱偼丄晛捠偺椏棟傕嶌傞偑丄偲偔偵偙偺擇偮偑娕斅偱丄媞偼戝掞偦偺壗傟偐傪拲暥偵壛偊傞偙偲偑懡偄丅
丂梤擏偺傎偐偵丄媿擏傕拲暥偱偒傞丅崱搙峴偭偨偲偒偼梤擏偑嫙媼晄懌偱丄媿擏偺曽傪懡偔弌偝傟偨丅偟偐偟撠擏偼愨懳偵巊傢側偄丅宱塩幰偑夞嫵搆偩偐傜偱偁傞丅偦偺揰偩偗偑丄傎偐偺椏棟揦偲偪偑偆偺偱偁傞丅
丂杔偼堦擔丄巗惌晎傊嬑傔傞桭恖偲偙偙傊斞傪怘偄偵峴偭偨丅桭恖偼偁傞帠審偺夝寛偵恠椡偟偨娭學偱丄偙偙偺庡恖偱偁傞挌摽婱巵偵楯傪懡偲偝傟丄偦偺擔傕娊懸偵偁偢偐偭偨丅庰娫偲偰棫擖偭偨榖偼弌棃側偐偭偨偑丄惉岟偟偨夞嫵搆彜恖偺揟宆偵愙偟偨偩偗偱傕堄奜偺廂妌偱偁偭偨丅偙偺揦偼丄堦擔嶰愮尦偺攧忋偘偑偁傞偲桭恖偼悇掕偟偰偄偨丅惻嬥偐傜妱弌偟偨偺偩偐傜枩峏嫊峔偱偼側偄傛偆偱偁傞丅揦偺奿幃偐傜塢偆偲丄擇棳丄偁傞偄偼嶰棳側偺偩偑丄攧忋偘偺揰偱偼杒嫗戞堦偩偦偆偱偁傞丅峔偊偼偒偨側偄偑丄偦傟偱傕愄偐傜尒傞偲戝暘棫攈偵側偭偰偄傞丅嶰奒寶偱丄堦帪偵悢昐慻傕廂梕偱偒傞丅偦傟偑怘帠帪偼杦偳嬻惾偑側偄丅戝偟偨斏徆偱偁傞丅偦傟傪塢偆偲丄庡恖偼偟偒傝偵尓懟偺尵梩傪塳偟偰偄偨偑丄堦彧昐嬥傪嶶偢傞墐夛椏棟壆偲偟偰偱側偔丄偄傢偽戝廜椏棟壆偲偟偰崱擔偺杒嫗堦偺抧埵傪抸偄偨揰偑丄偲偔偵宧暈偡傋偒傕偺偵巚偊偨丅亙棯亜
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮俁乯偺弌揟偼拞栰尓擇挊乽怴杒嫗嵨帪婰乿俀俆俀儁乕僕丄徍榓俆俇擭俆寧丄搶曽彂揦亖尨杮丄
乮係乯偼枮栔暥壔嫤夛曇乽枮栔乿侾俆擭俀崋侾俉俋儁乕僕丄戝捤椷嶰乽杒嫗椏棟崱愄婰乿丄徍榓俋擭俀寧丄枮栔暥壔嫤夛亖尨杮丄
乮俆乯偼抾撪岲挊乽抾撪岲慡廤乿侾係姫俆侽俉儁乕僕丄斞憅徠暯乽夝戣乿丄徍榓俆俇擭侾俀寧丄拀杸彂朳亖尨杮丄帒椏偦偺俀偼摨俁俇俀儁乕僕丄摨
|
丂偱偼搶棃弴偑偳傫側揦峔偊偩偭偨偺偐丅栭偺幨恀側偺偱傎偲傫偳傢偐傜側偄偺偱偡偑丄杒嫗偺梤擏揦傪嶣偭偨偙偆偟偨幨恀偑巆偭偰偄傞偩偗偱傕捒偟偄偺偱丄僗儔僀僪偱傒偣傑偟傚偆丅偼偄丄偙傟偼埨摗峏惗偲偄偆怴暦婰幰偑徍榓侾俇擭偵弌偟偨乽杒嫗埬撪婰乿偲偄偆杮偺乽杒嫗偺斞娰巕乿偲偄偆復偵嵹偭偰偄偨傕偺偱偡丅偩偐傜幨恀偺嵍忋偵乽杒嫗偺斞娰巕乿偲擖偭偰偄傞偺偱偡丅搶棃弴偲塃彂偒偟偨娕斅偼揹摂偺岝偑幾杺偱偡偑丄側傫偲偐撉傔傑偡丅
丂埨摗傕乽夞嫵宯偺夞夞娰偲塢傆偺偑偁傞丅偙傟偼栧岥傪尒傞偲堦栚偱傢偐傞傗偆偵夞乆偺暥帤埥偼乽夞夞惔崃乿偲偐彂偄偰偁傝媿偲梤傪庡偲偟撠偺椏棟偼愨懳偵嶌傜側偄丅(6)乿偲彂偄偰傑偡偐傜丄搶棃弴傕昞偺偳偙偐偵偦偆偟偰昞帵偑偁偭偨偼偢偱偡偑丄偙偺幨恀偱偼慡慠傢偐傝傑偣傫偹丅
丂傕偭偲傢偐傜傫幨恀偑墱栰偝傫偺乽杒嫗璧婰乿偵偁傝傑偡傛丅乽搶埨巗応偺屵慜搶棃弴梤擏娰偺慜捠傝丄戝杒嫗偺挬偺屰摦丅(7)乿偲愢柧偟偰偄傞偺偱偡偑丄傎偲傫偳恀偭崟偺夋柺偺塃忋偐傜幬傔偵嵶偄岝偑嵎偟崬傫偱丄俇丄俈恖偺巗柉偑彫楬傪曕偄偰偄傞偺偑傗偭偲傢偐傞掱搙側偺偱妱垽偟傑偟偨丅偙傟偺曽偑偼傞偐偵儅僔偱偡傛丅
丂丂丂丂
丂丂乮埨摗峏惗挊乽杒嫗埬撪婰乿傛傝乯
丂埨摗偺乽杒嫗埬撪婰乿偼乽愭偯杒嫗偺庡側椏棟壆偲丄偦偺摼堄側椏棟丄媦傃強嵼傪挷嵏偟偨偺傪嫇偘埲偰嶲峫偵嫙偡傞丅乿偲偟偰丄嶳搶椏棟傪摼堄偵偡傞椏棟揦傪嶳搶娰偲偄偆彂偒曽偱挷巕偱嶳搶娰侾俉偱偙傟偑嵟傕懡偄丅埲壓偼熖梘娰俈丄閩愳娰俇丄峀搶娰係丄婱廈娰侾丄梤擏娰俉丄壨撿娰俀丄惛恑椏棟壆俀丄惣梞椏棟俋偲偵暘偗偰崌寁俆俈揦傪徯夘(8)偟偰偄傑偡丅帒椏偦偺俁乮侾乯偼偦偺梤擏娰傪敳偒弌偟偨傕偺偱偡丅嵟屻偺堦悿墍偲偄偆梤擏娰偼廧強傕壗傕偁傝傑偣傫偑丄屻偱榖偡彫愢壠崅尒弴偑朘傟偨揦偲偟偰嫇偘偰偄傑偡丅
丂壗恖偐偑搶棃弴偼壆忋偱從偔傛偆偵側偭偰偄傞偲彂偄偰偄傑偡丅傛偔抦傜傟偰偄傞偺偑丄塱堜棿抝偺抁曇乽庤傇偔傠偺偐偨偮傐乿偱偡偹丅暯惉侾俆擭偺摴怴偺乽扵掋抍偑偨偳傞僕儞僊僗僇儞暔岅乿偱傕徯夘偝傟偨丅偝傢傝傪帒椏偦偺俁偵偟偨偐傜尒偰壓偝偄丅偙偺拞偺乽惉媑巚娋乮僕儞僊僗僇儞乯撶偼丄搶埨巗応乮僩儞傾儞僔乕僠儍儞乯偺壆忋偵偁傞偺偩偝偆偱(9)乿偲偄偆屄強偼彫妛娰偺乽擔杮崙岅戝帿揟乿戞俀斉偺乽僕儞僊僗僇儞撶乿偺梡椺偵庢傝擖傟傜傟偰偄傑偟偨丅帿揟偺梡椺偱偼帺枬偟偨偄偙偲偑側偄傢偗偱偼側偄偗偳丄傑偨偺婡夛偵偟傑偟傚偆丅
丂帒椏偦偺俁乮侾乯偼丄埨摗偺乽杒嫗埬撪婰乿偺梤擏娰偺敳悎丄偦偺乮俀乯偼塱堜偵傛傞搶棃弴偺撶偺昤幨偱偡丅
帒椏偦偺俁
乮侾乯
丂丂丂丂梤擏娰
搶棃弴丂丂涮梤擏丄烤梤擏丄檡栥寋
丂丂丂丂丂鄖梤擏丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搶埨巗応
惓梲極丂丂烤梤擏丄涮梤擏丄搴
丂丂丂丂丂奍椏棟丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂慜奜擏巗
惣樢弴丂丂仭亙侾帤晄柧亜嶰敀丄嵐撶嫑憷丄
丂丂丂丂丂烤梤擏丄涮梤擏丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂惣挿埨奨
摨榓尙丂丂愳嶶扥丄栘鈕擏丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂慜奜棝鑓夳幬奨
椉塿尙丂丂搩巣枾丄鄘嶰條丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乂
淎暉嫃(懎偵杝壠陰)丂鄒烤醫鄺媿擏丂丂丂丂丂丂屲摴昣
摨阙娰(懎偵镼栞廃)丂镼栞丄悈敋梤
丂丂丂丂
丂丂丂丂丂丂汴丄烤涮梤擏丂丂丂丂丂丂攣巗奨
堦悿墍
摨乮俀乯
丂庤傇偔傠偺偐偨偮傐
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂塱堜棿抝
丂亙棯亜
乽愭惗丄愭惗乿偲婲偝傟偰傤偨丅亊偝傫偐傜揹榖偲偄傆偙偲偩丅
乽弌妡偗偵堦悺擿偄偨偑柊偮偰傤偨偺偱乗乗丄姦偔側偗傟偽丄亊孨傪寎傂偵忋偘傞偐傜弌偰偄傜偮偟傗偄丅弶愥偺拞偱丄烤梤擏傪屼抷憱偟傛偆丅偙偙偱偼弶傔偰偱偣偆乿亙棯亜
丂亊孨偑寎傊偵棃偰屶傟偨丅惉媑巚娋撶偼丄搶埨巗応偺壆忋偵偁傞偺偩偝偆偱丄堦帪偵懘張偱亊偝傫偲埀傆偲偄傆偺傕岲搒崌偱偁偮偨丅亙棯亜
乽巹傕丄烤梤擏偼偙偺搤弶傔偰側偺偱丄屼楃傪偄偼傟傞偳偙傠偱偼側偄丅愥傪尒偨傜偡偖孨傪堷挘傝弌偡偙偲偵偟傑偟偨傛乿
丂亊偝傫偑丄傐偮傝傐偮傝偲偟偨岥挷偱偝偆塢偮偨丅
丂媼巇偑寎傊偵棃偰嶰恖棫偮偨丅楲壓偺撍摉傝偺斷傪奐偔偲丄偪傜偪傜偲崀傞愥嬻偺壓偺壆忋傊弌偨丅撶偺壓偺巇妡偼朰傟偰椆偮偨偑丄惉媑巚娋撶偲偄傆撶傜偟偔側偄撶偼丄捈宎堦広梋偺幍椫偺偍偲偟傪鄘鄤傪暁偣偨傗偆偵拞崅偵偟偨傕偺偱丄愒乆偲壩傪摟偐偣偰傤偨丅懷偺崅偝傎偳偺偙偺撶傪埻傫偱丄慹枛側墢戜偑擇嶰媟抲偄偰偁傞丄偙傟傊曅懌偐偗偰弌廯偵怹偟偨梤傪從偔偺偑朄偩偲暦偄偨丅庎偺彫摽棙偵擖傟偰丄從庰偦偮偔傝側庰傪揧傊偰偔傞丅傑傑偛偲偵巊傆傗偆側彫偝側攖偱丄崌娫崌娫偵娷傓偲丄岥拞偺帀偑婏楉偵徚偊偨丅亙棯亜
乮弶弌偼乽暥寍弔廐乿徍榓廫敧擭巐寧崋乯
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮俇乯偲僗儔僀僪偺幨恀偺弌揟偼偄偢傟傕埨摗峏惗挊乽杒嫗埬撪婰乿俀俇俆儁乕僕丄徍榓侾俇擭侾侾寧丄怴柉彂娰亖尨杮丄
乮俉乯偼摨俀俇係儁乕僕丄摨丄
乮俈乯偼墱栰怣懢榊挊乽杒嫗璧婰乿岥奊幨恀丄徍榓侾俋擭係寧丄擇尒彂朳亖娰撪尷掕嬤僨僕杮丄
乮俋乯偼擔杮崙岅戝帿揟戞擇斉曇廤埾堳夛丄彫妛娰崙岅帿揟曇廤晹曇乽擔杮崙岅戝帿揟乿俀斉俈姫俆俇侾儁乕僕丄暯惉侾俁擭俈寧丄彫妛娰亖尨杮丄
帒椏偦偺俁乮侾乯偼埨摗峏惗挊乽杒嫗埬撪婰乿俀俇係儁乕僕丄徍榓侾俇擭侾侾寧丄怴柉彂娰亖尨杮丄摨乮俀乯偼暥寍弔廐幮曇乽暥妛奅乿俁俈姫侾侽崋乮憂姧俆侽廃擭婰擮摿戝崋乯俀係俀儁乕僕丄徍榓俆俉擭侾侽寧丄暥寍弔廐幮亖尨杮丄
|
丂巹偼偹丄搶棃弴偵偮偄偰彂偄偨傕偺傪偣偭偣偲扵偟偰偄傞偺偱偡偑丄傑偩屆偔偰傕徍榓侾働僞偺傕偺偟偐尒晅偗偰側偄丅柧帯偐傜偺揦側偺偱偡偐傜丄偦傫側傢偗偼側偄偲巚偭偰丄倗倧倧倗倢倕偺彂愋専嶕側偳傪棅偭偰偄傞偺偱偡偑丄偼偐偽偐偟偔側偄丅偦偺棟桼偲偟偰搶棃弴偼僕儞僊僗僇儞偺揦偲偄偆傛傝丄偝傫偢偄偵報嶞偺嶞丄偦傟偵梤擏偲彂偔僔儏儚儞儎儞儘乕丄梤擏偟傖傇偟傖傇偺揦偲偟偰巚傢傟偰偄偨偙偲偑戝偒偄偲巹偼峫偊偰偍傞偺偱偡丅
丂偄傑偱偙偦丄偟傖傇偟傖傇偲偄偆屇傃曽偑掕拝偟偰丄搤傛傝壞偺杒嫗娤岝傪岲傓擔杮恖偼搶棃弴偼偠傔梤擏娰偵擖偭偰偟傖傇偟傖傇傪怘傋偰偔傞曽偑辍偐偵懡偄傜偟偄丅備偑偔偙偲偱帀偑敳偗偰僿儖僔乕偲偄偆偙偲傕偁傝傑偟傚偆偑丄愴慜偱偼偝偟偰偦偆偄偆偙偲傪婥偵棷傔偰偄側偐偭偨丅偱偡偐傜丄搶棃弴偱怘傋偨巚偄弌偱傕偳偭偪傪怘傋偨偲柧婰偟偰偄傞偺偼彮側偄丅偄傗丄巹偑僕儞僊僗僇儞愱栧偱廤傔側偐偭偨偲偄偆偙偲傕偁傞偐側丄偼偭偼偭偼丅
丂偦傟偼偝偰偍偒丄偙傟偼儗億乕僩偺壽戣偵嫇偘偰偍偒傑偡丅偒傚偆偺帒椏偵嫇偘偨埲奜偱愴慜偺搶棃弴偺僇僆儎儞儘乕偺婰榐傪扵偟偰傎偟偄丅 梤擏偱側偔偰丄烤梤擏偵尷傝偩偑丄俀偮尒偮偗偰彂偄偨儗億乕僩偵偼嵟崅揰傪晅偗傑偡傛丄杮摉偵丅 梤擏偱側偔偰丄烤梤擏偵尷傝偩偑丄俀偮尒偮偗偰彂偄偨儗億乕僩偵偼嵟崅揰傪晅偗傑偡傛丄杮摉偵丅
丂搶棃弴偲柧婰偟偰偄偰丄撪梕偐傜帪婜傪悇掕偱偒傞傕偺傕擖傟偰丄擭戙弴偵暲傋偰傒偨偺偑丄帒椏偦偺係偱偡丅偦偺乮侾乯偼徏杮婽師榊偺乽拞壺屲廫擔熰婰乿偱偡丅徏杮偼搶嫗偲杒嫗偱楧恦偼偠傔懡偔偺拞崙恖偵擔杮岅傪嫵偊偨恖偱偡丅偦偺偨傔偵嶌偭偨乽娍栿擔杮暥揟乿偑崙夛恾彂娰偺嬤戙僨僕僞儖儔僀僽儔儕乕偵偁傝傑偡丅
丂幁帣搰彈巕戝偺擇尒崉巎偝傫偼乽徍榓榋擭幍寧弌斉偺亀拞壺屲廫擔梀婰亁偼徏杮偺帺揱偲傕徧偡傋偒挊嶌偱偁傞偑丄偦偺朻摢偵亀梊偑嫵応偵墬偰憡尒偊偨拞壺妛惗偼丄桪偵漭傪埲偰悢傊傞掱偱亁偲婰偝傟偰偄傞傛偆偵丄懡偔偺嫵偊巕偵愙偟偨婌傃偲帺怣偑斵偵廩枮偟偰偄偨偙偲傪帵偟偰偔傟傞丅漭傪悢偊傞拞偵偼岹暥妛堾傗搶垷崅摍梊旛妛峑偱偺妛惗偨偪偑娷傑傟傞傢偗偱偁傞偐傜丄杒嫗帪戙偲偄偆偙偲偵側傟偽丄悢傕尷掕偝傟傞傢偗偩偑丄亀晱巕偺怓庢傝偳傝偵嶇偒擋傆崙夰偐偟傒椃棫偪偵偗傝亁偲偄偆壧偑塺傑傟傞掱偵拞崙偼斵偵偲偭偰嵟傕恎嬤偐側奜崙偩偭偨偲偄偊偦偆偱偁傞丅(10) 乿偲乽嫗巘朄惌妛摪偲徏杮婽師榊乿偵彂偄偰偄傑偡丅
丂偦傟偖傜偄拞崙岅偑偱偒偨偺偩偐傜乽搶挿埨巗偺搶棃廬崋斞揦乿偲彂偄偰傑偡偑丄偙傟偼搶棃弴偲僀僐乕儖偱偁傠偆偲悇嶡偟偰庢傝忋偘偨傢偗偱偟偰偹丄傕偟偐偟偨傜丄偙傟偼暿偺揦偐傕抦傟傑偣傫丅
丂乮俀乯偼愳崌掑媑偺巚偄弌偱偡丅偙偺慜傪撉傓偲丄娭搶孯偑嬔廈傪峌寕偡傞慜偺傛偆側偺偱丄徍榓俇擭廐偺偙偲偱偟傚偆丅側偍愳崌偺夞憐偵偼儕僸傾儖僩丒僝儖僎傗旜嶈廏旤側偳傕搊応偡傞偙偲傕偁傝丄偦偺恀婾偵偮偄偰偄偔偮偐偺僒僀僩偱媍榑偑撉傔傑偡偑丄搶棃弴偼弌偰偒傑偣傫偐傜丄愳崌偨偪偑怘傋偨偙偲偼怣梡偟偰偄偄偺偱偟傚偆丅抾撪偑搶棃弴偼俁奒寶偰偲彂偄偰偄傞偺偵乽巐奒偺壆忋乿偲偄偆偺偼曄偱偡偑丄係奒偵摉偨傞壆忋偲偄偆偙偲偱偟傚偆丅
帒椏偦偺係
乮侾乯徍榓俆擭俆寧
丂亂挘泬巵偺惔恀椏棟拫巂橉亃丂敧擔惓屵挘泬巵偐傜搶挿埨巗偺搶棃廬崋斞揦偱丄夞乆嫵偺惔恀椏棟傪嬂偣傜傟偨丅棃夛幰偼崅曕鄆慘堫懛椉巵媦傃崅嫶孨暯巵偲丄梊摍堦峴巐恖偱偁偮偨丅偙乀偺椏棟偼惉掱晛捠偺斞揦偲堘偮偰嫃傞丅烤梤擏偺椏棟側偳捒傜偟偔姶偠偨丅惔恀椏棟偼堦愗撠傪梡傂偸偺偑摿挜偱偁傞丅
乮俀乯徍榓俇擭廐
乽偳偆偩丄媣偟怳傝偩偐傜戝孁傕岎偊偰堦攖傗傠偆偐乿
丂擔偑曢傟傞偲奨偵揰乆偲摂偑偮偔丅暃搰偺採埬偱媊桬戉偵偄傞戝孁偵揹榖偟偰丄嶰恖偼惙傝応搶埨巗応偺乽搶棃弴乿偵懌傪塣傫偩丅応撪偵偼旤偟偄巋廕偺孋傪偼偄偰帹忺傝傪偟偨屍柡偑嶰乆屴乆丄慯乆偲偟偰曕偄偰偄傞丅嶰恖偼杒嫗柤暔偺栔屆椏棟乽搶棃弴乿偺巐奒偺壆忋偵忋偭偰廐揤偺惎嬻偺傕偲偱乽烤梤擏乿傪怘傋庰傪堸傫偩丅烤梤擏偲偼擔杮偱偄偆惉媑巚娋椏棟偱偁傞丅揝偺戝偒側楩偵徏娵懢傪鄮傇偟偰丄懢偄揝偺嬥栐偺忋偵挿偄敘偱梤擏傪鄑傝側偑傜怘偆偺偱偁傞丅曅媟傪壩敨偵偐偗丄棫偭偨傑傑堸傒偐偮怘偆偺偱偁傞丅愴応巜屇偺娫偵揋傪朷傒側偑傜怘偆栰愴椏棟偺庯傪揱偊偨傕偺偱偁傞丅
丂廐嬻崅偔嬧壨傪嬄偓丄嶑杒偺栭晽镈乆偲偟偰鄮鄚傪姫偒忋偘丄墜偵婄傪愼傔偰嶰恖偼戝偄偵榑偠偐偮寏堸偟偨丅悓偄偑夞偭偰偔傞偲丄戝孁偼乽堦偮塖偄傑偭偟傚乿偲孎杮鎍傝偱乽偍偰傕傗傫乿傪塖偄乽崟揷愡乿傪塖偆丅
丂
丂徍榓俈擭偺婰榐偱偼抾撪岲偺乽慛枮擔婰丒梀暯擔婰乿偑偁傝傑偡丅乽堦嬨嶰擇擭偺敧寧偐傜廫寧偵偐偗偰丄搶戝嵼妛拞偺挊幰偑丄奜柋徣偐傜敿妟曗彆偺弌傞椃峴抍偵壛傢偭偰挬慛偲亀枮廎亁傪偨偢偹偨偝偄偺椃峴婰偲丄偝傜偵屄恖揑偵亀杒暯乮杒嫗乯亁偵懌傪偺偽偟偰堦寧偁傑傝懾嵼偟偨偝偄偺擔婰偐傜惉傞丅(11)乿偲夝戣偵偁傝傑偡偑丄偦偺乽梀暯擔婰乿偵偱偡偹丄搶埨巗応偺梤擏椏棟揦偑弌偰偔傞偺偱偡丅
丂偨偩丄抾撪偼偙偺偲偒弶傔偰拞崙傪朘傟偨偨傔枩帠弶傔偰偱丄僇僆儎儞儘乕偲巚偆偺偱偡偑丄嵟弶偼梤擏偺偡偒從偒偵帡偨椏棟偲彂偄偰傑偡丅揦柤偼偁傝傑偣傫偑丄徍榓侾侽擭埲慜偺婰榐偱偁傞偙偲偼妋偐側偺偱丄搶棃弴傜偟偄揦偱怘傋偨偔偩傝傪帒椏偦偺俆乮侾乯偲乮俀乯偵偟傑偟偨丅
丂偦傟偐傜徍榓俉擭廐偱偡偑丄楌巎妛幰偺杮懡扖師榊偑乽杒巟枮慛椃峴婰乿偵怘傋偨偙偲傪彂偄偰偄傑偡丅杮懡偼俋寧俀係擔偵嫗搒傪弌敪丄侾侽寧侾擔偵杒暯偵拝偒丄柤強尒暔側偳傪偟偰侾侽寧俁擔栭偵搶棃弴偲巚傢傟傞揦偵彽偐傟偨偺偱偡丅偦傟偑帒椏偦偺俆乮俁乯偹丅
帒椏偦偺俆
乮侾乯嬨寧嶰擔乮搚乯
亙棯亜杮擔丄搶曽暥壔悾愳巵彽懸偺倲倕倎丂倫倎倰倲倷偵偰丄擔杮暈偺柡偝傫墱偝傫傜帺摦幵偵偰懡偔棃傝晵摳堦朳傪搚嶻偵偟偰婣傞丅椆愭惗傜偲嫟偵弌偰丄搶埨巗応偵偰梤擏偺偡偒傗偒偵帡偨椏棟傪屼抷憱偵側傞丅偆傑偔丄偐偮埨偒偵嬃偔丅巗応杒岥偵偰暿傟丄変乆偼杮壆傪傂傗偐偟丄廫悢墌攦偄暔偟偰婣傞丅
乮俀乯嬨寧廫堦擔乮擔乯
亙棯亜屵岪丄挌丄梜椉巵棃傞偵敧栘巵棷庣側傟偽丄嫟偵巗応傪曕偔拞敧栘巵偵埀偄丄堦弿偵幨恀傪偲傝丄傑偨傕拫怘傪屼抷憱偵側傞丅烤梤擏側傝丅彜柋報乲彂娰乴偺亀嶰柉庡媊亁傪尒偮偗丄擇栄偱攦傢傫偲偡傟偽丄梜巵嬥傪偼傜偭偰偔傟丄幚偵婥偺撆側傝丅亙棯亜
乮俁乯
亙棯亜丂崯偺栭偼岝壀巵偺彽偒偵墳偠偰丄搶埨岞巌撪偺惉媑巣娋椏棟偺嬂墳傪庴偗偨丄梊偹偰懘柤偼暦偄偰嫃偨偑枴偼偆偺偼惗傑傟偰巒傔偰偱偁傞丅棫偪側偑傜曅懌傪鋓偵妡偗偰丄挿偄懢偄敘偱岥偵塣傇恀偵斬揑側傕偺偱偁傞偗傟偳傕枴偼拞乆壚椙偱偁傞丅廫帪夁婣廻偟偨傟偽悪懞丅壨枖巵摍偑丄梊偹偰埶棅偟偰抲偄偨彂壠傪摨敽偟偰樢傜傟偨偲偄傆偙偲丄枖懘偺愡偺榖偵丄巟撨壠掚傪傕尒偣傞搒崌傪塣偽傟偨偲偄傆偙偲偱桳偮偨偑丄悑偵擵偼婡夛傪摼側偐偮偨丅亙棯亜
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮侾侽乯偺弌揟偼垻晹梞曇乽擔拞嫵堢暥壔岎棳偲杸嶤乿俋俁儁乕僕丄擇尒崉巎乽嫗巘朄惌妛摪偲徏杮婽師榊乿丄徍榓俆俉擭侾侾寧丄戞堦彂朳亖尨杮丄
帒椏偦偺係乮侾乯偼徏杮婽師榊挊乽拞壺屲廫擔熰婰乿侾俈係儁乕僕丄徍榓俇擭俈寧丄搶垷彂朳亖尨杮丄
摨乮俀乯偼愳崌掑媑挊乽偁傞妚柦壠偺夞憐乿俋俆儁乕僕丄徍榓俆俉擭侾侽寧丄扟戲彂朳亖尨杮丅偙偺屄強偼徍榓愴憟暥妛慡廤曇廤埾堳夛曇乽徍榓愴憟暥妛慡廤乿暿姫侾俆侾儁乕僕丄乽抦傜傟偞傞婰榐乿偵傕偁傞丅摨彂偼廤塸幮偑徍榓係侽擭侾侾寧弌斉丄
乮侾侾乯偼抾撪岲挊乽抾撪岲慡廤乿侾俆姫俆俁係儁乕僕丄斞憅暯乽夝戣乿丄徍榓俆俇擭侾侽寧丄拀杸彂朳亖尨杮丄
帒椏偦偺俆乮侾乯偼摨俀侽儁乕僕丄摨
摨乮俀乯偼摨俀俁儁乕僕丄摨丄乮俁乯偼杮懡扖師榊挊乽杒巟枮慛椃峴婰丂戞擇廠乿俀俉儁乕僕丄徍榓侾侾擭俈寧丄擔枮暓嫵嫤夛杮晹亖嬤僨僕杮
|
丂
丂徍榓侾侽擭戙偱搶棃弴偱怘傋偨偲偼偭偒傝傢偐傞偺偼丄偄傑偄偭偨抾撪岲丄戝戭憇堦丄扟愳揙嶰丄搰堦榊偺彂偄偨傕偺偱偡丅偦傟傜傪帒椏偦偺俇偵傑偲傔傑偟偨丅乮侾乯偺抾撪偼徍榓侾俀擭偐傜俀擭娫丄奜柋徣偺曗彆偱杒嫗偵棷妛偟傑偟偨丅偦偺偲偒偺擔婰偑乽杒嫗擔婰乿偲偟偰慡廤偵廂傔傜傟偰偄傑偡偑丄俀擭娫偵搶棃弴傊峴偭偰烤梤擏傪怘傋偨夞悢傪悢偊傞偲乽搶埨巗応偵烤梤擏傪怘偆丅乿傕擖傟偰偨偭偨偺俀夞丅
丂弶傔偰偄偭偨偲偒偼侾僇寧傎偳偺娫偵俀夞怘傋偨偺偵丄俀擭娫偵俀夞偱偼彮側偡偓傑偡傛偹丅尒棊偲偟偨偐偲俀夞撉傒曉偟偨偗偳丄惓梲極偺烤梤擏傕俀夞偩偭偨丅偨偩烤梤擏偑俀夞偱丄梤擏偺椏棟偲偐壩撶巕傪怘傋偨偲彂偄偰偄傑偡偑丄搶棃弴偺烤梤擏偲柧婰偟偨偺偼俀夞側傫偱偡丅
丂偙傟偼烤梤擏偼擭拞怘傋傜傟側偄偙偲丄壗擔暘偐傑偲傔彂偒偑偡傞傛偆偵側傝怘帠傪巚偄弌偣側偔側偭偨偙偲偑偁傝傑偡偑丄嵟戝偺棟桼偼梀妔偵懌斏偔捠偄丄偦傟傪嵶偐偔彂偔傛偆偵側偭偨偨傔偱偡丅撉傫偩傜傢偐傞丄偼偭偼偭偼丅
丂乮俀乯偑戝戭偱乽戝戭憇堦慡廤乿偵偁傞旜嶈廏庽偺乽夝戣乿偵傛傞偲偹丄戝戭偼徍榓廫擭幍寧偺偄傢備傞枮慛婭峴偵偼偠傑傝丄徍榓廫堦擭嬨寧偺撿梞彅搰丄徍榓廫擇擭偐傜梻擭傊偐偗偰偺杒嫗丄彊廈丄撿嫗丄忋奀丄峀廈丄崄峘側偳偺拞崙奺抧傪椃峴偟偨(12)偦偆偱偡偐傜傕丄偙偺偲偒搶棃弴偱屼抷憱偵側偭偨傫偱偡側丅埨偐偭偨偲彂偄偰偄傑偡丅擔杮偠傖崅偄偲偄偭偰昹柤壠偲偄偆椏棟壆傪椺偵嫇偘偰傑偡偑丄偙傟偼丄傕偟偐偡傞偲擔杮嫶郷挰偺郷偺壠傪巜偟偨偺偐傕抦傟傑偣傫丅
丂乮俁乯偺扟愳揙嶰偺擔婰偼徍榓侾俆擭偺乽巚憐乿俈寧崋偵宖嵹偝傟偰偄傑偡偑丄僇僆儎儞儘乕偑怘傋傜傟傞傛偆偵側傞偺偼丄摉帪偼媽楋偺廳梲愡丄俋寧埲崀偩偭偨偼偢偩偐傜丄偦偺慜偺擭偺侾係擭偺尒暦偱偟傚偆丅嬤偛傠偼巊傢傟側偄傛偆偱偡偑丄埲慜偼偍偟傖傑側偲偄偆宍梕帉傪巊偭偨傕偺偱丄搶棃弴偱偦傫側彈偺巕傪尒偐偗偨偲偄偆榖偱偡丅
丂乮係乯偺乽惉媑巚娋撶乿偼忔悪壝庻偲偄偆恖偺堚峞廤偵偁偭偨徍榓侾俈擭偺擔婰偐傜偱丄侾侽寧侾俁擔偵枮揝偵彽偐傟偨榖偺傛偆偱偡丅乽偦偺柤晅偗恊偼擔杮恖偩偲偄偆偙偲偩丅妋偐偵寙嶌偱偁傞丅乿偲姶怱偟偟偨偮偄偱偵丄柤晅偗恊偼壗偲偄偆屼恗偐彂偄偰偁偭偨傜丄偁傝偑偨偐偭偨偺偱偡偑偹偊丅忔悪偝傫偵乽惉媑巚娋偑敪柧偟偨傕偺偱傕側偗傟偽丄偙傟傪斵偑忢怘偲偟偨偺偱傕側偝偦偆偩偑乿偲島庍偟偨恖傕抦傜側偐偭偨傫偱偟傚偆丅
帒椏偦偺俇
乮侾乯
廫擇寧弶幍乮楃攓擇乯
丂忋屵梜愭惗樢丅恄扟愭惗嶱徏巬揑峲嬻曋樢丅摴擵忋寧嶰廫崋乮丠乯幨揑丅晄扐擛崯丄怣晻栫旐奐拝丅恄扟愢亀寧曬亁廫擇寧崋樢椆丅懄忋搶曽暥壔愙庴丅娨桳夛彂榓壠彂丅尒娾懞嫀丄堜揷孾彑乮幚乯枻宱樢丅堜揷丄娾懞丄恄扟堦摨忋搶棃弴媓烤梤擏丅亙棯亜
廫擇寧擇廫擔乮寧乯
檳晽恟偟丅梉崗偵摓偭偰巭傓丅挬丄搉曈棾嶔巵尒備丅屵岪丄撉彂夛偵恄扟巵戭偵弌惾丅巐帪敿丄擔壺儂僥儖偵搉曈巵傪朘偆丅嫟偵搶埨巗応偵烤梤擏傪怘偆丅
偦傟傛傝慜栧偵備偒弔?堾丅椺偺徫寧丄偟偒傝偵攽傟偲偄偄丄墳懳忢偺擛偐傜偢丅亙棯亜
乮俀乯
丂杒嫗偺桳柤側搶埨巗応偱丄枮揝偺忛強巵偵惉媑巣娋椏棟傪屼抷憱偵側偭偨偑丄偙傟傕巐恖偱嶰墌埵偩偭偨丅擔杮偱傕傏偔偼偙傟偑岲偒偱帪乆怘偄偵峴偔偑丄昹柤壠偁偨傝偩偲丄傏偔偺傛偆側戝怘偄偼丄堦恖偱屲墌埲忋偐偐傞丅亙棯亜
乮俁乯
嬨寧擇擔
亙棯亜
丂栭丄搶樢弴偱從梤擏傪怘傋傞丅強堗僕儞僊僗僇儞椏棟偱偁傞偑丄傑偩婫愡偱側偄偣傤偐偆傑偔側偄丅巹偲摨偠鑓斅偱昳偺偄偄晇晈偑廫擇嶰偺彈偺巕傪偮傟偰怘傋偰傤偨丅偦傫側彫偝側彈偺巕偑堦恖慜偺庤偮偒偱偙傫側梘強偱偙傫側傕偺傪怘傋偰傤傞偺偑壗偐傪偐偟偐偮偨丅巟撨偱偼彫泏峑偺巕嫙偱傕銗醕偲偄傆傕偺傪怘傋側偄丄彮悢偺怴偟偄泏峑偩偗偵偼怘摪偑偁傞偑丄奨偺彫妛峑偺巕嫙側偳偼摴抂偱攧偮偰傤傞傕偺傪嬯椡偑怘傋傞傗偆偵怘傋
偰傤傞偺傪傛偔尒偐偗傞偲偄傆丅亙棯亜
丂乮係乯惉媑巚娋撶
丂搶棃弴偲偄偆椏掄偱丄懎偵惉媑巚娋椏棟傪屼抷憱偵側偭偨丅偙傟偼嵽椏偼梤擏偱偁傞偑偦偺曽朄偑旕忢偵捒婏側傕偺偱丄晛捠偵偼梤偺擏傪暒摣偝偣偨搾偺拞偵撍偒崬傒丄偦傟偑堦捠傝徚撆偝傟偨屻廯偵偮偗偰怘傋傞偺偱偁傞偑丄偙傟偼忋昳側曽朄偱恟偩暯杴偱偁傞丅檤偱傕偆堦偮偺怘傋曽偼丄惗偺梤擏傪戝壩敨偺壩偺忋偱偮偗從偟偰傓偟傖乛乢嬺偆偺偱偁偭偰丄媞偼偙偺戝壩敨傪埻傫偱崅椑庰傪堸傒撫傜偮傑傝媿堸攏怘揑偵慠傕棫偪怘偄傪偡傞偺偱偁偭偰丄偄偐偵傕屆偄帪戙偺梀杚柉偑岲傫偩傜偟偄椏棟偱偁傞丅惉媑巚娋偑敪柧偟偨傕偺偱傕側偗傟偽丄偙傟傪斵偑忢怘偲偟偨偺偱傕側偝偦偆偩偑惉媑巚娋偑岲傫偱怘傋偦偆側乗乗椫偵側偭偰棫偪暲傫偱堸傒撫傜嬺偆恾側偳側偐乛乢栰庯偑偁偭偰恮拞偱偱傕梡偄偦偆偱偼側偄偐乗乗椏棟偩偲偄偆扨側傞憐憸偐傜晅偗偨柤偱丄慠傕偦偺柤晅偗恊偼擔杮恖偩偲偄偆偙偲偩丅妋偐偵寙嶌偱偁傞丅
丂堦懱梤偺擏偲偄偆搝偼拠廐偐傜梻弔嶰寧崰傑偱偑怘傋帪婜偱丄偦傟埲奜偼恟偩偟偄廘婥傪敪嶶偟偰怘梡偵揔偟側偄丅慠傕廐偐傜弔傊偐偗偰怘傋傞擏偼墦偔娚墦乗乗枮廎媑椦徣偺杒搶抂乗乗抧曽傛傝杚摱偵捛傢傟偰拫栭寭峴媥傓偙偲側偔擇儢寧傪曕懕偗偰杒暯偵拝偔偺偱偁傞偑丄偙偺摴拞悋柊傪庢傜偣側偄壵崜側楯摥偺堊偵梤偼尒傞偐偘傕側偔憠偣偰椆偆丅偮傑傝嬯栶偺堊偵恎懱拞偺桘偑徚旓偝傟偰偟傑偆偺偱廘婥偑柍偔側傞偲偄偆偙偲偱丄弔埲屻偼梤偺巚弔婜偵擖傞偺偱桘偑忔偭偰擏偺曽偼媝偭偰晄枴偄偦偆偱偁傞丅恖娫側傫偰彑庤側傕偺偱丄嵾傕側偄梤傪擇儢寧娫傕堷偒偢傝夢偟偰丄偦偺偁偘偔偺壥偑從偄偰怘偭偰椆偆偺偱偁傞丅
丂偙偺搶棃弴偲偄偆椏掄偵偼偙偺嵾怺偄偍媞偑壗愮壗昐偲嫃偰丄晇乆屓傟偺枴妎傪枮懌偝偟偰偄偨丅
丂梋傕偙偺嵾側杒暯柤暔偵枮暊偟偰丄婣傝偼嶐栭偺擛偔搶埨巗応傪夁傝丄椺偵埶偭偰廫慘椡幵偱廻偵栠偭偨丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮侾俀乯偺弌揟偼戝戭憇堦挊乽戝戭憇堦慡廤乿侾俈姫俁俋俉儁乕僕丄旜嶈廏庽乽夝戣乿丄徍榓俆俈擭俁寧丄憮梞幮亖尨杮丄
帒椏偦偺俇乮侾乯偼抾撪岲挊乽抾撪岲慡廤乿侾俆姫侾俉俆儁乕僕丄乽杒嫗擔婰乿丄徍榓俆俇擭侾侽寧丄拀杸彂朳亖尨杮丄師偼摨侾俉俋儁乕僕丄摨丄
摨乮俀乯偼戝戭憇堦挊乽戝戭憇堦慡廤乿侾俈姫俀俉俁儁乕僕丄乽戝棨椃峴宱嵪妛乮徍榓侾俁擭俉寧乯乿丄徍榓俆俈擭俁寧丄憮梞幮亖尨杮丄
摨乮俁乯偼娾攇彂揦曇乽巚憐乿俀侾俉崋侾侽俁儁乕僕丄扟愳揙嶰乽杒嫗擔榐彺乿丄徍榓侾俆擭俈寧丄娾攇彂揦亖尨杮丄
摨乮係乯偼忔悪湒曇乽忔悪壝庻堚暥廤俀俁侾儁乕僕丄暯惉俈擭俉寧丄忔悪湒亖尨杮
|
丂偦傟偐傜帪婜偼偼偭偒傝偟傑偣傫偑丄愴慜偺搶棃弴偱怘傋偨巚偄弌傪廤傔偨偺偑帒椏偦偺俈偱偡丅帒椏偦偺俈乮侾乯偼帊恖偺憪栰怱暯偱偡偑丄憪栰偼乽戝惓侾侽擭偵拞崙偺椾撿戝妛乮尰丒拞嶳戝妛乯偵棷妛(13)乿偟偰偄傑偡丅
丂摨乮俀乯偺搰堦榊偺偼僕儞僊僗僇儞奣榑偱偡偑丄惓梲極偲暲傋偰搶棃弴偺柤慜偑擖偭偰偄傑偡丅抧柤偺偵傫傋傫偵廫偺撉傒偼僕儏僂丄偦傟偵檵撨偺檵偩偐傜俁帤偱僕儏僂僙僢僇僀偱偡偹丅巼嬛忛偺惣杒偵偁傞恖岺屛偱偡丅
帒椏偦偺俈
乮侾乯丂丂烤梤擏
丂弶傔偰烤梤擏傪怘傋偨偲偒偼壗傫偲偄傆偍偁偮傜傂岦偒偐丄愥偑傆偮偰傤偨丅
丂烤梤擏傪偨傋傞側傜偽愥偑梸偟偄偲偦傟偐傜巚傂丄撿嫗偱偼椉嶰搙偨傔偟偨偙偲偑偁傞偑丄偦偟偰傑偨愥偺擔偱偼側偐偮偨偑丄忋奀傗娍岥偱傕偨傋偨偺偩偑丄栴挘傝梤擏偼丄烤偵偟傠悈偨偒偵偟傠梘巕峕増娸傗偦傟偐傜撿偺戙暔偱偼側偄丅
丂崱偵偼偠傑偮偨偙偲偱偼側偄偑怘傋暔偵偼梘強偲恖偲偑梫傞傗偆偱偁傞丅
丂巹偼偄偮偐堦悺偟偨暔岲偒偐傜搶棃弴偺偰偮傌傫偱儘僔儎偺彈嫟嶰巐恖偲烤梤擏傪怘傋偨偙偲偑偁傞丅弶傔偰偩偮偨傜偟偔丄偆傑偄偲偐慺揋偩偲偐偄傂撫傜傓偟傗偮偄偰傤偨偑丄偳偆傕傄偮偨傝偟側偐偮偨丅烤梤擏側傜丄杮摉側傜偽栔屆偱怘傋傞傋偒側偺偩傜偆丅栔屆暈偱傕岤偔拝偙傫偱丅偗傟偳傕岦偆偐傜傒傟偽曄側奜棃偑攪擖偮偨傝偡傞偲丄愜妏偺屼抷憱傕丄偦偺暤埻婥偑偙偼傟偰偟傑傆偐傕偟傟側偄丅
丂偦傟偼偝偆偲偟偰戝搒偱怘傆側傜杒暯偱偁傜偆丅嵟弶偺愥傕杒暯偩偮偨丅愥偑從偗偰傞揝斅偵偍偪丄擏傪嬺傂敀庰傪偺傒乮嫲傜偔偦傟偼奀櫜偁偨傝偺傕偺偩偮偨傜偆乯偦傟偼側傫偲傕尵偼傟側偄堦偮偺嫮楏側挷榓偩偮偨丅
丂偳偆偣拞崙偺桭恖偵楢傟傜傟偰偄偮偨偺偩傜偆偑丄偄傑偼扤偩偮偨偐憐傂弌偣側偄丅
丂扅巹偵偼拞崙偺嵷娰偵偼傂偮偰備偔偲戜強傪偺偧偒偨偄僋僙偑偁偮偰丄偦偺帪傕巹偼撈傝偙偮偦傝偺偧偒偵偄偮偨丅偡傞偲梤擏傪擇恖偺抝偑戝珉偺傗偆側曶挌偱愗偮偰傤偨丅巹偼偦偺媄弍偺尒帠偝偵嬃扱偟偰丄壗擭傗偮偰傤傞偺丄偲偒偄偰傒傞偲丄擇廫屲擭愗偮偰傞偲擭榁偮偨曽偺偑摎傊偨丅烤梤擏偺揝斅偼昐巐廫擭偲偄傆楌巎傕偺偩偝偆偩偑丄擏愗傝偺擇廫屲擭傕堦悺偟偨傕偺丅奀撠偺椏棟偺戝曄偝傕抦偮偰傤傞偗傟偳傕丄偦傟偼傓偟傠傗傝峛斻偺偁傞丄暋嶨偝偺扨弮壔偱偁傞偑丄偙傟偼扨弮偦偺傕偺偺擓屲擭側偺偱偁傞丅
乮俀乯
亙棯亜丂傕偮偲傕僡儞僊僗僇儞椏棟偲偄傆偺偼丄擔杮恖摨巙偵偺傒捠梡偡傞尵梩偱丄惓偟偔偼亀烤梤擏亁偲偄傆丅捈宎悢広偺執戝側鑓惢偺楩偵丄偦傟偵憡醕偟偨執戝側鑓媱傪偐偗傞丅擔杮偱鑓媱偲尵傊偽戝掞恓偑偹偱弌樢偰傤偰偍偝傫偳傫偺庤偱偟偰偝傊丄梕堈偵僋僯儍僋僯儍偵側傞偗傟偳丄偙偪傜偺偼丄擔杮嬧峴偺嬥屔幒偵挘偮偰抲偄偰傕焼偯偐傂側偄傗偆側婃忎側鑓偺朹偱慻棫偰傜傟偰傤傞丅擱椏偲偟偰偼亀敀栘亁偲屇偽傟偰傤傞桍偺妱栘傪梡傆傞偑丄偦傟傪楩偵偔傋偰壩傪揰偢傞偲丄巒傔偺傎偳偼庽帀僢焼偺側偄敀戺偺墝偑偁偑傝丄娫傕側偔鑓媱偺鑓偺寗朹偺娫偐傜丄崃僢峠側彫幹偺傗偆偵丄儊儔乛乢偲墜偑慚傔偔丅偦偺帪傪懸偪偐偹偰丄擏傪嶳惙傝丄忋偵偺偣丄桪偵堦広屲榋悺偼偁傜偆偲偄傆挿偔懢偄敘偱堦擇暘娫傂偮憕偒傑偼偡乨乨偡傞偲丄傕偆偦傟偱棫攈側從擏偲側傝丄岥偵漞傝崬傔傞偺偩丅悽偺拞偵偙傟傎偳娙扨側椏棟傕側偄傕偺偩傜偆丅僡儞僊僗僇儞椏棟偲偼扤偺柦柤偐抦傜側偄偗傟偳妋偐偵巚傂偮偒偱偼偁傞丅
丂崱偟偑偨尵偮偨傗偆偵丄崯偺椏棟偱偼惓梲極傗搶樢弴偑桳柤偱偁傝丄傑偨擵摍偺揦偼偦傟乛乢丣栔屆偵洆懏偺杚応傪桳偟丄枅擔氺偟偄梤傪搄偭偰傤傞偲偄傆傗偆偵丄巇妡偗傕側偐側偐戝偒偄丅帺慠桳柤偱偁傝丄廬偮偰桳柤偑岲偒側擔杮恖偼栜榑偝偆偄傆強傊墴妡偗偰峴偔丅偟偐偟巹帺恎偺岲傒偐傜尵傊偽烤梤擏偺烤梤擏偨傞杮醕偺枴偼傂偼丄傓偟傠丄廐偐搤傊偐偗偰偺毢棫偮姦偒奨摢偵偁傞偺偱偼側偄偐偲巚偮偰傤傞丅偨偲傊偽欫払栧偺奜偲偐揤嫶偲偐丄搶巐攙偺戝奨偲偐丄偝偆偟偨恖捠傝懡偒業揤偱丄嶑晽層恛傪悂偔偲偄偮偨傗偆側岝宨偺側偐偵棫偪側偑偪丄擱棫偮墜偵婄傪愒傜傔丄亀敀姳帣亁偲屇偽傟偰傤傞塻偄從拺傪娷傒偮乀丄偫偮偲丄帀傪偟偨乀傜偡擏偺嶳偲嵘傒偮偔傜偟偰傤傞偲偙傠偵壗偲傕尵傊側偄忣弿偑偁傞偺偱偼偁傞傑偄偐両丂峏偵屼杮懜偺拞殸恖偵尵偼偣傞偲丄亀巆壸丄枹偩幱偣偞傞抮偺斎偺桍偺偐偘側偳偱丄沔偵壩傪暟偒丄沔偵擏傪偮乀偔偺偑堦斣偩亁偲偄傆丅擛壗偵傕偁傝偝偆側偙偲偱丄嫲傜偔廦檵奀偺傎偲傝側偳偱乁傕傗傞偺偑嵟傕晽忣偵晉傓栿偩傜偆丅扐偟廦檵奀偺傎偲傝偵烤梤擏傪嬺偼偣傞強偑偁傞偐偳偆偐偼丄傑偩峴偮偰傒側偄偺偱丄曐鏆弌樢側偄丅亙棯亜
丂
丂師偼夵憿幮堳偩偭偨悈搰帯抝偺庤婰丅悈搰偼徍榓侾俆擭俆寧偐傜忋奀偺摿柋婡娭偵偄偨偺偱偡偑乽徍榓廫屲擭廫寧枛丄怷壀挿姱偐傜懪偪偁傢偣偨偄偺偙偲偑偁傞偺偱丄杒嫗傊棃偰偔傟丄偲偺柦椷偑偁偭偨偺偱旘峴婡偱峴偭偨丅(14)乿丅怷壀挿姱偲偄偆偺偼嫽垷堾嵼杒嫗壺杒楢棈晹挿姱偱棨孯拞彨怷壀嶩偱丄怷壀偑梻侾俇擭偵乽嫗搒偺巘抍挿偵揮擟乿偟偨偺偱丄悈搰傕摿柋婡娭傪傗傔偰婣崙偟偨偺偩偑丄(15)帺暘偺憲暿夛偺巚偄弌偺僇僆儎乕僘傪彂偄偨彉偱偵僇僆儎儞儘乕偵傕怗傟偨偲偄偆偙偲偱偡偹丅
帒椏偦偺俉
亙棯亜丂怷壀拞彨偼巐寧敿偽偵擟抧傊弌敪偟偨偑丄巹偼媫偖偙偲傕側偄偺偱丄屲寧敿偽傑偱悁棷偟偨丅偦偺娫偵丄旈彂偺惵嶳擇榊巵偼晹彁偑偐傢傝丄偦偺塰揮偲巹偺戅怑偲傪寭偹偰丄憲暿夛傪峀曬晹偺庒偄彅孨偲偱嵜偟偰偔傟偨丅偦偺偲偒偼偠傔偰杮応偺烤姏巕傪偨傋偨丅杒嫗偺崅媺偺柤暔椏棟偱丄恖岺梴怋偲偄偆偐丄偁傂傞偺岥傪庤偱偁偗偰丄恖栤偑擹岤帞椏傪柍棟傗傝偔偪偽偟偵媗傔偰丄偺傒偙傑偣娵乆偲傆偲傜偣偨傕偺偱丄偦傟傪娵偛偲忲從偒偵偟偨偺傪椏棟恖偑惾偵塣傫偱偒偰丄樧斅偺忋偱揔摉偺戝偒偝偵旂偩偗丄恎傑偱偗偢傜側偄傛偆偵曶挌偱偦偖偺偱偁傞丅偦傟傪閌巕乮僊儑僂僓乯偺旂偺忋偵嵶挿偔偒偞傫偩嬍擪偲娒偄桘枴慩傪偮偗偰庤偱偔傞傫偱偨傋傞丅偦偺応偱椏棟偡傞帀偺偺偭偨偁偨偨偐偄偁傂傞偺旂偺枴偼揤壓堦昳偱偁傞丅傕偆堦偮偺堩昳偼烤梤擏偲偄偆丅擔杮偱偄偆僕儞僊僗僇儞從偱偁傞丅梤偺擏偼偝傞偙偲側偑傜丄僔僫偳傫傇傝偵擖偭偰偄傞敄拑怓偺撈摿側偨傟丄戝偒側揝壩敨偺拞偵擱偊偰敀偄奃偵側傞慹濻偺暟栘丄揤堜偼悂偒敳偗偺惵嬻丄惎偺偒傜傔偒丄栘惢偺挿偄崢妡偗偵曅懌傪偺偣偰丄棫偭偨傑傑嶰廫僙儞僠傕偁傞挿偄敘偱丄偆偡偄梤擏悢曅傪嶮偐傜偮傑傒偁偘丄偨偭傉傝偨傟傪偮偗偰丄暘岤偄揝栐偵偺偣偰僕儏乕偲從偔丅傕偆堦傌傫偨傟偵偮偗偰傂偭偔傝曉偟偰傎偳傛偔從偔丅偦偄偮傪怘傋側偑傜丄娒恷偵偮偗偨娵偛偲偺偵傫偵偔偲從栞乮偛傑傪偮偗偨暯傋偭偨偄屌從傑傫偠傘偆乯傪偐偠傞丄墝偑傕偆傕偆偲忋偭偰峴偔丅偙偆偟偨崑夣側栰愴椏棟偺暤埻婥偑偁偭偰偙偦偆傑偄偺偱偁傞丅嵗晘偱昳傛偔偨傋偨偺偱偼偙偺枴偼偱偰偙側偄丅杒嫗偵偮偄偰巚偄弌偡偺偼婏柇偵怘偄傕偺偺偙偲偱丄怘偄傕偺偱僲僗僞儖僕傾傪姶偠丄偦傟偐傜偍傕傓傠偵夞憐偵偆偮傞偺偱偁傞丅亙棯亜
丂
丂師偺帒椏偦偺俋偼丄旕攧昳偱偐偮徍榓俀侽擭弌斉偲偄偆傔偭偨偵偍栚偵偐偐傜側偄杮偐傜偱偡丅昅幰偺杮揷徃擇楴偼婰幰楌侾俇擭梋傝偺寣婥惙傫側嶳宍怴暦暷戲巟嬊堳丄傕偟偐偡傞偲暷戲巟嬊挿偩偭偨偐傕抦傟傑偣傫丅徍榓侾俋擭偵峅慜巘抍娗壓搶杒巐導崌摨峜孯堅栤抍摿攈婰幰偲偄偆尐彂偒偱枮廎偲拞崙杒晹傪尒偰夞偭偨曬崘偺堦晹偱偡丅専嶕偡傞偲丄摨惄摨柤偺嶳宍導夛媍堳偑偄偰丄徍榓俀俆擭偵乽拞墱擔曬乿偲偄偆怴暦幮傪憂愝偟偨(16)偲乽暷戲擔曬乿偺儂乕儉儁乕僕偵偁傞偺偱丄偦偺曽偑搶埨巗応偱乽暷戲弌敪埲樢偺嬻暊傪乿僕儞僊僗僇儞偱枮偨偟偨杮揷偝傫偩偭偨偺偱偟傚偆丅
帒椏偦偺俋
亙棯亜敀栴孨偼丄寢嬊暊偵怘暔偑懌傝側偄偐傜丄婰幰偑嫽暠偡傞傫偩側偲丄摢傪摥偐偟偰丄梞幵傪搶埨巗応杒偺丄惉媑巚娋椏棟揦偵媫偑偣偨丅偦偺椏棟揦偼丄堦奒攧応偐傜丄拏懅偟偦偆側擇奒丄嶰奒偺嫹偔傞偟偄奒抜傪丄偖傞乛乢忋偮偰丄偙傟偼壗偲丄儂僣僩堦懅偺偮偗傞丄惵嬻偺偁傞戝怘摪偩偮偨丅
丂乽僒傾丄忋堖傪偸偄偱丄惉媑巚娋傪傗傝傑偣偆丄杮醕偼姦偄擔偵棁偱傗傞傫偱偡偑乿
丂偲敀栴孨偼丄偑傜傝丄奜搮傕忋拝傕丄僠儓僣僉傕偸偖丅偦偺惃傂偵姫偐傟偰丄婰幰傕壗偑壗偩偐暘傜偢丄壋崋暈傪偸偓丄僠儓僣僉傪偸偄偩丅惉傞掱怘摪偵偼丄堦広梋偺恉傪偔傋偨丄捈宎擇広丄崅偝嶰広梋傔閈摢宆偺幍椫偑丄忋偺揝栐偐傜郺乆偲墝傪揻偒丄擱偊偰傤傞丅偦偺廃埻偵摜傒鋓偑偁偮偰丄曅懌傪捈妏偵嵹偣丄栐偵敿崢偺妴岲偱岦偮偨傜丄堦広偽偐傝偺丄懢偄朹偺傗偆側娵敘傪帩偪丄梤偺擏傪偮傑傒丄從栐偵從壛尭偺檤傪丄惗栰嵷傪崗傫偩丄偟偨偠偵怹偟撫傜嬺傆偲偄傆悺朄偱偁傞丅
丂惉媑巚娋偑丄愴彿傪廽偟偰丄彑楱傪偁偘側偑傜丄墐傪嵜偟偨丄偙傟偼夎弌搙偄栰愴椏棟偱偁傞丅愒乆偲擱偊傞栐栚偵丄堦偲偮傑傒擇廫栨埗偺寣偺偟偨乀傞擏傪從偒丄僕僕僕乨乨乨乨偲從壛尭傪尒偰丄僠儎儞僠儐僂偲偄傆從拺傒偨偄側嫮庰傪庤庌偱僌僀偲偁傆傞丅梤擏屲廫嶮丄僠儎儞僠儐僂廫杮傗傟偽崑寙偺晹椶偵姩掕偝傟塸梇偵嬤偔側傞偲偄傆丅敀栴孨偑栴扡偵娊惡傪偁偘傞偺偱丄婰幰傕丄暷戲弌敪埲樢偺嬻暊傪丄偙乀偧偲媗傔崬傓丅旤枴偟偄偺丄岲偄偺偲丄偄傆宍梕帉偱偼丄捛晅偐側偄丅抝堦旵搢傟傞枠偼娵敘傪棧偝側偄丅偦偟偰嬌姦偵嬍偺娋傪棳偟丄捝堸偡傞偲偄傆偺偑丄惉媑巚娋偺楃媀偩偦偆側丅
丂乽堲岮偵擏偑丄偮偐傊偨傜丄摜傒鋓偺懌傪丄偲偮偐傊偰壓偝偄乿
丂偲敀栴孨偼丄鋓偵傆傫挘偮偰傤偨塃懌傪丄嵍懌偲丄庢偮姺傊傞丅偦偟偰岎屳偵廫曊懌傪庢偮姺傊偨傜丄姩掕傪巟暐偮偰婣傞傫偩丅偲崑岅偡傞丅婰幰偼丄棳愇偵丄擏偺擋傂偑嫻偵偮偐傊偰樢偨丅揦撪偺寲殑偲恉偺墜偲丄墝偲丄揝峧偺弸偝偵傓偣偰丄僠儎儞僠儐乕偺棙偒栚偑丄枖丄嫲傠偟偔憗偔丄堦幒偺栰庯偵丄娵偮棁偵側傝偨偄傗偆側徴寕偑樢傞乨乨乨乨丅亙棯亜
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮侾俁乯偺弌揟偼 偄傢偒巗棫憪栰怱暯婰擮暥妛娰儂乕儉儁乕僕亖http://www.
k-shimpei.jp/01.htm丄
帒椏偦偺俈乮侾乯偼憪栰怱暯挊乽憪栰怱暯慡廤乿俋姫侾俁俆儁乕僕丄徍榓俆俉擭俈寧丄拀杸彂朳亖尨杮丄
摨乮俀乯偼拞墰岞榑幮曇乽拞墰岞榑乿俇俀俈崋俉俈儁乕僕丄搰堦榊乽杒嫗偩傛傝乿丄徍榓侾係擭侾侾寧丄拞墰岞榑幮亖尨杮丄
乮侾係乯偼悈搰帯抝挊乽夵憿幮偺帪戙乿愴拞曇侾俉俁儁乕僕丄徍榓俆侾擭俇寧丄恾彂弌斉幮亖尨杮丄
乮侾俆乯偲帒椏偦偺俉乮侾乯偼摨侾俋俆儁乕僕丄摨丄
乮侾俇乯偼暷戲擔曬儂乕儉儁乕僕亖http://www.yone
zawa-np.jp/company.html丄
帒椏偦偺俋偼杮揷徃擇楴挊乽栔嫯偵惇偔乿侾係儁乕僕丄徍榓俀侽擭係寧丄戝暷戲報嶞強亖娰撪尷掕嬤僨僕杮丄
|
丂偐偺暥壔戝妚柦偱丄峠塹暫偨偪偵偵傛偭偨杒嫗偺榁曑偺娕斅偼奜偝傟丄壆崋傕曄偊偝偣傜傟偨丅搶棃弴傕柉懓斞涞偲夵柤偝傟偰偄偨偺偱偡偑丄侾侽擭娫懕偄偨偦偺棐偑夁偓丄徍榓俆俆擭傑偱偵楌巎偺偁傞尦偺搶棃弴偵栠偭偨(17)偺偱偡丅俆侽擭慜偺偙偲偱偡偐傜丄偦偺偙傠偺峠塹暫偑儕僢僠側幚嬈壠偵側偭偰杒奀摴娤岝偵棃偰丄崑梀偟偨偐傕抦傟傑偣傫傛偹丅
丂堦帪揦柤傪曄偊偨偙偲偼徍榓俇侽擭偵弌偨乽惉媑巚娋乿偲偄偆杮偵捖弚恇晇恖偺捖嬔墩傕彂偄偰偄傑偡丅偦傟偵偼乽杒嫗偺搶晽巗応偵亀搶棃弴亁偲偄偆屆偄揦偑偁傝丄涮梤擏偱桳柤偱偡丅偙偺揦偼暥妚拞偵偼亀柉懓斞彲亁偲夵柤偟偰偄傑偟偨偑丄偙偺柉懓偼杒曽梀杚偺柉懓傪堄枴偡傞偺偱偟傚偆丅偄傑偼傕偲偺柤偵栠偭偰偄傑偡丅巹傕壗夞偐懌傪偼偙傃丄偦偺偨傃偵偍偄偟偔偄偨偩偒傑偟偨丅梤擏偼恖偵傛偭偰岲偒寵偄偑偁傝傑偡丅堦庬偺側傑偖偝偝偑偁偭偰丄傓偐偮偔偲偄偆恖傕偁傟偽丄偦傟偙偦梤擏偺戠岉枴偩偲偄偆恖傕偄傞偺偱偡丅偲傕偐偔丄梤擏椏棟偵偼偨偔偝傫栻枴偑偮偄偰偄偰丄搶棃弴偱傕偦偺庬椶偑懡偔偰媞偑柪偆傎偳偱偡丅栻枴偼偍傕偵側傑偖偝偝傪徚偡偨傔偵梡偄傞偺偱偟傚偆丅(18)乿偲偁傝傑偡丅
丂偟偐偟丄榁曑側傜慡晹曄偊偰偟傑偊偲偄偆傕偺偱偼側偐偭偨傛偆偱丄媨掛椏棟傪揱偊傞嵐撶嫃偲偄偆揦偼丄偦偺傑傑偩偭偨丅拞崙怘暥壔尋媶壠偺栘懞弔巕偝傫偼乽揱摑椏棟傪揱偊傞榁曑偺揦柤偑丄暥妚摉帪夵柤偝傟偨椺偼懡偄傛偆偩偑丄巐恖慻慡惙偺榋擭慜丄杒嫗偺捠傝傪憱傞僶僗偺憢偐傜亀嵐撶嫃亁偲偄偆揦柤傪尒偨婰壇偑偁傞偐傜丄偦偺柤慜偼巆偭偰偄傞偺偩傠偆偲巚偆丅(19)乿偲彂偄偰偄傑偡丅偄傑側傜僀儞僞乕僱僢僩偱娙扨偵寬嵼傪妋偐傔傜傟傞偑丄徍榓俆俆擭偱偼柍棟偱偟偨偹丅
丂偦偆偦偆丄栘懞偝傫偼乽杒嫗椏偲偦偺摿挜乿偲偄偆偦偺婰帠偱丄僇僆儎儞儘乕傪愢柧偟乽巹傕桳柤側搶埨巗応偺搶棃弴偱涮梤擏丄烤梤擏傪怘傋偨偑丄偙偺揦傕夞嫵搆偺憂嬈偱偁傞丅乿偲彂偄偰偄傑偡丅乮摨俁俀儁乕僕乯
丂偦傟偐傜愴慜偺搶棃弴偲偄偆娤揰偐傜偼扙慄偩偗偳丄栘懞偝傫偑暯惉侾俆擭偺乽偟偵偐乿侾俀寧崋偵彂偄偨乽杒嫗椏棟偺摿挜乿偵晅偄偰偄傞僇僆儎儞儘乕偺幨恀偑偡偛偄丅(20)朘傟偨揦偺愢柧偲楩偺宍偐傜搶棃弴偩偲巚偄傑偡偑偹丄怘傋偰偄傞恖乆偺敘偺挿偝偨傞傗丄榬傛傝挿偄偲偄偭偰傕僆乕僶乕偠傖側偄丅僗儔僀僪偱尒偣偨偄偺偼嶳乆偩偗偳丄挊嶌尃栤戣偱帺怣偑側偄偺偱偹丄尒崌傢偣傑偟偨丅偤傂尒偨偄恖偼暥妛晹恾彂幒傊峴偒側偝偄丅
丂乽杒嫗偺榁曑乿偺偲偄偆杮偵丄從偒擏偺榁曑丄烤擏婫偺宱塩幰丄棝妕恇偲偄偆恖偺夞屭択偑嵹偭偰偄傑偡丅帒椏偦偺侾侽偑偦傟偱偡偑丄搶棃弴傕愊嬌揑偵巟揦傪愝偗偰帠嬈奼戝傪恾偭偨帪婜偑偁偭偨偺偱偡偹丅偙傟偱偼搶棃弴傕僕儞僊僗僇儞椏棟偺働乕僞儕儞僌傪傗偭偨偐偳偆偐偼傢偐傝傑偣傫偑丄徍榓侾俀擭偵杒嫗偺奀孯晲姱偑惓梲極偐傜摴嬶傪塣偽偣偰峲嬻戉堳偵怳傞晳偭偨偲偄偆巚偄弌偼侾審偁傝傑偡丅
帒椏偦偺侾侽
亙棯亜擔杮巟攝偺偙傠丄擔杮偺恖偼偨偄偰偄從擏偑岲偒偩偭偨偺偱丄彮側偐傜偸恖偑棃偨丅堦曽丄傢偨偟偨偪偼擏傪撏偗傞僒乕價僗傕偟偨丅堦夞屲僉儘埲忋偺拲暥偑偁傟偽丄壠傑偱撏偗偰偁偘丄帪偵偼傢偨偟偼彫偝側庤墴偟幵傪梡堄偟偰丄摴嬶丄擏丄挷枴椏丄恉側偳傪忔偣偰丄庤揱偄傪擇恖傎偳楢傟偰弌慜傕傗偭偨傕偺偱偁傞丅師戞乆乆偵丄從擏傪怘傋傞恖偑抜乆憹偊偰偒偨偺偱丄偦傟偼傗偑偰晛捠偺怘傋曽偺堦偮偲側偭偨丅
丂怴拞崙惉棫慜偺堦帪婜丄杒嫗偱偼偐偮偰從擏偺揦偑偄偭傌傫偵椦棫偡傞忬嫷偑偁偭偨丅彜攧恖偼嫞憟傪偡傞傕偺偩偐傜丄從擏彜攧偑栕偐傞偲尒崬傫偱丄堦晹偺恖乆偼傢偨偟偳傕偺嬤偔偵從擏傪巒傔偨丅偨偲偊偽抧奜戝奨偺棿奀嫃丄摨嫽嫃丄枩弴嫃丄憗偄帪婜偺攏奙怘摪側偳偺揦偑傒側從擏傪宱塩偟偰偄偨丅搶忛偺搶棃弴傑偱悢恖傪搳擖偟偰屰極榩偱夞柉懓斞揦傪嶌偭偰擏偺鄒傔丄從偒偲偟傖傇偟傖傇傪愱栧偲偟偰偄偨丅偲偔偵烤擏婫偺搶懁偵偼乽烤擏媑 Kaorou ji乿偑尰傢傟偰丄乽媑乿偲乽婫乿偺敪壒偺憡帡傪棙梡偟偰恖傪閤偦偆偲偟偰偄偨丅偦偺揦偼応強偑峀偔偰愝旛傕惍偭偰偄偨偑丄嵟弶偐傜偤傫偤傫怘傋傞恖偑偄側偐偭偨偺偱丄擇丄嶰偐寧傕偟側偄偆偪偵偮偄偵捵傟偰偟傑偭偨丅亙棯亜
丂擔拞愴憟偱擔杮孯偑拞崙偺杒晹偐傜弴師愯椞抧傪峀偘傞偲丄擔杮偐傜偳傫偳傫椃峴幰偑杒嫗傪朘傟傞傛偆偵側傝丄偦傟偵墳偠偰拞崙偺椃峴僈僀僪丄娤岝埬撪偑弌斉偝傟丄僕儞僊僗僇儞傪徯夘偟偰偄傞偺偱敳偒弌偟偰帒椏偦偺侾侾偵偟傑偟偨丅
丂偦偺拞偺乮俁乯偼徍榓侾侽擭侾侽寧丄忋奀偱擔杮偲拞壺柉崙椉惌晎偵傛傞搶梞岺嬈夛媍偑奐偐傟丄偦傟偵弌偨幮夛妛幰丄墌扟峅偵傛傞傕偺偱偡丅墌扟偼杒嫗側偳婑偭偰偍傝丄怘傋偨偺偼惓梲極偵堘偄側偄偺偱偡偑丄柧婰偟偰偄側偄偺偱堦椃峴幰偺尒暦婰偲偟偰偙偙偵擖傟傑偟偨丅
帒椏偦偺侾侾
乮侾乯烤梤擏
丂壴壆偺揦愭偵媏偺壴偑崄傪偨傔巒傔傞偲丄偦傠偦傠杒嫗柤暔偺烤梤擏偑斞娰巕偺怘戩傪擌偼偣傞丅烤梤擏偲偄傆偺偼丄擔杮偱懎偵塢傆乽僡儞僊僗僇儞椏棟乿偲偄偭偰傤傞傕偺偱丄廮偐偄梤偺擏傪嗾摿偺忀桘偵怹偟丄巐屲広傕偁傞戝偒側鑓壦偺偆傊偵偺偣丄徏傗桍偺恉傪擱傗偟側偑傜丄從偄偰怘傆偺偱偁傞丅悷傒偒偮偨栭嬻偺壓丄敀姡帣傪偺傒側偑傜烤梤擏傪偮偮偔晽忣偼幪偰擄偄傕偺偩丅偙偺椏棟偼堦恖偱擇嬕傗嶰嬕暯偘偰傕堦岦暊偵傕偨傟側偄丅擏偺朢偟偄擔杮偱偼堦悺弌樢側偄椏棟偱偁傞丅杒嫗嵼廧偺擔杮恖偼偙偺烤梤擏偑戝岲偒偩偲尒偊丄烤梤擏僔乕僘儞偵側傞偲丄偳偺揦傕丄擔杮恖媞偱枮堳偵側傞丅偙偺偨傔夞娰乮夞嫵搆偺斞娰巕乯偺洆栧偩偮偨偙偺椏棟傕嬤崰偱偼晛捠偺巟撨斞娰巕偱庢埖傆傗偆偵側偮偨丅桳柤側斞娰巕偱偼丄栔屆偵乽梤寳乿偲偄傆帺壠洆梡偺杚応傪桳偟丄巈梤偺帪暘偐傜丄摿暿偺拲堄傪暐偮偰堢偰偰傤傞丅
乮俀乯亙棯亜
丂師偵斞娰巕偱偼搶埨巗応偺拞偵偁傝傑偡偲偙傠偺搶棃弴傗弔梲極丄慜栧偺攣巗奨偵偁傞抳旤釼摍偱丄傢傟傢傟擔杮恖偑擇丄嶰恖楢傟偱怘帠傪偡傞偺偵嵟傕揔摉偐偲巚傂傑偡丅亙棯亜
乮俁乯
丂丂俆丂閜閗偲惉媑巚娋椏棟
丂杒暯偺巗奨偱丄梤偺孮偑摪乆偲奨摢傪峴恑偟偰傤傞偺偵弌崌傆丅悢廫摢偺梤偑捛偼傟撫傜揹幵楬傪備偔丅揹幵傕楅傪柭傜偟撫傜丄杤朄巕偱桰乆偲梤偺偆偟傠偐傜彊峴偟偰備偔丅傑偙偲偵偺偳偐偱偁傞丅亙棯亜
丂杒暯懾嵼拞偵丄巹偼梤偺峴曽傪偨偯偹傞栿偱偼側偐偮偨偑丄揹捠偺杒暯巟嬊挿偺埬撪偱僕儞僊僗僇儞椏棟傪怘傋偵峴偮偨丅僕儞僊僗僇儞撶偲偐偄傆偺偼丄嬤崰搶嫗偱傕嬺傋偝偣傞檤偑偁傞傗偆偩偑丄偙偺杒暯偺僕儞僊僗僇儞椏棟偼摿桳側庯傪傕偮偰傤傞丅晛捠偺巟撨椏棟壆偺峔憿偩偑丄壠偺拞偵拞掚偺傗偆側偲偙傠偑偁偮偰丄惵揤堜偺壓偵慹枛側僥乕僽儖偑挿偄儀儞僠偵埻傑傟丄拞墰偵偼捈宎嶰広埵偺揝偺楩偑偁偮偰丄偦偺拞偱擇広埵偺徏娵懢偑惙偵崟偄墝傝傪忋偘偰擱偊偰傤傞丅偙偺楩偺忋偵偼峳偄揝偺栐偑從偗偰傤傞丅梡堄偺偳傫傇儕偺拞偵偼拫娫尒偨梤偺孮偐偳偆偐抦傜側偄偑丄恀愒側梤擏偑弮敀側帀擏傪晅偗丄惵偄擪偺崗傒崬傑傟偨偺偲堦弿偵側偮偰忀桘偵捫偗偰偁傞丅偙傟傪堦広埲忋傕偁傞挿偄敘偱偼偝傫偱丄愒偔從偗偨揝栐偺忋偵梘偘偰鄤傞偺偱偁傞丅塃庤偱偙偺敘傪岻偵偁傗偮傝側偑傜擏傪從偄偰嬺傋傞丅棫偮偰堉巕偺忋偵嵍懌傪忔偣丄旼偺忋偵嵍庤偺旾傪偮偄偰丄庤愭偵偼嫮楏側從拺偑攗偐傜岥傊塣偽傟傞丅偙傟偑偙偺僡儞僊僗僇儞椏棟偺嶌朄偩偦偆偱偁傞偑丄嬌傔偰尨巒揑偱拞乆偆傑偄丅業揤偺偙偲偲偰丄搤偵側傞偲愥偺僠儔乛乢偡傞壓偱丄偠備偆両偠備偆両偲丄徏壩偵梤擏偺帀傪偝傜偟丄擬偄搝傪岥偵塣傇丄從拺偼堓戃偺嬿乆傑偱從偒恠偡乧乧偙傟偼杒暯惗妶幰偱側偗傟偽枴偼傊側偄偲偄傆偺偱偁傞偑丄摿挜偺偁傞椏棟偩丅椏棟偲塢傆傛傝丄傓偟傠怘傋曽偺曽偑揔摉偱偁傞偐傕抦傟側偄丅亙棯亜
丂偦偺傎偐宯摑棫偰偰挷傋偨傢偗偱偼偁傝傑偣傫偑丄徍榓侾侽擭偵偼擔杮夋偺愇堜攼掄傗梞夋偺摗揷巏帯傜偑彽偐傟偰偍傝丄愇堜偼乽撿枮嶨娤乿偲偄偆僗働僢僠晅偒悘昅傪彂偄偰偄傑偡丅偙偺偲偒偺枮揝彽懸偲偼暿傜偟偄偺偱偡偑丄摗揷偼徍榓俋擭侾侾寧偵杒嫗偵峴偒丄梤擏椏棟傪怘傋偨偲乽暥錣弔廐乿偵彂偄偰偄傞偺傪尒偮偗傑偟偨丅乽忋嫗棤嫀乿偲偄偆悘昅偵乽栔屆椏棟曮尮極偲尵傆偵梤擏傪帋怘偟偰尒傞丅(21)乿偲偄偆偨偭偨堦尵偱丄偆傑偄偲傕捒偟偄偲傕彂偄偰偄傑偣傫偑偹丅
丂傕偭傁傜業揦偱傕怘傋偨傜偟偄偺偼夋壠偺栰岥媊宐偱偡丅乽塰梴偲椏棟乿偵嵹偭偰偄傞悘昅乽杒嫗偺枴乿偼乽杒嫗傪擿偄偨偺偼愴憟偺偼偠傑傞彮偟慜偱懾棷嶰働寧亙棯亜乿偲偁傞偺偱丄徍榓侾俀擭俈寧偺岣峚嫶帠審傪敪抂偲偟偨巟撨帠曄偺彮偟慜側偺偱偟傚偆丅乽杒嫗奨偵灔偑偮傗乛乢偲怓偯偒丄傒偫偐偄桵偐傜婲偒偩偟偺屍柡偺榬偵栭晽偑椻偨偔偁偨傝弌偡偲偦傠偦傠惉媑巚娋撶偑偼偠傑傞丅亙棯亜乿偲偄偆偐傜廐偩偭偨偺偱偟傚偆丅偨傟偺枴傕偝傞偙偲側偑傜乽慜栧奜偺惓梲極偑堦斣偲暦偔偑丄巹偵偼柤傕側偄揦偺娬庘側枴傕枖暿側枴傂偲側偮偰丄怓偁偞傗偐側巚傂弌偲側偮偰傤傞丅乿偲寢傫偱偄傑偡丅
丂偙傟偵偼乽惗棃偺怘偟傫朧偵辶偑偐乀偮偰丄幨惗挔傪偐乀偊偰奨偐傜層摨傊偲廔擔曕偒夢傞擔壽偺偐偨偼傜丄傆偲偙傠偺傗傝偔傝傪偟偰偼怘傋曕偄偨乿偲偒昤偄偨乽惉媑巚娋撶丂惣扨攙極僯僥乿偲偄偆憓奊偑晅偄偰偄傑偡丅(22)撶偺岦偙偆偵拞崙暈偺抝侾恖丄庤慜偵梺堖偺擔杮恖偺抝偑俀恖丄偦傟偧傟挿堉巕偵曅媟傪忋偘偰戝偒側撶傪埻傫偱偄傑偡丅
丂偮偄偱偱偡偑乽塰梴偲椏棟乿偱偼傕偆侾偮丄拲栚偡傋偒巚偄弌偑偁傝傑偡丅偦傟偑帒椏偦偺侾俀偺彑枖壏巕偺乽廳梲愡偲杒暯椏棟乿偱偡丅偙傟偵偼撶偲偦傟傪埻傫偩擏偺嶮側偳傪嵹偣偨僥乕僽儖俁戩傪忋偐傜尒偨奊偑晅偄偰偄傑偡丅彑枖帺恎偑昤偄偨偺偐傕抦傟傑偣傫偑丄郷偺壠偺幨恀偺撶偲偼堎側傞偟丄偳偪傜偐偲偄偊偽鄡楩偺峔憿偼乽拞崙柤嵷廤嬔丂杒嫗嘥乿偵宖嵹偝傟偰偄傞乽烤擏婫乿偺撶傒偨偄偩偑丄揝斅偑堘偆傛偆偱偡丅
丂偳偪傜偺奊傕僀儞僞乕僱僢僩忋偱尒傜傟傞偺偱丄僗儔僀僪偵偼偟偰偄傑偣傫丅彈巕塰梴戝妛偺乽塰梴偲椏棟乿僨僕僞儖傾乕僇僀僽偵傾僋僙僗偟側偝偄丅
帒椏偦偺侾俀
丂烤擏乮梤丄媿摍偺僡儞僊僗僇儞椏棟乯
丂廳梲偺崰偐傜惙偵側傞烤擏偼杒暯巗撪偵偙傟偱柤傪攧偮偨揦偑擇丄嶰偁傝丄嬤擭偼慡慠愄偺枴傪幐偮偰偟傑偄傑偟偨偑帠曄慜枖偼帠曄屻擇擭埵傑偱偼栔屆偐傜塣傫偱枴傪屩偮偨暔偱偡丅偟偐傕懘塣傃曽傕憪傪怘傋偝偣撫傜曕偐偣偰樢偨暔傪忋暔偲嬫暿偟偨傕偺偱偟偨丅偙傟傪愱栧偵愗傞怑恖偑嫃偰巻偺條偵敄偔愗傞偺傪摿挜偲偟傑偡丅戝偒側揝斅偺堦悺嬓埵偺傕偺傪堦暘埵姶妎傪偍偄偰暲傋娵偔偦偟偰拞墰傪彮偟崅偔嶌傝丄崅偝傕堦広埵偮偗偰堦曽偵岥傪偁偗偨戝摴嬶傪戝偒側揝楩偵偐偗丄岥偐傜桍偺傑偒傪擖傟偰僪儞僪儞擱傗偟揝斅偺擬偔側偮偨強偱惗擏傪悢曅偼偝傫偱堦悺挷枴椏傪偮偗偰偡偖偺偣偰僡乕僡乕從偒撫傜捀偔偺偱偡丅栜榑偍庰傪偺傒撫傜偱偡偟恮拞椏棟偱偡偐傜棫怘偱偡丅枖崯帪從栞偲塢偮偰曅柺偵崄偽偟偔僑儅傪偮偗偰從偄偨庡怘傪怘傋崌傢偣傑偡偑丄從栞偼堦曽傪偐偠偮偰乮枖曅庤偱乯拞偵敘傪擖傟傞偲億僇僣偲岥傪偁偔條偵傎偐傎偐弌樢偰嫃傑偡偺偱崯拞偵從偄偨擏傪擖傟偰捀偗偽摿偵旤枴偟偄偺偱偡丅晅偗廯偼忋摍拞崙忀桘丄庰傪崌傢偣丄擪丄惗錑媦傃崄嵷偲塢偮偰丄嶰偮梩偲僙儕偺崌偄偺巕偺條側崄婥偺嫮偄惵偄暔傪崗傒崬傫偩傕偺丅捫暔偼昮偺嵒摐捫偲偒傑偮偰嫃傑偡丅
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮侾俈乯偺弌揟偼搶梞巎尋媶夛曇乽搶梞巎尋媶乿俁俋姫俀崋侾俇侾儁乕僕丄栘揷抦惗乽杒嫗棷妛婰乿丄徍榓俆俆擭俋寧丄搶梞巎尋媶夛亖尨杮丄
乮侾俉乯偼旜嶈廏庽丄嬵揷怣擇丄捖弚恇曇乽惉媑巚娋乿侾係俉儁乕僕丄捖嬔墩乽梤偁傟偙傟乿丄徍榓俇侽擭俁寧丄墵暥幮亖尨杮丄
乮侾俋乯偼戝廋娰彂揦曇乽寧姧尵岅乿俋姫俁崋俁俁儁乕僕丄徍榓俆俆擭俁寧丄戝廋娰彂揦亖尨杮丄
乮俀侽乯偼戝廋娰彂揦曇乽寧姧偟偵偐乿侾係姫侾俀崋俀俈儁乕僕丄栘懞弔巕乽杒嫗椏棟偺摿挜丂乗杒偺晽搚偲搒偺楌巎乿丄暯惉侾俆擭侾俀寧丄戝廋娰彂揦亖尨杮丄
帒椏偦偺侾侽偼杒嫗巗惌嫤暥巎帒椏尋媶夛曇丒梜嬇彿栿乽杒嫗偺榁曑乮抷柤嫗壺揑榁帤柤乯乿俆俀儁乕僕丄暯惉俀擭俋寧丄怱岎幮亖尨杮丄
帒椏偦偺侾侾乮侾乯偼壺杒岎捠姅幃橉幮帒嬈嬊曇乽杒巟乿俀俉崋係俉儁乕僕丄乽杒巟挩択乿丄徍榓撨侾俇擭俋寧丄壺杒岎捠姅幃橉幮帒嬈嬊亖尨杮丄
摨乮俀乯偼堜愳崕枻曇乽拞崙偺晽懎偲怘昳乿侾俋俇儁乕僕丄戝栘堦榊乽拞崙椏棟偵偮偄偰乿丄徍榓侾俈擭丄俀寧丄壺杒岎捠幮堳夛亖尨杮丄
摨乮俁乯偼墌扟峅挊乽巟撨幮夛偺應検乿俀俋係儁乕僕丄徍榓侾侾擭俋寧丄桳斻妕亖嬤僨僕杮丄
乮俀侾乯偼暥寍弔廐幮曇乽暥寍弔廐乿侾俆姫侾侾崋俀侽侽儁乕僕丄乽慭梀巟撨乿丄摨侾俀擭侾侾寧丄暥寍弔廐幮亖尨杮丄
乮俀俀乯偼塰梴偲椏棟幮曇乽塰梴偲椏棟乿侾俁姫侾崋俁俀儁乕僕丄栰岥媊宐乽杒嫗偺枴乿丄徍榓俀俀擭侾寧丄塰梴偲椏棟幮亖尨杮丄
帒椏偦偺侾俀偼摨侾係姫侾侽崋係係儁乕僕丄彑枖壏巕乽廳梲愡偲杒暯椏棟乿丄徍榓俀俁擭侾侽寧丄塰梴偲椏棟幮亖尨杮
|
丂偲偙傠偱彑枖寷帯榊偲偄偆棷妛惗偑抾撪岲偲摨帪偵杒嫗偵峴偒傑偡丅偦偺屻偺抾撪偺擔婰偵壗搙傕弌偰棃偰丄墱偝傫偑偄偨偙偲傕傢偐傝傑偡丅彑枖側傫偰偦偆僓儔偵偁傞柤慜偱偼側偄偐傜丄帒椏偦偺侾俁偺彑枖壏巕偑丄偙偺彑枖偺墱偝傫偱偼側偄偐挷傋偰傒傑偟偨丅
丂彑枖寷帯榊偑彂偄偨乽戝棨柉懎偺晽栾乿傪撉傫偩傜乽怘乿偲偄偆復偵乽巹偑偙偪傜傊樢偨醕嵗丄柉廜怘傪傗偮偰尒偨偄偲埥傞戝恖亙偨偄偠傫偲儖價亜偵楻偟偨傜丄戝恖偼栚傪傓偄偰丄柉廜怘偲偼堦懱壗偺偙偲偩偲暦偐傟偨偐傜丄巹偼嫲傞乛乢椺偺奨忋偵暲傫偱傞怘傂傕偺偱偡偲曉摎偵媦傫偩傕偺偩丅偡傞偲戝恖偼塿乆晄夣偝偆偵丄偦傫側棎朶側偙偲偼偍傛偟側偝偄偲幎偮偰偍偄偱偩偮偨丅慠偟巹偺埆庯枴偼崱擔傕桙傜側偄偱丄戝偒偄斞娰巕偺曵傟偨挷棟傛傝傕丄摴朤偺桘栞傗摛晠憻偵帄枴偑偁傞偲巚偮偰傤傞丅奰丄摐層錬丄烤敀彃丄偦傟傜傪嫕炠偟恠偟偰偙偦杒嫗偺枴偑傎偺乛乢丣偲敾傞偺偱偁傞丅亀堦懱擛壗側傞椏棟偱傕丄擬怱偵慜埲偰榑偠偨傝丄怘偆偰偐傜斸昡偡傞偲偄傆晽偱側偗傟偽丄偦偺椏棟傪傎傫偨偆偵妝偟傫偱傤傞偺偱偼側偄偺偩丅亁偙傟傕椦岅摪濰偔偱偁傞丅(23) 乿偲偼偁傞偗偳丄僇僆儎儞儘乕偆傫偸傫偼側偟丅
丂棷妛偼乽巐寧弶傔偵撍慠杒嫗峴偺榖偑偁偮偰彫偝偄拞栰偺壠傪戝憶偓偱忯傓偲鷬纭偲偟偰搫煒晆摢偵偁偑偮偨丅巹偼擇搙栚偺戝棨偩偑丄嵢偼弶傔偰偺奜崙峴偱偁傞丅(24) 乿偲偟偐彂偄偰傑偣傫偱偟偨丅
丂寷帯榊偲壏巕偑晇晈偩偭偨偲壖掕偡傟偽丄晇偑偙偆側傫偱偡偐傜丄杒嫗偺柉廜怘偲偄偆偐丄捒偟偄怘暔傪榑偠斸昡偟崌偭偰偄傞偆偪偵丄壏巕偝傫偑巟撨椏棟偺尋媶偵摜傒崬傓偙偲偼偁傝偆傞偑丄偳偆傕壏巕偝傫偼傕偲傕偲椏棟尋媶壠偩偭偨傜偟偄偺偱偡丅
丂徍榓侾係擭偵杒嫗偵偄偨擔杮恖偺僋儕僗僠儍儞偑擔杮婎撀嫵惵擭夛娰傪寶偰傛偆偲塣摦傪婲偙偟丄壖夛娰偱偄偔偮偐曌嫮夛傗島廗夛傪奐偄偨丅偦偺偙傠壏巕乮僴儖僐乯偝傫偑杒嫗偱敪峴偝傟偰偄偨擔杮岅偺乽搶槺怴曬乿偵椏棟偺婰帠傪彂偄偰柤傪抦傜傟偰偄偨偨傔丄壏巕偝傫偑椏棟島廗夛傪奐偔偲乽庡晈払偑墴偟偐偗偰丄怘摪傕挷棟応傕拫娫偼堦攖偱偁偭偨丅(25)乿偲偄偆曬崘偑偁傝傑偡丅
丂偝傜偵徍榓侾俈擭偺乽塰梴偺擔杮乿俉寧崋偵崙棫杒嫗戝妛堛妛晹彫帣壢嫵幒偲偄偆尐彂偒偱乽拞崙擕梒帣偺怘塧偵廇偰乿丄侾俋擭偵杒嫗摨恗夛偺夛帍乽摨恗夛曬乿戞侾俇嶜偵杒巟塹尋偲偄偆尐彂偒偱乽堦斒拞崙恖偺壠掚怘偵廇偄偰乿乮徍榓侾俋擭侾寧乯偲偄偆曬崘傪彂偄偰偄傞偙偲偐傜丄壏巕偝傫偼塰梴妛偺尋媶幰偩偭偨偐傕抦傟傑偣傫丅
丂傑偨壺杒岎捠偑杒巟暥壔徯夘帍偲偟偰弌偟偰偄偨寧姧帍乽杒巟乿俀俋崋乮徍榓侾俈擭侾侽寧乯偵偼巟撨椏棟尋媶壠偲偄偆尐彂偒偱椏棟悘昅乽鄝栞偲奍乿傪彂偄偰偄傞丅愴屻堷偒梘偘偰偒偨偲偡傟偽丄俉擭偼杒嫗側偳偵偄偨偙偲偵側傝丄椏棟揦偲堦斒壠掚偺幚忣傪抦傞偙偲偑偱偒偨偺偱偟傚偆丅
丂偩偐傜乽廳梲愡偲杒暯椏棟乿偵乽杮醕偵擏傪枴偄偵備偔杒嫗恖偼屻偼埦偵彫摛傪擖傟偨撈摿偺偍姛偵嵒摐傪廩暘偵擖傟偰偡偡傝墫恏栚偺扨枴怘偺屻岥偺枮懌傪偝偣偰婣傞偺偑偮偒傕偺偱偡丅烤擏偺屻暯杴側怓乆偺椏棟傪拲暥偡傞恖偼杮摉偺杒暯偺枴傪抦傜側偄恖偺偡傞帠偱偡丅乿偲尵偄愗傝乽壠掚偱彽媞偵梡偄傞帪偼愱栧揦傪屇傋偽摴嬶帩嶲偱壠偺拞掚偱娙扨偵怘傋傜傟傑偡丅(26)乿偲働乕僞儕儞僌偺懚嵼傕抦偭偰偄偨偺偱偡偹丅
丂僨僓乕僩傒偨偄側姛傪怘傋傞偙偲偼搶梞巎偺徏揷庻抝偑扤偐偵暦偐偣傞傛偆側宍偱彂偄偨巚偄弌偵傕偁傝傑偡丅帒椏偦偺侾俁偱傢偐傞傛偆偵徏揷偼擔杮偺撶偼彫偝偄偲扱偄偰偄傑偡偑丄偄偄偠傖側偄偱偡偐偹偊丅偲偠傚偆撶傗嶗撶傪尒側偝偄丅悢恖偱傗傞偡偒從偒撶偱偝偊丄偁偺戝偒偝側傫偱偡偐傜偹丅戝惃偱戝撶傪埻傒丄挿偄敘偱怘偆側傫偰愭恖偵偼巚偄傕傛傜偸偙偲偩偭偨傫偱偡側偁丅
帒椏偦偺侾俁
丂丂丂丂擏怘偺栔屆偲僕儞僊僗僇儞側傋
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂憗戝嫵庼丂徏揷庻抝
丂偆傑偄傕偺偼朷傔側偄偵偣傛丄偣傔偰庡怘偺擏傪暊偄偭傁偄怘傋偨偄擭崰傪丄偁傢傟傗栘偺幚丄憪偺崻偱偑傑傫偟偰曢偟偨僕儞僊僗僇儞偺柤傪懷傃偨椏棟偑偁傞丅傕偪傠傫栰憪椏棟偱偼側偔偰丄栔屆恖偺摼堄側擏椏棟丅偍偦傜偔栔屆椏棟偲柫偆偪偨偄偲偙傠傪丄僕儞僊僗僇儞偵柤傪庁傝偰丄恖栚傪傂偙偆偲偟偨偺偱偁傠偆丅栔屆偐傜偺婣搑丄杒嫗偵棫婑偭偰丄偙偺椏棟傪徯夘偝傟偨偲偒丄幚偺偲偙傠巹偼丄揝側傋偺拞偺梤偺墫偆偱傪梊憐偟偨丅偲偙傠偑戝偪偑偄丅
丂側偵偟傠丄崱偱偼傕偆擇廫擭偺愄偵側偭偰偟傑偭偨偐傜丄偲偐偔婰壇偑傏傗偗偰偄傞偑丄埬撪偝傟偨擇奒偺堦幒偼丄偐側傝峀偐偭偨丅斅挘傝偺彴偵丄偄偔偮偐偡偊偮偗傜傟偨攚偺崅偄墌偄僇儅僪丅偦傟傜偵偼丄揝惢偺僇儅儃僐宍偺栐偑偡偭傐傝偲偐傇偣偰偁偭偰丄偪傚偆偳恖偺嫻忎傎偳丅媞偼偦偺傑傢傝偵棫偭偨傑傑丄僗僉儎僉偺媿擏偝側偑傜偵嶮偵側傜傋偰偁傞梤偺擏傪偮傑傒偁偘丄栐偺幬柺偵偁偰偰從偔丅偙偺栐偑揝惢側偑傜栔屆恖偺僥儞僩偺崪慻偝側偑傜側偺偵丄偼傞偐偵墱抧傪偟偺傫偱擏傪偁偰偰偄傞偲丄擏廯偼壓偵棳傟偰丄傆偪偵偮偗傜傟偨儈僝偵偨傑傞丅偩偟傪偮偗偰偼從偒丄偨傑偭偨廯傪偮偗偰偼怘傋傞丅傕偪傠傫曅庤偵斞榦側偳偼偵偓偭偰偄側偄丅弌傞偼偢傕側偄偺偱偁傞丅
丂偟偨偨偐偵梤偺從擏傪暊偵偮傔偰丄暿惾偵戅偔偲丄傾僘僉偺僇儐偑堦榦偼偙偽傟偰偔傞丅偆傟偟偄偙偲偵偼丄偙傟偼変乆偺偄偆屼慥廯暡偦偭偔傝丅僉儊傕嵶偐偵丄傾僘僉傪偰偄偹偄偵偙偟偰偁傞偐傜丄揷幧廯暡偵偼偨偲偊傜傟偸丅偦偺巼怓偑丄栚傕偝傔傞傎偳偁偞傗偐偱旤偟偐偭偨丅傓傠傫丄廯暡偱偼側偄偐傜丄娒枴側偳偮偗偰偼側偄丅媞偼偦偙偵偝偟偩偝傟偰偄傞嵒摐氣偐傜丄偍偺偍偺帺暘偺岥偵偁偆偩偗偺嵒摐傪偲偭偰丄僇儐偵擖傟偰偨傋傞丅幚偵偆傑偄傕偺偱偁偭偨丅側傫偱傕儅僱岲偒側擔杮恖偑丄偙傟偩偗偼傑偩傑偹偰偄側偄丅壡暦偱偼偁傞偑丄偄傑傕巹偼偦偆巚偭偰丄巼怓偺偝傜傝偲偟偨杒嫗偺僇儐傪側偮偐偟傫偱偄傞丅
丂偦偺偲偒壗攖偨傋傑偟偨偐乧乧偭偰丠丂偳偆偄偨偟傑偟偰丄堦攖偒傝偟偐偔傟傑偣傫丅側偵偟傠栔屆恖偺怘帠偺棫慜偱偼丄偦傟偼柧偐偵揧偊暔偵偡偓側偄偺偱偡偐傜丅擔杮恖偑惣梞椏棟偱僷儞偺偍偐傢傝傪偡傞偺偲偼丄偪偑偄傑偡傛丅
丂偮偄偱側偑傜擔杮偺僕儞僊僗僇儞側傋偼丄杒嫗偺傕偺偵偔傜傋傞偲丄傑偭偨偔娺嬶偵摍偟偄傕偺偱偁傞丅巹偼偁傑傝懡偔傪宱尡偟偰偄側偄偗傟偳丄偦傟偼捈宎栺嶰乑僙儞僠偺娵傾儈偵傗傗孹幬傪偮偗偨偩偗偺傕偺丅傑偝偵搰崙揑偲偄偍偆偐丄巐忯敿庯枴偲偄偍偆偐丅
側偝偗側傗僕儞僊僗僇儞偺梇戝傪幟偽偣傞傕偺偼壗傕側偐偭偨丅
丂徏揷偼偄偮偛傠栔屆椃峴傪偟偨偺偐挷傋偰偍傝傑偣傫偑丄夑棃晀晇偑徍榓侾俀擭偵弌偟偨乽愒棁偺巟撨乿偵傛傟偽乽栔屆椏棟偲塢偮偰杒暯偱徿旤偡傞偺偼梤擏偺敄偔愗偮偨偺傪壆奜偺暟壩偺忋偵偁傞揝忦偺忋偱丄帺暘偱挿偄敘傪帩偮偰廯傪晅偗偰從偄偰怘傆偺偱丄擏偑崟徟偘偵側偮偰梋傝婥枴偺傛偄傕偺偱偼側偄偑丄懘拞偵堦庬偺枴偑偁傝丄棫怘偱偁傞偺偲丄庰偼崅怆庰偟偐堸傑偣偸偺偑摿怓偱偁傝傑偡丅(27)乿偲愢柧偟偰傑偡丅偙偆偟偨昞尰偐傜尒偰丄徍榓侾侽擭戙偺杒嫗偵偼丄傑偩栔屆椏棟偲屇傇恖偨偪偑偄偨傛偆偵巚傢傟傑偡丅
丂偝偰丄憗堫揷偑弌偨偐傜偵偼宑墳丅帒椏偦偺侾係乮侾乯偼乽嶰揷暥妛乿偵偁偭偨拞懞宐偺乽杒嫗惗妶戞堦壽乿偱偡丅弫柧極偲偄偆揦柤偼乽杒嫗彜岺柤娪乿偺斞憫摨嬈岞夛偺柤曤偵傕偁傝傑偡偟丄搶埨巗応偺柤曤偵傕偁傝傑偡偹丅埨摗峏惗偺乽杒嫗埬撪乿偱偼嶳搶娰丄嶳搶椏棟偺揦偵暘椶偝傟偰偍傝丄(28)偩偐傜僕儞僊僗僇儞偼弌偝側偄偲偼尵偄愗傟傑偣傫偑丄拞懞偼徍榓侾俁擭偺俋寧枛偐傜杒嫗偵廧傫偩偽偐傝偱偟偨偐傜丄怘傋曽偺偳偙偑擔杮幃偵側偭偨偺偐丄傛偔傢偐傜側偐偭偨偲巚偄傑偡傛丅傑偩尒偍傝傑偣傫偑丄拞懞偼乽嶰揷昡榑乿偵乽杒嫗偺朰擭夛乗媦愳嫵庼傪埻傫偱乗乿側偳傕彂偄偰偄傑偡偹丅偁偁丄偦傟偐傜偄傑偄偭偨搶埨巗応偺柤曤偱偡偑偹丄惿偟偄偙偲偵揦柤偲宱塩幰偺柤慜偩偗側偺偱奺揦偺彜攧偑傢偐傜傫丅偱傕侾侾俁揦偺偦偺柤曤偼丄斞憫摨嬈岞夛偲摨偠偔島媊榐偺曽偱傒傜傟傞傛偆偵偟偰偍偒傑偡丅亙島媊榐傪尒偰偄傞恖偼偙偙傪僋儕僢僋偟側偝偄丅亜
丂帒椏偦偺侾係乮俀乯偼晳摜壠偺愇堜敊偺杮偐傜偱丄搶棃尙偲彂偄偰偄傑偡偑丄搶棃弴偱偡偹丅愇堜偼偙偺俁擭慜偵傕暫戉偝傫偺堅栤偱杒嫗偵棃偰偍傝丄偦偺偲偒壗夞偐怘傋偵棃偰偄傞偺偱丄椺偺搶棃弴偱偁傝丄婄側偠傒偺儃乕僀偲彂偄偨傢偗丅壠偺楢拞偲偄偆偺偼搶嫗偐傜楢傟偰偒偨晳梮抍偺儊儞僶乕偺偙偲偱偡丅
丂嵟屻偺乮俁乯偼丄搶棃弴偵擖偭偨壺杒岎捠幮堳丄拞搰峳搊偺幐攕択偱偡丅搶棃弴偱偼宱塩幰偩偗偱側偔廬嬈堳傕慡堳夞嫵搆偱偁傝丄斵摍偑偄偐偵撠丄撠擏傪寵偆偐偑偆偐偑偊傞僄僺僜乕僪偱偡丅尒傞偐傜偵撠旂偺嵿晍偐傜庢傝弌偟偨偍嶥傕庴偗庢傜側偐偭偨偐偳偆偐傑偱彂偄偰梸偟偐偭偨偲巚偄傑偣傫偐丅傆偭傆偭傆丅
帒椏偦偺侾係
乮侾乯亙棯亜
丂搈愭惗乗乗偙傟偼惓偟偄敪壒偱嫵傊傜傟偨丄俽孨偑徯夘偺偲偒嫵傊偨偺偩偑丄杔偺妎偊偨嵟弶偺巟撨岅偱偁傞丅俽孨偼搈愭惗偺椙偒桭恖偱偁傞偽偐傝偱側偔丄搈愭惗堦壠偺埥傞堄枴偱偺憡択栶偱傕偁偮偨丅斵偺杮幮婣娨偺擔傕偄傛乛乢敆偮偨偺偱丄巹傪搈堦壠偵徯夘偟偰憡択栶傪堷偒偮偑偣傗偆偲塢傆焼帩傗丄棫偪傇傞傑傂偺擇偮偺堄枴偐傜搈愭惗偺壠懓敧恖偲巹偲傪搶嫗巗応偺弫柧極偵彽偄偨丅弫柧極偼杒嫗偺擔杮恖偺娫偵惉媑巚娋椏棟偱桳柤偩丅懞忋抦峴巵偵尵偼偣傞偲丄擔杮恖偑樢偰偡偮偐傝擔杮幃偺椏棟偵偟偰偟傑偮偨偲塢傆偙偲偩偑丄楑偔偰恊偟傒偺偁傞熐憪偺暷媣偺傗偆側姶偠偱偁傞丅巟撨椏棟偼傕偲乛乢媞偺拹暥傪庴偗偱偐傜壩傪擖傟偰備偮偔傝椏棟偺枴傪枴傆傕偺偩偲偄傆偺偵丄擔杮恖偼偣偮偐偪偵偣偒棫偰傞偺偱嬤崰偼弌樢崌傂傪嶌偮偰偍偄偰壏傔偰帩偮偰樢傞揦偑懡偄偝偆偩丅弫柧極傕枓擔杮恖偵傛偮偰枴傪僗億僀儖偝傟偨椏棟壆側偺偩偦偆偩偑丄偦偺曈偼樢偨偽偐傝偺巹偵偼彮偟傕敾傜側偄丅亙棯亜
乮俀乯亙棯亜
丂嵞夛傪栺偟偰戝巊娰傪弌偨巹偼丄搶埨巗応偵擖傜偆偲偡傞偲丄嬼慠偵傕壠偺楢拞偵弌夛偮偨偺偱丄柤暔偺惉媑巚娋撶偺栺懇傪壥偨偡堊傔偵丄椺偺搶棃尙偺偆偡墭偄奒抜傪搊偮偨丅
丂嶰奒偵峴偔偲婄撻愼偺儃乕僀偼丄恀偮崟偵攣傏偗偨丄憢偺偸偗偨壆忋偺幒偵埬撪偝傟偨丅懘張偵偼崢偺崅偝偺恉鈣偺傗偆側傕偺偑暲傋傜傟偰丄偦偺忋偵偼恀偮崟側揝偺朹偑拞崅偵暲傋傜傟偰偁偮偨丅恉壩偑儊儔乛乢偲愒偄墜傪揻偄偰擱偊偝偐偮偰傤傞丅偦偺忋偵擝廯傪偸傝偮偗偨梤偺擏傪從偒側偑傜怘傋傞偺偱偁傞偑丄偦偺慜偵偼屆傏偗偨堉巕偺條側鋓偑廃埻偵抲偐傟偰偁傞偑丄偙偺忋偵曅懌傪偺偣棫怘偡傞崑憇側偝傑偼丄偨偟偐偵惉媑巚娋撶傪偼偯偐偟傔側偄傕偺偱偁傞丅
丂堦峴幍恖偑枮暊偵側偮偰傕丄戙嬥偼嬐偐屲墌懌傜偢偺巟暐傂偵夁偓側偄偲塢傆偙偲傕丄搶嫗偱偼摓掙憐憸傕弌棃側偄偙偲偱偁傞丅亙棯亜
乮俁乯
亙棯亜丂嫀擭偺崱崰偱偁偮偨丅扤偐傪埬撪偟偰搶埨巗応偵峴偮偨帪丄弔梲極偱寧栞傪攦偮偰偦傟傪帩偮偰岦椬偺搶樢弴偺壆忋偵忋偮偨丅烤梤擏傪嬺傋傞偮傕傝偱偁傞丅灗巕偺慜偵崢偐偗偰曪巻傪奐偗偨傜氺寁偑旘傫偱樢偰欛柭傝弌偟偨丅偦傟偼壗偐丄偳偙偐傜攦偮偰樢偨偐丄奐偗偰偔傟偨傜崲傞偲尒傞傕墭傜偼偟偄婄傪偟偰灗巕妡傪堷奜偟偨丅偁偁柧敀柧敀丄巹偼湳傟偰傗偮偲婥偑偮偄偨偗傟偳傕氺寁偑寖偟偄偺偱暊傪棫偰堄抧偵側偮偰堦偮嬺傋偨丅偝偆偟偰偙偙偼惔崃乮夞乆嫵搆乯偩偐傜撠擏傪巊偆偨寧栞偑焼偵怘偼傫偺偱偡傛偲敿暘偍媞偵幱偮偨丅惔崃偵偼惔崃偺寧栞偑偁傞偺偱偡丅亙棯亜
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮俀俁乯偺弌揟偼彑枖寷帯榊挊乽戝棨柉懎偺晽栾乿侾俀俈儁乕僕丄徍侾俈擭侾寧丄墿壨彂堾亖尨杮丄
乮俀係乯偼摨俀俀俆儁乕僕丄摨丄
乮俀俆乯偼抮揷慛挊乽撥傝擔偺擑乿俁俁俁儁乕僕丄暯惉俈擭俇寧丄忋奀擔杮恖倄俵俠俙係侽擭巎姧峴夛亖尨杮丄
乮俀俇乯偼塰梴偲椏棟幮曇乽塰梴偲椏棟乿侾係姫侾侽崋係係儁乕僕丄彑枖壏巕乽廳梲愡偲杒暯椏棟乿丄徍榓俀俁擭侾侽寧丄塰梴偲椏棟幮亖尨杮丄
帒椏偦偺侾俁偼梇寋幮曇乽栰奜椏棟丂僺僋僯僢僋椏棟偲僶乕價僉儏乕 栰嶳丒奀丒偍掚偱乿侾俇儁乕僕丄徍榓俁係擭俇寧丄梇寋幮亖尨杮丄
乮俀俈乯偼夑棃晀晇挊乽愒棁偺巟撨乿俉俈儁乕僕丄徍榓侾俀擭俋寧丄嶰妢彂朳亖尨杮丄
乮俀俉乯偼埨摗峏惗挊乽杒嫗埬撪婰乿俀俇係儁乕僕丄徍榓侾俇擭侾侾寧丄怴柉彂娰亖尨杮丄
帒椏偦偺侾係乮侾乯偼嶰揷暥妛夛曇乽嶰揷暥妛乿侾係姫侾崋俀俈俇儁乕僕丄拞懞宐乽杒嫗惗妶戞堦壽乿丄徍榓侾係擭侾寧丄嶰揷暥妛夛亖尨杮丄
摨乮俀乯偼愇堜敊挊乽峜孯堅栤丂杒巟偐傜拞巟傊乿俁俇儁乕僕丄徍榓侾係擭係寧丄戝擔杮梇曎夛島択幮亖娰撪尷掕嬤僨僕杮丄
摨乮俁乯偼枮廎暥榖夛曇乽戝棨偺憡杄乿俀俇係儁乕僕丄拞搰峳搊乽拠廐乿傛傝丄徍榓侾俇擭係寧丄枮廎擔擔怴暦幮媦傃戝楢擔擔怴暦幮丄摨
|
丂彫愢乽恖惗寑応乿傪彂偄偨旜嶈巑榊偼係夞丄拞崙偵峴偒傑偟偨丅係夞栚偼楌巎彫愢乽惉媑巚娋乿傪彂偔偨傔偺庢嵽偱偹丄徍榓侾係擭俋寧壓弡丄枮廎偺怴嫗傑偱峴偒乽摨抧偵嶰擔傎偳懾嵼偟丄嬨寧嶰廫擔偵杒嫗偵擖偭偨丅偦偟偰梻廫寧堦擔偝偭偦偔栔屆崙嫬偺曪摢傊峴偒丄杒嫗偵岦偐偭偰岤榓丄戝摨丄挘壠岥傪弴斣偵傑傢傝丄堦廡娫屻偵栠偭偰偒偨丅(29)乿偦偆偱偡偑丄偦偺杒嫗擖傝偺弶擔偵僕儞僊僗僇儞傪怘傋偨偙偲傪彂偄偰偄傑偡丅
丂捠楬榚偺彫晹壆偱懸偨偣丄傑偨偦偺晹壆偵栠偭偨偙偲偐傜傒偰惓梲極偩傠偆偲巚偆偺偱偡偑偹丄揦柤偑傢偐傜側偄偺偱惓梲極偺巚偄弌偵偼擖傟側偄偱丄崱夞偺帒椏偦偺侾俆乮侾乯偵偟傑偟偨丅旜嶈傪桿偭偨敧栘徖偼丄枮揝偑媏抮姲側偳暥弔堦峴傪彽懸偟偨偲偒柺搢傪傒偨尦枮揝憤柋晹弾柋壽堳偱偡丅
丂攐恖斞揷幹鈹傕杒嫗偱怘傋偨偙偲傪彂偄偰偄傑偡偑丄旜嶈偲摨偠偔揦偺柤慜偑傢偐傝傑偣傫偺偱丄偙偙偺乮俀乯偵偟傑偟偨丅偙偺乽惉媑巚娋椏棟乿偼嬪帍乽塤曣乿偺徍榓侾俆擭俉寧偐傜侾俈擭係寧傑楢嵹偟偨乽戝棨婱椃嶨婰乿偺侾曇側偺偱丄偄偢傟挷傋偰弌揟偼乽塤曣乿偺惓妋側宖嵹擭寧偵庤捈偟偟傑偡丅從偒柺傪乽栘嬚偺傗偆偵媟崅偺扞乿偲昤幨偟偰丄娵偄偲偼堦尵傕彂偄偰偄側偄偺偱丄偙偺揦偺從偒柺偼曽宍偺傕偺偩偭偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
丂傑偨揧偊傜傟偨嬪偐傜擔嵎偟偺柧傞偄弔偵怘傋偨偙偲偐傢偐傝傑偡偹丅偙傟偼媽惓寧偱僇僆儎儞儘乕偼廔傢傝偲偄偆杒嫗屆棃偺揱摑偑丄婫愡偼偍峔偄側偟偵怘傋偵棃傞擔杮恖偵傛偭偰曵偝傟偰偟傑偄丄擭拞怘傋傜傟傞傛偆偵曄傢偭偰偄偨偨傔偱偟傚偆丅揦堳偨偪偼丄壧庤偺扤偐傒偨偄偵丄偍媞條偼恄條偱偡偲偄偭偰偄偨偐偳偆偐偹丅
帒椏偦偺侾俆
乮侾乯惉媑巚娋撶
丂巹偑枮廎偐傜杒嫗偵擖偭偨偺偼嬨寧嶰廫擔偱丄師偺擔偺屵屻偼憗偔傕曪摢偵岦偐偭偰弌敪偟偰偄偨偑丄偦偺斢乮嬨寧嶰廫擔乯惉媑巚娋撶偑揦傪傂傜偄偨偽偐傝偩偲偄偆偺偱丄巹偼媣偟傇傝偱夛偭偨敧栘徖忎晇丄峳栘復偺椉桭偵桿傢傟丄慜栧奜偺丄柤慜偼朰傟偨偑屆怓憮慠偨傞揦傊擖偭偰偄偭偨丅撦偄揹摃偺摂偐偘偺壓偱丄婔偮偐偵巇愗傜傟偨晹壆偺拞偼擔杮恖偺媞偑婄傪側傜傋偰偄傞丅揝奿巕偺撶偵偼梤偺偁傇傜偑徟偘偮偄偰偮傛偔旲傪杘偮偵偍偄偑堦庬堎條側栰惈傪嵈傝偨偰傞丅偳偺僥乕僽儖傕媞偱堦攖側偺偱丄巹偨偪偼擖岥偺捠楬偐傜偡偖塃偵偦傟偨偆偡埫偄晹壆偱偍拑傪堸傒側偑傜懸偭偰偄偨丅
丂庒偄愰晱姱傜偟偄抝偑擇丄嶰恖偱桖夣偦偆偵擖偭偰偒偨偑丄敧栘徖偺婄傪尒傞偲傃偭偔傝偟偨傛偆偵偍帿媀傪偟偨丅乮敧栘徖偼杒巟偺愰晱憤斍挿偱偁傞乯 亙棯亜
丂惾偑弌棃偨偲偄偆儃乕僀偺抦傜偣偱巹偨偪偼偡偖棫偭偰偄偭偨偑丄崅怆庰傪欖傝側偑傜嬺偆乮偲偄偆傛傝傕傓偝傏傞乯梤偺擏偼巹偺怘梶偵夣偄挷榓傪偁偨偊偨丅巹偼屲嶮傪戙偊廯傃偭偟傚傝偵側偭偰尦偺晹壆傊傕偳偭偰偔傞偲丄偝偭偒偺榁恖払偼傑偩摨偠惾偵偄偰摨偠懍搙偱庰傪堸傒丄敘傪摦偐偟偰偄傞丅乗乗乽偄偄側傽乿偲偙傫偳偼巹偑姶扱偟偨丅柡偺婄偵偐偡偐側丄桱怓傕偆偐傫偱偄側偄偙偲偑巹偺怱傪傎偭偲偝偣偨偺偱偁傞丅媁堾偲彥極偼偦偺業楬偐傜偁傑傝墦偔側偄偲偙傠偵堦奻傪惉偟偰偄傞偺偱偁傞丅
乮俀乯丂惉媑巚娋椏棟
亙棯亜丂撿杒孨偺搶摴偱杒嫗偺奨塹傪墴偟曕偄偰傤傞偆偪丄摨孨偑徴偲堦屗偺偊偨偄偺敾傜偸壠偺栧傊傆傒擖傝
乽偝偁乿
偲偐壗偲偐塢偮偨挷巕偱丄偖傫偖傫偲崈隳孨偲巹偲傪漟抳偟偨丅偦傟偑壗傪峸傆揦曑偱偁傞偺偐丄壗偺偨傔偵嫮峴偱埬撪偡傞偺偐奆栚敾偠偐偹傞壠壆偺峔憿偱偁偮偨偑丄楬抧偺傗偆側暻偲暻偲偺娫傪捠傝偸偗傞偲丄棤掚偺偁傫偽偄偱慺杙側椏棟壆偱偁傜偆偲偄傆尒摉偑傎傏偮偄偨丅孓搚偑彮偟偼偘偐偐偮偨暻偵傛偮偰梜桍偺恉偑戲嶳愊傑傟偰偁偮偨丅偦偺恉偼撪抧偺炆偺傗偆偵抁偔扥擮偵愗傝懙傊傜傟偰偁傝丄妿偮敿從偵憤偰偑徟偘偰傤偨丅掚偺拞墰偵丄妴搙嫻傊偲偳偔傎偳偺崅偝偵悩傦傜傟偨慹枛側鋓偑偁偮偨丅偦偺鋓偵偼媟偐傜媟傊偐偗偰堦枃偺斅偑搉偟偰偁傝丄懘傟傊揇孋傪偐偗偰鋓忋傪偺偧偒崬傓偵搒崌偺媂偄傗偆偵弌樢偰傤偨丅
乽惉媑巚娋椏棟偱偡乿
偲撿杒孨偑寉偔変乆偵殤偔屻傠偐傜丄拞壺恖偑椺偺嬻怓偺暈傪拝偰丄壗偐偺廱擏傪嶳惙傝偟偨婍傪偝偝偘帩偮偰樢偨丄撿杒孨偺愢柧偵傛偮偰偦傟偼梤偺擏偱偁傞偙偲偑敾偮偨丅暿偺婍偵傛偮偰枖廯偲嬟偺傗偆側惵乆偟偨漪嵷偑彮偟偽偐傝塣偽傟偰樢偨丅偦傟偲摨帪偵鋓忋偵悩傦偮偗傜傟偨揝偺壩敨偱偳傫偳傫暟壩偑擱偊偼偠傔偨丅壩敨偵偼栘嬚偺傗偆偵媟崅偺扞偑巇妡偗偰偁傝丄偦偺揝斅惢偺扞偼梜桍偺恉偑擱偊傞墛偱崥偪從偗啵傟偰偄偮偨丅撿杒孨偑婍偵偦傊偰偁傞挿偄敘傪偲偮偰擏傪偼偝傒忋偘偰偼壩扞偺忋傊偺偣偨丅擏偺從偗傞壒偑偫傝偫傝偲楏偟偔嬁偄偨丅偙偙偼惵揤堜偱偁傞偑堊傔偵擔偺岝傝偑偫偐偵変乆偲從擏傪徠傜偟偨丅懢屆偝側偑傜偺暟壩偺墛偼傔傜傔傜偲扞傪攪傂傑偼傝丄惉媑巚娋偺杍偘偨傪徠偟偨傗偆偵変乆偺柺忋偵擬傪憲偮偨丅偨偪傑偪曅柺偑從偗偰偔傞擏傪堦丄擇搙廯偵怹偟偰偼從偒側偑傜彫嶮偵偲偮偰歏傆偺偱偁傞丅
乽梤偺擏偼偙偺梜桍偺壩偱從偔偲寛偟偰廱偔偝偄擋偑偟側偄偺偩偝偆偱偡乿
丂撿杒孨偑擏傪杍挘傝側偑傜愢柧偟偨丅傢傟傢傟傕枓鋓媟偺孋妡偗斅傪曅懌偱摜傒丄擏傪偁偝傞偺偵揔摉側巔惃傪偨傕偪側偑傜惉媑巚娋偺遽傪恀帡傞傋偔恖屻偵棊偪偞傜傫偲偟偨偺偱偁傞丅
丂丂丂弔弸偔椃恖偯傟偺擏傪從偔
丂丂丂擏鄑傞忋屆偺墛弔偺拫
丂帒椏偦偺侾俇乮侾乯偼戝幠塹偑彂偄偨杮偱丄彂柤偑偡偽傝乽杒嫗偺捛壇乿偐傜偱偡丅墱晅偺挊幰棯楌偵傛傞偲尦杒嫗擔杮戝巊娰暃椞帠偱丄杮傪弌偟偨偲偒偼昉楬岺戝嫵庼偱偟偨丅偙傟偼乽巟撨椏棟乿偲偄偆復偐傜側偺偱偡偑丄戝幠偼烤姏巕傪巟撨椏棟偺悎偲朖傔乽屆棃杒嫗傪愯嫃偟偨柉懓偱昐擭懕偄偨傕偺偼側偔乿偆傑偄巟撨椏棟傕娷傔偨乽壏搾偺傛偆側娐嫬偵朣偝傟偰偟傑偮偨偺偱偁偮偨丅擔杮恖偼壥偟偰塱媣偵杒嫗偺庡偲側傝摼傞偱偁傠偆偐偲榑偤傜傟偨傕偺偱偁傞丅亙棯亜偲偙傠偑昐擭偼偍傠偐丄傑偩愩偺崻偺姡偐偸偆偪偵擔杮恖偼攕戅偟偨丅(30)乿偲寢傫偱偄傑偡丅尦奜岎姱側傜偱偼偺尒曽偩偲巚偄傑偡丅
丂偦偺乮俀乯偼戝嶃枅擔怴暦偺婰幰戲懞岾晇偑彂偄偨杮偐傜偱偡丅変乆偼拞崙偺梤偺嶻抧偲偄偆偲杒晹傪巚偆偺偱偡偑丄戲懞偵傛傞偲丄撿偺曽偱傕帞偭偰偍傝丄屛昅偲偄偆桪傟偨栄昅偺嵽椏偼撿偺曽偱嶾偺暢偱帞偭偨梤偺栄偵尷傞偲偄傢傟偰偄傞偦偆偱偡丅偨偩丄擏偺枴偼杒嫗傗揤捗偱怘傋傞梤擏傛傝偐側傝棊偪傞(31)偲彂偄偰偄傑偡丅偁偁丄偦傟偐傜恀傫拞偁偨傝偵恀偭崟偔尒偊傞帤偑偁傞偑丄偙傟偼幁偺帤傪俀偮暲傋丄偦偺忋偵傑偨幁傪抲偄偨帤偱僜偲撉傓丅峳偭傐偄偲偄偆堄枴偹丅
帒椏偦偺侾俇
乮侾乯丂巟撨椏棟
亙棯亜偲偙傠偱堦恖傗擇恖偱巟撨椏棟傪怘傋傞偵偼揔摉偵嶮悢傪彮偔偡傞懠偼側偄丅偦偆
偄偆梘崌偼丄傓偟傠偪傛偮偲曄偮偨偲偙傠傊峴偮偰捒偟偄椏棟傪怘傋偨曽偑傛偄丅偦偺戙昞揑側傕偺偲偟偰偼丄傑偢惉媑巚娋偵巜傪孅偟側偗傟偽側傞傑偄丅偙傟偼偦偺愄栔屆偺塸梇丄惉巚媑娋偑墦惇偵弌偨帪偺栰愴椏棟偲偄偆堗傢傟偺偁傞傕偺偱搶埨巗応偺拞偵偦偺椏棟壆偑偁傞丅拞崙偺懠抧曽偐傜偱傕傑偨擔杮偐傜偱傕丄杒嫗傊椃峴偵棃偨恖偼昁偢偙傟傪怘傋偰偙偄偲嫵偊傜傟偨傕偺偩丅偦傟傎偳桳柤偱偁傝丄妿偮捒偟偄偐傜墦棃偺媞偼偙偆偄偆強傊埬撪偡傟偽妱崌埨偔偰妿偮姶幱偝傟傞丅偙偙偺岝宨偼恟偩桬傑偟偄丅捈宎嶰広埲忋傕偁傞戝偒側揝偺壩敨偺拞偵娵懢偑擇嶰杮惙傫偵擱偊偰偄傞丅偦偺忋偵揝斅偑嵹偣傜傟偰偁傝丄擃偐偄梤偺擏偑廫嶮擇廫嶮偲塣偽傟偰丄媞偼傔偄傔偄帺暘偱梤擏傪揝斅偵偺偣偰從偗偨傜怘傋傞偺偱偁傞丅揔搙側枴傪偮偗偨廯偲僱僊側偳偲堦偟傛偵怘傋傞偺偱偁傞偑丄拠乆偵旤枴偟偔丄擇廫嶮傗嶰廫嶮偼崥偪暯傜偘傜傟傞丅偙偆偄偆壩敨偑幒撪偵廫屄埲忋傕偁傞偺偱墝偑憡摉棫偪崬傔偰偄傞丅偙偺墝偺郺乆偨傞拞偱丄曅懌傪壩敨偺慜偵偁傞戜偵嵹偣偐偗偰梤偺擏傪偮偮偄偰偄傞偲丄愄偺栔屆偺塸梇偺婥帩傕庒姳枴傢偊傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅亙棯亜
乮俀乯丂堦屲丄烤梤擏丒姏巕
丂偍偄乛乢栄旂偺奜搮偑拝偨偔側傞偙傠丄杒嫗偺戝奨彫岼丄偍傎傛偦梤擏娰偺偁傞偲偙傠丄偍偺乛乢栧慜偵堦惽偺楩鈣傪愝偗丄楩拞偵偼幠壩傪擱偟乗偙傟偵梡傆傞恉偼桍偺栘傪晛捠偲偡傞偑丄忋摍偺恉偲偟偰偼徏偺栘偵尷傞偝偆偱偁傞丅桍偺栘傕扨側傞恉偱偼晄壜丅扽傪嶌傞偲摨偠曽朄偱丄愒偄墜傪偁偘傞傪尷搙偺敿鄮偱側偗傟偽側傜偸偲偄傆乗偦偺忋偵堦惽偺揝饴巕傪偍偔丅堦斒屭媞摍偼丄暊偺拵傪偠偮偲梷傊偰丅偦偺楩傪傔偖傝偰丄敄曅偵愗傝側偝傟偨梤擏偺堦斦乆乆傪偲偮偰丄揝饴忋偵偍偒丄堦柺偵烤傝丄堦柺偵挷崌偝傟偨壛栻傪榓偟偰戝殣偡傞偺偱偁傞丅偙傟偑杒嫗柤暔偺偄偼備傞亀烤梤擏亁側傞傕偺偱丄僜償僀僄僩偺僗僞傾儕儞偑岲傫偱怘傆偲偄傆僇僂僇僒僗偺僔儎僔僄儕僣僋偲堦斒偩丅偨乁丄偟偐偟丄梤帀偑壩偵烤傜傟偰揝饴巕偺娫寗偐傜恉忋偵拲偑傟傞偲丄恉壩偼偙傟偵傛傝偰丄堦抜偺壩惃傪嫮傔丄擏帀堦帪偵徟偘偰丄鄮墝偲婏廘偲傪偦偙傜拞偵燐傜偡麤栰側庯偼丄惣偺儓僂儘僣僷偵揔偼偢丄傑偝偵搶偺層嵒悂偔敊抧偵尒傞傋偒傕偺偱偁傞丅傕偮偲傕丄摨偠梤擏娰偱傕丄戝娰巕偲徧偟偰偄僣傁偟椏棟揦偲偟偰峔偊傞壠丄偨偲傊偽慜栧奜擏巗偺惓梲極偺擛偒偼丄鈣傪堾撪偵愝偗偰梤擏偺屭媞傕夞嫵搆偲傕尷傜偢丄拞棳埲壓偺恖偽偐傝偱傕側偄丅烤梤擏偵梡傆傞壛栻偼丄擏偺憬廘傪徚偡偲偄傆崄嵷偺奜偵丄椏庰丄層灒丄墫丄忀桘丄忀摛晠側偳廫梋庬偵払偡傞偝偆偩偑丄偦傟偼戞堦棳梤擏椏棟揦偱偺偙偲偱偁傞丅亙棯亜
丂偒傚偆偺島媊偼愴慜偺搶棃弴偺巚偄弌偑拞怱側傫偱偡偑丄搶埨巗応偺搶棃弴偲惣扨攙極偺惣棃弴偑烤梤擏偺憃帏偲傒傞惣棃弴僼傽儞偺巚偄弌傕偁傞偺偱帒椏偦偺侾俈偲偟傑偟偨丅徍榓侾侽擭偵塅搒媨崅摍擾椦傪弌偰枮廎柷壴嫤夛丄壺枮揝杒巟帠柋嬊傗壺杒岎捠側偳偵柋傔(32)丄攕愴屻堷偒梘偘偰偒偨憪愳弐偺乽嶨崚暔岅乿偐傜偱偡丅偙傟偼徍榓俆俇擭偐傜乽擾椦悈嶻徣峀曬乿偵楢嵹偟偨乽嶨崚暔岅乿偵庤傪擖傟偰俆俋擭偵弌偟偨杮偱偡丅
丂椉幰偺摨偠売強傪斾傋傞偲丄楢嵹侾夞栚偺乽埦乿偼係俋俉帤偩偭偨偑丄杮偺曽偼晹壆側偳偺愢柧偲埦姛嶿旤偑徻偟偔側偭偰偍傝丄抁壧俀庱傕偁傞偺偱侾俋係俇帤偲係攞偵憹偊偰傑偡丅惣棃弴偺從偒柺偼儘僗僩儖宆偱側偔揝斅偩偭偨偺偱偡偹丅
帒椏偦偺侾俈
亙棯亜丂斢廐偐傜搤偵偐偗偨崰偵偼丄傛偔烤梤擏乮僇僆儎儞儘乕乯傪怘傋偵弌偐偗偨丅偄傢備傞僕儞僊僗僇儞乮惉媑巚娋乯撶偱偁傞丅杒嫗偱偼摉帪丄墹晎堜偺偦偽偵偁傞搶埨巗応偺拞偺搶棃弴偲惣扨攙極偵嬤偄惣棃弴偲偄偆揦偑丄僕儞僊僗僇儞椏棟偺憃帏偩偭偨丅烤梤擏偼挬梲栧奜偑敪徦抧傜偟偄偑丄偙偺曽柺傊偼堦搙傕弌偐偗偨偙偲偑側偄丅
丂巹偼搶棃弴傛傝傕惣棃弴偺傎偆偑岲偒偩偭偨丅搶埨巗応偼杒嫗偺嬧嵗捠傝墹晎堜偺偦偽偱丄偄偮傕偛偭偨曉偟偰偄偨丅偦偺拞偺搶棃弴偼丄偛偆偛偆偨傞斏惙傇傝偱偁傞丅擔杮恖偺媞偑懡偐偭偨丅
丂惣棃弴偼搶棃弴傎偳偺寲殑偝偼側偔丄擔杮恖偺巔傕彮側偐偭偨丅戝掞偺桳柤側椏棟壆偱偼丄庰偑傑傢傝暊偑傆偔傟偰偔傞偲丄戝惡傪弌偡擔杮恖偑懡偐偭偨丅偦傫側擔杮恖媞偺娫傪偍傠偍傠偟偰曕偔儃乕僀偑婥偺撆偩偭偨丅
丂惷偐側揷幧曢傜偟偵撻傟偰偄偨偺偱丄憶乆偟偄揦傛傝傕惷偐側揦偑岲偒偩偭偨丅偦傟偱擔杮恖媞偺彮側偄惣棃弴偑婥偵擖偭偨丅搶棃弴偵偔傜傋傞偲墂偐傜偼彮偟墦偄偑丄攏幵偱峴偗偽側傫偱傕側偐偭偨丅
丂僕儞僊僗僇儞椏棟偼墝偑棫偪偙傔傞偺偱丄業揤偱傗傞偺偑杮幃偩傠偆丅惣棃弴偱傕烤梤擏椏棟偺晹壆偼擇奒偵偁偭偰丄揤憢偑戝偒偔奐偄偰偍傝丄墝偑奜傊弌傞巇妡偗偵側偭偰偄偨丅揤憢偵惎傪偪傝偽傔偨斢廐偺栭嬻偑丄偄偭傁偄峀偑偭偰偄偨丅
丂捈宎堦儊乕僩儖敿傕偁傠偆偲偄偆娵偄揝斅偑丄楖姠愊傒偺楩偺忋偵丄偱傫偲忔偭偐偭偰偄傞丅楩偺廃傝偵丄暆屲悺丄挿偝嶰広偽偐傝偺岤斅傪懪偪偮偗偨崢妡偗條偺傕偺偑丄偄偔偮偐攝偟偰偁偭偨丅偙傟偼堉巕偱偼側偔偰丄懌傪偺偣傞戜側偺偱偁傞丅烤梤擏偼棫偮偨傑傑怘傋傞偺偱丄偙偺崢妡偗傒偨偄側戜偵曅懌傪偺偣丄挿偄抾敘傪庤偵彮偟偽偐傝慜偐偑傒偵側傞偲丄揝斅忋偺傎偳傛偔從偗偨梤擏偑丄偆傑偄嬶崌偄偵偼偝傔傞偺偱偁傞丅
丂懌傪偺偣傞戜偼丄揝斅偐傜堦掕偺嫍棧傪曐偪丄偼偹偨梤擏偺帀偑懱偵偐偐傜側偄偨傔偺岺晇側偺偩傠偆丅敀偄僄僾儘儞傪偐偗偰傕傜偭偰怘傋傞搶嫗晽偺僕儞僊僗僇儞側偳丄傑偙偲偵丄傇偞傑側妴岲偱偁傞丅杒嫗偺烤梤擏偵偼丄偝偡偑偵戝棨傜偟偄晽奿偑偁偭偨丅
丂僗儔僀僗偟偨梤擏傗娞傪偺偭偗偨敀偄嶮偑傒傞娫偵嬻偵側傝丄偁偲偐傜偁偲偐傜偲塣偽傟偰棃傞丅栻枴偺崄嵷傪偨偭傉傝偲擖傟偨僞儗偵擏傪怹偟丄擬偟偨揝斅偺忋偱從偄偰偼丄傂偭偒傝側偟偵岥偵塣傇丅擏傗娞偺從偗傞娫偵偼崅怆庰傪堸傓丅傑偙偲偵桬傑偟偄椏棟偩偭偨丅
丂拠娫偲偄偭偟傚偺帪偼丄怘傋偨嶮悢傪偒偦偭偰丄帺暘偨偪偺慜偵嬻偒嶮傪廳偹偰枮懌偟偨傕偺偱偁傞丅廫枃偖傜偄偺嶮偼丄傑偨偨偔娫偩偭偨丅
丂儃乕僀偺栶栚偺堦偮偵丄楩偺壩壛尭傪尒傞偙偲偑偁傞丅壩偑偍偲傠偊偨偙傠傪尒寁偭偰丄恉傪撍偭崬傓偺偱偁傞丅烤梤擏偵偼梜偺恉偑堦斣偩偲暦偄偨偙偲偑偁偭偨丅
丂枮暊偟丄崅怆庰偺悓偄傕揔搙偵夞偭偨偲偙傠傊塣偽傟偰棃傞偺偑傾儚姛偱偁傞丅彫傇傝側拑榪偵丄揔搙側壏搙偺墿怓偄傾儚姛偑惙傜傟偰偄傞丅
丂帀偺懡偄梤擏傪偨傜傆偔怘傜偄丄傾儖僐乕儖搙偺嫮偄崅怆庰傪堸傫偱朿傟偨堓偺銬偑丄傾儚姛傪偡偡傝崬傓偲丄側傫偲側偔丄偡偭偒傝偲棊偪拝偄偰棃傞偐傜柇偩偭偨丅傎傫偺傝偲娒枴偑偁傝丄偲傠傝偲偟偨愩偞傢傝偑偆傟偟偔丄壗攖傕偍戙傢傝偟偨傕偺偱偁傞丅
丂傾儚姛偑忾側偺偐怊側偺偐偼暦偒塳傜偟偨偑丄偳偆傕怊傾儚偺傛偆側婥偑偟偰側傜側偄丅擔杮偱傾儚偲尵偊偽丄傾僼栞傪怘傋偨宱尡偐偐傞偩偗偩偭偨偟丄拞崙偱偼怘傋偨偙偲偑堦搙傕側偐偭偨丅傾儚姛偑丄偙傫側巪偄傕偺偩偲偼丄巚偄傕偍傛偽側偐偭偨丅
丂傾儚姛傪偡偡偭偨偺偼丄偼偠傔偰烤梤擏傪怘傋偨偲偒偩偑丄偁偲偱烤梤擏偺屻偱偼丄偒傑偭偰弌傞傕偺偲抦偭偨丅壗帪偡偡偭偰傕丄嵟弶偺偲偒偲曄傢傜側偄枴偩偭偨丅烤梤擏偺屻偱傾儚姛傪偡偡傞偺偼丄拞崙椏棟偺抦宐側偺偩傠偆丅摉帪偼丄怘偄婥傗堸傒婥偽偐傝墵惙偱丄傾儚姛偺桼棃側偳暦偒弌偡備偲傝偡傜側偐偭偨丅
丂傾儚姛傪偡偡傝廔傢傞崰偵側傞偲丄晹壆偺拞偵郺乆偲棫偪偙傔偨墝傕徚偊丄堦暈偮偗偰揤憢傪尒忋偘傞偲丄棙姍偺傛偆偵嶀偊偨嶰擔寧偑丄偪傚偆偳揤憢偺恀傫拞偵丄傑傞偱妟墢偵偼傔傜傟偨傛偆偵偐偐偭偰偄傞偙偲偑偁偭偩丅偦傫側搤偺栭偼丄奜傊弌傞偲椻偊傞偵傑偪偑偄側偐偭偨丅
丂惣棃弴傪弌傞偲丄巚偭偨捠傝姦偄丅偟偐偟丄梤擏偵枮暊偟丄崅怆庰偱壩徠偭偨杍偵偼丄悂偒偡偓傞嶑晽傕傕偺偐傢偱偁傞丅暊偺傾儚姛偑丄傑傞偱搾僞儞億傪書偊偰偄傞姶偠偝偊偟偨丅
丂杒嫗偺傾儚姛傪偡偡偭偨偺偼巐廫擭嬤偄愄偺偙偲偱偁傞丅杒嫗傪偼側傟偰擇搙偲偡偡傞婡夛偵宐傑傟側偄丅偦傟側偺偵杒嫗偺傾儚姛偼丄嶐擔偺傛偆偵巚偄弌偝傟傞丅偁偺傎偺娒偄傾儚姛偑丄怊偩偭偨偺偐忾偩偭偨偺偐偲峫偊弌偡偲丄杒嫗傊偺嫿廌偑偐偒棫偰傜傟偰丄偡偖偝傑旘傫偱峴偒偨偄婥帩偪偱偁傞丅
丂丂烤梤擏偺偁偲偱偡偡傝偟埦偑備偺娒偝側偮偐偟杒嫗偺搤傛
丂丂偝偞傔偒偰烤梤擏偵峏偗偟惣棃弴偺揤憢傪傛偓傞搤偺寧嶀備
丂偙偺屻偼愴慜丄杒嫗偱怘傋偨巚偄弌偲傢偐傞傟偳傕丄偄偮偛傠丄側傫偲偄偆揦偱怘傋偨偐偼偭偒傝偟側偄婰榐偱偡丅帒椏偦偺侾俉乮侾乯偼撨恵揹婡揝岺偺幮挿丄撨恵恗嬨榊偝傫偑彂偄偨傕偺偱丄偄傠偄傠旤枴偟偄傕偺傪怘傋偨拞偱傕丄僕儞僊僗僇儞偑朰傟偑偨偄偲偄偆偺偱偡偐傜丄偆傟偟偄偱偡偹丅奆偝傫傕丄巹傒偨偄側擭偵側偭偨傜丄杒戝偱偺僕儞僷偑朰傟偑偨偄偲彂偔偙偲偑偁傞偱偟傚偆丅
丂乮俀乯偺昅幰丄巐僣嫶嬧懢榊偼乽枮慛傪椃偡傞乿偲偄偆杮傪彂偄偰偄傞偺偱丄偦傟偵傕僕儞僊僗僇儞傪彂偄偰偄傞偐抦傟傑偣傫偑丄庢傝姼偊偢晉嶳偺嫿搚尋媶嶨帍乽崅巙恖乿偐傜偱偡丅
帒椏偦偺侾俉
乮侾乯傂偮偠
亙棯亜丂摝偘傞偵懌傞媟傕側偗傟偽,偐偔傟傞抭宐傕帩偨偨偄掱廬弴偱庛偔丆慡偔摨忣偺傢偔偙偺彫摦暔傪恖椶偺棙梡偩偗偱峫偊傞偺偼堦悺巆崜偺傛偆側婥傕偡傞偑丆愭偢怘傋暔偱偼惉媑巚娋椏棟偱偁傠偆偐丅
丂梤擏傪敄偔戝偒偔愗傝,栻枴偺捫偗廯偵偮偗丆寉偔從偒側偑傜怘傋傞丅搤偵傛偔壞偵傕傛偔丆巐婫傪捠偠偰嵟嬤偱偼嵽椏傕梤偵尷傜偢丆懠偺擏椶傗栰嵷傪庢傝擖傟偨堦斒壠掚椏棟偲側偭偰偄傞丅
丂愄僕儞僊僗僇儞偑愥尨偺愴偵栰奜偱恀愒側暟壩傪偐偙傒丆孯惃偵姇傪撶偲偟偰挿偄敘偱梤擏傪鄤傝從偒偵偟偰怘傋偝偣偨偲偄傢傟傞偑丆惉媑巚娋椏棟偼傑偞傑偞偲偦偺岝宨傪渇渋偝偣偰偔傟傞丅
丂偍椬傝偺拞崙偱偼丆梤偼屆偔偐傜恄惞側傕偺偲偝傟偰偄傞偑丆巹傕愴慜愴屻偲丆偐偺抧傪朘傟偨愜偵丆拞崙捠偺抦恖偵楢傟夞偝傟偰悢愮擭棃偺旤枴扵媶偺楌巎偺強嶻偱偁傞偄傠偄傠偺怘傋暔偵傔偖傝偁偭偨偑丆側偐偱傕愴慜杒嫗峹奜偺戝偒側揦偱丆戝惃偱埻傒側偑傜挿偄敘偱偮傑傫偩杮応抧尦偺枴偲傕偄偆傋偒惉媑巚娋椏棟傪丆嫽枴怺偔枴傢偭偨偙偲偼傑偙偲偵朰傟偑偨偄丅亙棯亜
摨乮俀乯曻榖夛僕儞僊僗僇儞撶
亙棯亜丂偗偆偼乽僕儞僊僗僇儞椏棟乿偲偄偆偙偲丅
丂抶崗偟偨偺偱丅彫憱傝偵岇崙恄幮妏傑偱偒偨傜丄傾僲梤擏撈摿偺廘偄偑棳傟偨偩傛偮偰偄偨丅偊傜偄偲偙傠傑偱廘偄偑偡傞傕偺偩丄偲偍偳傠偄偨丅偲偨傫偵丄暊偺拵偑僌僣偲偆側偮偨丅
丂杒嫗偺堸怘揦奨偵棳傟偨偩傛偆丄傾僲廘偄傪側偮偐偟偔巚偄弌偟偨丅偗偆偙偺偛傠傕丄偒偮偲丄偨偦偑傟偺拞嬻偵巼偺偗傓傝偑瀶乆偲棫偪偺傏偮偰偄傞偺偵堘偄側偄丅
丂揦偺柤偼丄傢偡傟偨偑丄杒嫗偺慜栧奨偵僕儞僊僗僇儞撶偱桳柤側斞揦偑偁偮偨丅偙偺揦偼偄偪偽傫憗偔巼墝傪偁偘傞偺偱桳柤偩偮偨偑丄傢傟傢傟弶暔怘偄楢偼丄偝偒傪偁傜偦偮偰廫寧枛偺慜栧奨偵偍偟偐偗偨傕偺偱偁傞丅
丂僕儞僊僗僇儞撶偲偄偆偑丄撶傕偺偼悈偩偒梤擏偱丄傎傫偲偆偺僕儞僊僗僇儞偼丄壆奜偵戝偒側僇儅僪傪暁偣偰丄恉傪傕傗偟丄偦偺忋偵揝偺栐傪偺偣偰丄敄偔偒偮偨梤擏傪僒僣偲從偄偰偨傋傞偺偱偁傞丅懌戜偵曅懌傪偺偣丄側偑偄敘偱梤擏傪從偒側偑傜幍枴偺忀桘偱棫偪偼偩偐偮偰偺栰怘偼丄傑偙偲偵婥塅憇戝側傕偺偑偁傞丅傑偮偨偔偺栰愴椏棟偲偄偆偲偙傠偱偁傞丅亙棯亜
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮俀俋乯偺弌揟偼垽抦廼摽戝妛曇乽垽抦廼摽戝妛榑廤丂暥妛晹丒暥妛尋媶壢曆乿俀俉崋俁係儁乕僕丄搒抸媣媊乽旜嶈巑榊偲拞崙乿傛傝丄暯惉侾俆擭俁寧丄垽抦廼摽戝妛亖http://aska-r.aasa.ac.jp/
dspace/bitstream/10638/
1254/1/0021-028-200303-(027)-(037).pdf丄
帒椏偦偺侾俆乮侾乯偼旜嶈巑榊挊乽旜嶈巑榊慡廤乿侾侾姫侽俁儁乕僕丄乽娭働尨乿傛傝丄徍榓係侾擭侾侽寧丄島択幮亖娰撪尷掕嬤僨僕杮丄掙杮偼乽娭働尨乿丄徍榓侾俆擭侾俀寧丄崅嶳彂堾丄
摨乮俀乯偼斞揷幹鈹挊乽揷墍偺柖乿俁侾俈儁乕僕丄徍榓侾俉擭侾俀寧丄暥懱幮亖娰撪尷掕嬤僨僕杮丄
乮俁侽乯偲帒椏偦偺侾俇乮侾乯偼戝幠塹挊乽杒嫗偺捛壇乿俁俉儁乕僕丄徍榓俀俉擭俆寧丄弜壨戜彂朳亖尨杮丄
摨乮俀乯偲乮俁侾乯偼戲懞岾晇挊乽巟撨憪栘拵嫑婰乿俆俁儁乕僕丄徍榓侾係擭俉寧丄搶垷尋媶夛亖娰撪尷掕嬤僨僕杮丄
乮俁俀乯偼憪愳弐挊乽嶨崚暔岅乿墱晅丄徍榓俆俋擭俇寧丄擔杮宱嵪昡榑幮亖尨杮丄
帒椏偦偺侾俈偼摨係儁乕僕丄摨丄
帒椏偦偺侾俉乮侾乯偼宱嵪抍懱楢崌夛曇乽宱抍楢寧曬乿俀俈姫侾崋俇係儁乕僕丄撨恵恗嬨榊乽傂偮偠乿丄徍榓俆係擭侾寧丄宱嵪抍懱楢崌夛亖尨杮丄摨乮俀乯偼墺媣堯曇乽崅巙恖乿俀俁姫侾崋俁俉儁乕僕丄巐僣嫶嬧懢榊乽曻榖夛僕儞僊僗僇儞撶乿丄徍榓俁俁擭侾寧丄崅巙恖幮亖娰撪尷掕嬤僨僕杮
|
丂愴慜丄杒嫗偲偄偆傛傝拞崙偺偳偙偐偲傒傞傋偒巚偄弌傕偁傝傑偡丅傕偆朣偔側偭偨偗傟偳崟揷弶巕偲偄偆彈惈傪抦偭偰傑偡偐丅搊嶳傗僗僉乕丄椏棟偺杮傕偨偔偝傫彂偄偨崟揷偑徍榓侾係擭乽壠抺乿偲偄偆愱栧帍偺俋寧崋偵乽朓枿傪巊梡偟偰嶌傞偍壻巕偲朓枿傪偐偗偰怘偡傞偍壻巕乿偲戣偡傞椏棟婰帠傪彂偄偰傑偡丅崟揷偑偙偺嶨帍偵彂偄偨偺偼弶傔偰偩偭偨偙偲傕偁傝丄偦偺儁乕僕偵崟揷偺悘昅乽偮傒偔偝乿敪姧傪徯夘偟偰乽彈棳搊嶳壠偲偟偰抦柤側挊幰偑(33)乿偲偁傞偺偱丄摉帪偼嶳偺曽偑抦傜傟偰偄偨傛偆偱偡偑丄偦偺師偺崋偵乽旤枴偟偄梤擏偺怘偟曽乿偲偄偆婰帠傪彂偄偨偺偱偡丅
丂崟揷偼乽杒嫗偐傜栔屆傊偺椃峴拞偵丄嵟傕巹偺枴妎傪枮懌偝偣偰偔傟偨梤擏椏棟乿偲偟偰乽梤偺悈偨偒乮僔儓儚儞儎儞儘乕乯乿偲乽僕儞僊僗僇儞從乿傪徯夘偟偰偄傑偡丅偲偙傠偑崟揷偼悈偨偒偺曽偑婥偵擖偭偨傛偆偱丄係俆峴傕旓傗偟偰徻偟偔嶌傝曽傕愢柧偟偰偄傞偺偵丄僕儞僊僗僇儞偼晅偗偨傝傒偨偄偵偨偭偨侾侽峴丅(34)偦偺抁偄婰弎偑帒椏偦偺侾俋乮侾乯偱偡丅
丂乽枴偲帺慠偺嶶曕摴乿偵乽徍榓廫擇擭偐傜廫嶰擭偵偐偗偰偺搤偵偼嶰偐寧偽偐傝杒巟栔嫯抧曽傊弌妡偗偨丅柤屆壆戝妛偺恵夑懢榊棟攷偲崟揷偲彆庤奿偱巹偑壛傢偭偨丅(35)乿偲偁傝傑偡偐傜丄偙傟偼偦偺偲偒偺懱尡偱偟傚偆丅
丂帒椏偦偺侾俋乮俀乯傕丄偦偺偲偒妎偊偨怘傋曽偲巚傢傟傑偡丅崟揷偼僕儞僊僗僇儞偺嶌傝曽傪偄傠偄傠側杮偵彂偄偰偄傑偡偑丄擪偺潌傒崬傒傪彂偄偨傕偺偼丄偙傟埲奜偵側偄傛偆側偺偱丄壛偊偰偍偒傑偟偨丅偙偺旈朄偼丄揝栐忋偵偁傞旝恛愗傝偱側偄擪傪敘偱庢傝忋偘偰丄擪偺偸傔傝傪怘傋傞偮傕傝偺擏曅偺昞懁偵側偡傝偮偗傞峴堊偲巹偼棟夝偟偲傞偑丄崟揷椏棟嫵幒偱偼偳偆惗搆偵嫵偊偰偄偨偺偐抦傝偨偄偲偙傠偱偡丅
丂傕偆侾恖丄彈惈偺巚偄弌偑偁傞偺偱丄偙偙偺乮俁乯偵偟傑偟偨丅偙傟偼丄愴屻偼東栿壠偵側偭偨尦怴暦婰幰丄朷寧昐崌巕偑丄嫗寑偺攐桪偺壠偵彽偐傟偰怘傋偨巚偄弌偹丅朷寧偼徍榓侾俁擭偵枮廎傊揮嫃偟偰偄傞偺偱丄偦傟埲慜偲偄偆偙偲偱偡偹丅朷寧偺偙偺巚偄弌偺屻敿偼枮廎偺尒暦側偺偱丄傕偆堦搙丄枮廎帠忣偺島媊偱巊偆偮傕傝偱偡丅
帒椏偦偺侾俋
乮侾乯丂僕儞僊僗僇儞從偒
亙棯亜丂擵偼栴挘傝嬌偔敄偔愗偮偨梤擏傪丄擝偲傑偤偰丄偨傟
乮忀桘偲庰傪敿乆偵崿偤偨傕偺乯偵捫偗偰偍偒丄栘扽壩
偺忋偵偐偗偨鑓偁傒偺忋偵敘偱偙偡傝偮偗偰丄億儘億儘
偵從偄偰怘偡傞偺偱偡丅擔杮偱傗偮偰傤傞傗偆偵岤偔愗
偮偰敘偱椉柺傪曉偟側偑傜從偔偺偱偼偁傝傑偣傫丅偙偺
椏棟偲堦弿偵從栞偲偄傆僷儞偺傗偆側傕偺傪堦弿偵怘傋
傞偲旤枴偱偡丅慠偟敀暷偺屼斞傕丄傛偔枴偑偁傆傗偆偵
巚傂傑偡丅扐偟擵偼旕忢偵墝偑弌傞偺偱丄暵傔偒偮偨晹
壆偱偼弌樢傑偣傫丅偍掚偱栰愴椏棟婥暘偱彚忋傞偺偑偄
偄偲懚偠傑偡丅
乮俀乯丂僕儞僊僗僇儞從偒偺旈朄偼偹偓偺傕傒崬傒
丂僕儞僊僗僇儞從偒偼杒嫗偱傕偨傃偨傃偄偨偩偒傑偟偨偑丄偹偓傗僯儞僯僋傗挷枴椏傪擏偲傑偤偰偍偒丄偙傟傪揝栐偱從偔帪偼丄挿偄偍僴僔偱擏偵擪傪傕傒崬傓偺偑旈朄偱丄擔杮偺僕儞僊僗僇儞偲堎側傞揰偩偲巚偄傑偟偨丅偁偁偟偨曽偑擏偑偍偄偟偔側傞偼偢偱丄巹偳傕偱偼埲屻偢偭偲偦偆傗偭偰偄傑偡丅
乮俁乯惵憪偵憐偆
丂丂丂丂丂僕儞僊僗僇儞撶
亙棯亜丂巹偼埌峚嫶帠審偑婲偮偨徍榓廫擇擭偺惓寧
傪杒嫗偱寎偊偨偑丄偁傞擔斢巂偵烤梤擏傪彽
偽傟傞偙偲偵側偮偨丅攡棖朏偲暲傃徧偝傟偰
偄傞柤桪掱尌廐偑巹偺偨傔偵摿偵姦栭偺捒枴
傪梡堄偟偰偔傟偨偺偩偮偨丅
丂儀儔儞僟偵崅偄楩傪棫偰徏恉偑旤偟偄墜傪
忋偘側偑傜僶僠僷僠偲擱偊偰偄傞丅寧偺側偄
惎偺崀傞傛偆側幗崟偺嬻偵偦傟傪壗偐柌尪揑
側旤偟偝偵徠傝塮偊偨丅
丂墜偺忋偵擇僙儞僠暆埵偺揝偺丄拞崅偄惙傝
忋偮偨栐傪偺偣偰丄偙偺栐偑愒偔擬偟偨偲偒
傔偄傔偄梡堄偝傟偨梤擏傪挿偄敘偱偮傑傫偱
偺偣傞丅僕儏乕偲偙偘傞偲棤曉偟偰丄傕偆堦
搙僕儏乕偲偙偑偟偰丄恷忀桘偵僯儔偺惵枴傪
晜偐偟偨僞儗偵僔儏儞偲偮偗偰怘傋傞丅傗傢
傜偐偱寉偔偰偄偔傜怘傋偰傕怘傋偁偒傞偙偲
偑側偄丅崌娫偵榁庰傪傆偔傓偲偝傜偵擏偺枴
偑傛偔側傞丅
丂偦傟偼楇壓壗搙偲偄偆丄懪偰偽僇儞偲嬁偒
偦偆側栭婥偺拞偩偮偨偑姦偝抦傜偢丄偟偐傕
戩巕偱弌偝傟傞偐偟偙傑偮偨椏棟偲偪偑偮偰
弶懳柺偺桭払偲傕偡偖恊偟傔傞暤埻婥側偺偱
堦憌怘梶傪偦偦傜傟傞傕偺偑偁偮偨丅
丂搤偼壠偵偲偠偙傕傝偑偪側杒嫗偺惗妶偱偙
傟偼栰奜傊偺嫿廌偱傕偁傝丄傑偨暥壔揑偵枩
帠昳傛偔偙偲偛偲偵儃乕僀傗彈拞偺庤傪偐傝
傞僽儕僕儑傾惗妶偺栰惈傊偺摬溮偺尰傢傟偱
傕偁傠偆丅
丂偄偮傕偼悵偺怘帠偲塢傢傟傞傎偳彫怘側巹
偑偦偺栭堦嬕埲忋傕梤擏傪怘傋偰偍暊傕偙傢
偝側偐偮偨偙偲傪巚偄崌偣偰傕偦傟偑偄偐偵
偍偄偟偔妝偟偔傑偨堓偵寉偄椏棟偱偁偮偨偐
偑暘傠偆丅亙棯亜
丂愴慜丄杒嫗傪朘傟偨懡偔偺擔杮恖偑柤偺偁傞椏棟揦偱怘傋偨偺偼偄偄偺偱偡偑丄朏偟偔側偄塭嬁傕傕偨傜偟偨丅偦傟傪帒椏偦偺俀侽偵擖傟傑偟偨丅偙偺杮偼徍榓侾係擭偵搶妛幮偐傜弌偟偨曽偱偡偑丄梻侾俆擭偵摨偠彂柤偱惉岝娰彂揦偐傜傕弌偟偨偍傝丄崙夛恾彂娰僒乕僠偱偼嵞斉偲側偭偰偄傞偺偱拞恎偼摨偠側偺偱偟傚偆丅
丂昅幰偺搶暥梇偑偳偆偄偆宱楌偺恖暔偐傢偐傜側偄偺偱偡偑丄偙偺杮偼侾僇寧偖傜偄偐偗偰挬慛丄枮廎丄巟撨傪尒偰夞傠偆偲偄偆屄恖岦偗偵彂偄偨(36)偲乽傑傊偑偒乿偵偁傝傑偡丅奜崙岅偑偱偒側偄偲偄偆惂栺偵壛偊偰丄杮応偺枴傊偺堌宧偲偄偄傑偡偐丄妛廗梸廫暘偲偄偆偐丄奜崙偱椏棟揦偵擖偭偨擔杮恖媞丄偙偲偵彮恖悢偺嵺偺偍偲側偟偝偼丄偄傑傕曄傢偭偰側偄傫偠傖側偄偡偐偹偊丅
帒椏偦偺俀侽
亙棯亜丂杒嫗偼偳偆偟偰傕堦廡娫偼懾嵼偟側偄偲丄堦捠傝偩偗偱傕尒暔偡傞偙偲偼偱偒側偄丅擇擔傗嶰擔埵懾嵼偟偰杒嫗傪尒偰樢偨傗偆側偙偲傪尵傂傆傜偡偺偼岤偐傑偟夁偓傞偲偄傆傕偺偱偁傞丅杒嫗傪抦傞偲偄傆偙偲偼丄扨偵堦擔傗擇擔偱柤強媽愔傪尒偰夢傞偙偲偱偼側偄丅巟撨偺椏棟傪偨傜傆偔怘傋丄巟撨庰傪僡僣僋儕偲枴傂丄杒嫗偺搚拝恖偵棁偱岎嵺偟偰丄杒嫗偺奨乆偵廩偪堨傟偰傤傞堎殸忣弿傪怱偐傜懱尡偡傞丄偙傟偱側偗傟偽堄枴偑側偄偟丄杒嫗偵樢偨峛斻偑側偄丅
丂偙偺巟撨偺椏棟偺榖偑偱偨偐傜彉偱偵彂偔偑丄巟撨偵樢傞偲丄偲偵偐偔偙偺巟撨椏棟偩偗偼嬺傂偨偔側傞丅摿偵杒嫗偵偍偄偰偦傟偼慠傝偱偁傞丅巟撨椏棟偵偼怓乆偁偮偰愮嵎漭暿偩偑丄嵟嬤偼偲偐偔椏棟偑傑偯偔側偮偨偲偄傆榖偱偁傞丅偦傟偼側偤偐偲偄傆偲丄擔杮恖偼椏棟壆傊峴偔偲暿偵椏棟偑旤枴偔側偔偲傕壗偲傕偄偼側偄丅偦傟偵嬥偼僉僠儞偲暐偮偰峴偒丄偟偐傕偦偺忋偵栚災傪愗偮偰僠僣僾傑偱抏傫偱峴偔丅偩偐傜巟撨恖偼擔杮恖偲偄傆傕偺偼椏棟偑彮偟埵偼傑偯偔偲傕栙偭偰嬥傪暐偮偰偔傟傞殸柉偩偲偄傆峫偑抜乆忢幆壔偝傟偰偟傑偮偰丄偁偺杒嫗嗾摿偺枴偺偁傞屆樢偺巟撨椏棟偲偄傆傕偺偑師戞偵掅壓偟偰樢偨偺偩偲偄傆丅偩偐傜嵟嬤偺杒嫗椏棟偼斾妑揑偵崅偔側偮偨丅嵟嬤偼杒嫗偵傕擔杮恖宱塩偺椏棟壆側偳偑懡偔側偮偰樢偨偑丄巟撨恖偼偝偮傁傝嬤偯偐側偄丅巟撨恖偵尵偼偣傞偲乽戝懱怘傊傞傕偺偑側偔偰崅偄乛乢乿偲偄傆偺偩偝偆偩丅擔杮恖偺怱棟傪傛偔暔岅偮偨傕偺偱丄怘傋暔壆偵钀偡傞尷傝偼偳偆傕擔杮恖偼巟撨恖偺憡庤偵側傜側偄傗偆偱偁傞丅偙傫側榖偼暦偒婞偰乀偟傑傊偽暿偵壗偱傕側偄傗偆偱偁傞偑丄偝偆偱偼側偄丅戝棨偺奐敪偼傢偑擔杮恖偺執戝側傞巊柦偱偁傟偽丄偦傟偑擔忢偺惗妶偵钀學偁傞怘傋暔偵偼捈愙偺塭嬁偑偁傞傢偗偩偐傜丄崱屻偼怘傋暔偺嵞曇惉塣摦偵傑偱榖偑恑傑側偄偲杮醕偱偼側偄丅
丂偟偐偟杒嫗偱枴傆僡儞僊僗僇儞偺枴偼朰傟擄偄丅杒嫗偺抧偺怘捠偵偄偼偣傞偲丄僡儞僊僗僇儞椏棟偼敧寧偺枛崰偐傜嬨寧崰偵偐偗偰娋偩偔乛乢偱嬺傆偺偑巪偄偺偩偝偆偩偑丄傑偨姦偄搤偺擔偵擇丄嶰偺恊偟偄桭払偲偱傕楢傟揧偮偰慜栧奜偺惓梲極偁偨傝偱峠偺墜偺忋傞撶偺忋偱岮傪徟偡傗偆側從庰傪彟傔偨偑傜広偵偁傑傞挿偄敘偱從偄偰嬺傆僡儞僊僗僇儞偺枴傕杒嫗偺傒偑桳偮嗾摿側旤枴椏棟偺堦偮偱偁傞丅僡儞僊僗僇儞椏棟偲偟偰柤偺偁傞傕偺偼丄偙乀偵宖偘偨惓梲極埲奜偵偼搶樢弴丄堦悿墍丄摨榓尙丄椉塿尙側偳偑堦棳偳偙傠偱偁傞丅巹偑嬺傊偨偺偼惓梲極偱偁偮偨丅亙棯亜
丂塒堜晲晇偼乽杒嫗捛憐乿偵乽僕儞僊僗僇儞椏棟偲屇偽傟傞椏棟偼懡偔偺擔杮恖偵抦傟傢偨偭偰偄偰丄偙傟傪怘傋偝偣傞揦傕曽乆偵偁傞丅傒側拞崙偺摿偵杒嫗偺偦傟偲摨偠傕偺偩偲徧偟偰偄傞傜偟偄偑丄擔杮恖偑彑庤偵柦柤偟偰僕儞僊僗僇儞椏棟偲屇傫偱偄傞杒嫗偺乹烤梤擏乺偲偼帡偰傕旕側傞傕偺偱偁傞丅(37)乿偲彂偒丄偦偺憡堘傪係偮嫇偘偰偄傑偡丅惓梲極偵埬撪偡傞憐掕偱彂偄偨屻偵晅偗偰偁傞傕偺偱丄帒椏偦偺俀侾乮侾乯偑偦傟偱偡丅
丂摨乮俀乯偼寑嶌壠偺娸揷崙巑偑徍榓侾俀擭侾侽寧偐傜敿寧傎偳丄暥寍弔廐偺摿攈婰幰偲偟偰摉帪杒巟愴慄偲屇偽傟偨拞崙杒晹偺愴摤抧堟傪帇嶡偟丄偝傜偵杒嫗丄揤捗側偳傪椃偟偨婰榐乽杒巟暔忣乿偐傜偱偡丅娸揷偼棨孯巑姱妛峑弌恎側偺偱丄愴慄帇嶡拞偵壗恖偐摨憢惗偵弌夛偭偨偙偲傕偙偺杮偵彂偄偰偄傑偡丅
丂摨乮俁乯偼怘暔巎傗柉懎偺尋媶側偳偱抦傜傟傞幝揷摑偺悘昅乽杒嫗偺廐偼梤擏偐傜乿偺慜敿丅宖嵹偟偨嶨帍偺乽怘摴妝乿偼丄徏嶈揤柉偑曇廤偟偨摨偠柤慜偺乽怘摴妝乿偲偼堘偄丄峀崘偐傜柤屆壆偱敪峴偝傟偨偲傒傜傟傞傕偺偱丄崙棫柉懓妛攷暔娰偺幝揷娭學偺帒椏偵偁傝傑偡丅幝揷偼嫗戝偱摦暔妛愱峌偟丄棨孯偺媄巘偵側偭偰拞崙偵峴偭偰偄傑偡丅
丂摨乮係乯偼杒嫗戝偵妛傃枮揝挷嵏晹丄摨峅曬幒側偳偵嬑柋偟丄愴屻偼戙乆栘僋僢僉儞僌僗僋乕儖忢柋棟帠側偳傪柋傔偨戝搰摽栱偺乽昐枴銍棎丂乗拞崙丒枴偺嵨帪婰乿偐傜偱偡丅戝搰傕乽柧帯偐傜戝惓偵偐偗偰杒嫗偵廧傒丄椃峴偟偨擔杮偺恖偨偪偵僕儞僊僗僇儞椏棟偲柤偯偗傜傟偨丅杒嫗偱僕儞僊僗僇儞椏棟偲偄偭偰傕偗偘傫側婄傪偝傟傞偽偐傝偱偁傞丅乿偲彂偄偰偄傑偡丅偆傑偄偆傑偄偲侾恖偱壗嶮傕擏傪怘傋傞偺偱偡偐傜丄慖傝偵慖偭偨擏偼偡偖恠偒傞偱偟傚偆丅椺偊偽嵟弶偼戁丄師偼尐丄偦偺師偼庱偲偄偆傛偆偵摨偠傛偆偵尒偊傞擏偱傕丄柤揦偵偼弌偡擏偺弴彉偵旈揱偑偁傞偺偱偼側偄偐偲巹偼峫偊傑偡丅仭偼拵曆偵壓偲彂偔帤偱儐僯僐乕僪偵傕側偄帤偱偡丅僯儑僋儅儉偲偐僫儞僾儔乕偲摨偠傛偆側壼傪巊偭偨嫑忀偱偡丅
帒椏偦偺俀侾
乮侾乯
丂偙偙偱丄擔杮偺僕儞僊僗僇儞椏棟偲偺憡堎傪弎傋偨偄偲巚偆丅
丂戞堦偵丄梤擏偼丄岤偄愗恎傗丄夠傝偱偼側偄丅擔杮偺傆偖偺巋恎偺條偵丄偛偔敄偔愗傜傟側偗傟偽側傜偸丅惓梲極傗搶棃弴偵偼丄敄恘偺曪挌偱丄巻偺擛偔敄偔愗傞払恖偑柤恖寍傪尒偣偰偄傞丅擔杮偵偼偙偺條側柤恖偼堦恖傕偄側偄丅晛捠偺擏曅偲偼岤偝偑堘偆偺偱偁傞丅傑偟偰丄僠儑僢僾偺條側傕偺偼栤戣偵側傜側偄丅
丂戞擇偵丄儅儕僱乮暓岅丄梤擏摍偺廘偄傪徚偡堊偵丄桘偵嬍擪傗昮摍偺旝恛愗傝傪崿偤偨傕偺偺拞偵擏曅傪捫偗偰抲偔椏棟朄乯偺曽朄偑摿庩偱偁傞丅偙傟偵偼乹崄嵷乺偲偄偆拞崙摿嶻偺栰嵷傪巊偆丅偙傟偼擔杮側傜丄乽傒偮偽乿偺條側摿庩側崄婥傪帩偮傕偺偱丄偦偺旝恛愗傝偼梤擏撈摿偺廘婥傪徚偡偲嫟偵丄傛偒崄傝偲枴偲傪壛偊傞傕偺偱偁傞丅崄嵷偼丄偙偺崰偱偼丄墶昹偺撿嫗奨摍偱擖庤弌棃傞條偵側偭偨偑丄擔杮恖偵偼岲埆偑偁偭偰晛媦偼偟側偄丅慠偟偙偺崄嵷側偔偟偰偼烤梤擏偼惉傝棫偨側偄丅
丂戞嶰偵丄杮奿揑擱椏偲偟偰敀徏偑偁傞丅偙傟偼偦偺墝偵傛偭偰丄梤擏偵撈摿偺崄婥傪偮偗傞偙偲慜婰偺捠傝偱偁傞丅偦偟偰丄偙偺擱椏偼擔杮偵偼側偄丅乮敀徏偼彮側偄偐傜拞崙偱傕懠偺恉偑巊傢傟傞傜偟偄乯
丂戞巐偵丄敀姡帣偑偁傞丅擔杮偺從拺偱偼敀姡帣偺戙梡偼弌棃側偄丅
丂烤梤擏偼攐嬪偺婫戣偱尵偊偽乽搤乿偺傕偺偱偁傞丅杒嫗偺搤偼崜姦偱偁傞丅怘傋傞偺偼幒撪偱偼側偄丅拞掚偲偼尵偊屗奜偱偁傞丅怘傋巒傔傞傑偱偼丄奜搮偺嬢傪棫偰偰偄偰傕姦偄埵偱偁傞丅
尒忋偘傟偽丄搤偺揤偑偁傞丅寧楊偺庒偄帪偼枮揤偺惎扖偑嬄偑傟傞丅栚偺慜偵偼壩楩偑偁傞丅怘傋傞傕偺偼擬僢擬僢偺梤擏偱偁傝丄堸傓傕偺偼敀姡帣偲偄偆壩庰偱偁傞丅
丂杒嫗偺惓梲極偱烤梤擏傪怘傋偰偄傞偲丄暡愥偑僠儔僠儔偲堾巕偵晳偄嶶偭偰棃傞偙偲偑偁偭偨丅壩楩偐傜偼丄敀徏偺擱偊偰弌偡傎偺偐側墝偑丄嬻偵偁偑偭偰峴偔丄偦偺嬻偐傜偼僠儔僠儔偲姡偄偨暡愥偑崀偭偰棃傞丅偦傟偑烤梤擏傪怘傋傞暤埻婥偨偺偱偁傞丅暤埻婥傪敽傢偸怘帠偵偼嵃偑側偄丅擔杮偺僕儞僊僗僇儞椏棟偼慡偔帡偰旕側傞傕偺偲巹偑尵偆棟桼偼彮偟偼傢偐偭偰捀偗偨傠偆偐丅
丂杒嫗傪朘傟傞恖巑偼丄烤梤擏傪帋怘偝傟傞偑傛偄偲巚偆丅偦偺帪婜偼搤丄偦傟傕尩搤偺帠傛偄丅楇壓廫悢搙偺崜姦偺栭偱偁偭偰傕丄婣戭偡傞傑偱丄偄傗婣戭偟偰屻傕懱偼儂僇儂僇偲壏傑偭偰偄傞偱偁傠偆偙偲傪巹偼曐徹偟偨偄偲巚偆丅
乮俀乯
亙棯亜丂偦偺栭偼丄杮応偺梤椏棟丄偐偺崑夣側鄑擏偺棫偪怘傂傪帋傒偨丅僡儞僊僗僇儞偲偼擔杮恖偺柦柤偩偝偆偩偑丄嵐敊偵奐偐傟傞孯椃偺栭墐偼楢憐偲偟偰傑偯偔側偄丅梤椏棟偺揦偼媼巇偺彮擭傑偱傒側夞乆嫵搆偩偲偄傆偙偲傕偼偠傔偰暦偄偨丅
乮俁乯
丂枅擔偺傛偆偵偁偮偨梉棫偑娫墦偔側傝丄嬻偵偼敀偄塤偺偐偗傜傕柍偔丄峀乆偲尷傝側偔恀僣惵偵側傞丅奨堦柺偺梞炁傗炁偺梩偑丄棳愇偵墿偽傒偙偦偡傟丄怱側偟偐偄偝乀偐寴偔姡忋傝丄晽偵悂偐傟偰僇僒乛乢偲壒傪偨偰傞丅
丂丂廐樢偸偲栚偵偼偝傗偐偵尒備傟偳傕
丂丂丂丂丂丂丂丂丂晽偺壒偵偧嬃偐傟偸傞
偲丄擔杮側傜偽偔傞強偩偑丄杒嫗偱偼嵍偵旕偢丄偙偙偱偼廐偺朘傟偼丄挰乆偺彫椏棟壆偺昞偵偐乀傞丅
丂丂丂從丂丂丂烤 丂丂丂涮
偺娕斅偵巒傑傞偺偩丄
丂從偼懄偪從梤擏丄烤偼烤梤擏丄偮傑傝偍撻愼偺惉巚媑娋偺偙偲丄偦偟偰涮梤擏偼梤擏偺悈偩偒偱偁傞丅
丂巈梤偼戝懱擇丄嶰寧偐傜巐丄屲寧傑偱偵嶻傑傟傞丅惀偑敧働寧廫働寧偲宱偰偽僜儘乛乢敪忣傪巒傔偰丄擏偑廘偔側偮偰偔傞丅敧寧枛偐傜嬨丄廫寧偼巈梤側傜偽屲丄榋働寧栚丅壞廩暘憪傪嬺傋偰惀偐傜搤傓偒偵偲帀偑忔傝弌偡丄堦斣偍偄偟偄帪偱偁傞丅
丂廫堦寧丄廫擇寧偲丄姦偔側傟偽嫀惃梤偑搊応偡傞丅帀偺忔傝偒偮偨堦嵥偺嫀惃壊梤偺枴偲樢偰偼丄偦傟偙偦暥帤捠傝乽偙偨偊傜傟側偄乿丅
丂変崙偺條偵巆弸偑搚梡傛傝傕弸偄偲備偆偺偲堎傝丄崟挭偺塭嬁偺彮偄戝棨墱抧偺杒嫗偱偼丄棫廐偼儂儞僩偵廐偺弶傔丅偦偺廐偑棫偮偲摨帪偵偙偺從丄烤丄涮丄偺娕斅偑奨傪偵偓傢偟丄偐偔偰杒嫗偼廐偵側傞丅
丂烤梤擏丄懄偪擔杮恖偺強堗惉媑巚娋撶偼丄恖傕抦傞捠傝丄梤擏傪偽懢栚偺嬥栐偱恉偺壩偱鄤傝丄忀桘偵偮偗偰嬺傋傞傕偺丅擏偺廘傒傪偸偔堊偵丄偮偗忀桘偵偼嬟嵷丄擝嵷壴丄幣杻忀丄鐓巕桘側偳丄庬乆偺栻枴偑傑偤偰偁傞丅涮梤擏偺応崌丄椺偺恄愬楩乮壩撶巕乯偵僟僔傪幭偨偓傜偣丄壩偑僒僣僩摟傞掱搙偵梤擏傪幭偰乮捠恖偼擏傪敘偱嫴傫偩傑乀椉嶰搙嵍塃偵塲偑偡忎偩偦偆偩乯乗乗幭偡偓傞偲峝偔側傞乗乗偮偗忀桘偵偮偗傞丅
丂偄偯傟偵偣傛丄揤崅偔攏旍偊丄恖枓戝偄偵怘梸傪姶偠傞弶廐偵丄偟偙偨傑媗傔偙傫偱壞憠偣傪夬暅偝偣傛偆偲備偆丄揟宆揑偺塰梴椏棟偱偁偮偰丄曇廠幰偑昅幰偵梫媮偟偨乮丠乯擔杮晽偺廐偺枴丄椺偊偽桵偺崄傪偒偐偣偨從徏戼偲偐丄夎澍傪僺儕僣偲岠偐偣偨殓偺愻偄偲偄偮偨椶偺丄拑恖岲傒偺廰偄戙暔偲偼抐慠庯偒傪堎偵偡傞丅朞偔傑偱傕尰悽揑丄愊嬌揑丄妶摦揑側枴妎偱偼偁傞丅亙棯亜
乮係乯
丂丂丂烤擏乮僕儞僊僗僇儞椏棟乯
丂杒嫗偺烤擏偼柧偺枛丄惔偺弶傔偵巒傑偭側偲偄傢傟偰偄傞丅尰嵼杒嫗偱桳柤側揦偼乽烤擏墤乿丄乽烤擏婫乿#28900;擏墤亙偐偍傠偍偊傫偲儖價亜乿偲偄偆擇偮偺揦偑偁傞丅烤擏墤偼慶揱偡偱偵榋悽丄擇昐桳梋擭偲偄偄丄烤擏婫偼嶰悽偱昐梋擭傕宱偰偄傞揦偱偁傞丅烤擏墤偼忛偺撿丄烤擏婫偼忛偺杒偵偁傞偺偱乽撿墤杒婫乿偺徧偱恊偟傑傟偰偄傞丅
丂烤擏偺摿怓偼擏傪慖傇偙偲偲丄擏偺愗傝曽偵崅搙偺媄弍傪梫偡傞偙偲偱偁傞丅擏偼庡偲偟偰梤丄媿傪巊偄撠偼巊傢側偄丅媿擏偼巐丄屲嵨偱堦屲乑僉儘埲忋丄廐憪傪怘傋偨媿偑嵟傕傛偔偰丄嶳搶徣偺媿偺傛偆偵偁.傝旍戝偵側偭偨偺偼揔偝側偄偲偝傟偰偄傞丅梤偼媥廳擇乑僉岥偔傜偄偑嵟傕傛偔丄堦屲僉儘埲壓偼傛偔側偄丅擇屲僉儘丄嶰乑僉儘偵側傞偲偙傟傕埆偄丅偱偼丄偙偺傛偆側婯奿偺媿傗梤偑慡晹巊梡偝傟傞偐偲偄偊偽丄偦偆偱偼側偔丄堦屲乑僉儘偺堦摢偺拞偐傜烤擏偵巊梡偝傟丄偙傟偵揔偟偰偄傞擏偺晹暘偼擇乑僉儘撪奜偱慡懱偺堦屲僷乕僙儞僩偵夁偓側偄丅梤偱傕丄擇乑僉儘偺傕偺偐傜敧乗嬨僉儘偱屲乑僷乕僙儞僩偵枮偨側偄擏偺巊偄曽傪偡傞丅偳偺晹暘偑揔偟偰偄傞偐丄偙傟偼偦偺揦偺旈揱偱偁傞丅
丂傑偨偙傟傪從偔曽朄偑傓偢偐偟偔丄擱椏偵偟偰傕攼丄桍丄徏偺栘偲偝傟丄拞偱傕徏偺彫巬丄徏偐偝傪嵟忋偲偡傞丅妱敘偔傜偄偺戝偒偄揝朹偺栐傪偐傇偣偨戝偒側楩偱從偔偺偱偁傞偑丄偩偄偨偄業揤偐壠壆偺壆忋偵怘戩傪弌偟丄怘戩偺夞傝偵儀儞僠傪抲偒丄偦偺忋偵曅懌偩偗傪偺偣偰棫偮丅怘戩偵偼擏偲栻枂偑暲傋偰偁傞丅栻枴偼偹偓丄惗汭偺偣傫愗傝丄挷枂椏偼惗汭廯丄忀桘丄庰丄仭桘乮偊傃偐傜偲偭偨墫廯乯側偳偱偁傞丅偙傟傜偺栻枴偲挷枴椏傪揔搙偵崿偤崌傢偣丄偮偗廯傪嶌傝偙傟偵擏傪捫偗偰偍偔丅擏傪從偔慜偵梤偺旜偐傜偲偭偨桘偱揝栐傪揾傞丅傎偐偺桘偱偼枴偑棊偪傞丅揝栐偑擬偔側偭偨偲偙傠偱丄悈傪堦揌棊偲偟偰傒偰丄偡偖姡偗偽丄偹偓丄惗汭偺偣傫愗傝傪傑偢偺偣丄偮偓偵擏傪偲傝弌偟偰從偔丅
丂擏傪從偔敘偼榋乑乗幍乑僙儞僠偔傜偄偺挿偄傕偺偱丄偙傟偼丄擔杮偺偡偒從偲摨條丄怘傋傞偺偵偄偪偄偪嶮偵惙傜偢丄從偄偰擬偄擏傪晲愙岥偵塣傇偺偑偍傕偟傠偄偟丄旤枴側偺偱偁傞丅
丂偙偺從偒擏偲偄偭偟傚偵怘傋傞偺偵丄嵒摐捫偗偺偵傫偵偔偑偁傞丅偙傟傪怘傋傞偲梤偺廘傒傕側偔丄傑偨偵傫偵偔偺廘傒傕徚偊傞偺偱偁傞丅傑偨丄從栞乮偛傑偐偗偺僷儞乯偑暷斞傗閈摢側偳傛傝揔偟偰偄傞丅
丂偄傑傗岼偺僕儞僊僗僇儞偑杒嫗偺偦傟偵帡偰傞偲偡傟偽丄梤擏傪從偔偲偙傠偩偗偱丄儌儎僔丄嬍鍐媜傗撿塟丄捙戼丄壥偰偼偙傫偵傖偔丄査椶傑偱惙傝偩偔偝傫偵擖傟偪傖偆傫偱偡偐傜偹丅塒堜偺嫇偘偨憡堘偵傕偆俀偮俁偮懌偝偵傖側傜傫偱偟傚偆丅
丂嶌壠崅尒弴偺擔婰偵傛傞偲丄徍榓侾俋擭侾侾寧俀係擔偵丄帒椏偦偺俀侾偵弌偰偒偨堦悿墍偱拫怘傪偲偭偰偄傑偡丅傑偨崅尒偑昤偄偨撶偲鄡楩偺奊偑嵹偭偰偄偰(38)丄恉偱從偄偰偄偨偙偲偑傢偐傝傑偡丅僗儔僀僪偱尒偣傑偟傚偆丅偦偺応偱庤挔偐壗偐偵昤偄偨偺偱偟傚偆偑丄從偒柺偑懷忬偺揝斅偱寗娫偑嫹偄偙偲側偳偑傢偐傝傑偡偹丅堦悿墍偲偄偆柤慜傕擖傞傛偆偵偟偨偨傔廲挿偵側傝夁偓偨偑丄徫傢側偄偱偔偩偝偄丅
丂丂丂丂丂
丂帒椏偦偺俀俀乮侾乯偼丄懢暯梞愴憟偺捈慜丄僴儚僀偐傜熮廎側偳偺戝棨椃峴偵弌妡偗丄杒嫗偱汎傜傟偨惉媑巚娋椏棟偺擏偼撠擏偩偭偨偲怣偠偨傑傑彂偄偨巚偄弌偱偡丅
丂宖嵹偟偨偺偼擔晍帪帠偲偄偆朚帤巻偺徍榓侾俇擭偺尦扷崋偱偡偑丄儁乕僕悢偑偡偛偄丅偄傑側傜偄偞抦傜偢丄愴慜偱偡傛丄暔帒朙晉傪屩偭偨傾儊儕僇偩偭偨偲偟偰傕丄僴儚僀嵼廧朚恖岦偗偺怴暦偑杮巻偲係晹偺摿廤傪崌傢偣偰丄側傫偲俆侽儁乕僕丅怣偠偵偔偄偑帠幚側傫偩丅乽梸偟偑傝傑偣傫彑偮傑偱偼乿偱偼彑偰偭偙側偄偹丅
丂偙偺悘昅偼戞俀摿廤偺係柺偵偁傝傑偟偨偑丄杮巻俀柺偱偼徍榓侾俆擭廐偺婭尦俀俇侽侽擭曭廽峴帠偱丄嵼棷朚恖敪揥岟楯幰偲偟偰彽偐傟偨係恖偺嵗択夛偑偁傝丄擔暷娫偺嬞挘傪嫮偔姶偠偰偄偨偐傜偙偦偱偟傚偆偑丄擔杮恖偼暯榓偺垽岲幰偱偁傝丄僴儚僀奐敪偲擔暷椉崙偺恊慞偲擔杮柉懓偺奀奜敪揥偵搘椡偲偰偒偨丄崱屻傕寛偟偰偙偺怣擮傪娧偄偰惗偒傞傎偐偵摴偼側偄(39)乗偲岅偭偰偄傑偟偨丅
丂摨乮俀乯偼搶戝弌偺奀孯庡寁戝堁丄嶳忋扥屲榊偺嬪廤乽杒梞乿偐傜偱偡丅骐偵傛傞偲乽戝搶垷愴憟杣敪偲嫟偵丄孯愋偵偁傞巹偼柦傪曭偠杒巟偵搉傝杒嫗偵偰埥傞庬偺嬑柋乿偵暈偟乽偮偄偱巹偼孯娡偵忔慻傒杒曽曽柺偵嬑柋乿偟偨丅乽婣娨埲崀乿乽愴椡憹嫮偵娭楛偡傞C柋傪壥偨偟側偑傜悈尨廐嶗巕栧壓偲側傝丄巜摫傪庴偗偨(40)偲偁傝傑偡丅
丂偙偺嬪廤偑弌偨偺偼徍榓俀侽擭侾寧丄偦偺俈僇寧屻偵戝擔杮掗崙偼傾儊儕僇側偳楢崌崙偵柍忦審崀暁傪偟偨偺偱偡丅偄傑偩偐傜徫偭偰榖偣傞偑丄彫妛俇擭惗偺巹偼丄傾儊儕僇恖偺搝楆偵偝傟傞偲杮摉偵怱攝偟偨傕傫偱偡丅
帒椏偦偺俀俀
乮侾乯惉媑巚娋椏棟
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂麷揷宑惍
栺廫働寧慜偺帠偱偁傞丅戝
媫偓偺慛熮杒巟堦恖椃偺愜
杒嫗偺傒偵偼柇偵崢傪棊拝
偗偰屲擔娫棷傑偮偨偑丄偦
偺堦擔摨憢偺桭俿巵偺埬撪
偱墭偄彫搻橺巗応偲塢偼
傟恖娫偲撠偲偛偮偪傗偺毢
偩傜偗偺僥儞僩奨丄慠傕嫲
傠偟偔柉廜揑娊妝嫬偺揤
嫶傪尒偰偺焏搑亀堦偮拫
怘偵捒椏棟傪屼抷憱偟傗
偆亁偲楢傟偰峴偐傟偨偺偑
慜栧丂偺斏壺奨偺棤層摨傪
擇嶰挰擖偮偨屆傃偨敄墭偄
榁斞揦偱偁傞丅愇忯偺拞
掚偵嶰巐婎偺堎條側揝啖偑
暲傋傜傟愭媞偑偦偺夢傝偵
婑偮偰傤傞丅嵄偐偟傝崬傒
偟偰傤傞彫惗偵丄俿巵偼偄
偐偵傕庤嵺傛偔巟撨恖億乕
僀偺帩偮偵樢偨撠擏偺愗傟
傪擝偺擖偮偨弌偟廯偵怹偟
偰偼啖忋偵暲傋傜傟偨揝朹
偺忋偵偺偣偰偼鐉偑偟偰僷
儞偵嫴傫偱偼嬺傋撫傜亀孨
崯傟偑椺偺嵐敊栔屆偺惗傫
偩晄悽弌偺塸梇惉媑巚娋偺
悽奅惇暈偺梇恾偵擱偊偰惇
栰枩棦偺壥偵媔偟偨栰愴椏
棟偩偲塢偼傟偰傤傞丅孨巟
撨偱偼墭偄偲巚偮偨傜堦偮
傕怘傋傞暔偼側偄傛桬婥傪
弌偟偰傗偮偰傒傛亁偲姪傔
傜傟嫲傠偟偔挿偄栘敘傪晄
婍梡偵巊偮偰杍偽偮偰傒偨
偑丄幚偵栰庯枮乆偨傞偦偺
棫怘椏棟偵慠傕偦偺旤枴偵
嫲傟擖偮偰巇晳偮偨偑丄屼
忋昳側忯偺忋偺擔杮偺僗僉
從椏棟偵斾偟偰丄栰揤偱戝
偒側揝啖傪慜偵棫怘偺惉媑
巚娋椏棟偙偦偼幚偵偙傟埵
栰庯偵晉傫偩丄崑寙揑偲塢
偼偆偐丄戝棨宆偲塢偼偆偐
塸梇揑椏棟偼懠偵偁傞傑偄
亂昅幰偼搶杮婅帥暿堾奐嫵巊亃
丂丂丂烤梤擏偲壩撶巕
丂丂丂丂丂丂偄偢傟傕搤偺柤暔椏棟側傝
丂丂丂巟撨奨傗梤擏娰偺楬抧嫹偔
丂丂丂梤擏偺彽攙屆傝偟層摨偐側
丂丂丂梤擏傪烤偔傗栄旂偺恖孮傟偰
丂丂丂梤擏傪烤偗偽搤揤婥塅戝偵
丂丂丂梤擏傪烤偗偽惎嵗傕備傜傔偗傝
丂嵟屻偼戝暔丅帒椏偦偺俀俁偼嶃媫僨僷乕僩偺夛挿傗塮夋偺搶曮幮挿傪柋傔偨惔悈夒偑愴慜偵彂偄偨乽惷悈嫃枱昅丂懕乿偐傜偱偡丅嶃媫僨僷乕僩偼徍榓侾俁擭偐傜揤捗偵恑弌偟偰嶃媫嫟塰栻朳傗庻奨巗応偲偄偆僨僷乕僩揑嶨壿揦傪奐偄偨(41)偺偱偡偑丄惔悈偼偦傟傜傪巜婗偟偰丄壗搙傕揤捗丄杒嫗偵弌偐偗偨丅乽惷悈嫃枱昅乿偼徍榓侾係擭丄偦偺懕偒偺乽惷悈嫃枱昅丂懕乿偼侾俇擭偵弌偟偨帺壠杮偱偡丅
丂偙傟偱傢偐傞傛偆偵惔悈偼僕儞僊僗僇儞偑戝岲偒偵側傝丄杒嫗偺僕儞僊僗僇儞椏棟揦偐傜撶傪攦偄丄擔杮偵帩偪婣偭偨丅偦偟偰愴屻丄偦偺撶傪侾侽侽枃偖傜偄暋惢偟偰丄嶃媫宯楍偺榋峛嶳儂僥儖偺嬤偔偱僕儞僊僗僇儞椏棟揦傪奐嬈偟偨丅偦傟偑偄傑偺僕儞僊僗僇儞僥儔僗側傫偱偡傛丅
帒椏偦偺俀俁
乮侾乯島墘丂怘帠偲戜強
亙棯亜丂偄偮偐巹偼丄嫟塰夛偺嶨帍偵丄僡儞僊僗僇儞椏棟偺帠傪堦悺彂偒傑偟偨偑丄搤娫丄杒嫗傊峴偒傑偟偰丄巹偼偙傟傪嬺傋傞偺偑幚偵妝偟傒偱偁傝傑偡丅戝偒側丄偙傫側揝偺撶偵丄梤偺擏傪廯偵偮偗偰丄偺偣偰從偒傑偡丅僥乕僽儖偺廃埻偵崢妡偑偁偮偰丄偦傟偵崢傪偐偗側偄偱曅懌傪偐偗偰丄挿偄敘偱擏傗栰嵷傪偮乀偄偰丄屼拑偺偐傢傝偵榁庰傪堸傒傑偡丅
丂惵揤堜偺壓偱丄姦晽偵悂偐傟側偑傜丄梤擏傪偮乀偔姶偠偼拞乆壋側傕偺偱丄偦傟偑嵪傓偲椬偺僥乕僽儖偱姛傪偡乀傝拑傪堸傫偱択徫傪岎傊傞偺偱偁傝傑偡丅
乮俀乯杒巟偺椃偐傜
丂栚捠傝擇広偽偐傝偺徏偺栘傪椫愗傝偵偟偰丄偦偺愗栚傪偐傑傏偙宆偵壛岺偟偨傕偺偑丄梤偺擏傪偆偡偔愗傞帪偺傑側斅偱偁傞丅
丂偖傞傝偵旂偺偮偄偰傤傞偺偑丄偙偺傑側斅偺抣懪側偺偐丄偳偺壆戜揦傪尒偰夢偮偰傕丄幚偵棫攈側旂偑偮偄偰傤傞丅揦偺墶偵揝朇晽楥偺條側傕偺傪偡偊偰丄偙偺拞偵梤偺擏偑昘偲嶨嫃偟偰傤傞丅偙偆塢傆偯偆懱偺戝偒偄傕偺偑丄強堗杒嫗偺乽巗応乿偲傛傇嶨壿傗壔徬昳傪攧偮偰傤傞揦偺廤抍偺拞偺椏棟壆偺慜偵丄強嫹偒傑偱偵暲傫偱傤傞丅
丂僕儞僊僗僇儞椏棟偼丄偙偺椏棟壆偺壆崻偺忋偱丄姦偄惵揤堜傪尒側偑傜丄巟撨庰傪拑榪偵偮偄偱丄曅懌傪堉巕偵偁偘偰丄挿偄敘偱梤偺擏傪從偒側偑傜嬺傆偺偱偁傞丅
丂嬺偮偰廔傆偲丄椬偺僥乕僽儖偱丄埦偺姛偵嵒摐傪偐偗偰偁偮偄偺傪偡乀傞丅
丂婔搙樢偰傕丄杒嫗偲僕儞僊僗僇儞椏棟偼巹偵偼暿屄偵偟偰峫傊傜傟側偄丅
丂僕儞僊僗僇儞僥儔僗奐嬈偵帄傞宱堒偼丄惔悈偑徍榓俆係擭偵弌偟偨乽榋峛偩傛傝乿偺乽戞榋怣乿(42)側偳偵徻偟偔彂偄偰偁傝傑偡丅僕儞僷妛尋媶偱戝帠側偺偼奐嬈偵帄傞悢擭慜丄惔悈偼乽愴憟偑偡傫偱戝暘偨偭偰偐傜乿偲彂偄偰偄傞偺偱偡偑丄挬擔怴暦偑偦偺撶偺幨恀傪嶣傜偣偰偲偄偭偰偒偨偺偱丄墱偝傫偲從偄偰傒偣偨丅偙偺婰帠偺採帵偼僥儔僗偺敪抂傪愢柧偡傞忋偱寚偐偣傑偣傫丅怴暦偵嵹偭偨傜偟偄偱偼丄巚偄偮偒偺懎愢偲摨偠偱偟傚丅
丂偦傟偱偹丄惔悈偝傫丄偁側偨偺撶偺婰帠傪攓尒偟傑偟偨側傫偰丄峴偔愭乆偱偄傢傟偨傫偱偟傚偆丅偦偙偐傜偑丄巹傜偲堘偆傫偱偡側偁丄幚嬈壠偼丅偙傝傖棳峴傞傫偠傖側偄偐偲撉傫偱丄暋惢撶傪偨偔偝傫嶌傝丄傑偢戝嶃偱僕儞僊僗僇儞偺揦傪奐偙偆偲偟偨偲偄偆偺偱偡丅
丂惔悈偺撶偺婰帠偑嵹偭偨偲偟偰傕丄挬擔偺壗偲偄偆抧曽斉偵嵹偭偨偐嶥杫偵偄偰偼挷傋傛偆偑側偄丅堦墳偼挬擔偺暦憼嘦偼摉偨偭偨偗傟偳丄偙傫側儘乕僇儖側婰帠偼擖偭偰偄側偄傫偱偡傛丅偦傟偱偹丄尰抧偵峴偭偨曽偑憗偄偲恄屗巗棫丄惣媨巗棫偲俀偮恾彂娰傪偍朘偹偟偰偩丄帒椏傪嫵偊偰捀偒丄恄屗斉偲嶃恄斉偺儅僀僋儘僼傿儖儉傪彮偟尒偣偰傕傜偭偨丅偍堿偱惔悈偼愴屻丄惣媨巗偵廧傫偱偄偨偐傜婰帠偼惣媨偵攝払偝傟傞嶃恄斉傜偟偄丅挬擔偱偼俀俀擭俉寧暘偐傜偺嶃恄斉傪娷傓暫屔斉偺儅僀僋儘僼傿儖儉傪嶌偭偰偄傞偲傢偐偭偨丅偙偆側傟偽偙偭偪偺傕偺偩丅
丂偦傟偱崙夛恾彂娰偵捠偭偰徍榓俀俀擭偐傜俁侽擭枛傑偱偺挬擔暫屔斉傪侾夞撉傫偩偺偩偑丄巆擮側偑傜尒偮偐傜側偐偭偨丅媮傔傛丄偝傜偽梌偊傜傟傫乗偩丄偦傟偱丄傕偆侾夞撉傒捈偟偰偄傞偲偙傠偱偡丅僥儔僗奐嬈偼徍榓俁侾擭偲偄偆愢傕偁傞偺偱偡偑丄偄偢傟尒偮偗偰丄恄屗偺僕儞僊僗僇儞偲偟偰夵傔偰庢傝忋偘傑偟傚偆丅廔傢傝傑偡丅
丂乮暥專偵傛傞僕儞僊僗僇儞娭學偺巎幚峫徹偲偄偆尋媶偺惈幙忋丄挊嶌尃怤奞偵側傜側偄傛偆堷梡側偳偺柧帵傪怱妡偗偰慡儁乕僕傪惂嶌偟偰偍傝傑偡偑丄偍婥偯偒偺揰偑偁傝傑偟偨傜丂jinpagaku@gmail.com丂恠攇枮廎抝傊偛堦曬壓偝傞傛偆偍婅偄偟傑偡乯
| 丂丂 |
嶲峫暥專
忋婰乮俁俁乯偺弌揟偼巕埨擾墍撪壠抺尋媶夛曇乽壠抺乿俀俁姫俆崋俆俀儁乕僕丄崟揷弶巕乽旤枴偟偄梤擏偺怘偟曽乿丄徍榓侾係擭俋寧丄巕埨擾墍撪壠抺尋媶夛亖尨杮丄
乮俁係乯偲帒椏偦偺侾俋乮侾乯偼摨俀俁姫俇崋俆俀儁乕僕丄徍榓侾係擭侾侾寧丄摨丄摨乮係乯偼戝擔杮彈巕幮夛嫵堢夛曇乽彈惈嫵梴乿侾俋俈崋俁俉儁乕僕丄崟揷弶巕乽僕儞僊僗僇儞從偒偺旈朄偼偹偓偺傕傒崬傒乿傛傝丄徍榓俁侽擭俇寧丄戝擔杮彈巕幮夛嫵堢夛亖娰撪尷掕嬤僨僕杮丄
乮俁俆乯偼崟揷弶巕挊乽枴偲帺慠偺嶶曕摴乿俀俋侾儁乕僕丄徍榓俆俁擭係寧丄昡榑幮亖尨杮丄帒椏偦偺侾俋乮俀乯偼摨係俋儁乕僕丄摨丄
帒椏偦偺侾俋乮俁乯偼彈惈嫵堢幮曇乽彈惈嫵堢乿侾俋俈崋俁俉儁乕僕丄徍榓俁侽擭俇寧丄彈惈嫵堢幮丄摨丄
乮俁俇乯偼搶暥梇挊乽慛枮巟戝棨帇嶡椃峴埬撪乿偺乽傑傊偑偒乿丄徍榓侾係擭俇寧丄搶妛幮亖尨杮丄帒椏偦偺俀侽偼摨俇侽儁乕僕丄摨
乮俁俈乯偲帒椏偦偺俀侾乮侾乯偼塒堜晲晇挊乽杒嫗捛憐丂忛暻偁傝偟偙傠乿侾俋俇儁乕僕丄徍榓俆俇擭侾侾寧丄搶曽彂揦亖尨杮丄
摨俀侾乮俀乯偼娸揷崙巑挊乽杒巟暔忣乿俀俈侾儁乕僕丄乽巗拞尒暔乿傛傝丄徍榓侾俁擭俋寧丄敀悈幮亖嬤僨僕杮丄
摨俀侾乮俁乯偼怘摴妝幮曇乽怘摴妝乿侾姫俆崋係儁乕僕丄幝揷摑乽杒嫗偺廐偼梤擏偐傜乿傛傝丄徍榓俀俋擭俋寧丄怘摴妝幮亖尨杮乮崙棫柉懓妛攷暔娰丒尋媶傾乕僇僀僽丒幝揷傾乕僇僀僽乽挊嶌栚榐丂値倧丏侽俉俀乿乯丄
乮係乯偼戝搰摽栱挊乽昐枴銍棎乗乗拞崙丒枴偺嵨帪婰乿俈侽儁乕僕丄徍榓係係擭係寧丄暥壔暈憰妛堾弌斉嬊亖尨杮丄
乮俁俉乯偼崅尒弴挊乽崅尒弴擔婰乿俀姫偺壓俉俉侽儁乕僕丄徍榓俁俇擭俆寧丄櫎憪彂朳丄摨丄
乮俁俋乯偼徍榓侾俇擭侾寧侾擔晅擔晍帪帠挬姧戞係晹俀柺丄暷崙僼乕僶乕尋媶強僨乕僞儀乕僗傛傝丄
https://hojishinbun.hoover.org
/en/newspapers/tnj19410101
-01.1.26
帒椏偦偺俀俀乮侾乯偼摨戞俀晹係柺丄暷崙僼乕僶乕尋媶強僨乕僞儀乕僗傛傝丄
https://hojishinbun.hoover.org
/?a=d&d=tnj19410101-01.1.50
&srpos=57&e=
摨乮俀乯偲乮係侽乯偼嶳忋扥屲榊挊乽嬪廤丂杒梞乿俁係儁乕僕丄徍榓俀侽擭侾寧丄嶳忋扥屲榊乮旕攧昳乯亖尨杮丄
乮係侾侽乯偼惔悈夒挊乽惷悈嫃枱昅乿俉俋儁乕僕丄乽揤捗偐傜乿傛傝丄徍榓侾係擭俈寧丄惔悈夒乮旕攧昳乯亖娰撪尷掕嬤僨僕杮丄
帒椏偦偺俀俁乮侾乯偼惔悈夒挊乽惷悈嫃枱昅乿俋俆儁乕僕丄徍榓侾俇擭侾俀寧丄惔悈夒乮旕攧昳乯丄摨丄
摨乮俀乯偼摨侾俈侽儁乕僕丄摨
乮係俀侾乯偼惔悈夒挊乽榋峛偩傛傝乿俉俀儁乕僕丄徍榓俆係擭俇寧丄惔悈夒亖尨杮乮旕攧昳乯
|
|