私の好きなエッセイ
〔メニュー〕
1、カイチュウ博士おおいに語る 『清潔はビョーキだ』から抜粋
藤田紘一郎(東京医科歯科大学教授・寄生虫学)
(添付資料)回虫はアレルギーの“特効薬”
大石芳野(写真家)、写真3点つき
3、私の生きている証し−『悪魔の飽食』。人生の三点セット
森村誠一(作家) 『森村誠一公式サイト』
(添付資料)「著作権侵害は中国の恥」訴えたら
〔北京の裁判所〕森村誠一さん勝訴の判決
松山幸雄(共立女子大学教授・元朝日新聞論説主幹)
(注)4人の方との出会いは、1998年8月23日付、朝日新聞「ひととき」欄に『夫婦でホームページ』の題名で掲載されました。それに加筆したものを、「インターネットことはじめ」の章に載せました。
4人の方の文については、すべて原文どおりにしてあります。
カイチュウ博士おおいに語る
アブナイ超清潔志向
(CG・コンピューターグラフィックス 宮地徹)
藤田紘一郎教授は、2000年11月愛知県芸術文化会館で、愛知県主催の
『文化夜話』に講師として招かれ、満員の聴衆に熱弁を振るわれました。
教授のユニークな研究、理論は15年間学会で無視され続けたそうですが、
たまたま『笑うカイチュウ』というエッセイが、講談社の出版科学文化賞
に選ばれてから、注目され出しました。
インドネシヤのカリマンタン島へ30回以上出かけられた藤田教授は、
ジャングルに住む人たちの健康状態を調べて、汚れた川で毎日水浴び
している人たちの肌がすべすべして黒光りしているのに驚いたといわれる。
アトピー性皮膚炎を思わせる肌は見当たらないし、花粉症で目を真っ赤に
したアレルギー性疾患にかかっている人がほとんどいないことに気付いた。
帰国後の研究で
寄生虫は、1gE抗体という物質を人間につくりださせることがわかった。
実験を重ねて、寄生虫の分泌液や、排泄液中にある分子量二万の
糖タンパクがその物質と分かったそうです。
巷の声から
60代男性 「自分の体にカイチュウを飼うとは、ジェンナーばりの、学会への凄いレジスタンスだなー」
50代女性 「研究が地味な分野だから、陽があたらないって?・・・先日もテレビで見たし、藤田先生は近頃、陽が当り続けているわ」
40代男性 「お腹にカイチュウを飼ってる先生でしょ。アレルギーの問題、ぼくもおおいに関心あります」
〔小目次〕 藤田紘一郎著『清潔はビョーキだ』からの抜粋
1、崩れた共生 なぜ先進国にだけO157?
2、免疫力の低下 外で遊び抵抗力養おう
3、異物への嫌悪感 超潔癖志向に歯止めを
なぜ先進国にだけO157?
医学部で寄生虫学を専門にしている私は、ふだんは注目を浴びることが少ない。それが、このごろやけに忙しくなった。病原性大腸菌O157のような新しい感染症が出現し、私の分野と密接にからんできたためのようだ。
最近も、NHKの番組で、クリプトスポリジウムという原虫による下痢症の話をしたら、全国の医療機関から多数の「下痢便」が私の研究室に送られてきた。ただでさえ汚い部屋は、東京で最も「臭い」「汚い」場所になってしまった。
下痢症というと、まず頭に浮かぶのが、O157による食中毒だろう。一九九六年は、集団感染でパニック状態になったが、九七年はほとんどが散発的だ。しかし、感染の症例数はそれほど減っていないから、油断はできない。
実は、O157による感染は日本ばかりでなく、世界の先進国を中心に拡大を続けているのだ。
英国のスコットランド地方では、九六年十一月に肉入りパイが原因で、四〇〇人以上が感染し、十九人が死亡した。九七年六月にも一人が亡くなっているので、英国は、この感染による死亡数では、世界最悪の事態となっている。米国、カナダ、スウェーデン、ドイツ、ベルギーなどの先進国でも流行している。
しかし、発展途上国では、O157の集団感染は見られない。なぜ、先進国にだけ、このような大腸菌が出現したのだろうか。
私たちの腸の中には、腸内細菌叢(そう)といって、乳酸菌、ビフィズス菌、大腸菌、ウェルシユ菌などたくさんの細菌類が棲んでいる。このうち、大腸菌は、一般には「悪玉菌」として扱われてきた。確かに、腸の調子が悪い時に、腸内細菌叢を調べてみると、乳酸菌やビフィズス菌が減っていて、大腸菌は逆に増えている。
しかし、大腸菌は、人間が正常な健康状態の時には、消化を助けたり、ビタミンを合成したり、むしろ人間に良いこともしているのだ。
このように、もともと人間と「共生」している大腸菌の一部がなぜ、凶悪なO157になってしまったのか。「凶悪犯」になるには、それなりの理由があるはずだ。
その一つが、日本人をはじめとする先進国の人たちの「清潔志向」と、その延長である抗生物質や消毒剤の乱用であると私は思う。
これらの物質の乱用によって、大腸菌が平穏に生きる環境が奪われ、変質へと追い込まれたのではなかろうか。
外で遊び抵抗力養おう
『細菌の逆襲』(中公新書)を著した吉川昌之介東大名誉教授と私は同じ研究室で働いていたことがある。彼は、寄生虫にくら替えした私と違い、ずっと細菌学を研究し続けてきたので、O157などが騒がれる今では貴重な存在となっている。
東京医大の中村明子客員教授も今、最も多忙な一人だ。大腸菌O157やサルモネラ菌による食中毒がここ数年急増しているからだ。
中村教授は一九九六年、O157が集団発生した埼玉、岡山両県の小学生を調査した。同じ給食を食べ、検便によりO157が検出された児童三〇〇人の症状の差を調べたのだ。
その結果、食中毒の原因となった同じ給食を食べ、O157に感染していながら入院が必要な重症の子どもは、全体の一割だった。下痢程度の軽症ですんだ子どもが六割、残り三割は全く症状がなかったということだ。
腸内にはさまざまな種類の菌が一〇〇兆個以上も混在し、腸内細菌叢を形作っている。これらの菌類は、バランスを取りながら、外部から侵入した菌と対抗している。しかし、体力や免疫力が弱いと、このバランスが崩れやすく、発症してしまうのだ。
中村教授は述べている。「子どもたちは抵抗力がまだ弱いが、全員がO157で発病するわけではない。むやみに消毒したり、抗菌の製品ばかりそろえたりして、神経質になり過ぎると、かえって腸内の有用な菌が少なくなり、菌に対する抵抗力が弱まることになりかねない。衛生管理は当然のことだが、無菌状態がいいとは言い切れない」
中村教授は、子どもをできるだけ外で遊ばせることを勧める。私も同じ意見だ。外でいろいろな菌に少しずつ触れることは、免疫力を高めるうえでも、感染症への抵抗力を養う意味でも必要だと思う。
九七年は新しいタイプのサルモネラ菌、サルモネラ・エンテリティディスによる食中毒が大発生した。この菌はネズミが運ぶ従来のサルモネラ菌と違って、主に鶏卵から感染する。欧米では八五年ごろから被害が増えていたが、日本ではやや遅れて広がったことになる。
この菌は明らかに外国から入ってきたものだ。今後もいろいろな細菌類が輸入食品と共に日本に侵入してくるだろう。これらの細菌類が日本国内で定着する背景には日本人の免疫力の低下が関与している。
超潔癖志向に歯止めを
私は、今日本の子どもたちが、「あぶない」と思う。日本の子どもたちが肉体的にも精神的にも衰弱しているように思う。どうしたら子どもたちが元気に、丈夫になれるのだろうか。
私はまず子どもたちが自分の体から出る「きたないもの」への嫌悪感を薄めることが大切ではないかと思った。そんな時に『きみのからだのきたないもの学』という絵本に出合ったのだった
人間の体から出るものを忌み嫌うことを続ければ、それは「人間が生き物」であることを否定することにつながる。やがて自分もなるであろう老人や病人の体臭も嫌うようになる。その結果、老人や病人と自然につき合うことができなくなっていくだろう。
体から出るものを忌み嫌うことは、当然、ヒトに共生している寄生虫や細菌を「異物」として排除しようとする。その結果、人間が本来もっている免疫システムまでも弱めてしまうのだ。
今の若者たちは大抵、脂取り紙や手鏡を携えているそうだ。女友達の「臭い」の一撃は致命的だからだそうだ。なかには、自分の汗やうんちのにおいを消す薬までせっせと飲んでいる若者もいるということだ。
抗菌物質で囲まれているトイレ、消毒剤や消臭剤が置かれ、そのまま便器におしりをつけられない人たちのために便器をふく紙類などが多量に使用されている。
その他、洗濯には強力な洗剤のほか殺菌剤までも使用され、ふろには一日に数回も入り、そのたびにいろいろなシャンプーが使われるようになってきた。もちろん台所にも抗菌製品と消毒剤や消臭剤があふれている。
このように「不潔ぎらい」は、多量の資源を無駄に使用し、その結果、不必要な物がどんどん地球上を汚染していく。「清潔」は環境汚染を増長しているのだ。「抗菌グッズ」の流行は、ただ単に資源を無駄に使用し環境を汚染しているばかりではない。ヒトにとって敵か味方かと見極めず、すべての細菌を「異物」として排除しようとする発想を生んでいるのだ。この「抗菌的発想」が今の日本には蔓延しつつあるように私は思う。
私たちの周辺でも、この種の発想は広がりつつある。
たとえば、医療の見地からいって駆除すべき昆虫は病気を媒介するハマダラカ(マラリアを媒介)といった「害虫」なのに、現在では駆除の対象はゴキブリやハエなどの「不快昆虫」に変わってしまったのだ。これなどは、今はやりのイジメと同じではないか、と思う。「ムカつく」とか「気にくわない」といってすぐ排除してしまう現代日本は「抗菌社会」と呼べそうだ。
日本人の清潔志向は画一的な学校教育にも現われている。制服を着せ、同じメニューの給食を食べさせている。運動会でも一等賞をとるような生徒はつくらない。個性はいわば体臭なのに、平等主義の旗印の下、脱臭に取り組んだりして、とにかく「目立たないよう」に努力しているのだ。そして、校則は「不純物」や「異物」の排除に精を出しているようにさえ思えるのだ。
企業側も同じだ。異物を嫌い、無臭の人材を求める傾向が目立つ。品質管理の面で世界にとどろく産業界は人の面でも均質な規格型を好むようになっている。
私は先日、商事法務研究会の方とお会いした。総会屋とか企業ゴロといわれるものも企業社会に巣喰う寄生虫とかダニとかいわれているが、そういう寄生虫とかダニのようなものも「強い企業社会」をつくるためには必要な場合があるのではないか、という話だった。
もちろん、この件に関して適切なコメントができる立場に私はいない。しかし、考える価値のあるテーマだと思う。
神戸のあの町であのような痛ましい小学生殺害事件が起きたのも、ニュータウンが「異物」の存在を許さないような整然とした街並みであって、住人も中流以上で占められ、そこには町のダニみたいにいわれる人も汚い場所もない、そのような状況と無関係ではないと思う。
全く「異物」が目に入らず、また全く「異物」とつき合わないでいると精神的にも免疫力が低下する。そのような人々だけで構成される社会は、社会全体の免疫性が低下したものになるであろう。
あの神戸の町にもダニといわれるようなおじさんがいて、猫を殺している少年がいたら「お前、何してるんだ」と喝でも入れれば、あのような事件も起こらなかったのではないか、と思う。
そう考えると、やはり見た目がいいものだけでは人間の生活がうまくいかないのではないか、町のダニといわれるような人も、意外なところで人間の生活には役に立っているのではないかと思うのだ。
横浜国立大学におられた青木淳一教授はヒトに嫌われているダニ類の研究を四〇年間も続けておられる。
ある時、青木教授はこんなことを私に語ってくれた。「藤田先生、地球に生きている生き物はすべて意味があるんですよ」と。
「ダニの話をすると、すぐ寄生虫としてのダニ、衛生害虫としてのダニの話が先行してしまう。しかし、実は無害のダニはたくさんいるんです。ヒトにしか寄生しないダニは、ヒゼンダニとニキビダニの二種類にすぎません。残りの大部分は、大自然の中でのんびりと暮らしている。
たとえば、ササラダニ類は腐りかけた落ち葉や枯れ枝をコツコツ噛み砕いて食べ、糞として排泄している。この糞をバクテリアがさらに分解する。つまり、自然界のゴミ掃除人なのです。このダニがいなければ自然界のゴミは片付けられないのです。少しばかり嫌な奴を含んでいますが、ダニ族は私たち人類の大切な共存者なのです」
〔著書『清潔はビョウキだ』から、藤田教授の許可を得て抜粋しました〕
においの文化論
排除招く消臭社会、異物除き免疫低下
藤田紘一郎
(東京医科歯科大学教授・寄生虫学)
「悪臭退治」がいよいよ本年度から政府主導ではじまろうとしている。環境庁のちょっとした目玉事業なのだそうだ。
悪臭防止法に基く国家資格に「臭気判定士」というのがある。現在、臭気判定士は全国に約千六百人いる。悪臭の苦情が自治体にくれば、彼らが「悪臭ハンター」となって出動し、「悪臭」を採取して持ち帰る。そして「きゅう覚テスト」に合格した六人がそのにおいをかいで、基準を超えていれば改善勧告を出すというものだそうだ。
機械でにおいを測る「においセンサー」を開発している研究者によれば、「イヌには及ばないがヒトの鼻も大したもの、イヌと違ってヒトはしゃべることはできるし」と語っていた。
ところで、「悪臭退治」といえば、「脱オヤジはまず脱臭から」と昨年、さかんにキャンペーンを繰り返した企業のことを思い出した。化粧品大手メーカーが、中高年の体臭を消すボディーシャンプーやローションなどを売り出したところ、大当たり。半年で二十五億円の売り上げという。本年度も梅雨期にむけて、さらに売り出しに懸命となっている。
企業戦略が成功したのだ。抗菌グツズはここにきて、市場としては成熟してしまい売り上げ増は見込めない。企業が目をつけたものは高齢化社会をにらんでの中高年者を対象にした消臭グツズなのだ。
若い女性を対象にした調査で、最も嫌なものとして「オジン臭」を登場させる。若いOLの調査で汗の臭いが一番くさく感じるのは「お父さん」だと答えさせる。しかし、実際は「オジンくさい」というにおいなど存在しないのだ。人間四十歳をすぎると中高年独特の体臭、いわゆる「加齢臭」なるものが確かに出てくる。しかし、これには性差はない。「オジン臭」も「オバン臭」も同じにおいなのだ。それなのに「オジンくさい」だけを持ち出してさわぎたてるのは許されないことだと思う。
人間、年をとってきて新陳代謝が十分でなくなってくるとにおいが出てくるのは当然のことだ。病人になると、もっとにおってくる。人間は生物であり、においを出さなくなるのは「死ぬ」時だ。生きている以上、様々なにおいを発生せる。オジサンのにおいに限らず老人のにおい、赤ちゃんのにおい、妊婦のにおい。いろいろのにおいを持つのが人の集団だ。その中で特定のにおいを持つ人を非難するが如き風潮は、排除の論理にほかならないのではないだろうか。
私はインドネシアのカリマンタン島が好きでよく行く。その農村では、子どもがウンチの流れる川で泳いでいる。いろいろなにおいのある日常生活にいるから、老人にも病人にも優しく接することができる。社会のあり様とはそんなものではないだろうか。
日本では今、社会的にひ弱な人間が増えてきているように思う。人間社会は本来、異物を抱え込んで成立している。異物を排除していくと、集団が均一化して免疫力が落ち、生き物としては弱体化していくのだ。
テレビや新聞の広告でも、においを消そう、清潔にしようというのが目立つ。そういうコマーシャルが自分がにおっているのじゃないかという自己臭症や、例えば何時間も手を洗い続けるプリック病などの精神的障害を助長している。小学生が学校のトイレに行けないことなどは、笑い話ではない。実は、いじめの問題にも直結する深刻な問題なのだ。
一方、外に向かっては他人のにおいに過度の反応を示し拒絶する人間、あるいは「おまえはクサイ」と非難するような人間、つまり他人とコミュニケーションできない人間を増やしているのだと思う。
抗菌グッズは社会の免疫力を落とすと私は指摘してきた。消臭商品にも同様なことが言える。いくら売れるからといって、過度に消臭をあおるのは、反社会的な面さえあるのではなかろうか。
時代は抗菌社会から消臭社会に突入したようだ。消臭社会の標的は、このところ自信を失っているオジサンたちだ。職場では部下の女性が顔をしかめながら茶わんを出し、家庭では「お父さんのパンツは臭い」と言われ洗ってもらえない。オジサンはやむなく、消臭シャンプーで体を洗い、ウンチのにおい消し錠剤をのみ、消臭下着を着る。かくして、消臭グッズは売れに売れ、一大市場に成長してきたのだ。
本年度から政府主導ではじまる「悪臭退治」が、この消臭社会をさらに発展させるものではないことを祈りたい。
(東京医科歯科大学教授)
――2000.4.3 中日新聞・夕刊掲載――
藤田紘一郎
(東京医科歯科大学教授・寄生虫学)
今「いじめ」が社会問題になっている。弱いもの、醜いものに対して、多くの人がよってたかって攻撃している。寄生虫に関しても同じことがいえると思う。なまじヒトに寄りかかる生活を覚えたばかりに、やれ独立精神を忘れた生き物とか、怠け者とか、病気をおこす張本人とか、世の嫌われ者になり下がっている。
僕は30年問、この寄生虫とつき合ってきた。その間次第に僕は寄生虫が好きになり、愛おしくなってきた。寄生虫は有史以前からヒトと仲良く共生してきた。寄生虫は宿主であるヒトをあまり攻撃しない。一方、ヒトは抗体などの免疫の力で虫を排除しないで、体内に心地よい状態で棲まわせていたのだった。
寄生虫はヒトに悪いことばかりをやっているのではなかったのだ。花粉症などのアレルギー病にヒトが罹からないようにしていたことに僕は気がついたのだった。
これらの寄生虫とのつき合いを僕は初めてエッセイにまとめ、先ごろ講談社より『笑うカイチュウ』と題して出版した。
一方、医学の世界では「寄生虫学」が「今日的な学問ではない」という理由で「いじめ」られてきた。僕は医学界のなかでも孤独な闘いを強いられてきたのだった。そんな時思いもよらず、賞をいただくことになった。平成7年度講談社出版文化賞、科学出版賞をいただけるということであった。「カイチュウを愛し、寄生虫学を守りなさい」という激励の言葉をかけていただいたような気がする。
*
それにしても「いじめ」がなぜ今の日本の社会に生れてきたのであろうか。僕は日本人の「笑い」のなかにその原因をみつけることができた。
日本人はいつから弱いものや醜いものをさげすんだり、侮辱したりするようになったのだろうか。先日、僕は何げなくテレビを見ていた。「とんねるず」が腰の曲がったお婆さんを舞台にひっぱり出し、裸にして派手な水着をきせて、皆を笑わせていた。それを見てやはり自然に「笑っている」自分自身を発見して、僕は愕然とした。
少し前の日本の「笑い」には、人生の機微からなる「あ、おれもやった、やった」といったような、自己に置き換えた共感の笑いがあった。落語にみられるような人情に触れる笑いも多かった。ところが、今、僕たちが笑っている「笑い」は弱い人、醜い人の人格をはずかしめて笑っている種類のものだ。
この種の「笑い」には、少し前の日本人なら全員気分を悪くしたはずである。しかし、今の僕たちはこの「気分を悪くする」感覚をすでに完全に失っている。
戦後50年、日本人は世界でも例をみないような生活体験をしてきた。戦後の「極貧」からわずか30年で世界の経済大国に成長。繁栄の頂点に立ったら、一転してバブル崩壊。最近の天井知らずの円高と株価暴落、神戸の大震災に続くサリン事件などの社会不安。この目まぐるしく動く変化のなかで、日本人は本当の意味の「笑い」を失ったのであろう。そしてそれが子供たちの間に「いじめ」を生む土壌を醸し出してきたのであろう。
昔、子供たちはスクリーンに映る植木等さんのマネをして、手をブラブラさせながら「スーダラ節」を歌った。今、子供たちはテレビに映るたけし軍団をマネているという。企業コンサルタントの辛淑玉さんは「たけしの笑いの功と罪」と題して次のように書いている。
「たけし軍団の笑いは、たけし自身は安全なところにいながら、他の者をいたぶって笑いをとる支配と従属による<いじめ>の構造によって成り立つ笑いである。そして、視聴者はさらに安全な場所から軍団員の苦しむ姿を楽しむという二重の支配構造を作り上げている。だからこそ、たけしには<功>と同じだけの<罪>がある」
*
僕がはじめて書いたメディカルエッセイに「笑うカイチュウ」という題をつけたのはそれなりの理由があった。カイチュウは戦後の「極貧」時代には日本人の70パーセント以上に寄生していた。それが、戦後の日本の衛生管理の徹底により、有史以前から続いたカイチュウとの共生を全く絶縁してしまった。その結果、日本人はカイチュウに「いじめ」に似た感情を持つようになった。
かつて、虫は日本人の潜在意識のなかにあった。つまり虫との共生を認めていた節がある。森本哲郎氏によれば、実は日本人を動かしている力は日本人の身体に棲みついている虫そのものであるという。「虫がいい」に始まり、「虫が納まらぬ」「虫が知らせる」「虫を殺す」「虫が好かない」「虫のいどころが悪い」「虫ずが走る」さらに「虫がつく」に至るまで、日本語には「虫」に結びついた慣用句が実に沢山ある。「大言海」によれば虫は「蒸」に由来するという。つまり、虫は蒸して熱気の生ずるところに現われるということで、熱気で生きている人間の体内で虫が棲むのを当然のこととして、日本人は受入れてきたようだ。
日本人はこのように太古の昔から寄生虫と共生してきた。しかし、ここ30年間で日本人は歴史的に大変なことをしてしまったようである。有史以前から続いた寄生虫との共生を絶ち切ってしまったのである。
その結果、日本人に何がおこったのだろうか。花粉症やアトピーや気管支喘息などのアレルギー病に苦しむという、思いがけない結果を招いたのだった。
日本はかつてカイチュウなどの寄生虫に悩まされていた。僕たちは先頭にたって、カイチュウ・ゼロ作戦を展開し、みごとに成功した。しかし、ここで気がついてみると、多分数百万年間にわたって続けてきた寄生虫との共生をこのわずか30年でやめた、ということである。
日本は世界一清潔な国になっていたのだ。寄生虫が一時的にも全くいないような特殊な環境を作ったのは日本だけである。数百万年にわたって寄生虫と共生してきた日本人の体内には、寄生虫に対する防衛を任務とする「特殊部隊」が用意されていた。この特殊部隊はこの30年で、突如として失業集団となってしまったわけである。この失業した免疫細胞軍団は寄生虫の代りに、僕たちが今知らない間に吸込んでいるダニや花粉などを攻撃するようになり、アレルギー反応を誘発するようになったのである。
カイチュウ駆除にやっきとなっていた時代には見かけることがごく稀であった気管支喘息や花粉アレルギー、小児のアトピーなどに悩む人々が、最近では異常に増加してしまったのだ。清潔を徹底させた日本人が寄生虫との共生をいみきらうあまり、極端にはしり、生物界の生態系から外れる振舞をしたため、思いがけない結果を招くことになったのだと僕は思う。
群馬大学医学部の鈴木守教授はカイチュウの笑い声を聞いたとおっしゃる。「皆さん、オレたちカイチュウをあまり短兵急に悪者ときめつけて、しゃにむにおいつめたりすると、もっと悪いことがおこることもあるのですよ。ハハハハ」
世の中が豊かになると外国産の生鮮食品も多数市場にでまわってくる。さらに奇妙な食習慣もはやったりする。そのため、今までにあまり見られなかった寄生虫も僕たちの体に入り込んでくる。貧乏の時代にはカイチュウ、金持になると舶来の寄生虫を含めて多種多様な寄生虫……。寄生虫を人の身辺からすっかりなくすことはどうやら不可能のようである。
そして、ここでふたたび、鈴木教授はカイチュウの笑い声を聞いたという。「皆さん、おわかりになりましたか。オレたちカイチュウは、そう簡単にはくたばりません。むしろ、今の日本で少しずつ仲間が増えてきているのですよ。では、サヨナラ、サヨナラ、アハハのアハハ」
「本」6月号
(注)、このエッセイは、96年版ベスト・エッセイ集(日本エッセイスト・クラブ編)に掲載されたものです。このホームページに全文を転載することについては、著者のご了解をいただいています。
なお、藤田氏は、1998年、朝日新聞・家庭欄で『清潔日本 健康学』を連載しました。
(注)これは、ニュースの追跡<特報>として、1998年4月28日、中日新聞(夕刊)に掲載されたものです。藤田氏のエッセイの内容とも関連がありますので、添付しました。
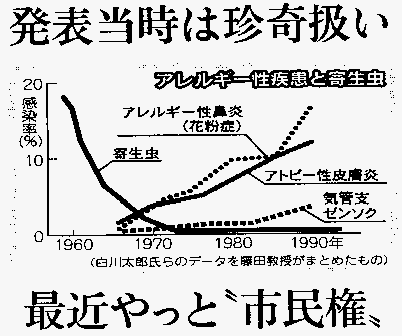
回虫はアレルギーの“特効薬”
『集団駆除』で60年代に激減
アトピー、ぜんそく、花粉症 急増
抑制物質の抽出成功、あとは副作用の問題
藤田紘一郎教授の持論
「回虫が消え、だからアレルギー性疾患が増えたんですよ」。回虫とアレルギーの秘話――。一体、どんな関係なの?
東京・御茶ノ水の東京医科歯科大。藤田紘一郎医学部教授(58)=寄生虫免疫学=が語る。
「集団駆除で回虫が1960年代に激減したんですよ。それでアトピー性皮膚炎、気管支ぜんそく、花粉症などが急増したんです。これを発表当時はもちろん珍論、奇論扱い。でも最近は『聞いてやろう』というムードになってきました」
研究室には寄生虫のホルマリン漬けや標本が並んでいる。藤田教授が手にするのはサナダムシの標本。名前はヒロミちゃん。藤田教授が一時、体内に取り込んでいたものだ。
「サナダムシは人間の腸管に寄生しますが、食べ物を横取りされるくらいで悪さはしない。西洋ではダイエットに使っているほど。おなかが冷えたら腹巻きをし、よしよしといってやったくらいですよ」
その昔、日本人の多くは回虫を持っていた。回虫は太古の昔から人間と共生してきたのだ。藤原京の便所がどこかを探るには、回虫の卵の化石を探せばよかった。日本では「虫」という言葉をよく使う。「虫が知らせる」「虫の居所が悪い」…。藤田教授は「自分の体内に別格のものが住んでいるということを知っていたからでしょうね」と言う。
太古からの共生
排せつ物を有機肥料として使っていたことなどに由来するが、終戦直後の日本人の感染率は70%を超えていた。ところが、日本に進駐してきた米国人が生野菜を食べ、回虫感染を出した。「何と不潔な国か」となって国は法律で回虫駆除を決め、集団検便・駆除が徹底された.その結果、感染率は60年代に10%を切り、70年代に2%台、80年には0・2%まで下がった。
減少が決定的になった60年代に、逆に急増してきたのがアレルギー疾患だった。東京都花粉症対策検討委員会によれば、最近では都内でスギ花粉症にかかっている人が5人に1人という。このスギ花粉症は東京医科歯科大の斎藤洋三博士が、63年に栃木県日光市の男性症例を報告したのが初めて。藤田教授は「日光の杉並木が植えられたのは17世紀前半のこと。なぜ、昔の日本人は花粉症にならなかったのか」と問う。
実は、藤田教授がこの研究生活に入ったのは、68年にインドネシア・カリマンタン(ボルネオ島)に滞在したときの見聞からだ。「現地住民のほとんどが回虫感染してましたが、皮膚はつやつやでアレルギー症状の人はいなかった。これは何かある」と。
日本に帰った72年から研究に没頭。その年、回虫とアレルギーの関係について初発表した。77年には、回虫のアレルギー抑制物質を解明した。
「回虫の排せつ物中の『分子量2万の物質(ESC)』がアレルギーを抑制していることが分かった」と藤田教授。回虫には大変な力が秘められているというのだ。
が、学会で発表してもだれも相手にしてくれない。「学会で私の姿を見ると、みなさっと逃げ散りましたよ」と当時を語る。花粉症やアトピー性皮膚炎は当時、排ガスなどの公害や食品添加物のせいといわれてきた。ところが、公害が減少し、食品添加物も厳しく規制されるようになったのに、アレルギー患者は増え続けている。
京大霊長類研究所もニホンザルの花粉症がここ20年間全く増加していない事実に注目、寄生虫感染が抑制したものと結論付けた。しかし、それでも世の中には受け入れられなかった。
「そんなに分かってくれないなら、よし、キレてやろう」。藤田教授は5年前、自説を学会ではなく、一般市民に説いてみようと路線を変更した。そして本を書き始めた。「笑うカイチュウ」「空飛ぶ寄生虫」(いずれも講談社刊)「体にいい寄生虫」(ワニブックス)など。奇抜なタイトルが受けた。回虫とアレルギーの関係が徐々に世に知られるようになった。
ドイツにも同説
何より藤田教授を勇気づけたのが、最近のドイツの研究発表だ。旧西ドイツ人と旧東ドイツ人を比べると、花粉症罹患(りかん)率は西の方が約3倍も高い。公害対策や住環境では西の方が勝っているのに、なぜか。ハンブルク大が旧東西両国の寄生虫検査をしたところ、東の方が高率と分かった。研究は寄生虫の増減に関係していると結論した。藤田教授は「ドイツの研究が発表されて、やっと話を聞いてやろうというムードになった」と言う。
では、アレルギーを根治するには――。
「回虫と共生するのが一番。しかし、そんなことを今の母親らに言えっこない。それに、悪さをする回虫もいる。だから、回虫から抑制物質を取り出せばいい」と藤田教授。
回虫の排せつ物にはアレルギーを起こす細胞を占拠し、花粉やダニに反応しない物質が含まれている。この抑制物質の抽出には既に成功している。治療に用いれば効果が十分なことも分かっている。
ただ、藤田教授によれば、免疫反応が強過ぎ、がんになりやすい体にしてしまうという副作用があるという。生きた回虫ならアレルギーを抑え、がんにも拮抗(きっこう)させる機能を持ち、それがバランスよく働いているのだけれど。
「まさに神秘です。このバランスを保たせるための研究は大学院生4人と取り組んでいます。研究は順調に進んでいます」。実用化の暁、世の母親の悩みも春先の鼻のグシユグシユもなくなるか。 (村串栄一)
ふじた・こういちろう
1959年、三重県立宇治山田高校卒業。65年、東京医科歯科大医学部卒業。70年に東大大学院医学系研究科を修了、東大医学部助手に。順天堂大、金沢医科大、長崎大を経て、87年から東京医科歯科大医学部教授に。日米医学協力研究会主任研究員や日本寄生虫学会幹事などを務めている。
小さな草に
大石芳野(写真家)
絹の輝き
街を行き交う人のなかに、着物姿がめっきり少なくなった。
その分、アジアから来日した女性たちの民族衣装には、目を奪われることがある。都内で開かれたアジアのある交流会に参加すると、様々な衣装がゆったりと会場を行き交っていた。
韓国人のチマ・チョゴリ、ベトナム人のアオザイ、カンボジア人のサンポット、インド人のサリー、フィリピン人の……、タイ人の……と、民族色豊かだった。素材は絹が多く、会場には華やいだ雰囲気が漂っていた。暖かくなったとはいえ、南国の衣装にはまだまだ肌寒そうだ。
絹と一口にいっても、民族によって生地の質も風合いもかなり違うようだ。着物は正座にも耐えうる強さと、「絹ずれの音」に代表されるしなやかさが相まっていることが欠かせない。
例えばサリーは、体に幾重にも巻くために生地は透き通るように薄い。また、アオザイは風にひらひらと羽ばたく蝶のように軽いものが適している。ロングスカート式のサンポットは、腰にフィットさせるためにかすり織りの張りが特徴だ。
どの女性にも、異国での厳しさに負けない生き生きとした表情がある。何ともいえない豊かな気分に浸りながら、私はかつて訪れた国や地域の風土を目の前の女性たちに重ねていた。
大きな黒い瞳のカンボジアの女性が、私の洋装を見てにこやかに話しかけてきた。
「これはクメール(カンボジア)の絹ね」
そう、サンポットにする絹かすりで、私は上着を作った。クメールの伝統的な柄が光に映えて、我ながらうっとりとする色調の一着だ。もっとも、カンボジアの太陽のもとだとさらに輝きを増して、それはそれは美しい。
同じ太陽とは思えないほどの光線が、カンボジアには確かにある。
その光の中では、アンコールワットなどのレリーフ模様に見られる伝統的な花や鳥、虫といった柄が、生地の中から飛び出してくるように見える。赤、黄、青、緑、紫……鮮やかな糸と糸を組み合わせる。が、決して派手ではない。少し離れて眺めると、私にはむしろ、寂しさや悲しさが感じられる。
ポル・ポト時代が終わった1980年7月、私はプノンペンに降り立った。そこで目にした凄(すさ)まじい状況に私は強い衝撃を受けた。その1つが色だった。
青い空や緑の樹木以外、町も村も色が消えうせた世界のようだった。痩(や)せこけて闇を見つめているような人びとの表情が、ポル・ポト時代のジェノサイド(大量虐殺)政策の恐怖を物語っていた。さらに人びとの衣装は大半が黒一色だった(解放後にタイから持ち込まれたわずかな生地には色や柄が見られた)。
翌年、再び訪れた私の耳に機織りの音が響いてきた。急いで農家の庭先に入ると、痩せた女性が手作りの簡素な織り機を懸命に動かしていた。
「4年間の地獄は生きて帰れるとも、再び機織りができるとも思いませんでした。恐怖のあまり、織り方を忘れてしまい、女たちが頭を寄せ合って、やっと思い出して……」
機に掛かった織りかけの生地は、元来のクメールの色調にはほど遠かった。それでもカメラのファインダーには、途絶えた技術を少しでも取り戻そうとする真剣な姿が見えた。生きることの本当の意味を教えられたような気がして、胸が熱くなったものだった。
それ以来、軒先を覗(のぞ)いては手織りの絹地を丹念に見て歩いた。単に機織りだけではなく、人びとの表情や健康、生活や文化など随所に復興し、自立していく様子が感じられた。
原色に近い鮮やかさを組み合わせていながらも哀愁を誘うのは、歴史に翻弄(ほんろう)された人びとの姿が重なるからだろうか。それだけに、絹地の輝きを再び手中にした女性たちの深い喜びが、ひしひしと伝わってくる。

(カンボジア 1981年)
小さな草に
新緑が眩しくなるにつれて、都会の路地でもしばしば野鳥の姿を見かけるようになる。ある日、チーチーという可愛らしい響きに、私は心を躍らせながら立ち止まった。
ひょっと後ろを見ると、少し離れた所に15歳くらいの2人の女学生が、やはり足を止めて耳を澄ましていた。微笑みを返してくれた少女たちの黒い瞳には、真摯(しんし)な心が投影されているように感じられた。
別れ際に、一方の少女が青春の深みにはまっているように感じられて妙に印象に残った。そして遥(はる)か彼方(かなた)になった私の、小枝に出た若芽のような時期を思し出した。その年代の多くが通過する人生の悩みに突入して、私は身動きができなくなっていたのだった。
生とは? 死とは? 実とは? 虚とは? 自分とは?・・・などの疑問や不安が溜まりに溜まって、ひどい鬱(うつ)の状態だった。
生暖かい日のこと、見上げた薄青い空を数羽の小鳥が横切った。ゆっくりと足もとを見ると、まだ砂利だった路地の隅に草の緑が、まさに萌(も)えようとしている。珍しくもないごく日常的なこの光景が、この時、ふと違って思えた。
柔らかい薄緑色の葉が精いっぱい伸びようとしている。その姿に、圧倒されながら「ああ、生きているんだ……」と、心の中で叫んだ。病んだ気分の私には、この小さな生命力が渇き切った根に滴る水に感じられた。
長い眠りから覚めた時のように、まだもうろうとした状態はしばらく続いていた。それでもこの時に、小さな草から生きる意志の強さを教えられたような気がした。
もしあの時、あの名もない草に出会わなかったら、私の人生はきっと別な方へ向かっていただろう。
それから7年ほどして、私は写真家の卵として社会人になった。あの砂利の道も、経済の成長による恩恵を受けてアスファルトに舗装された。
男女が平等に付き合っていた学生時代とは異なり、社会での男性からの言葉は陰に陽に刺すように私に向けられた。例えば、こんなである。
「お茶を飲むなら女性、仕事は男性と」
「仕事の失敗は女性の方が多い」
「女性に仕事を出すからには見返りを」
キャリアウーマンという言葉もまだ定着していない時代で、ましてや写真の分野に女性は少ない。
「カメラは重いから、早くお嫁に行った方がいい」
何回こう言われたことだろうか。写真で身を立てたいと必死になっている私にとっては、実に情けなかった。小さな草に「早く年をとりたい」と、愚痴をいったものだ。
ところが20歳代の後半になった時、仕事の相手からこんなパンチが飛んできた。
「まだ若いから仕事があるが、30歳過ぎたババアじゃできないだろう」
まだまだある。
「撮るのは男性。撮られるのは女性。女性のあなたが、何を撮るの?」
よく耳にしたが、初めのうちはその意味が分からなかった。そんなある日、今は亡き先輩の写真家がおもむろに、こう付け加えた。
「女性が撮るんだから、スカートをひらひらさせて。そう、女風呂でも撮ったらどう? 男じゃ撮りにくいからね」
今となってみると、男性たちの言動は若い私を心配してのことかとも思えるが、そう思えるには歳月とキャリアがいる。その間、どれほど悔しかったり、情けなかったり、ウンザリしたことか。
それでもどうにかここまで来られたのは、私を支えてくれた小さな草があったからだともいえる。その姿と重なるような人びととの出会いに、私はどんなにか励まされただろうか。こうした付き合いのなかで撮った人びとの写真はどれも、私の大切な財産となっている。

(東京)
大石芳野(おおいし・よしの) 東京生まれ。写真家。
主な著書に『沖縄に活きる』(用美社)『夜と霧をこえて』(NHK出版)『カンボジア苦界転生』(講談社)『HIROSHIMA 半世紀の肖像』(角川書店)など。93年度芸術選奨(文部大臣新人賞) ほか。

(沖縄)
(注) この2編のエッセイは、大石芳野著『小さな草に』(朝日新聞社)に掲載されたものです。このホームページに全文を転載することについては、著者のご了解をいただいています。
人生の三点セット
作家 森村誠一
私の生きている証し−『悪魔の飽食』
『悪魔の飽食』は731(ななさんいち)部隊という日本陸軍の細菌戦部隊の実態を究明した作品です。731部隊は、簡単に申しますと、太平洋戦争、特に日中戦争の頃、昔の満洲、今の中国東北地方ハルピン郊外にその本部がありました。当時の日本はソ連の南下を非常に恐れていたのです。
当時日本はソ連の南下阻止のために何か決定的な兵器、核兵器のような強力な兵器が欲しかったのでしょう、そういう兵器の開発を急いでいました。その時に731部隊の創設者である石井中将が、細菌(ウイルス)を兵器に使えないかという着想を持ったのです。
特にウイルスで最も伝染力の強力なペスト菌、コレラ菌を兵器に転用しようとおもい立ち、そのための研究開発部隊をハルピン郊外に設けました。ウイルスを兵器にするためには、人体実験をせざるを得ない。その人体実験の材料として、凡そ3千人ほどの中国人を主体とした人間を実験材料に使ったのです。
731部隊は、ドイツのアウシュビッツの虐殺に比肩されるほどの残酷性を持っていますが、アウシュビッツの残酷性と違う点は、アウシュビッツは職業軍人によって遂行された。けれど731部隊の場合は大体民間人が従事したということです。
731部隊の残酷性はどういう所にあるかというと、人間を伝染病ビールスの実験材料として、それを殆んど無駄のない実験材料として使った点にあります。まず健康な人間実験材料をA丸太と呼びます。人体実験に使った人間を丸太と呼んだのですが、このA丸太に対して、伝染病の実験を行なって、伝染病が発症した丸太をB丸太に落とす。B丸太を今度は凍傷の実験に使ったんです。
当時満洲の日本軍の将校が1番悩んでいたのが凍傷でした。B丸太に水を掛けて、零下何10度という屋外に立たせて、どういう状況で凍傷が発生するかという実験をしたのです。手足が欠け、鼻が欠けというように、人間だるまみたいになっていくわけです。損傷した丸太はCに落とし、C丸太に対しては、今度は毒ガスの実験をしたのですから、本当に人間を全く無駄なく実験に利用したということです。
この731部隊に携さわった優秀な医者は全国から募ったのです。医者が医学に於いて成功するためには、人体実験は見果てぬ夢であるわけです。動物実験から類推したのでは、どうしても直接的なデーターが得られない。ところが731部隊に来れば、人体実験が自由にできるというので、日本国内の優秀な医者、薬学者、化学者がスカウトされて、満洲に於いて、いろいろな実験を行なったのです。
これが戦後、国民の目から秘匿(ひとく)されたのは、731部隊のデーターをアメリカが独占したかった。731部隊の関係者を戦犯として訴追した場合は、当然ソ連側に知られてしまう。ソ連側に知らせずに、アメリカだけが独占するために731部隊の幹部と取引をして、その部隊が開発したノウハウを、総てアメリカに提供する。そのかわり731の隊員は戦争犯罪人として訴追しないという特約が取り交わされました。そのために終戦後も長い間、この731部隊の秘密が保たれていたという事情があります。
『悪魔の飽食』は、1度は絶版の憂き目にあったり、また、これを執筆した私や、私の家族まで、目に見えぬ相手から、理不尽な迫害を受けたりもしました。
目に見えるものとしては、1978年の日米ガイドラインあたりから、国家秘密法をめぐる動きが出てきたわけですが、私たちのような作家、あるいはジャーナリストにとって、このような法案は、言論・表現の自由を侵す点で絶対許せないものです。私は自分の作品にかけられる制限は、いかがわしい作品は書かないという自ら課した自制だけだと考えています。いかなる国家的制限も拒否します。
作家の場合、抑圧は直接かけられてくることになるから、危機感も強いわけです。
私が自由に作品を書きつづけることと、私が私の人生をかけて、自由と民主主義を守りつづけることは、私の生きている証しなのです。
人生の三点セット
(一)
私はエッセイを読むのも書くのも好きである。適切な例えではないかもしれないが、小説が尾頭付きの料理であるとするなら、エッセイは単品の食物のような気がする。大長篇小説が豪勢な懐石料理やフルコースであるなら、短篇小説はア・ラ・カルトである。料理の素材だけではなく食器や盛りつけ、飾りつけ、食堂なども吟味を重ねる。エッセイの身上は素材だけである。素材以外の要素で味を引き上げようとはしない。
それだけに美味(うま)いものは美味い、不味(まず)いものは不味いと受取手に味がはっきりとわかる。喉が渇いたときに差し出された冷たい一杯の水。空腹時に振る舞われた握り飯。尾頭や飾りつけも付いていなければ、食器も吟味されていない。飲食する環境にも一切工夫はない。
それでいながら一流レストランや、料亭で食べる料理に決して負けない味を持っている。
私はエッセイとはそのように認識している。
そもそもエッセイの虜(とりこ)なったのは若いころ読んだエリア・エッセイやシャルドンヌの随想集、『アミエルの日記』、串田孫一の山岳エッセイがきっかけである。私は、何の装飾もないが、四季折々生活と共にある作者の精神の素顔から小説とは異なる魅力を覚えた。
小説には作者の断片や反映はあっても、作者そのものではない。文は人なりと言うが、小説は必ずしも作者ではない。小説特有の粉飾やデフォルメが加えられる。性格凶悪にして精神邪(よこしま)なる人間が万人を感動させる小説を書くこともできる。それが小説の技巧であり、また小説の身上でもある。エッセイに技巧や粉飾がまったくないこともないが、小説のように技巧やテクニックを宿命としていない。小説は作者の人生、と言うよりは人生観を投影するが、エッセイは生活の反映であると言ってよい。
私小説の場合、作者の生活そのものである場合もあるが、小説が小説たる所以(ゆえん)の虚構性は少ない。エッセイに多少の粉飾を加えることはあっても、最初からエッセイに虚構性を盛り込もうとはおもわない。虚構のエッセイであれば、小説を読むほうがましである。
(二)
本書に収録した「老いのエチュード」は、60の大台に乗ったころからそろそろ意識していたことであった。老いの終点に死の終止符が待っていることは理屈ではわかっているつもりでも、まだ実感がない。いつ死ぬか、いつ死ぬか、考えていては人間をやっていられなくなる。
老いるということは、老いるに値する人生を生きることである。
個人の人生の価値を誰が判定するか。社会的な判定もあれば個人の価値判断もある。その両者が必ずしも一致するとは限らない。他人の目には、なんとまあつまらない一生だと見えても、本人は結構満足していることもある。「いいじゃないの、幸せならば」である。
また波瀾万丈、大いに社会に貢献した人でも、自分の人生を不満におもっている人もいるだろう。老いるということの意味を自分なりに模索し、人生の生き方が人の数だけ異なっても、結局は同じ行き先に収束されていく老いの行方を見つめようとした。そんなものを見つめたくない人もいるだろうが、見つめれば霞む遠方の星のように(近視の場合)視野の中に確実にある。視野の中にありながら見えないほうが幸せかもしれないが、それは知らぬが仏の幸せである。
知らぬが仏、知ればもっと仏というような老いを狙って書いてみた。
私にとって読書は、生きるに値する人生を生きるための不可欠な要素である。『老いのエチュード』を支える生き方は、そのまま私の読書遍歴でもある。
(三)
第三部「作家のスタンス」は主として憲法問題を中心とした私の政治観が濃く現れている。戦時中の思想統一と言論弾圧を経験しているだけに、戦争と平和の問題には非常に敏感である。言論と思想の自由を保障する民主主義は平和を前提にして成り立つ政治形態である。戦争状態になれば、民主主義社会においても言論や表現の由由は制限を加えられる。作家は民主主義を蝕む敵に対して、どんなに警戒しても警戒しすぎるということはない。体制(政府)がどんなによい政治を行なっていても、作家は政治的に反体制でなければならない。ジャーナリストや言論に携わる者は常に体制を監視する側に回っていて丁度よいのである。第三部「作家のスタンス」を併せて、このエッセイ集は私の人生即ち生き方の三点セットと言える。
(注)、 このエッセイは、森村誠一著『老いのエチュード』(1995年、角川春樹事務所発行)に掲載されたもので、「人生の三点セット」は、そのあとがきです。このホームページに転載することについては、著者のご了解をいただいています。
著者略歴
森村誠一(もりむら・せいいち)1933年,埼玉県熊谷市に生まれる。青山学院大学英米文学科卒業。10余年のホテルマン生活の後、1969年「高層の死角」で江戸川乱歩賞を受賞して以来、本格推理作家として活躍、「空洞の怨恨」で小説現代ゴールデン読者賞、「人間の証明」で角川小説大賞を受賞。一方で、関東軍満洲731部隊(石井細菌部隊)の実体を究明した『悪魔の飽食』は大反響を呼んだ。『忠臣蔵』他の力作歴史小説も多い。
「著作権侵害は中国の恥」訴えたら
〔北京の裁判所〕森村誠一さん勝訴の判決
海賊版天国「返上の証明」
「印税」67万円、戦後補償支援に
(注)、これは、1998年4月26日、朝日新聞(朝刊)に掲載されたものです。森村氏のエッセイの内容とも関連がありますので、添付しました。
中国語で「センツンチャンイー」といえば、推理小説作家の森村誠一さん(65)のこと。中国国内で翻訳、出版された小説は数10冊、計1千万部以上に及ぶといわれる。大半が著作権を無視した海賊版だ。ところが、中国人の戦後補償要求訴訟を支援している森村さんが「お互いに筋を通すべきではないか」と中国の出版社を相手取って北京で裁判を起こしたところ、このほど「出版社は4万元(約67万円)払え」という判決が出た。中国当局が「海賊版天国」の悪評を返上しようとするサインなのではないか、と関係者の驚きを誘っている。

「中国では私の本が無断で大量に出版されているんですが、私は何ももらったことがないんです」
森村さんが3年前、宴席でもらした言葉がきっかけだった。森村さんは、日中戦争時代の中国人慰安婦や虐殺の被害者たちが起こした裁判を支援する会の代表を務める。同席していた弁護士らが本気になった。
「我々は、日本政府に対して筋を通すべきだと主張している。だったら中国に対しても遠慮するのはおかしい。正すべき点はお互いに正さないと」
渡辺春己弁護士を通じて中国の弁護士に委任。調べただけでも、数社にまたがって61冊も翻訳出版されていた。
「悪魔の飽食」→「食人魔窟」。「日本アルプス殺人事件」→「情債血案」。「青春の反旗」→「私生子」。
こんな具合に題名を変え、数社が発行していた。森村さんは、大手の「群衆出版社」を相手取り、8冊について著作権侵害で約50万元(約804万円)の賠償金を求めた。
中国が長い間「著作権後進国」と言われたのは、国際著作権条約が浸透していないことと関係があった。しかし、1992年、外国の作品は許可なしでは使用できないとする国際条約を批准し、国内規定を整備したため、これとの兼ね合いが争点になった。
判決は昨年末に出て確定した。森村さん側の主張をほぼ認める内容だった。
「国際条約加入前に出版した本であっても、いまだに売り続ければ、著作権侵害といえる」
「2冊分は森村氏側が出版を許可した形跡があるが、その際の条件だった本の寄贈や、一部の印税を払うなどの約束を守っていないため違約責任が生じる」というものだった。森村さんは「金が欲しいわけではなかった。本当は裁判ざたにする話でもないと思ったのですが……」と控えめながら、判決が画期的な先例になるのではないか、と話す。「中国だから海賊版の横行も仕方ないと思われたら、中国にとっても国家的な恥でしょう。中国が経済、軍事大国だけでなく、文化大国も目指していることが感じ取れます」
このほど、ようやく4万元が払い込まれた。森村さんは、中国人の戦後補償裁判を支援するために、全額を寄付するという。
『森村誠一公式サイト』へ行く
松 山 幸 雄
(共立女子大学教授・元朝日新聞論説主幹)
(一)
欧米人のスピーチのさいのサービス精神と周到な準備とには、いつも感心させられる。かつて日本滞在中の講演で、チャールズ英皇太子は福沢諭吉に言及し、フォード米大統領は佐久間象山、キッシンジャー国務長官は貝原益軒の言葉を、それぞれ引用した。
昨年6月、天皇・皇后両陛下が訪米されたさい、クリントン大統領は歓迎のあいさつの中に幕末の歌人、橘曙覧(たちばなあけみ)の和歌を入れた。「たのしみは朝起きいでて昨日まで 無かりし花の咲けるを見るとき」――私にはまるで、ひたすら「豊かさ」を求めて突っ走って来た日本人に対して、アメリカ人から、「立派な先人のように、もう少し『心のゆとり』を持ったらどうですか」と忠告されたような気がした。
実はこの歌には、私は特別な個人的思い出がある。太平洋戦争の初期、東京の下町の中学校に入学した私は、先輩から、橘曙覧という歌人に「たのしみは……」という分かりやすく、心温まる和歌がたくさんあることを教わった。
「たのしみは稀に魚煮て児等皆が うましうましと言ひて食ふとき」(江戸時代、人びとがいかに貧しかったかがわかる)「たのしみはそぞろ読みゆく書(ふみ)の中に われとひとしき人をみしとき」――
われわれも彼を手本にして「学生生活『たのしみは』」という歌集をこしらえようということになり、私は「たのしみは登校の途中街角で 親しき友と出会ひたるとき」という1首を提出した。(50余年前の駄作をいまだにそらんじているのは、それ以後和歌といぅものを、1度も詠んでいないからである)
それはともかく、このときの「どんなにつらくとも、忙しくとも、日常生活の中に何か楽しみを見出すゆとりを持たねばいけない」という教訓は、たいへん印象的だった。
だが、戦争が激しくなるとともに、ゆとりをもつどころでなくなった。軍人勅諭の暗記、分列行進、防空演習、神社仏閣での必勝祈願……だれもが、目の吊り上がった、余裕のない、面白みに欠けた人間になるよう「刻苦勉励」したものだ。
軍人のゆとりのなさを心配した作家の吉川英治さんが、陸軍幼年学校で講演し、「弓の弦は張りっぱなしにしておくと、いざという時、バネがきかなくなる。使わないときには外しておかねばならぬ」と戒めた、との話が残っている。竹のように、空白の部分をこしらえ、節々をきちんとする方が、雪にも風にも強いものだが、日本では「努力する」ということが、のべつ幕なし、陰ひなたなくやる、ということになりがちである。「ゆとり」が「さぼり」ととられてしまうからだ。
太平洋戦争当時、アメリカ側の名提督といわれたスプルーアンス大将は、日本軍との遭遇近し、という段階になっても、いつも通りの食事、睡眠のペースを守っていたという。「大事な瞬間に全軍の安危を左右する判断を下さねばならぬ指揮官は、十分な休養をとって頭脳をすっきりさせておかねばならない」という理由で。
これに対して日本側の司令官や艦長には、不眠不休、あるいは艦橋に簡易ベッドを持ち込んで常時臨戦態勢をとる、というタイプが少なくなかった、という。この伝統は戦後も引き継がれている。残業、休日出勤……身体の不調を我慢して仕事に打ち込み、難病が発見された時にはもう手遅れ、といったサラリーマンの“美談”を、これまでどれだけ耳にしたことか。
(二)
10数年前、朝日新聞の教育雑誌『のびのび』が(教育ママたちに人気がなく)廃刊になったさい、日本語の名手であるイギリス人のロナルド・ドア教授がわれわれをひやかした。「朝日は『のびのび』の代わりに、今度は『がりがり』という雑誌を出すんですか?」
中学1年生の“がりがり派”の男の子が「下宿したい」「下宿してどうするの?」「何もせず、ボンヤリひっくりかえって何日か過ごしてみたい」――テレビの人生相談でたまたま耳にした会話である。この子は、「人間は今日も働いて食べた、明日も働いて食べた、そうやって自分の一生を毎年毎年働いて食べ続けるだけだったら、そこに何か立派なことがあると言えるでしょうか?」(ゴーリキー『母』)といった心境になったのだろう。
東大法学部を出て国家公務員試験行政職に1番で合格した大蔵省のエリート官僚が、突然原因不明の自殺をし、まわりのものを驚かせた。
この両者は明らかにどこかでつながっている。受験戦争、出世競争、と続く狭いエスカレーターに乗るには、“ゆとり”とか“余裕”は不必要、というより、邪魔になりかねない。彼らには橘曙覧の和歌、あるいは「人生は短い。わずかな時間しか生きられないから、というよりも、人生を楽しむ時間をほとんど持たないからだ」(ルソー『エミール』)といったことを教えてくれる先輩が、いなかったに違いない。「忙」といぅ字が「心を亡ぼす」と書くのは意味深長である。
「自殺の通産、離婚の大蔵」という話を他省の役人から聞いた。オーバーな言い方だと思うが、エリートほど私生活を犠牲にして働く傾向が、高度成長期に強まったのは否定できない。外務省幹部の子供が外交官試験にパスし、外国の研修を終わって本省に配属されたら、毎晩帰宅が午前さま。母親があきれてご主人に「あなたはいったい、どういう労務管理をしているのですか」となじったら「ボクの若いころは、そんなに仕事をしなかったなあ」
30余年前、私がワシントン特派員になった時には、国務省の昼の記者会見のあと、すぐそばのゴルフ場へみんなで出掛け、2時間で9ホール回ってくることがよくあった。時には日本大使館の幹部とウィ−クデーの午前中ラウンドし、昼過ぎにオフィスに出勤、ということもやったものだ。このごろは、特派員も外交官も、ウィークデーの昼間ゴルフをやるなんていう余裕は全くないらしい。
国連などを見ていると、トップは別として、一般の職員の勤務ぶりはまことに悠々としたもの。「国連にはどのくらいの人が働いているのですか(つまり職員は何人ぐらいいるのか)?」と質問したら「まあ、働いているのは、半分ぐらいでしょう」との答えが返ってきた――というジョークをきいたこともある。
「日本人は働き蜂のようだ」とよくいわれるが、専門家によると、蜂は結構息抜きをし、実際に働いているのは、1日約6時間。蜂の方で「日本人といっしょにされてはかなわない」と迷惑がっているかもしれない。
(三)
欧米人は休暇の取り方も、「カリブ海で4週間」とスケールが大きい。日本人が折角有給休暇の権利がありながら、不時の病気用に残しておく、あるいは自分が休んだら他の人に迷惑をかけるからと棄権する、のとだいぶ違ぅ。
機内映画で『男はつらいよ』を見て以来、フーテンの寅さんのファンになったウィーンの市長さんは、寅さん一行のロケをウィーンによんだほどの親日家。その彼の曰く「日本の観光客のウィーン滞在は平均約2日、アメリカ人は1週間。でも、落とすお金は同じくらい」――彼は日本人とアメリカ人のどちらを、“大国民”と感じているのだろう。
イタリア観光旅行中、通訳兼ガイドさんに「日本人ハ金持チダケド、時間ハ貧乏デスネ」と皮肉られた。変な日本語だけれど、意味は分かる。彼の目には、日本人はベルトコンベヤーに乗せられた家畜か、部品のように見えるのではないか。
イタリア語を勉強している人の話によると、会話のテキストに「今日は、汽車が正確な時間に発車しました」「それはすばらしいですね」とか「いま汽車は予定より遅れているけれど、フランス領に入ったら、遅れを取り戻すでしょう」といった文章があるという。「几帳面」は必ずしも美徳とされていないようだ。
ブラジル旅行中、約束の時間にちょっと遅れた。会うなり謝ったが、相手は別に苛立っている様子もない。「おおらかで、いいですね」と日本商社の駐在員に言ったら、「この逆を毎日やられているこっちの身になって下さいよ」とこぼされた。
最近、米国防次官補からハーバード大に戻り、ケネディ・スクール(政治行政大学院)の学長になったジョセフ・ナイ氏は、「日米安全保障条約は、冷戦後もアジアの安定に必要不可欠だ」との「ナイ報告」を書いたことで、日本でもよく知られている。しかし、この国際関係論の大家が、趣味として堆理小説を書くことを知っている人は、少ないと思う。
ハーバードの教授が3、4人集まったとき、彼の“余技”が話題となった。「どうも、奥さんに『女がうまく書けていない』とけなされたんで、出版はとりやめるらしいよ」「濡れ場はともかく、国際陰謀のプロットの方は、読んでみたかったね」――日本の学者の間なら、にがにがしげな、あるいは揶揄(やゆ)的な口調になりかねないところだが、まことに好意的なやりとりだったのが、記憶に残っている。
小説といえば、根本長兵衛・共立女子大教授(元朝日新聞パリ支局長)によると、ジスカールデスタン元フランス大統領は、財政経済の大秀才なのに、同時にモーパッサンの研究家でもあり、自らも恋愛小説を書いたそうだ。詩に関する著作のあるポンピドー元大統領は、記者会見でしばしば古典小説の文章を引用して、政治外交のコメントをしていたという。
(一部の例外的人物を除くと)日本のエリートには、“ふくらみ”のない「まじめ人間」が多い。もちろん「まじめ」自体は悪い事ではないが、「まじめ」という形容詞が、「まじめ」「きまじめ」「くそまじめ」といった変化をしがちなところが問題。本業を離れると語るべきものなし、ということがいかに悲劇かに、ご本人が気付かないのが、大悲劇なのである。
菅原真理子埼玉県副知事(前総理府男女共同参画室長)は「これからの日本人は“金持ち”より“文化持ち”に」と主張しているが、人生の前半で「受験戦士」「企業戦士」としてゆとりのない生活をしてしまうと、あとがたいへん。やっと“日本代表”になれても、教養の幅も奥行きもないから、国際社会に出ていった場合、押されっぱなしになってしまう。私自身、湿地帯に高層ビルを建てるのは不可能、ということを、身をもって痛切に感じてきた。
日本社会の随所にみられる教条主義、シャクシ定規も、「反ゆとり主義」の産物だ。舞の海が新弟子検査を受けたさい、ほんの何センチか身長が足りないので頭にシリコンを埋めこんで合格、あとからシリコンをとったという。これではいくら何でも身体に悪いということで、最近は、学生相撲である程度実績をあげているものは、身長や体重が合格基準に達しなくともパスさせることにしたそうだ。
夏休みの始め、3年ぶりにアメリカから帰国した小学生が、秋から近所の小学校に復帰するつもりで、8月に校庭のプールに泳ぎに行ったら、9月の入学手続きが済むまでは泳いではいけない、と断られた、との話をきいた。「たのしみは前例規則を振り回し 他人(ひと)が困るを冷ややかに見るとき」といった人間にはなりたくないものである。
新聞社にいたとき、コラムで「チョピンとはオレのことかとショパン言い」という川柳を引用したら、大学生から「それは『ギョエテとはオレのことかとゲーテ言い』が正しい」という投書が来た。どちらも川柳にあるのだが、自分の知っている通りでないと「間違い」と思うのだから始末が悪い。
「犬が吠えてもラクダの隊商は進む」というアラブの諺を記事で紹介したら「私は長年アラブ文化を研究しているが、そんな諺は読んだことがない」との投書が大学の先生から来た。私は別にアラブの専門家ではないが、ニューヨーク特派員当時、国連在勤20余年というサウジアラビアの名物大使が、米ソ両超大国の横暴を非難する演説で、この諺を何回も使うのを聞いている。日本の学者は、自分が文字で読んだもの以外は信用しないのかとびっくりした。自分(のグループ)の信ずることだけが絶対的に正しい、と思い込む人には“まじめ人間”が多いようだ。私は極左や極右のグループ、あるいは狂信的な宗教関係者に親しい知人がいないのでよくわからないが、恐らく彼らには「人間は不完全なもの」という大前提に立って人生の哀歓を軽妙洒脱に語る森繁久弥や柳家小さんのファン、あるいはお互いにへマばかりやりながら笑いとともに暮らす「サザエさん」の愛好家は、少ないのではないか。
(四)
私は、きまじめな日本人は、よい意味でチャランポランを心掛けるぐらいの方がよいことがある、と感じている。このごろは、ひょっとすると「いい加減」とは「よい加減」のことなのかもしれない、と思うことさえ、ときどきある。とくに長いこと内外の政治問題を観察して来たので、声高に「絶対に」というような力み方をすることの無意味さが、よく分かるようになった。
例えば、国会が全会一致で採択した「お米は外国から1粒たりとも入れない」という決議が、いかにはかないものであったか。社会党の「消費税絶対反対」「小選挙区制断固反対」が、いかに空しいものであったか。
ベトナム戦争の時の米国防長官だったマクナマラ氏が、最近「ベトナム戦争は間違いだった」と告白し、問題になった。私はワシントン特派員時代に、彼の「アメリカはベトナムから絶対に撤退しない」「勝利は目前にある」との言葉を記事にしたこともあるので、昨今の「アメリカ・べトナム友好ムード」をみていると、「ドミノ理論」(ベトナムが共産化すれば、インドシナ全土が赤化する危険がある、との説)を信じて異郷で戦い、死んでいった青年があわれでならない。
少し暗い話が続いたが、丸くて、小粒で、ひと粒では役に立たない「仁丹」型秀才ばかり目立つ日本でも、このところ(高度成長がストップして以後)、徐々にではあるが、若い世代に、余裕のある、規格外れの、個性的な人材が出て来たように思われるのは心強い。今年夏の甲子園で健闘した智弁学園のチームの合言葉は「必笑」。まなじりを決して「必勝」を期す、というムードとは縁遠く、選手がお互いに仲間を笑いでリラックスさせることに努めていた。汗と涙(と時には鉄拳)の高校野球も、明らかに変化しつつある。
牛尾治朗経済同友会代表幹事は「昔はスパルタ方式で強くしようとする体育会型。野茂英雄や伊達公子は同好会型。個性的に自己規制して強くなってゆく」という。日本の国際化――つまり日本人、及びその集積である日本文化が先進諸国からagreeable(快い)、せめてacceptable(受け入れられる)とみられるようになるには、各分野でもっと「同好会型」のヒーローが出てくることが不可欠であろう。
「1994年度新卒就職戦線ガイド」(朝日新聞)の「トップが語る、こんな人がほしい」を読んで、快い驚きを味わった。小学校から進学塾に通い、中学、高校、大学へと進む過程で力を入れることと、一流企業の求める人物像とが、まるで食い違っているのである。
「学生時代に何かひとつ、個性を伸ばすことをしてほしい」(三菱商事)、「和を守るより多様性を」(富士銀行)、「自分の夢を持つ人」(JR東日本)、「やりたい事はっきり」(松坂屋)、「決まった仕事をこなすだけでなく、創造的な能力を」(東芝)、「指示待ち型ではダメ」(東京電力)、「自ら課題を作り出す能力」(川崎製鉄)、「鼻柱の強い若者を」(ユニチカ)……時代の急流ははっきりと「国際戦闘力のある人材――個性的な人物」を尊重する方向へ進んでいるように思われる。そして、ゆとりのない生活からは、強い個性は生まれにくい、ということ、さらに、ゆとりある人生の方が楽しい、ということも、だんだんと分かってきたようだ。
毎日新聞の小話投稿欄『みんな集合』に出ていた「すてき! 男たちと虹」には、思わず吹き出し、また考えさせられた。「虹が出て タイムとってる 草野球」という川柳を見て、敵も味方も大きな虹に見とれている光景が目に浮かび、なんてすてきな句だと思い、もう1度読み直してみたら「虹」でなく、「蛇」だったのでびっくりした――という話である。
私も「蛇」より「虹」である方が、はるかに味わい深い句になると思う。われわれの人生はどうせ草野球のようなもの。勝っても負けてもたかがしれている。あとで振り返って思い出されるのは、スコアなどよりも、仲間みんなでしばし壮大な虹に見とれていたことの方なのではないだろうか。
「暮しの手帖」59・冬
(注)、このエッセイは、96年版ベスト・エッセイ集(日本エッセイスト・クラブ編)に掲載されたものです。このホームページに全文を転載することについては、著者のご了解をいただいています。
以上
幸子のホームページに戻る