�{���V�F���B�L�̃e�����ƃW�F���W���X�L�[
�X�^�C���x���O
�@�i���j�A����́A�X�^�C���x���O���w�����Љ�v���}�P�X�P�V�`�P�X�Q�P�x(���ԎЁA�P�X�V�Q�N)����̉��L�k�ڎ��l�����̔����]�ڂł��B��łł����A�S�̂�ǂ݂������ɂ́A�}���ّ݂��o���̕��@������܂��B�{�����̖T�_�����������ɂ��܂����B�S�̂��������ƂQ�P�y�[�W�ɂȂ�܂��B
�@�k�ڎ��l
�@�@�@�Љ�E���(�{�n)�@�����Љ�v���}�ƃX�^�C���x���O�o��
�@�@�@���@(����)
�@�@�@��P�P���A�{���V�F���B�L�̃e�����@(�S��)
�@�@�@��P�Q���A�{���V�F���B�L�E�e�����������@(�S��)
�@�@�@��P�U���A�t�F���N�X�E�d�E�W�F���W���X�L�[�@(�S��)(�S�l�̎ʐ^�Y�t)
�@�@�@����A���c���Y����t�҂̂ӂ��̊磁@(����)
�@(�֘A�t�@�C��)�@�@�@�@�@�@�@�@����l�d�m�t�ɖ߂�
�@�@�@�u�ԐF�e�����v�^�Љ��`�ƃ��[�j�����E�����u�������v�̐��v�@(�{�n�쐬)
�@�@�@�u�X�g���C�L�v�J���҂̑�ʑߕ߁E�E�Q�ƃ��[�j����v�����^���A�ƍ٣�_�̋��\
�@�@�@�u�����v�_���ւ́w�ٔ��Ȃ��ˎE�x�w�ŃK�X�g�p�x�w�߂Ɓu�J�_�����v�_�̋���
�@�@�@����E�ґS���e�E�^�Љ��`�ƃ��[�j���̊v���ϗ���@�i�{�n�쐬�j
�@�@�@�u���\���F�g�v�m���l�̑�ʒǕ��w���x�ƃ��[�j���̓}�h���@(�{�n�쐬)
�@�@�@���H���R�S�[�m�t�w�e�����Ƃ������̃M���`���x�w���[�j���̔閧�E��x�̔���
�@�Љ�E���(�{�n)�@�����Љ�v���}�ƃX�^�C���x���O�o��
�@�����Љ�v���}
�@���̓}�́A����h�G�X�G���������G�X�G����Ƃ������܂��B�w���V�A�E�\�A��m�鎖�T�x(���}��)�̐��������p���܂��B�w�G�X�G���}�iSR�D�Љ��`�ҁE�v���Ɠ}�j�̍��E����͑�ꎟ���ɑ���ԓx�ɒ[���Ă���B�P�X�P�V�N�v���̉ߒ��œ}�嗬�͗Վ����{���x���A�y�n�D����肤�_���̎u���ƑΗ��������A�����ᔻ���鍶�h�̓{���V�F���B�L�̏\���v���Ɏx����^����ɂ�����A�}������菜�����ꂽ�B12���R������P�P���i���V�A��P�P���Q�O�`�Q�W���j���̐l�X�͍��h�G�X�G���}���}�����J�����B�i�^���\���̂悤�ȎҊ����̂ق��D�X�s���h�[�m���A�J���R�t��Ⴂ���オ���S�ƂȂ�A��s�A�o���g�C�͑��A�J�U���A�E�t�@�A�n���R�t�Ȃǂ����̋��_�ł������B�P�Q���Q�Q���i���V�A��P�Q���X���j�A�{���V�F���B�L�̋��߂ɉ����āA�R���K�[�G�t�i�_�Ɓj�A�X�^�C���x���O�T�EZ�ESteinberg�i�i�@�j�D�v���V�����i�X�ցE�d�M�j�炪�l���ψ���c�i���t�j�ɓ������B���̓}�͌��@�����c�̉��U�ɂ����ӂ�^�������A�P�W�N�R���h�C�c�Ƃ̃u���X�g�u�a��肪��l�߂��}����ƁA�}�̎嗬�͒��ہA�v���푈�_�̗�����Ƃ����B�u�a��y�̂̂��A�l���ψ���c�ɉ�����Ă����t�������g���A���삵���B�t���珉�Ăɂ����ĐH�Ɩ�肪�[�������A�{���V�F���B�L�������H�Ɠƍ٘H����ł��o���ƁA�J���҂�_���ɂ�����������̂Ƃ��ċ����������A�h�C�c�푈�̒��ł̘J�_�̈�̉��Ɋ��H�����߂āA�V���U���������N�������B�h�C�c��g���E�Q���A���h�̕������������ēd�M�ǂ�苒���A�A�s�[�����e���ɑœd�����B���̈��̕����f���͗�������̒������łԂ���A�J�Ò��̑�T��S���V�A�E�\���F�g����c�����R0�����߂����}���邱�̓}�͔@������A�w���҂͑ߕ߂��ꂽ�B���̍s���ɔᔻ�I�ł������l�X�́A�v���I���Y��`�ғ}�ƃi���[�h�j�L���Y��`�ғ}������A�̂��ɋ��Y�}�ɍ��������x(�o�D�Q�R�P)�B
�@�X�^�C���x���O�̌o��
�@�ނ́A���h�G�X�G���w���҂̈�l�Ƃ��āA�P�X�P�V�N�P�Q���X�����[�j���̘A���\���B�G�g�����Ɏi�@�l���ψ��Ƃ��ĎQ�������v���Ƃł��B�P�X�O�V�N�A���X�N����w�@�Ȃ̊w���ł��������A�@�G�X�G���}���Ƃ��đߕ߂���A�V�x���A�ւR�N�̗��Y�ɏ������܂������A�h�C�c�֖S�����ăn�C�f���x���O��w�Ŗ@�����w�т܂����B�̂��A�����āA���X�N���ŕٌ�m���J�Ƃ��邩�����A�@�����ɏ]�����܂����B��ꎟ���u����A�@�������s�̂��ǂōĂёߕ߂���܂������A�v����͍��h�G�X�G���h�ɑ����܂����B�A���\���B�G�g�����̎i�@�l���ψ��̃|�X�g�ɂ��A���U�l�̍��h�G�X�G���o�g�̐l���ψ��ƂƂ��ɁA�R�J���Ԋ������܂����B�P�X�P�W�N�R���A�A�������őS�����l���ψ�(�t��)�������܂����B�P�X�P�X�N�����A���X�N���ŁA�u���v�����}�v�w���҂Ƃ��āA�`�F�[�J�[�ɑߕ߂���A�T�J���ԓ������܂����B�Ȍ�P�X�Q�R�N�S���܂ŁA���{���V�F���B�L�n�������ɏ]�����ă`�F�[�J�[�ɍđߕ߂���܂����B�������A���N�E�����ăh�C�c�֓���܂����B�{���́A�P�X�T�T�N�A�����h���ŏo�ł���܂����B
�@�{���̍ő�̓���
�@�����́A���̓��e���A�A���\���B�G�g�����̎i�@�l���ψ�(�t��)�̗��ꂩ��́g�ɗ�ȓ��������_���h�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B����́A�A�����ԂR�J���ɂ����钼�ڂ̌���̌��Ɋ�Â��A�����Ƃ����X��������[�j���E�{���V�F���B�L�̍��ƃe������ᔻ�����ł��B�{�������͂�����Ԃ́A�P�X�P�V�N����P�X�Q�P�N�܂łł��B���̓��e�́A���[�j���ɂ�镐���I�N�E���͒D�掞�_����N�����V���^�b�g���������܂ł̍ō����͎҃��[�j���ᔻ�ƂȂ��Ă��܂��B�Ƃ��Ƀ��[�j���̢�ԐF�e��������͂ƃW�F���W���X�L�[�ᔻ�̓��e�ɂ��ẮA�l���ψ���c(�\���B�G�g)�����̏Ɋւ��錻��،��Ƃ��Ă���߂ċM�d�Ȃ��̂ł��B���h�G�X�G���́A�������Ɋv���O�́A�c�A�[���鐭���̢���ƃe����ɂ������颔����ƃe��������s���܂����B�������A�X�^�C���x���O�́A���͎ґ��ɂȂ��Ă���A�������A�i�@�l���ψ��ɏA���ĈȌ�́A���J�ٔ��ɂ��ƍ߁E���v���������咣���A���[�j���E�W�F���W���X�L�[�̢�ԐF�e��������`�F�[�J�[�ɂ��ٔ��Ȃ���ʏ��Y�ɉ��x���A����ɔ����܂����B
�@���͂��������}���N�X��`�҂���
�@���[�j���́A�}���N�X��`�̗B�ꐳ����p�҂����̂��A����̓R�~���e������ʂ��āA���E���̃}���N�X��`�҂ɔF�߂��Ă��܂����B�\�A�����A�u���[�j���閧�����v�U�O�O�O�_��A���q�[�t(������)�����������ƌ��J����܂����B����ɂ���āA���[�j�����A�����̎��������Œᐄ�v�łԐF�e������Ő��\���l�E�Q�������Ƃ������ɂȂ��Ă��܂����B���[�j���́A��������ʎE�l�^�E��}�ƍف����}�h��ŎE�l�^�̃}���N�X��`�҂������̂ł��B�ȉ��̃X�^�C���x���O�̏،��ƃ��[�j���������e����^������������Ƃ��A�������ɂ���ďؖ��������܂��B�����̏ڍׂȃf�[�^�́A(�֘A�t�@�C��)�̂T���ɂ���܂��B
�@�P�X�W�X�N����P�X�X�P�N�ɂ����āA�g���������Љ��`���h�P�S�J�����A�P�O�J���Ƃ��̃}���N�X��`���}�������������܂����B����ɂ���āA���[�j���E�X�^�[���������łȂ��A�g���͂��������}���N�X��`�҂����h�́A���ׂĂ̍��ŁA�ᔻ�E���Έӌ����������̎��������ʎE�Q���A���}�h��\�͂Ő�ł����Ă������Ƃ��������܂����B���ꂾ���łȂ��A�ނ�́A���[�j�����n�݂����u�ԐF�e�����v�I���K���̃`�F�[�J�[�����K���āA���h�C�c�̃V���^�[�W�A���[�}�j�A�̃Z�N���^�[�e�Ȃǂ�n�݂��A������閧�����x�@�^�Љ��`���ƣ�ɕώ������Ă������Ƃ��\�I����܂����B
�@�g���͂����������S���l�̃}���N�X��`�҂����h���A���̂悤�Ȣ�O�q�}�ƍߣ��Ƃ��������͂ǂ��ɂ���̂ł��傤���B(�P)�}���N�X�̍��Ƙ_�E���͘_�ɍ��{�I�Ȍ��ׂ�����̂��B�}���N�X�́A�Љ��`���͂̕��s�h�~�V�X�e���ɂ܂��������m�E���S�ŁA�y�ϓI�������̂��B����Ƃ��A(�Q)�u�ԐF�e�����v�^�E��}�ƍٌ^�́g��ΓI���́h���A�l�މ���̗��z�ɔR���A���`�����ӂ�錠�͒D��O�̃}���N�X��`�҂������A���̓V�X�e���̖@���ǂ���A�g��ΓI�ɕ��s�h���������Ƃ������Ȃ̂��B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@���@(�����A�o�D�X�`�P�P)
�@�{���V�F���B�Y���́A��������̑����p��Ƃ������֑̌�ȖƎЉ�`�▯�������̊m���Ƃ��������ƂŖڊo�߂���l�тƁA���N������l�тƂ𖣗�����B����́A�������Ƃɑ��邻�̖җ�ȁA��ΓI�ȓG�ł����Ĕނ�̖ڊo�߂�����ꂽ����ɑi��������B���������Ƀ{���V�F���B�Y���́A���̎c�E�Ȃ����₻�̑S�̎�`�I�v���A����ɌR���I�K���ɂ���Ĕނ�ɔ����̔O���N�������Ă���B�����������Ƃ̌̂ɂ����A�{���V�F���B�L�̃e�����Ƃ������Ƃ��A�{�����т����̈�ƂȂ��Ă���̂ł���B
�@���␢�E�̕���ւƓo�ꂵ����l�ނ̑命���́A�������āA��̖C�̔��݂ɂȂ��Ă��邩�̂悤�Ɋ����Ă���B�{���V�F���B�Y���́A�����������̖��O���v���I�ϊv��]�ނȂ�A�܂��Ƀ\���F�g�E���V�A�ɂ����Đ������Ɉׂ�������ꂽ���Ƃ��A�{���V�F���B�L�I�`�Ԃɂ����āA�����āA���̎w�����ɂ����Ă̂ݔނ�͊v����B���ł���̂��Ǝ咣���āA�����I�ȏ��������g�̖ړI�ɗ��p���Ă���B�s���V�A�t�͈�Z���v���Ɠ��ꉻ��������A�s��Z���t�̓{���V�F���B�L�}�Ɠ��ꉻ�������Ă���B
�@����͋U��ł���B���V�A�ł́A�����ԉ���̗��z�ւ̌��g���ׂ���Ă����̂ł���A��Z�Z�N�ȏ�ɂ��킽�����{���V�F���B�Y���̖ڎw�����̂Ƃ͗y���ɈقȂ����ڕW�������������̐�m�����ݏo���Ă����̂ł���B���V�A�I�ȉ���^���l���̂��킾���������́A��Ɂs�ł��[���Ȑl�Ԑ������ő���̊v���I�s���t�Ɍ��т��Ă����B���̌̂ɁA����͂��ꎩ�̂ŁA���_�Ǝ��H�̑o���ɂ����ă{���V�F���B�L�̕����Ƃ͊��S�ɑ������Ă���̂ł���B
�@���E���̐l�тƂ͂���́A�{���V�F���B�Y�����l���ɑ��āA�Ƃ�킯���V�A�v���̎和�ł��葱�����_���ɑ��ĉ����ׂ�������m��˂Ȃ�Ȃ��B�l�тƂ́A�{���V�F���B�L�E���V�A�ɂ����ās�v�����^���A�[�g�ƍفt���̋^�������K���ł���Y�ƘJ���҂��ǂ������^�������ǂ������A����ɒm���K���A�������Ė����͂������V�A�E�C���e���Q���`�����ǂ������^�������ǂ��������A���܂��Ƃ���Ȃ��ڍׂɒm��s���˂Ȃ�Ȃ��B�l��������قNj���Ȑ��_�I�A�����I���Y���g���Ă��̊v���ɓ��B�������Ƃ͋H�L�Ȃ��Ƃł��������A�܂��A�l���x�z�����̂���̐��ɂ���Ă���قǓO��I�ɐl���̂��ꂪ�͊�������ꂽ���Ƃ��H�L�Ȃ��Ƃł������B
�@���̂悤�ȁs����I(���x���[�e�B���O)�t�z�ꉻ�̉a�H�ƍĂтȂ�̂�����邽�߂ɁA���E���̐l�тƂ̓��V�A�v���̍ł������̏��i�K�Ɍ��������ӂ������˂Ȃ�Ȃ��B�l���̏��^�ȐM�����Љ�I�����ɂ���čł��e�Ղɑ����Ă䂭�̂́A�ނ炪�M��Ɗ��傳�Ƃɐ��߂������Ă��铮���̏����ɂ����ĂȂ̂ł���B�]���āA���̈Ќ��ɖ������������ߌ��I�Ȏ������狳�P�������o�����߂ɁA�s�v���̚���(���)�t�̍ŏ��̔N�����l�����邱�Ƃ͏d�v�Ȃ��ƂƂȂ�B
�@���ꎵ�N�ɂ́A���V�A�̐l���͎���̂��߂Ɠ����ɐl�ނ̂��߂ɂ��s���������Ɗ��]���Ă����̂ł���A����Ɍ����Ă̔ނ�̑����́A��]�Ɗ��҂Ƃɖ����Ă����B���������A�ނ炪�����ɂ����Đl�ނɑ��邻�̍��ۓI�ȉe���͂�ϋɓI�ȕ��������ێ��ł��ʂ悤�^���Â����Ă����̂��Ƃ�����A���V�A�l���̂��̋��Ɩ����̍R�c�Ƃ����Ȃ��Ƃ���Ȍx���Ƃ��Č��݂ɐ������߂悤�ł͂Ȃ����B���S���Ƃ������E���ꂽ���т̒��ŁA���V�A�͑S���E�Ɍ����āA�v�����{���V�F���B�Y���Ƃ͈قȂ邱�Ƃ��A�l�ނ̓{���V�F���B�L�̎肩��v���̓Ɛ茠��D�悹�˂Ȃ�Ȃ����Ƃ��A�v���N�����Ă���B���V�A�̍L��Ȍ���ɗN���N��g�債�Ă������v���̃h���}�́A���V�A�����̃h���}�ł͂Ȃ��\�\����͑S���E�̂��̂Ȃ̂ł���B
�@��P�P�́A�{���V�F���B�L�̃e�����@(�S���A�o�D�P�Q�Q�`�P�Q�V)
�@�{���V�F���B�L�̋����g�ł����Ċ��������Ƃ̂���҂������A���̃e�����̐^�̈Ӗ���m�肤��B�v���㒷�N�ɂ킽���ă��V�A�̎s���́A�e�����ɂ�鋭�͂Ȓ��߂��Ɋ��炳��Ă����B���̂��܂��܂Ȍ`�̔����́A�����͋��J�I���p���ׂ����̂Ɗ�����ꂽ���A����ɂ�����܂��̂��Ƃƌ��Ȃ����悤�ɂȂ����B�����Đl�тƂ͏��X�Ɍ��炳��Ă䂭�p���̔z���ɏ������Ă����悤�ɁA���̂����Ɏ������������������Ă������̂ł���B
�@�����̔敾�����������V�A�l�Ɂu�e�����Ƃ͉����H�v�Ƃ��Ƃ��q�˂Ă݂Ă��ނɂ͎�����}�����Ă���\�͂̑̌n��`���o�����Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B�ނ́A���ɔނ̖ڂ����������ꂱ��̃e�����̒f�ʁ\�\���Ӗ��ȑߕ߁A��ʏ��Y�A�����̉��\�Ȃǁ\�\��������ɂƂǂ܂�ł��낤�B�����āA��������������V�A�l�͌���Ă���A�Ƃ����̂́A�e�����͌l�I�s�ׁA�Ǘ������s�ׁA���͂̈ꎞ�I�ȓ{��̋��R�I�\���Ƃ��������̂ł͂Ȃ�����ł���B
�@�e�����Ƃ́A�����Ƃ͋�ʂ��ꂽ�\�͂��̌n�Ƃł������ׂ����̂Ȃ̂ł���B�e�����́A�Њd�����|�����邱�Ƃ�ʂ��Đl���]������Ƃ���v��I�������@�I�j�̂ł���B�e�����́A�x�z�̐����l�������̐�ΓI�ӎu�ɏ]�킹�邽�߂́A�ڍׂɍl���ʂ��ꂽ�����ƒ����̌v��Ȃ̂��B
�@����ł͒N�����̌��͂��s�g����̂��H�@�N���S�l���̓���ŋ�����������̂��H�@�������l���Ƃ͑��e��Ȃ��ʌ̐N�Q�҂����݂��Ȃ��Ɖ��肵�āA�l���������������g�����̂悤�ɗ}������ȂǂƂ������Ƃ����肦���ł��낤���H
�@���_�A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ��B���������̌n�ɂ����ẮA�����̎x�z�Ƃ������̂͑��݂����Ȃ��̂��B�e�����ɂ��x�z�́A��ɏ����̎x�z�ł���A�Ǘ��������A���������������Ă��鏭���҂̎x�z�Ȃ̂ł���B�₦�܂Ȃ��p�j�b�N���A�e�����X�g�̐������Ă��̖Ԃ̖ڂ��X�Ɋg���A�l���̐V���ȕ�������Ɏ��Ȃ̓G�ƒ�߂Ă������Ƃ�]�V�Ȃ������Ă��܂��̂��B
�@�e�����̑̌n�̈�[��S���҂Ƃ��ās�v���̓G�t���o�ꂵ�A�v���̂����鎸��Ɛl���̋��Ƃɂ��ĐӔC���ׂ��g���(�X�P�[�v�S�[�g)�Ƃ����B�v�����O�i���Ă������s�G�t�͏d�v�Ȃ��̂Ƃ��Ă͑��݂��Ȃ��B��������������v���̕��������ς��A����͐g�߂Ɋ�������悤�ɂȂ�A�ڂɌ�����悤�ɂȂ�A���m�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���̂ł���B�v���̐i�H���l���̑命���ɂ���ē�����Ă������A�s�G�t�������K�v�͂Ȃ��B����͂��₷������������̂��B�����A�������͂����a�ŌǗ������ȋ^�S�̋��������h�̎�Ɉ������s�v���̓G�t�i���邢�̓t�����X�v���ł����s�e�^�ҁt�͋��l�ɐ������A���̉e�������ɓ��������A���ɂ́s�x�z�҂������S���t���v���̓G�ƂȂ��Ă��܂��B�s�G�t�͐l�����̂��̂Ɠ��`��ɂȂ�̂ł���B
�@�������Ă����x�z�҂Ƃ��́s�G�t�Ƃ́A�e�����̑̌n�Ƃ��������̓o��l���ƂȂ�B�ł́s�G�t�ɓ˂������e�����Ƃ�������Ƃ͉����H�@�����������̕���̂��ׂĂ������҂����݂��邾�낤���H�@����͐���������ɂ͗]��ɑ������邵�A�������e�����Ƃ���������s�g����҂̑z���͂́A�ʂĂ����Ȃ��g�����Ă䂭���̂Ȃ̂��B�e�����̗ʓI�K�͂́A�X�l�ɂ��Ă̔ƍ߂̏؋��ɂ���Ăł͂Ȃ��A������l�Ԃ��s�^�킵���t�Ƃ����ϔO�ɂ���Č��肳���̂ł���A���������Ă���͖����̂��̂ƂȂ�B�����Ă��̎��A�����e�����̎����I���e�́s���ׂĂ��������t�Ƃ��������̌��ʁA�������Ɋg�����Ă����̂ł���B�͂Ɉˋ����Ďx�z���鏭���҂́A���炩���ߓ����I�ƍߕ��Ƃ������̌����𗬕z���A���Ԃ�����P�������Ă��܂��B�s�l���̓G�t�ɑ��Ắs���ׂĂ��������t�\�\���ꂪ�e�����̓�̎w���I�ϔO�ł���B���H�ɂ����ẮA����͂��ׂĂ̎҂ɑ��邠��Ƃ�����\�͂���ђe����i�̍s�g�ɂ������B�����Ă��ꂪ�A�s�v���̖��ɂ����āt�A�l�ނ����]�����鎊���̗��z�̖��ɂ����āA�s�Ȃ���̂ł���B
�@�e�����̂悭�m��ꂽ�`�Ԃɂ��č���x�ڂ������Ă݂悤�B���̓I�e�����Ɛ��_�I�e�����Ƃ���ʂ���K�v�͂Ȃ��A���̂Ȃ�ǂ̂悤�ȗ}���s�ׂ������̗v�f���܂�ł��邩��ł���B����͂���l�тƂɂ͒��ړI�������̑Ō���^���邪�A�ԐړI�ɂ͑��̐l�тƁA�X�ɑ����̐l�тƁA��l�ЂƂ�̐l�Ԃɑ��Ă��e����^����̂��B
�@�e�����͎E�l�ł���A�����ł���A���Y�ł���B���������Y�́A�e�����Ƃ������z���̒P�Ȃ�듃�ɂ����Ȃ��B�e�����͖����̖e(����)�������Ă���̂ł���B����̓\���F�g��}�⎄�I���P�c�̂Ƃ��������@�I���g�D�����U�����邱�Ƃ̒��ɂ���F�߂邱�Ƃ��ł���B�����������ׂĂ̑g�D�̒��ɁA���O�̎�̓I�ӎu�͂��̎��R�ȕ\���������o���Ă����̂ł���B���̂悤�Ȃ͂����������A�l�Ԃ͋����R�ƂȂ�B�e�����͊v���I���Ƃ̒ÁX�Y�X�ŗ��j�̍ł�����I�ȏu�ԂɎ��R�Ȕ��������E���邱�Ƃ̒��ɑ��݂��Ă���B������̌`�ł���A���J�̐Ȃł���A�g�D�̒��ł���A�x�z���͈͂�̔��Έӌ��������͂��Ȃ������B���Ƃ������A�s���ӂɂ����邩���邢�͑�_�ɂ�����l�Ԃ̌�����A�ᔻ�A�R�c�������͐�]�̌��t�������悤�Ȃ��Ƃ�����ɂ��Ă��A���̌��t�́A���̔����������Ȃ�������A���̔����҂̏����ɂ���邪�̂ɁA�ŋ����ʂ��ƂƂȂ�B�ނ̌��t�́A���͂̒��O�̊��X�Ƃ����A���J�I�Ȓ��قɏo��݂̂ł���B
�@�e�����̎x�z���鍑�ɏZ�ސl���́A���R�ɘb�����Ƃ��A���������ɂ��Ă̐^����m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�e�����́A�l�̎v�z�Ƒn���I�G�l���M�[����������ɂ��錟�{�Ƃ����d�����̒��ɑ��݂��Ă���B���̌��ʁA�v�z�͗�₩�Ȓ��قւƓ�����Ă������A�����Ȃ��Γz��̕��]�ւƑ����Ă����B�s�ق��Ă͂���ʁt�Ɣ��R�̐���������̂��A�l�Ԃ̖{���ł���B�������e�����̎x�z���鍑�ɂ����ẮA���̐l�Ԃ̏Փ��ɍł��������K�����ۂ����Ă���̂ł���B�������Ďv�z��̋���A���Q�����Ē���A���l�̈ӎ��̓����ւƐZ�����Ă������ƂƂȂ�B
�@�e�����́A���͂��Љ�̂�����זE�E�g�D�ɂ�������ƒ���߂��炵�������I�Ď��̖Ԃ̒��ɑ��݂��Ă���B����͌X�l�̈ꋓ�������Ď����Ă���\�\���邢�͊Ď����Ă���ƌ��������Ă���\�\�閧�x�@�̒��ɑ�����B�e�����͉A���Ȉ����̔@���X�p�C�����A���݂̖����A�����̒��ɍ݂�A�l�̓��ɔ�߂��v���������x�z�̐��̑O�ɂނ������ɂ��Ă��܂��̂ł���B�e�����́A��^�҂��q�₳���ۂ݂̂̕ƚ}��ɍ݂�A�j���p�ɂ��A���������т��сs�v���ƎЉ��`�t�̖��ɂ����čs�Ȃ��鐸�_�I����̍ۂ�����(��������)�Ȏd�|���ɍ݂�B�X�Ƀe�����́A�Q�����j�������ӂ��悤�ɉ������܂�Ă���č��ɁA���������̑�͂̍ۂɂ��قƂ�ǖ傪�J���ʊč��ɑ��݂���B�e�����́A�����̋�͗l�̂悤�ɗ\������s�������������̗L�ߔ����̒��ɑ��݂��Ă���B�e�����́A�L�߂Ƃ��ꂽ�҂����̎�Ő��������ėV�Ԑ��{�̏o����`�҂����̋C�܂���̒��ɍ݂�B�e�����́A�x�T�҂�ΏۂƂ���Ǝ咣����Ȃ�����A���ۂɂ͕n���҂Ɣ�ꂽ�҂ɑŌ���^���霓�ӓI�Ȓ�������p�̒��ɑ��݂���̂ł���B
�@�������Ȃ���A�e�����̍ł�����ׂ����e�́A������Y�ł���B�����́s���Ȃ�M���`���t�̂悤�ɁA����͍Ăсs�v���t�̍őO���ɗ����ǂ����Ă���B���̐n�͒��ɒ݂�グ���A�L�ߖ��߂��킸�A�l��I�Ԃ��ƂȂ��A���@���Ȃ鎞�ɓ���ɗ������Ă��邩���m��ʁB�e�����́A�����߂ɁA���Ӗ��ɗ����ꂽ�������������̒��ɑ��݂��Ă���̂��B
�@�e�����́u�ǂɗ��āI�v�Ƃ������т̒��ɍ݂�A����͏����őؔ[�A�R������̓��S�A�n�⍒���̉B���A��t�߁A�����D�A�����݂��̏��ƓI���@�A�ړI�ӎ��I�Ȕ��v���A�d�A���邢���ȁs���̐��ɑ��镎�J�t�ȂǂƂ��������ɑ��ē������l���������B
�@�e�����́u�ǂɗ��āI�v�Ƃ������т��e�F���ꂽ�K�͂ƂȂ��Ă���Ƃ��������A��҂△�͎҂ւ̉̕ߒ��Ől�Ԃ̒��̖�b�������S�ɕ��C����Ă���Ƃ��������̒��ɂ���B�e�����͈ӎu��Ⴢ����Ă��܂��A�����l�Ԃ����k�������点�A�����đS�l�����A�e����ɂ����l�ԂɈ����n�����ƂƂȂ�A�����I�ȋ��|���̒��ɑ��݂���̂ł���B
�@�Ō�Ƀe�����́A���͂̎�ɕ߂����邩�A���邢�͂��܂��ܓ�������Ă���G�ΓI���K���̐����������ʂɈ����o����āA���̐l�Ԃ̍߉Ȃ𒅂�����ۂ̂悤�ȁA���(�ނ�)�̎҂ɑ����ʏ��Y�ɍ݂�B���������ăe�����́A���l�̍s�ׂ̌̂ɒN�����ӔC�킳���Ƃ����A�l�����x�̒��ɑ��݂���Ƃ����悤�B
�@�e�����́A�x�z���͂����ȕېg�̂��߂ɂ��ꂱ��̖\�͍s�ׂ�Ƃ��ɂƂǂ܂炸�A���������̑S�ǖʂɂ킽���Ď��Ȃ�Z�������邽�߂ɗގ��̂���s�ׂ��ی��Ȃ��ɉi�v�ɌJ��Ԃ��A�Ƃ��������̒��ɑ����Ă���B�e�����͂��̎��H�ɂ�����̂Ɠ��l�A���ꂪ�L���鋺�Ђɂ����Ă������I�Ȃ��̂ł���B�s�f�̋��Ђ�^���邱�Ǝ��̂��A�e�����Ȃ̂��B
�@�e�����͐l�тƂ��̐w�c�ɕ����A�����e�������s�Ȃ����Ǝ鑤�A�ł���B�O�҂ɂƂ��ăe�����́A�E�����A���x���A��_���ł���A���炭�����I���̌�ɏ��߂Ċl���������Ȏ咣�̋@��Ȃ̂ł���B��҂ɂƂ��Ă���́A�ߒQ�A���J�A���|���Ӗ����Ă���B���҂̊Ԃɂ́A���ݗ��������낤�����Ȃ��A�������O�Ƒ���������݂̂ł���B����̑��ɂ́A���͂���ɂ��������A�����A��x�z�҂ɑ��₦���̂��Ă䂭���̂̔O�\�\�@�ꌾ�Ō����A�x�z������B��������̑��ɂ́A�����ɑ��鋰�|�A���݁A�����̑A�]�A���͎҂ւ̂ւ炢�\�\�����ꑮ������B�������āA��Ȃ��̎Љ�I�E�S���I�[���Ɋu�Ă�ꂽ�V���ȓ�̊K�������ݏo�����\���F�g�l���ψ�(�R�~�T�[��)����т��̕��������Ƃ����K���ƁA�\���F�g�́s�b���t�Ƃ����K���Ƃ��B
�@�\���F�g�E���V�A�ɂ����邱�̂悤�Ȍ��͂̓����I���s���́A���炩�ɑΐl���Ƃ̊W�ɂ����Ă̂ݐ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�l�����݊Ԃ̊W�ɂ܂ŋy��ł���B�ꑮ��Ԃ��l���̒��ɐZ�����Ă����ɂ�A����͐l���f���A�ł��Ђ����B���݂̉��^�ƕs�M�A�S�\�̗D�z�҂̏Ί��D�ӂ����߂Ă̑����A�אl�ւ̌��R�E����R�̗���A�s�ی�F�t�̑����\�\����炷�ׂẮA��ӂł̂���A�~�j�`���A�Ƃ��Ẵe�����̍Č��ł���B���������ԓx��s���́A����ׂ��K�͂ŁA�x�z�҂̋ʍ��̎��͂ɂ����W�܂�l���̏��K�w�Ɋg�����Ă����B���ׂĂ̐l�Ԃ����ƂƂ̊W�ɂ����ēz��ł���̂Ȃ�A�z�ꓯ�m�݂͌��ɓG���邱�ƂƂȂ낤�B�ォ��̃e�������s���̓�����ь����Ă���A�s���̊Ԃł͉�����̃e������������ł��낤�B�X�ɂ܂��\���F�g�E���V�A�ł́A���̗͂}���̋K�͂͑��̂ǂ�ȎЉ�̐������y���ɑ傫���A��I�ł���Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�c�@�[���̐���u���W���A�̐��ɂ����ẮA�x�z�̐��̎����́A�����A�@���A�i�V���i���Y���Ƃ���������ꂽ����ł̂ݔ�������A�o�ϓI����ɂ����Ĕ�������邱�Ƃ͋H��ł������B�s���̌l�I�����Ƃ������S�ɖ������ȗ̕��́A�����������ƌ��͂̎x�z�̊O�ɂ������̂ł���B�Ƃ��낪�\���F�g�E���V�A�ł́A�l�A�o�ϓI�A�Љ�I�����̂��ׂĂ��A���ƌ��́A�r���I�Ȃ܂łɃe�����ɗ��r�������͂̎�Ɉ����n����Ă��܂��Ă���̂��B
�@�܂肱�ꂱ�����A���V�A�̃e�����Ȃ̂ł���B�l���̂ǂ̂悤�ȏW�c�ł��낤�Ƃ���ɏ]�킳��A����͐����̑S�̈�������Ă���B���V�A�ōs�Ȃ��邱�Ƃ͂��ׂāA�����ƚ}�ɂ���Ă���A�����Ɠ��ӂɂ����͉̂��ЂƂȂ��B���̂悤�Ȍ̈ӂɔ|��ꂽ�����{��Ԃɂ���̐��́A�ǂ̂悤�ȍ����ɂƂ��Ă��ߎS�Ȃ��̂ƂȂ낤�B�����I�ɂ��킽��ꑮ��Ԃ��甲���o��������̍����V�A�ɂƂ��ẮA���Ƃ����s�K�Ȃ��Ƃ��낤�I�@�c�@���[�Y���̈�������Y���V���ȃe�����̓łƍ������킳��鎞�A����͂ǂ�قNJ댯�Ȃ��̂ƂȂ邾�낤���I
�@��P�Q�́A�{���V�F���B�L�E�e�����������@(�S���A�o�D�P�Q�W�`�P�S�Q)
�@�{���V�F���B�L�̃e�������l�@����ɂ������ẮA���ꎵ�N��Z������k���Ĉ��ꎵ�N�̊v���J�n���ɘb��߂��̂��D�s���ł��낤�B���V�A�l����ƊO���l����Ƃ��킸���j�Ƃ̊Ԃł́A�v���́u�����v�ɂ��ĕ��a�I�v���ł���A�P�ӂɖ������ӂꂽ�q�̂Ƃł������ׂ����̂������A�Ƃ����̂��ʐ��ƂȂ��Ă���B�c�@���[�Y���̕���Ɩ����`�I���̂ւ̈ڍs�́A���͖����v���̖͔͂Ƃ��āA��Z���I�N�̖���Ƌ��\���Ƃɂ͂�����ƑΔ䂳��ďq�ׂ��Ă���B
�@�������������͗��j�̐^������͂قlj������̂ł���B���ꎵ�N�̏t�̓��X�́A�c�@�[���̐��̑�\�҂����ɑ���l����O�ɂ�鐔�����̖\�͍s�ׂɂ���ē܂炳��Ă������A�قƂ�NJF���ƌ����Ă悢�قǂ����ɂ��Ă͌���Ă��Ȃ������B�Ⴆ�A���q�R�i�ߊ��f�j�L�����R�́u���ׂ��郍�V�A�v�A�ނ͊v���������Ă̂����A�ɂ��Č܊��̒�����o�ł��Ă��邪�A���̖��ɂ́A��Z���ɖ�����ɐG��Ă��邾���ł���B�f�j�L���͂��������Ă���B�u�v���̍ŏ��̓��X�ɂ������s�̋]���Ґ��́A����قǑ����͂Ȃ������B�y�g���O���[�h�ł́A�����҂͈�l�l�O�l�ŁA���̂������Z��l���R�l�ł���A����ɂ��̘Z�Z�l�����Z�ł������B���R���̐����́A�����҂̐������ׂĊ܂ނ��̂ł͂Ȃ��v
�@�������ꂾ���ł���B�y�g���O���[�h�����ň�܁Z�Z�l�ɂ��y�Ԏ����҂̐����u����قǑ����Ȃ������v�ƕЂÂ����Ă���B�Ƃ��낪��X�́A���X�N���⑼�̑�s�s�ł������������N�����̂�m���Ă��邵�A�o���g�C�͑��̐����ɂ��㊯�ւ̑�K�͂ȕ��Q���L���ɂƂǂ߂Ă���B���������̊v���̍Ւd������ꂽ�����̋]���҂����َ͖E���ꖳ������Ă����̂ł���B�p�[���F���E�~�����R�[�t�A���B�N�g���E�`�F���m�t�A�A���N�T���h���E�P�����X�L�[�Ƃ��������V�A�̌��Ђ�����j�Ƃ���Ƃ̒���ɂ��A����ɂ��Ă̏ڍׂȐ�����A�⊶�̈ӂ̕\���ɂ���������Ȃ��B���̎����̏����҂₻�̏̎]�҂����́A�����̎S���Ƌ]���҂̋ꂵ�݂��A�߂��ނׂ����Ƃł��邪��ނʂ��̂Ƃ��āA�����Ĕ��͂����A��ÂɐÊς��Ă����B�S���I�ɂ����ł����̂́A�ނ炪�u���W���A�����`�v����S�̂Ƃ��Ď���Ă�������ł���B�Љ�I���Q�Ɛ����I���_���ނ�̖ڂ��瓹���I�����B���Ă��܂��Ă����̂������B
�@�������Ȃ���A�\�͎����͌����Ȋϓ_���猟������ᖡ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����͖����̑�O�A�������炩�ɒN�̎�ł��g�D����邱�Ƃ̂Ȃ�������O�̏Փ��I�ȍs���ł������B�������������I�Ȑ����I�����`��ʂ��āA�����ɂ�蒷���ԓz�ꉻ������������Ă������O�́A�T�ς����R�c�̊�����ꋓ�ɕ\�������̂������B���̂悤�ȑ�O�̓{��̕��o�́A���Ƃ��Ďc���Ȍ`�Ԃ��Ƃ������A����͌����āA���ݏ����ꂽ�薳������Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł���B�������A���̎�̌����͒������͂��Ȃ������A�Ƃ����̂́A���ꂪ���R�����I�Ȃ��̂���������ł���B���O�́A�Z���Ԃ̗��̂悤�ȏՓ��I�s���œ{��̏Ք���������ƁA�₪�ĕ��Âɖ߂����B�Ԃ��Ȃ��F���A���u���A�A�тƂ���������D�����߂Ă����B���������O�́A���Ă̎��������̓G���͂��Ƃ����ނ��܂�ȓx�ʂ��������ƂƂȂ����B�{��Ƒ����݂ɂ�����āA����ނ�͓G�ɑ�������ƌy�̂��o���邾���������̂ł���B
�@���̃��V�A���O�̎������A��̏d�v�ȗ��j�I�����������Ă���B�ނ炪�ǂ�Ȍ����������������ăc�@�[���ꐧ��ł������́A���m�̎����ł���B��������O�̒��ɂ́A�c�@�[���l�₻�̉Ƒ��ɑ��čŌ�I�Ɍ���������Ƃ����I���ȗ~���͑��݂��Ă��Ȃ������B�����\���F�g�ɂ����Ă��c�@�[�������J�ٔ��ɂ�����Ƃ����ϋɓI�Ȏ咣���Ȃ��ꂽ���Ƃ͈�x�Ƃ��ĂȂ������B���C��Z���̌��I�Ȏa��Y�ƃp���ɂ�����M���`���E�p���[�h�Ƃ������̖����ȃt�����X�v���̐��ɂȂ炤���Ƃ́A���V�A�̊v���I��O�̐S�ɓ���S�����ыN���͂��Ȃ������B
�@���āA���낻��{���V�F���B�L�ƍ����Љ�v���}�̘A������ɐl���ψ���c�Ńc�@�[���ꑰ�̉^�����_����ꂽ�A�ŏ��ɂ��čŌ�̐܂̂��Ƃ�z�N���ׂ����ł��낤�B���̖�肪�ˑR��N���ꂽ�͈̂��ꔪ�N�̂��Ƃł���A�h�C�c�R�����V�A�ɑ���N�U���ĊJ�����댯�ȓ��X�̍Œ��̂��Ƃ������B�_�����̑�\�������A�l���ψ���c�̐ȏ�Ɍ����A�c�@�[���ꑰ�����J�ٔ��ɂ����邽�߃g�{���X�N�i�V�x���A�́j����A��߂��Ƃ������c���o�����̂ł���B���������v���̔w��ɂ��铮�@�𗝉�����͍̂���Ȃ��Ƃł͂Ȃ������B���̋N���҂́A�����������j�I�ȉ��o�ɂ���āA�V���ȌR���I��@�ɋ����Ă���l�����ە����E�C�Â��邱�Ƃ��ł���ƐM���Ă����̂��B
�@�l���ψ���c���A���̐��`�ƕƂ̑傪����Ȍ������𗧈Ă����o���邱�ƂƂȂ�i�@�l���ψ��̈ӌ������߂��͓̂��R�̂��Ƃ������B���������͂��̌v��S�̂Ɋ���̋^�`�������Ă����B�ł���Ȃ��Ƃ́A�l���ɂƂ��Ē鐧�����͂�؎��Ȗ��ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���A�O�c��̍ٔ��́A���ꂪ�����Ɍ��l�A�����I�Ȃ��̂ł��낤�Ƃ��A�V���Ȋ�т��E�C�������炷���̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ���L���邱�Ƃł������B���͔��������A�Љ�v���͂����ƈقȂ�ړI�ƃV���{���������Ă���A�ƁB����Ɏ��́A�V�x���A����̃c�@�[���̒��r�ڑ��͋��M�҂⎩�̊v���Ƃ����̃����`��U������ƌx�������B
�@�l���ψ���c�̊��l���̑��̃����o�[�����̌������q�ׂ����A�Ō�ɑS���̖ڂ��c���ł��郌�[�j���ɒ����ꂽ�B�Ƃ��낪�A����߂ĕs�v�c�Ȃ��Ƃ́A���̎������ނ����ɓ��ӂ����̂ł���B�ނ͗�ÂɁA�ނ��܂����̂悤�Ȏ����ɍٔ����s�Ȃ����Ƃɂ��Ă̋^��������Ă���A��O�͑��̎����ɐS��D���Ă��邪�̂ɍٔ��͉������������]�܂����Əq�ׂ��B�������Ďi�@�l���ψ����́A�����̂��߂Ɋ֘A������p�ӂ���C�ɂ����邱�ƂɂȂ����B������[�j���́A�ގ��g���Ƃ�������Ɋւ��ĔނȂ�̐����I�ǂ݂��������̂ł���B�Ƃ��낪�A���̔Ӗ��͒I�グ����A���������ɂȂ��Ă��܂����B�i�@�l���ψ����́s������p�ӂ���t�ɋy�Ȃ��Ȃ��Ȃ����̂ł���B
�@�v���̓i�K��ʂ��āA�������̖\�͍s�ׂɂ�������炸�A�l���͑S�̂Ƃ��Ă͊���Ől���I�ł��邱�Ƃ��������B�������̂��Ƃ́A��������̈�Z���I�N�̍ۂ������������̂ł���B���ۈ�Z���ɂ����鎩�R�����I�\�͍s�ׂ̐��́\�\��K�͂Ȃ��̂ł���A�l�I�Ȃ��̂ł���\�\�������O�Ƃ͔�r�ɂȂ�ʒ����Ȃ������B���̂��Ƃ͒��ڂ��ׂ����Ƃł���A�Ƃ����̂́A�l���͈�w���������݂�����Ĉ�Z���v���ɓ˓������̂�����ł���B�������A�Љ�I����������炵���傢�Ȃ銽�삪�]��ɂ����傾�����̂ŁA����͐l���̒��̂ǂ̂悤�ȕ{�\�������킵�Ă����B�Ȃ�قǁA��Z���̏����ɑ������X�ɂ͍Ăуo���g�C�͑��A���C�͑��ɂ����ď㊯�ɑ���c���Ŗ��Ӗ��ȎE�C������ꂽ�B���R�ō��i�ߊ��h�D�z�[�j�����R�̓����`�ɂ�����ꂽ�B����Ɉ��ꔪ�N�ꌎ�ɂ́A�̃J�f�b�g�̑O��b���ނ����炵���E�Q���ꂽ�i��Z�͂��Q�Ɓj�B�������Ȃ���A�I�\�s�͊g�債�Ȃ������B�Ԃ��Ȃ����V�����l���̓{��ɂ܂������s���͂����܂�A�����I�����`�͂�̂ł������B
�@�m���Ɉ�Z���v���̗��j�ƂƉ�z�L�^�҂����́A���̖�Ɍ��h��ꂽ�r�ɂ��Č��`���邱�Ƃ��~�߂悤�Ƃ͂��Ȃ��B�������ēx�������A����́A���j�I�^�������߂�^���ȒT���S�̕\���ł͂Ȃ��A�����I����ɂ���ꂽ�����Ȃ̂��B�̖\�͂��k�����Ō������̓����Ⴊ�A��Z���v����]������̂Ɋg�勾��p�����̂ł���B
�@�Ƃ���Ől���̖\�͂����Ȃ�̒��x�܂Ő��䂳��A�����\�Ȃ��̂ł���Ɣ��������A�Ƃ����܂��ɂ��̌̂ɁA����ȏ�̗\�z����閳�@�s�ׂ������A�����ɐl���𐳋`�̓��֓����̂��v���w���҂̓����I�C���ƂȂ����B�Ƃ�킯�㋉���{�@�ւ≉�d���邢�͎Љ��`�I�V������́A�����ƕ����悤�Ȓ����͌��ɐT�܂˂Ȃ�Ȃ������B�������A�s�K�ɂ����̐^���𗝉����悤�Ƃ��F�߂悤�Ƃ����Ȃ��W�c������݂��Ă����B�{���V�F���B�L�}�́A���̖����܂������t�Ɍ��Ă����B�ނ�́A�l���̓��Ȃ���Ɉӎ��I�ɑi�������邱�Ƃɂ��v���𑀂邱�Ƃ��D�̂ł���B����ɁA���̑�O�ɑ���f�}�S�[�O�I�����́A���a�ɑ��邻�̑ԓx�A�v�����^���A�[�g�̌��͂Ƃ������ꓙ�̌̂ɁA��O����̐M����悸���������}�h�ɂ���ĂȂ��ꂽ�̂ł���B���������Đl���́A�{���V�F���B�L�̋}�i�I�ȎЉ�I�Ȑ���ɂƂǂ܂炸�A����Ƌ��ɂقƂ�ǖ��ӎ��̂����ɁA�ނ�̊v���̓����I���l�ɑ���j�q���ŃV�j�J���ȑԓx�̈ꕔ�������ꂽ�B�����Ɋ댯������ł����̂��B
�@��Z���̂��������̏��߂̓��X���A���[�j���͂��̓��������ɁA�\�́A���Y�A�e�����ɑ����ΓI�K�v����͐����Ă����B����l�N�ɔ��s���ꂽ���[�j���ɂ��Ă̒���ŁA���I���E�g���c�L�[�͂��̂��Ƃ��ؖ����鐔�����̑}�b�ɐG��Ă���B��Z���I�N�����F�����\���F�g���̐ȏ�ŁA�{���V�F���B�L�̃J�[���l�t�́A�g���c�L�[�̎^�ӂāA�O���ł̎��Y�������P�����X�L�[�̖@�߂�p�����悤�Ƃ̒�Ă��s�Ȃ����B���̖@�߂́A�����Ɏ������ꂽ�B���[�j���́A�����Ƀ\���F�g�̂��̍ŏ��̍s�ׂ�m���ė�̔@���{�����B�u������n���������Ƃ��v�Ɣނ͋��B�u���N�́A���Y�Ȃ��Ɋv��������Ƃł��v���Ă���̂��H�@�������������Ă����āA�G��|����Ƃ����̂��H�v�B�ނ́A�v����肠�郍�V�A�l�C�����u����Ă����v�B�ނ́A���V�A�l���B�R����ԓx���Ƃ肤��̂��ǂ����ɂ��ĕs�M������Ă����̂ł���B�u�D��������A�]��ɗD��������̂����V�A�l���v�Ɣނ͒f�������B�u���V�A�l�ɂ́A�v���I�e�����Ƃ����f�ł����i���Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��v�B
�@���̌�ɂ��A���[�j���͐l���ψ���c�̐ȏ�œ����l�����J��Ԃ��q�ׂ��B�����Ĉ��ꔪ�N�A�h�C�c�R���U�����J�n�������A���{�́u�Љ��`�c���͊�@�ɕm���Ă���I�v�i���ꔪ�N�����j�Ƃ����錾�������Đl�����������߂邱�Ƃ����肵���B���̋N���҂̓g���c�L�[�ł������B�ނ́A���V�A�l���̃q���C�Y���ɑi�������邱�̕����ɁA���{�̖��߂ɔ�����҂��ׂẮu�����ɏ��f�����v�Ƃ��������荞�ނ悤��Ă����B�l���ψ����������̕��Ă����������ہA���́A���̎c���ȋ����͐錾�S�̂̃p�g�X���E���Ă��܂��Ƃ��Ĕ������B���[�j���͚}��������ē������A�u����ǂ��납�A�����ɂ����^�̊v���I�p�g�X������̂��B�N�́A��X���c�����̂��̂ł���v���I�e�����Ȃ��ɏ����ł���ȂǂƖ{�C�ŐM���Ă���̂��H�v�B
�@���̓_�ɂ��ẮA���[�j���Ƌc�_���邱�Ƃ�������Ȃ��Ƃł���A��X�͂����ɍs�l���Ă��܂����B��X�́A�L�͈͂̃e�����\�͂������i�Ȍx�@�I��i�ɂ��ċc�_���Ă����B�����v���I���`�̖��ɂ����Ă���ɔ��������Ƃ����[�j���𗧕��������B�����Ŏ������S���ċ��A�u����ł͉��̂킴�킴�i�@�l���ψ����ȂǂƂ������̂ɂ������炤�̂��B�������̂��ƒ��B(���傭����)�ɁA�Љ�G�o�Ől���ψ����Ɖ��̂��A�����ɂ܂������������Ȃ����I�v�B���[�j���͓ˑR����P�����ē������A�u�����c�c�܂��ɂ������ׂ��Ȃ̂����c�c�ł������ĂԖ�ɂ������܂��v�B
�@�{���V�F���B�L�̃e�����ɂ��Č��ɍۂ��Ď��͎��������ꔪ�A���A��Z�N�ɂ��ڂ낤�Ǝv���B���̗��R�͂��̎����Ƀe�����̔g�����ЂƖ���ɂ����čō��ɒB��������ł͂Ȃ��B����ɑ����N��A���Ɉ��O�Z�N��͖������ĒN�ɂ��z���ł��Ȃ������������܂����e�����̍��܂���������ƂƂȂ����B���������ꔪ�N�����Z�N�ɂ����āA�V�j�J���ȃe�����̑̌n�\�\����͂���ȍ~������܂��̂��ƂƂȂ邪�\�\���n�o����A���������悤�ɂȂ����̂ł���B���̎����ɋN�����������́A��Ƀ{���V�F���B�L���Ƃ����݂�����b���`�����邱�ƂƂȂ����B�����Ċv�����V�A�̓y��́A���̎����ɓł���A�₪�ď��������ɓŁX�����ʎ�������͕̂K�R�������̂ł���B���ꔪ�N�����̐錾�́A�����̏e�E�Y�𐳓������A��������������̂Ƃ��āA�`�F�[�E�J�[�ɂ��e�����ւ̓���|�����߂��B����Ȍ�S�y��Ԃ����ߐs�����ƂƂȂ������̉͂ɂ��ẮA�����ŏڍׂɏq�ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u�Љ��`�̖��ɂ����āv�����Ȃ������������m��ɂ́A�w�`�F�[�E�J�[�T��x�ɔ��\���ꂽ���Y�҂̒����A���������S�Ƃ����ɂ͂قlj������X�g������Ώ\���ł���B
�@�h�C�c�Ƃ̃u���X�g�����g�t�X�N�������i���ꂪ�����Љ�v���}�̐��{����̈��g���̌����ƂȂ����j��̎��Ԃ̑S�ʓI�����Ƒł������H�Ɗ�@�Ƃ́A���ǂ̂Ƃ��됭�{�ɒ�������ђ�����������g�D���Ĕ_���֔h�����邱�Ƃ�]�V�Ȃ����������A�����ł����̕������͎c�s�ȋ�����i���s�g���邱�ƂƂȂ����B���ꔪ�N�̎O�����甪�����܂ł��������F�̂��̂ł͂Ȃ��������A������̐ԐF�e�����̈ꎞ���ł��������Ƃɋ^��̗]�n�͂Ȃ��B�v���@�삪���Y�p�~��������Ƃ����w�߂��������̂͂��̊��Ԃ̂��Ƃł������B�`�F�[�E�J�[�́u�����@�I�v���Y�ƂȂ��ŁA���Y�鍐�̌���������@��ɂ��F�߂��邱�ƂɂȂ����B�������ē��Ɉ��ꎵ�N��Z���̑���\���F�g���Ŋm�F���ꂽ�v���̍ō��̐��ʂ́A���������Ă��܂����̂ł���B���̂悤�Ȃ�����ʂ��Ĕ��v���I���������̔C����тт��`�F�[�E�J�[�A�v���@��A��������������ɌR���̊����͂��ׂČ��э��킳��āA�U���I�ł͂�������������̃e������Ԃ���肠���Ă������B������P�v�I�̐��֓]����ɂ́A�ق�̉��قǂ��̂��������ƂȂ����������悩�����̂��B
�@�{���V�F���B�L�́A���ꔪ�N�����̖��Ɋ��D�̌������������B�y�g���O���[�h�E�`�F�[�E�J�[�����E���c�L�[���y�g���O���[�h�ňÎE����A���X�N���ł́A�����Ȋv���ƃh�[���E�J�v�����ɂ�郌�[�j���̈ÎE����Ă�ꂽ�̂ł���B�S�{���V�F���B�L�̕����ƕՓ��Ƃ����������ꂽ�B����{�̐V�������₩�܂������юn�߂��B�u����l�Ƃ����G����X�̓��u�̎��ɑ��ď��������˂Ȃ�ʁv�ƃy�g���O���[�h�́w�N���[�X�i���E�K�W�F�[�^�x�͏������B�u�Z���`�����^���Y���͂�����R���B�G�͖����߂Ȃ̂ł���c�c��X���܂�����̂Ă邾�낤�B��X�́A�u���W���A�W�[�ɁA�z����i�v�ɕЂÂ��Ă��܂��Ƃ������̋��P���v���m�点�Ă��̂��B���c��Ƀe�������I�@���u�����A�J���ҁA���m���N�I�@���q�R�ƃu���W���A�W�[�̎c�}�ǂ����Ō�̈�l�܂şr�ł���B�w�u���W���A�W�[�Ɏ����x����������̃X���[�K���Ƃ���v�B�܂��w�v���E�_�x�������Ă����A�u�J���ҏ��N�I�@���������N���u���W���A�W�[��|���˂Ȃ�ʎ��������A�����Ȃ��u���W���A�W�[�����N��|���ł��낤�B�v���̓G�ǂ��Ɍ����Ēf�ł����i�𐮂���B�s�s����u���W���A�I���s����|����B�u���W���A�K���̐l�Ԃ͏��Z�Ƃ��ǂ��Ď����ɒu����˂Ȃ炸�A�v���̑�`�Ɋ댯�������炷�悤�Ȏ҂͂��ׂďl������˂Ȃ�Ȃ��B�������A�J���ҊK���̎]�̂͑����ƕ��Q�̎]�̂ƂȂ�A�h�C�c�l���p���l�ɑ��ĉ̂����̂��͂邩�ɋ��낵�����̂ƂȂ�ł��낤�v�B
�@�����Łu�K���ӎ������v�����^���A�̂��߂̋����ⓚ����̓�̉����i�攪����ё�ꁛ���j���f���Ă݂悤�B�i�����j�@�w�v���E�_�x���ꔪ�N�����l���t�B�u�J���ҁA�n����A�e������B�ˌ��ɍI�݂ł���B�w��̃N���[�N�┒�q�R�̔����ɔ�����B�\���F�g���͂Ɉ���`���s�Ȃ��҂��e�E����B�\���F�g���͂ɑ�����U��グ��y�ֈ�Z���̒e�ۂ��v�u�u���W���A�W�[�͖O�����ƂȂ��G�ł���B���{�ƁA�n��A�m������ɏ��Z���Ō�̈�l�����ɐ₦��܂Ŏ��{�̗͂����ł��邱�Ƃ͂Ȃ��̂��v�B
�@�V���ɂ��L�����y�[���̌�ɐ��{�̑[�u���������B���ꔪ�N�㌎����A�\���F�g�������s�ψ���̉�ɂ����āA���[�j���̈ÎE���������Ȃ�тɃE���b�L�[�̈ÎE�Ɋւ��Ĉȉ��̂悤�Ȍ��c���Ȃ��ꂽ�\�\
�@�u�������s�ψ���́A���V�A����јA�����̂��ׂẴu���W���A�W�[�̉��l�ǂ��Ɍ��l�Ɍx������B���ׂĂ̔��v���h�Ƃ������������҂́A�\���F�g���{�̃����o�[�ƎЉ��`�v���̎v�z�̒S����ɑ��邠����P���̐ӔC�������邱�ƂƂȂ邾�낤�B�J���ҁE�_�����Ƃ̓G�ɂ�锒�F�e�����ɑ��ẮA�J���҂���є_���́A�u���W���A�W�[�Ƃ��̎�悫�ւ̑�O�I�ԐF�e�����������ĕ�ł��낤�v�B
�@���㌎�O���̒��A�����l���ψ��y�g���t�X�L�[�́A���̂悤�ȓd��ɂ�閽�߂����ׂĂ̒n���\���F�g�ɔ������\�\�u������畏��ɂ͒����ɏI�~�����ł���˂Ȃ�ʁB�n���\���F�g�ɔ������Ă������̔��v���I�Љ�v���}���͑����ߕ߂��邱�ƁB���{�ƂƏ��Z�c���瑽���̐l�����m�ۂ���B���q�W�c�ɂ����ċ͂��Ȓ�R�������͓���������ꂽ�ۂɂ͗�����ʏe�E�Y�Œ����ɒ�������B�n�����s�ψ���͗��悵�Ď��ɓ���ׂ��d�c��O�I�e�����̔����ɍۂ��Ă��S�O�A���^�͖��p�ł���v�B
�@���{�̍ō��@�ւ����̂悤�Ȍ��t�Ō���Ă���Ƃ���A���̎��s�@�ցA���̒n���@�ւ̍s���͐����Ēm��ׂ��ł��낤�B�����Ď����A�������s�ψ���̕z���������u�x���v�ɂƂǂ܂��Ă���̂ɁA�n���ł͊��ɕ��Q���J�n����������̂ł���B
�@�y�g���t�X�L�[�ƃ`�F�[�E�J�[�����̌��t�́A���ۂɂ̓��[�j�����g�ɂ���ė\������Ă����B���ꔪ�N��������ނ��j�W�j�[�E�m���S���h�s�\���F�g�ɑ������d��́A�e�����X�g�I�����̓T�^�I�ȗ��^���Ă����B�d���͓�Z�N��̈��O���N�ɂȂ��ď��߂Č��J���ꂽ�B
�@�u�j�W�j�[�E�m���S���h�Ō��R���锒�q�R�̔��������炩�ɏ����������B���N�͑S���͂����ēƍٌ��͂��������A������K�͂ȃe���������A�E�H�g�J�ŕ��m�Ə��Z�Ƃ��ė����鉽�S�l���̈����ǂ����ˎE���Ǖ�����B�������S�O���Ă͂Ȃ�ʁB�q���ɍs�����N���A��K�͂ȉB������̑{������єƐl�̏��Y�A�����V�F���B�L�̑�ʒǕ����s�Ȃ��āA�댯��h�~����B�@���N�̃��[�j���v�B
�@�E���c�L�[�ƃ��[�j���ւ̏P���͔����O�Z���ɋN�������A�㌎����܂łɂ́A�j�W�j�[�E�m���S���h�́s�Δ��v�����������ψ���t�́A���Ɏl�Z�l���e�E���Ă����̂ł���B�j�W�j�[�E�m���S���h�w�J���Ҕ_���u���`���x�͂����Ă����A�u���Y��`�҂̈ÎE���邢�͂��̊�Ă̊e�X�ɑ��āA��X�̓u���W���A�W�[�̐l���̏e�E�������ĕ�ł��낤�B�E���ꏝ������X�̓��u�����̌������A���Q�����߂Ă��邩��ł���v�B
�@�y�g���O���[�h�̃`�F�[�E�J�[�́A�����ɍS�����Ă����l���̒�����܈ꔪ�l�����Y�����B���̓r�����Ȃ����͊��l���̃{���V�F���B�L���������������A����ƂƂ��ɑ��̎҂����̉��O(����)�������ە����邱�ƂƂ��Ȃ����B�s���C�Ƌ���(���傤��)�t�ւ̂��̂悤�ȑ�ʂ̐��т́A�ԐF�e�����̐M��҂����̊Ԃɂ����Ă���A�����炩�̔������Ђ��N�������A�����Ƀ��V�A�S�y�ɐl���Ƃ���������蒅�����铹���J�����̂ł���B
�@�u���u�E���c�L�[����ѐ��E�v�����^���A�[�g�̎w���ҁA���u���[�j���ɑ���P���̕Ƃ��đS�I�`�F�[�E�J�[�̓��X�N���ň�ܐl���A����Ɍ�ɂ͒lj��Ƃ��ċ�Z�l���e�E�����v�i�����j�w�`�F�[�E�J�[�T��x��Z���B���̒��ɂ́A�����g�����⊯���ɑ��ē��݂����ޓ��Ƃ�R�\�D�A�U���Ƃ����A�������R����Y���Ƃ��܂܂�Ă����B�Ƃ��낪�c�@�[���ꐧ���̃��V�A�ł����A�Y���Ƃɑ��鎀�Y�͑��݂��Ă��Ȃ������̂��B���������ă{���V�F���B�L���͂́A���̐��̂����������e��������̎�Ŗ��E���A�G�J�e���[�i���ȑO�̎���ɍs�Ȃ�ꂽ��ȁs�ق��t�̕��@���ċ������킯�ł���B
�@�u�E���c�L�[�̈ÎE����у��[�j���̈ÎE�����̕Ƃ��āA�A���n���Q���X�N�E�`�F�[�E�J�[�͋�l�A�L�����C�E�`�F�[�E�J�[�͎O�l�A���B�e�t�X�N�ł͓�l�A�Z�x�V�ł͈ꎵ�l�A���F���V�ł͓�l�A���H���O�_�ł͈�l�l�A���F���X�^�ł͎l�l�A�k�h���B���X�N�ł͌ܐl�A�N���X�N�ł͋�l�����Y�����v�B�����Ƀ|�`�F�z�[�j�D�`�F�[�E�J�[�͎O��l�����Y�i�V�����B�G�t�ƌܐl�A���H���R�t�Ǝl�l�A�Z�~���[�m�t�Ɠ�l�̉Ƒ����܂ށj�A�y���U�ł͔��l�A�`���[���j�C�ł͉��̍߂ł��܂��ܓ������Ă����O�l�̒j�A���@���m�t�X�N�ł͔��l�A�m���S���h�ł͔��l�����Y���ꂽ�B���l�̎����́A���X�`�X���t�A�����U���A�^���{�t�A���y�b�N�̊e���ł��N�����B�X�������X�N�ł̓`�F�[�E�J�[�́A�Y���ƁA�O�n��A���Z�A�x�@�����܂ގO�l�l���e�E���A�܂��撲�ׂɍۂ��āA�����̃`�F�[�E�J�[�͓��̓I������s�Ȃ����B
�@���C�r���X�N�̎��s�ψ���́A�x�������Ńh�C�c�̑����ƃJ�[���E���[�v�N�l�q�g���ÎE���ꂽ�Ƃ�����ɐڂ���ƐԐF�e�����������ās�n���u���W���A�W�[�t�ɕ��邱�Ƃ����������B���̎��s�ψ���̃����o�[�S���͌�ɁA���̂���ю��d�ƍٔ��ʂ��ɏ��Y���s�Ȃ����Ȃōٔ��ɂ������L�߂Ƃ��ꂽ��B�����������������Ƃ��A�ی����Ȃ��������̂ł���B
�@�����́s�v���t�Ƃ�����`�����̂��Ƃł̋��Q�I��ʃe�����̒��_�����鎖���́A���̑̐��̒��S�l�����[�j���ɑ��ĉʊ��ɂ�����U��グ���l���ւ̋��ԈˑR���镜�Q�s�ׂł������B���[�j���̕������������Ƃ��������A�c�@�[�����J�[�g���K(�č�)�Œ��N�߂������̃e�����X�g�̂悭�m��ꂽ�Љ��`�҂Ƃ��Ă̌o���A����ɂ͉ߋ��̓��l�̎����ł͑����̏ꍇ����ȏ��u���Ƃ�ꂽ�Ƃ������j�I���A�����������Ƃǂ��ɂ�������炸�A�h�[���E�J�v�����͏��Y���ꂽ�̂ł������B
�@���̓����A�}���A�E�X�s���h�[�m���͂��������Ă���A�u�����������������傳�́A�P�Ȃ�ׂ₩�Ȑ����I�z���ɂƂǂ܂�Ȃ������ł��傤�B�����ꌾ�̋C�������t������̂����������t��������Ȃ��A���̋��C�Ɠ{��݂̂��������Ă��鎞��ɂ����ẮA���̊��傳�͎������̊v���ɂƂ��ċM�d�Ȃ��̂ɂȂ��Ă����ł��傤�Ɂv�i�����j�}���A�E�X�s���h�[�m���̃{���V�F���B�L�����ψ���̌��J��B
�@�����͑����A�e�����́s���R�t�Ɓs�ԌR�t�����S�Ȑ퓬�œB�Â��ɂȂ��Ă������̍őO���ɂ����邻��łȂ��Ă��d��Ȏ����Ґ����A���������Ă����B���������̏ꍇ�Ɠ��l�A���m�����͓G�������킸�펀���������B�`�F�[�E�J�[�̍ŏd�v�l���̈�l���c�B�X�́A���ꔪ�N������O���A�w�C�Y���F�X�`���x�ɘ_���\�����A���A���̌��o���͗Y�قɓ��e����Ă���
�@�\�\�u����ɖ@�͑��݂����v�B�ނ͑����Ă����\�\�u�قƂ�ǂ����鎞���ʂ��āA�����鍑�ƂŁA�푈�ɂ��Ă̊m�����ꂽ���s������������Ă����B���{�ƊԂ̐푈�́A���܂��܂ȋ���̂������ŏq�ׂ��Ă��鎩�g�̖@��L���Ă���B�H���A�ߗ��͏��Y����邱�Ƃ͂Ȃ��A�a���g�߂��U�����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�ߗ��̌������s�Ȃ��c�c�����������A��X�̓���ɖڂ�]����A���̂悤�ȗނ̂��͉̂�����������Ȃ��B���Ă͐_���Ȃ��̂ƌ��Ȃ��ꂽ�A���������@�̓K�p�����݂���v�������肷�邱�Ƃ͔n�����Ă���B���N�ɑ���퓬�ŏ������҂͂��ׂ��炭�E���\�\���ꂪ����̖@�Ȃ̂��B�u���W���A�W�[�́A��������Ɏ���Ă��邪�A��X�͖���������䂪���Ƃ��Ă��Ȃ��B���ꂪ��X�̎�_�ł���d�c����̖@�͖�������������Ă��Ȃ��A�悤�₭���݂��̋��\�Ȑ퓬�̒��ł���͌`���Ƃ����̂��B��X�͂���ɒʋł���悤�ɂȂ�˂Ȃ�ʁd�c�G�͉�X��S�l�A��l�Ƒ�ʂɎˎE���Ă���B��X�͈ˑR�Ƃ��Ĉψ���Ɩ@��ł̒������c�̖��ɓG����l�ÂˎE���邾�����B����ł͓G�ɑ���ٔ��͕s�K�v�ł���B���N���G��|���Ȃ���A�G�����N��|���B������G�ɕ��ӂ����O�ɓG�ӂ���v�B
�@���ꂪ���c�B�X�̓���ɑ��錩���ł���B�����ɓ����M�҂̑��̕�����̈��p�����邪�A�ނ̃C�f�I���M�[�S�̂���Ԃ������т��Ă��邱�Ƃ��悭�݂ĂƂ��B�ނ́A�����������ꂽ���v�����q���ق��@��ɂ��Ę_�q���Ă���\�\�u�N�i�ɍۂ��A���̎��l���\���F�g�ɑ��ďe�������Ĕ��t�����̂����t�̏�Ŕ��t�����̂��ɂ��ď؋������߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B�悸���̎��l�ɁA�ނ��ǂ̊K���ɑ����Ă���̂��A�Љ�I�o�g�͉����A�ǂ̒��x�̋�����ǂ�ȐE�Ƃɂ��Ă����̂��A��q�₹�˂Ȃ�Ȃ��B����ɑ�����A�퍐�̉^����������̂��B���ꂪ�ԐF�e�����̂��Ӗ��ł���v�B
�@����ɂ�����c�E���ɂ͔@���Ȃ鐧�����ۂ����Ȃ��������A�����̃e�����ɂ��Ă����l�ł������B�n���̎���́A��U���҂̎�ɂ���Ďn�����ꂽ�U�q���ǂ��܂ŐU�����g����̂����₪�Ď������ƂƂȂ����B��s�̐��{��َ҂́A�_���I�������̑����̉��ł��̕ڂ��ˑR�Ƃ��Ĕ��v�����q�ɑ��Ă݂̂ӂ���Ă������Ƃł��낤�B�����Ӌ��̒n�֍s���A���̗��_�͒������c�ȉ�����A�v�������S�Ɏ���ꂽ���₻�̐l���ɏP���������Ă����̂ł���B���ꂩ��q�ׂ�̂́A�������̑}�b�A�^���̘b�ł���A���V�A�̉ʂ��Ȃ���m��ʔ߂��݂̂ق�̈�f�ЂȂ̂ł���B�i���j�ȉ��̈��p�͈����N�ɂ�����_���̈�A�̕Ɛ��{�������Ȃ���Ă���B
�@�R�X�g���}���E���j�B���ł́A�u���s�ψ����\���n�[���t�Ɣނ̓��������͋����قǖ\��܂�����B�\���F�g�ɂ����鐿��҂ւ̉��ł͓��풃�ю��ł��邵�A⚑ł͌����̂��ׂĂ̑��ōs�Ȃ��Ă���B�Ⴆ�x���\�t�J�ł́A�_���͌��łƖ_�ʼn����Ă����B�ނ�͒��C��E���Œ����Ԑ�̒��ɍ��点��ꂽ�B�E�����X�N�n���ł́A���n�ꃍ�t�Ƃ��̔z���͒P�Ƃł͂Ȃ��A�o���i�r���X�N���s�ψ���ψ��̃K���z�t�A�}�[�z�t���̑��̎҂�������Ă����B�ނ�̓p���̒����̍ہA�Ƃ�킯�����U�������B���ɋ߂Â��ƁA�K���z�t�ƃ}�[�z�t�̕������͏Z�������������߂ɔ��C����̂��킾�����B���l�����͑ۑłɑς��邽�߂Ɍܖ��ȏ���̃V���c�̏d�˒��������肷�邪�A�ۂ͝�(�悶)�ꂽ���C���[�Ȃ̂ł��܂���ɂ������A�x�X�V���c�����ɋ���ł��܂��A���ꂪ�����Ɠ��ɐZ���Ĕ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂł������v�B
�@����ԌR���m�͂������Ă���A�u�}�[�z�t�͉�X�ɑߕ߂����_���������҂ǂ������悤�ɁA�܂�⚂ł������̂߂��悤�ɖ��߂����B�ނ́A�ނ���������ĂĘA�s������ɑۑł��ă\���F�g���{�̋��낵�����v���m�点�Ă��A�Ƃ����̂������v�B�܂��R�X�g���}���̂��鑺�̏W��͋L���Ă���A�u�ނ�͎�������łڂ����Ƃ��Ă���B�������̎��R�ӎu�ɑ������͂߁A���������܂�ŋ����ȉƒ{�łł����邩�̂悤�Ɍy�̂��Ă���v�B
�@����ɕʂ̕ɂ��A�u�T���g�t���̃n���@�����X�N�n���ŁA�ԌR�Ɠ��ʐH�ƒ��������������ɓ��������B�O�l�̏��Z����ɑ��l�����W�߁A���̗����g�߂Ă����֎Ⴂ��������ǂ����ނ悤���߂����B�w��Ԕ��������ǂ��ɎႢ�������I�x�B�_�������͋��сA�ߖ������n�߂��B�Փ˂��N��A�ԌR���m�̈�l�����C�����B��Ӓ��킢�͑����A����ɏ��Z�̈�l�͎E����A�c���l�͒����������ƈꏏ�ɓ����������v�B�������Ė����́s�_���\���t�������ɋN�邱�ƂƂȂ������A����͌�ɖ����߂ɒe������Ă������̂ł���B
�@����̑��ł́A�`�F�[�E�J�[���_����O�������q�ɂɕ����߁A���ɂ��ďe�̑�K�ʼn��ł����B�n�������͎��̂悤�Ɍ���Ă����A�u�����ł͉�X�ɂ����������A���͒��r���[�ɂ����́A���߂�������ǂ��̂��A�Ɓv�B
�@�}�J���B�G�{�̔_���̕ł́A�u�̂́A���̌x���͔_���̔w�ɂ܂�����Ƃ������Ƃ͂��Ȃ��������A���̃R�~���j�X�g�����͋Y��ɔ_���̔w�ɏ��̂ł���v�B���B�e�t�X�N���̃r�G���X�N�S�ł́A�_���͒n��\���F�g���s�ψ���̖��߂őۑł��ꂽ�B�X�������X�N���̃h�D�z�[���`�i�́u���s�ψ������͈�����̂Ȃ炸���̂ŁA�\���̐ӔC�͋����Ĕނ�ɂ������v�B�����n���ψ����́A�H�ƈψ�����̎��̂悤�Ȗ��߂��������A�u�s�������Ɉꖜ�v�[�h�̃p�������o����̂ɎO���̗P�\��^����|�z������B����ɏ]��Ȃ��ꍇ�A�������邷�łɃo���o�����J�̑��ň�l�̂Ȃ炸�҂��ˎE�����悤�ɁA�S�����ˎE����B�����������Y�@�ւ́c�c�s���]�̏ꍇ�A�Ƃ��ɔڗ�Ȃ��܂������ꂽ�ꍇ�ɂ́A�e�E���邱�Ƃ�������Ă���c�c�v�B
�@�I�����[�������u�j�C�ł́A�ł̔�����[�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃɑ��đۑŌY�Əe�E�Y�����s���ꂽ�B��l�̔_�����莆�ŕ��Ă���A�u�ނ�͎��������牽�������c�炸���D���čs���܂����B�w�l����͈ߗނ≺���������A�j����R�[�g�A���C�⎞�v�Ƃ��������̂܂ł��ł��B�����ăp���͂�������܂ł�����܂���v�B�܂��ʂ̔_���͂��������Ă����A�u�ނ�͎������̎��グ�ۑł��܂����B�����ď]�����Ƃ��Ȃ�������l�̒j���E���܂����A���̒j�͐��_�ُ킾�����̂ɁB�ނ�́A��R�̏����q��p���t���b�g��u���Ă����܂������A�������͂�����݂�ȏĂ��Ă��܂��܂����B�R�ƋU��ȊO�̉����ł��Ȃ�����ł��v�i�����j���̍Ō�̎莆����т���ȍ~�̎莆�́A�}���A�E�X�s���h�[�m���̃{���V�F���B�L�}�����ψ���́u���J��v������p���ꂽ���̂ł���B
�@�ȏ�̏��q�������Ċv���̍����\���ȐF�ʂŕ`�����邾�낤���H�@��X�́A���܂ŏq�ׂ����Ƃ���s�Љ��`�ւ̈ڍs�t�Ƃ������_�����Ƃ��ł��邾�낤���H�@��X�́A�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��Ɍ���������߂��̂��낤���H�@�ہA�����ł͂Ȃ��B�������̐悪����̂��B��X�͂���ɐi��ŁA���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@����ɑ��̎莆�͏q�ׂĂ���A�u�������́A�p�����B������͂��܂���ł����B�z���Ŗ�����ꂽ�ʂ�ɁA��l�����N���Ƃ��ċ�v�[�h�̃p�����Ƃ��Ă����������Ȃ̂ł��B�Ƃ��낪�ނ�́A���v�[�h�����c���Ďc��̓�v�[�h�����o����Ƃ̖��߂�`���Ă��܂����B�������͂��̒ʂ�ɂ��܂����B���ꂩ��{���V�F���B�L�Ƃ��̕������Ƃ�����Ă��āA���������j�Ă��܂����̂ł��B�Ƃ��Ƃ��������͋N�����܂����B���Ԃ̓��t�m�t�X�N�n��ł͈������A�C���ɂ���Ď������͉�ł������܂����B���X�͉��ɕ�܂�A�Ɖ��͒n�ʂɈ����|����܂����B����ł��Ȃ��������͂��ׂĂ������o�����̂ł��B�������͕��a�I�ɂ����������Ƃ��s�Ȃ������Ɩ]��ł��܂����B�������͓s�s���Q���Ă��邱�Ƃ�m���Ă��܂������A���������������������悤�Ƃ͎v���Ă͂��Ȃ������̂ł��v�B
�@����ɂ�����̎莆�ɂ́A�u�ނ�́A�l�������Љ�v���}���ł�������A�܂����݂������ł���Ƃ������R�����ł��̐l�X���E�����̂��B�Ⴆ�R�e���j�`�ł̓}�z�[�m�t�ƃ~�V���m�������ނ炪�A�����Љ�v���}��������Ƃ������R�����ŎE�����̂ł���c�c�������ނ炱���l���v���̐^�̑��q�����ł���A���̐[�݂���N��������҂����������B�ނ�͏�ɂ��̎p���𐳂��āA�����Ɍ��g�����̂ŁA�~�V���m�̌��ꂽ�����鏊�ŁA�ނɂ��Ď��ۂɓ`�������܂��قǂł������v�B�ނ�́u��X�̈�Z���v�������̑o���ɒS���ĂȂ��Ƃ��������̉p�Y�����v�������A�ƃX�s���h�[�m���͂������Ă���A�u�~�V���m�́A�����̕���@�邱�Ƃ����ۂ������ߏ��Y�̒��O�ɍ����ڂɂ��킳��܂����B�}�z�[�m�t�͎��ʑO�Ɉꌾ���������^������Ȃ�A�Ƃ����������ł����F�߂��̂ł��B�ނ̍Ō�̌��t�́w���E�Љ��`�v�����I�x�ł����v�B
�@�J���K�����W���X�N�S�ł͈ꎵ�Z�l�̒j�Ǝl�l�̏����t���e�E���ꂽ�B�ނ�́A�e�e�ɓ|��čs���Ȃ���A�u����Ȃ��\���F�g���͖��I�v�Ƌ��̂ł������B
�@����ɑ��̎����ɂ��Ắ̕A�����q�ׂĂ���\�\�u�X�n�b�N�S�ɂ́A�l���ɂƂ��ɐ��q����Ă������B�`���X�N�̐��ꑜ���������B���̑��́A���̑S�Z���ɓ`�����A�g�܂����u�a�ɋꂵ�߂��Ă����B�����Ől�тƂ́A�~�������߂�F����Ɛ��ꑜ(�C�R��)�ւ̍s�i���v���������B�Ƃ��낪�`�F�[�E�J�[�̌S�ψ����́A�i�Ղ�ߕ߂��A���̐��ꑜ��v�������̂ł���B�{���Ŕނ�́A���̐��ꑜ���ȂԂ���̂ɂ��A����f�������A���̏����������܂킵�A����ɁA�i�Ղ�����Ƃ�������@�ŐJ�����߂��B�X�n�b�N�S�͔��ɒx�ꂽ�Ƃ���ł���B�l�тƂ͌��V���A�w���q���V�l���ꏏ�ɂȂ��Đ�����Ƃ肩�����ɉ������B�`�F�[�E�J�[�̌S�ψ����́A�ނ�ɑ��Ĕ��C�����v�B
�@�ڌ��҂ł���_�v�̓X�n�b�N�����ɂ��Ă��������Ă���A�u���́A���m�Ƃ��ăh�C�c�R��ɐ������̐퓬���o�����Ă����B�������A���̂悤�Ȍ��i�͖������Ėڂɂ������Ƃ��Ȃ������B�e�ۂ͔ނ�̗���o�^�o�^�ƂȂ��|���Ă������B����ł��ނ�͂��ꂪ�ڂɓ���Ȃ����̂悤�ɁA�����҂����z���đO�i���������B�ނ�̖ڂ͑����ɔR���オ��A�������͂��̎q�������ɂ�������������߁A�w���ꂳ�܁A���~���������A�ǂ������b�݂��B�������F�A�M�����܂̂��߂Ɏ��ɂ܂��x�Ƌ��тȂ���B�ނ�́A�����̂�������͂��Ȃ������̂��B�����́A���ɑ����̐l�тƂ��A��]�I�ɂȂ����{���V�F���B�L�̎�ł��̓��E���ꂽ�v�B
�@��������Ŏ~�����Ƃɂ��悤�B��X�͂��ׂĂ�������߂��킯�ł͂Ȃ��A���A���ɂ��������Ƃ���ŁA��X�����ׂĂ�������߂����Ƃɂ͌����ĂȂ�Ȃ��A�Ȃ��Ȃ�A���������L�q�͖����Ɍp������A���̋���ׂ������Ƒ��l���Ǝc�s�ƂŐl�̐S���������h�蓮����������ɈႢ�Ȃ�����ł���B���͂��X�́A���������X�̎����ɗ����߂邱�Ƃ͂Ȃ��B��X�́A�����Ŕ�����ꂽ���t�ƈׂ��ꂽ�s�ׂƂ��L���ɍ��݁A��Ƀe�����A�{���V�F���B�L�̃e�����ɑ��čŌ�I�Ȍ��_�������ۂ̗ǐS�Ɨ����̈ꏕ�Ƃ��悤�B
�@��P�U�́A�t�F���N�X�E�d�E�W�F���W���X�L�[�@(�S���A�o�D�Q�O�O�`�Q�P�O)
�@�t�F���N�X�E�G�h�����h���B�`�E�W�F���W���X�L�[�́A�`�F�[�E�J�[�̑S�\�̓��ځ\�\���̋��t�A�����҂����či�Y���ł������B�ނ́A�ߋ����ے�����l���Ƃ��āA����ɂ͖����ɑ�����߂Ƃ��āA���j�Ɏc�邱�ƂƂȂ����B���̂��Ƃ̌̂ɁA�ނ̐��U�́A��w���Ӑ[����������ɒl����̂ł���B���̑O�ɂ́A�W�F���W���X�L�[���g�̎�ɂȂ�A���̏����̍����������q�ׂ��L�^������B�ꔪ�㔪�N�ɓ�Z�̎�҂ł������ނ́A�ŏ��̗��Y�n�k�����V�A�̃m�����X�N���A���̎o�ɏ��������Ă����\�\
�@�u�o����́A�q�����҂̍��̖l���䑶�m�ł����B�ł����l�́A�������͂�����Ƃ����l����g�ɂ�����l�ł���Ɗm�M���Ă��܂��B�l���́A������Z�Z�N�̎�����~�̖�ł��|���悤�ȈӖ��łȂ�A�l��j��ł���ł��傤���A����ł��l��ς��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�l���͖l�̐i�ޓr���߂Ă���܂����A�����Ėl���Ƃ炦�Ă��܂����v���́A�l���R���s����܂ŁA����ɐ��ւƖl���^��ł䂭���Ƃł��傤�B�������������l�̓������~�߂邱�Ƃ��ł����A�Ƃ����킯�ł��v�i�����j�S�Ĉ��p�́A���O��N�ƈ��O���N�́w�v���E�_�x�����Ȃ���Ă���B
�@�����������t�́A�ӎ�������ْ[�R�⊯�̎��摜�����Ă���B���̎�҂́A�����̈ꐶ�̓W�J�\�\����͎l��̎��ɐS������ɏP���Ė�������\�\�𐳂����\�����Ă����A�����ނ́A�����Ɓs���t�̒��Ɏ����������o���Ă����̂ł���B�����A�ނ͂������鍢����Ȃ����l�\�\����l�Ƃ����\�\�̎��ɑ������邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@��ɂȂ��Ĉ��Z��N�ɁA�|�[�����h�̃Z�W�F���c�č�����̎莆�ŁA�W�F���W���X�L�[�́u�l�́A���r���[�ɑ��舤������͂ł��Ȃ��B�l�͎����̑S���݂𓊂��o���˂Ȃ�Ȃ��A�����łȂ���Έ�͖��Ȃ̂��v�B�����������t���܂��A���̐l�Ԃ̌���I�ȐS�𖾂炩�ɂ��Ă���A�Ƃ���A��X���ނ̎莆��ǂގ��A�����Ȃ����@�����̎Љ��`�҂����̂��A�Ɩ₤�͓̂��R�ł���B���̍������L�̈��Z���N�܌���Z���t�̏������݂œ����č��ɂƂ���Ă���ꔪ�̏��H�̔ߌ��I�ȉ^���ɂ��ċL�����ہA�ނ͂��̋^��ւ̖��m�ȉ�^���Ă����\�\
�@�u����ׂ��������I�@�������A�q���̎����炻����������Ȑ������h���Â����Ă���l�тƂ��A�ǂ�قǑ������邱�Ƃ��H�@�����邱�Ƃ̖{���̍K���Ɛ^�̊��тƂ��A���Ƃ����̒��ɂ����Ă������A�����Č��Ă͂Ȃ�ʂƐ鍐���ꂽ�l�тƂ��A�ǂ�قǑ������邱�Ƃ��I�@�ɂ�������炸�l�Ԃ́A�K���������Ƃ�A�Ƃ鎑�i�������Ă���B�ق�̈ꈬ��̐l�����A���S���Ƃ����l�тƂɑ��āA��������ۂ��Ă����̂ł���B�����l�ނ��Љ��`�̐��ɏƂ��o����Ȃ��Ƃ���A���ɂƂ��Đl���͐�����ɒl���Ȃ����낤�A���̂Ȃ�A���́s���t�́A�Љ��`�������̐��E�Ɛl�ނƂ��ۂ��Ȃ�����A�����Ă����Ȃ�����ł���B�Ƃ��Ắs���t�́A�����������݂Ȃ̂��v�B
�@�����萔���O�A�l���O�Z���ɁA�ނ͂��̓��L�ɂ͂邩�ɏd�v�ȏ������݂��s�Ȃ��Ă����\�\�u�����ł͂����Ă��C�f�I���M�[�I�ɋ��͂��ꈬ��̐l�����A���Ȃ̎��͂ɑ�O�����W���A�ނ�Ɍ����Ă�����̂�^���A�ނ�ɐV���Ȋ�]��������ł��낤�c�c���(�ނ�)�̐l�тƂ̌����͖��ʂɗ�����Ă͂Ȃ�Ȃ����A��O�̋Q���Ƌꂵ�݁A�q�������̋������A��e�����̐�]�́A����������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��v�B
�@�����̕��͂ɂ́A��O�ɑ���[������S�A�ނ�̖��͂�コ�ɑ���̎��A�Ƌ��ɁA��O�������A�ނ�̋��̕��Q���s�Ȃ������Ƃ����M��ȗ~�]�\�\�����������ׂĂ��܂܂�Ă���B�W�F���W���X�L�[�́A��O�̕��Q�҂ƂȂ��Ă����ł��낤�B�����A�ނ͑�O�����g�̉^���ɂ��Č���������̂�F�߂�̂��낤���H�@��x�ɂ킽���Ĕނ́s�ꈬ��̐l�тƁt�\�\�@����͑S���E�̕x�𗪒D���Ă���A��������́u���Ȃ̎��͂ɑ�O�����W���Ă���v�\�\�ɂ��Č��y���Ă���B���j�I�����́A���̋��͂ȏW�c�̊Ԃł���������̂ɔ����āA�l����O�͂��̓����̑Ώە��ɂ����Ȃ��̂ł���B
�@���N�ɂ킽���ăW�F���W���X�L�[�́A�@������������A�č��ɂԂ����܂�A�V�x���A�֗��Y����A�J�[�g���K(�č�)�ʼn߂����B�ނ̌������Z�C�Ȑ��i�́A���̋�Y�A�����A���]�ɏ[�����S���Ԃ�ς������̂ɋ�ɂȂ킹�邱�ƂƂȂ����B�ނ̐S�́A�ΎR�̂悤�ɁA�v���̔��������Ē���߂��͂ł��ӂ�����ł������B���̗͂Ƃ͉��������̂��H�@����́A�܂����Ɂs�}���҂���}���҂����Ȃ��t�V���Ȑ����A���ۓI�ȎЉ��`�I�g�D�ւ̊�]�ł���A���ɁA���Љ�ɑ���R�c�A�{��A�����̍r�ꋶ���͂ł������B�������������������̑ΏۂƂȂ����̂͒N���H�@�W�F���W���X�L�[�́A�{���V�F���B�L�I�Ӗ��ɂ����Ăł͂��������A�Љ���`�҂������B����̂ɔނ́A����ׂ��v�����A�J���ҊK��������ȉe�����y�ڂ��u���W���A�����{��`�I�v���ƌ��Ȃ��Ă����B���������Ĕނ̓G�́A�c�@�[�������̐��̂��ׂĂ̑�\�ҁA�n��K���A�����I�ɂ́A��H�Ǝ҂���Ǝ҂����ł������B�ނ̊č���i�l�N�Ԃ́j�d�J���ł̉Ս��ȑ̌��́A���̍�����c�@�[���̖�l�����ւ̌l�I��������w���������̂Ƃ��Ă����B
�@��Ɉ��ꎵ�N�ɂȂ��Ĕނ́A���ڂ̎Љ��`�v���Ƃ������Ɋւ��ă��[�j���ƈ�v�����B���̎������Ƃ��āA�ނ̑����̑ΏہA�ނ̓G�́A���{�Ƃ��̂��́A��s�Ƃ��̂��́A���{��`�I�\���ɎQ���������ׂĂ̎��A�f�Տ��A���l����Ɂs���@�Ɓt�̂��ׂĂ��܂ނ��ƂƂȂ����B���R�̂��ƂȂ���A����ނ̓G�Ύ҂ɂ́A�{���V�F���B�L�ɔ����鉸���h�Љ��`�҂̈��W�c���܂��܂܂�Ă����B
�@���́A�ǂ����ă��[�j���������̐l���̒�����ނɁA�s���ψ���t�����`�F�[�E�J�[�Ƃ��Č��܂݂�̗E�����͂��邱�ƂƂȂ����A���v���ɑ��铬���@�ւł���g�D���A�C����悤�ɂȂ����̂��͒m��Ȃ��B���ꎵ�N���Z���A�ނ͂��̏���ψ����ɔC�����ꂽ�B����ǂ��A���炩�ɂ������������\�\�G�ɑ��錵�����Ď��Ɩ����߂Ȕ��Q�\�\���A�W�F���W���X�L�[�ɂ��̍˔\������@���^�����̂ɔ����āA�ˑR�Ƃ��ă��V�A�̉���^���ɂ�����`����g�ɑтсA�c�@�[���č��̋�ɂ����Ȃ��L���ɂƂǂ߂Ă��鑼�̒����ȃ{���V�F���B�L�����́A���̎d������K���݂��Ă����B
�@���̐��i���炵�āA�W�F���W���X�L�[�́A���Ȃ́s�E���t�Ɋ��S�ɖv�������B���̃}���N�X��`�I�P���ɂ�������炸�A�ނ́A�Љ�I���K���Ƃ��̋@�ւƂɑ��铬�����A�X�̊K���G�ɑ��钼�ړI�푈�ɒu���ウ���B���������푈�̑����ɂ����ẮA�ނ͎����̍s����ɁA���̓G�̎Љ�I���i����ł͂Ȃ��A���̗e�e�Ƃ��g�̂��Ƃ����������̓I�݂�������l���ɓ��ꂽ�A�܂�Ƃ���ނ́A�G���l�I�ȓG�Ƃ��đ��̂ł���B���̓_�ɂ����A�W�F���W���X�L�[�̋���ׂ��댯��������ł����̂��B
�@�`�F�[�E�J�[�̐�����ŏ��̐��T�Ԃ́A�܂��ɂ��̊댯�Ȑ��i�������������̂������B���̐E������x�ɏW�߂邱�Ƃ��A����߂č���ł��邱�Ƃ͔����Ă����B�W�F���W���X�L�[�́A�����̍ł��ٖ��ȋ��͎҂Ƃ��ă��c�B�X�����G�E�y�g���X��I�A���A���̓�l�̖��͂₪�ċ��M�I�Ȏc�E���̏ے��Ɖ����Ă䂭�i��X�͌�ɔނ�̃e�����̗L�v���ɂ��Ă̐��������ƂɂȂ낤�j�B�����Љ�v���}�́A�`�F�[�E�J�[�̑S�@�\����т��́s���_�t�ɔ����Ă����B�ɂ�������炸�ނ�́A���Ȃ̊ē����s�g���邽�߂Ƀ`�F�[�E�J�[�]�c��ɑ�\�𑗂邱�Ƃ��K�v�ł���A�ƍl�����B�I�ꂽ�̂́A�A���N�T���h�����B�`�Ɛ����G�����A�[�m�t�ŁA��l�Ƃ����x�Ȑ��_�͂����Ȃ����l����`�I�ȎЉ��`�҂ł������B�ނ�͊��x�ƂȂ��A���̐g�̖т��悾�悤�ȋ��c���ނ��������Ăق����Ɣނ�̓}�ɒQ�肵�Ă����B�����āA�A���N�T���h�����B�`�͎��Ȃ̔C���̑㏞�Ƃ��Ă��̐������x�������ƂƂȂ����\�\�@���ꔪ�N�����A�ނ̓W�F���W���X�L�[���g�ɂ���ďe�E���ꂽ�̂ł���B
�@�����A�����`�F�[�E�J�[�́s�㕔(�w�b�h)�t�ɉ��炩�̕��@�ł��̔閧�x�@�I�@�\���v���̎��Ƃ̌̂ɐ��������悤�Ǝ��݂�l�тƂ������ɂ��Ă��A�`�F�[�E�J�[�̋@�\���ꎩ�̂�����������d����e�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ł��낤�B���̋@�\�́A��i�̖��߂ɋ^���������ƂȂ��A�������������i��p���Ď��s����悤�ȐM���ł���l�Ԃ�K�v�Ƃ��Ă����B���v���ɑ��āA�Ӌ�(�T�{�^�[�W��)�ɑ��āA���@�ɑ��āA�킢�̉ΊW�͐��ė����ꂽ�B��������щ����̃`�F�[�E�J�[�����́A���[�ȃC�f�I���M�[�������A�`���Ƃ��C�ǂ������q�\�\�r�͂������A�ˌ����֒e�𓊂���̂��f�����l�Ԃǂ��\�\�̒�����肠���莟��ɑI�����ꂽ�B�ނ�́A������Ɖ�������@�ւ֓��ݍ��ތ����A�q�₵�������錠���A�l�̎����ׂĂ̌��������錠���������Ă����B
�@�Ƃ���ŁA�S�I�`�F�[�E�J�[�͂��̊������y�g���O���[�h�Ɍ����Ă����̂ł͂Ȃ������B�x����n���`�F�[�E�J�[���A���������ׂĂ̎s��֘A�n�ɊJ�݂��ꂽ�B�n���̃`�F�[�E�J�[�ł́A�����Ő����Ȑl�тƂ�I�ׂ�\���͂͂邩�ɏ��Ȃ��A�����́A���̕s���̐l�ԁA�Â��O�����������l�ԁA�����Ĉꕔ�͂��Ẵc�@�[����@�x�@�܂��I�t���[�i������������ꂽ�l�ԁA�ň�w�}���Ɉ�t�ɂȂ��Ă������B��ʎs�����x�z����r�����Ȃ����͂��A�ނ�̎�ɏW�����ꂽ�B�������܃��V�A�S�y���`�F�[�E�J�[�̊��킵���������̌��͂̉��ə�Ⴗ�邱�ƂƂȂ����ɂ��Ă��A�����������ɂ͂�����Ȃ��B�s���v���t�I������|����͂��̑g�D���A���������ȕs���Ɨ}�����ő�̔ƍߎ҂Ɖ����Ă������̂ł���B
�@�����́A�W�F���W���X�L�[���g�A�`�F�[�E�J�[�̊댯�����������Ă����B���́A���ꎵ�N���I�낤�Ƃ��鍠�A�W�F���W���X�L�[���\���F�g���{�̊t�c�̋x�e���Ɏ��̏��ւ���Ă������̂��Ƃ������Ă���B�ނ́A�i�@�l���ψ������܂߂āA�s�@�t�Ƃ������̂��D��ł��Ȃ������B�͂��߂���ނƃ��[�j���́A�`�F�[�E�J�[��ʌ́s�x�@�ȁt�Ƃ��Ďi�@�l���ψ�������Ɨ������n�ʂɒu�����̂ł���B���ꂪ�����ŁA�`�F�[�E�J�[�Ǝ��Ƃ̊Ԃ́A�₦����ْ��W�ɂ������B
�@��������߂čl�����l�q�ŁA�W�F���W���X�L�[�͎��ɁA���ɓ��@���Ă���y�g���O���[�h�̎R�t�ǂ��̒��Ƀ`�F�[�E�J�[�����������𑗂荞�ނ̂͌����ȍǂ����ɂ��Ęb���͂��߂��B�ނ͖��炩�ɁA�v�����{���\����҂��ϋɓI�ɓ��@�ɉ����A���̂��Ƃɂ���č��̌o�ς��@������菕��������Ƃ����悤�Ȏ��Ԃ̂��\�Ԑ��������Ƃ��Ă����̂ł���B�������̂��Ƃ�ނɎw�E����ƁA�ނ͓��ӂ��邩�̂悤�ɂ��ȂÂ����A�����_�����A�u�����A���ɂǂ�ȕ��@�œz���Ɠ����悢�̂��H�v�B
�@�}���A�E�X�s���h�[�m���͌�ɂȂ��āi���̃{���V�F���B�L�}�����ψ���́w���J��x�Łj�A�`�F�[�E�J�[�̈ψ����ɂȂ肽�Ă̍��悭�W�F���W���X�L�[���A���̊���u�y�g���O���[�h�łق�̐��l�̗��D�҂��e�E������ŁA���l�̂悤�ɑ����ɂ���ɂɂ䂪�߂āv�߂��Ă������Ƃ��A�z���N�����Ă����B�ނ��A�`�F�[�E�J�[�̎c�s�s�ׂ��Ȃ����{�\�I�Ɍ������鎩�Ȃ̗ǐS��݂点�邽�߂ɁA����ɓ������Ă���Ƃ����M���ׂ��\���g�܂����̂��A�̂Ȃ����Ƃł͂Ȃ������B�ނ͂��̐����I�G�Ύ҂��y�̂��Ă����A���A�l�Ԃɓ��̓I�����������O�ɂ́A�����̊ԁA�k����̂������B
�@��������A��Z���v�������ł̏Փ˂������Ă����B�v�����̂��̗̂̈悪�g�債�Ă䂫�A���̊g��Ƌ��ɁA�v�����������˂Ȃ�Ȃ��l�Ԃ̐��������Ă������B���������l�ԂƂ́A���͂�u���W���A��n�傽���ɂƂǂ܂炸�A���̖��̉��Ɋv�������ꂽ�J���Ґl���\�\�v�����^���A�Ɣ_���\�\�����₻�̒��Ɋ܂܂�邱�ƂƂȂ����B��҂��A�N�Ղ���}�ɔ�����悤�ɂȂ�ɂ�āA���X�ɔނ���܂��s�K���G�t�ƂȂ�A���̐�y�����Ɠ����悤�ɗe�͂Ȃ��f��������̂ƂȂ����̂ł���B���Ύ҂̐������傷��ɏ]���āA�W�F���W���X�L�[�ƃ`�F�[�E�J�[�̌��́A�����Đ������A�e�����A��������Ƃ����ނ̖�]�A���܂����債�Ă������B���ꔪ�N�܌����ɁA�`�F�[�E�J�[�ψ����Ƃ��Ă̎����̐E���ɂ��āA���̍Ȃɏ������������ŁA�ނ͏q�ׂĂ���\�\
�@�u���͍őO���̕����ɔC������Ă����A�����Ŏ��̌��ӂ́A���ГI�Ȏ��Ԃ̂�����ׂ��댯���Ɠ����A��������邱�ƁA����ɁA�G���o���o���Ɉ����ɂ������āA�����Ȃ�Ԍ��̔@�������߂ƂȂ����Ƃł���v�i�����j���̈��p�́A���O���N���Z���t�w�v���E�_�x�̃W�F���W���X�L�[�v�l�̘_������Ȃ���Ă���B�T�_�͎��̂��̂ł���B
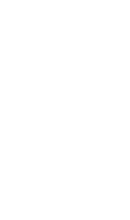
�W�F���W���X�L�[�́A�P�X�P�W�N����S�N�ԂŁA�P�Q�V�R�R�l�����Y�����B
�ނ́A�w���Ƃ������̎҂̓���ɐn��U�艺�낷���Ƃ�����ɂ���A
�`�F�[�J�[�͊v�������A�G��ł��j��Ȃ���Ȃ�Ȃ��x�Ƃ����B
�R���N�G�X�g�����w�Ԃ��鍑�|�ʐ^�Q�V�O���A�ڂŌ���\�A
�̉B���ꂽ���j�x(�����ʐM�ЁA�P�X�X�Q�N�A��ŁA�o�D�T�W)
�@�����ł���v���̍��Ƃ�N�I�������������Ɩ\�͂Ƃ𗝉����邽�߂ɂ́A�l�͂����������t���A���ꔪ�N�܌��Ƃ����̃R���e�L�X�g�̒��ŋᖡ���˂Ȃ�Ȃ��B���̎��ȗ����S���Ƃ������V�A�l���̐��_�Ɠ��̂Ƃ��A�ǂ�قǑ����A�ǂ�قǐ[���A�r�p�������Ă��������𐔓I�ɊT�Z���邱�Ƃ����A����Ȃ��Ƃł���B��X�́A���̓V����Ƃ̑̐��̋���ׂ��s�ׂƈ��ꔪ�N�Ƀ`�F�[�E�J�[�̉��ɊJ�n�������i���ꔪ�N�`�����N�j�̊��Ԃ�ʂ��Čp�����ꂽ�e�����Ƃ�{���̂�����Ƃ���ŗᎦ���Ă����B�����̗��j�Ƃ́A�{���V�F���B�L���ƂƓ��`��Ɖ������i�v�I�s�e�����ɂ�鐭�{�t�\�\�l���̍���ƎE�Q�A�z��I�J���L�����v�A�l���A�u�ٔ��v�ɂ��\�\�̑S�̌n���A�`�F�[�E�J�[�ɂ���ē������ꂽ�̌n�̉����ɂ����Ȃ����Ƃ���L���˂Ȃ�Ȃ��B
�@�W�F���W���X�L�[�Ƃ��̓��������́A���̎���������A�l���̖��E�A�ނ�̕n�������Y�₻�̉ƒ됶���̔j��Ɋւ��閽�߂�����ƂȂ��������B�ނ̎�͈�u�̐S�̓����ɂ����k���͂��Ȃ��������낤���H�@�ނ͎�����A�͂���Z�N�O�ɂ��̍������L�Ɂu��O�̋ꂵ�݁A�q�������̋������A��e�����̐�]�v�ɂ��ď����L�������Ƃ��A�����o���͂��Ȃ��������낤���H�@�������͂���ɂ����ۂ�ނ̕W��(�E�I�b�`���[�h)���u�G���o���o���Ɉ����v���Ƃւƕς���Ă��������ɁA���������v�z����̒N�̂��߂ɂȂ����Ƃ����̂��B
�@�����Љ�v���}���s�M�ƌ����̔O�������ă`�F�[�E�J�[�̊����ɓG���Ă������Ƃ́A���̋@�ւ̒a���ɍۂ��ăW�F���W���X�L�[�Ƌ��ɂ�����G�E�y�g���X�̋L�q�̒��Ŗ��炩�ɂ���Ă���B�ނ́A����Z�N�ɏ����Ă���B
�@�u�ŏ��̍��l���ψ���c(�\���F�g)�́A��̓}�A�������Y�}�i�{���V�F���B�L�j�ƍ����Љ�v���}�̃����o�[�ɂ���č\������Ă����B�����A�i�@�l���ψ����́A�\���F�g���͂̓G�Ƃ̐킢�ɂ����鑽���Ƃ��f�łƂ����[�u�ɂ͂��ׂău���[�L�������Ă��������Љ�v���}�̃X�^�C���x���O�ɗ������Ă���A�ނ̓`�F�[�E�J�[�����Ȃ̎x�z���ɏ]�������悤�Ǝ��݂Ă����B�����Љ�v���}�́A�`�F�[�E�J�[�̎�������Ƃ��Ƃ��֒����A���̌����ɒ��킵�Ă����v�i�����j�s��Z���̎��ҁt�ƌĂꂽ�W�F���W���X�L�[�ɂ��Ẵy�g���X�̘_���i���{�o�ŏ����s�A���X�N���A����Z�N�j�����p�B
�@�����y�g���X�́A��ɁA�{��ɖ��������s�Ȃ��Ă���\�\�u�ߕ߂������q�R�̓k�������ɏ������邩�Ƃ������ɂ��āA�`�F�[�E�J�[���c��̓��ʼn�X�ƍ����Љ�v���}�Ƃ̊ԂɁA�s���s��v������ꂽ�B�����A��X�́A���l�ɂǂ������Y����^����ׂ��������肷��ψ����C�����Ă����B�����A�����̑��Ⴊ���܂�ɂ����m���������߁A�ψ���̍\�������x�ɂ킽���Ď��ۂɕύX���ꂽ�ɂ�������炸�A��X�͑S����v�̌��c�ɓ��B�ł��Ȃ������\�\���Ƃ��Ƃ��A�����Љ�v���}�̂��߂ɁB�ނ�́A�\���F�g���͂̑��Ɉꂽ��͗��܂��ĕ�E���Ȃ��������ɋt����Ĕ��������ǂ悤�ȁA�����Z�ǂ��ɑ��鎀�Y�����ۂ����̂��v�B
�@���ꔪ�N�����ɐ������{���V�F���B�L�ƍ����Љ�v���}�Ƃ̍ŏI�I����̌�A�`�F�[�E�J�[�͏��{���V�F���B�L�^�ɍđg�D���ꂽ�B�e�����ɑ��ă`�F�[�E�J�[�ɉۂ���邢���Ȃ铝�����A������ƊO����Ƃ��킸�A���͂⑶�݂��Ă��Ȃ������B�����ăy�g���X�́A�����ւ��Ă������邱�Ƃ��ł����B�u�`�F�[�E�J�[�̑��u�́A���⊮�S�ɋ��łȂ��̂ƂȂ��Ă���B��X�́A�\���F�g���͂̋����ł͂Ȃ����̉�̂�ړI�Ƃ��鍶���Љ�v���}�������̈ӌ����l�����˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ϑ��I�Ȏ��ԂƉ����ꂽ�̂ł���v�B
�@���ꔪ�N�ăW�F���W���X�L�[�́A�����Ȃ����݂��Ă��������̔�{���V�F���B�L�h�V���̑�\�����Ƃ̃C���^�r���[�ɉ������B�ނ�͔ނɁA�`�F�[�E�J�[�������������A�X�l�ɑ��ĕs���s�ׂ����Ƃ����肤��Ƃ͍l���Ă��Ȃ��̂��A�Ɛq�˂��B
�@�u�`�F�[�E�J�[�͖@��ł͂Ȃ��v�ƃW�F���W���X�L�[�͓������B�u�`�F�[�E�J�[�́A�ԌR�������ł���悤�ɁA�v���̖h�ǂ�����B���x�A�ԌR������ɍۂ��āA�X�l�ȏ����͂��܂����Ɨ����~���čl���邱�ƂȂǏo�����A�����u���W���A�W�[�ɑ���v���̏���������O���ɂ����˂Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�`�F�[�E�J�[�́A�v����h�q���G���ł��˂Ȃ�Ȃ��̂��\�\���Ƃ��A���̌�����X�����̎҂̓���ɂӂ肨�낳���悤�Ȃ��Ƃ����낤�Ƃ��v�B
�@�i�����j�����Ŏ��́A����O�N�Ƀx�������ŁA�}�N�V���E�S�[���L�[�����Ɍ�����o�������L�^���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�ނ͂��̍��͖����s�ނ�́t�\�\�����{���V�F���B�L�́\�\�c�s�s�ׂɑ��ĕ����̔O���������Ă����B�ނ̌�����b�Ƃ́A���������̒����R���`���[�N���R�̌R���ɐ�̂���Ă���ԁA�s�\���F�g�̑I�o���ꂽ�c���Ƃ��Ċ������������g�N�[�����s�̈�c�̃����V�F���B�L�h�J���҂����Ɋւ�����̂ł������B���̎s���{���V�F���B�L�̎�ŒD�ꂽ���A�����̘J���҂����́u�R���`���[�N�̋��͎ҁv�Ƃ��čٔ��ɂ������A���Y��鍐���ꂽ�B���X�N���̔ނ�ٌ̕�m�́A�����̋��a���@������N�E�X�E�N���C�����R�ɏ��������߂��B�퍐�������������^�ɂ��Č����ł��邱�Ƃ��ނɔ����������A�ނ͓������A�u��X�͍߂̗L���Ƃ͊W�Ȃ��A���Y�����s���˂Ȃ�ʁB�����̎҂̏��Y�́A�͂邩�ɑ�O�ɋ�����ۂ�^���邱�Ƃ��낤�v�B
�@�S�[���L�[�́A���̌��I�Ȏ��������낵�C�ɉ�ڂ��Ȃ���u���͔ނ�̂����̊��l�����l�I�ɒm���Ă����B�ނ�͐���Ȃ���̍˔\�ƍ��x�̋�����������D�G�ȘJ���҂������v�Ƃ��������B
�@�����܂������s��������܂�Ȃ������������t�́A�W�G���W���X�L�[�̋L�O�Ɍ�����ꂽ�J�[���E���f�b�N�\�\�����A�{���V�F���B�L�̎w���I���_�Ƃł������\�\�̘_���̒��ŁA���������Ȃ��Ɉ��p���ꂽ���̂ł������B���قlj����Ȃ������ɁA�ގ��g���]���Ă�܂Ȃ��������̑g�D�̗����ƂȂ�A�₪�āA�����̎҂̓���Ƀ`�F�[�E�J�[�́u������X�ӂ肨�낳���v�̂�g�������Ēm��悤�ɂȂ�̂�ނ��\���������̂��ǂ����͋^�킵���B
�@���f�b�N���l�AN�EE�E�u�n�[�������܂��A�N�����ɂ�Ĉ�w�p�ɂɃ`�F�[�E�J�[�̊v���I��������]�̂��̂����̂������B�ނ��w�v���E�_�x�̕ҏW�҂��������A�ނ́A�`�F�[�E�J�[�͊v���̍ł��d�v�ȋ@�ւ̈�ł��邱�ƁA����͍��ƂƓ}�Ƃ̒P�Ȃ��@�ւɂƂǂ܂炸�S�}�͋����ă`�F�[�E�J�[�̓��u�ƂȂ�˂Ȃ�ʂ��ƁA�����A�{���V�F���B�L�͈�l�̗�O���Ȃ��u�`�F�[�E�J�[�������閼�_�̌M�́v���ւ�������Đg�ɑтт�ׂ��ł��邱�Ƃ��������B�ނ͑z���������ł��낤���H�@������܂��A���́u�_���Ȃ�ْ[�R�⏊�v�̂����ɂ��ƂȂ�A�`�F�[�E�J�[�̎�ŝs�����ꂽ�ߏ�ɂ�荐������Ė@��ɗ��悤�ɂȂ邱�Ƃ��B�܂��A�ނ����������ō��ӔC�ҁA�`�F�[�E�J�[�����̃��S�_�������̔Ԃ�����Ă��ē����@��ɐl���̓G�Ƃ��ė����A�����ł��̏���������悤�ɂȂ邱�Ƃ��B����ɂ́A���S�_�̑㗝�l�A�`�F�[�E�J�[�̐V�����G�W���t���A�܂����ƃ{���V�F���B�L�}�Ƃ����̊C�ɓM�ꂳ���A�����œ����`�F�[�E�J�[�̎�ŁA������l���̓G�Ƃ��ď�����Ă������낤���Ƃ��B
�@�i�����j��X�́A�S�I���ψ�����A���̎��ۂ̖��̂��N����ǂ����x�ɂ킽���ĕύX���ꂽ�ɂ�������炸�A�`�F�[�E�J�[�ƌĂё����邱�Ƃɂ���B�����N���ɁA����́s�đg�D���t����āAGPU�A�������Ɛ����s�����ƌĂꂽ�B���O��N�Ȍ�A�����NKVD�A���������l���ψ����ƂȂ����B���݂ł͂���́AMVP�A���������Ȃł���B�����A���̐��_�Ƃ����ɂ����ẮA����͏�ɓ����`�F�[�E�J�[�ł��葱�����̂ł���B
|
|
|
|
|
���S�[�_(1891-1938���Y) |
�G�W���t
(1895-1939���Y?) |
�x���A(1899-1953���Y) |
�g�o�w�j�f�a�ƃW�F���W���X�L�[�x���]�ځB���ɃW�F���W
���X�L�[�̐؎�Q���ʐ^�A�ڍׂȢ�j�f�a�ϑJ�}������^
�@�W�F���W���X�L�[�̗F�l�����́A�ނ̐��i���������m�肷��ۂɁA�G��e�����鎞�̖����߂��������ނ̓����ł͂Ȃ��A�ނ��u�l�ނɑ��邱�̏�Ȃ��[�����ɖ������ꂽ�v�i���f�b�N�j���̎���ł��������Ƃ𖾂炩�ɂ������Ɗ���Ă����B�ނ�́A�J��Ԃ������{�݂ɂ��Ă̔ނ̊S���q�ׁA�u���������S�v���������l�ԂƔނ��Ă̂ł���B�����炭����͐^���ł��낤�A�Ƃ����̂́A�ނ́A���̎Љ��`�҂Ƃ��Ă̊������A�܂������}�����ꂽ�l�Ԃɑ������݂���J�n�����̂�����B�������̂��Ƃ́A�ނ����牽�S���邢�͂���ȏ�̐l�тƂɎ�肩�����̂��Ȃ��s�K�������炷�W���Ƃ͂Ȃ�Ȃ������̂��B�ނ��q�������̂��Ƃ�S�z���Ă����Ƃ����̂��H�@����ł��ނ́A���̖��߂����e��v�������E�����тɁA����l�Ƃ����q���������ǎ��ɂ��A�����̍Ȃ����𖢖S�l�ɂ����ł͂Ȃ����B
�@����ɂ��鎞�A���͂��Ă̊č�(�J�[�g���K)���ԃW�F���W���X�L�[���A�ނ̃`�F�[�E�J�[�����̃e�����̎x�z���J�n������ł�����A�����̉ߋ��̌o�������S�ɂ͖Y�ꋎ��Ȃ��ł��邱�Ƃ��v���m�炳��邱�ƂƂȂ����B����Z�N�ɁA�ܖ��̍����Љ�v���}�����A�Ŏ�a���ɕ����������āA���X�N���č����甒���E�������B�����̎Ⴋ�v���Ƃ����́A�܂��Ȃ��đߕ߂��ꂽ���A���̑�_�s�G�ȒE���Ԃ�́A�`�F�[�E�J�[���������̊Ԃɂ����̎^�̔O���܂��N�����̂������B��ɁA�W�F���W���X�L�[�ƒɗ�ɂ�肠���Ă��鎞�A�������̎����̂��Ƃ�z���N��������ƁA�ނ͒Z�������ĉ������A�u�悩�낤�A�N�����Ԃ�����ł����͉̂�X�̎d�������A�E�����悤�Ƃ���̂͌N���̎d�����v�B��u�A�ق�̈�u�̊Ԃ����A�ނ̉ߋ����A�˂��j���ĕ\�ւ��̊���̂��������̂������B
�@�����N�A���[�j���͓ˑR�W�F���W���X�L�[����ʉ^�A�l���ψ��ɔC�����A�����ň���l�N�ɂ͍��ƍō��o�ω�c�c���ɔC�������B����ǂ����Ǝ����̊Ǘ��������p�������ł���A�W�F���W���X�L�[�̓`�F�[�E�J�[�́s�ō��w���ҁt�ł��葱�����B���ݓI�ȁs�Љ��`�I�C���t�ւ̓]�C���A�{���V�F���B�L���Ɠ��ł̔ނ̎�v�Ȏd�������ꂩ��ύX���邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B�ގ��g�̓��u�����́A�܂��ɍŌ�Ɏ���܂ł̔ނ̈ʒu�����̂悤�Ɍ��Ȃ��Ă����B
�@����Z�N�Ƀ��f�b�N���������b���A���̂��Ƃ��ؖ����Ă���\�\�u�����N�A�|�[�����h�Ƃ̐푈�̍Œ��̂��ƁA�O���֕����A�|�[�����h�̘J���҂�����̃\���F�g���Ƃ���������̂��������ׂ���X���������Ă������A�W�F���W���X�L�[�����ɂ���������A�w���������������ɂ́A�l�͋���l���ψ��������������ˁx�B���̉�b�̏�ɋ����킹�����u�����́A��₩�ɏ����B�W�F���W���X�L�[�́A�g������点���v
�@�W�F���W���X�L�[�������ɕn�����l�тƂ����݁A�ނ�̂��߂ɐV���Ȑ��������݂��邱�Ƃ�S�ꂩ�疲�݂Ă����Ƃ��悤�B����ɂ��Ă��ނ̖��́A���̐V���Ȑ������߂����s�ނ̐킢�t�̎S���̒��ɏ������Ă��܂��A�l�тƂ́A�ނ��l�Ԃɂ����炵���܂Ɛ�]�Ƃ̊C�ɑ����Ă������̂ł���B�ނ́A�����ނ���������ŁA�ނ�������邱�Ƃ��Ȃ��������̂ɁA�l���������Ԃ��Ă��܂����̂��B�ނ́A���̎��ɂ�����܂ł����ł��������A�c���ȗ���݂ɏ[�����j�ł������B
�@����A���c���Y����t�҂̂ӂ��̊��@(�����A�o�D�Q�W�P�`�Q�W�T)
�@�\���̊v���ŁA�v�����^���A�łȂ��_���̈ӎu�d���Ȃ���A������{���V�F���B�L�͌��͂��ێ��ł��Ȃ����Ƃ����[�j���͒m�����B���ꂾ����A�i���[�h�j�L�̒����ł���Љ�v���}�̔_����������̂܂��s���āA�����ւ����݂Ƃ߂˂Ȃ�Ȃ������B���V�A�̊v���͔_���̈ӎu�����Ă͂����Ȃ��Ȃ��Ƃ����_�ŁA�Q���c�F���ȗ��̃i���[�h�j�L�̍l���́A����܂��Ă��Ȃ������B
�@�i���[�h�j�L�����̂Ȃ��ł��A�����Ƃ������Ȕ��t�҂������A�����Љ�v���}�Ɍ��W�����Ƃ����Ă����B�ނ�������Ȕ��t�҂ł���Ƃ����̂́A�v���̂��ƁA�u���W���A�ƘA�����{�����邱�ƂɁA�O�ꂵ�Ĕ���������ł���B
�@�����Љ�v���}���\���v���̂̂��ɁA���}�������Ƃ́A�d��ȈӖ�������B�ނ�͔_�����\���������ł͂Ȃ��B�_���̓y�n�����łȂ��A�l�Ԃ̎��R������\�����B�u�y�n�Ǝ��R�v���{���V�F���B�L�̌��͂̂��Ƃł܂��낤�Ƃ����̂ł������B
�@���̓_�ň��ꎵ�N��������N�܂ł̍����Љ�v���}�̍s���Ǝw���҂̐S����������X�^�C���x���O�́w�����Љ�v���}���ꎵ�`�����x�͋M�d�ȕ����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����̓{���V�F���B�L�ɂ���Ė��v����Ă��܂��������̏o�y�Ƃ��������ł͂Ȃ��B�v�����͂ƌl�̎��R�̖��������Ƃ��؎��Ȍ`�ł����Ă���B
�@�����͂��I�ȗ͂ɂ���đœ|�����V�������͂́A����߂ĕs����Ȏ������ނ�����B���������V�A�ɂ����ẮA�p���[�E�|���e�B�N�X���푈�̌`�ł����Ɏ��ӂɐؔ����Ă��鎖��̂Ȃ��ŐV�������͂������������˂Ȃ�Ȃ������B��@�̂Ȃ��̐V�������͂́A��̎�i�������Ď������ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���͂̊�@�Ƃ͖@�̑��݂̋^�킵���Ȃ̂�����A�s�@�ȕ����I�ȗ͂����͂ɂ���Ă��������邱�Ƃ�h�����Ȃ��B�����I�ȁA����߂Đ����I�ȏł���B���̎����ɐl�Ԃ̑������܂��낤�Ƃ��������Љ�v���}�̐l�����́A������ABC���킫�܂��Ȃ��l�ԂƂ��āA�������Ă����B
�@�ނ�̗v�������悤�ɁA�R���ɂ����鎀�Y�̔p�~�����s�����Ȃ�A���S�������o���ăg���c�L�[�͐ԌR��n�݂ł��Ȃ������낤�B�ނ�̗v�������悤�ɁA�u���X�g�����g�t�X�N�Ńh�C�c�R�Ƃ̘a�������ۂ��āA�v���푈�s������A�v�����͕͂������낤�B����Ȃ獶���Љ�v���}�̂����Ȃ������܂��܂̐����s���͎��Y�ɗނ������s�ł��������낤���B
�@�u�S���E�̒����̂����ɐl���̎�Ŏx�����Ă���Љ�v���́A���̓����I��������ێ����邱�Ƃɂ���Ă̂݁A�S���E��Ȍ�������B��X��l�ЂƂ�́A�����Ȃ���ɂ����Ă��A�v���̎��h���ɑ������I�ɐӔC���Ă���v�i�{�����y�[�W�j�B
�@�v���������I�ł��肤�邩�B
�@�����N�h�C�c�v���̂Ȃ��ŁA�}�b�N�X�E�E�F�[�o�[�͂��̖��ɂӂ�Ă������B�u���ۂɁA�����͓��]�ɂ���čs������̂ł��邪�A���]�����ōs������̂łȂ����Ƃ͑S���m���ł���B���̓_�ɂ����ĐS��ϗ��Ƃ͑S���������B�����A�l�X�͐S��ϗ��ƂƂ��čs�ׂ��ׂ����A����Ƃ��ӔC�ϗ��ƂƂ��čs�ׂ��ׂ��ł��邩�Ƃ������ƁA�Ȃ�тɔ@���Ȃ鎞�Ɉ�������A�@���Ȃ鎞�ɑ��������ׂ����Ƃ������Ƃɂ��ẮA���l�ɂ��w�}���邱�Ƃ͏o���Ȃ��v�i���������Y��͏o�Ő��E��v�z�S�W21�@���Z�y�[�W�j�B
�@���ʂɂ������ĐӔC�����������ƂɁA���]�ɂ��v�Z�����łȂ��ɁA�S��������čs������Ƃ������Ƃ͗e�Ղł���B�S��̓����ɂ��ƂÂ��čs�������Ƃ����ʂɂ��ĐӔC�����Ă邩�ƁA�t�ɖ��ꂽ��S��ϗ��Ƃ͕ԓ��ɋ����邾�낤�B�E�F�[�o�[�́A�S��ϗ��ƐӔC�ϗ��Ƃ́u���݂ɕ₢�������́v�ł���Ƃ����\�����̂������B
�@���Ƃ��A����͌���̃\�A�̐��Y�������ێ����邽�߂ɂ́A�X�^�[�����̂�����悤�ȑ�l�������Ȃ��ł��悩�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����u�\���v�̂��Ƃł��낤�B�܂����݂̃\���F�g�Љ���ێ����邽�߂ɁA�Ȋw�҂��Ƃ������قǑ������Ȃ��ł����̂łȂ����Ƃ����u�\���v�̂��Ƃł��낤�B�����Љ�v���}���A���̏����Ȍ��ɂ���ă��V�A�j�̂Ȃ��ɂ����̂��������Ƃ����́u�\���v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@���́u�\���v�̍ŏ��̉\���͈��ꎵ�N�\�ꌎ��\�����̕z���ɂ������鍶���Љ�v���}�̍R�c�̏d�v�����{���V�F���B�L�̑��łǂꂾ���l�����邩�Ƃ����Ƃ���ɂ������B�\�ꌎ��\�����̕z���́u�v���ɑ�������̎w���҂����̑ߕ߂Ɋւ���z���v�ŁA�\���F�g���s���ւ̑��k�Ȃ��Ƀ��[�j���A�g���c�L�[�A�A���B���t�A�����W���X�L�[�A�X�^�[������̏����Ŕ�����ꂽ�B����̓J�f�b�g�}�i�u���W���A�̓}�j�̎��s�@�ւ̃����o�[�����͐l���̓G�Ƃ��đߕ߂���A�v���@��ōٔ��ɕt����邱�Ƃ������������̂ł���B
�@�\���F�g�̎i�@�l���ψ��ł������X�^�C���x���O�́A�\���F�g��c�Ŕ��������B�u���������v���ɂ́A���̓G�Ύ҂𗪎��ٔ��ŗL�߂Ƃ���K�v�͂Ȃ��B��X�����҂́A�����ȍٔ�����������ɏ\���̗͂�L���Ă���B�����l�Ƃ��ăJ�f�b�g�}�����l���ɑ���A�d�̂��ǂō������ꂽ�Ƃ�����A�ނ��l�I�Ɍ��J�ٔ��\�\���̎��ɂ́A��X�͏؋�����ׂ��ł���A�ނٌ͕�̌�����L����ׂ��ł���\�\�ɂ����悤�ł͂Ȃ����B�����A��̏W�c�S�́\�\�s���葽���̐l�тƂ̏W�c�\�\��l���̕ی�O�ɒu�����Ƃ͉�X�ɂ͂ł��Ȃ��v�i�{���܌܃y�[�W�j�B
�@���͂̒D��ɂނ����āA���ׂĂ̔��t�҂����������Ă���Ƃ��́A�l���̓G�͌��͂ł��邱�Ƃ͖����ł���B�����A���t�҂����͂�D�悵�����_����l���̓G�͕s���m�ɂȂ�B�l�����s���锽�t�҂��A�͂����Ăǂ̓_�܂Ől���Ɠ��ꉻ�ł��邩�킩��Ȃ�����ł���B���̎��_�ɂ����Č��͂������������t�ҁA�V�����x�z�҂ɂƂ��čő�̗U�f�͎�����l���ƊϔO�I�ɓ��ꉻ���邱�Ƃł���B
�@�x�z�҂�������l���Ɠ��ꉻ���āA�l���̓G�ɂ������Ă��ׂĂ͋������Ƃ����Ƃ��A�x�z�҂͐l���ɂ������āA����߂Ċ댯�ȊW�Ɏ������������ƂɂȂ�B�x�z�҂̐���ɂ��Ȃ炸�������ӂ���Ƃ�����Ȃ��s���葽�����A�������ɔ����邱�Ƃ��ł��邩��ł���B��@�����������x�z�҂ɂ���āA�l���̓G�Ƃ������b�e�����͂�ꂽ���̂͂��ׂėL�߂ɂȂ�B
�@�v�����������邽�߂ɂ́A�������ɕs���葽���̋��͂��K�v�ł������B�������A�������v�����͂Ƃ��Ĉꊇ���邱�Ƃ́A�v���ɎQ�������X�̃C�����A�X�̃}���A�̐l�Ԃd���Ȃ����ƂɂȂ�B�C�����Ȃ�A�}���A��l���̓G�Ƃ��ėL�߂ɂ��邽�߂ɂ́A�ނ��s���葽���̂Ȃ�����A�l�Ƃ��ĂЂ낢�����A�C�����̐ӔC�A�}���A�̐ӔC�Ƃ��č�������̂łȂ���A�ނ�̐l�Ԑ��͖��������B�s���葽���̂Ȃ�����l�����ʂ��邱�ƁA���ꂪ��{�I�l�����݂Ƃ߂�Ƃ������Ƃł���B�����Ȃ�ƍ߂����ꂪ�l�Ԃ̔ƍ߂ł��邩����ɂ����āA������ł���͂��͂Ȃ��B
�@�X�^�C���x���O���{���V�F���B�L�̎w���҂����ɗv���������̂́A���͂̔�l�Ԑ��Ƀu���[�L�������邱�Ƃł������B���ꂾ�����A�v���̓��������܂��邱�Ƃ��ł�����̂������B
�@�����ǂ�Ȕ퍐�ɂ������Ă����J�ٔ��ł������Ƃ��v�������̓����I�`���Ƃ��Ċm������Ă�����A����Ȍ�̃\�A�̗��j�͂����������̂ł��肦���낤�B
�@�����āA���R���E�̌��͂������Ă��Ȃ��ꐭ�}���A�����ƈӌ��̂������s���葽���Ɂu�l���̓G�E�g���c�L�X�g�v�ȂǂƂ������b�e�����͂�K���������Ȃ��������낤�B�܂��A�e�����X�g�̏����W�c�ɂȂ������t�҂������A�u�l���ٔ��v�Łu�l���̓G�v���������Ƃ��Ȃ��������낤�B
�@�@��㎵��N�O����Z��
�ȏ�@�@����l�d�m�t�ɖ߂�
�@(�֘A�t�@�C��)
�@�@�@�u�ԐF�e�����v�^�Љ��`�ƃ��[�j�����E�����u�������v�̐��v(�{�n�쐬)
�@�@�@�u�X�g���C�L�v�J���҂̑�ʑߕ߁E�E�Q�ƃ��[�j����v�����^���A�ƍ٣�_�̋��\
�@�@�@�u�����v�_���ւ́w�ٔ��Ȃ��ˎE�x�w�ŃK�X�g�p�x�w�߂Ɓu�J�_�����v�_�̋���
�@�@�@����E�ґS���e�E�^�Љ��`�ƃ��[�j���̊v���ϗ���@�i�{�n�쐬�j
�@�@�@�u���\���F�g�v�m���l�̑�ʒǕ��w���x�ƃ��[�j���̓}�h���@(�{�n�쐬)
�@�@�@���H���R�S�[�m�t�w�e�����Ƃ������̃M���`���x�w���[�j���̔閧�E��x�̔���
�@�@�@�����s�w�l���̃��J�j�Y���x


