旅、山を歩く

〔3DCG 宮地徹〕
〔メニュー〕
1、 ダイヤモンド輝く山小屋- 西穂高
3、寝る方法−奈良公園での昼寝
4、紅葉は 来るべき冬の前奏曲-国見峠、国見岳
5、東北の「ブナッコリー」よ お達者で−白神山地のブナ
8、ヒルが飛ぶ
10、月山
12、お茶が化ける (メール)知覧についての『青春譜』
13、雪
14、山歩き考
15、山歩きの悦び
18、これから
19、ショッピング
20、晩秋
21、ごみ
22、尾瀬 あの尾瀬で、ごみの不法投棄 遥かなる尾瀬 湯浅寿之
23、屋久島
ダイヤモンド輝く山小屋- 西穂高![]()
50年ぶりに北アルプス西穂高に登った。と言っても、松本、島々まで夜行列車で行き、上高地から延々と歩いた山登りは昔話になった。
現在でも、その方針の登山家もおられると思うが、今回、岐阜県高山まで鉄道で行き、高山からバスで奥飛騨温泉郷を経て、バスに1時間半ほど乗り、新穂高ロープウェイ駅に着く。そして、1000mから、一気に2000mの地点まで行った。
奥飛騨温泉郷の民宿でゆったり一泊した。「歳だから無理しない」と言い訳しながら泊り、翌朝早くスタートの計画だった。
客は笠ガ岳登山の客だけで、食事の大部屋も私たち夫婦と、もうひと組だけだった。
山ぶどうの食前酒、ぐみのジャム、いずれも近くで採ったもの。そして山魚の塩やきや、きのこの天ぷらなど、素朴な山の幸に満足した。
男女別の小振りな露天風呂がいくつかあり、透明でしっとり感のある湯に満足しながら、のんびりシャンソンなど口ずさんで愉しんだ。見上げた夜空にたった一つ、星が光っていた。
ロープウェイに乗ったとき、二組の車いすの女性と一緒になった。家族らしい人に車いすを押して貰って、風もなく、穏やかに晴れた10月の陽気の中、一気に高度を上げるロープウェイから、目の前に広がる北アルプス穂高連峰、特徴のある槍ヶ岳や、少し角度を変えて笠ガ岳を眺めながら、「こんなに近くで素敵な山が見られて、来た甲斐があったね、よかったね」と言い合っていた。
別の中年夫婦も笑顔で「風もなく穏やかで、晴れて最高だね」と、山々を確認していた。
中高年がほとんどのロープウェイ、中高年は元気だった。
思い出の北アルプス、西穂高、槍ヶ岳を目の前にして、目頭が熱くなった。
50年の歳月が流れたのだ。
ロープウェイや高速道路は、大自然を壊す行為だと、反対する意見も一理あるが、日本の美しい3000m級の山々を、一部の登山家だけでなく、多くの人たちが愉しめることは、素晴らしいことではないか。
因みに、このロープウェイは2156mの千石平まで一気に登る東洋一のスケールとのこと。
10分ほどでロープウェイを降り、満員の乗客は公園になった周辺を散策してから、再びロープウェイに乗って帰る人が殆どだった。
登山する人は、登山届けを書いてから、いよいよ登り始める。大きなリュックを背に山小屋まで登る。小屋が近くなるほど、登山道は次第に岩登りになり、角度が急になってくる。
背中の重いリュックさえなければ、もっと楽に登れるのにと何度も思いながら、やっと西穂山荘に辿り着いた。
一息ついてから、身軽になって2701mの「独標」を目指す。
それからの登りは、急角度の岩登りで、大きな岩、小ぶりな岩のどこを登ればいいかを探りながら、這うように前進した。到達したのは2452mの丸山である。
すばらしい見晴らし地点だ。急峻な「独標」と、その向こうに悠然と聳える西穂高の頂上2909mが目の前に見える。
さらに、山は連なり、少し向こうに槍ヶ岳の頂も視界の中だ。
カメラをかまえてシャッターを切る、絶好の場所で休憩した。
途中で、若い男女のグループに会う。槍ヶ岳から縦走してきたメンバーで、さすが若い足はしっかりしていた。
頂上を目の前にして、あと2時間急な岩場を登り、下る体力はあるか夫婦で考えた。
ここまでくれば、登ったも同然だ。歳を考えて無理しないで、一度小屋へ戻ろう。となった。
2500mの小屋まで下るのも、慎重でなければ・・・。
ゆっくり下って、やっとに西穂山荘に到着だ。
近くに平らな広場があって、1人用のテントが2張り張られていた。あたりの景色を眺めていると、そのうちの一人がカメラで「撮ってくれ」の合図をされた。歳は自分たちと同じ位と見た。
近くまで行って「テント張って、縦走なんてスゴイですね」と言うと、意外な返事が返ってきた。
「惨めだ」「え? 立派、立派ですよ」
テントを離れた。惨めってどういう意味だろう。
一泊9600円の宿泊費の節約? それが惨め? それとも、奥さんを亡くされた寂しさ? テントを離れて少し上から眺めると、その方は小さなテントから顔だけ出して、もう寝ておられた。
山小屋の食事は、若者たちの料理人や世話役で、時間を決めて整然と取り合った。
席が同じだった東京から来たという40代の夫婦は、「たった一人しかない連れ合いだから、なんでも一緒にしたい」と言いながら、「私が働いているのでよく間に合う夫です」「あら、わが家もそうよ」と、笑い合った。
向かい合わせの席には、律儀に食器や飲み物を運ぶやさしく若い夫がいた。
翌朝は、新潟からと関西から落ち合ったという親子と同席だった。
「素晴らしい旅になった。冥土の土産ができた」という母親と若い男性、「こんな親孝行する人も珍しいですね」というと、納得したような笑顔になった。
整備された山小屋で、こんな会話が交わせるなんて、50年前は考えられない。当時の登山者は若い人ばかりだったから・・・。
山荘の目の前に穂高、槍の北アルプスが並ぶ。この贅沢はどうだ。
夕方見たのは2000mあたりから雲が、次第に広がる雲海で、見る間に山々は姿を消した。それは、一幅の絵「神代」のそれだった。
夜中にふと窓を開けて夜空を眺めた。降り注ぐダイヤモンドの光、光、光。
両手を拡げれば次々と落ちて来そうで、高貴な輝く宝物たちを見上げ続けた。
木曽駒ガ岳の頂上で仰いだ感激の星座もきれいだったが、2500mを超えると、このように星たちが間近で、光り輝くのかと、大宇宙の小さな己を思い、身が引き締まった。
1年前の10月、昼間は初冠雪の白馬岳が見事だったが、大勢のカメラマンが泊まる栂池(つがいけ)の山小屋に泊まり、夜空を見に外へ出た。小学生の男の子が父親と暗い中を歩きながら話していた。
「白っぽいのが天の川で、織女と牽牛がこの川を挟んで、年1回しか逢えないんだよ」星に詳しいイクメンパパだったなぁ。
高貴な高齢者も間近くなった夫婦の、挑戦する喜びと、限界を自覚した山登り。
西穂高への登り降りの5時間という、かなりきつかったが、幸せな登山は終った。
中部山岳国立公園特別地域の栂池自然園は、JR大糸線の白馬駅からバス、それからはゴンドラとロープウェイでしか行けない。
村営の宿に泊まったが、かつては標高2000メートル地点まで車でも行けたそうだ。
道路の整備が問題になったとき、地域の人たちはCO2排出による植物への影響を考えて、ゴンドラとロープウェイにする道を選んだというから、先見の明があったと思う。
それから約15年、尾瀬もそうであるが、安易に車を乗り入れて自然を破壊し、地球全体が青息吐息の異常気象になっている。この事を忘れないようにしたい。
白馬岳〔2932m〕は、右に小蓮華山〔2766m〕、左に杓子岳〔2812m〕を従えて聳えている。春から夏にかけて雪解けの時期に、山に馬の雪形が現れる。その山をシロウマダケと呼んでいた。
それから、呼び方の混同が始まったようだ。山はシロウマ、駅や村はハクバと。
標高1800メートルから2000メートルの高地に広がる見事な湿原、栂池自然園は、冬はマイナス20度以下、積雪6メートルにもなるとのこと。
近頃、若い女性の間で歴史好き、カメラ好きそして山歩きが流行とか、要するに女が元気なのだ。
この10月、久しぶりに山に逢いに行ったときも、それを感じた。
初冠雪に輝く白馬岳、見事な白馬三山をバックに秋を撮ろうと、三脚つきのカメラに付き添うカメラマンが群れた。女性一人の人も多かったが、夫婦でそれぞれにカメラを備えて覗く。
「三脚を担いでの山歩きは大変でしょう」と言うと、「撮りたいところが微妙に違う。当然撮る時間も違うし」。
その女性は、最近退職してカメラに懲りだした夫より腕が上で「展覧会によく入選しているのよ」と笑いながら話してくれた。
二人の話題はカメラ撮影のことで、途絶えることなしとか。
若くはない私たち夫婦も、贅沢な山歩きをした。何が贅沢か、車でなくゆったりと、3泊4日の鉄道の旅だった事,そして白馬岳の初冠雪と、平地より1ヵ月早い紅葉を楽しめたことである。
(写真は、2009年10月、初冠雪の白馬岳と大雪渓−栂池自然園)

若い頃の山歩きやスキーは、日帰りとか夜行列車が常識だった。車社会になり、近くまで車という人が多い時代になった。
夜、村営の山荘〔と言っても、改装して立派な旅館並み〕を出て、夜空から、こぼれ落ちそうな山の星たちを仰いだ。
真っ暗な道に親子連れが天を仰いでいた。「あれが織女、こちらが彦ぼし、真ん中は流星群、つまり天の川だ」「やっぱり、そうですよね」と私たちも思った通りだ。
「南を向いて左、つまり東がカシオペア、右、つまり西がオリオン座だ。パパはね、若いときから星座に夢中だったよ」。なるほど、よく分かった。顔も分からない親子にありがとう。冷えてきたね。お休み。
翌日、自然園をトレッキングしてから、白馬駅に戻りタクシーで猿倉へ走り、白馬尻まで山歩きした。大雪渓が、夏を越して痩せ新しい雪を待っていた。猿倉山荘、白馬尻山荘とも冬仕舞いで閉鎖、解体の日だった。
その工事関係者以外、誰とも会わない静かな登山だった。
振り返れば、山々は赤茶と黄色に輝いて、年寄り夫婦を温かく見送ってくれた。
2009年10月
寝る方法−奈良公園での昼寝
「寒紅をさして阿修羅に会いに行く」−中学時代の師の、何かの入賞作である。
半世紀ぶりの奈良だ。予定では、かなりの距離を歩くはずだった。が、近鉄奈良駅で乗ったタクシーの運転士が「二月堂まで登りですから、まず二月堂三月堂へ行って、それから東大寺、春日大社と下った方が楽ですよ」と教えてくれた。
同じ古都でも、よく行く京都に比べて、人が少なく落ち着いた感じがする。
東大寺だけは世界遺産目指した団体客が多く、八割が外国人とみた。
幼い子とすれ違った。手をつないだ祖母に「どうして、顔が同じなのに、ことばが違うの?」と聞いていた。
祖母は「それはね、アジアにいろんな国があって、アメリカもあってね・・・」。難問に思わず微笑んだ。
大仏さまはやはり大きく、泰然としていた。台だけは古い昔のままでも、焼けて野ざらしの状態だったこともあり、それを嘆いた芭蕉の句−「初雪やいつ大仏の柱立」も知った。
出口で人力車が数台待っていた。近付いて来た若者に「どうですか。上流階級の気分になれますよ」。笑顔で話しかけられた。
熱心な勧めに、連れ合いと相談し「ま、いいか来年はどうなるか分からないし・・・」と、最短距離30分だけと、初めて人力車に乗る。二人で8000円のまるで御所車のような、黒塗りの大きな車輪、走りながらの若者の説明が生きていた。
1300年になる平城の都、東大寺、興福寺などの寺と、春日大社などの神社が共存している。喧嘩にならないように、若草山を焼いて境界線にした。奈良の語源は、平城→平らにならす→奈良となった。人力車を引っ張りながら語ってくれた。
鹿たちは、昼間こうして平穏に人間と戯れ、夜は山の方へ帰るのです。食べ物は公園の草、糞は肥料になって一石二鳥ですよ。
巧みな話を聞きながら、ここの鹿は人と共に生きているなと感心した。
早朝の出でやや眠気がきたが、それは貴族のような気分からきたゆったり感だったのかも知れない。
「浮き見堂」で人力車を降りたが、それが池に浮かぶ姿は、貴族たちが遊び、歌よみ文化が、このゆとりの中から生まれたことを実感させる。
緩やかな起伏、生まれたての緑で彩られたこの一帯が広く奈良公園として、のんびりと大らかに私たちを迎えてくれた。
中でも1200頭といわれている鹿の多さと人懐っこさには驚いた。但し、おやつの鹿せんべいを買った人だけには、どこまでも付きまとうが。
万葉粥を食べ、公園でぼんやり景色を眺める。新聞を敷いて、横になった。
寝るには、このように、空は蒼く、風はなく、遠くを行く何人かが、絵のように静かでなければならない。
向こうの方で、ヴァイオリンの練習をしている人がいる。繰り返し、何度も何度も同じ曲を練習する人でなければならない。
鹿はこのように、一緒に座って、静かに待ってくれなければならない。
うとうとしながら、天平の世に遊んだ。
唯一の不運は、阿修羅さまが東京国立博物館に出張中だったことである。
儲けは、奈良国立博物館の鑑真和上展で、中国から日本に仏教を伝えるため、何度も海で遭難しかけ、日本に着いたときは盲目となっていた鑑真像と資料が、穏やかな顔と共に印象的だった。
紅葉は 来るべき冬の前奏曲-国見峠、国見岳
11月というのに、いつまでも寒くならない。冬衣装にも替えないで日々が過ぎていた。やはり温暖化かなどと考えていた。
そんなある日、夜から、急にというか、極端に寒い日が続いた。
「ああ、秋なのだ」と納得した。昼間は寒いといってもそれほどでもないが、夜間の冷え方が晩秋というより、初冬のそれだ。急いで床暖房を入れ、ストーブもつけた。
こんな冷え方は、紅葉が美しいよ、きっと。
驚いたのは、久しぶりに何人かの友人に便りをしたら「仙台の姉が、ひざ関節の不調で手術、入院中に院内感染で死亡」「がん闘病中の妹が・・・」。
あるいは「弟が急性心不全で亡くなりました」という友もあり、愕然とした。
世間が秋の紅葉で美しくなり、束の間を楽しもうと思ったのに、樹木より先に、弱っていた人たちが逝ってしまった。
自分たち夫婦も、しわしわ、よれよれの「高貴」高齢者になったのだから、そういう年代になったのだから、こんな状態は当然かもしれない。
「白山」登山の下りでひざを痛め、高い山歩きは自重していたが、降り注ぐフィトンチッドで、元気になってしまう体験が忘れられず、鈴鹿連峰国見岳に挑戦してみた。御在所裏道が遮断なので、ロープウェイで御在所の頂上まで登り、そこから国見峠、国見岳と登り下り二時間程度だった。
大昔、岩石が噴火してそのまま山々が残った感じの岩山で、難儀な登山だった。歩き易い土の尾根道はほんの僅かで、大きな岩石に縛られた鎖や、垂れ下がったロープに必死にすがり付いて登り、下った。
やや擦り切れた感じのロープもあり、以前登った大杉谷を思った。
あのときは、途中二泊して、日本一雨が多く、深い谷底は、目を見張るほど澄んだ藍色の水、その三重県大杉谷から奈良県大台ケ原のコースだった。
「ここ転落場所」「ここ転落危険場所」いくつもの立て札があったが、その後の豪雨によって、大杉谷は登山できない山になってしまった。
御在所の裏道が、前回の豪雨で山小屋も登山道も崩れ、山小屋の主が、ボランティアの人たちと、復旧活動に取り組んでいる。
ここ国見岳も、豪雨や極端な気候変動で山を修復できなくなる。そんなこともあり得ない話ではない。加えて地域の過疎、荒れた山の多さを考えると、そう思えてきた。
頂上の、少し平らな岩に腰を下ろして弁当を拡げた。
山々の斜面が見渡せ、陽の当たる斜面は柔らかな表情であるが、北西側からは寒風が吹き付け、長居は出来なかった。山で出会った人はほんの数人「こんにちは」と挨拶を交わす。
片隅に緑色の熊笹と、真っ赤にもえるようなかえでが私たちを見送ってくれた。
山はすでに冬、少しだけ秋が残る。人生の晩秋を迎えた自分たち夫婦のようだ。
(2008年11月)
世界遺産の「白神山地」に会えた。
千メートル余りの山々が、青森と秋田の県境に横たわるブナの原生林は、ガイドつきでなければ登れないことになっていた。
「二つ森」の頂上から眺めた連山、山々のブナは、まるでブロッコリーが連なっているように見える。ガイド仲間のことばで「ブナッコリー」とか。
水をたっぷり吸い込んだ、太っちょのブナたちは、ガイドさんがまわり道して見せてくれた日本一背高ノッポ〔58m〕杉や、都会で見慣れたスマートなケヤキとは対照的に、木が太く堂々としており、空を蔽うように広がった枝が力づよく伸びていた。
感動的だったのは、山の地形の関係で吹き付ける風によって、幹が太くならないスマートなブナばかりの林に出会ったときだった。
きれぎれに、午後の日差しを浴びて輝くみどりの葉っぱ、スラリとしたブナが立ち並ぶ様はまさに美人ブナの勢ぞろい、圧巻だった。葉緑素やオゾンが木々の間を漂い、降り注ぐのを実感した。
(写真は、白神山地のブナ原生林)

登山は、どうしても一刻も早く頂上に立ちたいとペースを上げる。若い頃から、ひたすら登ったように思う。が、周りの植物や生き物、風景を観察し、大自然を愛でながら登ることを、白神山地で教わった気がする。
同行してもらったガイドさんは、1989年から「原始の森 白神山地」の絵ハガキを発行し続けている。
第8集「クマゲラ」は日本最大のキツツキで、国の天然記念物、原生林の奥深く生息している。学術的にも価値の高い仕事を続けるカメラマン江川正幸氏がガイドだったことは運がよかった。
江川正幸カメラマン『白神山地の生態系のなかで』photoエッセイ48編
江川氏は、これまで写真集を何冊も発行し、当地でかなり活躍しているカメラマンであるが、「白神山地」資料館について「官製臭い。もっと現地の生き生きした自然の動きがないと」と、プロらしい不満も漏らしていた。
日本の高度成長期、開発の名の下に、どんどん木を切り倒した。林道はどこまでも伸びたが、自然保護派たちが立ち上がり考え方の違いもあ、り、県境を挟んで深刻な対立があった。
世界遺産になって自然保護運動もひと段落したが、それまでの苦労は並ではなかっただろう。2時間半の車の中で、あるいは山を歩きながらガイドの心遣いを忘れず、無理じいしないで自然を守り、その考えを広める「エコツーリズム」に全生活の生き甲斐をかけるカメラマンだった。
山の帰り道で見つけた「みず」という植物を「天の恵みを少し頂きます」と言いながら採り、宿に持ち帰った。みんなで皮をむいた茎を、女主人はさっとゆでて食卓に並べた。都会で食べるふきの感じである。軽く塩味をつけた実も、緑色した自然の漬物として食卓に出た。さっぱりとして美味しかった。
また、ご飯を小さなすりこ木でつぶし、それを箸の太いような軸の棒にこすりつける。少し火であぶってたれをつければ、キリタンポの出来上がり、夕方のご飯にする。それらの実体験をさせてくれた。
自然の恵みを守り、必要な量だけとって食べる。まことに縄文人になった気分である。
インターネットで探した宿で、豪華なホテルではないが、ガイドさんと同じ理想に燃える、旅行社の若い女主人だった。
二泊目は近くの宿を予約した。その宿は、1964年父親が買っていた山に温泉が自噴していたのを先代が温泉宿にした。お金がないので建物だけは大工さんに頼み、夫婦で手作りした苦労が実った湯元の温泉だった。質素ながら本物の素晴らしい湯に満足した。
以前、山の下りで膝を痛めて、登山は4年ぶりだったが、夫婦ともいつの間にか70歳で、白神山地に登れた幸せを噛み締めた。
ただ一つ、原生林だけあって登山口まで遠いことが難点か。
中部空港→青森空港→JR奥羽本線→さらに、車で2時間半走って、漸く登山口に到着。それでも、悠々とブナの原生林で輝いている、都会ずれしない大自然の世界遺産「白神山地」は、登ってみる価値があった。
黄金いろに輝く秋田の田んぼ、全国区の銘柄米「秋田コマチ」の刈り取りの季節だった。天日干しの稲の束が、まるで何十匹もの狸が行列しているように見えた。
11月下旬からは、深い雪に閉ざされる「白神山地」である。
2007年10月上旬
JR松本駅でローカル線に乗り換え、姥捨駅で降りた。
「姥捨て」や「田毎の月」ということばは知っていたが、JRに「姥捨」という駅があることさえ知らなかった。
駅員が誰もいない無人駅には「姨捨伝説の地」と看板が立っていた。列車が走り去った後、線路に沿った土の田舎道を懐かしく踏みしめて歩いた。信州の知人に会いに訪れたのに、珍しい駅名と看板を読むうちに、いつの間にか伝説の主人公になっていた。
ここは信州更級の地、ここに住んで40年、棚田を作りながら俺を育ててくれた親もすっかり年取った。腰がひどく曲がり、立ち居振る舞いがのろく、いつあの世に召されても何の不思議もないほどに弱ってきた。
貧しいこの村では、60を過ぎて役に立たなくなった年寄りは、山に捨てるのが江戸時代からの慣わし、秘密の掟みたいなもんだ。それは、凶作で食べる物がない年の口減らしにもなった。年寄りの足では、とても下りられそうにない深い山で、「ここはどこじゃ」という声を振り切って、逃げ帰ったのだ。
俺は育ててくれた親を捨てた。だから、あの冠着山〔かむりきやま〕を姨捨山っていうんだ。「姨捨」なんて言う停車駅なぞ、全国探してもここだけだろ?
俺は、親を捨てたことが気になって仕方ない。
ここを旅された芭蕉さんが、いつも俺にささやく。「おもかげや 姥ひとりなく 月の友」 なくは、泣くだろう。そう思うと余計切ない。
先日、村のおふれ板で「知恵者を出せ」の知らせを読んだ。とくに「この問題が出来なければ藩を取り潰す」と、お上からいくつか問題が出されていた。
幕府は、貧しい藩を取り潰したいばかりで、領主にいろいろ難題を吹っかけるのだ。
その中のひとつに、謎解きの問題があった。こういう問題は、ばあさんが得意だった気がした。俺は人に知られないように、ばあさんを背負って登った山を再び登った。
久しぶりに逢ったばあさんは、かなりやつれていた。この前逢ったとき、紙と墨汁が欲しいと頼まれたから持って行ってやったが、黙々と何かを書いている。
「姥捨てた奴も一つの月夜かな」 一茶
芭蕉さんの句もさすがだが、ここ信州出の一茶さん、中々鋭い句を読まれる。ああ、ばあさんは全部分かっていたんだ。申し訳ない。申し訳ない。
ばあさんは、それでも俺の顔見て嬉しかったとみえ、ぼそぼそしゃべってくれた。
「少し離れた場所に、藁だけの小屋があってそこに人がいた。たいさんとこうさんだ。まだまだ元気であそこの近くを流れる細い川で洗濯してたんだ。川を教えて貰っておらも助かった。洗たくはいい気持になるから」
「たいさんは、いつもナンマンダブ、ナンマンダブ 〔南無阿弥陀仏〕 と小声で唱え、『親鸞さんの教えの通りだ、この世は苦の裟婆だ』と言う。こうさんは、『この歳まで生きりや、なあの悔いもねえ』などと、よく言う」。
「それに、これもたいさんとこうさんに教えてもらったんだが、ゆっくりでも歩いてあの小屋の後側へ廻ると、わらびが生えとる。木の実も落ちているんだ。とくに、どんぐりはたくさん落ちているから、拾ってきて、皮をむいてから、石で潰すんだ」。
話を聞きながら、おれは、なんとかしてばあさんを助け出したいと余計思った。でもいまのままの村では出来ない。
そこで試みに謎解きの問題を訊いてみた。「針を使わずに、曲がりくねった管に糸は通せるものかな」。
ばあさんは、暫くの間沈黙した。それから、ゆっくりした口調で言った。
「簡単だ。管の先っぽに、多めに蜜を塗っておき、そこらへんの蟻を捕まえるのじゃ。その蟻を細い糸でくくり、管の中へ入れるのだ」。
長年の生活からの知恵、何と見事なこと。 ばあさん、もう少し我慢して。もう少し頑張って。
よし、おれでは解けない謎を、ばあさんは見事に解いてみせた。これを村長に出して、
年寄りの知恵をもっともっと活用しようと、命乞いしてみよう。心は決まった。
さて、この山を下って少し脇によると、長楽寺という古い寺がある。
あの寺の境内を歩くと、芭蕉さんや一茶さんだけでなく、立ち並んでいる心に沁みる句碑だけ見ても、人の心は昔から同じだなぁと思わせるんだ。
「更科や嬢捨て山の月ぞこれ」の虚子さん、「隈もなき月の光をながむれば まず姥捨の山ぞ恋しき」の西行法師さんたちが、おれを千年以上も昔の「古今和歌集」や「大和物語」の世界に引き込んでしまうのだ。
それにしても、千曲川が流れる善光寺平といわれるこの辺りは絶景だなあ。この景色を眺めると、農作業の疲れも吹っ飛ぶよ。昔から文人が好んでこの地を訪れたのには、ちゃんとわけがあるんだ。
長楽寺から、ゆるい山道を少し登るとあたりは水を張った棚田だ。棚田がおれを待っていてくれる。田植え間近い5月半ばのいまが一番の見ごろだろうナ。
幅4〜5メートルの小さな棚田から、奥行きは狭くても、横に10〜20メートルもありそうな田まで、透き通った水が張って、田の地底が見える。よくもこんなにきめ細かく作ったものだと思うよ。
斜面を細かく耕した棚田は、日本人の誠実さを現していないか?特にここの棚田は16世紀ごろから作られたと聞くぞ。
棚田が48枚固まっているのを「48枚田」と言うんだ。こんな所にもと思う小さな棚田から、かなり広い田まで、自然の草の仕切り、あぜが生き生きしているよ。
山の斜面に折り目をつけたような棚田の水の管理が問題で、想像以上の難問だったろう。
夜、月が出ると、全部で2千枚もの鏡が、見事に輝く。
この棚田ごとにひとつずつ映る月が、田の数だけある。それを「田毎の月」と言うんだ。
田植えが済み、か細い稲の苗が5センチほどの束になったら、田んぼはみどり一色だ。その柔らかなみどりの美しさは、眼が喜びの歓声を上げそうだが、「田毎の月」とは当分の間お別れだ。
天空に一つだけ余分の月が・・・。この不思議な美の世界は昔の文人をとりこにした。自然美への驚嘆、おれだって感動する。大自然の美しさだ。
「空にひとつ あまりて月の田毎かな」と松堂さんが歌った絶景は、この国の宝なんだ。
年寄りの知恵で、ひとまず藩取り潰しは逃れた。土地の領主はおれに訊いた。
「所望するものはないか?」と。おれは必死で、腹の底から答えたぞ。
「山に親を捨てるのは辛い。何とか止めたい」と。
「おもかげや姥ひとりなく月の友」松尾芭蕉の句碑をそこで見つけた。「なく」は「泣く」だろう。
(2007年9月改定版)
2005年5月7日の中日新聞は、「2004年9月の台風21号の豪雨で、壊滅的な打撃を受けた」三重県大杉谷登山道の7ヶ月後の惨状を、何枚かの写真入りで伝えていた。
とくに5枚の写真を添えての報道は、入山禁止が続く登山道へ、村職員と一緒に足を踏み入れた記者とカメラマンの、死にもの狂いの山歩き記事であることが、ひしと感じられた。
そして、以前読んだ「風がつよくなる」という文を思い出した。
「世界的に風が強くなってきたのではないか、と懸念し始めたのは、1990年1月、イギリス北西部で大風雪となり、千人以上の死者が出た頃である。
日本では91年にリンゴ台風といわれた台風19が来襲したが、リンゴの落果が多かったのは風の息〔突風〕が強いためであった。
95年戦後最大級といわれた台風12号によって伊豆、小笠原の被害が甚大だった。八丈島の最大瞬間風速48m/秒は最大風速の2倍になっている」
これは「風がつよくなる」と題した、気象研究家根本順吉氏の文章である。
この文章を思い出したのは、日頃、最近の気象の変化が極端で、風が強くなっていると感じていたからでもある。
最後の秘境といわれたこの大杉谷を夫婦で歩いたのは6年前。アルプス登山のような華やかさとは違う、つり橋と岩に巻き付けられた鎖だけが頼りの秘境、始めて見る深い透明な水の藍色がこころに焼きついた。その強烈な印象をこのホームページ「山歩き考」に載せた。
あのときも、1年に7〜8回の転落事故があり、「ここ転落場所注意」という看板に何回も会った。
大杉谷登山は緊張の連続だったが、今回の記事によれば、「登山道に沿い岩盤に打ち付けられた金属チェーンの手すりは至るところで寸断」、「長さ70メートルのつり橋が跡形もなく消えていた」とあり、根こそぎ倒された木々や、大きな岩が崩れ落ち、不安定な状態で止まったままの登山道を、必死で登る記者たちの写真に息を呑んだ。
山小屋の閉鎖も続くとあったが、山が荒れ、自然が壊れ、美しい日本の秘境が失われていくことが哀しい。
最後に、私たち読者は、今回の中日新聞のような、体を張った真剣な、胸を打つ報道記事を求めている。そうあらためて感じた。
ところは、海抜3000メートルを超す中国雲南省の秘境、ご来光と、雲海から高山が頭だけ覗かせる様は、大自然に生かされている人間を実感する。
事故は下りに起き易いというが、時間を節約しようと近道をしたので、難所続きの下山になった。くさり場に次ぐくさり場で、両手両足を使って急坂を下りる。およそ2000メートルあたりまで下りたと思われる。
一日中、陽の射さない雑木が生い茂る斜面、細かいブヨのような虫が顔全体に集団で襲いかかる。払いのけ払いのけしたが、とうとう1匹が右目の横を刺す。痛かゆさを我慢しながらの下山だったが、今度は針金のような、あるいはミミズくらいのヒルが顔に当たり始めた。目もあけていられない。この秘境にはヒルが飛ぶ。伝説のとおりだ。
人間の体に吸盤で喰らいつき、手で払うと手に吸いつく。そこは傷口となり、血が出る。見ると両足に10匹ほどが登山靴にとまっている。
現地の人の話では、雨の日は全身ヒルだらけになるという。下りに強い仲間の男性2人はもう5メートルほど下を歩いている。私はヒルと闘い、テンポを落としたうえに疲れ果て、わずかな斜面を見つけて腰を下ろした。
山も昼寝なのか、昼過ぎの山は静寂そのものだ。透明な空気を肺の奥深くまで届けたくて、思わず深呼吸した。と、かすかな音声が耳に入った。
木が茂った道が右に曲がった辺りに大きな岩が見える。そろりと近づくと、高さ2メートル近い洞窟になっている。それは奥深くから聞こえて来る。
どうやら、動物たちの会議らしい。熊、猿が真ん中で、右側に小さな池があり、メダカ、ザリガニ、ドジョウがいる。
左の古木の切り株が動いたように感じた。それもそのはず、長さ5センチくらいのヒルが、太いの細いの入り混じって、うじゃうじゃしている。よく見るとヒルで埋め尽くされた洞窟の中は、巨大なゴムまりのごとく、微動し続けていた。
猿と熊が近頃の食料問題と、生態系の破壊について現状を伝えていた。この百年で約百種類の鳥や哺乳類、両生類が絶滅した。この速度は自然に起こる絶滅の千倍の速さだという。
また、メダカ、ザリガニやトンボたちは、湿地はここ百年で半分になった。このままなら結婚もできない。子孫は絶滅しそうだと嘆いていた。
頭のいい猿と熊が、人間もわれわれと同じ運命だ。われわれは子孫を残すため、恋人のために特攻隊になって民家を襲うと決意を表明していた。と、洞窟を埋め尽くしたヒルたちが、一斉に立ち上がった。おれたちも、全員飛び立つ決意は固い。そう宣言した。
その会議の活き活きした様子に、ときが経つのを忘れて、傍聴してしまったが、全身がにわかにむずがゆく、悪寒がしだした。
先に下山した仲間は、遭難ではないかと、今頃大騒ぎしているだろうな。
うしろ向きになった門、大山〔鳥取県〕登山で歴史の面白さを味わった。
登り始めに、大山寺という大きな寺をめがけて長い階段を登る。その脇の道を、やはり長い階段で登ると、そこに大神山神社・奥宮〔おおかみやまじんじゃ・おくのみや〕があった。
遠い昔、1200年以上も、人々の信仰は神も仏も区別しなかった。素朴な人々の信仰心に、できたばかりの明治政府は、庶民のまとまった力を恐れて、神と仏を分離させることにした。明治初年、政府は政令で神仏分離を決めた。
一方は大山寺という仏に、片方は奥宮という神に、それぞれ信仰を分けよと指令したわけだ。
面白かったのは、双方立派な建物だったが、奥宮への入り口になる門がうしろ向きだったことである。
門がうしろ向き、これは変だなとしげしげ眺めるうち、ある考えが浮かんだ。もしかしたら、これは庶民の強烈な政治に対するレジスタンスではなかったか。そうに違いない。夫婦の意見が一致した。
そういう目で見ると、盛況な大山寺に比べ、やや人も少なく、神社も古い感じの奥宮で、「出雲大社はここがもとなんですよ」と、何度も繰り返す宮司の態度も自然に理解できる気がしてきた。
民主主義といいながら、過半数の国民が反対している自衛隊の海外派兵に、納得できる説明もない。国会での十分な審議もなく、巧妙に国の進路を大きく曲げる権力に、有効な抵抗ができない現在の私たちは、どうしたらいいのだろう。
中国地方でただひとつの山らしい山、大山。1700メートルの休火山は、北壁の崩落が激しく、そこからの登山は禁止になっていた。近くから仰ぐとかなりの険しさで迫ってくる。
朝6時から登り始めた。日本海や、穏やかな中国地方の平野を望みながらゆっくり登った。
7時半、高さ20メートル以上あると思われるブナ林、楽しげに大空を泳ぐようなたくさんの葉っぱたちが、出たばかりの朝日に光り輝く。その木々の下で、朝飯のおにぎりを頬張った。最高の贅沢だった。
錦繍ということばがあるが、色づき始めた自然の木々は、『山は病院』とばかりに、名古屋から飛行機で駆けつけた中年夫婦を、温かくもてなしてくれた。〔2003年10月、大山登山〕
標高1984mの月山は、羽黒山、湯殿山と共に、出羽三山として古くから知られた山である。
登山を計画した9月、突然、兄の訃報が入った。葬儀の翌朝、迷ったが予定通り決行した。
芥川賞受賞の森敦著『月山』によれば、羽黒三山は別名「臥牛山(がぎゅうさん)」で、牛が北に向けて臥したような山で、首の部分が羽黒山、背のあたりが月山というのだそうだ。
ガスと雨と、横なぐりの風に吹き飛ばされそうになりながら、8合目から頂上まで3時間かかった。夫婦で「兄の涙雨だ」と言い合った。月山は、「死後を考える山」といわれる。偶然親族の死と登山が重なったが、なぜ月山はそう言われるのだろう。
辿り着いた頂上に、いかにも歴史を感じさせる古い小さな神殿があった。一時的に雨が止んだので思いついて、お祓いを頼んだ。30代半ばくらいの若い権禰宜(ごんねぎ)さんが、達筆で木の板に故人の名前を書き入れ、祝詞と何首かの歌を読み上げた。それは2000メートルの静かな大気に響いた。
「惜しむべく 悲しむべきは世の中の 過ぎてまたこぬ月日なりけり」
両の手を合わせながら、朗々と読み上げられる歌を心に刻んでいるうちに、自然に涙がこぼれた。そのとき、木製の小さな神殿から、やわらかい何かが、灰色の空へ昇ったのを見た。
1400年の昔も、人々は、神も仏もなく信仰した。この高い山の、深閑とした山頂で、人知を超えた何かに自然に手が合わさった。
兄は2月に連れ合いが急死し、第二の職場も定年退職した。死後の整理中、電気、ガスがそれぞれ千円程度しか使っていない領収書が出てきた。そこには猛暑の中、冷房のない家で、暑さと心の虚しさと必死に闘った姿が刻まれていた。
子どもがなかった2人は、近々家を改築のため節約したらしく、小金が預金通帳に埋まっていた。
ペイオフを意識してか、いくつかの金融機関に預金を分散してある。それから死まで2ヵ月、どんな心境の変化があったのか?
少なくとも、人はどんなささやかでも生きるには希望が要るよと、兄から教えられた気がした。
「家の後始末をお願いします。銀行等の預金は適当に処分してください」遺書に記された文字が憐れで、切なかった。それは、口下手で、頭がよくても頑固な狭さで不器用に生きた、兄の人生そのものだった。
『いま、ここに生きて―五十人・百編のエッセイ集』掲載
(中部エッセイスト・ソサイエティ同人、創栄出版、2003年4月)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
月山の山頂で心に沁みたうたを、もう一度正確に知りたくて、期待しないで神社に便りを出した。思いがけず以下のような親切な返事が届きもう一度感激したので、ここに紹介します。
『月山は9月15日閉山し、静かに聳えております。
拝復
先日は遠路遥々月山神社本宮にご参拝戴き、定めし大神様ご満悦の事と拝察申し上げます
御兄様がお亡くなりになり、さぞかしお嘆きの事と存じます
その慰霊の為に月山神社本宮の霊祭所で御霊様の御供養のご奉仕をさせて頂き、御霊様もお喜びになられたと拝察申し上げます。
古来より出羽三山は御霊様が鎮まる山として、大勢の皆様より篤い御信仰をお寄せになり、とりわけ月山は一番高いお山であり多くの皆様が御供養をなされております。
初めてご参拝の方は普通はただ手を合わせるだけの方が多い中で、宮地ご夫妻様はご供養のお申し込みをされましたので、印象深く記憶しております。お印の線香を差し上げたのもその為であります。
ご供養の中で祝詞の後、何首かの詠歌を奏上致しております。その中の一首がお問い合わせの歌と存じますので、記してみたいと思います。
惜しむべく悲しむべきは世の中の過ぎてまた来ぬ月日なりけり
別れにしその日ばかりはめぐり来て行きもかえらぬ人ぞ恋しき
百足らず八十のくまぢに手向けせば過ぎにし人にけだし逢はむかも
御霊前にお捧げ下さい
月山は今月十五日閉山致しました。静かに聳えております。来年七月一日がお山開きとなっております。又のお来山をお待ち申し上げております。 敬具
出羽三山神社 月山神社奉行代理 権禰宜 大江忠彦』
北海道の北西の海に、大粒の涙のように浮かんでいる礼文島と利尻島。最果てのその島を訪れ、利尻山に登ったのは9月だった。利尻富士と呼び、憧れる人も多い。頂上付近が岩で切り立って、険しい美しさだ。
登り下りで10時間の登山は、楽ではない。そのせいか出会った登山者の大部分は若者だった。朝6時、スタート地点の林道で昨日知り合った青年と、大勢の高校生と一緒になった。私たち夫婦は、休憩の度に高校生たちを抜いたり、抜かれたりした。
7合目あたりからは、全身から吹き出る汗を拭きながら、息を弾ませ、這うようにして登った。やっとの思いで辿り着いた9合目に『これからが、正念場』という看板があった。自分では最大限の努力をしたと思っても、もうあとひとがんばりが・・・というのは人生によくある。
高校生の何人かが「もうゲンカーイ!」と叫んだ。スタートから既に5時間半以上登り続けた。私は思わず「頂上はほんの目の前だよ!」と大声で言った。すると、「ホント?」と倒れそうだった子たちの目の色が変わった。実は私たちも、ダウン寸前の小休止だった。
頂上近くなると、ガレタ急斜面をずるずる滑りながら、ロープ一本にすがって登り続け、ついに最後の難所をふんばってみんなで笑顔の昼食となった。
狭い頂上に、先着の2人の青年が私たちを待っていてくれ、一緒に写真を撮った。
引率の先生からはおいしい紅茶をご馳走になり、少し話ができた。「東京からの修学旅行です。約百人来た中の有志30人」という。「挑戦してみたい生徒がこれだけいて、励ましの声をかけて貰ったりして目標が達成できた。これが人生のどこかできっと活きてくる」。
何もしなければ楽なのに・・・。そういう心意気のある先生が頼もしかった。
この計画では事故でも起きたらと、父母から意見もいろいろ出たが、同行の校長先生と女性のガイドさんも笑顔を輝かせていた。
利尻山は、若者の笑顔がいっぱいの、思い出深い山になった。
一年前のいまごろ、職業生活卒業記念にと、夫婦で鹿児島県の特攻隊基地だった知覧へ行った。平和記念館の入り口近くにグランドピアノがあった。
ベートーヴェンのピアノソナタ『月光』を弾いて、特攻隊として死の出発をした若者が弾いたのと、同じ機種のピアノだとのこと。これは『月光の夏』という映画になった。
記念館には、たくさんの遺書や写真などが陳列してあった。
『あんまり緑が美しい。今日これから死にに行く事すら忘れてしまいそうだ。真っ青な空 ぽかんと浮ぶ白い雲 6月の知覧は もうセミの声がして夏を思わせる・・・』
『人の世は別れるものと知りながら別れはなどてかくも悲しき』
『俺が死んだら何人泣くべ』
これらの遺書に、17歳から22歳くらいの若者たちの、ほんの半世紀前の、人としての切なさが胸に迫ってきた。
青年(少年)たちが命を捨てに沖縄に向かったとき、計器もない、おんぼろ飛行機に乗って、必ず目印にしたという開聞岳にも登った。海に突き出た見事な円錐形の山である。
指宿から知覧に向かうとき、ずっと茶畑が続いていた。そのときの、タクシーの運転手がとつとつと語ってくれた。
「いまは飛行場も茶畑です。特攻隊の話が過去の物語になるのが哀しい。さらに口惜しいのは、日本の南端で、太陽をしっかり浴びて早い時期に出る新茶なのに、知覧茶の知名度が低いため、知覧からのトラツクと、静岡からのトラックが出荷の途中で落ち合い、『新茶静岡茶』というラベルに張り替えること」。
知覧は切ない町、開聞岳は哀しい山である。
知覧についての『青春譜』 船山昭
東北の船山氏から、メールが届きましたので、掲載します。
戦争、とりわけ特攻隊、そして知覧。
知覧は終戦記念日が毎年やってくると、民放で関連ドラマがあり、そこで知覧を知りました。
今も知覧に存命している実在のおばあちゃんが若い戦士を送り出した話、もちろん当時の娘であり、彼らと同年齢だった・・・・。私も機会を見つけて知覧の武家屋敷など見たいと常々思っておりました。
「おまえ、戦争を美化するな、悲惨だ」と言われようが、やはり特攻にあこがれ、きっと自分も志願するだろうなどと書いておそらくひんしゅくをかったと思います。「聞けわだつみの声」や、戦争に触れたのは高校2年のときです。その一年は、私にとってバーチャルでも、人生を、人生観を決定した年です。その後今日まで、本当にオレは特攻にいけるだろうか、口先だけなのだろうかいつも自分に自問してきたような気がします。
ここらでは進学校ですから、そろそろ大学入試を考えるときでした。私は親と同じように山形大学の教育学部から、教員なのかな、だろうなぁと、自分の人生、宗教の言う「与えられた人生」・・・そのどちらでもない普通の高校生でした。
私は社会、歴史の成績がよくなかったので、図書館で何気なく近代史の分厚い本を見ていたら、2ページの見開きで特攻に行く、にこやかな写真に目が動かなくなりました。帽子を振って水杯で基地を飛び立つ動画は、テレビで見たことがあったのですが特攻の「人」を見たのは始めてでした。
そのころ、歴史については大人が問題をしかけて、子供がその後始末をする。それは当然だ(現代の赤字財政も結果そうなる)というスタンスは持っていました。しかし、この写真は決定的でした。
零戦の翼に、はしごをかけてもらって、小さい野草の花束を翼の上でかがんで整備士から受け取っている写真です。胸を締め付けたのは、その顔です。明らかに私と同年くらい、いや、もっと若い中学生くらいに見えました。このころ、黒くならない白いひげが鼻の下に私も伸びてきたころです。
その逆光をあびた顔の口の上の白いひげが金色に(モノクロ写真)光っていたのです。数時間後、海に消えて無くなるひげです。
問題は手渡す側の整備士はあきらかにおっちゃんの顔でした。我々高校生はつっぱっていても、やはり親の庇護のもと、何不自由無く高校生しています。子供は何時の世も大人が社会全体で守るものだと思っていました。
その後、戦艦大和に特攻出撃命令を出した大人(参謀本部)は、戦後も生き、俺も後から必ずついて行くと言って送り出した大人、特攻隊の生みの親、大滝も生き、関東軍がシベリアへやられても日商岩井の会長は生き、南方の島で玉砕しても、カダルカナルの辻参謀は生き・・・・・、悪魔の飽食の部隊長はミドリ十字で、戦後もエイズで死なせて自分は生き・・・・・死に往く彼ら同士は「靖国神社でまた会おう」と言いました。約束した人たちはだれも居ないので、いま、いろいろ問題になっていますが、もし約束して片方が、たまたま生きていたなら、死んだ戦友と、どこで会ったらいいのでしょうか。
このように、今日の私のエキスが全部「知覧」の語彙に篭っています。
知覧のお茶をもらって、過去の歴史の責任は否応無しに、われわれ後世の人に「負わせられる」という、歴史のアイロニーを強く感じます。
近所の小学生たちが雪だるまを作っている。大きな雪だるまにしたくて、手付かずのわが家の庭の雪を求めて、数人が小さなソリを引いてきた。「その舟いっぱいの雪、面白いね。写真撮ってあげる」と言うと、「舟じゃないよ、ソリだよ」。楽しく子たちと話しながら、心は青春時代のスキー場へ飛んでいた。
その日、山奥の白骨温泉スキー場は夜から降り続いた雪が、さらに新雪となって覆いかぶさった。白く濁った温泉の湯がいいと評判だったが、交通の便は悪く、スキーを担いでかなり歩いた。
当時、三重県の研修施設で半年から1年間、全国からの挑戦者が研修を受けた。千人規模の学園で、年末年始休暇に私たち男女10人が、スキー旅行を計画した。
スキーは、初歩の直滑降、斜滑降、ボーゲンが出来る程度だったので、現地で指導員を頼んでもう少し技も磨こうというつもりだった。
天気は快晴、新雪が眩しく蒼い空に映えて、気分は最高だった。
やや急な斜面に立った指導員を前に、10人はズラッと並んだ。「1人ずつ、斜滑降で滑ってください」。その指示に、みんなひるんだ。新雪は美しいが深くて、斜面も急で怖い。
6人の男性は、九州や、関西圏の出身が多かったが、特にスキーがうまい人はいなかった。
無鉄砲にも思わず私が滑り出していた。最初は順調だった滑りが、新雪はスキー板にまといつき、いつもの感じが出ずに、アッという間もなく転倒した。
ふんわりした新雪に深く抱き込まれて、私は起き上がることができなかった。それを見て、男たちは大あわてで助けにきてくれた。結局左足のひざ捻挫で身動き出来ず、スノーボートで下山するはめになった。
年が変わって研修が再開したが、ねんざした足を包帯でぐるぐる巻きにし、広い学園内の移動には女友達に自転車に乗せて貰った。治療に1カ月ほど通ったが、男性が大部分の学園では目立った。
同行した男性たちは、友人から「可哀相に、君たちは何してた」と責められたとか。浴びるほど親切を貰ったのに・・・。恥多い人生の青春のひとこまである。
暖冬続きで、雪とはすっかり縁が切れた近ごろ、珍しく天から冷たい贈り物が届いて、久しぶりに青春時代の気分に浸った。過ぎ去ってみれば、みな愉しい思い出になる。雪には人を愉しくする魔力がある。
『ここ転落事故現場』という看板が、登り坂の岩場にあった。岩に打ち付けられた太い鎖を、両の手で必死で掴みながらそれを見た。重い大きなザックを背にした自分も、底深い谷に吸い込まれそうで、絶景にカメラを向ける余裕はなかった。鳥のさえずりさえ聞こえない、深山幽谷の世界だった。
「そんな思いまでしてなぜ登るの?」。登山とは無縁の知人は理解できない面持ちで問いかける。なぜなのだろう。
深い谷と滝、それに10近いつり橋を渡る三重県の大杉谷、山の高さは千メートル余りで高くはない。が、渓谷の深さと、濃く、限りなく澄んだ藍色の水の美しさは、ハッと胸をつかれる、感動的な天然色だった。
前へ進むしかない山の中、山小屋へ2泊し、奈良県大台ケ原へ向かう。ゆとりをもった計画で、1日5時間位ずつ登り降りしたが、危険の多い登山から、よく無事で帰れたと思った。それは、この山で98年1年間で、8人もの転落事故があり、私たちが下山した翌日、また転落死亡事故のニュースを聞いたから、なおのこと感慨深かった。
山で死ぬことに、美しい憧れに似たものを抱いた若い時期もあった。『いつかある日 山で死んだら 古い山の友よ つたえてくれ・・・』深田久弥がフランスのアルピニスト、デュプラの詩を訳したという歌で、当時評判だった井上靖の小説『氷壁』の中でも取り上げられた。詩とともに、旋律に素朴な魅力がある。
しかし、「山での死は、天候の判断その他、技術的力量不足であり、恥ずかしいことだ」。と言った山のベテランの言葉の方が正論だろう。とくに最近の登山事故多発は、中高年の登山者増加が1つの大きな要因かも知れない。
勿論、山歩きが一部のアルピニストだけのものから、私たちのような普通の庶民が、その悦びに浸れるのはいいことである。日曜日の夕刻の駅などで、1人で、あるいは夫婦や友人数人で、山歩きの帰りらしい姿に会うと、山の清々しい空気が匂うようでうれしくなる。しかし、数年前、立山や尾瀬で会った人の中で、観光バスで乗り付けたままの軽装や、サンダル履きのような姿を見ると、山に失礼だと思う。
大杉谷は吉野熊野国立公園になっており、いたる所に滝が流れ落ちる、日本有数の多雨地帯だ。日本の滝百選に選ばれた「七つ釜の滝」など、豊かな水量の滝と、姿が美しいつり橋が続いた。下から大杉谷へ登るコースで、出会った登山者はわずか2組、静かな山の息遣いを満喫した。
岩場から岩場、くさり場からくさり場と、緊張した登り下りの連続で、『ここ転落事故現場』の看板をいくつか通過しながら、親友でも、夫婦でも各々、自分の責任でしつかり足場を確保して登る以外途はない。これが、登り終えたとき、深い連帯感につながる。
山登りの悦び、それは極上の大自然が味わえること。全身から汗が吹き出て、体の細胞の隅々まで生き返るような爽やかな気分になれることである。緊張と疲労を乗り切った達成感、大自然の中のちっぽけな自分が、生かされていることを実感する瞬間にあるのではないか。
日本百名山を選んだ深田久弥は、1500メートル以上の山を対象にしたという。百名山をいくつ登ったと、競うように山歩きをするのは愚かなこと、今日登れたこの大杉谷が、私にとっての百名山である。
木曾駒ケ岳(2956m)に登った。
ロープウェイが、2600mの高さまで一気に運んでくれるからと、軽くみるのは危険だ。3000mの高さに、体が慣れる一定の時間が要る。私たち夫婦も、1時間半ほどの登りの前半で息が切れた。ロープウェイを降りて、その辺りを暫く散策した方がいい。
整備された登山道だったが、途中で小休止していたら、地下足袋を履いた土地の人が3人降りて来て「落石に気をつけて」と注意された。見上げればごろごろとした小さな岩だらけ、頭を直撃されたらと、気を引き締めた。
頂上は5つの峰が連なっており、駒ケ岳の本岳、宝剣岳、それに伊那前岳、木曾前岳と中岳の5つ、すべてを登り、下った。宝剣岳(2931m)の岩場は、所によっては垂直にも見える急角度の鎖場を、登り降りする緊張感ある登山だった。天気に恵まれたからすべて登れてすっきりしたが、山歩きの第1の悦びは、こういう「達成感」だろうと思う。
山歩きのもうひとつの悦びは、大自然の息吹きを肌で感じることである。清らかな空気を吸って、思いきり体のエネルギーを使うので、登っているときはきつくても、体調がよくなる。
やっとたどり着いた山小屋で、西方浄土を思わせる黄金色の夕陽を見た。光の波の音が、聞こえてきそうな空、それが次第に燃え出し、真っ赤になって、遂に山全体を影絵のように浮かび上がらせる。3000mの高地で見る、大自然の叙事詩だった。夜、小屋の外に出てみると、満天の星がこぼれそうだ。山の星は1粒1粒が大きな宝石のようで、若者が「天の川なんて初めて見た」と叫んでいた。気温は零度、思わず身震いした10月初旬の夜だった
翌朝、雲海の上に顔を並べる山々、南に富士山が頭だけ出し、赤岳が見えた。「あのぎざぎざしたのはのこぎり岳ですよ」と年配のベテランが教えてくれた。のこぎり岳と並んだ甲斐駒ケ岳が見えた。北方に目を移すと、すぐ近くに御岳、乗鞍岳がゆったりと優雅な姿を見せ、遠くに初心者でもすぐ分かる槍ヶ岳や鹿島槍、それを隠そうとするかのような笠ケ岳、快晴という運に恵まれた者が味わえた大パノラマだった。
畳1畳に2人という山小屋は、寒くてヤッケを着たまま、靴下も履いたまま、きれいでない毛布、破れた布団にもぐりこむ。水が少ないので顔は洗えず、口だけうがいする。物が豊かな平地では耐えられないだろう。野宿よりましと考えればありがたいと思えた。大部分が中高年というのも、こんな所に理由があるのかも知れないと、そのとき思った。
山小屋では、いろいろな人との出会いがある。その夜は、6畳くらいの部屋に4夫婦がひしめき合って寝た。テレビも新聞もない食後のひとときは、山歩きの体験談で盛り上がった。百名山を80近く登ったという夫婦は大ベテラン、あとの2組の夫婦も、今年槍ヶ岳や白馬に登ったとか。2泊目の頂上小屋で隣の布団に寝た夫婦は九州の人で、山岳小説をことごとく読んでいた。面白かったのは、このホームページにも出ている森村誠一氏が、初期の頃ずっと山岳小説を書いていたと九州男児がいったこと。不勉強だった。『悪魔の飽食』で知り、このホームページが縁で、僅かな触れ合いの中で知った氏の誠実な人柄、別の友人もそれをいっていた。意外性が面白かった。
私たちも、若いときには登山やスキーもしたが、人生の夏は共働きで忙しく、余裕がなかった。10年前、私の退職記念でスイスの山を5日間歩いて病みつきになった。そして屋久島や尾瀬を歩いた話をした。九州の人、関東の人から、北海道や北アルプスの山々の、いい話がいっぱい聞けた。私たち以外はどの夫婦もベテランで、夫婦で山歩きをする中で、絆を深めている様がうかがえ、和やかな雰囲気が好ましかった。
恐らくもう逢うこともないであろう、彼らとの一期一会は少し切なく、楽しかった。これが山歩きの悦びのおまけである。
乗物はなんといっても自動車より鉄道、特に旅は列車に限る。真っ直ぐのびる2本のレールを見ると、心は遙かな旅先へ飛ぶ。
1989年夏、標高4千メートルのユングフラウヨッホ目指して、一家でスイスの登山鉄道に乗った。
3輌連結の列車は小さく、乗客同士はすぐ触れ合う近さになる。列車は標高2千メートルから3千メートルを越す高地を走る。聞こえてくるのは英語、フランス語とドイツ語ばかりである。日本人は私たち4人だけだ。黙って耳を傾けていると、宇宙を飛び回る『銀河鉄道』に乗ったような、不思議な気持ちになっていった。
間もなくトンネルに入る。列車はアイガーの固い岩盤へ突き刺さる。車内放送が始まった。「高山病に注意」とのこと。案内は3カ国語と日本語だ。
5分間停車。トンネルに作られた大きな窓から外を見た。魔の山ともいわれるアイガー北壁をぶち抜いた窓だった。そこには氷のヨーロッパアルプスが輝いていた。長年憧れたヨーロッパアルプスは、泰然として、あまりにも静かだった。
列車の中はどんどん気温が下がり、思わず上着をはおる。高度を上げながら約40分間、トンネルの中を走る。
終点のユングフラウヨッホで下車し、そのまま洞くつの中をゆっくり歩く。高地での急な動作は禁物である。暫く洞くつの中を行くと、遂に真っ白な山に囲まれた氷河に出た。標高4千メートルを越すユングフラウが目の前にそびえる。暗い空と対照的に、山も氷河も真っ白な固い光を放っている。雄大な大自然に畏敬の念が沸く。
この『夢の氷河鉄道』が完成したのは1921年、もう70年も昔だった。スケールの大きな着想と鉄道建設の技術には脱帽である。
大自然と、科学技術の発達が見事に共存している姿に、あらためて感慨を深くした。
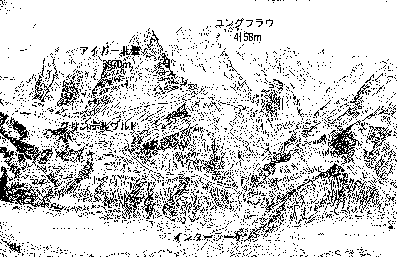
一番住みたい所はスイスである。昨年スイスを旅してからその魅力のとりこになった。
アイガー北壁、ユングフラウヨッホなど4千メートル級の山々、なかでもマッターホルンが天に向かって屹立する姿は、他の山々とは違った孤高の美とでもいう姿で私の胸をうった。
透明な空気のなか、リッフェルアルプ湖に逆三角形に映ったマッターホルンには、ただ自然の美への感嘆しかなかった。
2千メートルの高地を5日間歩き廻ったが、おっとりした牛たちが人なつっこくすり寄って来て、まさに『アルプスの少女ハイジ』の世界だった。黙々とごみを拾っていた人に逢ったのも印象的だった。
「スイスがいい事は分かった、だけどずっと住む気になる?」と知人は言った。だが私は本気でそう思っているのである。
私を本気にさせたのは、単に神秘的な自然に魅せられたというだけではない。それは10年前国民議会で国連に加盟を議決したにもかかわらず、2年後国民投票で否決したという事実を知ったからである。政府も議会も賛成したものを、国民多数が拒否するという事は普通の国では考えられない。真の意味の民主主義であり、それだけでも大変な国だと思った。
スイスの国是は「永世中立」である。国連に加盟すれば中立維持が出来ない。筋道の通らないことはしないというのがスイス流なのである。大統領の任期は1年で、権力の集中から生まれる禍が起こり得ない仕組みであることが分かった。州単位の徹底した民主主義が確立するまでに700年を要したという。
どんな田舎でもトイレがきれいで、窓という窓には例外なく花が飾ってあった。一人当たりの総所得が世界一で、国民全体が自分の生活に満足しているという。「人に親切にする」というスイス人気質の源が理解出来たような気がした。
もっとも名古屋生まれ名古屋育ちの私は、名古屋は嫌いではないし、終焉の地はここにしたいと思っている。でもまだわずかにスイスへの未練が絶ち難いのは、風光明媚な土地というばかりではなく、やはり庶民主体の民主主義への憧れだろうと思う。
この夏、国内外で、これからの権利意識について考えさせられる体験をし、話を聞いた。
ローマ空港から映画「終着駅」で有名なテルミニ駅へ向かう列車の中だった。列車は満員で半分以上の客が通路に立っていた。そんな中で車掌が座席4人分をとって事務仕事を始めた。間もなく車掌は検札に立ち、若い2人のイタリア人が座った。10分間ほどで検札を終えた車掌は、当然とばかりに、強制的にこの2人を立たせた。
車掌は再び4人分の座席に書類を広げ、平然と事務をとり始めた。満員の乗客は誰1人不満をいわない。
彫りの深い顔に口ひげを蓄えたその車掌に、夫が思わず「ここの席はOKか」と聞いた。「ノー」。私たち夫婦は大きな荷物でふさがれた通路で、他の客と一緒に体を傾かせていた。
その時私は塩野七生が『イタリアだより』で書いた、イタリアの郵便事情を思い出した。「半年前までは、5日で着いた郵便物が、このごろでは1カ月かかる。ミラノのある支局では、500人出勤すべきところ通常150人が欠勤する」というのだ。
働く人の条件が良くなるのは大賛成、しかし郵便も鉄道も、こんな「権利意識」はおかしくはないか? これからもこんな状態を続けてイタリアは生きのびられるのだろうか?
わが名古屋市でも似たケースを聞いた。近頃市民から長時間保育の要望が多く出される。子供の数が減って、保母は余り気味である。しかし労組からはパート保母300人増員要求が出された。夫の友人I職員部長は「保母増員なんてとんでもない。現在の人員で時差勤務すべきだ」と一喝し、団交は決裂した。
その後市側の言い分が通って、1人の増員もなしで現在、長時間保育は順調に進んでいるとの事。夫から詳しくその後の経過を聞き納得できた。
これからは長時間保育の希望が増えるだろう。けれど子供の数は激減している。子供のためのいい保育環境と、働く人の権利、社会の変化と共に、権利意識も変わるのであろうか?
日本の若い娘が、外国で、大きな袋を両手に下げ、ブランド商品を買いあさる報道を苦々しく見た。日本の恥をさらす思いである。
外国旅行そのものは決して悪い事ではない。しかし、わたしなら断然その国の歴史を確かめて歩く旅にする。あるいは芸術三昧の旅にしたいと思っていた。
3日間ローマ遺跡を歩き回り、芸術に埋まりそうなフィレンツェの古い街を、新たな感動を押さえながら歩いたのは昨年の夏だった。
そして次の目的地に向かう列車の時間まで、ファッションの店を見て回った。『グッチ』や『ルイヴィトン』など、日本でもよく聞 くブランドの店は中まで入ってみた。しかしこれはという商品にはお目にかかれず、日本の店とあまり変わらないという印象だった。ファッションでも、特別胸が踊るような服はなく、私の感覚がおかしいのかなと思い直した。
そろそろホテルへ荷物を取りに帰る時間になった頃、街なかのウィンドーに初めて心引かれる服を見つけた。しかも夏の終わりでバーゲン品の札がかかっていた。素材はシルク、色合いはいかにもイタリアらしい地味なグレーが基調のパンツスーツだった。
こうなるとぱっと胸に明かりが灯ったように興奮し、値段を確かめた。安い。日本で買う値段の半額である。ためらうことなくドァを押した。そして、単語をつないだような英語で、ウインドーの商品を指し、「パンツスーツ」と言った。
どの店もそうであるが、イタリアの店員は男性が多く、彫りの深いギリシャ 彫刻のような顔で、試着を指示してくれた。映画『旅情』のヘップバーンのような気分で、足が隠れてしまうほど長過ぎるブラウスの試着を終えた。「偉そうな事を言っても、バカギャルと変わらないじゃないか」もうひとりの私がささやく。強い円で世界をのし歩く嫌な日本人、それを演ずる自分に、一方で抵抗しながら店を出た。
かくして、中年の小母さんは、立派な袋を隠すようにしてホテルへ急いだのである。その袋には『トラサルディ』とあった。
11月のその日、鈴鹿連峰釈迦ケ岳は快晴だった。登ったコースは、崩壊性のガレが深く切り込む急坂で、ロープに掴まりながら、まるで岩登りのように両手両足を使って登った。
およそ2時間、少し平らな一角を見つけてひと息ついていると、小学生2人とその両親の4人連れが登って来た。「もう死にそう、ここで弁当にしよう」と子どもが言えば、母親が「なんで登らなきゃいけないの?」とブツブツ言っている。文句を言われる父親が気の毒だなと思った。すると「山があるから」とボソッと父親が言ったので何故かホッとした。
頭から背中まで汗びっしょりで、半袖のTシャツ1枚で登ったが、頂上で弁当を広げて、20分もすると、谷から音を立てて吹き上げる風は初冬の冷たさで、思わず上着を羽織った。
頂上を極めた達成感とダイナミックさは、里歩きにはない。頭の芯まで染み渡る新鮮な空気、緑の中に時折ハッとする楓の黄色と、モミジの朱が晩秋の山を彩る。
今年『夫の始末』で女流文学賞と紫式部賞を貰った田中澄江は88歳で山登りの現役、雑誌にこんな文を書いている。「私はまだ痴呆化した高齢の山仲間を1人ももたない。90歳を越えて週1度、80歳を越えて月20日は山という人たちも知っている」。さらに「健康で意志を強くもてば、周囲の人を幸せにする。それが生き甲斐」と。
私にはとても真似ができない驚異的な体力、意欲である。しかし、命は永遠ではない。
『杖つきて歩く日が来む そして杖が要らぬ日が来む 君も彼も我も・・・高野公彦』こんなうたが身に染みる。
50代になったとき、考えるところあって勤めていた大企業を退き、自宅での仕事に切り替えた。ゆとり時間が増えた喜びを感じる日々になったが、今年は早や還暦、人生も晩秋である。残り時間が少ない。
若葉が萌えた山も紅葉し、落ち葉になり朽ちていく。この大自然のように、自然体がいい。子供たちも自立していった。親はその肥やしになればいいのだ。オレンジ色の入り陽が、鈴鹿連峰を影絵のように浮き上がらせ始めた。晩秋の山が暮れてゆく。
標高2500メートルの、立山室堂(むろどう)まで交通機関が通る。便利な時代になった。
2千メートルを越すと、景色は一変する。夏でも雪渓の白い帯を縦にかけて、静かに横たわる3千メートル級の山を目の前にすると、不思議な感動が体中を走る。
しかし、近そうでいて、その頂上に立つことは容易ではない。不安定な岩場が続き、傾斜60度位に感じる。私たち夫婦はあえぎながら、立山の頂上にたどり着いた。
シーズンとあって頂上には、学生や女性のグループなどがくつろいでいた。
たまたま、さして広くない頂上の一角に、直径2メートルもあろうかと思われる、大きな袋に入れられたごみが、ずらり並んでいる事に気づいた。量の多さから、春以来のおよそ半年分と思われたが、あらためて人間の出すごみの多さに驚いた。
その時、上空にヘリコプターが飛んできて旋回しながら着地点を探し始めた。すると全員同じ藍色の半纏を着て、登山の装備をした人々20人ほどが、休憩所から次々出てきた。聞けばその日は、地域の人たちがボランティアでごみを山から下ろす日だそうである。ここまで登ってくるだけでも大変なのにと感心する。
ヘリ3台は、騒音を出しながら急降下し、3千メートルの山から、順次ごみをぶら下げて紺碧の空に舞っていく。まるで空中サーカスを見る感じだった。頂上でひといきついた人たちも、視線をその風変わりな空中ショーに向けていた。
天気快晴で微風、絶好の登山日和であった。
細胞のひとつひとつにしみ込むような爽やかな空気に満足して、いよいよ下山時刻になり、自分たちのごみをごみ箱の前まで持っていった。空き缶だけでもジュース、お茶、それにビール缶が各2つずつ、さらに弁当の空き箱が2つである。ここに捨てれば荷物が減る。捨てるべきか否かでおおいに迷った。
いままでなら、当然のようにごみ箱に捨てただろう。 けれど、先程から見た現地の人達の苦労を知って山に捨てるのはマナー違反というもの。結局、ごみはナップザックに入れられ、 私たちはごみと一緒に下山した。
夏休みに夫婦で3泊4日の「尾瀬」横断を計画した。夏休みの「尾瀬」は満員だった。 「たたみ1畳に1人、石鹸シャンプー禁止です」山小屋へ電話したときの相手の言葉に私は少しひるんだが、重い登山靴で出掛けた。
国立公園の「尾瀬」へ、漠然と憧れてきた私達だったが、そこで得難い清楚な自然と、 それを守る切ない人生に出会った。
「峠には細い道があった。広葉樹の緑のトンネルの中に、小さな冷たい泉がわいていて、数百年もの間通り過ぎる旅人を慰めてきた。 峠の名は尾瀬三平峠、いま若葉がもえ、鳥たちの歌うこの季節に峠の道は死につつある。泉から100メートル足らずに迫るブルドーザーを見た。すでにブナの木は切り倒されて転がり、木陰はなかった」。
昭和46年の朝日新聞に載った『峠の泉が涸れる』という題の投書である。投書の主は尾瀬の山小屋の主人、平野長靖氏だった。平野氏は環境庁長官大石氏に直訴して、進行中の自動車道路建設は中止になった。
しかしその冬、山小屋のきつい仕事と、自然を守るための闘いのなか、36歳で遭難死した。同世代の私は胸打たれた。
行程の半分程は45度の急坂で、息を切らして何時間も上り下りしたが、その姿は現代風にカッコいいものではない。不器用な生き方の方が私には合っているかなと思いつつ、登り、かつ歩いた。
湿原に咲く黄色いミズギクや、紫色のオゼアザミが穏やかに私達を待っていてくれた。 「ワインいかがですか?」山小屋の夕食は食卓が一緒になった男性の言葉で和やかになった。「夏休みですから新幹線に12時間乗りました」。芒洋としたその若い父親は、九州から男の子3人と奥さんで尾瀬に来たという。すでに親ばなれし友人達と夏休みを楽しんでいるわが子達が、一瞬頭をよぎった。「尾瀬」浸けの夏休みは終わった。
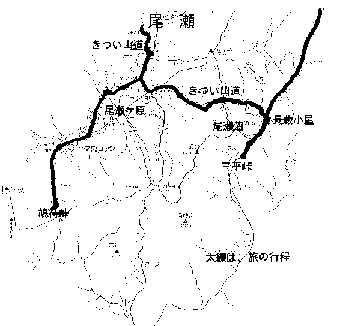
〔付記〕 思いがけず、この文をお読みくださった朝日新聞社の深沢氏から、『尾瀬』に出てくる平野長靖氏と親しかったという貴重なお便りをいただきましたので、本人のご了解を得て、一部を紹介します。
文中に出てきた尾瀬の平野長靖は、大学時代の親友の一人でしたので、なつかしく読ませていただきました。卒業後、平野は北海道新聞を希望して入社、(ちなみに私は信濃毎日新聞へ)、新聞労連運動にも貢献しました。奥さん(今の長蔵小屋の主)は、当時の道新労組青年婦人部の仲間だった人です。
父親の死で小屋を継ぐため山に帰り、環境保護の闘いに献身するのですが、その徹底ぶり、冷静さは、平野らしいものだつたと思います。壮絶ともいえる死でしたが、本当に惜しんで余りある人物でした。
1998・8 朝日新聞事業開発室 編集制作センター 深沢俊介
あの尾瀬で ごみの不当投棄?
新聞報道に驚き
10年前の1992年8月、夫婦で4日間尾瀬に浸った。「尾瀬は春がいい。夏行っても素敵、秋がまたすばらしい。年中、行きたい」。
同室になった方が、そう言って、ベテランらしくいろいろ話をしてくださった。その大自然の、侵すことができない偉大さを感じた尾瀬、そこでのゴミ問題は、信じたくないけれど、やはり、最近の倫理なき世相の反映なのだろうか? 以前、HPを見てお便りをくださった朝日新聞社の深沢氏が、親友だったという平野長靖氏を「環境保護の闘いへの徹底ぶり、冷静さは平野らしく、壮絶な死は惜しんであまりあるものでした」と書かれたその手紙を読み直しました。その活動のスタートになった「峠には細い道があった」ではじまる『峠の泉が枯れる』という平野氏の投書。私たちみんなが、原点に戻って考えたい。
今年は国際山岳年、国際エコツーリズム年
「山岳はきわめて壊れやすい環境である。地球温暖化で北アルプスや上越の山地に降る雪が減り、夏まで残る雪渓が消えてしまえば、その水に依存してきた東京や名古屋などの大都市は存続できない〈北海道大学教授 小野有五氏〉」
2002年8月25日中日新聞
このHPを読んで「遥かな尾瀬」という文章とメールをいただきましたので、ご本人の了解を得て、以下に載せました。
湯浅寿之
私が初めて尾瀬に行ったのは中学2年(昭和32年)の時である。父の実家である沼田に一泊し、夜中のバスに乗り大清水から三平峠を越えて尾瀬沼に着いた。この時咲いていたニッコウキスゲの群落に感激したことを今でもはっきりと覚えている。
あれから、何度尾瀬に行っただろうか。その度に与えられる新鮮な感動は、1度として同じではなく、雨の時も風の時もまた雪でさえも、生きている喜びを肌と心に感じさせてくれる。今では尾瀬は私の第2の故郷になった。
尾瀬は四季それぞれにすばらしい衣装を身につけてくれる。リュウキンカの咲きだす早春。白いミズバショウ、ニッコウキスゲの黄の模様、晩秋を告げる草紅葉、燧ケ岳の山裾を取りまく朝霧の模様、初夏にポツリと咲く池糖のヒツジグサは、池糖そのものを光琳の描く模様にしてしまう。そして湿原に遠く立つ数本の白樺は白い腕を高く掲げ我々に呼びかけているようにさえ見える。
長靖(長蔵小屋3代目)が愛した三平峠。36年間喜びと悲しみを背負いながら登り下りを繰り返し生きてきた。その長靖が東京で行われる「尾瀬の自然保護設立準備会」に出かける途中、三平峠で遭難し休息という名の死を与えられてから、振向けば30年。今、尾瀬は日本人の心身の安らぎの場として遺され愛されている。それは、入山者ひとり一人の心がけと、あらゆる分野の「尾瀬を守る」運動の結果である。
私は、長靖の死後初めて彼の生き様を知った。彼の遺稿集である「尾瀬に死す」を読み、彼が「尾瀬の自然を守る会」(ボランティア組織)を設立し、大清水から尾瀬沼を経て沼山峠へ通じる道路の中止を訴えていたことを知った。「尾瀬の自然を守る仕事を環境庁の初仕事にしたい」と初代環境庁長官に言わしめたほどである。しかし、環境庁はその外郭団体である「尾瀬保護財団」を1995年に設立し、ビジターセンターを尾瀬沼畔と山の鼻に建ててしまった。我々「守る会」では御池や大清水等の登山口に建てるよう要請したが全く無視されてしまった。さらに最近では、沼山峠〜尾瀬沼、一之瀬〜岩清水そして鳩待峠〜山の鼻では登山道がどんどん木道や木の階段に整備?され、土の感触のする山道が少なくなってきている。「守る会」は1997年に解散に追い込まれたが、尾瀬を「財団」に任せたままでいいのだろうか。このままでは、尾瀬は都会の公園のようになってしまう。尾瀬を守るのは全国の尾瀬を愛する人たちのボランティアによってのみ可能なのだ。「守る。峠の緑の道を、鳥たちの住処を。皆の尾瀬を。人間にとって大切なものを。」これは長靖が最後に残した言葉である。
1992年、小学校6年の国語の教科書に長靖の「守る。みんなの尾瀬を」が載った。子供たちは教科書で長靖の生きかたを学んでいるという。尾瀬の自然を守る運動は、21世紀を担う子供たちに引き継がれていくものと確信している。(2001-9-1)
「二人連れだぞ、用心しろ」そう聞こえた。屋久島で、標高800メートルの白谷雲水峡を歩いていたら、杉の木の上で屋久ざるが叫んだ。
人っ子ひとりいない静かなこの山に「よそ者が来たぞー」という甲高い警告の渦巻きがひろがり、その声は、10匹、20匹いや30匹にも聞こえるボリュームで広がった。それは九州の高崎山や、愛知県犬山市のモンキーパークにいる、いかにも人なつっこい猿とは違う、大自然の中で生きる野生の、逞しい猿たちだった。
屋久島は、日本列島最南端 種子島の南西洋上に浮かぶ小島である。 1993年、世界遺産に登録されて俄然注目され始めた。海抜1500メートルを越える山岳地帯、なかでも1935メートルで九州一の宮之浦岳が、紺碧の海からいきなり天にそそり立つように見える。面積500キロメートルの小さな島だ。屋久島が洋上アルプスと呼ばれる所以だ。とりわけ樹齢7千年といわれる縄文杉に逢いたいと、心躍らせて屋久島空港に降り立った。
宿に比較的近い白谷雲水渓での、屋久ざるとの出会いで「生きてる島」を実感した。空港から乗ったタクシーの運転手は、お世辞にも愛想がいいとは言えなかったが、「名古屋から電話で案内所に聞いたら、縄文杉まで登るのは50代後半では無理と言われたけれど、やはりだめかしら」と諦めつつ言ってみた。暫しの沈黙の後、「気だけだわナー」ポツリとそう言ってくれた。その一言で、わが中年夫婦は往復10時間の登山に奮い立ったのだ。
その運転手に翌朝6時に宿に来て貰う約束で別れた。約束どおり翌早朝、タクシーで登山口に到着し、トロッコ道を2時間歩いた。
日頃、ノーカーで歩き慣れた足も、さすがに重くなり始めたころ、本物の登山口に辿り着いた。人ひとりがやっと通れる道で、しかも急坂、いきなりのアルプス並みの登山に緊張しながら、しかし嬉しかった。あたりが俄かに深山めいて来たから。9月初旬の日曜だったが、途中出会ったパーティは10組足らずだった。片道2時間半から3時間続く急な登りは、太古の世界に触れさせて貰う最低のお払いなのかも知れない。緑の味がする空気に満足しつつ、しかし高い湿度に喘ぎながら、シャワーを浴びたように汗をかいた。
ウィルソン株は樹齢約3千年の切り株で、根回りが30メートルを超す。翁、大王、夫婦などと名前をつけた屋久杉は、朽ち果てそうな深い山の奥深く、何千年も生き続けていた。さらに登り詰めると、一番深い山奥に風雪に耐えた、樹齢7200年とも言われる縄文杉が泰然としていた。樹の表面が岩のようで、40メートルを超える根回りだ。たかだか7、80年、喜び、悩んで生きる人の命に比べ、この大自然の営みに圧倒された。
屋久島には昔から「10日は山に、10日は里に、10日は海に」という言葉があったという。それは「サル2万、シカ2万、人2万」とも言いならされた。バランスのとれた自然と人との共生の感覚が素晴らしい。人類が謙虚さを忘れ、自然を征服しようとした結果、『沈黙の春』のような自然界の異常を進めたのではないかと思った。
1955年のキネマ旬報 ベストワンに選ばれた映画『浮雲』は、ここ屋久島が舞台だった。雨がじとじと降り続き、暗く救いのない恋は、当時若い恋に悩んでいた私にとって屋久島という地名と共に、切ない青春を想い出させる。
新幹線も航空便もない当時のこの島は、鹿児島から、さらに船に乗らなければ行かれない、孤島だった。
いま私が立っている屋久島は、海沿いに亜熱帯植物のガジュマルが群生し、亜寒帯までの気象が垂直に分布する自然の宝庫で、鹿も猿も昆虫も飛び跳ねている、活気溢れる「生きてる島」だ。この島が気に入って居着いてしまった人も多いと、タクシーの運転手が話してくれた。
「気だけだわナー」のひとことで、太古の息遣いを肌で感じ取れた達成感が、深い喜びとなって、余計、素朴なこの島への愛しい気持が増幅していった。
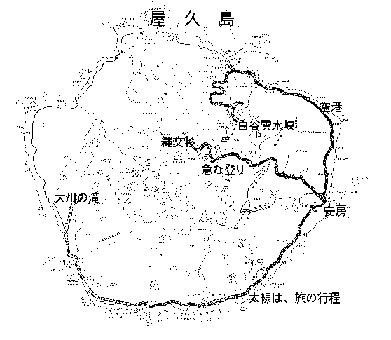
NEXT
1、幸子のホームページに戻る
2、次の『名古屋の話』へ行く