|
家庭からのインターネット接続を簡単にして、インターネットに関連したビジネスを広げようと、いろいろな企業がアイディアを出しています。こうした試みの中には、例えばWebサーバーの住所であるURLを電話番号のような番号で置き換えるサービスとか、インターネットに直接接続できるテレビや電話器や冷蔵庫といった家電製品があります。このような、インターネット関連のサービスや製品は、この先つぎつぎに私たちの手の届くところに現れてくるでしょう。ただ、家電製品の場合は、ちょっとお試しするには高すぎたりもしますが。 このホームページでは、表紙の下の方にインターネット番号というのを表示しています。これは、http://www2s.biglobe.ne.jp/~shell/といったURLを入力する代りに、電話番号のように8600425223といった番号でホームページにアクセスするものです。もちろん、目的のサーバーのインターネット番号は、下の窓で104を入力して検索するか、あるいは、広告の中に印刷している番号をメモして入力することになります。また、Windowsユーザーであれば、専用のソフトを使うことで、ブラウザ(IEかNetscape)のURLの入力欄に番号を入力しても接続することが可能になります。番号とURLを比べて、どっちが覚えやすいかは議論が有りますが、これを運営しているD&I Systemsによれば、例えば口頭でURLを伝えることを考えれば、「ダブリュウ・ダブリュウ..」などと教えるよりも、番号の方が正確に伝わるとか、いろいろとメリットがあると説明しています。確かに、電話を使ってURLを相手に伝えても面倒くさいだけですが、数字であれば簡単でありますね。この番号は、インターネット系雑誌の「あちゃら」に載っている、あちゃらコードと同一のものです。もちろん、これは普及しないと意味がないものですし、ホームページはURLの手入力かリンクで十分という従来の考えも根強いとは思います。ただ、もし、高齢者も含めてインターネットのWebサービスを広げるのなら、電話と同様にアクセスできる方法は、意外と効果的ではないかと思うのです。
電話でインターネットと言う意味では、PHSでWebが見られるというものもでていますね。例えば、インターネットパルディオというのは、見かけはPDAですが、機能はインターネットにも接続できるPHSといったものです。手に取ってみると、意外と軽くてポケットに入れて持ち歩けるものです。でも、既にザウルスなどのPDAを使っている人にとっては中途半端かも知れません。電話をするときには、マイク付きのイヤホンをするすると引きだして耳に付けます。個人的には、イヤホンを付けて電話というのはうっとうしいですが、電話しながらPDA操作をすることを考えているようです。このPDAでインターネットに接続する場合には、NTTパーソナルが提供している、完全従量制の接続サービスのパルディオネットサーフィンを使うようになっています。これは、場所によらず一分15円でインターネット接続するサービスで、NTTパーソナルの契約者なら手続き不要というものです。電子メールの方も、パルディオEメールという、PHS契約者専用の従量制電子メールサービスを使います。言ってみれば、このPDAを買った日から、(モノクロ画面だけど)ウェブも見られるし、電子メールも使えると言うことですから、まさに簡単にインターネットにアクセスできるツールであります。PHS業界も、いろいろなサービスでシェアを競っているのですね。
こうした、インターネット家電製品を見ていると、だんだん、家庭から簡単に接続できるインターネットというイメージがわいてきます。想像するに、こうした家電製品のインターネット接続は、インターネット電話やWebTVのセットトップの様なインターネット接続機能をもった家電製品をそれぞれ独立して回線に接続するような方法から始まるように思います。インターネット冷蔵庫の様なサーバーを中心に置くという形態は、その後ではないでしょうか。すくなくとも、コンセントからISDNに接続[W]するような家庭内の配線は、すでに可能になっていますから、そうしたコンセントに電源と電話線を接続する家電製品は、設置も簡単でしょう。では、その次の、家庭内ネットワークは冷蔵庫がサーバーになるのか、それともテレビがサーバーになるのか。それは、そのネットワークをどんな信号が流れるのかで変わってくるでしょう。でも、いまの所、わざわざテレビから冷蔵庫に流す信号の用途は不明でありますね。
このページに使用した写真は、98年10月20日から23日まで開かれたNTT主催のつくばフォーラム会場で、展示担当者の許可を得て赤兵衛が撮影したものです。転載は御遠慮ください。なお、[W]が付いているリンクは、別の窓に写真を表示しています。写真がでないときは、表示した窓が裏に隠れていないか確認してください。
|
| 1998.10.23 |
 電話と同様にアクセスすると言う意味で、面白いと思ったのが
電話と同様にアクセスすると言う意味で、面白いと思ったのが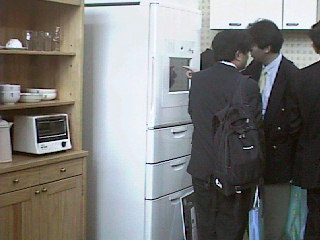 インターネット接続した家電製品として、何度もこのページで何度も出てくるのがインターネット冷蔵庫ですが、実は、赤兵衛はついに実物に触れることができました(^_^)。この冷蔵庫についは、
インターネット接続した家電製品として、何度もこのページで何度も出てくるのがインターネット冷蔵庫ですが、実は、赤兵衛はついに実物に触れることができました(^_^)。この冷蔵庫についは、