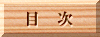御大会の砌
是の如く、我成仏してより已来(このかた)、甚だ大いに久遠なり。
寿命無量阿僧祇劫なり。常住にして滅せず。(法華経433ページ)
今夕は本年度における総本山恒例の宗祖日蓮大聖人御大会を奉修のところ、法華講総講頭・柳沢喜惣次氏、同大講頭・石毛寅松氏をはじめ、各支部講頭・役員各位、法華講連合会役員各位、一般信徒の皆様、さらにははるばる海外各国よりの信徒の方々が多数参詣され、盛大に仏恩報謝の大法要を厳修つかまつり、まことに有り難く存ずる次第であります。 さて本年は、ただいま拝読の寿量品の御文の、特に「久遠」の二字について少々申し上げます。
この御文は寿量品の全体のなかで、三世益物(やくもつ)のなかの現在益物の所に当たり、さらに、その「生(しょう)に非ずして生を現じ」「滅に非ずして滅を現ずる」化導のなかで、「非滅」すなわち釈尊の仏身の久遠常住を説かれる部分であります。
この久遠の「久」とは「ひさしい」と読み、時間が長いという意であります。また「遠」とは「とおい」ということで、近いことに対します。すなわち空間的な距離の長いことを示す語ですが、また久しいという字に通ずる上からは、時間のながい意味もあります。
寿量品に「久遠」と示されるのは、釈尊の寿命の長いことを説く故に、主として時間の長さを言い、傍ら空間の広大の意をも含むのであります。故に、この久遠ということからの時間と空間を考えた場合、これらは我々の思考や推測・推定の域を超えた無限、絶対的なものであります。
現在の科学的知識で到達する宇宙における地球とか、あるいは星座・星雲に関する認識は、一々の観測乃至、実験証明に基づいて、かなりの事実的認定がありますが、そこから先は結局、推論・推定に過ぎません。天文科学では、全宇宙の膨張が見られる状態より帰納して、一番初めの宇宙の存在を「ビッグバンからだ」と論じますが、そこに時間の初めを区切ることはできないと思います。同様に空間の問題についても「宇宙には、いったい限界が有るのか、無いのか」ということも、これだけあらゆる科学の発達と計量計器が充ちあふれていながら、いまだにそれを決定することができません。一つひとつの証明の積み重ねという限られた形からの確定や推定によるのが科学の在り方でありますから、それも当然のことと思います。
しかし、それならば無限大の時間、空間を素直に認め、それが法界の生命として存すること、そしてその永遠の上に仏が存在し給うことに真摯(しんし)、敬虔(けいけん)な態度を持つべきであります。
また、無限絶対の内容を説く各宗教においても、漠然と神の存在とその絶対性を信ずるところに、理と事、真理とそれを悟る個体、すなわち人法の二を欠く不備を免れず、正しい衆生救済の利益に当(とう)を失するものが多々であります。
しかるに仏教は、真理の内容として法界のすべては因縁因果の法則であるとし、また、その実理は空諦・仮諦・中諦の不可思議な生命の当体としての十界互具に存することを明らかにしております。さらに、これを含む法界一切の森羅万象は色法と心法の2つであり、動物・植物・山や川乃至、地球をはじめ無数の恒星・惑星等の天体に至るまで、地・水・火・風・空の五大による離合集散、生滅離和の姿であります。その五大がそのまま色心の二法の存在であることを喝破(かっぱ)しております。
仏教のなかの真実の法界を照らす教えである法華経においては、まず方便品に諸法すなわち法界全体の実相として、相・性・体等の十如是を説いております。この「相」とは色法、「性」とは心法であり、「体」とは色心ニ法の当体を示すのであり、あらゆる存在としての法界全体が色心の二法なのであります。故に、色心すなわち物質と精神の存在は、あらゆる時間による変化、万物の変遷を超えて無限であり、悠久であります。
その色心の二法は、この無限のなかに地獄乃至、仏界等の十界として開かれ、常住に存続するのであります。これについて法華経の迹門では、諸法実相に約して空間的にこれを悟った仏様がその意義を開説されましたが、その空間の無限における十界互具の相をさらに時間の上に常住であるとして悟られ、開顕されたのが釈尊の本門の教説であります。
現代の科学においては、地球の生成、生物や人類の誕生が有限的経過のなかに説明されており、それは科学の分野における人類の認識として、一往、肯定するにやぶさかではありません。しかし、それのみを一切の基準にすると、先程も述べたように、未定にして不確定な分野を大量に含む科学認識にのみ執われることになり、もし、それによって科学の範囲を超えた法界と生命の実相を否定するに至るならば、仏法で示す信の功徳をもって生命と実相に通達し、真の安心立命を得る礙(さまた)げとなるのであります。
法華経の本門寿量品には、その初めに極めて広大なる仏の寿命の久遠に関する譬えが説かれております。すなわち、この三千大千の世界を、人あって、すりつぶして小さな塵となして、東方五百千万億那由佗阿僧祇の国を過ぎてその一つの塵を下し、また東方五百千万億の世界を過ぎて次の一塵を下し、このようにして数限りない微塵をすべて尽すとき、通過した世界の数量はいったい、どれほどかを弥勒菩薩に質問されます。弥勒等は「その諸々の世界は無量無辺であり、一切の声聞、辟支仏(ひゃくしぶつ)はもちろん、阿惟越致地(あゆいおっちじ)という境界に住する私自身も算(かぞ)えることは不可能であり、その心力の及ぶところではありません」と答えます。これに対して釈尊は「この無量無辺の微塵を下した数の世界と下さざる世界をも含めて、それをことごとくまた微塵となし、その一微塵を一劫という長さと計量し、これによる無量無辺の長時よりも、我が昔において成仏して己来は、まだこれに超えて長いこと百千万億那由佗阿僧祇劫である」と説かれました。
この譬喩による仏界ならびにそれに伴う九界の久遠常住は、まさにあらゆる時間的変化によるこの世界の変遷をそのなかに内在しつつ、かつまた超越するものであります。僅々50億年ほどの地球の歴史として、そのなかの有限な存在知識にのみ頼るのがあらゆる近代科学の所産による学問分野ですが、寿量品に説示される仏身による法界は、これを超越した無限の広大性を持ち、したがって、この世界には信の一字をもってのみ帰入しうるのであります。
これについて、仏教では成(じょう)・住(じゅう)・壊(え)・空(くう)の四劫を説きます。諸々の世界が現れる根本要素としての「空」と、そのなかの地・水・火・風が様々の様相に変化しつつ生命の器を入れる世界を形作る長い時節を「成劫」と言い、それから生物・人類等が住して繁栄し滅亡する長い時期を「住劫」と言います。次には、火と風と水が作用して世界が壊れる長い時間を「壊劫」と言い、一切が爆発消滅した結果、混沌(こんとん)として空中に漂(ただよ)う長い時が「空劫」であります。これが春夏秋冬の如く、無限大の法界中に繰り返されるのが仏教の世界観たる実相であります。今の科学においても、やがて遠い未来に太陽系が滅亡する時が来ることを予測しておりますが、これは仏教で説く四劫のなかの一つの「壊劫」に過ぎないと思います。
寿量品の説法は、このように無量に繰り返される成・住・壊・空の四劫を超越する内容において、仏身の長久すなわち久遠を示されていることを、まず信解すべきであります。
しかし、このことは実に信じ難く、解し難いのであります。故に、これを開説するに当たって釈尊は法華経の会座(えざ)で、あれほどの大掛かりな準備を用意されました。その一は多宝如来の宝塔の涌現であり、その二は提婆品・勧持品・安楽行品の弘通順序の化導を経たのちの、地涌千界の大菩薩の出現であります。それによって一切大衆の大疑念を生ぜしめ、初めてこの一切衆生の認識と智慧を打ち破って、はるかに超越した久遠常住の仏身と、その法界国土を説き顕すことができたのであります。
故に、これについて釈尊は、まず寿量品の一番初めに、「汝等当信解。如来誠諦之語(汝等当なんだちまさに、如来の誠諦の語(ことば)を信解すべし)」(法華経428ページ)の語をもって、法界無辺の仏身による悟りと功徳を成就するためには「信解」の二 字、特に「信」の一字こそ大事・大切である所以(ゆえん)を述べられました。
また大聖人様も、この釈尊の本有(ほんぬ)常住の本門本尊に関する説法と、これを聴聞した在世の衆生の観心すなわち、一念三千について、『観心本尊抄』に、「今(いま)本時の娑婆世界は三災を離れ四劫を出でたる常住の浄土なり。仏既(すで)に過去にも滅せず未来にも生ぜず、所化以て同体なり。此即ち己心の三千具足、三種の世間なり」(御書654ページ)と仰せであります。
この文の「今本時の娑婆世界」の「本時」とは、単なる我々の住む穢土(えど)の娑婆世界のみではなく、これを内に含みつつ、しかも超越する広大無限の時間における娑婆世界であり、故に「住劫」が終わって「壊劫」に入り、世界が破れる時の火・風・水の三災を離れ、さらに成・住・壊・空の四劫における世界の大変化を超越した、常住不変の仏国土であると仰せであります。
次の「仏既に過去にも滅せず未来にも生ぜず」とは、寿量品に説かれるところの、滅に非ずして滅を現じ、生に非ずして生を現ずる「非生現生・非滅現滅」の仏身を要約される文です。次の「所化以て同体なり」以下は、霊山・虚空一会(いちえ)の大衆がことごとく本有常住の釈尊の仏身と不離一体を成じ、無始の仏界に九界を具すとともに無始の九界の開覚に仏界が融じて、真の十界互具百界千如一念三千の境界において、すべての所化が無明(むみょう)を断破して、初住乃至、等覚の悟りに至ったことを言います。これは文上の体外(たいげ)の意によるもので、次の分別功徳品の前半における得益(とくやく)の相がこれを示しております。
しかし、右文の能所同体の一念三千を文上体内、すなわち文底の意義から拝すれば、在世において寿量品を聞いた衆生は、その身が釈尊と等しく久遠の常住であることを信解して、一往、初住乃至等覚に登って文上の悟りを得ましたが、それのみならず再往は、時間・空間に遍満する我が身即法界の証悟を得て、初住乃至等覚の菩薩も一転して名字凡夫の上の妙覚の極果を得たのであります。いわゆる「等覚一転名字妙覚」という本宗独特の相伝法門であります。
これは久遠本果の釈尊の顕本の奥に久遠元初本因名字凡夫即極の本仏の成道があり、その法界全体の時間・空間と一如する、いわゆる地・水・火・風・空の五大即我が身と示される境智冥合の仏身による故であります。この五大のうち、地・水・火・風は有限の存在ですが、これを含みかつ生ずる空大は時間・空間共に無限であり、そのなかに常にあらゆる有限的存在を生じております。
在世高位の菩薩は文上釈尊の三十二相の化導のなか、その長寿を拝して、さらに再往、名字凡夫即極にして法界全体の仏たる久遠元初自受用身と一体となり、凡夫の位に立ち返って名字妙覚の位に至り、即身成仏の大利益を得ました。大聖人様が『観心本尊抄』に、「一往之(これ)を見る時は久種を以て下種と為し、大通・前四味・迹門を熟と為して、本門に至って等妙に登らしむ」(同656ページ)と仰せられ、また『法華取要抄』に、「法華経の本門の略開近顕遠に来至して、華厳よりの大菩薩・二乗・大梵天(乃至)竜王等位(くらい)妙覚に隣り又(また)妙覚の位に入るなり」(同734ページ)と御教示の如く、法華経本門の利益の相を示す分別功徳品には全く説かれていない妙覚の利益、衆生の即身成仏を大聖人様のみが示し給うのはこの意であります。
さて、釈尊の化導は三十二相の本果の仏身によるものですから、その常住を説く場合、時間に約して、その無限大の譬えをもって過去の成仏を示されたのです。これに対し、大聖人様が久遠の成仏を説かれるのは本因名字凡夫の位における成仏ですから、釈尊のように過去の成仏を説くことは全く意味がありません。つまり三十二相八十種好に荘厳する権威づけの上にその寿命の久遠を説く釈尊に対し、時間・空間を超絶した無限大の法界の当体、いわゆる地・水・火・風・空即色心の二法たる妙法蓮華経における、智妙法蓮華経と境妙法蓮華経の境智冥合の真仏身が、寿量品の文底久遠元初の仏身であります。
このところより大聖人様の一期(いちご)の御化導の道理・文証・現証を拝すれば、その歴然たる御化導の順序が明らかであるとともに、その本懐の法門が特に弘安以降に要示されております。特に『御義口伝』における寿量品に関する御指南は、釈尊の文上の発迹顕本に対し、文底の寿量の仏身を法界即座開悟の自受用身と無作三身の上から御指南であります。すなわち『御義口伝』「自我偈始の事」に、「自とは始めなり、速成就仏身の身とは終はりなり、始終自身なり。中の文字は受用なり。仍(よ)って自我偈は自受用身なり。法界を自身と開き、法界自受用身なれば自我偈に非ずと云ふ事無し。自受用身(ほしいままにうけもちいるみ)とは一念三千なり」(同1772ページ)と説かれ、釈尊の如くインド出現の始成正覚において発迹顕本し、久遠の長時に約して成仏を示されるのではなく、直ちに法界を自身と開く自受用本仏を明かされるのです。
ここに久遠についてもインド出現の垂迹の仏身からの釈尊の開顕と、本門の本身の上からの自身を法界と開くなかに無限の時間・空間を含ませられる大聖人様の開顕との違いが明らかに拝されるのであります。ここに大聖人様の下種本門の久遠の本質がましますのであります。
故に『御本尊七箇之相承』に、「法界の五大は一身の五大なり、一箇の五大は法界の五大なり。法界即日蓮、日蓮即法界なり。当位即妙不改、無作本仏の即身成仏の当体蓮華、因果同時の妙法蓮華経云々」(聖典379ページ)との御指南が、まさにこの極地を示し給うものであります。
さらに久遠について『御義口伝』を拝しますと、「久遠とははたらかさず、つくろわず、もとの侭と云う義なり。無作の三身なれば初めて成ぜず、是動(はたら)かさゞるなり。三十二相八十種好を具足せず、是繕(つくろ)はざるなり。本有常成なれば本の侭なり。是を久遠と云うなり。久遠とは南無妙法蓮華経なり。実(まことに)成(ひらけたり)、無作と開けたるなり」(御書1772ページ)と説かれますが、この文は久遠について、無作の法理と仏身をもって解明されております。
そこで、これについて少々申し述べますと、無作とは円満無欠な法理を示すもので、改めて付け加えることも削ることもない故に、要するに造作する必要がないことを言います。
ただし、この円満無欠な理が法界に遍満し、我々の生命もまた、それであると仏は悟られておりますが、我々衆生は見惑・思惑、塵沙惑、無明惑が充満するために、本来の完全無欠なものをすべて歪(ゆが)んで見るのであります。そこに様々な苦悩と不幸を生じております。故に、仏は方便の形を造り上げて衆生を導かれるのであります。つまり円満の法理からその一部を分けて、あるいは道徳の道を、あるいは天上に至る道を、あるいは空を説いて声聞・縁覚に至る道を、あるいは仮諦・中諦を説いて菩薩の無量の修行を起こさしめるなど、その導きはすべて衆生の種々の迷いに当てはめて、わざわざ造作したもの、作ったものなのです。これを無作に対する有作(うさ)と言い、蔵・通・別・円の4つの教理のなかで、蔵・通・別の方便の3つがこれに当たります。これは当然、真実円満の理より分け離して作り上げたものですから、一分の道理はあるが、また欠陥があります。
この方便を打ち破って円満無欠な円の法理を顕したのが、四十余年の経々のなかで、ただ法華経なのであります。ここに至って煩悩即菩提・生死即涅槃の大光明が、我らの生命・生活に燦然(さんぜん)と現れるのであります。先程の御文で「久遠とははたらかさず、つくろはず、もとの侭」と示されるのは、それが久遠以来の常住不変の法理であり、本仏はその上に立って永劫に衆生を導かれるとの意であります。
次に「無作」の語について、単なる円の法理のみではなく仏身について、いわゆる「無作三身」と示される教示が、この『御義口伝』全体に行きわたっておりますが、特にこの御文で無作三身とは、初めて仏に成ったのではなく、したがって通途(つうず)の仏の相好たる三十二相八十種好を具足しないところの、しかも法身・報身・応身の三身と得を具える仏であり、本来あるがままの常住の仏を顕すところに、真実の久遠の義があるとの御教示であります。
つまり釈尊は法理の上からは蔵・通・別の方便に対して円経を説き、それは華厳・阿含・方等・般若等、四十余年の方便経ののち真実純円の法華経を説かれましたが、まだ仏身においては方便が残っておりました。すなわち真実本懐究竟の寿量品においても、なおかつ三十二相の方便をつけた仏身であったことがそれであります。
大聖人様は「久遠とは南無妙法蓮華経なり」と仰せられ、その一念に即久遠を開く故に、そのままが本有常住であります。この久遠の悟りを文底本覚の上に説かれたのが、『総勘文抄』の、「釈迦如来五百塵点劫の当初(そのかみ)、凡夫にて御坐(おわ)せし時、我が身は地水火風空なりと知ろしめして即座に悟りを開きたまひき」(同1419ページ)の御文であります。いわゆる久遠元初凡夫即極の成道であり、実に仏法の本源を示されております。
この久遠元初は「元初」というところに初めがあるようですが、実は元初に即して無始無終の法体なのです。いわゆる法界の色心の常住のところにそのまま本有の十界が存する故に、その当体たる南無妙法蓮華経と開くところの一念は無始無終の過去と未来にわたります。
すなわち『御義口伝』の寿量品、「我実成仏已来」の文についての御指南に、「法界無作の三身の仏なりと開きたり。仏とは是を覚知するを云ふなり、已(い)とは過去なり、来(らい)とは未来なり。已来の言(ことば)の中に現在は有るなり。我実(じつ)と成(ひら)けたる仏にして已も来も無量なり、無辺なり」(同1766ページ)と説かれる如くであります。
さて、この久遠元初の法は大聖人様のみの御教示であり、釈尊の寿量品は、この外郭(がいかく)のみを「我本行菩薩道」と説かれたのですが、しかし、大聖人様がこの久遠元初の仏を示される『総勘文抄』では、それが釈尊の名称となっております。したがって、大聖人様は一往、久遠元初の仏を釈尊と主(ぬし)づけられておるのであります。
この理由としては、けだし釈尊の名称は一代五十余年の垂迹の教えから久遠の開顕、そしてその久遠元初に至ったのであり、これは浅きより深きに至る相対妙であり、この意義において示されたと拝されます。しかるに、この久遠元初の本仏の当体を示されたのは釈尊ではなく末法出現の大聖人様なのであります。故に、大聖人様の妙法蓮華経の御当体にその境智冥合の仏身がましますのです。しかれば、久遠元初の本仏釈尊は末法の日蓮大聖人であり、いわゆる久遠即末法であります。また末法出現の日蓮大聖人は、法界即日蓮、日蓮即法界の絶対妙の境地であり、これすなわち末法即久遠であります。故に末法即久遠の上から、久遠元初の自受用身にさかのぼれば、その御名もまた日蓮大聖人と拝されるのであります。
以上、本日は寿量品の「久遠」の語について、その具わるところの深義を種々に述べてまいりましたが、末法と久遠の両面より本仏日蓮大聖人の三世常恒の御化導を仰いで信じ奉るべきであります。そのところにこそ、我々凡夫の貪・瞋・癡三毒充満の当体が本有無作三身と開く所以があります。
於夏期講習会第9・10期
今日は、第八問答から最後までの御文を拝講してまいります。なかでも後半部分は、各末寺の御会式の際に必ず儀式として奉読する部分に当たりますので、難しい内容でもありますが、皆様方もかなり聞き慣れているところもあるかと思います。さて、この第八問答は、謗法禁断の方法を説くのであり、斬罪の用否ということがあるのです。つまり、第七問答のところで、大聖人様が過去の2つの事例を挙げておられます。それは涅槃経の中における謗法の者に対する処置ないし誡める方法として、一つは首を斬るということ、つまり悪い者を殺してしまうということであります。びっくりしたような顔をしている方がいますけれども、この例は涅槃経に説かれてあり、『安国論』の第七問答でも引かれてあります。ただし、刀剣や弓箭(きゅうせん)、鉾槊(むさく)というような色々な武器をもって正法を守ることが大切であるということが説かれておるけれども、最後には「刀杖を持つと雖も、命を断ずべからず」(御書246ページ)という言葉があって、やたらに人を殺してよいということではないということが付け加えられております。
さらには、もう一つの方法として、謗法の布施を止めるということも述べられてあります。これらのことに対する用否がきちんと示されるのが、今日の第八問答からであります。それでは拝読してまいります。
<第八問答:斬罪の用否>
客の曰く、若し謗法の輩を断じ、若し仏禁の違を絶たんには、彼の経文の如く斬罪に行なふべきか。若し然らば殺害相加へ罪業何が為んや。 則ち大集経に云はく「頭を剃り袈裟を著せば持戒及び毀戒をも、天人彼を供養すべし。則ち為れ我を供養するなり。是我が子なり。若し彼を
打(かだ)すること有れば則ち為れ我が子を打つなり。若し彼を罵辱せば則ち為れ我を毀辱するなり」と。料(はか)り知んぬ、善悪を論ぜず是非を択ぶこと無く、僧侶為らんに於ては供養を展ぶべし。何ぞ其の子を打辱して忝くも其の父を悲哀せしめん。彼の竹杖の目連尊者を害せしや永く無間の底に沈み、提婆達多の蓮華比丘尼を殺せしや久しく阿鼻の焔に咽ぶ。先証斯れ明らかなり、後昆最も恐れあり。謗法を誡むるに似て既に禁言を破る。此の事信じ難し、如何が意得んや。
・客の曰く、若し謗法の輩を断じ、若し仏禁の違を絶たんには、彼の経文の如く斬罪に行なふべきか。
この段の客の質問は「あなたの言われるように、謗法の輩の罪を断ち、仏の誡めに違う教えをなくすためには、経文に説くように謗法者を斬ってその命を奪うべきか」という質問です。この「彼の経文」というのは、先出の文、すなわち涅槃経において仙予国王が大乗の仏教を誹謗する婆羅門の命を直ちに絶ったということであります。そういうことをもし例とするならば、謗法者を殺してしまうべきであるのかと言うのです。
・若し然らば殺害相加へ罪業何が為んや。
法然は謗法の者と前から論じられておりますから、その法然等の類(たぐい)を斬罪に行うとしたならば、殺すということが相加えられて、その罪は実に大きなものになるではないかと、客が詰問するのであります。
それについて客は言葉を続け、さらに経文を挙げて反論します。
・則ち大集経に云はく、
この文は、大集経の『法滅尽品』の中に述べてある釈尊の言葉であります。
・「頭を剃り袈裟を著せば持戒及び毀戒をも、天人彼を供養すべし。則ち為れ我を供養するなり。是我が子なり。
これは、どのような僧侶であっても、頭を剃って袈裟を着けておる者は我が子供であると、仏様が自らおっしゃっておる文です。
その文に「持戒及び毀戒」とある中の「持戒」というのは、僧侶として仏様の教えを守って正しい行いをしておる僧侶のことです。それから、「毀戒」というのは、仏様の教えが守りきれずに色々な仏の誡めに背く行為をする、戒を破るような僧であります。そのように、悪いことをする僧侶もいるけれども、共にこれは仏の子であると、仏様自らがおっしゃっておるわけです。ですから天人、すなわち天も人も共に、仏子としての僧侶へは、持戒に対しても毀戒に対しても供養すべきであるというのです。これは「我が子」、つまり仏の子であるからであります。
・若し彼を
打(かだ)すること有れば則ち為れ我が子を打つなり。
もしも、何らかのことを取り上げて、その僧侶を「
打する」、つまり殴ったり打ったりするようなことがあれば、それはすなわち私の子供を打つことになる。
・若し彼を罵辱せば則ち為れ我を毀辱するなり」と。
さらに、その僧侶を罵り辱めることは、すなわち私を謗(そし)ることになると、仏が仰せになっておるのです。
・料(はか)り知んぬ、善悪を論ぜず是非を択ぶこと無く、僧侶為らんに於ては供養を展ぶべし。
客はその経文を挙げ、したがって善いとか悪いとか、そういうことをあえて言わずに、僧侶である以上、基本的には供養をなすべきである。
・何ぞ其の子を打辱して忝くも其の父を悲哀せしめん。
どうしてその子供を打ち辱めて、その父を悲しませることがあろうかと言うのです。つまり謗法の者だからと言って僧を殺すなどということは、とんでもないことだという意見であります。
次に客は、仏子を殺すにおいては、地獄に堕ちるという現証がある事例を次に挙げるのです。
・彼の竹杖の目連尊者を害せしや永く無間の底に沈み、
この「竹杖」というのは、常に杖を持っていて、自分の気にくわない者がいると殴りかかるというような、非常に横暴・乱暴な外道の集団であります。そのような竹杖外道というのが釈尊在世におりました。
この者たちは、仏様とその教えを信ずる弟子たちを非常に憎んでいたわけです。そこであるとき、舎利弗と目連という2人の釈尊の弟子が、王舎城へ向かって歩いているときに、その竹杖外道に捕まってしまったのです。そして、竹杖外道が「お前の師匠の瞿曇(釈尊)が正しい教えを説いておるというが、我々はお前たちのその教えを聞きたい」と言い、さらに「もしその答えで我々の気にいらぬことがあったら、お前たちをここで打ち殺す」と宣言したのであります。
外道は、まず舎利弗に「お前たちの言う道とは何か」と聞きました。舎利弗は非常に智慧のある人ですので、非常に難しい哲理の深い文をもって答えたのです。すると竹杖外道は、何を言っているか判らないために、「これは自分たちを誉めてくれたんだ」と思って、「お前は差し支えない」と言って通したのです。
次に目連に「お前はどう考えるか」と聞いたところ、目連は「私は神通力をもって過去に地獄へ行ったことがある。すると、そこにお前たちの死んだ師匠が地獄に堕ちており、妄語の罪としてその師匠の舌が無量の広さになっていて、その上で鋤(すき)や鍬(くわ)を持った者が無惨にも縦横にその舌を裂いていた。そのような苦しみを受けておるのである。したがってお前たちの教えは、まことに間違った教えである」と答えたのです。それを聞いた竹杖外道が大変怒って、杖をもって目連をさんざんに殴りました。
さて、先に行った舎利弗が、どうも目連の来るのが遅いということで引き返してみたら、目連は殴り打たれて、ほとんど死ぬ直前の状態になっていたのです。それを見た舎利弗は、「神通第一と言われたお前が、なぜ得意の神通を使ってその災難から逃げなかったのか」と質問したところ、虫の息の中から目連は答えて「これは私の過去の宿業である」と申しました。ですから、どんなに善い功徳があっても、過去の宿業というものは避けられない場合があるわけです。そして目連は、いよいよ死ぬときに「私は竹杖から打たれたときに、神通の“神”という字も思い出すことができなかったのだ」と言って絶命したということです。
しかし、その罪の報いによって竹杖外道は無間地獄に永く沈んだということをここに挙げております。
・提婆達多の蓮華比丘尼を殺せしや久しく阿鼻の焔に咽ぶ。
この「提婆達多」という人は、五逆罪のうちの三逆罪を行った大悪人であります。三逆罪とは、一つは仏身より血を出だすこと。これは釈尊が歩いてくる道の脇の、高い山の上から大きな岩を投げ落として釈尊を殺そうとしたのです。その岩が足の指に当たって血が出たということです。このとき釈尊は殺されなかったけれども、これは出仏身血(すいぶつしんけつ)、すなわち仏身より血を出だすという罪で、五逆罪の一つになっておるのです。つまり殺仏という規定はないのです。父を殺す、母を殺す、阿羅漢を殺すということはあるが、仏は殺すことが、できないからです。
これは大聖人様も同様であります。文永元(1264)年11月11日、房州の小松原において、東条左衛門の指揮による何百人かの武器を持った者に囲まれて殺されそうな状況にはなったけれども、結局、その者たちは大聖人様を殺すことはできなかったのです。そのときに、やはり大聖人様も眉間に4寸の傷を負われ、血が出たということがありました。これも仏の身から血を出だすということで、五逆罪の一つであります。
次に、和合僧を破すということです。これは長くなりますので省略しますが、やはり提婆達多が釈尊の弟子を誘惑して自分の弟子にしようとしたということがありました。
さらに3つ目が阿羅漢を殺すということで、これが今ここに示されておる「提婆達多の蓮華比丘尼を殺せしや」という事例です。蓮華比丘尼という方は、尼さんではあるけれども、釈尊の弟子として深く仏教の修行をした方であり、阿羅漢の悟りを得ていました。かつて提婆達多は、阿闍世王に「私は釈尊を殺して、代わりに仏に成る。だからあなたは父の頻婆舎羅王を殺して国王になりなさい。そしてあなたは国王として、私は仏と成って世を改めていきましょう」というようなことを言って誑かし、その言葉に阿闍世王が乗って、自分の父である頻婆舎羅王を幽閉し、最後に殺してしまったのであります。
その悪業によって阿闍世王は身体に大変な悪瘡を生じ、苦しみに苦しむような状態が起こりました。そのときに耆婆等の賢明な大臣に教えられて釈尊を訪ねて懺悔をし、その大きな慈悲の功徳をもって悪瘡を治すことができたのであります。そこで阿闍世王は、提婆達多が非常に恐ろしい男で、自分をこのように騙して悪業を行わせた大悪人であることをすでに自覚しておりました。そこへ提婆達多が従前どおり供養を受けるために城へ来たわけであります。
当然、阿闍世王は、提婆達多を城の中に入れることを拒絶したのです。そこで提婆達多が憤慨しているところへ、城の中から蓮華比丘尼という方が出てまいりまして、提婆達多を見て「お前は釈子でありながら、このような悪業を働き、仏に背いて実に不届きな者である」と、強く叱りました。提婆達多は大変怒って、拳(こぶし)をもって蓮華比丘尼を殴り、ついに打ち殺してしまったのです。
ところが城の門の外に大きな穴が空いて、提婆達多は直ちにその穴から地獄の底へ堕ちてしまったのであります。それが「蓮華比丘尼を殺せしや久しく阿鼻の焔に咽ぶ」ということです。玄奘(げんじょう)三蔵が17年間にわたってインドの国々を回ったときには、提婆達多が地獄へ堕ちた穴がまだ存在していたということが、玄装三蔵の『西域記』という本に書いてあります。
・先証斯れ明らかなり、後昆最も恐れあり。
この文が客のこの段における結語です。前にも述べておるごとくに、僧侶を殺すということをすれば、その罪業として阿鼻地獄に堕ちるということが明らかである。ですから「後昆」、すなわち後の子孫、後の人々のためにも、僧侶を殺すということは実に恐るべきことであるというのです。
・謗法を誡むるに似て既に禁言を破る。此の事信じ難し、如何が意得んや。
したがって、このようなことは仏子を哀れみ、仏子に対して供養をしなければならないという仏様の金言を破ることになるではないか。邪教を説くと言っても、その僧を殺すのが正しいということは、まことに信じ難いことであるという反論であります。
主人の曰く、客明らかに経文を見て猶斯の言を成す。心の及ばざるか、理の通ぜざるか。全く仏子を禁むるに非ず、唯偏に謗法を悪(にく)むなり。夫釈迦の以前の仏教は其の罪を斬ると雖も、能仁の以後の経説は則ち其の施を止む。然れば則ち四海万邦一切の四衆、其の悪に施さずして皆此の善に帰せば、何なる難か並び起こり何なる災か競ひ来たらん。 ・主人の曰く、
次は、客に対する主人の答えです。
・客明らかに経文を見て猶斯の言を成す。心の及ばざるか、理の通ぜざるか。
あなたは、私が挙げておる経文を明らかにご覧になっておるにもかかわらず、なおこのようなことを言うとは、結局、あなたの心が経文の真意に及ばないのであろうか、それとも経文に示す道理があなたに通じないのであろうかとまず指摘され、次に客の思い違いを矯(ただ)されるのです。
・全く仏子を禁むるに非ず、
すなわち、従来述べてきたことは「仏子を禁むる」のではないということです。つまり客が大集経の文を引いて、持戒や毀戒でも僧侶は共に仏子であるということを論じました。したがって、そういう一般の僧侶については当然、仏子として考えるべきであるから、これを禁めるべきではない。すなわち「仏子を禁むるに非ず」と言われるのです。
・唯偏に謗法を悪(にく)むなり。
この「謗法」ということは、前の第七問答に「一闡提」ということが出ましたが、この一闡提とは、仏法の根本精神を破る者のことであります。この謗法の行為のみを悪むのであると示されます。 ですから、酒を飲んではいけないという戒に対して酒を飲んでしまったとか、あるいはちょっとした嘘を言ったりする。都合が悪いと嘘を言うのが、今の人間の常だけれども、とにかくそういうことは全部戒を破ることになるのです。これらを犯した者は謗法であるとして、その者を殺すべきだというようなことでは絶対にないという意味であります。
ところが謗法の僧侶の場合は、仏法の根本精神を破っているのです。仏教と仏様の敵になっておるわけです。したがって涅槃経に禁ずるところであり、この禁めは謗法の悪比丘に対するものであって、通常の僧侶の持戒・毀戒に対することではないということが「全く仏子を禁むるに非ず、唯偏に謗法を悪むなり」の文で、謗法の者こそきちんとけじめをつけるべきであるということをまず仰せであります。
それならば、その謗法の者に対して、いわゆる法然のような悪言を述べて仏法を破壊する者に対しては、どのようにすべきであるかということが、この次に述べられるところです。
・夫釈迦の以前の仏教は其の罪を斬ると雖も、能仁の以後の経説は則ち其の施を止む。
この「釈迦の以前の仏教」というのは、前に涅槃経等に述べられた過去の事例、これも釈尊の行為として説かれたのでありますが、例えば仙予国王が大乗を謗るところの婆羅門を直ちに殺してしまったこと。あるいは有徳王が覚徳比丘を守るため、武器をもって戦ったことなどがあるけれども、そのような意味で釈尊の出世される以前の仏教の形においては、その謗法者の罪を斬るということがあったという事例を言われるのです。
・能仁の以後の経説は則ち其の施を止む。
この「能仁」とは釈尊を指すのであり、慈(いつく)しみすなわち慈悲の上から一切を大きく包んで衆生を導くという意味でありますが、その能仁である仏様の化導からいって、釈尊以後の経説においてはすなわちその施を止めるのであると示されるのです。
この「施を止む」とは、つまり念仏等の悪義を述べる謗法の者に対しても殺すのではなく、その者に対しての布施を止むべきであるということを、釈尊がはっきり示されておるわけです。したがって「施を止む」ということこそ、謗法退治のための要術であり、大切なことであると、ここに言われておるのです。
・然れば則ち四海万邦一切の四衆、其の悪に施さずして皆此の善に帰せば、
そのようにきちんと仏法の善悪のけじめをつけ、そしてその悪に施さず、正法の善に対してのみ供養をするということが、世の中のあらゆる国や民衆に徹底して実現するならば、あらゆる正義がそこに確立するわけであります。
・何なる難か並び起こり何なる災か競ひ来たらん。
したがって、このように邪義が根本から止められるならば、その上にどのような難が来たるであろうか、災いが起こるであろうか、全く起こることはないという意味です。すなわち世界万邦に通ずる正法治国・邪法乱国の指導原理による捨悪持善の行為こそ、まさに災いを止めるところの秘術であることを、ここに述べられているのであります。
<第九問答:疑いを断じて信を生ず>ここからが第九問答になります。ここに至って客が始めからの主人の言を理解できたのです。この第九問答の趣意は、破邪顕正によって安国が現ずることを示されるのであります。そこで客が、いわゆる疑いを断じて信を生ずるという意義が篭められております。
客則ち席を避け襟を刷(つくろ)ひて曰く、仏教斯れ区にして旨趣窮め難く、不審多端にして理非明らかならず。但し法然上人の選択現在なり。諸仏・諸経・諸菩薩・諸天等を以て捨閉閣抛と載す。其の文顕然なり。茲に因って聖人国を去り善神所を捨て、天下飢渇し、世上疫病すと。今主人広く経文を引いて明らかに理非を示す。故に妄執既に飜り、耳目数朗らかなり。所詮国土泰平天下安穏は、一人より万民に至るまで好む所なり楽ふ所なり。早く一闡提の施を止め、永く衆僧尼の供を致し、仏海の白浪を収め、法山の緑林を截らば、世は義農の世と成り国は唐虞の国と為らん。然して後法水の浅深を斟酌し、仏家の棟梁を崇重せん。 ・客則ち席を避け襟を刷(つくろ)ひて曰く、
この「客則ち席を避け」ということは、きちんと座り直すということで、主人の言うことをよく理解し、その人格はまことに尊敬すべき方であると感じたために、改めて座り直したことを表します。そして、自らも身繕いを改めて、さらに主人に対して答えます。
・仏教斯れ区にして旨趣窮め難く、
初めに客は「私は、まだ本当に仏教というものが判っておりません」ということを述べるのです。この「仏教斯区にして」とは、ありとあらゆる意味で仏教の経文や文献、さらに大小乗の宗旨がたくさんあるという意味です。したがって「旨趣窮め難く」とは、すなわちそれぞれの論ずる旨とするところ、趣くところを見極めることが難しいということです。
たしかに仏教は難しいのです。小乗仏教一つを取っても、小乗仏教の経論をそのまま読んで直ちに理解できる人は、現代においておそらくいないでしょう。大乗仏教がまた実に広く、そしてなお深い意味がありますから、より一層難しいのです。ところが仏教の法理をきちんと教えられた正しい筋道の上から読めば、大体判るのです。いきなり読んだのでは、何が何だか全く判らないはずです。
・不審多端にして理非明らかならず。
訝(いぶか)しく不審不明なところが多く仏教の理が深遠であるため、その道理と非理について明らかに知ることができませんと客が述懐します。
・但し法然上人の選択現在なり。
そこで客は続いて、しかし法然の『選択集』というものが現に存在することは、そのとおりであると肯定します。法然は、世間で非常に尊ばれておりますから、この客もここではまだ「法然聖人」と尊敬の言葉を示しておるわけです。
・諸仏・諸経・諸菩薩・諸天等を以て捨閉閣抛と載す。其の文顕然なり。
その『選択集』において、あらゆる「諸仏・諸経」すなわち浄土の三部経というわずかな念仏の経典以外の全部、それらのあらゆる経典に説き示されているところの、釈尊を含めた様々な尊い仏や菩薩とその修行・功徳等の一切、それから「諸天」とは、この仏法を護る天人等ですが、これらについて悉くを「捨閉閣抛せよ」と言っていることは、まことに明らかであると申します。
「捨閉閣抛」とは、すなわち捨てよ、閉じよ、閣け、抛てということで、『選択集』の文章の中のあちらこちらに、この捨閉閣抛の四字が出てくるのです。つまりあらゆる経文や仏菩薩、諸天に対し、「捨閉閣抛せよ」と言うことは、たしかにあなたの仰せのとおり、その文が明らかであると答えます。
・茲に因って聖人国を去り善神所を捨て、天下飢渇し、世上疫病すと。今主人広く経文を引いて明らかに理非を示す。
この『選択集』によって、聖人が国を去り、善神が所を捨てるが故に、天下には様々な災難が起こり、飢渇し、疫病があるということを、今あなたは広く経の文証を引いて、その上から明らかに道理と非理を示されておる。
・故に妄執既に飜り、耳目数朗らかなり。
したがって「私は今まで法然なる僧も偉いと思っていたし、念仏の教えもまた仏教の中では非常に尊いものであると思っていたけれども、それは私の間違った執着であり、私の耳も目も正しい道理を聞き、正しい道理を見ることにおいて、非常に明らかになってまいりました」と言うのであります。
・所詮国土泰平天下安穏は、一人より万民に至るまで好む所なり楽ふ所なり。早く一闡提の施を止め、永く衆僧尼の供を致し、
客はそこで、国土泰平・天下安穏は上一人より下万民までの皆が願うところであり、早く一闡提の施を止め、仏法護持のため未来に永く正しい僧や尼への供養を励みましょうと言います。「一闡提」というのは、前にも出てきたとおり、謗法の仏敵として仏教の精神を破る者です。その一闡提に対しても、殺すのではなく、布施を止めることが大事であると理解したのです。ですから謗法の者には絶対に布施をしてはならないのであり、このことをきちっと肚に入れることが日蓮正宗の僧俗として大事なことであります。
・仏海の白浪を収め、
一闡提への布施を止めることにより、仏法を正しくする昔の例言であります。
中国の後漢の最後に霊帝という国王がいましたが、その時期に、黄色い布をもって身体を包むという出で立ちの黄巾(こうきん)の賊というのが起こったのです。その賊は、張角(ちょうかく)という道士が首領でしたが、さらにその余党がいまして、これが西河の白波谷(はくはこく)という所において様々な賊の所業を働いていたのです。そこで、その賊のことを「白波」と称したのであります。ですから、日本でも盗賊のことを白波(しらなみ)と言うのです。芝居でやる「白波五人男」などがその例です。
「仏海」というのは、仏様の教えが非常に広大であり、海のように広いという意味の譬えであります。しかし、その中において風によって波が立ち、海が非常に荒れて白波が立ちます。要するに、仏教の中においての賊=白波とは、法然の『選択集』であることを、客の言葉として表しておるのです。
・法山の緑林を截らば、
それから「法山の緑林」とは、前漢の末の頃に荊州の緑林山という所において賊が起こったことが元であります。これによって「緑林」が盗賊の異名となったのです。ですから、この偉大な山のごとき仏法の中における緑林の賊とは、すなわち法然の『選択集』であることを表す語であります。
・世は義農の世と成り国は唐虞の国と為らん。
そこで、そういう邪悪の教を収め、その禍根を截ってしまえば、「世は義農の世と成り国は唐虞の国と為らん」と言うのです。
この「義」は三皇の中の伏羲(ふくぎ)のこと、「農」は同じく神農(しんのう)のことであります。「国は唐虞」というのは、三皇五帝の五帝のほうの4番目と5番目の人と国のことで、「唐」は唐尭(とうぎょう)、「虞」は虞舜(ぐしゅん)のことです。この唐尭という王様は、帝
(ていこく)という方の子であり、その唐尭がさらに帝位を譲ったのが虞舜であります。このことについてもいろいろな話がありますけれども省略いたします。
要するに、こういう昔の伏羲・神農というような方々が世を治めたところの平和な天下太平の時に戻るであろうということを、この客の言葉として言うのであります。
・然して後法水の浅深を斟酌し、仏家の棟梁を崇重せん。
ここにおける客の認識は、法然の『選択集』によるところの諸仏・諸経・諸菩薩・諸天をことごとく捨閉閣抛せよという極端な教えが誤りであったということは、よく理解したわけです。故に、この邪教を止めさせた上で法水の浅深を斟酌する。この「法水」とは、仏法の水の流れ、つまり伝承ということで、仏法において衆生を導くための功徳の水に浅いもの、深いものがあるという、譬えの言葉ですけれども、その浅深を正しく計るということであります。
当時、南都においてすでに倶舎・成実・律・華厳・法相・三論という六宗がありましたが、その後、平安朝になってからは天台・真言の二宗が加わり、さらに鎌倉へ入ってから禅宗と念仏が出てきました。厳密には法然の浄土宗は平安末期からですが、要するにその十宗等がありました。
そのうちの念仏は邪義として除き、あとのものについては、どれがよいかということをよく計り定めつつ、いわゆる「仏家の棟梁」となるべきところの勝れた教えを中心として尊重いたしましょうと言うのです。けれども、その棟梁たるべき教えが何であるかという認識がまだはっきりしていないのであり、そこにこの段階における客の領解があるわけであります。
この次が、いよいよ第九問答の主人の答えです。末寺の御会式で捧読されるのが、ここから後のところであります。
主人悦んで曰く、鳩化して鷹と為り、雀変じて蛤と為る。悦ばしいかな、汝欄室の友に交はりて麻畝の性と成る。誠に其の難を顧みて専ら此の言を信ぜば、風和らぎ浪静かにして不日に豊年ならんのみ。但し人の心は時に随って移り、物の性は境に依って改まる。譬へば猶水中の月の波に動き、陣前の軍の剣に靡(なび)くがごとし。汝当座に信ずと雖も後定めて永く忘れん。若し先づ国土を安んじて現当を祈らんと欲せば、速やかに情慮を廻らし怱(いそ)いで対治を加へよ。所以は何。薬師経の七難の内、五難忽ちに起こり二難猶残れり。所以他国侵逼の難・自界叛逆の難なり。大集経の三災の内、二災早く顕はれ一災未だ起こらず。所以兵革の災なり。金光明経の内、種々の災過一々に起こると雖も、他方の怨賊国内を侵掠する、此の災未だ露はれず、此の難未だ来たらず。仁王経の七難の内、六難今盛んにして一難未だ現ぜず。所以四方の賊来りて国を侵すの難なり。 ・主人悦んで曰く、鳩化して鷹と為り、雀変じて蛤と為る。
この鳩が化して鷹となるなどということは、皆さん方も、一体どういうことなんだと思っていらっしゃるでしょう。これは中国の『礼記集説』という古い書物にあるのです。その中に、「仲春(ちゅうしゅん、2月)に鷹化して鳩となり、仲秋(ちゅうしゅう、8月)に鳩化して鷹となり」と記されておるのです。つまり2月の寒いときには、鷹が化して鳩となるとあり、鷹のような強いものが逆に弱い鳩になる。それが陽気が非常によくなってくる8月には、今度は鳩が化して強い鷹となると言うのです。この8月の「鳩化して鷹となり」という諺を、ここに挙げられておるのであります。 また「季秋(きしゅう、9月)に雀大水に入り蛤となる」という諺もある。これは9月の季節の変わり目には、このようなこともあると言うのです。要するに季節の移り変わりによる物事の変化を表す昔の諺であります。
これを引かれたのは、正論を聞いて劣ったものが勝れたものに変化するという意味の譬えとして仰せられているのです。
・悦ばしいかな、汝欄室の友に交はりて麻畝の性と成る。
この場合に御自身をまさしく「蘭室の友」とおっしゃっておるわけであります。蘭の香りのする部屋、つまり非常に勝れた清浄な部屋に住んでおるということは、清浄な人間が正しい心を持っておるが故に、その住む部屋が自ずから清浄になるということで、それを御自身に当てはめておっしゃっているのです。つまりあなたは私の話を聞いて「麻畝の性」となったと言われるのです。
「麻畝の性」の「麻」とは、植物の麻のことです。「畝」の字は2つの意味があり、一つは田地の長さを測る場合に、1畝とか2畝と言うように面積を示す言葉なのです。もう一つは、田圃などでお百姓さんが鍬で土を高くして畝(うね)というものを作るのですが、そのことを言います。ですから「麻畝」とは、麻の畑のことを言うのであります。
この「麻畝の性と成る」というのは、麻がたくさん植えられている中に、一緒に蓬(よもぎ)を植えた場合、蓬は本来曲がって伸びるものですが、麻の中の蓬は真っ直ぐ伸びるということです。要するに、正しい人と交わり、正しい人の中に入っていれば、曲がった心根の者もまた正しくなっていくという譬えであります。
ですから、あなたは曲がった気持ちを持っていたけれども、今、蘭室の友であるところの主人すなわち私と交わって話を聞くことにより、まっすぐな心になったと言われるのです。
・誠に其の難を顧みて専ら此の言を信ぜば、風和らぎ浪静かにして不日に豊年ならんのみ。
この文は、先ほどからずっと述べてきたように、災禍・国難等が起こっておるのは挙一例諸の上から法然の『選択集』に原因があると言う私の言葉を信じて、あなたがまさしく邪を捨てて正に帰そうと志すならば、緑林の風が和らぎ、また海に立っておる白浪が静かになるという譬えのごとく、謗法をことごとく退治する形が現れることにより、日ならずして豊年、すなわち豊かで安楽な年月を迎えることができるのだと言われるのであります。
・但し人の心は時に随って移り、物の性は境に依って改まる。
この文は、人心の変動しやすいことを警告されるのです。人の心が常に移り変わるように、あなたは今、判ったと言うけれども、あてにならない意味があり、かつあらゆるものの性質は境遇によって改変するものであると指摘されます。
中国の諺に、「江南の橘(たちばな)、江北に移れば枳(からたち)となる」というのがあります。枳というのは刺がたくさんある悪い木と言われておるのです。江南においては橘という立派で有益な木であっても、江北に移ればそれが枳になってしまうと言うのです。これは要するに物の性は境遇によって変わっていくということです。ですから、善い境遇にいれば立派な人であっても、悪い境遇の中に入っていくと、悪い人に染まって悪人になってしまうという意味です。
・譬へば猶水中の月の波に動き、
次は、その人心の変化の譬えを示されます。すなわち水に映った月は、風がなければそのまま月の形をもって映っておるけれども、風によって波が起これば、水の上の月は形が崩れて本来の姿を止めない。そのように縁によって物が変わり、間違ってくるのです。
・陣前の軍の剣に靡(なび)くがごとし。
また、戦いの前軍において甲冑(かっちゅう)を着、武器を手にして敵と戦う軍勢が揃ったけれども、しかし敵が非常に鋭い刀槍をもって強く当たってきたときには、せっかく戦いの支度をしておりながらも、敵の勢いに恐れて退く。つまり初めには戦おうと思っていても、その志が萎(な)えていくようなものだと言われるのであります。
・汝当座に信ずと雖も後定めて永く忘れん。
この譬えのように、あなたは今は信じたようだけれども、この座を去ってしまえば、この正しい道理を定めし忘れてしまうであろうとの警告です。だから直ちに謗法の退治を実行せよということを示されるのが、この次の文です。
・若し先づ国土を安んじて現当を祈らんと欲せば、速やかに情慮を廻らし怱(いそ)いで対治を加へよ。
つまり国土の安穏、天下の泰平を願い、そして「現当」、すなわち現在と当来の世という二世におけるところの真の安楽を願わんとするならば、心を正道に向かって思い回らせ、急いで謗法を退治すべく実行すべしと言われるのです。
信心に入って直ちに折伏をせよということは無理という面もあるかも知れませんが、この仏法は正しいのだから、間違ったものにはきちんとけじめをつけるという気持ちを持って入信することが大切であり、その意味からまた御題目をしっかり唱えて功徳を得、確信を持って折伏をすることが大事なのです。それが「忽いで対治を加へよ」という意味であります。つまり折伏という意味において正しいことを実行に移すということが大切であると、はっきり指南されるのであります。
次には、その理由が何であるかを経文の意をもって教示されるのです。初めにも述べましたが、第二問答において金光明経、大集経、仁王経の二文、薬師経、また仁王経、さらに大集経と、四経のうちの七文を挙げておられるのですが、この4つの経典においては仏法の精神に背くことによって起こる難をずっと挙げられております。それについて、その難が現在どのような状態になっているかを、ここから述べられるのです。
・所以は何。薬師経の七難の内、五難忽ちに起こり二難猶残れり。所以他国侵逼の難・自界叛逆の難なり。
まず「薬師経の七難」というのは、前にも挙げましたが、人衆疾疫の難・星宿変怪・日月薄蝕の難、非時風雨の難・過時不雨の難があって、その他に他国侵逼の難と自界叛逆の難があります。つまりこの七難のうちの前の5つは、すでにはっきりと起こっておるけれども、自界叛逆の難と他国侵逼の難の2つが、まだ残っておると仰せであります。
・大集経の三災の内、二災早く顕はれ一災未だ起こらず。所以兵革の災なり。
次に挙げられる「大集経の三災」とは、一には穀貴、二には兵革、三には疫病の3つであります。穀貴というのは、いわゆる穀物の値段が高くなる、すなわち物価騰貴を意味するのです。今現在でも経済は混乱しているようだけれども、時代の特異性から経済の動乱にはいろいろな状況があるのです。今は今なりにデフレというような形で、いろいろな人が困っておるようであります。当時は大体がインフレという形で、物が少ないことから次第に物の値段が高くなって、ついには物を得ることができなくなるという状態、つまり穀貴であり、それから疫病等が常に盛んであったのですが、しかしまだ兵革の災いのみが現れていないという指摘であります。
・金光明経の内、種々の災過一々に起こると雖も、他方の怨賊国内を侵掠する、此の災未だ露はれず、此の難未だ来たらず。
先に挙げられた金光明経に多くの難が述べられ、その中に「他方の怨賊国内を侵掠する」ということが説かれておるけれども、これがまだ起こっていないと言われるのです。
・仁王経の七難の内、六難今盛んにして一難未だ現ぜず。所以四方の賊来りて国を侵すの難なり。
「仁王経の七難」というのは、日月失度の難・星宿失度の難・災火の難・雨水の難・悪風の難・亢陽の難・悪賊の難で、これらは前に引かれたように、非常に長く述べられております。このうちの六難は盛んであるけれどもへ最後の賊来の難、つまり賊が来たって国を侵すという一難が未だ現じていないと指摘されるのです。