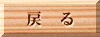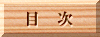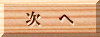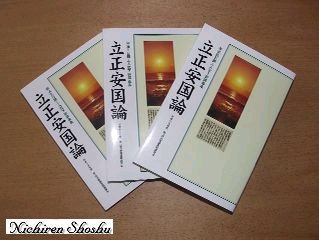☆御法主上人猊下御講義集 『立正安国論』が発刊この度、法華講連合会より、「御法主日顕上人猊下御講義集『立正安国論』平成15年第1回法華講夏期講習会」が発刊された。これは、平成15年の5月〜7月、総本山において行われた第1回法華講夏期講習会における御法主日顕上人猊下の十期にわたる御講義のうち、本紙に奉載した第2期・4期・6期・8期・10期の5期分を一冊にまとめたものである。
御法主上人猊下御言葉
3月度唱題会の砌
おはようございます。ただいまは3月度の広布唱題行を皆様と共に執り行いました。皆さん方がお元気にここにお集まりになりまして、私も大変うれしく思う次第であります。この唱題行は、申すまでもなく大聖人様が御指南である、「自行化他に亘(わた)りて南無妙法蓮華経」(御書1595ページ)の修行であります。すなわち、自行の唱題行とともに、また他を導いていくところの折伏の元となる唱題行であります。皆様方も、本年度において一人が一人の折伏を必ず行じようという志をもって唱題行に励み、縁のある多くの方々を折伏していっていただきたいと思います。
折伏の心は、色々とありますが、このことは皆様方も既に体験されておることと思います。大聖人様の御指南で、「閻浮の内の人は病の身なり、法華経の薬あり、三事すでに相応しぬ、一身いかでかたす(助)からざるべき」(同891ページ)という、有名な御文があります。この御指南の如く、一閻浮提の人はことごとく病の身なのです。この病には心の病と身体の病とがあります。元気で活動しているような人でも、心の病は必ずあるのです。なぜならば、十界を見てみると、地獄・餓鬼・畜生等を基本とした極めて不幸な生活をしておる衆生もおります。また、少し上がって修羅・人間・天上界等の境界もあります。しかし、まだこれは凡夫の、六道輪廻のなかのことであります。さらに一歩上がって、声聞・縁覚のところに行っても、なおかつ自調自度という次第でありますから、自分の悩みの解決だけを考えて、ほかの人のことを考えない、すなわち菩薩の境界になれないというところに、塵沙(じんじゃ)の惑という大きな病が存するのであります。六道の衆生はもちろん、見惑・思惑、塵沙惑、無明惑の全部を持っておりますから、大きな心の病を抱えておるのです。
それからまた、身体の病も色々とあります。実は私も2月度において少し体調を崩しまして、色々な体験をいたしました。詳しいことは敢(あ)えて言いませんが、毎日、少しずつ唱題行を行うことによって回復できたと思っております。そういうところから唱題行の時間がだんだんと延びていって、今は1時間の唱題行もできるようになりました。
このお題目の功徳は、身体に対しても心に対しても存するのであります。多くの人は病の身なのであります。皆様方が、唱題行の功徳によるところのしっかりとした境界から、縁のある人々の命、生活を見るとき、そこに必ず折伏をしなければならないという境界が起きるのであります。それが仏界即九界、九界即仏界なのであります。
ある言い方では「仏界涌現」という言葉もありますが、仏界涌現という言葉自体が間違っておるとは思いません。しかしながら、凡夫から直ちに仏界へ行くというように取ると、得てして増上慢が起こる感じもあると思うのであります。妙法から離れての成仏はないのです。したがって九界即仏界・仏界即九界が一念三千であり、「一念三千の成仏」(同563ページ)ということを大聖人様も御指南であります。
一念三千の尊い法は、南無妙法蓮華経の唱題に存するということを深く御自覚いただき、いよいよ御精進されることを心からお祈りいたしまして、一言、本日の御挨拶といたします。御苦労様でした。
彼岸会の意義
彼岸会は、春分と秋分の年二季に行われる法要です。その春分に当たる今月20日には、総本山において御法主日顕上人猊下大導師のもと春季彼岸会が奉修されます。また、この法要は全国の各寺院においても執り行われます。仏教では、私たちが現在生活している世界のことを穢土(えど)、または娑婆(しゃば)世界などと呼び、煩悩(ぼんのう)や苦しみの充満した穢(けが)れた国土であると説きます。そして、この娑婆世界を「此岸」に譬(たと)えるとともに、これに対して悟りの境界、成仏の境界のことを「彼岸」に譬えるのです。
法華経以前に説かれた40余年の経々には、釈尊在世や正法・像法時代の菩薩たちが、無量劫(こう)という長い期間、何度も生死を繰り返しながら六波羅蜜(ろくはらみつ)等を修行して悟りを得たことが説かれています。けれども末法の衆生は大聖人様が、「生死の大海には爾前の経は或は筏(いかだ)或は小船なり。生死の此の岸より生死の彼の岸には付くと雖も、生死の大海を渡り極楽の彼岸にはとヾ(届)きがたし」(御書350ページ)と仰せのように、爾前諸経に説かれる歴劫(りゃっこう)修行では成仏の彼岸に到ることは到底叶わないのです。
私たちが成仏の境界に到るためには、大聖人様が、「日蓮がたましひ(魂)をすみ(墨)にそめながしてかきて候ぞ(中略)あひかまへて御信心を出だし此の御本尊に祈念せしめ給へ」(同685ページ)と仰せのように、大聖人様が御図顕あそばされた御本尊を一心に信じ奉り、御祈念することによって、「六度の功徳を妙の一字にをさ(収)め給ひて、末代悪世の我等衆生に一善も修せざれども六度万行を満足する功徳をあたへ給ふ」(同605ページ)と示されるように、六度万行を満足する功徳である即身成仏の大利益を戴くことができるのです。
ですから彼岸の法要においては、私たち一人ひとりが唱題を根本とした折伏・育成等の実践によって戴いた功徳をもって、諸々の先祖を追善回向(ついぜんえこう)していくことが大切なのです。
また、彼岸会においては各々の先祖供養のために塔婆を建立して回向を行いますが、大聖人様はこの塔婆供養の功徳についても、「丈六のそとば(卒塔婆)をたてゝ、其の面(おもて)に南無妙法蓮華経の七字を顕はしておはしませば(中略)過去の父母も彼のそとばの功徳によりて、天の日月の如く浄土をてら(照)し、孝養の人並びに妻子は現世には寿(いのち)を百二十年持ちて、後生には父母とともに霊山浄土にまいり給はん事、水すめ(澄)ば月うつ(映)り、つゞみ(鼓)をう(打)てばひゞ(響)きのあるがごとしとをぼしめし候へ」(同1434ページ)と仰せです。
御法主上人猊下御講義
『本門の本尊』(下)
第三項 三大秘法と戒定慧
(1)御義口伝(弘安元年1月1日付)
御義口伝に云はく、此の本尊の依文とは如来秘密神通之力の文なり。戒定慧の三学、寿量品の事の三大秘法是(これ)なり。日蓮慥(たし)かに霊山に於て面授口決(めんじゅくけつ)せしなり。本尊とは法華経の行者の一身の当体なり云云。 ○此の本尊の依文とは如来秘密神通之力の文なり。
本尊の依文は、文上からは釈尊の如来秘密神通之力の当体になりますが、文底においては久遠元初の如来秘密神通之力、一身即三身・三身即一身の仏身であります。これは、通途の釈尊等の色相荘厳の仏身ではなく名字即の凡身、即座開悟の仏です。
○戒定慧の三学、
仏教の内容というのは要括して言えば、戒・定・慧なのです。皆さん方も、他の人と話をしている時に、仏教とは何か聞いてみてください。世間の人は、たいてい答えられないと思います。ですから皆さん方には、今日は、それが戒・定・慧の3つであることをしっかりと覚えてもらいたいのです。
今、大正年間の刊行された『大正新修大蔵経』という、正篇・続篇を合わせて85巻、さらに図像部・総目録を合わせると100巻ほどに及ぶたいへん厚い本があるのです。その本を開いてみると、細かい漢字がすき間のないほどびっしりと並んでおり、さらに返り点も送り仮名も付いてませんから、読んでもなかなか内容を理解することができないのです。しかし、そこの説かれてある内容を分けてみると、結局、戒・定・慧のどれかに属しており、他にはないのです。ですから、それだけ膨大な教えの内容が説いてある経々であったとしても、結局、その内容は戒・定・慧の3つのどれかを説いてあるということであります。
それから、皆さん方も自分の子供を教育しますね。この教育する気持ちも、戒・定・慧の3つのいずれかに当たるのです。悪いことをさせないようにする意味で導く上において「こんなことをしてはいけない」と注意するのは防非止悪ということですから「戒」に当たります。そして、これはまた善を勧めるという意味もあるわけです。それから「慧」は、智慧であります。ありとあらゆる意味で、問題に対して正しい解決をしてゆくところの心の用きであります。そしてもう一つは、やはり心に散乱があれば物事を成就することができず、必ず不幸になっていく意味があるのです。皆さん方の生活の中で、例えば仕事などあっても、心がそのところにきちっと向かわなければ、絶対によい仕事はできないのです。ですからこれが「定」ということであります。
したがって、我々の生活の中において戒・定・慧の3つが非常に大事であるいうことが、これでお判りになると思います。やはり仏法で教えておる道の根幹がそこにあるわけです。
○寿量品の事の三大秘法是なり。日蓮慥かに霊山に於て面授口決せしなり。
それで、この戒・定・慧の根本が、実は『寿量品』の三大秘法であるとおっしゃっておるわけです。このことが今まで拝してきた御文の結論としてはっきりと拝せられのであります。
○本尊とは法華経の行者の一身の当体なり云云。
法華経の行者というのは、法華経を身をもって振る舞われた方のことであります。その法華経の行者が日蓮であると仰せです。この行者の内容については、他には誰も肩を並べられる人はおりません。「勧持品二十行の偈」も、大聖人様以外は誰もこれを身に体して読んだ人はいないのです。先ほど「数々見擯出」ということを言いましたけれども、あの「数々見擯出」の経文も釈尊滅後、大聖人様お一人以外は誰も読んでいないのです。ですから各所に、「日蓮は閻浮第一の法華経の行者なり」(御書729ページ等)とおっしゃっている所以が、そこに存するのであります。
そして、その法華経の行者たる末法出現の大聖人様の当体こそが、そのまま本尊であるということを仰せになるわけであります。そのところを我々は信心の上からよく拝すべきであります。
◇戒に関する文(摘要) この後の御文は、どういう意味からこれを挙げたかと申しますと、大聖人様の一期の御化導は三大秘法でありますが、実際に一切衆生を救うという内容においては、やはり「戒」が主体になる意味があるのです。「事相彰顕」という意味がありまして、具体的なかたちでは我々が本尊を信ずるということは信ずる心であり、御題目を唱えるということは修業のかたちである。けれども、実際に法を持ち法を行じていくということは、戒という実践のかたちにおいて顕れるのです。
今日残っている大聖人様の御遺文の中で、大聖人様が一番最初にお認めになられたのが、仁治3(1242)年、御年21歳の時の『戒体即身成仏義』という御書であります。これは皆さん方が持っておる『平成新編御書』の一番最初にあります。この『戒体即身成仏義』は、今、我々が読んでも難しい内容なのです。
しかるに、大聖人様は天福元(1233)年に、当時、真言天台の寺である安房の清澄寺で出家されましたから、したがって真言の法門をずっと師匠から教わっておられました。内容においては一往、最後のところで真言を立てられておるのです。けれども、主には法華経を中心に述べられているのです。これはまだ宗旨建立以前の御書ですから、やむを得ない部分がありますけれども、ここのところに一代仏教の戒体を述べられると同時に、法華経の戒体が述べられておるのであります。この「戒」ということは、戒法・戒体・戒行・戒相という4つの意味があるのです。特にその中の「戒体」についての法華経による即身成仏義というのは、大聖人様がわずか21歳の御時にお認めになっているのです。
その次に寛元元(1243)年、22歳の御時にお認めになったのが『戒法門』という御書であります。これは『戒体即身成仏義』の次に載っています。ですから大聖人様が認められた一番最初の御書が戒についての内容でありますから、この戒ということがいかに大事であるかという意義がお判りかと思います。
その上から今度は「定」と「慧」のほうの経文や意義を各御書にずっと述べてられてきて、そして三大秘法の解明に入って初めて戒壇ということになるわけです。先ほどの建治2年の『報恩抄』では、三大秘法の本尊・題目についての内容を説かれておるけれども、戒壇という名目をあげられたのみで、その内容については述べられていないのです。ですから、その戒壇をお示しになるということが、大聖人様一期の御化導の中において非常に大事な意義を持っておるわけであります。そういうことから、三大秘法のうちの「戒」及び「戒壇」ということについて、この後の御文で拝する次第であります。
(2−1)戒法門(寛元元年)そこでまず最初は『戒法門』の御書で述べられております。まだ他のところにも戒の法門があちらこちらに述べられてありますけれども、だいたいはこのへんのところで括られている意味があります。
夫(それ)人は天地の精(せい)、五行の端(たん)なり。故に悟りあて直(なお)きを人と云ふ。心に因果の道理を弁へて人間には生まれける由を知るべし。一代聖教(いちだいしょうぎょう)のおきて(掟)には、戒を持(たも)ちて人間には生まるとおきて(おきて)たり。 このところでは、基本的に人間として生まれるのも、この「戒」によって生まれることができたと言われます。皆さん方も、人間として生まれたということは、過去において人間として生まれるだけの戒徳を積んでいるわけです。悪いことをせずに善いことをするという意味のことが戒であり、特に悪いことを戒めるのが戒でありますから、その悪いことを諫めた法の徳により、今世において皆さん方が犬にも猫にも生まれずに人間に生まれてきたのであり、それは過去の徳にあるということをおっしゃっているのです。
○夫、人は天地の精、
天地の魂、天地の心を悟るのは人間であるということです。犬や猫も生き物であるけれども、まだ天地の魂、心を悟っておるとは言えないのです。ところが人間は、天地の魂、心を知ることができる、また天地の心そのものが人間の深い心であるのです。
○五行の端なり。
「端」とは「ただしい」または「もと」という意味です。「五行」とは、木・火・土・金・水の5つで、人はこの精華としての在り方による運行を正しく悟っているとの意味でしょう。そこに天地の中において人事百般と通観して、やはりこのような5つのかたちと、その意義があるということは、中国の古代から現れてきている思想でありますが、この意味のことを大聖人様も用いられていらっしゃるわけです。
ですから、皆さん方の中には聞いたことがある方もおられると思いますが、総本山での御霊宝虫払大法会の「御真翰巻返し」の時に『木火土金水(もつかどこんすい)御書』というのがよく出ますね。この『木火土金水(もつかどこんすい)御書』の木・火・土・金・水が五行であります。これについて、東は木、南は火、西は金、北は水、中央は土に配し、また五臓について、肝臓は木、心臓は火、脾臓は土、肺臓は金、腎臓は水に配し、その他あらゆる人事百般を五行にあてはめてあり、その円表であります。
また、これには「相生相剋」ということがありまして「相生」は「生ずる」、「相剋」は「殺す」ということです。すなわち「相生」とは、「金化して水生じ、水流れて木栄え、木動じて火明かなり、火炎あって土貞なり。此れ則ち相生なり」(摩訶止観弘決会本下326ページ)とあるように、金は水を生じ、水は木を生じ、火は土を生じるということがあるのです。これに対して「相剋」とは、「火は水を得て光りを滅し、水は土に遇って行かず、土は木に値って腫瘡(しゅしょう)し、木は金に遇って折傷す。此れ則ち相剋なり」(同)とあるように水は火を剋し、土は水を剋し、木は土を剋し、金は木を剋するというこです。
ですから、「相生」は順次に生まれるほうで「相剋」は逆次に破るほうなのです。よく人との相性が良いとか悪とか言うのも、この五行の相生相剋から来ているのです。
それから皆さん方は、一白・二黒・三碧・四緑・六白・七赤・八白・九紫という、「九星」というのを聞いたことがあるでしょう。皆さん方も、そのうちのどれかに入っているのです。例えば、五黄土星の人は土で、六白金星の人は金だから、土が金を生ずるから相性が良く、三碧木星と五黄土星は、木が土を剋するから相性が悪いというようなこと言うのです。これを本当に勉強して占っている人は、8割くらいは当たるということを言っている人もいるのです。けれども、当たらない人もいますよ。
皆さん方のご夫婦の中で、相生でなく相剋のほうの相性の方もいるかもしれませんが、「だったら別れよう」なんて言ってはいけません。やはり今まで一緒になっていたのは、どこかにいいところがあり、またそのような因縁があるのです。したがって、こんな簡単なもので、過去・現在・未来にわたる人間の深い緻密な内容が律し切れるものではないのです。
けれども、御題目には三世にわたる生命の一切を包容しますから、かえって相剋の相性中において本当の妙法の功徳で、悪い因縁が善い因縁に変化することもあります。
○心に因果の道理を弁へて人間には生まれける由を知るべし。
つまり心に因果の道理を弁えることが大切であり、また過去にその道理を弁えて人間に生まれたということです。三世の因果を知る、これは大事なことであります。
○一代聖教のおきてには、戒を持ちて人間には生まるとおきてたり。
一代聖教における三世因縁果報の掟は善の行為、すなわち戒を持って人間に生まれるということを示されておるのです。顧みて人と生まれたことの尊さを知るべきであります。
(2−2)戒法門(寛元元年)
戒と申すは一切の経論に説かるゝ数は、五戒・八戒・十戒・十重禁戒(きんかい)・四十八軽戒(きょうかい)・二百五十戒・五百戒・乃至八万四千戒。此くの如く戒品(かいほん)多しといへども、始めの五戒を戒の本と申し候ぞ。 「戒」と言っても仏教の深い内容から見れば、このような戒がたくさんあるのです。それぞれの説明は時間がないので省略いたしますが、結局はこの多くの戒も、この中の「五戒」が基本であると言うのです。この「五戒」だけは、道徳の基本として我々も常に肚に入れておかなければなりません。「御題目をとなえているからには、どんなことをしてもよい」「戒なんかどうでもいいだろう」というのは、やはり短見です。
○五戒
五戒というのは、不殺生戒・不偸盗戒・不邪婬戒・不妄語戒・不飲酒戒の5つです。最後の「不飲酒戒」については、大聖人様の御在世当時よりもっと昔の僧侶は、釈尊の教えから来る方便の戒律で、酒を飲むことを誡めらていたけれども、大聖人様の時代において、下種仏法の根本戒律から浄化される意味があり、故に大聖人様も召し上がられたのです。ですから大聖人様のところへお酒の御供養をした人もたくさんいたのです。大聖人様が、薬酒として召し上がられたことが御書の文から拝されます。
では、何故に五戒中で飲酒だけは他の4つと異なるかと言えば、これには「性戒」と「遮戒」の違いがあるのです。五戒の中の他の4つは、仏の誡めの有無に関わらず、本来その行為の性質が悪であり、犯せば罪になるから、これを性戒と言います。それに対して「不飲酒戒」は、酒を飲むこと自体は他の4つのように悪いことではないが、酒を飲むことによっていろいろな不道徳な行為を起こしやすくなり、自分や他人を不幸にする意味があるのです。これは悪の行為となり、その実例が多くあったので、酒を飲まないように仏が誡められた。これを遮戒と言います。
酒を飲むことによって起こる不道徳の元は、一般的に言って心の中の貪・瞋・癡の3つが盛んに現れてくることが挙げられます。御題目を唱えてしっかりしていれば大丈夫なんですが、そうでないと酔っぱらうことによって、その人の性癖から貪りや瞋りや愚癡など低劣な心が生じてくる場合が多くあるのです。その結果、殺生・偸盗・邪淫・喧嘩・口論・悪口・誹謗等の不道徳や犯罪行為にまで発展します。また飲み過ぎて健康を害することも多々あります。このように酒の害が多いので、これを遮り誡められたのです。しかしまた、酒は憂いを払う玉箒(たまばはき)とも言われ、心身の慰安に最上の意味もあり、要は善く活用することが大切でしょう。
そこでこの五戒は、まず殺生をしてはいけない、それから盗みをしてはいけない、次が邪淫をしてはいけない、それから嘘を言ってはいけない、最後に今言った酒を飲んではいけないというように、この5つをきちんと守るということが大事であります。ですから「始めの五戒を戒の本と申し候ぞ」とお示しになっておるわけであります。
○八戒・十戒・十重禁戒・四十八軽戒・二百五十戒・五百戒・乃至八万四千戒。
この「十重禁戒(きんかい)・四十八軽戒(きょうかい)」は大乗戒で、それから「五戒・八戒・十戒・二百五十戒・五百戒乃至八万四千戒」は小乗戒のほうになります。
(3)教行証御書(健治3年3月21日)ここに来ると一挙に佐渡以降の御法門になってきます。
此の法華経の本門の肝心妙法蓮華経は、三世の諸仏の万行万善の功徳を集めて五字と為(せ)り。此の五字の内に豈(あに)万戒の功徳を納めざらんや。但し此の具足の妙戒は一度持って後、行者破らんとすれども破れず。是を金剛宝器戒(こんごうほうきかい)とや申しけんなんど立つべし。三世の諸仏は此の戒を持(たも)って、法身・報身・応身なんど何れも無始無終の仏に成らせ給ふ。此を「諸経の中に於て之を秘して伝へず」とは天台大師書き給へり。今末法当世の有智・無智・在家・出家・上下万人此の妙法蓮華経を持って説の如く修行せんに、豈(あに)仏果を得ざらんや。 ○本門の肝心妙法蓮華経
戒・定・慧のすべてを要括する根本の法体です。故に妙法蓮華経を受持することが、仏に成る真実の道であると同時に、根本の戒であるという御指南です。仏に成る道は、悪いことを止めることが大切であるけれども、その種々の悪いことを浄化する根本の道徳として真実の善を行う、すなわち妙法蓮華経を唱え持つことが真実の戒であり、三世諸仏のあらゆる行も善徳も、この妙法に一切が具わるという下種本仏の一大宣言であります。
○是を金剛宝器戒とや申しけんなんど立つべし
金剛宝器戒という意は、金剛石が堅固で不変のように、この戒は一度受けたならば、未来永劫にわたって絶対になくならないと言うのです。ですから大謗法を犯している人であっても、戒体はなくならないのです。宗門の下種三宝を謗っているあの創価学会の連中も、以前に宗門から本仏大聖人の仏法の法体としての御授戒を受けている者は、その戒体はなくならないのです。
けれども謗法とは、法と仏に背いていることですから、その罪業は必ずはっきりと現れてきます。それによって地獄に堕ちるのであります。彼らの宗門への怨嫉・憎悪・悪口罵詈・妨害・法義や化儀の改変等は、その心と行為がそのまま地獄の相であり、それは未来の阿鼻地獄を暗示しております。
しかし、一旦受けたその戒体はなくならないから、未来永劫の後において地獄より這い上がり、つぶさに六道を巡りつつも、やがて戒体の上から下種の妙法を発徳して成仏するということであります。正しい信心の人は、今世臨終までに成仏します。これが金剛宝器の戒体ということです。
この戒体ということは、一般的にも小乗・大乗にわたり、あらゆる戒に存在します。すなわち戒を受けるということは、受ける者においては必ずその戒を持つことを誓わなければならないのです。そうすると、戒を受け誓ったことによって、その受けた方の内容が、その人の身体の中に具わるのです。したがって、その戒の内容に基づいて悪いことをしないという意味の戒の命が、その人に具わるのであります。もちろん、謗法背反の池田や創価学会員の者共は、一旦受けた金剛宝器戒の内容に自ら背いているので堕地獄必定なのです。
さて、皆さん方は「尽形寿戒」(じんぎょうじゅかい)というのを聞いたことがあるでしょう。これは小乗の戒体で、尽形寿とは「形寿」すなわち生きている寿命のかたちが「尽」すなわち尽きるまでの戒ということで死んだら消滅する戒体なのです。生きている間だけ存在する戒なんですね。すなわち戒師が「不殺生戒を持つや否や」と言うと、「持ちます」と誓う。つまり「殺生をいたしません」と誓うことにより、その人の命の中に、その不殺生としての戒体が生ずるのであります。
これに関して、小乗に「無表色」という語があります。これは形として表れていない色法のことです。そもそも色法とは物質であり、質量のあるものを言います。しかるに、この「無表色」は表色がないこと、つまり質量として表れていないことで、誓うことによって地・水・火・風・空の五大により無形の色法がその法に則って身体の中に生ずることであります。これは大聖人様も『戒体即身成仏義』の中でお示しになっております。
さて、この戒体について、外道の戒、人天の戒、小乗の声聞・縁覚の戒、菩薩の戒、法華仏乗の戒の区別があります。
仏教外の外道の誡めは「空家戒」と言い、何もない家を造るようなもので、正しい因果果報が存在せず、したがってその戒は空虚にして必ずなくなってしまい、何ら善い結果が来ないのであります。
それから人天の道、いわゆる法華経の裏付けのない五戒などの戒は「楊葉戒」と言い、生きている間だけの尽形寿であって、死んだらなくなってしまうのです。この楊葉の「楊」の字は「猫柳」という植物です。この猫柳の葉は、秋になると紅葉し、陽光に照らされて金色に輝くけれども、時が経てば、すぐにその葉は枯れてバラバラと落ち消滅します。そのような戒体は安定せず、未来に持ち越さないということの譬えを言われるわけです。
次に声聞・縁覚の二乗の戒は、一旦は初果・二果・三果・四果等の悟りを得ますが、その先は灰身滅智して空に入ってしまう。その後は全く役に立たない。これを「瓦器戒」と言い、瓦のようなものであると言うのです。瓦は一度壊れたら、その後は用をなしません。その譬えによる名称です。
次に、菩薩の戒は「金銀戒」と言います。この戒は、金や銀の器は壊れることもあるけれども、仮に壊れたとしても金や銀そのものの値打ちは失われないという意味です。そういうところから、これは大乗の菩薩戒を譬えます。つまり金銀の器は壊れてもその値打ちが存するように、大乗の菩薩は自行化他の誓願により、死後もその法の命は失わず、仏道に精進します。そこでこの戒体を金銀戒と譬えるのです。
次に、実大乗の法華経の戒、特に本門の妙法蓮華経の戒は、永劫に失うことがないということから、金剛のごとき堅固にして不変の意味を持っておるので「金剛宝器戒」と言われるのであります。したがって、三世の諸仏もこの法華経本門を受持する戒によって法身・報身・応身の仏と成ったのであり、末法の一切衆生も妙法蓮華経を持つことにより、その戒の功徳として必ず仏果を得るとの大事を、この『教行証御書』で仰せであります。
(4−1)百六箇抄(弘安3年1月11日)
二十、脱益の戒体の本迹 爾前・迹門、熟益の戒体を迹とし、脱益の戒体を本とするなり。迹門の戒は爾前・大小の戒に勝れ、本門の戒は爾前・迹門の戒に勝るゝなり。 ○脱益の戒体の本迹
脱益の戒体というのは、法華経の本門に脱益と下種益の二義があるうちの脱益の戒体なのです。つまり釈尊在世の本門の戒体です。しからば、この戒体の具体的なかたちはどこにあるかと言うと、『寿量品』に、「爾時仏告。諸菩薩。及一切大衆。諸善男子。汝等当信解。如来誠諦之語」(法華経428ページ)とあるのが戒なのです。すなわち、「如来の誠諦の語を信解すべし」(同)と仏様がおっしゃているのが本門の戒なのです。
そして、その後のところで、「是時菩薩大衆。弥勒為首。合掌白仏言。世尊。唯願説之。我等当信受仏語。如是三白巳。復言。唯願説之。我等当信受仏語。」(同)すなわち、「唯願わくは之れを説きらまえ。我等当に仏の語を信受したてまつるべし」(同429ページ)と、弥勒菩薩が仏様の御言葉をまさに信受いたしますと誓いました。これが三誡に対する三請であります。「誡」は「いましめ」で、それに対する「請」は「こう」「ねがう」という意味です。ですから説法を願うということは、そこ志において誡を受け奉るということですから、まさに「如来の誠諦の語を信解すべし」という仏の語が、要するに本門戒なのです。
そこで、この「脱益の戒体」というのは、釈尊一代50年の化導において、その最後の法華経本門の戒体が一切の戒の根本究竟であることをお示しであそばされおるわけであります。
(4−2)百六箇抄(弘安3年1月11日)
二十一、下種の戒体の本迹 爾前迹門の戒体は権実雑乱、本門の戒体は純一無雑の大戒なり。勝劣は天地・水火尚及ばず、具に戒体抄の如し云云。 ○下種の戒体の本迹
下種の戒体というのは、大聖人様の末法下種の戒体であります。
○爾前迹門の戒体は権実雑乱、
「爾前」とは、法華経以前の40余年の経々です。また「迹門」とは、天台・伝教の弘通は法華一経のうち迹門を面とし、本門を裏にして説いております。これは、釈尊一代の化導が、久遠から垂迹した迹門の位置にあり、その本門も迹中の本門なのです。
その釈尊一代の化導を締め括るのが迹化たる天台・伝教の役目です。したがって、方便と真実の全体を範囲として法華を中心としつつ説く故に、天台の法門においては権実双用、つまり方便権経と真実の実教の戒を並べて用いておるのです。伝教大師も『山家学生式』において述べておるかたちの中では、法華経の受持の一乗戒を基本としておるけれども、権大乗の梵網経(ぼんもうきょう)や華厳経、瓔珞経(ようらくきょう)その他の十重禁戒・四十八軽戒等をずっと挙げておるわけです。 しかるに、これについて「権実雑乱」とは、天台の法門は釈尊仏法を法華経を中心としてまとめて衆生を導く像法時代の化導なのです。しかし、末法においては迹の全くない久遠元初独一の本門が弘通される時です。その末法に至っては、天台の戒は無用の諸戒となります。そこで末法に至っても、時と機に迷って権実双用することによって、それが権実雑乱の誤りとなるのであります。
○本門の戒体は純一無雑の大戒なり。
「純一無雑」とは、久遠元初本門根元の三大秘法中の虚空不動戒で、妙法受持のみの戒であるから、純一にして混じり気がないという御指南です。この本門独一の妙果と爾前迹門の戒を比べれば、天と地、水と火のごとき相違と言われるのです。
○具に戒体抄の如し云云。
「戒体抄の如し」と追記されるのは、要するにこの元意は久遠即末法、末法即久遠という意味で挙げられておるのです。十重禁戒は梵網経で、久遠元初の法華経から開会して、ひとまず本門の戒の形式を述べられておるのであります。この文に、本門脱益の戒体と下種の戒体のけじめは明かではありませんが、前に本門脱益の戒体を挙げ、下種本門の戒体と対比されてありますから、種脱の勝劣は当然です。そこに久遠即末法、末法即久遠の化導の、特に形式の上から、このことを『本門戒体抄』として示されておるということであります。
現在の宗門の授戒文は、この意を含みつつ、三戒三誓の捨邪帰正の方式に括られております。今日、皆さん方が入信される時に、各寺院において御授戒を受けます。これは末法の本仏日蓮大聖人様から皆さん方が戒を受けるということなのです。
ですから、寺院の僧侶から「のみ」戒を受けたのだと思っていたら、これは大きな間違いなのです。我々僧侶は伝戒、つまり大聖人様よりの戒を伝える役目なのです。したがって皆さん方一人ひとりは、末法の本仏大聖人様より、下種本門の大法を持つべく戒を受けているのです。それを忘れてはなりません。本仏大聖人様から戒を授かったのであると、有り難く思うことが大切であります。
第四項 三大秘法に於ける戒壇の意義
- 本尊所住の処
- 法本尊
- 人本尊
- 受持の処即戒壇(於我滅度後、応受持此経、是人於仏道、決定無有疑)
- 受戒の儀式とその場所
- 唱題修行の処
- 本因下種四妙(境智行位)中の位妙
- 事相の顕現(防非止悪・即身成仏の処)
- 所践の義
- 事壇建立の意義
○本尊所住の処(人本尊、法本尊)
この「戒壇」ということは、まず「本尊所住の処」なのです。そこには戒壇の大御本尊様を根本とする本門の大漫荼羅が法本尊であり、即また日蓮大聖人様が人本尊であり、その「本尊所住の処」が戒壇であります。先ほどの『南条殿御返事』の「教主釈尊の一大事の秘法を霊鷲山にして相伝し、日蓮が肉団の胸中に秘して隠し持てり」という御文のところでは、大聖人様の御尊体がおわします処が即「本尊所住の処」になり、これが戒壇に当たるのです。特に、一期御化導の最大最極の本尊が、広布の根本たる本門戒壇の大御本尊であり、根本の事の戒壇の道場であります。
○受持の処即戒壇(於我滅度後、応受持此経、是人於仏道、決定無有疑)
これは、我々が「妙法蓮華経を持ちます」と誓う処、この「受持の処」が戒壇という意義になります。それから「於我滅度後、応受持此経、是人於仏道、決定無有疑」というのは『神力品』の結要付嘱を説かれた文の偈頌の一番最後のところにこの文があるのです。これは大切な御文でありますが、要するに必ず仏になることができるが故に、「此経」すなわち本尊を受持すべしという觀文であります。その戒を受持する行には、本尊のまします場所として、ここにそのまま義の戒壇という意味があるのです。
○受戒の儀式とその場所
これは前のところと重複しますけれども、要するに皆さん方が受ける「受戒の儀式」と「その場所」が、義において戒壇に当たります。
○唱題修行の処
この「唱題修行の処」が、あらゆる功徳に能く通ずる「能通」の意義から戒壇に当たります。また「本尊所住の処」は「虚通」の義として一心一念遍於法界の意義が存する故に戒壇に当たるのです。ですから「唱題修行の処」においては、我々の信心修行の功徳によって、我々の凡夫の身がそのまま仏身を成ずるのです。したがって「唱題修行の処」が、仏の戒徳に通じておるという意義から戒壇に当たるのであります。
○本因下種四妙(境智行位)中の位妙
位妙という意義は、戒壇に当たります。
○事相の顕現(防非止悪・即身成仏の処)
折伏ということは、これは戒の実践ということになるのであります。つまり折伏においては、相手に対して「信心してみなさい」と勧めるでしょう。このことは「正しい信仰を持たなかったならば不幸になりますよ」ということや「あなたが現在信じている宗教は間違った教えであるから正しい信仰に入りなさい」ということを含めて、これはやはりひとつの誡めなのです。つまり「防非止悪」ということは、間違った教えを信じている人に対してそれを誡めて、そして正しい法を示すということですから、これはそのまま戒の実践になるわけです。したがって、三大秘法のうちでは本門戒を実践するところに折伏の意義が存するわけであります。
○所践の義
これは、我々が本尊所住の霊場を足をもって踏むわけですから、実際に「本尊所住の処」へ参詣していくところに「防非止悪」の本門戒の功徳が成就していくということが存するのであります。
○事壇建立の意義
これは、本門戒壇の御本尊まします処、事の戒壇という先師よりの相伝がありますが、さらに広宣流布の実現ということに「事壇建立の意義」があります。大聖人様が一切衆生を真に導き給う本門の戒法は、本門の本尊、三大秘法の広宣流布に存するわけで、そこに本門事の戒壇建立ということをもって日興上人付嘱をあそばされておる所以が存するのであります。それでは時間がありませんのでテキストの次の文は省略いたしまして、その次の『三大秘法抄』の御文にまいります。
(1)三大秘法抄(弘安5年4月8日)
戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ)を申し下して、霊山浄土(りょうぜんじょうど)に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並びに一閻浮提の人懺悔(さんげ)滅罪の戒法のみならず、大梵天王(だいぼんてんのう)・帝釈(たいしゃく)等の来下(らいげ)して踏(ふ)み給ふべき戒壇なり。 私は登座以来、この御文の文々句々について、部分的にもその解釈をさせていただいたことがあるとすれば、まことに申しわけなかったことと思います。と言うのも、この御文について日寛上人も広布の事相である故に「事の戒壇」ということをおっしゃっているけれども、それ以外の解釈は特になされていないのです。つまりこれは御本仏の大慈大悲の御遺訓で、世界の一切衆生救済の大理想ですから、このことについて「どうだ、こうだ」と我々が短絡的に、いい加減に解釈すべきものではないのです。ただ仰いで信心の上に御文の根本精神を拝し、将来この御文の内容が、御仏智において必ず顕れることを我々は確信すべきであります。
広宣流布の条件としては「王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて」という御文に拝せられますが、この「仏法」とは清浄無染の大法を正しく受け継ぐ下種本門の三大秘法の随一、本門戒壇の大御本尊と大聖人、日興上人以来嫡々相伝の仏法であります。大事な正法を、恐れ気もなく己の都合によって種々改変する創価学会などに、本仏大聖人の仏法は絶対に存在しません。
また、「勅宣(ちょくせん)」「御教事」等の語は、大聖人様の御在世当時の御指南でありますけれども、御仏智のどこにわたらせ給うかにつき、その一切衆生救済の大理想の時々の事相に約して拝していくべきであります。
ですから、過去において池田大作が正本堂を造ったから、あれが事の戒壇であるとか、現在あるのがそうだとかというような、御文に執われ、御仏智を踏みにじる謗法を犯しましたが、この御文の真義はそんなものではないのです。
大聖人様が末法万年の尽未来際に向かって、一切衆生の即身成仏を大慈大悲の上からお示しになった広宣流布の戒壇の御文であります。ですから我々はそれを深く拝し、広布への大前進をもって御仏智を実現させていただくというところに、即身成仏の上の尊い信心の姿があるということを申し上げておきます。
(2)一期弘法付嘱書(弘安5年9月)
日蓮一期(いちご)の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり。就中(なかんずく)我が門弟等此の状を守るべきなり。『一期弘法付嘱書』(弘5・9)○ この「事の戒法」という語は、前の御文にもあり、またこの御文にもありますけれども、これは要するに一切衆生即身成仏、広宣流布の実現が事の戒法ということであります。したがって、そこにおいて「本門寺の戒壇を建立」することが大事であります。
「国主此の法を立てらるれば」とありますように、この法を立てるのは国ではなく、国主がこの法を立てるとはっきり仰せですから、この建立の主体はあくまでも信心を持つ国主、いわゆる人にあるわけです。ですから、この戒壇のことを「国立戒壇」と表現してしてしまうと、これは国の機関が戒壇を建立するというかたちになってしまいますから、その意義が第二次的以下のことになり、この表現は適当ではないのであります。
国主について突き詰めた論議も、現在はあえて必要ではないと思います。「たヾをかせ給へ。梵天・帝釈等の御計らひとして、日本国一時に信ずる事あるべし」(御書1123ページ)の大宣言と、先の『三大秘法抄』の御文と、大聖人様が日興上人に与えられた『一期弘法付嘱書』の御文を信心の上から拝して、そこに時を待ち、またその国主建立の時を実現すべく、正法正師の正義を積極的に弘通していくことが大切であると思います。
そこで先ほども、申し上げましたように、戒壇の実践、本門戒の実践は、自行化他の折伏にあるのです。ですから皆さん方には、正法をしっかりと信じて御題目を唱えることにより、自らが即身成仏の利益を戴くことができるという確信を持って、自他共に救われていく折伏を成就し、常に広宣流布の前進を念じていくことを心からお祈りいたしまして、本日の私の講義を終了する次第であります。
体験発表 『6年の精進実り、母が御本尊を受持』
勝妙寺支部・田中悟史
私は、平成5年に妻の折伏で入信しました。そして平成13年、宗旨建立750年を目前にして、母と弟に御授戒を受けさせることができました。その後、平成14年・宗旨建立750年の30万総登山では全国輸送班の任務者にも登録し、一層折伏、信心活動が盛んになりました。このため、以前に比べて母のいる草津へ行く回数は減りましたが、電話やメールを使って、御報恩御講での御法話を母に伝えるようにしました。
30万総登山も中盤に差しかかり、私たちの登山予定日が近づいてきました。はじめに妻・子供たちと家族で御登山をさせていただきました。この年に生まれた次女は、妊娠7ヶ月目で破水し、「今、700グラムで出産すれば五体満足かどうかは判らない」と言われましたが、御住職・野村光照御尊師のお計らいで御法主上人猊下より御秘符を戴くことが叶い、それから2ヶ月間お腹の中で育ち、1700グラムと小さいながらも何の障害もなく生まれてきました。妙法の計り知れない功徳力に守られ、本門戒壇の大御本尊様への感謝の気持ちを込めた御登山となりました。そして、3人の子供たちへの法統相続をお誓いしました。
その翌週には、念願だった母と弟との御登山を迎えました。往路の道中では総本山の話や宗旨建立の話など、今までなかなか落ち着いて話すことのできなかった話をしながら、高ぶる気持ちを抑え、総本山へ向かいました。母と弟は総本山に着くなり目に飛び込んできた三門の大きさにびっくりしていました。客殿では、御法主上人猊下の御入場に合わせて、母と弟が自然に手を合わせ、照れながらではありましたが題目を真剣に唱えていました。その光景を見て、近いうちに必ず御本尊様を御下付戴ける日が来ると確信しました。
青年部の育成誓う
平成15年「広布大願の年」、私は支部の青年部長として、4名しかいなかった青年部員と、お寺に参詣していない部員宅への家庭訪問を粘り強くやっていこうと約束しました。日曜日はもちろんのこと、平日の夜も仕事で疲れた体に鞭打ち、地道に家庭訪問をしました。また部員宅での勤行会も取り入れて、とにかく皆で目標に向かって前進を開始しました。
家庭訪問で青年の心を動かすのは容易なことではありません。目先の欲に惑わされ、約束した時間にいなかったり、話を濁されたり、両親が出てきて子供をかばい、居留守を使われたり、ひどいときには罵声を浴びせられたこともありました。こんな状況のまま、月日だけが過ぎていき、気がつけば平成15年は残りわずかとなっていました。
この年は、男子3名・女子2名の増員、折伏成果はゼロという情けない有様で、講中の皆さんに申し訳なく、悔しくてたまりませんでした。残りの日々を、御本尊様の前で敗因について考え、反省することに費やしました。いくら唱題しても答えは出ません。青年部長を降りたいとも思いました。しかし、「一切を開く鍵は唱題行にある」との御法主上人猊下の御指南を思い出して、真剣な題目を唱えました。すると以前、御住職が青年部に向けておっしゃっていた「人間的成長なくして技術的進歩はない」との御指導を思い出し、わずかではありましたが光が見え始めたのです。
その後、家の掃除をしていて出てきた私たちの結婚式のビデオテープを子供たちと見ていると、御住職が祝辞として、知恩報恩のこと、父母の恩・衆生の恩・国主の恩・三宝の恩についてお話しされていました。私はそのなかで、父母の恩と衆生の恩のところが気になり、何度も繰り返し聞いて、自分に足りないことを痛感しました。30万総登山に母と弟を無事に参加させた安堵感が魔となり折伏行を怠ったこと、周りの人たちに対してもっと気遣ってあげられなかったことの報いだと知りました。「四恩を知って実践するのが人の道であって、知らないのは畜生である」と教えてくださったのだと思いました。私は、必ず目標を達成すると御本尊様にお誓いして、平成16年「破邪顕正の年」を迎えました。
1月の青年部会において、みんなに「成功の秘訣は才能ではない。重要なのは、正しくやる方法を知り、常に正しくやり続けることだよ」と伝え、昨年以上の家庭訪問を実施しました。また、各自が、基本となる朝夕の勤行をしっかり行い、広布唱題会、御報恩御講に参加して、気持ちを一つにしていこうと誓い合いました。
春季総登山会、夏期講習会と忙しい日々が続きましたが、皆、若々しく活動を行い、今何をすべきかという自覚も現れてきました。そうして私の母への御本尊御下付が一日も早く叶うようにと、環境を作り出してくれました。私は、部員一同に感謝し、本気になって活動しました。
母の仕事は、国立療養所栗生楽生園の看護婦長です。ここはハンセン病患者の療養所です。私は、母の仕事の忙しさを知りながら、母の目線に合わせてでなく、自分の都合でしか信心の話をしてこなかったことに気づいて、母の職場の話を聞いてみました。すると母の口から機関銃のように言葉が溢れ出し、なかなか止まりませんでした。私に足りなかった母への思いやりに気づかされ、今まで苦労をかけたことを申し訳なく感じ、また、母をいつもお世話してくれていた人たちに恩返しをしたいと思い、職場のこと、人間関係のこと、患者さんのことをたくさん聞きました。母が、一番気にかけていたのは、患者さんのことでした。そこで私は思い切って、「患者さんは身内からも縁を切られて寂しくないの、辛くないのかな」と問いかけると、「そう思っていても、顔にも口にも決して出さないよ」という返事でした。
早速、ハンセン病患者のことを必死に学びました。現在、全国に4200名の患者さんが療養中で、過去には凄(すさ)まじい偏見や差別を受け、長い間社会から隔離されていることも記されていました。私は、お金や名誉のためではなく、他人のために働いている母の偉大さを改めて実感しました。以前母から、患者さんの心の拠(よ)り所になっているのは、園内にある他宗の寺院だと聞いたこともありました。私は、患者さんの仏性を開花させるべく、必ず折伏しようと決心しました。
勝妙寺創立50周年まで残り1ヶ月と迫った11月頃、私はいよいよ、母が御本尊様を御下付戴きたいと言うまでは帰らないと自らを追い込み、片道2時間かけて草津へと向かいました。
母が仕事から帰宅するまでの間、私は、御本尊様を御安置できるように部室を整え、お仏壇を用意しました。そして、まだ何もないお仏壇に向かって、なぜか題目を唱えていました。母は帰ってくるなり「何をしているの」と言いました。御本尊様を御安置するために、部室を掃除していたのだと言いますと、「お前がそこまで御本尊様を信じているのであれば、お母さんも信じて、お守りしていくよ」と言ってくれたのです。私は、あっさりと承諾した母に向かって、ただ呆然とお仏壇を抱えながら、涙をこらえていました。
さらに母は、「今まで御先祖様に申し訳ないことをしてきたんだな。柴山のお爺ちゃん(妻の祖父)も、私がお寺に行くことを望んでいるんだろうね」と、決意を固めていました。折伏は簡単そうに見えて難しく、心底から相手を救いたいと願わなければ、絶対に成就できないと思い、尊い仏道修行の大切さを学びました。
家に帰ってすぐに、義父である柴山地方部長に結果を報告すると、たいへん喜んでくれました。また、御住職に報告したときには、「よくやった。最後まで気を抜くなよ」との言葉の後、満面の笑みでさらに喜んでくださいました。また、今回決意したハンセン病患者への折伏の話を申し上げてみると、「患者さんとよく対話していくなかで、住職の話が聞きたいというのであれば行きましょう」と言ってくださいました。
6年越しの念願叶う
創立50周年を迎える2日前の12月13日、母は無事に御本尊様を御下付戴き、翌日には義理の母と一緒に草津へ行って御入仏も無事に終えることができました。
私は、母親を折伏するのに6年という歳月をかけて精進してきました。今まで講中の人たちに助けてもらってスタートラインに立った私ですが、これで本当の折伏行が始まったと実感して本年を迎えた矢先の先月、信心においても私生活においても一番信頼でき、入信以来私を実の弟のように見ていてくれた支部の柳沢総務部長の突然の死去で、私の気持ちは崩れました。母を折伏できたと報告した時も、我が事のように喜んでくれた頼もしい先輩と、これから一緒に歩めない悔しさに、涙が溢れ出ました。柳沢総務は、私に「正義顕揚750年に向けて、人口は確実に減少し、さらに高齢化が進み、邪宗教が蔓延(はびこ)るなかでの厳しい折伏活動となるが、困難な時代を闘い抜くには、必死になって学ぶこと、智慧を磨くこと、そして、目の前にある尊い仏道修行をしていかなくてはだめだ。決してあきらめるな。信じ続けろ」と教えてくれていました。私は、この言葉を胸に、多くの人を折伏して救っていくことが一番の供養になると思い、一層の精進を約束しました。
昨年は、母への折伏が成就し、青年部員は男女合わせて12名増員して20数名になり、充実した年でした。これからも、朝夕の勤行は子供たちと一緒に行(おこな)って法統相続をし、御法主上人猊下御指南の「一人が一人の折伏」を実践して、活躍する法華講員をめざして前進することをお誓いします。
※今号の原稿は昭倫寺支部の若山さんの御協力で掲載致しました。