 |
| 伝わる肖像画を元に再現。元の絵がかなり傷んでいて見づらく、だいぶ想像で補ってます。 |
 |
| 伝わる肖像画を元に再現。元の絵がかなり傷んでいて見づらく、だいぶ想像で補ってます。 |
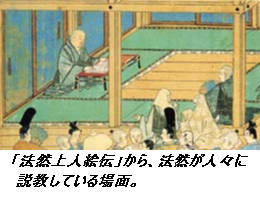 そういう中で文治二年(1186年、そ
の3年後という説もあります)に行われたいわゆる「大
原談義」は各宗派の著名な僧を相手にした論議で、ここで法然は末法の世といわれるこの時勢において、専修念仏こそが万人に適合
する教えであると説いて来聴者たちの共感を得、法然の存在と教えは庶民のみならず上級僧侶や貴族、武士にも広まって行きました。
そういう中で文治二年(1186年、そ
の3年後という説もあります)に行われたいわゆる「大
原談義」は各宗派の著名な僧を相手にした論議で、ここで法然は末法の世といわれるこの時勢において、専修念仏こそが万人に適合
する教えであると説いて来聴者たちの共感を得、法然の存在と教えは庶民のみならず上級僧侶や貴族、武士にも広まって行きました。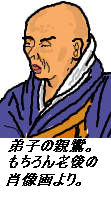 出家の門弟としてはまず、ともに叡空の元で学んでいて弟弟子といった方がいい信空、
さらには西山系の祖になる証
空、現在の浄土宗の主流となる鎮西派の祖となった弁長、
そして入門は建仁元年(1201年)と比較的遅めでしたが、浄土真宗の宗祖として後年の知名度が高くなった親鸞等
がいます。
出家の門弟としてはまず、ともに叡空の元で学んでいて弟弟子といった方がいい信空、
さらには西山系の祖になる証
空、現在の浄土宗の主流となる鎮西派の祖となった弁長、
そして入門は建仁元年(1201年)と比較的遅めでしたが、浄土真宗の宗祖として後年の知名度が高くなった親鸞等
がいます。 1月23日には「念仏の肝要について一筆賜り形見としたい」という門弟の源智の
求めで「一枚起請文」とよばれる遺戒を書い
ています。全部書くと大変なので(浄土宗
のHPで全文を読めます)一部だけ意訳しますが「観念の念仏でなく、学問して悟った念仏でもなく、極楽往生
のためには念仏を唱えて疑いなく往生すると思って申す他に別の仔細はない。いろんな考えや修行は称名で往生することに含まれるけど、他に余計な奥義なんか
知ろうとすれば二尊の憐みにはずれ、本願の救いから洩れるだろう。念仏を信じる人はどんなに勉強していても自分を愚鈍の身になし、智者のような高慢な振る
舞いをしないで一向に念仏しなさい」という内容で、専修念仏の教義を実にシンプルな形でまとめたものとなっており、どういう人
たちを教化の対象とすべきかをよくあらわしています。
1月23日には「念仏の肝要について一筆賜り形見としたい」という門弟の源智の
求めで「一枚起請文」とよばれる遺戒を書い
ています。全部書くと大変なので(浄土宗
のHPで全文を読めます)一部だけ意訳しますが「観念の念仏でなく、学問して悟った念仏でもなく、極楽往生
のためには念仏を唱えて疑いなく往生すると思って申す他に別の仔細はない。いろんな考えや修行は称名で往生することに含まれるけど、他に余計な奥義なんか
知ろうとすれば二尊の憐みにはずれ、本願の救いから洩れるだろう。念仏を信じる人はどんなに勉強していても自分を愚鈍の身になし、智者のような高慢な振る
舞いをしないで一向に念仏しなさい」という内容で、専修念仏の教義を実にシンプルな形でまとめたものとなっており、どういう人
たちを教化の対象とすべきかをよくあらわしています。