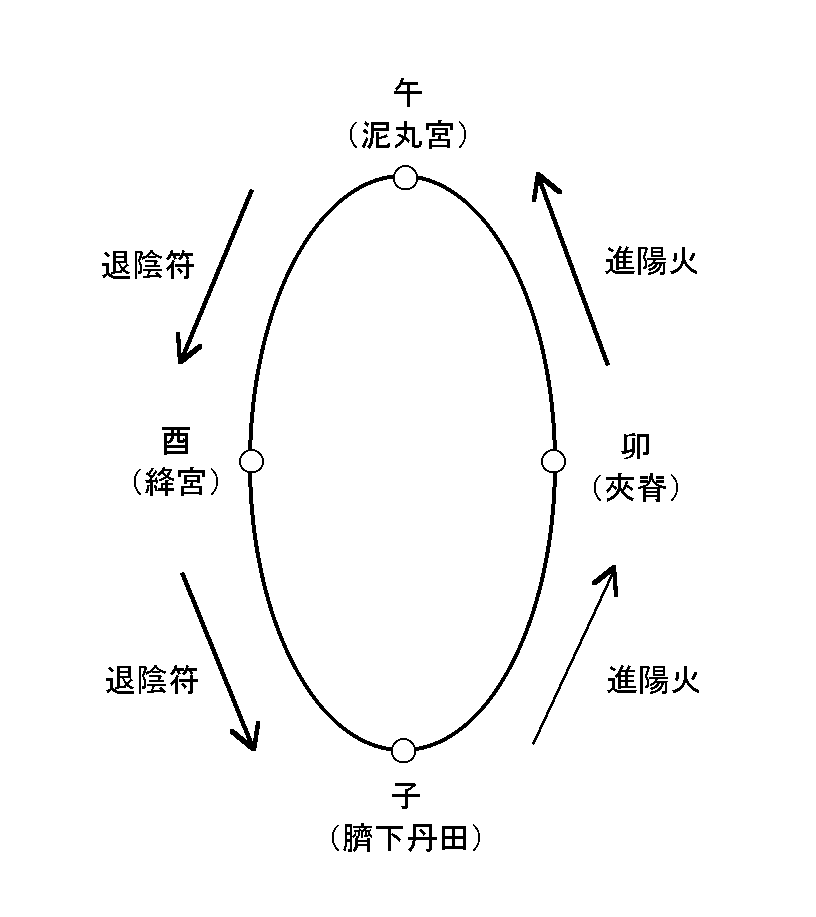
築基参証 第一篇 築基の原理
第3章 火候
許進忠 撰述
虞陽子 査定
神坂雲太郎 訳
凝神とは、普通真意で観照すること、すなわち心神を働かせて内面へと意識を凝らすという意味である。仙学では元神はその働きにより火と呼
ばれ、そのため凝神のまたの名を用火ともいう。
用火の説明をする前に、まず「火」の意味について四つに分けて説明する。
以上、火の概念を分析してきたが、次に用火の方法について説明しよう。
小周天のやり方とは、実際昔の人の導引や吐納の術にとてもよく似ており、ちっとも作用しないなどというものではない。ただ、それを行うにあ
たっては規則にそわねばならず、軽挙妄動してはならないだけなのである。小周天の修練には、文火と武火を替えたり組み合わせて用いることがあ
るが、つまりこれは、火候上の過不足による弊害を避けようとしているのである。
武火の意味とは、簡単にいえば心を集中することに尽きる。人の心とは、平素からすべて外へと向いているものであり、いつも体と同じ所にある
というわけではない。仙道を行う者は、心が外へと向かうと、身体がもともと備えている精気神を損ね、体が衰えるようになるということを認めて
いる。そこで、精気神が損なわれるのを防ぎ、日々にこれを益していかねばならないのだが、その唯一の方法がこれなのである。すなわち、外へと
向かう心を体の内側へと回収し、隠蔵するのである。そうすれば、体は心意により省みられることになり、ゆっくりと陽気を生むことができるよう
になるのである。
柳華陽曰く、「修行に熟達すると、座ったり横になっている時、不意に突然陽が生ずることがある。廻光返照し、炁穴に神を凝らし、一息ごとに
根へ帰する(訳者注:「帰根」の出典は『老子』。柳華陽は丹田などの根源的な竅へ意識をかける意に用いる)。このように神と気が交わろうとし
てまだ交わっていない時は、神を凝らしながら、綿々と絶やさぬように息をしようとしなくてはならない。これを武火という。」
また曰く、「武火とは、息を使って炁を取る方法である。また、炁は生まれると下へ向かい、ひとりでに逆行して上へは向かわない。もしこれに
逆らって、その源に帰そうとするには、呼吸によって招き取るのでなければ、その炉(訳者注:
柳華陽の『金仙証論』「危険説」では、炉を丹田と説明している。)へ炁を戻すことはできない。」
また曰く、「呼吸とは、すなわち元炁を採って巡らせる方法であり、緩やかに呼吸するものを文火といい、きつく呼吸するものを武火という。」
黄元吉曰く、「文火と武火の火候は、意識のあるなしの区別だけである。」
また曰く、「そもそもどうやって武火をするのか。何時するのか。最初にそれを行う時は、神がまだ凝っておらず、息も調っておらず、神と気の
二つは交わっていない。この時には、いくぶん意識をきつくかけねばならないのであって、すなわち、息を数えることで時を計ること、これが武火
である。」
李涵虚曰く、「心がたいへん散漫になると冷える。その自然な状態を守ろうと努力するのが武火である。」
文火の意味とは、簡単にいえば心をゆったりさせることに尽きる。人の心を体の内側へ向けいったん観照すると、しばらくすればその「真意」の
度合いは次第にうすれてしまい、わずかに「凡意」が残るばかりである。こうした「凡意」は陽気の役には立たないのであって、まさしく陽気へ影
響を与えるのは、「真意」に他ならないのである。このため、この段階に至るときには心をやすらかにする必要があるが、いったん「凡意」を澄ま
せさえすれば、同時に陽気も温養という素晴らしい効用へと至ることができる。
柳華陽曰く、「文火とは、吹嘘によって養うことである。(訳者注:
吹嘘とは、一説には文息とほぼ同義とする。柳華陽の『金仙証論』「危険説」では後天の気であり、神と炁(先天の気)が動かない状態とする。ま
た、吹嘘に対するものが闔闢で、一説には武息とほぼ同義とする。同じく「危険説」では、前天後天の二気が元関の中で応じ合って動く、あるいは
神と炁が不動の間に動くと表現される。)」
また曰く、「文火とは、神と炁がそれぞれ定まって動かないことを意味する。……さて、動かないことについては語ったが、また文火というのは
どういうことか。これを考えてみると、神と炁は動かないとはいえ、呼吸の気は、吹嘘が綿々と続くことを意味する。昔の人は呼吸を語り温養を
語ったが、これは神と炁が定まり、吹嘘をするという意味である。また、火は風を吸うことによって冷めてしまわず、薬は溶け暖かくなる。」
また曰く、「神と炁が交わってしまうと、陽炁は定まってしまい、また息を忘れ心を忘れて文火でこれを養わなくてはならない。」
また曰く、「これに意識をかけて温養することを文火という。しかし、交媾(訳者注:
神と炁が交わること)や周天の時でないならば、文火の方法を使って時間に従い養するわけだが、また煉己の修行でもこの方法を用いる。」
黄元吉曰く、「神がようやく凝り、気がようやく調って、神炁がおおよそ相交わるに及んでもまだ熟さないなら、文火を使って固済(訳者注:
もと外丹の用語。反応釜[鼎器]を密封することで、固際とも書く。ここでは、内丹的に陽気を漏らさず煉ること)しなくてはならない。意識はお
およそゆったりとして、それ以前にたびたび行っていたように必死に意識をかけるのでない。これがすなわち文火である。」
李涵虚曰く、「神を働かせずに呼吸をやすらかにして、主として自然にする。意識が非常にきついと燃え上がるので、つとめてその自然な状態に
任そうとするのが、文火である。」
静坐と呼吸の関係は極めて密接であり、呼吸の問題に触れない仙道書はない。火候の運用とは、主として風と火という二つの事項である。火と
は真意・元神であり、風とは呼吸である。呼吸をしなければ人は生きていくことができないし、修練も進めようがない。これで分かる通り、呼吸を
理解するということは、まことにとても必要なのである。
呼吸の分類には、外呼吸と内呼吸の二種類がある。では、外呼吸と内呼吸の範囲について一つずつ説明しよう。
1. 外呼吸
外呼吸は、体外呼吸ともいわれ、鼻の穴から空気を出し入れすることを指していわれる。この種の呼吸は、また次のように分けられる。
| (1) | 胸式呼吸 : また凡息ともいい、一般の人の正常な呼吸のことである。呼吸の時、肺の部分を膨らましたりへこましたりするも ので、訓練なしにできる。 |
| (2) | 腹式呼吸 : 因是子(訳者注: 本名、蒋維喬。『因是子静坐法』『続因是子静坐法』を著す。)は、腹式呼吸を自然呼吸という。この種の呼吸は、息を吸うとき腹部が外に膨れ、息を吐くとき 腹部が収縮する。やや胸式呼吸よりいい作用がある。 |
| (3) | 逆呼吸 : 因是子は逆呼吸を正呼吸といい、完全に腹式呼吸と反対である。息を吸うとき腹部は収縮し、息を吐くとき腹部は外へ膨れる。これは比較的特殊な呼吸で、普 通の人にとって訓練するのは難しく、また往々にして弊害が発生する。 |
2. 内呼吸
内呼吸は体内呼吸ともいわれ、口や鼻を経ない呼吸で、体内に自然に存在して生命を維持するある呼吸作用を指す。このような呼吸は外呼吸に
基礎を置き、その後日々の修練により完成するものである。この呼吸は、仙道を修行する時必ず通る過程であり、また鉱石を熱して金を取り出すに
は不可欠でもある。人の生死は、完全に呼吸に支配されている。人の体が母親の体の中から携えてきた一点の元陽は、人が元来持つ生の素なのであ
り、外界のどのような物質であれ完全にそれに取って代わったり、補ったりすることはできない。(仙学には、天元・地元の方法もあるが、現在残
念なことにあまり知られていない。)そのため、この人が元来持っている生の素が使い終わってしまったその日に、この生命も終りを迎えるのであ
る。この生命の個体の現象は、生産業の中の炭鉱業のように、人が燃料をいったん採掘するとただ減っていくばかりで、やがてまったくなくなって
しまい、仙道家の変換の方法以外では、人工的に再び作り出すことはできないのである。
小薬を得ることこそ、築基でせねばならないことである。築基の意義は、破れて漏れている身体をもう一度新たに補充するということであり、陽
気を旺盛にして小薬を採ることができてこそ、完成とみなせると説く。この小薬を得ることができて、はじめて体は十六歳のような純陽の体になれ
る。これは、身体のすでに消耗した生の素に対して、仙学の原理と秘訣を使って、再生・再造させることでなされる。こうした再生・再造の能力
は、内呼吸の作用の下で完成される。
内呼吸によってどうして長生きができるかという理由は、以上のようなわけであるが、今一度内呼吸についてその程度を考察して、分析を加える
と次のようになる。
| (1) | 武息 : 火には、文武の区別がある。風と火が同じように用いられるという理由のために、風にも
また軽重の区別がある。このため、息もまた文武の区別があるのであり、こうして武息と文息の名称が生まれた。いわゆる武息とは、
強くてきつい呼吸のことである。武息は、呼吸の長短によって三種類の異なる方法と効用がある。 吐く息と吸う息が同じ長さの時: 子時の場所で用いられる武火、また意識をかける時にも用いることができる。 吐く息が長く吸う息が短い時: 退陰符の時に用いられる武火。 吐く息が短く吸う息が長い時: 進陽火の時に用いられる武火。 |
| (2) | 文息 : 綿々と微妙かつ自由自在に、吸う息と吐く息の長さが等しく、軽くわずかに呼吸をして、 沐浴の時に用いる。 |
| (3) | 真息 : 静坐する際、あたかも呼吸器があっても用いないがごとく、口や鼻から息をしない。しか し、静坐の時以外は、普通の人と同じである。真息が始めて現れたとき、胸と腹に光明を感じるが(仙学を修練している過程で生まれ る内外の情景はすべて、感覚であって知覚ではない。さもなくば、それは必ず真境ではなく幻境に属すので、おおいに注意しなくては ならない。)、この光明は次第に現れる人といきなり現れる人がいる。光明が始まったばかりの時には、雲霧が胸腹部一帯を覆うよう だが、やがてゆっくりと「雲霧」はなくなってただ一面明るくなり、気が口や鼻と臍の下の間を上や下へと往き来する。しばらくし て、気の動きはさらに旺盛になり、口や鼻と臍の下の間を往来していた気は次第に見えなくなる。修行がここまで至ると、真息の段階 まで到達したということである。この真息の情景は大静ではあるが、まだ定に入ることはできず、もう一度修行に勤しまなければその 望みはない。真息の主要な効用は、「煉精化気」にある。 |
| (4) | 胎息 : 真息の修養を成し遂げて、はじめて大薬を採ることができる。大薬を採る前後には、定に 入る(定には昏定と正定の区別がある)ことができるある段階があり、これが必ず何日か続くのだが、大薬を採ることができるか、修 行が本物かどうか見て判断しなくてはならない。胎息の状態は、初めに必ず定に入らなければ決してあり得ない。さもなくば、まだ単 に大静である。胎息の修行では、最終的にはいつでも「口や鼻から呼吸をしない」ぐらいまで達することができる。始まって三ヶ月の 間は、二つの気が臍のまわりの空しい場所で微かに振動しているのが感じられるだけである。四、五ヶ月になると、二つの気は両方と も落ち着いて、食欲はすでに途絶えてしまっている。六、七ヶ月になると、心が生滅(訳注: 因縁により生じ滅すること)することはなく、完全に眠るということがない(眠っても意識はなくならない)。八、九ヶ月になると、あらゆる経脈が止まってし まい、再び動き出すことはない。十ヶ月になると、胎が完全なものとなる。精気神が一つになった「神」が、大いなる定に帰するので ある。これには、必ず六通の効験がある。この六通とは、漏尽通、天眼通、天耳通、宿命通、他心通、神境通である(訳者注: 六神通ともいい、行が進んだ結果得られる神秘的な能力を指す。おおよそ、漏尽通は一切の煩悩がなくなり自由自在になること、天眼通はあらゆる物を見通す能 力、天耳通はあらゆる音が聞き取れるようになる能力、宿命通は人々や自分の宿世行業を知る能力、他心通は人々の考えていることを 見通す能力、神境通は様々な境地を往来できることを指す)。しかし、以上は胎息の過程にすぎないのであり、胎息に至る主要な作用 こそ「煉気化神」である。 |
内呼吸の段階は一段一段と深くなっていくものであるが、まず武息・文息について、真息・胎息の前に議論したのは、それらが内呼吸の初歩の 訓練で、必ず通らなくてはならない調息の修行に基づいているため、一緒に論及したのである。これは武息と文息を説明することとはまったく違っ て純粋に内呼吸であり、ただそれらは内呼吸への訓練の過程であって、内呼吸が極めて深い源であることを表しているにすぎない。
静坐の最大の目標は、先天に通じて、後天の肉体を直接先天の気でうるおすことである。これからも分かる通り、「杳冥を鑚(うが)つ」とい
うことは重要な事柄であり、築基が完成するかどうかは、完全にこれにかかっている。杳冥を鑽つことができて、初めて陽気が生じる。その後は陽
気が日に日に積もり集まっていっぱいになると、関竅を開くことができない心配はなく、汚れを洗い落とし、気の質を変えるという目的が達成され
るのである。
筆者は、多くの静坐をしている友人を見、全員がすでに陽気を発生させて煉っているのだが、残念ながら各々の体験は異なるため、陽気の開関の
様子も異なることが多い。これらの異なる開関の様子を一度まとめて分析してみたところ、一般的な様子は大体三種類に収まった。
1. 開関の時、陽気がまっすぐに昇降する
ある一定の時間静坐すると、陽気が臍下丹田から現れて、丹田は一時引っ張り回されて止むことがない。また、これを経ると陽気の力はさらに
増し、右左に揺らめき、前後にぶつかり、上下に乱れ動き始める。こういった情景に出会ったならば、これこそ李涵虚が説くところの「開関展竅」
の段階なのである。陽気が臍の下で活動してかなり経つと、開関の情景が現れる。このとき、陽気は尾閭に集中して通り抜け始め、陽気が尾閭を通
過して一度道を切り開くと、自然とある経穴を捜し出すことができ、陽気を通過させる。陽気が尾閭を通過し後は、続いてまた夾脊へと上ることが
できる。陽気が夾脊を通過した後、玉枕へ真っ直ぐに上ることができ、最後に泥丸宮の中をぶらぶらする。
陽気は、泥丸宮の中にしばらく止まった後、印堂へ向かって降り、重楼を経て、絳宮へ下り、最後に臍下丹田に戻る。以上の陽気の開関の情景
は、真っ直ぐに督脈に沿って上っていき、再び任脈にしたがって降りてきて、辿った道筋は一直線となるというもので、これは正常な情景である。
この類いの開関の情景は、精の漏れた人に最もよく見られるものである。一般の人が開関に要する時間は、一定の標準があるわけではなく、それぞ
れの人の努力の具合や、体質、やり方を見なければ決められない。
2. 開関の時、辺り一面陽気が昇降する
ある一定の時間静坐すると、陽気が臍下丹田から現れて、丹田が暖まり、心地好く感じられる。陽気が臍の下を行ったり来りして揺れ動くの
は、展竅開関の兆しである。その時、陽気は次第に尾閭のあたりに集まる。これは、臍下丹田に陽気が十分集まった証しであり、かならず尾閭にか
ゆみやいたみ、とても大きな圧力、熱い流れが染み透り、並々ならない暖かさを感じる。この時、はじめて陽気が開関に達したと断定できるのであ
る。この関をいったん越えると、すぐ夾脊の辺りに熱い気が充満していると感じ、例え難いほど気が詰まって膨れ、全身が言い難いほど暖かくな
る。陽気が夾脊を越えると、腫れたような熱を感じるのが普通だが、その他にはいたみやかゆみを感じないのが最も多い。陽気が玉枕に到達した時
の開関の様子は、前の二つの関とは異なる。この関は比較的時間がかかり、また力を費やさねばならない関であり、この関を開いて通過した人は、
一般にどの人も、総じて他と比べて大変だという印象を持つ。というのも、精が漏れているいないにかかわらず、この関の辛さを述べるものが最も
多く、わずかでもいったんためらえば、関が開かないことが往々にして起こるからである。陽気が一度に玉枕を通り抜けると、必ずやだるくて痛い
ような感覚を持つが、こういった現象は何日かすると好転するだろう。陽気が玉枕を通り抜けると、次に泥丸宮へどっと押し寄せることがある。こ
の時、頭一帯がくらくらして、あつぼったく感じられる。このような現象は、陽気が泥丸宮へ進んだという証しである。この様な開関は、尾閭から
始まり、夾脊・玉枕を通過して、真っ直ぐ泥丸宮へ到達するのだが、すべて辺り一面の陽気が上っていき、平面を形成するようである。
陽気が泥丸宮でひとしきり変化すると、印堂に沿って重楼・絳宮に降りていき、臍下丹田へ戻る。この陽気の開関の様子は真っ直ぐ督脈に沿って
上り、再び任脈を経て降りていくのだが、陽気が通る経絡すべてにわたって辺り一面に広がる。これは、それでもいろいろ守るべきことに注意しな
くてはならないものの、よい種類のものと考えられ、精が漏れていない人か精が漏れてまだそれ程時間が経っていない人に最も多い。このような開
関の情景は正座を始めて七日経たないうちに完成し得るのが普通で、時間が短いものでは、初めて座って二三時間で開関することもある。これは、
胎児であった頃運行していた河車の道筋が、まだ塞がっていないことによる。しかし、まだこれまで督脈と任脈が開いていないのに、陽気が一面に
氾濫したからといって誤解し、いつも間違ったおなじ道を巡らせることはしてはならず、注意し区別しなくてはならない。
3. 開関の時、陽気が紆余曲折しながら昇降する
ある一定の間静坐すると、陽気が臍下丹田で活動し始め、尾閭へ進入して通り過ぎた後、陽気は夾脊の辺りで活動を開始する。経絡での陽気の
活動は、進んで上昇したり、迂回したりする。また玉枕に上がり、泥丸宮へ入る陽気もある。やはり、ここでもまた進まなくなることもある。いろ
いろな場合があり、一つにまとめられない。
陽気が泥丸宮に入ってしまうと、印堂に向かって下り、この印堂の一帯では普通の人はまだ感覚があるだろうが、恐らくその下の場所では感覚が
現れなくなってしまうだろう。言えることは、陽気が印堂にあっていくらか詰まって滞った感覚があるほかは、どれ程重楼をすぎて絳宮へ進もうと
も、まったく感じられなくなるということである。
このような開関の状態は精が漏れている人に最も多く、修行法が前の二種に比べて少し異なっていても当然である。もう一度開関に要する時間を
いうならば、前述の二種類の様子と比べて一般に時間がかかる。この種類の状態を修正するのは可能だが、すぐに修正しないならばしばらくは弊害
がなくても、後になって結局正果を達成することが困難になり、後悔せざるを得なくなるだろう。
静坐とは、この身体を使って実際に身体を健やかにする方法であり、修行にわずかな違いがあっても、その効果はすぐには異なって現れることは
ない。だが、その効果がないばかりか、もしも重大な間違いが起こると、逆に健康を損ねることだってあるのである。陽気が督脈を進んでいる時、
どうして迂回して進むことがあり得るのだろうか。これは、陽気がまだ十分でなかったり、間違ったやり方で気を運らせたり、功を急いたりするこ
とによるのであり、初めて陽気を運行させ、時間が分からないならば、ゆっくり行うよう注意しなくてはならず、運行させる時は時位(訳者注:
陽気を巡らせ温養する子・卯・午・酉などの場所。次節参照)での沐浴に注意して、元神を少したりとも陽気から離さないようにかけ続け、時位の
順番にしたがって一つずつ進んでいかねばならない。そのため、臍下丹田で陽気が真意を備え、遠くまで運行させようとしても、結局きちんと導く
ことができず、そのため迂回して進むという現象を免れないのである。
陽気が泥丸宮から印堂へ下っていく時に、どうして重楼・絳宮では感覚がなくなってしまうのだろうか。理解しなくてはならないのは、泥丸宮と
は精気が変化する重要な時位であり、まさに陽気が運行する十二時位の中で、最も重要な変化を起こす場所であるということである。一般の人が陽
気をここへ巡らせると、焦ってしまうことが多い。子・卯・午・酉のどれもが沐浴の場所であり、ひとしきり温養しなくてはならないことを分かっ
ておらず、すぐに陽気を任脈へと無理やり降ろしてしまうので、陽気はこの時位での準備が十分できていないのである。それゆえ、陽気がここへ運
行すると陽気の力が著しく弱まって、酷い場合には完全に消失してしまうのである。このため、もしこの理屈を分かっていなければ、陽気がいった
ん任脈に下ると、自然とどんな風に作用しているか感じられなくなってしまう。もともと任脈は督脈と違って、神経が通った通路でないということ
も主要な原因である。
図の子午卯酉の四つの時位のように、陽気を運行する時、この四箇所できちんと停火、停符、進火、退符をする必要がある。
| 静―――― | ↓ |
清浄にして無欲(訳者注: 原文は静篤。老子などにみえる語)を意味する。静座を始める 時には、まず文火でもって温養をして、文息で呼吸しなくてはならず、そうしてこそ陽気 が盛んになり得るのである。以上を静極とする。 |
|
| 動―――― | ↓ |
陽気の振動を意味する。ここでの様子は、清浄かつ無欲である状態であり、陽気が生 じる。この時、文火による温養を止めて、武火によって採取しなくてはならない。以上を 陽生とする。 |
|
| 子時位―― | | | | ↓ |
陽火を進めること[進陽火] : 火とは気のことであり、陽を使うために陽火という。陽
気 が生まれたら、これを子時という。陽気が生まれて盛んになり、活動を始めるわけだ が、これは時刻が固定していないので活子時というのである。この時には督脈に進め るために、やはり武火で臍下丹田の中の陽気を採取しなくてはならない。この時、火を 武火にして吸う時を武、吐く時を文にする。呼気は穏やかにしてその働きを作用させな いが、吸気は逆に陽気を進めるために用いるのである。以上、陽火を動とする。 |
|
| 卯時位―― | | | | ↓ |
陽火を停めること[停陽火] : この時には文火を使わねばならず、陽火をそのまま進 めてはいけないのであり、強弱をあらかじめ調節して、強すぎたり、弱すぎたりしてはな らない。この時、火を文火、息を文息にして温養し、いったん休憩しなくてはならない。 以上、陽火を静とする。 陽火は温養による休憩により、静止する。しばらくして活動の兆しが現れれば、その時 には武火を続行し、陰符を引き続いて上昇させてもよい。以上、陽火を動とする。 |
|
| 午時位―― | | | | | | | | | | | | | | ↓ |
陽火を停めること[停陽火] : 陽火がこの時位へ達したら、すぐに武火を止めて、文 火と文息を使わねばならない。すべきことは微かに神を凝らして泥丸宮を観照すること であり、呼吸は穏やかに自然にまかすことである。これが、文火温養の意味であり、ま た、陽火が一路上昇し、変化することなく慌ただしく任脈を下ったとしても、おそらく強す ぎるために弊害を起こして凡火(訳者注: 欲望などの世俗の感情)となってしまうだけだ ろう。それゆえ、午時位では文火・文息を行って、一度温養するべきである。この時位 では、卯と酉の二つの時位での温養の時間を足した分だけ温養するが、子時位よりは 少なくしてもよい。以上、陽火を静とする。 陰符を降ろすこと[退陰符] : 陽火が午時位に達したら、静止した状態を呈すが、しば らく後に一度温養すると、再び活動が始まり、印堂・重楼へ下るだけの勢いが生まれ る。これが一陰始萌(訳者注: 泥丸宮で陽気[陰符]が初めて生ずること)であり、陰符が 生まれるのは午時である。符とは気を指し、陰を用いるために陰符という。陰符が生ま れるとやがて活動を始め、活午時とも称されるが、この時、任脈を下へと降ろすため に、文火を武火に代えて、泥丸宮から下っていく陰符を煉らねばならない。この時、火 を武火として吐く時を武、吸う時を文にする。吸気は穏やかにしてその働きを作用させ ず、呼気は逆に陽気を降ろすため用いるのである。以上、陰符を動とする。 |
|
| 酉時位―― | | | | ↓ |
陰符を停めること[停陰符] : この時には文火を使わねばならず、陰符をそのまま降 ろしてはいけないのであり、やはりあらかじめの調節が必要である。この時、火を文 火、息を文息とすると、陰符は静止した状態を呈するが、温養して、いったん休憩しなく てはならない。以上、陰符を静とする。 陰符は温養による休憩により、静止する。しばらくして活動の兆しが現れれば、その時 には武火を続行し、陰符を引き続いて下降させてもよい。以上、陰符を動とする。 |
|
| 子時位―― | 陰符を停めること[停陰符] : 陰符が臍下丹田へ下って入れば、これを子時位とし、 また閏餘ともいう。この時、陰符の作用はもうなく、ただあるのは一塊の陽気だけで、臍 下丹田にとどまっている。陽気が静止すると文火でもって温養し、文息で呼吸するべき で、そうすると陽気はひとしきり十分に休むことができ、そうしてこそその後重ねて陽気 が生じ、勢いを回復することができるのである。以上、静極とする。 陽気がひとしきり温養を経ると、再び陽気が生じる。以上を陽生とする。 陽火を進めること[進陽火] : 陽気が生じると、これを子時とする。陽気が生まれて次 第に盛んになり活動を始めるわけだが、これを活子時とする。この時には、督脈に進 めるために再び武火で臍下丹田の陽気を採取しなくてはならない。この時、火を武火 にして吸気を武、吐気を文にする。この時は呼気を穏やかにしてその働きを作用させ ないが、吸気は逆に陽気を進めるために用いるのである。以上、陽火を動とする。 |
|
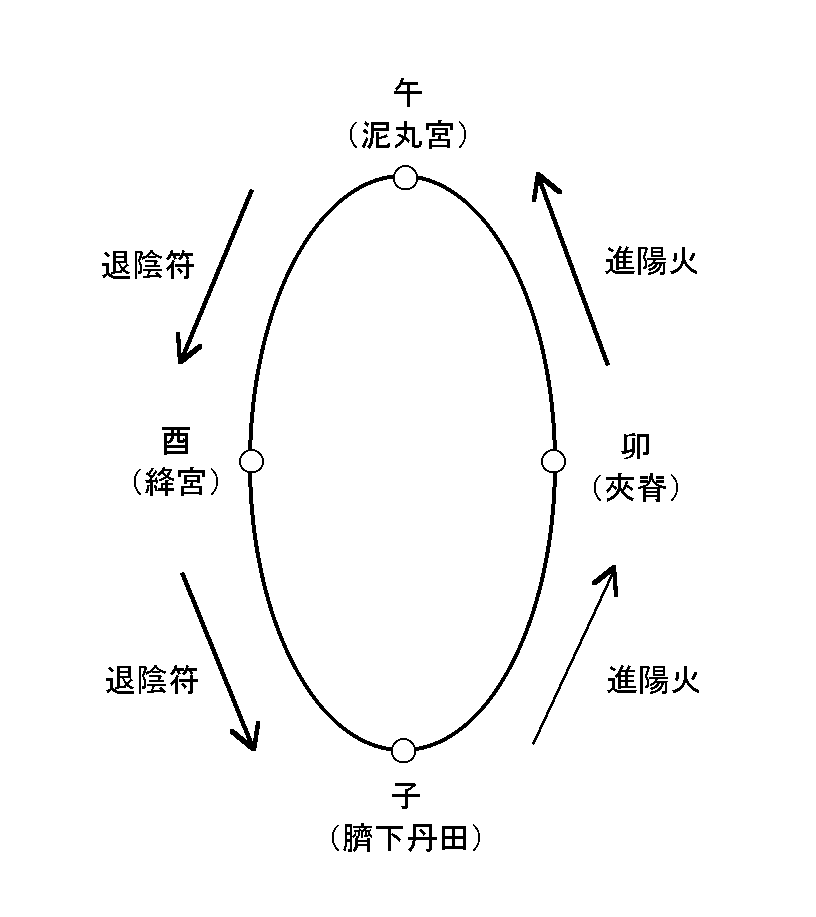
注 : 陽気が酉位(すなわち絳宮)に達して爽やかで愉快に感じるのは、酉時の証しである。陽気が卯位(す なわち夾脊)に達して温かく詰まって腫れたように感じるのは、卯時の証しである。
柳華陽曰く、「そもそも昇降する火は文武を兼ねて用いるので、柔から剛へと変わり、剛から柔へ変わり、剛と柔は丹道の妙旨であるというの
である。六陽を吸う気が入って上昇することを武というが、吐く気が回って定まることは文に属する。また、六陰を吐く気が退いて下っていくこと
を武といい、吸う気が進んで定まることは文に属する。それゆえに、時時に沐浴するとはこのことを指すというのである。」
これは、陽気が通る十二の時位ではどの時位もすべて文火と武火を兼ね備えているのであり、子・卯・午・酉の四時位の呼吸と火の強弱を調節す
ることにより陽気を穏やかに保つ外に、その他の八つの時位にもやはり文火と武火があって、同じように知らないうちに自然と変化を及ぼしている
ということを述べているのである。
陽気の運行の順序は、大体この通りであるが、ここで、陽気を運行させようとするとき、神と気がぴったり寄り添って進んでいくという原則につ
いて、説明を加えれば次のようになろう。
混然子曰く、「内側には天罡(訳者注:
次の斗柄とともに北斗七星の柄の部分のこと)が巡り行くことを隠し、外側には斗柄が移っていくことを用いる。」
柳華陽曰く、「冲虚は、『斗柄が外側を巡り、天心は常に存在する場所を離れない』と言っている。もし内側に天罡(訳者注:
原文ではこの箇所と次の箇所を天昰に作るが、柳華陽『金仙証論』風火経第六の註に従い、天罡に改める)を隠しても、外側に斗柄を移り行かせな
いならば、真炁が昇降することはない。もし外側に斗柄を移り行かせても、内側に天罡を隠さないならば、真種が結実することはない。」
また曰く、「周天の道筋は、およそ火を巡らせる時、神炁が必ずこの道を経て巡るのである。」
また曰く、「もし巡らせる気が通る道筋の外にうろつくならば、それは道を成さない。神がその炁を関知しなかったり、炁が神に伴うことができ
なかったりすると、空しく煉っても金丹はできない。守陽(訳者注:
伍冲虚のこと)はこういっている。『両方を互いに知っているという真意とは、このことである』と。」
また曰く、「天心を確立し、任脈と督脈に依拠する。」
また曰く、「総じて転法の時には、必ず真意を中宮に据えて、車軸の要として、これを巡らせることはない。」
また曰く、「一般に転法輪の時には(訳者注:
周天法を行う時。転法輪と同じ)、意と命は必ず任脈と督脈にしたがって進んでいくものである。意が進んでいっても命が着いていかなかったり、
命が進んでいっても意が伴わなければ、成就できないのである。」
陽火と陰符とは、もともとどちらも陽気であり、その働きに違いはなく、文字の上での違いがあるだけである。それでは、陽火とは何だろう
か。
李涵虚曰く、「この気というものは、名を壬鉛、後天の気といい、また陽火という。」
曹還陽曰く、「一般に進むものを進陽火という。」
また曰く、「また、陽を用いるものを火という。」
柳華陽曰く、「運火の時に、後天の気が進むと陽火という。」
これで分かる通り、陽火の意味は次の通りである。(1)小周天の煉精化気の作業には、子時位(一陽)にある陽気が上昇する作用があり、それ
を陽火という。(2)督脈を進んでいく陽気は、督脈が陽に属するため陽火という。(3)火は、陽気に他ならない。
進陽火のときには、二種類の呼吸を組み合わせなくては、その効果が生まれない。進陽火にとって組み合わせることが必要な二種類の呼吸のう
ち、呼吸の吸気の部分に重点がおかれる。進陽火の効果とは気を採取すること、つまり臍下丹田の陽気を採取することであり、督脈を経て泥丸宮に
至れば、「気質の変化」という作用を起こさせる。進陽火の時には、夾脊の一帯は暖かく感じられる。
では、陰符とは何だろうか。
曹還陽曰く、「一般に退くものを退陰符という。」
また曰く、「陰を用いるものを符という。」
柳華陽曰く、「火を運行させるときに、後天の気が上っていけば、それを陽火といい、後天の気が下っていけば、陰符という。」
『三皇玉訣』に曰く、「陰符とは、密かに合わせることである。天地の機を密かに合わせて、長生する根源をとって巡らせるゆえに、陰符という
のである。」
黄元吉曰く、「符とは陽気であり、陰を使うために陰符という。」
これから分かる通り、陰符の意味は次の通りである。(1)小周天の煉精化気の作業には午時位(一陰)まで運用した陽気が下降する作用があ
り、それを陰符という。(2)任脈を下っていく陽気は、任脈が陰に属するので陰符という。(3)符とは、陽気である。
退陰符のときには、二種類の呼吸を組み合わせなくては、その効果が生まれない。退陰符にとって組み合わせることが必要な二種類のうち、呼吸
の呼気の部分に重点がおかれる。退陰符の効用とは気を煉ること、すなわち、泥丸宮で煉った陽気を「気質の変化」という作用を完成させ、その後
任脈を経て臍下丹田まで下ろしていくことなのである。退陰符の時には、絳宮の辺りには爽やかな感覚がなくてはならない。
修行が日に日に進むと、陰符が泥丸宮から印堂・重楼の辺りまで下る時に、時としてある液体が分泌されて口に広がり、重楼を経て絳宮へ達する
のを感じることがあるかもしれない。しばらくすると、口に沸いた唾液は、だんだん甘くなる。陰符が降りていく後は、絳宮の一体で爽やかで愉快
に感じ、あたかもとても暑い日に冷たい水を体にかけるかのようである。同時に鼻は、モクセイやバラの香りなどのような香りをかぐことがある。
しかし、鼻の穴の間に特別に氷のような冷たさを感じ、まるで薄荷氷(訳者注:
ハッカエキスの結晶)を嗅いだときのようならば、神を凝らして(もう少し強く)内側に意識をかけねばならない。臍下丹田に、氷のように冷たい
状態が生じた時にも、上と同じ方法で処理しなくてはならない。
その後は、もっといろいろな情景があり、唾液や匂いが引き続いて生じることがあるが、どんな様子にもこだわらないことを原則にしなければ、
本物の効験にはありつけないのである。
栽接法の修行では、その過程が清浄法とはほとんど異なり、また修行法も流派によってそれぞれ違っている。次に列挙するのはその一方法であ
るが、比較してみたい。
栽接法を始める時は清浄法と同じだが、その次にやっと栽接法を使い、終わるときにはまた清浄法と同じである。二番目の栽接法の修行法は、二
種類の鼎器をうまく組み合わせることが必要とされる。この二種類の鼎器とは、内鼎と外鼎を指していっている。このため、一般に内鼎に発生する
火候を内火候と称し、外鼎に発生する火候を外火候というのである。
仙道書に曰く、「真気が長い間たまると、関竅は自ずと開く。」
また曰く、「その時泥丸は活発になり、腎気が上昇し、しばらくして鵲橋にはすばらしい香りがし、甘露が下降する。(訳者注:
内丹の理論によれば、人が生まれる前には督脈と任脈はつながっているものの、生まれ落ちた後は督脈と任脈は分断するとされる。この分断した箇
所をと鵲橋いい、上下の二箇所がある。ここでは、上の鵲橋の、印堂から鼻にかけての部位を指すと思われる。)」
また曰く、「外火候が極みに達すると、この時鼻から息を忙しく吸い、関を越える。訣にはこういっている。
| 垂簾閉兌目観頂 鼻引清風入金井 拳手縮脚似猿猴 明珠自上泥丸頂 |
(簾を垂れ兌[=七竅]を閉じ 目は頂きを観じ) (鼻は清風を引きて金井へ入れしめ) (手を拳[にぎ]り足を縮むること猿猴に似たれば) (明珠 自ずと泥丸の頂きに上らん) |
また曰く、「降薬活子時というのは、内腎から近い所に一点の真汞を巡らせ、薬を迎えて橋を渡る。これは、自分の身体が活子時だということ
である。」以上の引用は、すべて内火候を指していっている。
仙道書に曰く、「この上ない玉が荒んだ声を漏らし、鉛の鼎器が暖かである。これは降薬活子時である。」
また曰く、「上の橋が冷たくなって、薬が降りてしまうと、炉の中に火が発生して、沸き立つ湯の様に熱く、鉛の鼎器が暖かである。つまり、外
火候が極みに達したということである。」以上の引用は、外火候を指していっている。
ここで、栽接法の中のある方法と清浄法の修練の違いを比べると次ぎのようになるだろう。
この五つの段階では、栽接法を用いていて、環境的に問題が起これば、いつでも引き続いて清浄法の修行をすることができる。しかし、清浄法 に引き続いて栽接法の修行をしたいと思うならば剣を鋳ること[鋳剣]が必要で、さもなくば外鼎を扱うことはできない。また、栽接法は晩年の人 が修練するに適した方法であり、特にまだ精の漏れていない人や漏れていてもまだ日の浅い人にとってはふさわしくなく、清浄法をよしとするべき である。