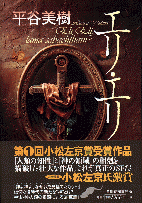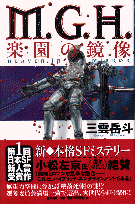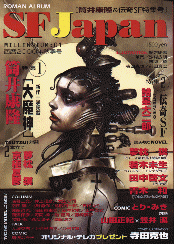『あふれた愛』☆☆☆☆ (天童荒太、集英社)
あの『永遠の仔』の著者の、待望の新作。が、これはミステリではない(『永遠の仔』だってミステリと言い切れない部分もあるのだが)。「愛」をテーマにした4つの中篇が収められている。
愛は凶器である。諸刃の刃である。強く愛すれば愛するほど、器からあふれたその愛は相手を傷つけ、わかりあえず、思いはすれ違う。こんなに深く愛しているのに…。最初の3作は、そういった痛い話である。あまりに優しすぎて、ゆえに繊細すぎて、自分の心を痛めつけてしまい、病んでしまう彼ら。このテーマは、『永遠の仔』にも若干通じるところがある。あれは児童虐待に傷つく子供というあまりにも悲惨で異常な話であったが、この話は大人の、もっと身近な、自分の隣で起きていそうな話である。まかり間違えば、自分もこの登場人物みたいになっていたかもしれない。そんな紙一重の危うさを秘めている。本当に人の心は危うい。ちょっとしたはずみで、ガラス細工のように砕けてしまう。
たとえば1作目の「とりあえず、愛」。私だって、この母親と同じく、高いベランダの上で生まれたばかりの娘を抱いていて、「ここで落っことしちゃったらどうしよう」といった想像をしたことは何度もある。のん気でアホな私はそんなことすぐ忘れるが、この登場人物の彼女はそんな残酷な想像をする自分が許せなかった。こんなに愛しい子に、時々恐ろしいことをやってしまいそうな衝動。そして、そんな妻を恐れ疑う夫。やがて徐々に悲劇は起こる。なぜ?どちらも、本当に家族を愛しているというのに。そこがまたなんとも痛い。
2作目の「うつろな恋人」は、ストレス・ケア・センターの入院患者の中年男性と、かつてそこの患者で、今はその近くの喫茶店で働く少女との愛とすれ違いである。
3作目の「やすらぎの香り」は、心に傷を持つ男女が、それでも精一杯支えあいながら生きていこうとする話。ふたりの一生懸命さと相手への思いやりが、けなげで胸を打つ。「がんばって」と心から応援してあげたくなる。きっと彼らなら、つらいことも乗り越えていけるだろうけど。
4作目の「喪われゆく君に」。これは泣ける。ただただ泣ける。というか、読んでいたらいつのまにか泣いていた。前の3作はどれも愛ゆえに相手を痛めてしまうというつらい話なのだが、これは違う。ただひたすらに聖母のような、温かさと優しさに満ち溢れた、相手をまあるく包み込むような愛情。しかも、もう喪われた人への愛情。深く深く、心に染みる物語である。天童荒太はこんなに優しい物語も書けるのか。驚き。(ワタクシ的にはこっち路線が好みだなあ)
よどみなく、流れるように読める文章の上手さはさすが。万人にお勧めしたい一冊。特に4作目は白眉の出来。この中篇を読むためだけでも買う価値がある。誰かを愛したことがある方、まだそういう相手にめぐりあっていない方、どちらも必読の傑作。天童荒太の「愛」、ぜひともご賞味あれ。暴力小説より、ずっとやさしい気持ちになれるよ。あったかいよ。
『海底密室』☆☆☆1/2(三雲岳斗、徳間デュアル文庫)
さみしい。読後、本を閉じてため息をついた。そんなにまで、ひとは孤独な存在なのだろうか。
『M.G.H.』(徳間書店)で日本SF新人賞を受賞した著者の、新作書き下ろしというふれこみ。読んだ感触も、『M.G.H.』によく似ている。あちらは、宇宙ステーションという密室での殺人だったが、今回は海底施設という密室での殺人と、シチュエーションも近いのだ。主人公の持つ端末の中に、擬似人格のようなものが存在する点もよく似ている。
しかしこの作品は、SF色はかなり薄い気がする。どちらかというと、森博嗣の理系本格ミステリに限りなく近い感じ。『M.G.H.』のトリックはまだSF的だったが、今回のトリックは(以下ネタバレなので略)だし。
深海4000メートルの海底実験施設《バブル》に、主人公のサイエンス雑誌記者、鷲見埼遊が取材に行くことになる。ここでは先日、職員が謎の自殺をとげていた。が、遊が到着するや、連続して殺人事件が発生する。しかも条件はすべて密室。いったい、この限られたメンバーの中の誰が犯人なのか?どういうトリックで?その動機は?
遊と、その古い友人である御堂健人の人格をそのまま入れた端末が事件を解決してゆく、という点ではSF的か。パソコンやネットに常日頃親しんでいる私のような者には、非常にすんなり受け入れられる設定である。ごくごく近い未来に、こういったことが実際に起きてもなんの不思議もない気がする(実際この小説の舞台は、ほんの数年先の近未来である)。夢物語でなく、今の日常のすぐ隣にありそうな話である。
ということは、この設定は非常に現実味を帯びているということだ。「連続殺人」といったものは別にして、だ。そもそのこの殺人からして、もとはといえば「現代人の孤独」が原因といえよう。人間同士のリアルなコミュニケーションが薄くなり、ネットやメールなどを通しての、バーチャルなコミュニケーションのほうが強くなってゆく。隣人よりむしろネットでつながってる友人のほうがずっと親しい、という状態に、あなたも心当たりはないだろうか。しかし、そこにはどこかぽっかりとした孤独がひそんではいないだろうか。
これはたとえば村上春樹の描く孤独とはまたちょっと違う。彼の孤独は、「こんなに近くにいても触れててもどこか淋しい、人間は結局ひとりだ」、というものなのだが、三雲岳斗は、「さまざまなツールにより、現代人におけるリアルとバーチャルの距離感は大きく変化した。近くの人が遠くなり、遠くの人が近くになった。でも、そこにはなんともいいようのない淋しさが存在しないか」と問うている。この静かな問いには、胸を突かれる。
話としては文句なくミステリなのだが、テーマのツボの突き方がSFという、実に稀有な一冊。「未来」というより、「今」を切り取った物語ではないか、と私には思えた。山田正紀の解説が絶妙。
『体は全部知っている』☆☆☆1/2(吉本ばなな、文芸春秋)
「体」をテーマにした短篇集。13の話が納められており、3つ以外は皆書き下ろしである。
吉本ばななって、こんなに淡白だったっけ?というのが正直な感想。昔の彼女の作品は、もっと鮮やかで華やかで、言いたいことがストレートに胸に飛び込んでくるような小説だった。イチゴショートのようにはっきりしていた(若かった、ということだろうか)。今の彼女は、懐石料理のお弁当のようだ。昆布だしがやさしい、あっさりとした口当たりの和食。それが少しずつじんわりと胸にしみてゆく、そんな感じを受けるのだ。
さすがに13話もあると出来のよしあしが若干あって、「ちょっとこれは唐突では?」と思う話もいくつかある。とはいえ、それでも全部読み進むうちに、徐々にどこか心の芯がほわほわっとほぐれていくのが快感で、最後には「まあ、これはこれでいいか」ということに落ち着くのだが。
私が特に好きなのをピックアップすると、「田所さん」「ミイラ」「サウンド・オブ・サイレンス」。「田所さん」は傑作。心がささくれだって、ゆとりを失った時に読んでみたい一篇だ。用もない(というか社員でもなんでもない)のに、毎日出社してきて、ちょっとしたみなの手伝いをしていくおじいいさん。「ビルの谷間の小さな花壇」みたいに、ちょっとそこに存在するだけで、周りの人の心をなごませる田所さん。そんな彼に向ける著者のまなざしの何とやさしく温かなことよ。誰かにやさしくするということは、要するに自分の心が豊かに満ち足りた気持ちになることなのだな、とふと思う。
「ミイラ」はかつて、20代になる直前だった「私」が、近所の顔見知りの青年宅に数日軟禁された体験という、ちょっとぎょっとするような、ものすごく奇妙な話である。が、妙に感性のみが鮮やかに研ぎ澄まされた話で、惹きつけられた。
「サウンド・オブ・サイレンス」は、昔の著者の作品を思い出させるような話。実は自分は養女だった、といった血縁関係の話だ。でも昔のように直球的に書くのではなく、わざと輪郭をぼやかした感じに書いており、ああ、著者の上を時間が通り過ぎたのだな、と思った。そして私の上にも。
昔のイチゴショートも好きだったが、こういう淡白な和食も悪くない。何よりカラダに心にやさしい、そんな気にさせられた一冊。
『少年たちの密室』☆☆☆1/2(古処誠二、講談社ノベルス)
むむむ、と腕組みをしてうなりたくなるような本格ミステリの傑作。うまい。推理の展開の仕方、話の運び、そして何よりキャラの存在感。小説の人物に、これほど強烈に暗い怒りを覚えたのは、ひさびさである。読了した直後は、本当にムカついてムカついて、この怒りをどこにぶつければいいのだ!!と身もだえするほどであった。架空の人物に怒ってもしょうがないのだが。
もちろん架空の話だが、9月某日、東海地震が発生し、たまたまマンションの地下駐車場にいた6人の高校生と担任教師1名が、そこに閉じ込められてしまう。が、その6人の間には、緊迫した憎悪が渦巻いていた。あるひとりの少年を中心として。この少年が、不良などというカワイイものではないのだ。低俗で性根の腐りきった悪党。弱いものを狙い、暴力にモノをいわせる、最低の、人間のクズ。
そんな不快な汗がじっとり出るような緊迫した暗闇の中、一人の少年が瓦礫で頭を打って死亡する。事故か?殺人か?殺人だとしたら、この中の誰がどうやって?
駆け引きと推理が交錯し、それが実に周到に組み立てられていて圧巻。ミステリの部分については、もう何も言うことなし。彼らと共に埃と冷や汗と喉の渇きを感じつつ、じっくり推理し、犯人を当ててみてほしい。たいがいのミステリ読みには、満足の出来だということは保証する。
ああそれにしても!人間の暗い感情を描くのがなんてうまいのだろう、この著者。この吐き気のするような悪意。自分の欲望しか見えない、利己的な人間。思い出しても虫唾が走る。主人公のやりきれない思いが痛い。どうか、こんな話が小説の中だけであることを祈るのみだ。
『神狩り』☆☆☆☆(山田正紀、ハルキ文庫)
あまりにも有名な、山田正紀衝撃のデビュー作。もう25年近く前の作品である。が、現在読んでも全く遜色ない。私にとっては、山田正紀初挑戦である。
結論。山田正紀のファンになりました(笑)。いやあ、これでデビュー作ですか!当時、どれほど驚かれたかが容易に想像できる出来栄えである。なにしろ文章が抜群にうまい。華がある。ハードボイルド系のカッコよさ。ほんのワンセンテンスでも、うーむとうなりたくなるくらい、うまいのだ。
若き天才学者、島津は、あるきっかけで《古代文字》を研究することになる。ところがこれが研究すればするほど、わからないというシロモノであった。これは人間の英知をはるかに超えている。そう、まさに神の言葉…?これを解読すれば世界を牛耳れるという野望に取り付かれたある組織に彼は拉致され、研究を強要される。やがて、彼はそこを脱出した後、数人の仲間と「神」の正体を暴くべく戦いを始めた…。
地球すべてを、邪悪な神の意思が覆っており、人間は所詮どこまでいっても釈迦の手のひらから出られない孫悟空、という発想は本格SFとして申し分ない、というのはすでに既読の皆様の評価の通りでしょう。神という、ともするとマユツバ的な荒唐無稽の大ウソの大風呂敷を広げているのに、思わず知らず納得させられてしまう。この圧倒的説得力はどこからくるのだろう。読者を自らの論理に巻き込むというテクニックの、実に優れた作家ではないだろうか。このSF的発想、読者をぐいぐい引き込む文章のテンポのよさ、そして主人公の青年が仲間を失いつつもひとりで戦いを挑んでゆく、というまさに一匹狼的ハードボイルドストーリー、この3拍子の意気が絶妙。
惜しまれるのは、さあこれから、というところで話が終ってるところだが(泣)、この大風呂敷の広げ方に成功しているのだから、SFとしてはオッケーなのでしょう。ワタクシ的には、起承転結の結まで読んでみたかったところだが。
堪能させて頂きました。山田正紀、おそるべし。他の作品も、おいおい読んでゆきたい。