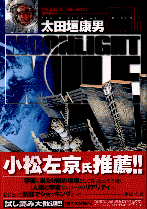『センセイの鞄』☆☆☆☆☆ 川上弘美 平凡社(01.6月刊)
ううむ、いいっ!☆5つの満点!文句なく、今年の大収穫!『椰子・椰子』(川上弘美、新潮文庫)を読んで以来、どうも川上弘美はよさそうだぞ、と思った予感がこの1冊で確実になった。ワタクシ的に、今年発見した作家ベスト1。本書は今年のワタクシ的ベスト3には入るであろう。
もうすでにあちこちで絶賛されているし、内容も紹介されているので今更だが、これは30代後半のツキコさんという女性と、そのかつての高校時代の国語教師であった、もう「おじいちゃん」と呼ばれるようなお年の「センセイ」との、なんともほわほわした恋愛小説である。駅前の一杯飲み屋で隣あわせになったところから、この物語は始まる。
ああ、恋愛って結局相手との距離の取り方が一番大事だったんだな、と強く思わされた。彼らは、決して相手の心やテリトリーにずかずか土足で踏み込まない。普通(かどうかは疑問かもしれないが)、誰かを好きになったりすると、もう相手のことを知りたくて知りたくて、そのひとの領域に踏み込んで陣地を確保したくて、いてもたってもいられなくなる。
が、彼らときたら、もうじれったいほど、相手との距離をキープしつづける。その距離の取り方が絶妙にいいのだ。つかず離れず、自分の生活をそのままのテンポで保ちながら、でも心ではいつも相手のことを視野の片隅に入れていて。で、ちょろっとひととき触れ合って、また自分の日常に戻っていく。あくまでマイペースを崩さず、相手のペースもかく乱せず、そんな感じ。今の世の中からみたら、おとぎ話みたいな恋愛だ。
お互いに、相手に異性の友人めいたのができると、これまた妙な感じに嫉妬してみたり。このツキコさんと小島孝との微妙な関係の章も実はとても好き。どちらにも簡単に転べそうな危うさとか、でもそう軽くいかないとことか、本当は大人なんだけど中身はやっぱりまだどこか子供だと思ってるとことか。ああ、なんかすごくよくわかる、この感じ。
そうやって時間をかけて、すこうしずつすこうしずつ、ツキコさんとセンセイの距離は縮まっていく。ふたりのやることはどっかユーモラスでわけわかんなくて、でも恋愛中の行動って端から見るとこんなヘンテコなもんだよなあ、なんてふふっと笑ったりして。
そう、恋愛って結局、その相手との距離を測りつつそろそろと手さぐりで進んでる、そこの過程、その時間こそが一番楽しいのだ。このふたりは、その微妙なところを、がつがつせずにゆっくりゆっくりと歩んでいる。そのテンポと相手への気遣いや優しさが、この物語を読む者をなんとも幸福にさせるのだ。と同時に、ぐぐっと切なさがこみあげる。
いとしくていとしくて、どうしようもなく切なくて、ぎゅっと抱きしめたくなるような、そんな1冊。
『おめでとう』☆☆☆☆ 川上弘美 新潮社(00.11月刊)
川上弘美にハマったよ第2弾(笑)。これは12章の短篇集。
『椰子・椰子』と『センセイの鞄』をたして2で割ったら、こんな味わいの短篇集ができるのではなかろうか。どこかシュールでヘンテコ、ユーモラスでいてなお恋愛小説っぽかったりするという(笑)。
どの話もほわっとあったかい、できたてのおまんじゅうみたいな淡い甘さ。う〜ん、どれもいいのだが、ワタクシ的にはあまりリアルなものより、『椰子・椰子』度の高い話のほうが好き。つまり、日常からぶっ飛んでる率が高めの話、ですか(笑)。
自分と同じ男にふられた気弱な幽霊にとりつかれる話「どうにもこうにも」とか、奇妙な女二人旅の「春の虫」とか、恋人が桜の木のうろに住みついてしまう「運命の恋人」とかが好きな路線。でも一番すごいのは表題作の「おめでとう」だ。驚愕。最高傑作。
川上弘美は短篇の名手でもあったのだなあ。
『いとしい』☆☆☆1/2 川上弘美 幻冬舎文庫(00.8月刊)
川上弘美にハマったよ第3弾(笑)。これは長篇恋愛小説。
実は昔一度読んだことがあったのだが、あのときには気がつかなかったことがいっぱいわかって興味深かった(単に忘れてただけかもしれないが)。当時は、なんだか登場人物が複雑に入り組んだわけわからんヘンな話、というもやもやした印象しかなかったが、今読んでみると複雑でもなんでもない。これはマリエとユリエというふたり姉妹の、それぞれの恋を描いたものだったんだ。もちろん、それ以外のひとたちの恋も書かれてるけど、スポットライトが当たってるのはなんとも対照的な、この2種類の恋だけだったんだ。
ふたりはそれぞれ、紅郎とオトヒコさんという相手を見つけるのだが、その思いはどちらもだんだんズレが生じてくる。で、やっぱり話は川上弘美らしいシュールさになっていくのだが(オトヒコさんの書き方がすごい)、どちらも相手を強く愛しているのにそうなってしまうところがなんとも切ない。
さらには紅郎の気持ち、鈴本鈴郎、ミドリ子、チダさんの気持ちも、一見妙ではあるが、実は一途で切ないのだ。互いの強い愛が交錯しあい、からみあう。
強烈なようで淡白なような、濃厚でいてさらっとしたような。この小説には名状しがたい空気が漂っている。わからない人には全然理解できない話かもしれない。でも、わかる人にはこれがなんだか、すぐ理解してもらえるであろう。ここに書かれてるのは、さまざまな愛と、その終わりなのだ。
『西の魔女が死んだ』☆☆☆☆ 梨木香歩 新潮文庫(01.8月刊)
西の魔女が死んだ。魔女とは、中学生の少女、まいの母方のおばあちゃんのことだ。2年前、ちょっとしたことで登校拒否になったまいは、ひと月あまりをこのおばあちゃんの家で過ごしたのだ。まいの回想から、この物語は始まる。
心に傷を負ったまいを、なぐさめるでもなんでもなく、ゆっくりとおばあちゃんはその傷を癒していく。その方法は、地に足のついた生活をさせることだった。森や畑をゆっくり歩き、ジャムを作り、早寝早起きをする。そういう、ごくごくシンプルな、でも生き物としての人間らしい生活だ。おばあちゃんは物知りで、生活におけるちょっとした知恵を何でも知っている。さらには死についてなどの、人生の知恵も。それらの知恵や知識、さらには超能力(というと大げさだけど、第六感かな)をもった人間を、おばあちゃんは「魔女」と呼ぶ。
このおばあちゃんの、教えるでもない教えがなんといっても秀逸だ。おばあちゃんは、自分の歩いてきた道に絶対的自信がある。それは自分でなんでもやってきた、という確かな手ごたえだ。このふたりは、どことなく、ハイジとおじいさんを連想させる。まいは、ここで少しずつ自分の潜在的に持っていた生きる力に気づき始める。ひとつひとつ、自分の力でクリアしていくことで、彼女は自信を取り戻すのだ。
ゲンジさんに象徴される、現実の汚濁みたいなものへの、まいの嫌悪感もよくわかる。それから逃げることなく、全てをあるがままとりこもうとするおばあちゃん。そこでちょっとすれ違ってしまったふたり。でも、おばあちゃんの器はやっぱりずっと大きかったのだった。
祖母と孫娘の心の交流に、ほっくりと心あたたまる。このおばあちゃんは実に素敵な「大人」だ。こういう大人が近くにいる子供は、本当に幸福だと思う。読後感が爽やかな、とてもいい物語だ。このカントリーな生活をいいなあと思うと同時に、自分のことを思わず考えてしまった。私の立場は、まいの母親とよく似てる。それがいいかどうかはともかくとして。
『泣く大人』☆☆☆☆ 江國香織(世界文化社、01.7月刊)
以前出したエッセイは『泣かない子供』だった。そして、今回のタイトルは『泣く大人』。彼女は、「泣く大人」になったと自ら語っている。泣くことができる大人になれてうれしい、とも。そう、たぶん彼女は泣きたいときも笑いたいときも、いつでも自分の気持ちに正直に生きているんだと思う。そんな彼女の日々の生活や、ちょっと昔の留学時代の話、男友達について、読書ノートなどがつづられている。
どこを切っても、すべて江國さんらしいエッセイだ。彼女は、小説とエッセイとのギャップがあまりない作家だと思う。彼女は、自分にとって何が幸福で何がそうでないかをよく把握している。というか、その選別に対して実に真摯だ。そして、好きなものにはとことん愛を語ってくれる。レーズンバターでも、ハンカチでも、男性でも、本でも。彼女の、好きなものについて語っている文章がとても好きだ。こちらにまで幸せな気持ちが伝染するから。しかも、そこここに彼女らしいセンスのよさが光る。なんとも心地よいエッセイ。
そして、その幸福な文章の奥底にある、かすかな切なさが、何より私を江國香織から惹きつけて離さないのである。