八、知的生産性向上のノウハウ
(1) 考えるとはどういうことか
問題解決のプロセスは何度も繰り返すように思考のプロセスそのものですが、本章では、その思考の生産性を挙げるためのノウハウを紹介いたします。まず、考えるとはどういうことかから、考えてみます。通常、何かを深く考えようといいますと、目を閉じるとか、天井を見上げるなどして、一生懸命考えようとしますが、それらのほとんどの場合は、自分の頭の中の引き出しから、過去に蓄積された情報で使えるものはないかと探しているに過ぎないといってよいでしょう。
つまり、考えているように見えますが、単に過去のことを思い出しているに過ぎないのです。「こういうアイデアはどうだろうか、やっぱり無理かな。では、これではどうだろうか。これもダメだ」と言うように、頭の中でアイデアが次々に浮かんでは消え、浮かんでは消えていきます。つまり、限られたアイデアで堂々巡りしているのです。
既に頭の中に存在するものを知識と呼ぶことができますが、ここでのべたような知識を引っ張り出すことが、考えることではありません。
考えるとは、既存の知識をベースに新しい価値を生み出すことです。つまり、知識と知識を組み合わせて新しい発想を得ることです。
(2) 強制発想法
知的生産性を挙げる方法の一つとして、強制発想法があります。強制発想法といいますと、何やらもっともらしく聞こえますが、平たく言えば、無理やり考えさせることです。本書では、最低十の問題挙げなさい、ミニマム五十の実施手順を考えなさい、といったことが頻繁に出てきますが、意見やアイデアの数を指定して、それを強制します。強制的に指定の数のアイデアを出させることから、強制発想法と言います。ただ、それだけのことです。しかし、この一見単純そうな方法は、かなり有効です。リードする側が数不足を容認すると言う妥協さえしなければ、何かしら出てくるものです。無理やり出させるのですから。もちろん使えないものも出てきますが、複数メンバーでこれをやれば、さまになってくるから不思議です。難しいことは何もないのです、とにかく一度試してみることをお勧めします。
これは、数多く出せは、何か使えるものがでてきます。つまり、「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」から行うのではありません。数多く列挙させれば、具体的に考えざるを得ないからです。問題も対策も具体的でなければ使い物になりません。
味の素の稲森俊介社長も「組織の活性化の最も重要な要素は、物事を変える力であり、そのポイントは、漠然とした目標ではなく、それを細分化する能力だ」と述べていますが(「日経ビジネス」1996年5月13日号)、まさに、細分化することによって具体性を持たせるのです。
このことは、問題点の検討、対策案の検討の両方に対してあてはまります。まず、問題点を挙げる局面を想定してみます。前述したように、「営業力が無い」と言う問題の出し方では問題提起になっていません。しかし、「営業マンの商品知識が不足している」「営業のマネジメント・システムが無い」というように、もう少し具体的に挙げてほしいと口をすっぱく繰り返しても、相変わらず抽象的な問題提起がなされるのが普通です。
そして、抽象的なレベルで考えるものですから、各人から提起される問題点は数が少ないのです。一般的に五つ、六つでてくればよいほうで、ひどい場合には、三つくらいになってしまいます。三つと言う大くくりのレベルで考えれば、各人の考えることに、そう大きな違いはありませんから、皆が出す問題が重複してしまい、たとえ二十人が問題提起しても、重複を削った後に残った問題点は五つしかないということになってしまいます。
そこで、重要となるのが、ただ単に「問題点を挙げてくれ」というのではありません、「このテーマに関して各人最低、十個ずつ出してくれ」というように、提起する問題の数を指定してしまうことです。漠然と考えている時には三つしか出てこなかったものを、無理やり十個出させるものですから、皆、苦労しますが、その過程で問題点は細分化され、具体的になってきます。
さらに、対策も同様に、できる限り細分化して、具体的に列挙することがポイントです。とくに、先の「営業力が無い」という問題点に対応させていえば、「営業力を強化する」といったような、問題点を裏返しにしたような表現がよく出てきますが、これでは小学生の答えです。読者には、私が極端な例を挙げているように思えるかもしれませんが、そうではありません、一流会社においてすら希なことではないのです。
また、このバリエーションとして、問題点の表現などの字数を制限するという方法もあります。これは、問題定義の際には、非常に有効です。たとえば、四十字以上六十字まで、というように指定すると、抽象的過ぎる表現もでてきようがありませんし、複数の問題点が一つの文章に表現されて混乱を招くことも避けられます。
このようなことに気を使わずに、ただ問題点を出させると、五~六字の見出しのような表現から、だらだらと何を言いたいのか分からないような長い文章までが出てきて、整理に苦労するばかりでなく、場合によっては、ほとんど使いものにならなくなります。
(3) 五分間メモの重要性
これは、発言前に五分間でよいですから、メモをして考えなさい! ということです。たとえば、会社の会議で衆知を集めようとする場合などに非常に有効です。
私は、マスコミのインタビューを受ける場合にも、できるだけぶっつけ本番を避け、事前に話すことをメモするようにしています。これは、たとえ五分間の準備であっても、話す内容の深みがまったく違ってくるのです。
非常に頭の回転の速い一部の天才的な人には、その必要は無いかもしれませんが、一般には、他の人の話しを聞きながら考える、あるいは、問われて準備なしに即答するのは、想像以上に難しいのです。自分はそのようなことは必要ないと思われる読者の皆さんもだまされたと思って一度試してみてください。知的生産性が驚くほど上がるはずです。
この五分間メモが知的生産性の向上に役立つのには、他にも理由があります。一つは、暗算ではなく筆算で考えることの効果です。この筆算の効果は非常に重要なことなので、また改めて詳述いたします。 他の一つは連想効果です。これは、会議の場合にとくに有効です。事前に多少でも考えていますがゆえに、他人の発言を聞いて連想したり、的確な反論ができるようになるからです。
要するに、人の意見を聞く準備が整っているわけです。したがって、意見を求める会議の場合には、先の強制発想法と結び付けて、「これこれのテーマについて、皆さんのお知恵を拝借いたします。ついては、十分間時間を差し上げるので、最低十項目を事前にメモして抱きたい」とやるのです。これまでとは、かなり違った会議になること請け合いです。
◆戻る(4) アイデア出しと評価は分けて行え
このことは、これまでも、問題解決時の留意点の一つとして、たびたび触れてきましたが、重要なことなので、改めて、そのポイントを説明します。 まず、思考には、拡散型思考と収束型思考があるといわれます。前者はあらゆる方向に思考をめぐらし、考えを発展させるものであり、後者は逆に拡散した情報を少数に、あるいは一点に向けて絞り込んでいくものです。
したがって、両者は、頭脳の使い分け方がまったく異なり、同時にやろうとすると、かえって思考の生産性が落ちてしまいます。
前者の拡散性思考は、平たく言えば「アイデア出し」であり、後者の収束型思考は「評価」であるといってよいのです。つまり、アイデア出しと評価は同時に行ってはならないのです。
六、で紹介したMBS(マネジメント・ブレーン・ストーミング)でも、アイデア創出のステップとその評価のステップは明確に分けています。
ところが、人間はなまじ器用なゆえに、あるいは、早く結論を導きたいために、ややもするとこの二つを同時にやろうとしてしまいます。
一つのアイデアを思いついては、すぐに評価を行い「これではダメです。では、このアイデアはどうだろうか」と、アイデアのはしごをして、結局行き詰まってしまうことが多いのです。
もちろん、このような即効的な思考でことがすむ場合もあります。比較的構造が簡単な問題の場合などです。
したがって、そのような場合には、いちいち二つのステップをわけずともよいが、複雑な問題や、大勢で議論する場合には、多少、面倒に思えても、拡散と収束の二つの思考をわけた手順を踏むことが必要です。まさに「急がば回れれです。理論的にも証明されているし、私の経験でも、間違いないと断言できることなので、問題解決の際にはぜひ意識していただきたいものです。
また、このことは前述のように、アイデア出しに限らず、情報収集と集めた情報の評価という局面でも、そのままあてはまります。自分は頭がよいと思っている人々は、いわゆるガセネタに近いものまで集めるのは非効率だと思い込み、失敗することが多いので注意が肝要ですが、その情報収集が失敗であったことにすら気がつかないことが多いのです。
しかし、そのような情報収集は一種のフィルターを通して行うことと同じですし、そのフィルターは既成概念と偏見によって作られたいるのです。
したがって、事態が過去の知識や経験では解きほぐせないような複雑な、あるいは新しい問題である場合には、使いものにはなりません。
現実に、CONSULTANTの世界でも、自分の頭を過信して最初の仮説にこだわりすぎ、挫折を余儀なくされた人はすくなくありません。
(5) まず全体像を描け
簡単な問題解決であれば、「全体像から云々」ということは考える必要もありませんが、構造が複雑になってくると、解決案のマスタープランを作り、それから詳細プランに入ります。という手順が必要になります。このこと自体は当然のことで、改めて述べるほどではないでしょうが、、ここで強調したいのは、この詳細プランも最初から完璧なものを作ろうと考えてはいけないということです。
イメージを持っていただくために、問題解決のケースではありませんが、本を書きます場合を例にとって、説明します。本を書きますときは、まず目次を考えることから入ります。目次は本の全体構成を示すものですし、前記のマスタープランにあたります。重要なのは、その次のステップをどうするかです。
なれていない、あるいは生真面目な人は、最初の章からきちんと、文章を推敲しながら書こうとします。しかし、それでは、時間がかかって何時までたっても完成しないか、途中でいやになってギブアップしてしまうのがオチです。「一つ一つ着実に固めながら進もう」という考え方は堅実に見えますが、実は挫折の元だといってよいのです。
原稿書きの例でもうしますと、最大のポイントは、ラフでも、いい加減でもよいので、まず最後の章まで一応書き通してしまうことです。最初の原稿などは、誤字脱字はもちろん、論理的に支離滅裂で、文章にすらなっていないところだけです。それこそ人に見せられたものではありません。したがって、それほど第一稿は雑なものです。それで、不完全でもひと通り書き上げてから、始めて細部の詰めに入っていくのです。
では、なぜ、このような方法が生産性が高いといえるのかといいますと、精神的な安心感です。
いくら不完全であっても、全体像が描けていますと、締め切りまでいくら時間が無いといった状況になっても、いざとなれば、多少の手直しで提出できます。品質について文句を言われるかもしれませんが、まったくアウトプットが出ないという最悪の惨めな思いは回避できるという安心感です。
安心感があると余裕ができますと、手直しにさいしても、よい発想が浮かんだり、忘れていたことを思い出すという言うメリットが生じます。なんといっても、焦りがあったのでは、よいものはできないのです。
また、ラフではあっても、目次レベルでは見えてこなかった全体像が頭に入ってくるので、著述の中の相互矛盾も避けられます。
全体像が頭に入っているために矛盾を避けられます。思考に一貫性を持たせることができることのプラスは大きい。思考に一貫性があれば、それが間違っていると気がついた場合に、修正も比較的に容易です。しかし、一貫性の無いストーリー、つまり支離滅裂であれば、修正すら容易ではありません。
すこし、問題解決というテーマから離れるかもしれませんが、参考までにご紹介しますと、新規事業の企画も、ごく簡単な、たとえば、一日くらいで書ける範囲であっても、全体シナリオを書きます、書かないで、その戦略の一貫性がずいぶんと異なってくるものです。 これらの事柄で、全体像を早めに描くことの重要性のイメージは掴んでいただけたと思いますが、まったく同様のことですが、問題の解決案のシナリオ作成にもあてはまるのです。
◆戻る(6) 考えるのは時間数よりも頻度
考える生産性は時間ではありません、頻度で決まるということも重要です。難しい問題に直面したとき、一度に十時間を費やすして考えるのと、毎日二時間ずつ五日間考えるのとでは、同じ十時間でも、後者のほうが圧倒的に効果が高くなります。考える頻度を増やすと、考えていないときでも、その問題に関連する情報や刺激に敏感に反応するアンテナが頭の中に形成されますから、ほとんど無意識のなかで脳が働き続けます。
これは、会議の生産性を高める上でも重要なノウハウです。結論のなかなかでないテーマを延々と五時間も六時間も続けるよりも、二時間くらいで打ち切って翌日なりに改めて開催したほうが結果はよいことが多いのです。
何も考えていない人の頭の中に突然、天の声のごとくヒントがひらめくということではなく、普段、一生懸命考え抜いているからこそ思考が醸成され、何かのきっかけでよい発想が出てくるのです。単なる思いつきとひらめきの大きな違いは、ここにあるといっても言い過ぎではありません。 ◆戻る(7) 暗算でなく筆算で考えよ
ここ十年来、エクセレント・カンパニー、あるいは「よい会社」という言葉がビジネスのキーワードの一つになっています。ちなみに、私の経験から来る「エクセレント・カンパニー」の共通項は、次のようなものです。- ビジネスのKFSをしっかり押さえています。
- 細かいように見えることも徹底してやりぬく風土がある
- 創意工夫を尊重し、そのためのインセンティブを導入しています。
- 十分な権限委譲がなされています。
- 暗算ではなく、筆算で考える癖がついています。
- 信賞必罰がハッキリしています。
- 管理部門が現場部門に対して強すぎない。
これは、単に「人間の記憶はあてにならないから、できるだけメモをしましょう」という程度のものではありません。うまく使えば、知的生産性を挙げるのにすばらしい効果を発揮します。この章の冒頭に述べましたように、考えているつもりでも、いつの間にか思考の堂々巡りに陥っていることは多いのですが、筆算で考えれば、そのようなことも防ぐことができます。
人間の頭脳はコンピューターとは比べ物にならないすばらしい力を持っていますが、短時間での計算能力や、いっぺんに考えることのできるキャパシティーは限られています。その限られたキャパシティーのなかでの少ない情報で考えようとするのですから、堂々めぐりになるのです。
コンピューターは、いろいろなことができる力を持っているものの、CPU(中央演算装置)の記憶容量が少ないために、あまり多くのことをさせようとするとハングオーバー(コンピューターが情報を処理しきれずにストップしてしまうこと)してしまいます。このような場合にはコンピューターでは外部記憶装置を活用しますが、人間も同じようにすればよいのです。
つまり、自分のアイデア、発想、情報のすべてを頭の中に記憶しておくような無理はしないで、外部記憶装置とも言える紙やホワイトボードにないったん書き出しておくのです。そうすれば、また新しい情報をインプットするだけのキャパシティーが頭の中に生まれ、紙という外部記憶装置に記憶させた情報は、目というインターフェースを通して必要に応じて再び脳に取り入れることができます。
その結果、頭の中の情報とアタマの外に記憶させた情報とを結び付けて、新たな発想を生み出すことが可能になるのです。
この「暗算より筆算」は、会議にも当てはまります。つまり、ホワイトボードをフルに活用すればよいのです。会議の場合には、みなの目に見えるようにすることによって誤解がなくなるという利点もあり、会議の生産性が挙がることは間違いありません。
したがって、私は自分だけで考える場合も、まず紙に書き出しながら筆算で考えるように心がけていますし、若い人たちに対しては、「頭でなく、手足で考えろ」と指導しています。
「手で」は「まず書いてみろ」ということでありますし、「足で」は「机上で考えるのではなく、事実を捕まえに行け」という意味になります。
(8) 最新の情報技術で理想像を描く
これは、いわゆる「デザイン・アプローチ」の一つです。会社の制度なり、システムなりを考える場合、現状の問題を解決しようというスタンスで積み上げ的に案を構築していく方法と、現状を無視して、白紙のゼロベースから、いきなり理想像を描くデザイン・アプローチの二つの方法があることは、ご存知のことと思います。しかし、デザイン・アプローチと口では簡単に言えますが、現実のとり組みは難しく、これまでは、せいぜい他社の成功例をベースに考えるのが関の山でありました。それが、コンピューターを駆使した情報技術(IT=インフォメーション・テクノロジー)の進歩により、その様相が変わってきました。今や、パソコンのネットワークやインターネットをうまく活用すれば、今までは不可能であったことが、それも昔とは比較にならないほどの低いコストで実現できる時代となっています。
そのため、世の中で最先端を言っているといわれるITを自社に適用したら何ができるかを考えることは、必ずしも非現実的なことではなくなってきます。つまり、以前であれば、このようなアプローチをとっても、コストがかかりすぎて現実的ではなかったのが、今はそうではありません。
何も手がかりがないところで理想像を描けといっても難しいですが、具体的な情報技術という手がかりがあると、格段に理想像のイメージが描きやすくなって、思考の生産性があがります。
たとえば、今、インターネットの技術を社内に業務に活用するイントラネットが話題になっていますが、そのイントラネットを自社の営業活動にフルに活用したら、どのような姿になるかを思い描くのです。
もちろん、その描いた像がそのまま目指すべき「あるべき姿」になることは少なくないでしょう。しかし、現状にとらわれない視点から発想しますので、思わぬヒントも出てきます。したがって、少しでも情報技術がからむ可能性のある問題には、最初のステップから、最先端の情報技術に詳しい人を参加させておくとよいのです。
◆戻る九、解決案を成果に結び付けるには
(1) 重要な手順計画
問題の解決案が「決めればすみ」という単純なものでなければ、解決案の詰め、あるいは実施のための手順計画を立てなければなりません。ところが、解決案が出たところで安心してしまい、その先に進まないことは珍しいことではありません。
◆実施手順計画のない計画は計画ではありません。たとえば、毎年威勢のよい年度予算が立てられるものの、達成できたためしがないという会社があります。そのような結末になる原因の大半が、ゴールは決めたものの、それにいたる道筋の計画がないことにあります。目標という意味でのプランがあっても、目標までの地図にあたる具体的なプログラムがなければ、掛け声だけに終わってしまいます。
複雑な問題になれば、問題の掘り下げをして、すぐ解決案が出てくるというほど簡単ではないため、最初は、せいぜい構想計画を立てるにとどまり、本当の解決策はプロジェクトを組んで検討するというスタイルになるでしょう。このような場合には、まさにいかに具体的な詳細手順計画が立てられるかで勝負が決まります。
ところが、一般には、この手順計画がきちんと立てられません。手順計画を立てようといっても、七つか八つのステップを書いておしまいにしてしまいますが、それでは、各ステップに進むたびに、そのステップ自体をどう進めるかの計画を立てることになるので、先がよく見えないまま進まなければならず、いつ完了するかも定かでない上に、効率も悪いのです。しかし、これでもよい方であって、それでもできずに、それこそ行き当たりばったりのプロジェクト推進になってしまうことが圧倒的に多くなります。
繰り返して言いますが、解決手順を如何に細かく計画できるかが勝負なのです。したがって、私は、どんなプロジェクトでも、ミニマム五十ステップは考えるようにしています。
◆ミニマム五十ステップの手順計画を作れ。もちろん厳密に言えば、ミニマムの数はプロジェクトによって変わってきますが、ミニマムというのは、、図35に示した例をイメージしてほしいのです。同図は、事務機器の発売計画を例に取ったものです。この図から、ある程度見当がつくと思いますが、少し複雑になれば五十ではとても足りません。しかし、慣れないうちはやむを得ないでしょう。
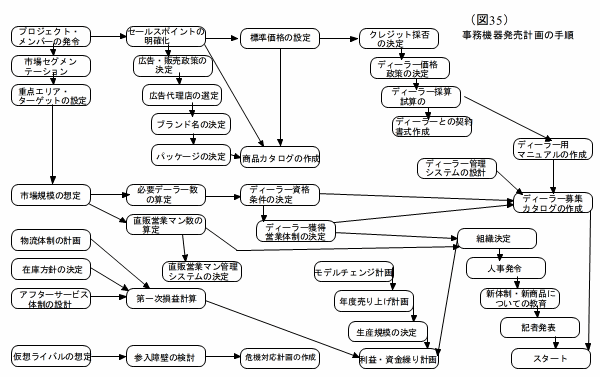
通常、「ミニマム五十ステップは考えるように」といいますと、皆、最初は「エッ」といった顔をします。それは無理だという反応です。しかし、しかし、無理やりにでも五十ステップを考えると、それなりに出てくるものです。前述の強制発想法です。要するに難しく見えても、それは慣れていないからできないだけの事です。
なお、図35には時間の要素が入っていませんが、それは入れなければ計画になりません。「誰が」「いつまでに」の抜けた計画は計画ではなくなります。したがって、この図は、次項で紹介するPERT図に展開するか、図36のような棒グラフに似た計画図(ガント・チャートとよぶ)に置き直すことになります。
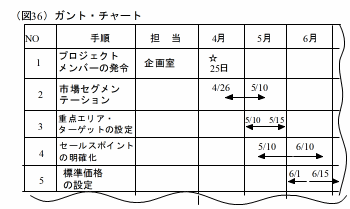 ◆戻る
◆戻る(2) 役に立ちPERT手法の考え方
◆ PERTの概略仕事の手順計画を立てる手法の一つに、PERTと呼ばれるものがあります。Project Evalution & Review Teccchnique の頭文字をとったものでして、そもそもは米国のNASA(米航空宇宙局)で宇宙開発計画をスケジュールどおりに進めるために開発された手法です。
多くの平行作業を伴った複雑なプロジェクトの計画に適していたため、プラント建設やビル建設などに用いられ、建設会社にはなくてはならない手法になっており、個人向けにも多くのパソコン用ソフトが市販されています。個々では、技術的な説明は避け、通常のプロジェクトに応用できる範囲の概要を紹介します。解説書も多いので、詳細を知りたい読者は、そちらのほうをご覧ください。
まず、このPERT法は、並行作業があり、関係者が連携を取って、タイミングを合わせながら、「待ち」が生じないように仕事を進めていくためには、非常に有効です。
たとえば、簡単な事例として、図37を見てください。これは、コンビニエンス・ストアやスーパーに冷蔵設備を売り込み、搬入する手順を想定したものです。もちろん、現実には、もっと細かく計画しなければならないのですが、考え方を理解するのが目的なので、非常に簡略化してあります。この図にあるようにPERTは、○印と矢線で描かれたネットワークと呼ばれる図を描くことから始まります。
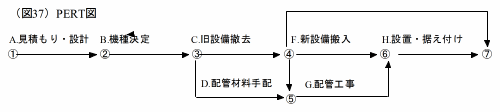
このネットワークは、各作業の相互関係を表示するもので、次のようなルールに従って表示されます。
①作業など時間を必要とする活動は矢線で表す。
②○印に番号が入った印は、各活動の始まり、あるいは、終わりの時点を示します。
③各活動は、それに先行する活動、(矢線)が全部終了した後でないと開始できないのです。
たとえば、図37の「H、設備・据付」は、「F、新設備搬入」と「G、配管工事」が終わらなければ着手できないのです。
点線は、ダミーと呼ばれ、「所要時間ゼロの擬似作業」をしめすます。これは、「G、配管工事」は「C、旧設備撤去」と「D、配管材料手配」が終わらなければできませんが、F、新設備搬入」は「D、配管材料手配」から独立していることを示すときに用いられます。
このダミーは若干分かりにくいかも知れませんが、線が錯綜して複雑にならないように工夫したものです。そのため、同じ○印の間に結ぶ矢線は一本に限定するルールになっています。ネットワークが描けたならば、各活動には所要時間(日数)を記入し、それぞれの完了日を書きます。(図38)
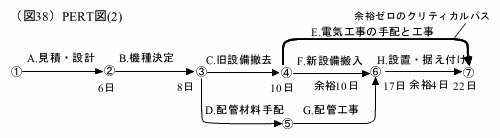
◆他の仕事の完了タイミングにあわせろ
計算方法などの詳細は省略しますが、図38をもとに、遅れの許されない作業はどれかを特定します。この図では、「A、見積もり・設計」→「B、機種決定」→「C、旧設備撤去」→「E、電気工事の手配と工事」が、それにあたり、この経路上にある作業が遅れると、その日数だけ、引き綿とが遅れることになります。この経路を遅れの許されない重要な、という意味でクリティカル・パスと呼びます。
また、言い換えれば、それ以外の作業が若干遅れても、そう慌てることはないことになります。たとえば、納期がきついからと、新設備の搬入を余計な費用をかけてまで急ぐことはありませんし、配管工事も四日の余裕があるので、その範囲であれば遅れても納期に影響はありません。
このようにPERT図を使えば、並行する作業間のタイミングを効率的に図っていくことができます。急ぐ仕事だからといって、残業までしてがんばったものの、他の並行作業が完了していないために、結局待ち時間が生じただけというような無駄はなくなります。
◆戻る(3) 実行部隊の心理と行動様式を無視しては成功しません。
「人を動かすには、参画意識を持たせろ」自分たちの問題として受け止めるように、ミーティングには必ず声をかけておけ」といったことは、どの会社でも耳にすることです。まことに、そのとおりですし、このことは企画部門の人たちのように、人を通じて仕事をする職種の人たちにはだいぶ浸透してきたようです。ただ、それでも、このことを軽視して失敗するケースはあとを絶ちません。
◆プライドと面子に配慮しないと失敗する人間は感情の動物だとよく言われますが、こと企業内においては、プライドと面子の動物と言い換えたほうがより正確なようです。それだけに本当に仕事をうまくやろうと思えば、単に話を通しておけばよいと言うことですませずに、連絡や報告の順番にまで気を配る必要があります。ときに、関連する部門の責任者がお互いに張り合っていたり、中が悪かったりする場合には、最新の注意が欠かせません。
後で話しをするつもりでいても、先に他の部署から情報が入り、「なぜ、俺のところに報告をしない」と気を悪くされることもありますし、報告をしたにもかかわらず、「アイツのほうに先に話をした」と、話を通す順番だけでヘソを曲げられることもあります。後者など、ずいぶん度量の狭い人物だと思いますが、それが現実である以上、それなりの対応をせざるを得ないのです。
関連部署の人には話を通しておいたにもかかわらず、その部内でのコミュニケーションが悪かったために、話しを聞いていなかった担当役員に、役員会でノーといわれるケースもずいぶん見聞きしてきました。
さらに、担当者は部長と副部長の両方に報告していたところ、部長のほうだけを見て話をしていたために、後で副部長から「そのようなことを部長に報告していたのを小耳に挟んだ気はしますが、正式には俺は聞いていない」と妨害されたことすらあります。それだけ、人間の社会は厄介なものです。
解決しようとする問題のキーマンに、「初めて聞いた」と言わせてはなりません。細かいテーマについてまで、いちいち気を使うことはありませんが、どうしても成功させたいと考える大事なテーマの場合には、キーマンその人に対する報告事項でなくとも、書類にCC(カーボン・コピー、参考配布先の意)を入れ、その手元に届くようにすることです。
前に「考えるのは頻度だ」と述べましたが、マメに情報をインプットしておけば、その人の頭の中で「やらなければ」という気持が醸成されることもありますし、うまくいけば、自分で考え出した気にもなってもらえます。いずれにしろ、関連部署に対する情報のインプットに気を配りすぎることはありません。
◆第一線の被害者意識を取り除け
以上は、どちらかというと本社内でのコミュニケーションの問題ですが、第一線を動かす場合には、また別の配慮が必要です。通常、第一線には「いつも何かやらされる」という被害者意識と、「本社は分かっていない」という気持があります。
したがって、問題解決の一環として第一線に何か新しいことを強いる場合には、会社としてのメリットだけでなく、それが彼ら自身に言ってどのようなプラスになるのかを懇切丁寧に説くことが必要です。
それを、「とにかく、やれ」と強制するだけでは、面従腹背を生むだけで効果は上がりません。また、そのメリットも、部分的でよいから早めに実現して、彼らに「本社は口先だけではない」と思わせることが望ましい。米国では、これをEarly Win(直訳すれば早めの勝利)と呼び、意識的に仕掛けていきます。
私は営業分野が専門であるため、営業の事例ばかりで恐縮ですが、セールス・マネジメントのシステム導入の場合を例にとると、彼ら営業マンが、このプロジェクトのおかげで助かったと思うようなものを早めに実現してしまうのです。それは、本来のシステムとは直結しないことでもよいのです。彼らが、このプロジェクトの一環で改善されたと思えばよいのです。
たとえば、新システムの導入に伴い、それまで手数がかかると嫌がられていた帳票や手続きを廃止したり、簡素化することでもよいのです。とにかく、本社も自分たちのことを考えていてくれると思ってもらえばよいのです。
逆に、新システムにちょっとした不具合があり、それが一時的にでも現場の大きな負担増につながるようなことがあっては、成功するものも成功しません。その不具合は、まだ、そのような現象を経験していない営業所にまで飛び火し、最初から拒絶反応を生む元になりますし、ましてや、あちらこちらの営業所で発生すると、もぐらたたきのように、火の手を消すだけで精一杯となって、定着どころではなくなってしまいます。
ですから、新しいシステムを現場に導入する場合は、会社一斉に導入するのではなく、特定の営業所をモデルに限定しながらテストを繰り返し、潰せる不具合は潰しておくことが成功の秘訣です。万全を期したつもりでも、やってみて初めて不具合がわかるということは実に多いものです。
◆実施指導者には現場経験者を配せ二番目に挙げた「本社は現場を分かっていない」という気持ちは、どこの会社でも、かなり根強いものがあります。それだけに、第一線を指導に回る担当者は、
①現場経験があること
②第一線の反発を受けるようなキャラクターの人物でないこと
③聞く耳をもっている人
であることが必要です。
賢明な読者には、①の現場経験の有無は本質的なものでないことがおわかりと思いますが、経験のある人の場合と、まったく経験のない人が回った場合とでは、現場の反応は天と地ほど違うのが現実です。
本当にプロジェクトを成功させ、問題解決をしたければ、無理をしてでも、そのような人物をプロジェクトの初動段階に参加させておくべきと考えます。
(4) 指示も実行メンバーの言葉に翻訳が必要
解決案自体には、まったく問題がないにもかかわらず、現場に理解されないために、十分な効果を挙げないで終わってしまうケースがよくあります。案を作成したメンバーは自分たちで作ったわけですから、その内容について熟知しており、しかも、肌で分かるレベルにまで達しています。そのため、簡単な説明で、皆もわかるはずだと考えがちになります。その結果、電話一本ですませた連絡をしたのですから、やってくれるはずだと思い込み失敗するケースも後を絶ちません。
◆実施定着化の指導は丁寧すぎるぐらいで丁度よいのです しかし、コミュニケーションはそんなに簡単ではありません。「なぜ、ウチの会社はこんな簡単なことすら徹底できないのか」と思ったことが、一度ならずとある読者も多いはずです。それは、大半が、徹底や定着には根気が勝負であることを本当に理解していないために、中途半端な実地指導で済ませてしまうからです。念には念を入れ、「幼稚園児ではあるまいし、ここまでやる必要があるのか」と思われるほどに徹底を図って丁度よいと思わなければなりません。二章の「なぜ問題解決ができないのか」の「失敗を恐れるこころ」の項で、やる気がないように見えるのは、本当はそうではなく、不十分な説明や指導が原因であることが多い旨を説明しましたが、その際に紹介した「やる気の三段階」(図6)を思い出してください。第三の最高のレベルまでは到達しなくとも、せめて、最初の二つのレベルはクリアしていることが必要です。
第一は、企業が組織としてやろうとしていることの必要性を理解させることです。「こんな無駄なことをやらせて」と思っていれば、絶対にやる気は出てきません。たとえば、営業のシステムを新たに導入しようとする場合、それが会社にとってどれだけの効果があり、本人とってどのようなメリットがあるのか、少なくともアタマでは理解できるレベルにまでもっていくことが必要です。
第二は、自分にもできると思わせることです。いくら会社にも自分にもプラスになることだと思っても、自分の力で達成可能だと思えなければやはり、やる気は出てこないのです。
◆現場の言葉で話せたとえば、達成可能と思わせて成功したケースとして次のような話があります。あるカメラ会社であったことです。同社で年度予算の策定に当たって、各営業所から提出された売り上げ目標を積算したところ、その積み上げ額がトップの期待値には及ばなかったのです。
そこで、本社は各営業所ごとに、後いくら目標値を積み増しせよという指示をしましたが、「無理に無理を重ねて作った目標にさらに上乗せをするなど、とんでもない」というのが第一線の反応だったのです。
そこで一計を案じたのが、金額ではなく、各営業所の上位何店に一眼レフをあと二台ずつ売ってもらえ、という台数による上乗せ指示でした。もちろん、この台数を金額換算すれば、当初に支持された金額イコールになります。しかし、第一線の反応はまったく異なったものとなっています。
たしかに大変ではありますが、後二台ならばできないことはないという気にさせることができたのです。金額の提示の時には大変だという気持だけが先にたって、まったく受け入れる余地はないように思えていたのを、どの程度の負担ましになるのかのイメージが具体的に湧くように、「現場の言葉」に翻訳して示したからです。
この「現場の言葉」に翻訳して示す、ということは、営業にしろ、工場にしろ、第一線を動かす必要のある解決案を実行しようとする場合の鉄則です。
しかし、マーケットシェア五パーセントアップというような目標がそのままの形で第一線の営業マンまで伝達されるケースが多くなります。このような目標では、営業マンとしても、自分が具体的に何をすればよいのか見当もつきません。中間の管理職が、トップの目標を営業マンの具体的な行動に結びつく言葉に翻訳して伝えなければ、標準や目標を伝えたことにならなくなります。
たとえば、シェアを五パーセント上げるには、「Aという地域では十パーセントの売上高増、B地区では拡販余地が少ないので現状維持でいこう、そして、A地域での10%売り上げ増のために、新規開拓を五件行い、既存店Xの売り上げを10%伸ばそう」といった具合の指示が必要です。
このように、ほんの少しの工夫でやる気にさせることができるのですが、現実には、部下に期待する達成水準さえ明確に伝達されていないケースが多いのです。どの程度やればよいのかがわからなければ、自分にできるかどうかなどは判断のしようがなく、したがって、やる気も起こりません。目標を明示しないで、やる気がないといっていることがないか、一度振り返ってみることが必要です。
また、自分でやれると思うには、やりかたがある程度分かっていなければなりません。何度も繰り返すようですが、やる気がないように見えるケースの70%が、この理由によるといっても過言ではないのです。
やる気を起こさせる三番目のポイントである「自分の存在価値を実感できる」体制にもっていくことについても、もう一度確認しておきましょう。これには、能力や貢献度を評価されていると思える、参加意識をもてる、自由度が与えられていると感じるなど、種々のレベルがありますが、「参加意識」ということについては誤解が多すぎます。
やる気を起こさせるには、「参加させることが重要である」と何かというと社員をできるだけ参加させようとする企業は少なくありません。しかし、参加さえすれば、参画意識さえ持てれば、それで自動的にやる気が起こるものではないのです。参加することによって、自分の存在意義を実感できるかが問題なのです。モチベーションの手段として、参画ということを考える場合には、存在意義の実感の手だてまでが考えられていなければなりません。 ◆戻る(5) 徹底しなければ効果は出ない
問題解決でせっかくよい解決案が見つかったのに、実施の段階で徹底しきれず、中途半端にお茶を濁したために、ほとんど効果が出なかったという体験を、多くの読者がお持ちのことと思います。前項で述べましたように、特に第一線を動かすというような場合には、通達一本でことが片付くほど簡単ではありません。
手取り足取り、くどいくらいに繰り返して丁度よいのです。まさに徹底的にやることがもとめられます。
しかし、それを、あと少しという段階で、もうよいだろうと手綱を緩めて失敗するケースが続発します。これは何も第一線を動かす問題に限りません。新規事業への投資を初めとしていたるところで見られる現象です。
ものごとには、ある線を超えるまで徹底しなければ、効果がゼロに等しくなり、それまでの努力が水泡に帰すというラインが存在します。したがって、そのラインを超えるまでは、何が何でも頑張らなければいけないのです。このラインを閾値と呼びます。
もともとは、薬の世界の言葉だそうです。一ヶ月間、毎日百ミリグラムを飲まなければならない薬があったとします。それを仮に毎日八十ミリグラムで済ませたとすると、効果は八割でなく、ほとんどゼロになってしまうといったことがあることから、このような言葉が登場しました。閾は「しきい」の意味であり、閾は超えなければならない「しきい」の値です。
この閾値の存在は日常生活の中でも体験します。たとえばゴルフを例にとると、キャリアも短く、プレー頻度も総多くないにもかかわらず、ある時期集中的に練習し、コースに出ている人がいます。つまり、一時期、閾値を越えるだけのゴルフをしたため、腕があまり落ちないのです。一方、二十年近くのキャリアを持ちながらも、毎年数えるほどしかコースに出ていない人は、コースに出た総回数は多くても、腕前はビギナーに等しい。一度も閾値を超えた経験がないからです。図39の上の図が前者であり、下の図が後者です。
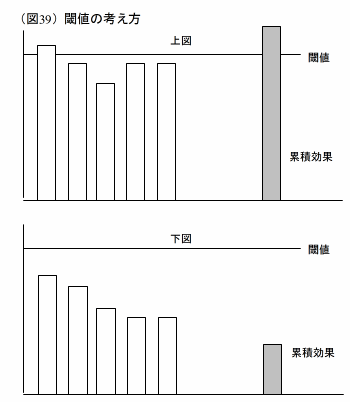 しかし、この常識的なことがビジネスになると、往々にして忘れ去られます。たとえば、何年にもわたって投資を続け、総投資額として相当の金額になったにもかかわらず、閾値を超えるだけの初期投資をしておかなかったために、結局投資が実を結ばなかったという例の話は新規事業には枚挙にいとまがありません。この中には、十分な初期投資をしておけば、もっと少ない総投資額で成果を挙げることができたものも少なくないはずでしょう。
しかし、この常識的なことがビジネスになると、往々にして忘れ去られます。たとえば、何年にもわたって投資を続け、総投資額として相当の金額になったにもかかわらず、閾値を超えるだけの初期投資をしておかなかったために、結局投資が実を結ばなかったという例の話は新規事業には枚挙にいとまがありません。この中には、十分な初期投資をしておけば、もっと少ない総投資額で成果を挙げることができたものも少なくないはずでしょう。
また、メーカーの営業マンが、新しく担当先となった問屋に対して、散発的にしか訪問しないために、いつまでたっても「裃」を着たままの状態から抜け出せないというケースもよくめにします。最初に集中的に訪問することによって人間関係の閾値を超えておけば、後は、場合によって電話だけでも商売ができたかもしれません。
ただ、残念なことに、ビジネスの世界では、薬と違って、これが閾値だという数値を特定する方法がありません。どのラインが閾値だか分からないのです。しかし、今のやり方で閾値を超えているか否かをチェックしてみるぐらいは、感覚的ですができないことではありません。それだけでも、閾値を意識しない場合と比べると雲泥の差が生じるのが私の経験です。
◆戻る(6) 危機対策計画を立てる(リスク・マネジメント)
ここで挙げた危機対応計画とは、「コンティンジェンシー・プラン」とも呼び、リスク・マネジメントの一種です。計画を実行していく上で予想される機器について、あらかじめ手を打っておこうということをさしています。つまり、予定通りいかなかった場合の、代替案の概要を決めておきす。
企業の中で発生するリスクには、様々なものがあります。その殆どが、起きるかもしれないが、起きないかもしれないと、いったリスクがあります。このような場合、リスクが必ず発生することを前提として計画を立てるわけにはいきません。かといって、リスクを無視したのでは、計画としては不完全なものになります。そこで、万が一に備えて、別途準備するのが危機対応計画です。
◆リスクに対して「引き金」を引くタイミングを決めておけしかし、まだ起きるか起こらないか不明な、予想されるあらゆるリスクに対して、あらかじめ対応策を決めておくのは簡単な作業ではありませんし、非効率でもあります。そのため、リスクの発生を予知する兆候が起きたときに初めて、対策の考察に着手するのが現実的になります。
そこで、どんな兆候が起きたらアクションを開始するのかを明確にしておくことが「危機対応計画」の基本となりますが、その兆候のタイミングを「トリガー・ポイント」と呼びます。「トリガー・ポイント」とは「引き金を引くとき」という意味です。つまり、リスク発生の合図が見えたときに準備開始の引き金を引こうというのです。
ここで重要なのは、トリガー・ポイントを決めたら、それを常に監視続ける責任者を決めておくということです。それは、トリガー・ポイントを決めてもウオッチャー(監視する人)を決めておかないと、状況の変化を見逃して結果的に何のアクションも取れないことになるからです。
トリガー・ポイントはできるだけ具体的に、たとえば技術革新については、「こんな内容の特許が出たとき」とか、「ライバル会社から、このような製品が発売されたとき、次世代製品の発売準備に取り掛かる」といった形で決めます。
家電製品などで、各社一斉に新製品が発売されて驚くことがありますが、これは一社が発売して他社が、すぐにそれを真似して追随するというケースとか、各社共にある程度予定しておいて、ライバルがいよいよ売り出すというタイミングを見計らって、すぐに生産して売る体制に入っていることが少なくありません。これは、ライバルが発売を始めた時点をトリガー・ポイントに設定しているわけでしょう。
◆リスクには二種類あるところで、危機対応計画には二つの種類があります。一つは「計画の前提になっている条件の変化した場合にどうするか」という計画であり、もうひとつは「不確実性が高いために、もともと計画に入れておかなかったことが発生したときにどうするか」という場合です。
条件の変化とは、たとえば為替レートです。一ドル九十円で設定していた計画が、一ドル七十円になった場合、何を行おうかということです。また、たとえば売り上げが予定通りいかなかったら、交際費をカットするなどの縮小予算をあらかじめ決めておく。これも一種の危機対応計画です。
後者の、不確実性が高いために計画に入れておかなかった事柄が発生するというのは、具体的には次のようなケースを言います。
たとえば、得意先が自社生産を始めるかもしれないという想定は、あらかじめ計画に入れておくことはできませんが、万が一発生すれば非常に大きな影響を受けるので、あらかじめトリガー・ポイントを設定しておくことが必要です。一例を挙げれば、医薬品のメーカーは、ライバル社の開発部のどの人間が、大学病院の誰と接触する頻度が多くなってきたら開発が間近い、といったことまで観察しています。
また、トリガー・ポイントを決めておくこともさることながら、想定しているリスクそのものが発生しないようにできればいうことはありません。したがって、リスク発生確率を低める手だてが考えられるものについては、その原因を除く策を講じておくのは当然です。
たとえば、強力なライバルが自社の仕様と大幅に異なる製品を発売して敵に回らないように、特許を供与して味方に引き入れておくというのもこれに当たります。最近話題になっている「デファクト・スタンダード」(実質的世界標準規格)作りにも、この無用な争いのリスクをあらかじめ避けるという側面があります。
日本では、昔、オリンパス光学が、マイクロ・テープレコーダーを発明したときに、松下電器に特許を無料で提供し、参入を促したケースが有名です。これは大手家電メーカーと戦って敗退することのリスクの原因の除去と、市場の拡大を狙ったものでありました。
いずれにしろ、危機対応計画は、問題解決を行う場合、そのメインの構成要素となるものではありませんが、計画の最後の押さえとして付け加えなければならないものであって、問題解決の最後の仕上げでもあるのです。
◆戻る