|
真夜中の脳みそ
詩集「半熟卵」(Update:2001.
9.16.)
コラム「午前3時の天気予報」(Update:2004.
8.21.)
AIBO日記(Update:2003.11. 3.)
アルバム(Update:2003.1.31.)
「紺野」とは?(Update:2004.
8.21.)
Links(Update:2002.10.20.)
更新ログ(Update:2004. 8.21.)
Mail Me !
|
第48回 コラム:生き急ぐ
生きることに急いではいないだろうか。
わずか数週間前のことが既に「懐かしい」という感覚になっていたり、現在のことや目先のことのみにとらわれ、数年後でさえも具体的に思い描くことができなくなっていたり、「新しい」とか「流行」とか特定のキーワードのみに過剰に反応したり、全てのことに目的や意味を見出せなくなっていたり等々。これらの感覚は現在という時間に閉塞を感じ、現在という枠組みの中でもがき、しかし急速に、かつ唐突に現在は終了することを知覚しているからからこそ、不安、焦りのようなものを感じながら、現在が終わってしまわないように急いでいる、ということなのではないだろうか。
圧倒的に情報供給過多の中、その情報洪水の中におぼれ、「処理」することだけを繰り返す日常。しかしながら現在という時間が積み重なることで文化や歴史や足跡が形成されてゆくことが知覚、想像できない余裕のなさ。ややもすると数時間前のことでさえ知覚できない現在だけが存在する感覚。だからこそ現在を生きなければならないと脅迫されるように焦燥感に駆られる。先が見通せず不安になる。目先のことだけで安心してしまう。未来を感じることができないのではない。過去を振り返ることができないわけでもない。現在だけしか認識できない。つまり、それは現在を生きることに急いでいる、ということではないのか(では急ぐことをやめるために、全てのものからの関係を断ち、「生きる」ことは可能なのか)。
その理由や必然性など想像できるわけでもなく、ただ与えられたシチュエーションで自分の知覚しうる範囲という舞台の上で、自分という役を演じることにのみ何故かしら必死になっている。それでいいのかという自問をする暇もなく。
「ぼんやりとした不安」。作家、芥川龍之介が自殺の前に残したとされる言葉であるが、彼が持っていた感覚、彼がはっきりとしないがそれ以外の言葉を見つけられずに不安と表現したものを、70年の歳月を隔てた今現在の我々は持っているのではないだろうか。かの才人が大正時代の終わりから昭和のはじめに感じていたものを、何となく我々が感じているのではないのか。結局彼はその不安と折り合いをつけられずに自らの命を絶ち、凡人たる我々はそこまで思いつめるだけの決断もなく適当に折り合いをつけて何とか日々を送っているだけではないのか。または折り合いをつけることすらも諦めてしまい、閉塞した時間の中に閉じこもっているのかもしれない。
現代はいったいどの方向に向かっているのだろうか。どの方向に向かうべきなのか。いや、もっと基本的なこと、我々はどんな向きで現在に立っているのか、実はそれすらも知覚できていないのではないのか。正立しているのか、逆さになっているのか、斜めになっているのか、2次元の平面に存在しているのか、3次元空間のある一点に存在しているのか、そうではないのか、そもそも向きというものは最初から存在していないのではないのか。
我々の生存する空間には絶対、というものは存在しない。全てのものは全てのものからの相対的な関係でのみ存在しうる。相対的な関係を考慮しなければあらないのはほぼ無限に近い。未発達な人間の脳ではそれを知覚、認識するのにおのずと限界がある。
さらに我々は例えば決まったレールの上だけを走っているのではない。たとえ今現在何かしらのレールの上を走っていたのだとしても、そのレールが数年後までレールであり続ける、ということはもはや幻想でしかないのだ。
それは星明りも月明かりも、当然街灯などない真っ暗闇の中を懐中電灯も持たされずに「歩け」と言われているようなものだ。自分だけが「歩く」ことによって「周り」から動くわけではなく、例えば「地面」と感じている部分もまた動く(常に全てのものが全ての方向に相対的に動き続けているため)。よって、「見えないから」といってしゃがみこんでいるだけでも、それだけでも何かしらの方向に動いてしまう。こんな状態はたまらなく「不安」だ。そして「間違える」ことも多いはずだ。いや、「間違い」の方が多いだろう。しかしその「間違い」を「間違い」として知覚するためには少なくともある程度の知識と多方面から冷静に分析できるだけの見識が必要だ。
その点では、言ってみればカルトな集団もテロリストも「現在」しか知覚できず、見識の部分を「信じる」ということで切除してしまう、ということでほとんど同じような存在となる。「間違い」と気付くこともできない状態に自らを置くことで「安心」してしまうのだ。不安を解消する「ナニモノ」かに依存しているだけだ。この場においては「信じる」ということと「依存する」ということはほぼ同義であるととらえてもいいだろう。依存している限りにおいては依存するということだけに必死になってしまい、結局生き急ぐ結果となる(だいたい、何がカルトで何がテロリズムかなんて結局のところ誰も明確な定義は与えられないのではないのか)。
情報が少なすぎても「ナニモノ」かに依存しがちになるだけで、情報が多すぎても情報に意味を見出す余裕もないまま情報を処理することだけに意識が向かいがちになる。どちらの状態も生き急いでいることには変わりはない。ちょうどよく落ち着かせる加減はないものだろうか。
かく言う私も自分自身が「生き急いでいる」ということに不安を感じている。底なし沼のような感覚だ。自分自身の足りない処理能力をカバーするためにその時点で集められるだけの情報を集め、事象を抽象化しメタ(meta)な概念としてとらえたことが、それ自身をメタ化することで逆にメタ化させたことを否定する結果にさせてしまう(またはまったく情報がなかった状態と同じ状態にさせてしまう)。しかもそれは自分自身でまいた種なのだ。
どうすれば自分自身が生き急ぐ状態から抜け出せるのかまだわからない現在は、当分生き急ぐしか道はなさそうだ。それが「よい」ことなのか「悪い」ことなのか判断する材料は今のところ持ち合わせていない。
(2000. 1.23.)
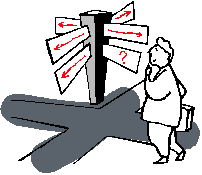
Prev  Next Next | 