�l���̉��F

�k�R�c�b�f�{�n�O�l
�@
�v�x���H�@�S����]�@�����������
�S���[�g���������̖̖_�Ƌ����z���œ͂��ċ������B
�b�����āA���s�̒��j����A������A�u�肷��̍ޗ�������A�b���ۗ����Ă���v�ƁB
���̑O�ɁA���e�������C�łQ����]���ƕ����āA�����l�b�g�ʔ̂ŏ㓙�̎肷������B���C�̃^�C���̕ǂɂӂ��A��J���Ď撅���Ă��ꂽ�B
����ɕ��C���ɂ���肷��ƈ֎q���c�B
�i�w�����s�������̂ŗ���ďZ�ނ��ƂɂȂ��Ă��܂�������ǁA�Z�������𐢑オ��������Q���Ԉȏ�Ԃŋ삯���Ă��ꂽ�B�d���͂܂�ňႤ���n�A�R�b�c�W�Ȃ̂Ɂc�B
�������B�H�삵�Ă���݂����B�Ƃ����Ȃ���B
�䏊�ɒʂ��鋏�ԂɁA�R���[�g���߂��肷���������B�t���t�������̘A�ꍇ���͑��сB
�肷�肪���������A�V�v�w�́u����͂������������ˁv�ƌ����������B
�������̎肷��͎�Œ͂ނƃz�b�Ƃ���B�����Ƒ����s����̘A�ꍇ���́A�u�ǂ������A�ǂ������v�Ƃɂ��ɂ���ł���B
�肷�肩�爤���������藎���Ă����B
�@
�X�ɁA��̃X���[�v�����H�����邢��ɂȂ��Ă��āA���\�����B�����ɂ��肷����B
���g�݂͉��x���̍H������ɐ\�����ށB�X���߂��߂��������B
�Ȃ���ł������ɂ��肷������悤�B�ƁA�X���[�v���猺��܂ł̎肷��𒍕������B
�Â��Ă���̂ł͂Ȃ��B�����邽�߂Ɏ肷��ɂ��܂��ĕ����̂��B
�����āA�����Đ�����̂��B
���F��́w�v�x���P�x�̒ʒm�Ɓw���ی����S�������x���͂����B�w�v�x���P�x�̍����͑�������B�܂��A�����ƁA�^�N�V�[2���̎x���𗊂B
�Q�O�Q�Q�E�Q�E�Q�P
�������ƕ����Ȃ��B�h���낤�Ȃ�
�v������v�x���̈Ⴂ���l���������܂ŗ����c
�A�ꍇ�����A�R�N�O�ɔ]�[���ł��낢�댟�������B
���ɂЂǂ��͂Ȃ��������A�ŋߕ����@�\���������A�U�����ɓ�x�]�B
�����āA�Ƃ��ǂ����Ƃ��I������ׂ�Ȃ��B�Ǐ���p�\�R���͕��C�ł��Ȃ��W�S��
���Ƃ̎n�܂�́A�v���Ԃ�ɋ��s�ɂ��钷�j�v�w�����Ă��ꂽ�B���̂Ƃ��A���j�̘A�ꍇ���u���̕������ł͊�Ȃ��v�ƈȑO�P�A�}�l�[�W���[�Ƃ��ē��������Ŕ������Ă��ꂽ�B
����Ȍ�X�[�p�[�Ǝ���̕��C��œ]�B
�ŋ߂��Ƃ̂������B����ɕ����e���|�̂̂낳���ڗ��B
���������Έꏏ�ɕ������Ƃ����������������Ȃ��B�߂ɌX���Ă��邩��B
�L���ԓ��̂ӂ���������B�������낤�Ȃ��B
�����˂����q������Ă��ꂽ�B
��{�����Ƃӂ�����A����ĂR�{���ɂȂ�y���ƌ����B
�����͎s��������ƁA��C���x�������Ƃ�����l�̏��������āA���ی��\���̂��߂̒��������ꂽ�B
�������A�u���H�ƕ��C��ō��v�l��]�v�ƌ������B����ȗ��V���L���ɂ��悭�o�Ă����u�A����p���c�v���K�v�ƂȂ����B�R�l�̏����̑O�œ��X�Ƃ��̐����p���c�������Đ�������B
���Ȃ���A����������x�����������B
�ȑO�A�����b�ɂȂ������w����̐搶(94��)����R�̃g�C���b�g�y�[�p�[���āA�u�A�R��p��v�ƌ���ꂽ������݂�����B
80��̒m�l�ɉ�����u���莆�����ς��������B�݂�ȔA�R��͌o�����Ă����B��ς�B�v
�Ƃ��Ƃ������܂ł����Ȃ��B�킪�v�w�A��l�Ƃ��W�O��Ȃ��̍���ҁB���C�Ŏ����̗͂ŕ�����A�����Ă���Ǝv������ʼn��x���Ȃ�čl���Ă����Ȃ������B
�������A���]���Ƃ��A�肷�肪�Ȃ��ƕ����Ȃ��Ƃ��A�S�������łƂ�ł��Ȃ��������l���o����c�B�����Ȃ̂��B���̏I���͂����܂ł��Ă����̂��B
���܁A�v�w�́u�v���5���x���ɂ��v���u�v�x��2���x���ɂ��v���A�ł����킹��c�̌��ʕ�҂��Ă���B
���x���́A�u�v�x��1�v�̌��ʂɂȂ����B�s��������u���ی���ی��ҏ��v�Ɓu���ی��������v���͂���ꂽ�B�u�x�����ځv�����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�Q�E�Q�E�Q
�k�ڎ��Q�l2�`36�͌�
�肷��A�肷��A�肷�肾�炯�̉Ɓ@�ƒ�@�@�v�x���H�@�S����]�@�����������
�@�@�u�A���C�W���O�E�O���C�X�v������钆�@�o���������@�F�l�ɗ��l������
�@�@�s�A�m�̉��F�@�@�s�A�m�����邳����
�@�@�t�ł鉹�ɂ͖�������B�����l���𑗂�ꂽ�Ȃ�
�@�@�u��̕��ɂȂ��ā@���낢��ȏ��S�͂����Ăˁv
�@�@���y�̗͂Ł@������y���܂��|�}�����o�R���T�|�g
�@�@���@�C�A�s�A�m���e�����@������S�E��p����Q�T�Ԃ��߂��c
�@�@���y�̂�����
�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�N�A���\��W�O��A�����̂͊ȒP������ǁc
�@�@�u�A���[�W���O�E�O���C�X�v���������@�@�@�@�@�@�K�q�̃z�[���y�[�W�ɖ߂�
�@�@�u���̎�͂��ꂢ����Ȃ��v�@�t�W�R�E�w�~���O�̃R���T�[�g�ɑz���@9�T�O�N�ƂT�O��ŏI���N
�@�@�V���p���u�ԑ��̒��ɉB���ꂽ��C�v�@���P���k�`�F�E�\���G�l��
�@�@�s�A�m�̓��@
�@�@���グ�Ă����@��̐����E�E�E�@�A�t�K�j�X�^���̓y�ɂȂ���
�@�@�e���Ȃ������u�t�B�������f�B�A�v
�@�@�E�肪�����Ȃ�
�@�@�s�A�m�͉̂�����
�@�@���肾���̉��t��
�@�@�l���̉��F
�@�@�V������Ł@�s�A�m�͂������|�C�i�o�E�A�[
�@�@�s�A�j�X�g�@������q�ɂ݂�l�Ԑ�
�@�@���y�ނ��Ȃ�
�@�@�u���z�ȕ��\�i�^�@�����v�ɑz��
�@�@���ɐF��������������z����̂��l����t�W�q�E�փ~���O��l���͊R�o�裗{�V�Ўi
�@�@�������
�@�@�N���b�V��(������)�@�@�@�@�@�����G�b�Z�C���Ԃ����֍s��
�@�@�s�A�m�͉̂�
�R���i�����������I�ɑ����A�ٌ������钆�A���ϋq�̃I�����s�b�N�@�p�������s�b�N���I������B�Ƃ��Ƀp�������s�b�N�͐��E�̏�Q�҂��A�ꂵ�݂Ȃ��畱�������B
�����l�Ƃ��ċ��������l�����������̂ł͂Ȃ����B
�R���i�Ől�Ԑ��E���A�ЊQ�̂悤�ȂЂǂ������Ɠ����Ă���B����ǂ̂悤�ɓ����Ă����̂��낤���B
����ȎЉ�ŁA����Ί�ɂƂĂ���܂��ꂽ�B����͐V���ɂR�N���A�ڂ��ꂽ���͂̍�҂��w��͂Ȃ�����ǁx���������r�䗢�ނ����B�����Ɠ����P�X�V�S�N���܂�B
�Q�O�P�T�N�ɑB�l�̂��E����Ő��؏����ꂽ�B���܂ł͊O�o�͎Ԉ֎q�A��Œɂ݂�}���A�x�b�h�ʼn߂������Ԃ��唼�ɂȂ����悤���B
�f�ڍŌ�̋L���w�ł��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���ɖڂ��������A�Ō�܂Ŏ����炵�������Ă�����Ǝv���Ă��܂��x(�����V���Q�O�Q�P�E�X�E�V)
�ʐ^�̏Ί炪�f���炵�������B����ȋꂵ����ԂȂ̂ɁB
�Ί�Ƃ����Ζ������d�ɂ��Ԃ������A������킹�Ă���S���`���̏Ί炪�A�܂��Ɍ��p�グ�āA�ڐK�������Ă�����B
���̕n�����h�T�N�T�̐��̒��ŁA�l�ꔪ��̊w�Z�̍Z������A���낢���ς������悤�ł��邪�A���̏Ί�ɘa�܂����B
�����͔����I���O�A���̒���ǂ����������z�Ő��������ɑS�͂𒍂����B�������z�ő呲��A�E�����E������߁A���������̐�]�����ƂɂȂ����A�ꍇ�����A�ٌ����������тɂȂ����B���N���������������́A���z�����ꐶ�����ꂵ���A�Â���̓��X�������B
���̂Ƃ��ł���B�u����ȈÂ��炵�����͌������v�j�Љ�œ����Z�p�Ƃɂ��Ȃ��ꂽ�B
�A�ꍇ���͓�N�ԍٔ��œ�������������Ȃ��A�؋����f���d���Ȃ��ٔ����������߂Ċw�K�m���J�����B�S�Q����U�R�܂ő������B
���ꂩ��S�O�N���܂�߂��A���낢����z���Ă����B
���ܖ����A�ڐK�������Č��p�オ��Ƃ�������B
���A�b�c���Z�b�g����Ƃ��B�C�ɓ��������y�Ɏ��X���Ă̂P���Ԃ̐V���^�C���B
��J�������q�ǂ���l���A���̒��Ŋ������B���������͎d�����I���A�K������Ă���Ȃ��B
��A�����^�C���B�Ɋy�A�Ɋy�B���ӁA���ӁB����ȂƂ��v�킸���ɂȂ�B
�Ƃ��͏H�@�w����قǁ@�����ׂ𐂂���䂩�ȁx�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�P�E�X�E�P�Q
�@�@ �u�A���C�W���O�E�O���C�X�v������钆�@�o��������
�@�@�@�@�@�@�@�F�l�ɗ��l������
�c���s�s�̂��̕ӂ�́A�U������ƂR�O�p���炢�Ɉ�����_�炩�Ȉ��݂̂ǂ肪
���̗����ɂт�����ŁA�S���炮�B
�ӂƁA�ȑO�ǂ��w�i�Z��̓`���x���v�ҏW�̕��͂��v���o�����B
�u�O�،{�Y�͓��{�ŏ��߂ăf�B�Y�j�[�f��Ǝ��g�B���̐l�����A�a�ŋꂵ�݁A���̕a�C�͐悪�Ȃ����玀��\�v���m�́w�A���C�W���O�E�O���C�X�x�ŏo���������Ɨ��܂ꂽ�v
�W�O�܂ł͌��C�ł������A�������V�ƂȂ���ʂ����˂Ȃ�Ȃ��B
�⑰����́u�����͕���������v�Ɣ����ꂽ���A�\�v���m�̎�̒��������������ɗ��B
�R�֏�ɂP�O�l���炢�̂��V�����ԁB����ł��̐l�Ƃ̖��ʂ������������B
�njo���������A�₨��̎�̒������w�A���C�W���O�E�O���C�X�x���̂��Ȃ��瓰�X�ƍՒd�Ɍ��������B�njo�ƃ\�v���m�̐������荇���A���������́A
�u�f���炵���������������v�Ƒ����̐l�����ł��ꂽ�B
�w�A���C�W���O�E�O���C�X�x�ƌ����Ȃ�m�����̂́A�u�T�O����̃s�A�m�����v�������B
���k�ɂ͎q�ǂ����ォ��s�A�m��e���āA��ȂC�Œe���l������A�����̂悤�ɒ��N�����āA�U�R���炱�̋����֒ʂ��n�߂��҂������B
����茳���勳�����A�f�l�ɂ����낢��ȋȂ��e����悤�ɐ��͓I�ɕҋȂ��ꂽ�̂ŁA���\�l�����鐶�k�����́A�����ɒʂ��������B
�Q�O�P�W�N�̉��t��ŁA�w�A���C�W���O�E�O���C�X�x��e�����B����Ȃł͂Ȃ����A����������ɋ����Ȃ���������B
����ɂ́u���Ƃ����Â������@���̂悤�Ȑ�܂����҂܂Ł@�_�͋~����������B
���l��̓Ɠ��̈Â��A�������S�ɂ��ݓ���f�G�Ȑ����ł��v�Ƃ������B
�����͌������u�����Ɨ��K���Ă����v�ƌ���ꂽ���Ƃ����鋳���̕]����
�u�\���̎d���������B��̕\������B�������s�b�^�����v�ɋ������B
�l�����Ȃ����Ƃ������B�L���X�g���k�ł��Ȃ������Ȃ̂ɁH�@���̂Ƃ��A���߂ċ����ɖJ�߂�ꂽ�B
�c�O�Ȃ���A�����͊Ԃ��Ȃ������Ă��܂�ꂽ�B�Ղ��������v���o�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�P�E�V�E�Q�W
�s�A�m�̉��F�@�@�s�A�m�����邳����
�킪�ƂɂЂȐl�`�͂Ȃ��B�j�̎q�@���̎q�Ɠ�l��Ă����B�@
���̎q�a���Ł@���j�͉��������H
�`��̖₢�ɁA����ς肨�ЂȂ��܂�����@
���ЂȂ��܁H�@����Ȃ̖��Ӗ��@���̂ق��ɉ����H
�������āc�@�s�A�m���������炢���ȂƂ͎v������ǁA�ƂĂ����������c�B
�`��͕n�R�ȑ��q�̂��߂ɁA�ق��Đςݗ��ĂĂ��������ی��������ɂȂ����ƁB
�킪�Ƃ��n�R�Ȃ̂́A�A�ꍇ�������}�̏�C�����ƂɂȂ�������c
�����͒x�z�A���z�����������B
�������R�ŕ����Ȑ��̒���ڎw�����B���ꂪ��҂̗��z�������B
���������Ȃ��犈���ƂƂ��Ċ撣���Ă�������B�A�ꍇ���͐�]�����ƂɂȂ������Ŋ������ꂽ�B
��J���đ�w�܂ő��Ƃ������̂ɂƁB
�s�A�m�͂T�O���~�A���ǂ����ł��Ă��犨���͂���ނ�ɂȂ�A�������ĖႤ�B
���Ƀs�A�m�w���B�R�O���~���Q�O�N�ԃ��[���ŕ������B
�N���V�b�N���y����D���Ȃ킪�v�w�A�����S�ɂȂ�����߂��̌l�s�A�m�����ցB
�͍��y��n�ŁA���N�Ԃ����t��ɂ��Q�������B
����Ƃ��ߏ��̉\�Ȃ��Ł@�s�A�m�̉������邳���@�̐����B
�������A�����������̂��c
���H����Ō����̉Ɛl�B���y�D���łȂ�����邳���ē�����O�B
�������āA���Ȃ��̂��Ƃ������s�A�m�ƂȂ�ɂ���
�b�����Ēn��̓y�n��搮���ŏZ���ړ]�����܂�B
�]��������A�߂��̉��y���t���f�G�ȃs�A�m�̉��F���������������B
�S�R��ɂȂ�Ȃ��������A����Ƃ��}�ɉ����������B
���Ȃ��̉Ƃ܂ŕ�������́H�@������C�ɂ��čI���s�A�m���́A�������ɏ������B
���y���D���ł��A���������l���Ȃ�s�A�m�Ƃ̂����Ȃ��߂����B
�U�R�Łw�T�O����̃s�A�m�x�����ցB�ǂ�������搶�����Ɍb�܂�A���N�������B
��Ȃł��f�l���e����悤�ɁA�������ҋȂ��ꂽ�����勳��
�����̐V���L���w�s�A�m�����肭�������x�Ƃ������B�킪�Ƃ̃s�A�m�Ȃ�P���~���ȁB
������Ƃ́A�ꂵ�ݎ₵������A�R���i�Ђł��݂�ȓ������ɗ������������X�Ȃ�B
�l�ɂ͊y���݁A�S��Ԃ��Ƃ�����A�����Ɏx�����Đ����čs���B
�s�A�m�e�����y���݂Ȑl����B���邳���v���l������B
���ꂪ�l�ԎЉ�ƕ����荇�������B�@�@�Q�O�Q�P�E�S�E�Q�R
�@�@�t�ł鉹�ɂ͖�������B�����l���𑗂�ꂽ�Ȃ�
�F�l�̐e�����X�O��Łu�s�A�m���e�������v�Ƃ����l�������邻�����B�Ȃ̂Ŋy���͂����ǂ߂Ȃ��B���A���ɓ������������Ղɑt�ł�B���X�Ɖ��������Ȃ��e����B
�V�l�{�݂ɍs���ăs�A�m��e������A�����҂�������ƒe���ė~�����Ɨv�]���o���ꎞ�X�o�����Ēe���Ă���Ƃ��B�{�݂̐l���������y���܂�Ă��鏎���̃s�A�m�ł���B
�����l�����Ȃ��A�����z��������l�̐l�B
����͂T�O�Έȏ�̍���҂ɓI�����ڂ��āA���g�̍�Ȃ�ҋȂȂǐ��͓I�ɂ��Ȃ���Ă����B���ʓI�Ȋ������ꂽ����̌������ł���B
�J���`���[�Z���^�[�ł́u�T�O����̃s�A�m�����v�B�s�A�m��t�ł��т����߂Đ��k�͂S�O�l�T�O�l�Ƒ����������B�c�N���̉��t����������B
�����͒��N�����������̂ŁA�ސE��U�R����Q�������B����̐l�����͑ސE�҂���A�ƒ�̎�w���肾�����B�v�����݂ɒe����l�������B
���K�������Q�����ĊԈႦ����u�����Ɨ��K���Ă����v�ƁA�������������v���������F�m�ǂŖS���Ȃ�ꂽ�B���܂ƂȂ��Ă͂��̎���ꂽ���Ƃ����������B
����t�ł��тȂ�āA�u�R���i�ЂŐl�ԊE���l�ꔪ�ꂵ�Ă���Ƃ��ɉ���ۋC�Ɂv�ȂǂƎ���ꂻ���B�ł��A����ȂƂ������炱���A�����͗������܂��ɂǂ��������炢���̂����l����K�v������B�D���ȉ��y�͔]�₱����̖����ɂȂ�B
���y�Ƃ̕����O�́A���w���̂Ƃ��ΘJ�����Ƃ��Ċ�n�œ�������펞���R�̂��蕷���Ă����B�w�k�̌��K�m������̒~���@�������ăV�����\�������Ă��ꂽ�B
�W���Z�t�B���E�x�[�J�[�̉̂��L���ȃV�����\���w�������Ă�@���̂��Ƃ��x�������ƌ�ŕ��������B���y�ɖڊo�߉��y�̓���i�B
���̗D�ꂽ���y�Ƃ��P�X�X�T�N�U�T�Ő����Ă��܂����B
���N�ׁ͂[�g�[���F�����a�Q�T�O�N�̔N�B
���̋Z���Ȃ������Ȃ̂ɁA�Ⴂ�����R�[�h�R���T�[�g�̒��Ԃɍ�ȉƂŒN���D���H�ƕ�����u�x�[�g�[���F���v�Ɠ����Ă��܂����B�̂����ɁB
�������A�{���ɍD���ȍ�ȉƂ������B�s�A�m�\�i�^�w�����x�A�����ȁw�^���x�A����荇�����́w�����ȋ�ԁx�B�����������Ȃ��Ȃ��J�̘A���ŁA���y����Ղ��ƁA�V�����ɒ��킷��̑�ȉ��y�ƃx�[�g�[���F���ɖ����ꂽ�̂����c���B�@�@�@�@�@�Q�O�Q�P�E�P�E�Q�R
�@�@�@�@�@�@�@�u��̕��ɂȂ��ā@���낢��ȏ��S�͂����Ăˁv
�u���������͂��̐؎肪�����ς��o�Ă��܂����B
�悭�莆��������邠�Ȃ��A���̐؎�ł��낢��ȏ��S���͂���̕��ɂ��Ă��������v
�����L���ꂽ�莆���o�Ă����B
���E����e�����������̗F�͐É����̏o�g�A�������Ƃ��č̗p����Ă��玎���������ČP���{�݂ŕ�����V�X�e�����������B�����Ŗ��É��o�g�̔ނƒm�荇�����������B
�P���I����A�z�����ꂽ�Ǘ�����͒j������̐E�ꂾ�����B
�ۂɂP�l���Q�l�̏����Ј�����������A���͓�l�ł悭�O�H���Ă���ׂ荇�������ł���B
�̗͂�����A�D��S�����ʼnf����D���A�Ǐ������낢��S����ŊO���ւ̗����悭�o�������s���h�B
��l�Ƃ��d���Ǝq��āA�������������Ƃ����Ȃ��Ă����B���W���O�A�ߓS�d�ԁA���S�d�Ԃŋ삯���A���É��w�O�̎��]�ԓX�ɗa�������]�ԂŊ����X�܂łQ�O���قǑ���B
�J�̓�����̍~������K���Łc�B��l�Ƃ�����Ȃ�̎v�z�ŏ[�����������Ă����B
���ꂪ�Ԃ���鎖�����N�����B
��͔ޏ��̂R�l�̎q�����������ɎЉ�l�Ƃ��ĕ����o�����̂ɁA�₳�����^�ʖڂȉ��̑��q�����������������c�Ƒ����ŁA�Ƃ��Ƃ����_�I�ɎQ���Ă��܂����B����Ŏ��������Ռ��ɕv�w�ŋ����������B
������A���e�ł���ނ��A���R�[�����łɁB�����ɏo���R�[�X���s���ǒ��܂łȂ����̂ɁA���ɋ����͂ŁA���낢��ȏ���܂Ƃ߂Ă����̂Ɂc�B
�@�e�����F�̂��̋ꋫ����X���ɂ��A������ŗ܂��Ȃ���A�������ďグ���Ȃ��B
�N�Ƃ��ɂ��₩�ɕt�����������ɂ����ʂ��Ă����ޏ����u�l���͋�Ȃ�v�ƌ����Ă����B
�u�b�_�̂��̂��Ƃ��~�߂�悤�Ɂc�B��l�ł悭�b�������x���������B
���̗F�͂V�S�������������ɂȂ�A���̐��֗������Ă��܂����B���������R�N�ɂȂ�B
�W�R�܂Ő����i�炦�����́A�l���̉��R�����A���ӂ��ĕ����˂c�B
�悭�̂�ꂽ�H���j���w��̕��x���Ȃ��������Ă����B
�@�@���̂���̑O�ŋ����Ȃ���
�@�@�@�@�����Ɏ��͂��܂���
�@�@�@�@�����ĂȂ��܂���
�@�@��̕��ɂȂ��ā@���̑傫�ȋ��
�@�@�@�@�@�@�����n���Ă��܂��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�Q�O�E�S�E�Q�U
�@�@�@�@�@�@�@�������y������������
���鉹�y�Ƃ����w��N���̂Ƃ��ɁA�푈�ɋ��͂���w�k�Ƃ��ē������ꂽ�B
�����֊w�k�����Œ��p����Ă�����w�������K���m���ƂȂ�ړI�Ŕz�����ꂽ�B
�푈���I���ɋ߂��P�X�S�T�N�������B
���ʂĂ����w���Ƃ͉��y�������O�ŁA���̑�w�����u�������y�������Ă����悤�v�Ǝ莝���̒~���@�Œ������Ă��ꂽ�B
���ꂪ�t�����X�̃V�����\���w�������Ă�@���̌��t���x�������B
�т����肷�钆�w���A�����R�̂����̂킹�ĖႦ�Ȃ���������B���̉��y�̑f���炵���Ɉ��|���ꂽ�B�푈���͉��Ă̂قƂ�ǂ̉��y�́A�G�����y�Ƃ��Ăقڋ֎~����Ă����B
���̋L������g���X���s�̎G���w�}���x�Q�O�P�X�N�W�����œǂ݁A�����Ƃɂ���b�c�Łw�������Ă�@���̌��t���x���A�W�J�̂�q�̐��ł��݂��ݒ������B
���������Βߌ��r��ďC���w�l���̃G�b�Z�C�@�������̎��͕������Ă��邩�@�����@�O�x���Q�O�N�߂��O�ɓǂ��Ƃ��v���o���A�{�I��T���܂����y�[�W��ǂݒ������B
�W���Z�t�B���E�x�[�J�[�Ƃ����̎肪�̂��Ă����B�w�p�����E���A�E�_�A���[���x�w�������Ă�@���̌��t���x�������B
�����O�́u����ȑf���炵�����y�����̐��ɂ������̂��Ǝv�����v�ƁB��������I��ɂȂ��ĉ��y�ɊS���W�����Ă������ƌ����B
�����O�́u���y�Ƃ������̂͐l�Ԃ̌ǓƂȊ���A�߂��݂�{��A�ꂵ�݂Ȃǐl���ꂼ��̊���ƌ��т��Đ��܂�Ă�����̂ł��v
�u�����͂ЂƂ肾���A�����������̑��l(�Ђ�)�Ɏx�����Đ����Ă���v
����́A�W�Q�̍���҂ƂȂ�������v���B�ŋߐl����U��Ԃ�����z�����A����́u�����������������̐l�����ɁA�x�����Đ����ė����v�ł���B
���y�ƂƂ��Ċ��������O�́A�P�X�X�T�N�ɂU�T�ł��̐��ɗ������Ă���B
�����w�}���x�Ō��ߒ��������S�́A���w���Ő푈�̂��߂ɋΘJ�������A���鎞���y�̑f���炵�������Ă��ꂽ�l���������B���y���g�c�G�a���A�펞���ɉ�����̒��ŕz�c�����Ԃ��ăx�[�g�[���F����V���[�}����~���@�Œ����������A����Ȑ푈�꒼���̎��オ���̍��̌������������ɋ��ł����B
�e���r�Ȃ��A���R�[�h�Ȃ����̕n�����̒��ň�Ă�ꂽ�킪�o���́A�����[�������łR�l�吺����グ�āA���w���̂��������ߏ��ł��]���������������B
�N���V�b�N���낤�ƃV�����\�����낤�ƁA���R�ɍD���ȉ��y���y���߂鐢�̒��B
���������o���D���ȕ����H�ׂ���Љ�A���R�ɗ����鎖���o���鎖�A���ꂪ�����̑҂��]��ł���Љ�Ǝv���B
�ŋ߂̊ȒP�ɐl���h���A�x�����Ƃ��������Ă���B����͉��̂Ȃ̂��H
�@�݂�Ȃōl�����������Ǝv���B�@�@�@(�Q�O�P�X�E�W�E�R�O)
�@�@�@�@���w�������Ă戤�̌��t���x�����߂ă��R�[�h�ɐ@�����݂����̂́A�w�}���x�ɂ��ƃ����V�F���^�E�{���C�G�ł���ƌ��K�m���̂��Ƃ�����B
�@�@�@�@�@�@�@���y�̗͂Ł@������y���܂��|�}�����o�R���T�|�g
���̐V���^�C���͓łP���ԁA�ґ�ˁB�ܘ_�A��������͂���ȗ]�T�Ȃ��A���o�������ߓǂ݂����B�����A�[����[�H��ɂ܂Ƃߓǂ݂��������Ƃ��v���o���B
�t����]�����ɂȂ�A�x�b�h�ŐQ�Ȃ��璮�����V���p���́u���z�����ȁv�ɋ��ł��ꂽ�B�ȗ��N���V�b�N�ɐe���B
�v�w�����N�D�N���V�b�N�̂b�c�������Œ����Ȃ���V����ǂށB�ŋ߁A�g�����y�b�g�̎��l�ƌ������u�j�j�E���b�\�̐��E�v����ɓ��莨�X����B
����Ȓ��Łu�N���V�J���E���[�h�v��u���E�̝R��v�̋Ȓ��A���{�̋ȂƂ���v������ł悭�̂��Ă�����̐瑐�������̏h���A�A�C�������h���w��C���O�����h���w���������Ƃ�m�����B���̒��x�̉��y�t�@���A�N���V�b�N�t�@���ł���B
���āA�ސE��U�R����n�߂��s�A�m���b�X���A���̐搶�̊W�ŋv���Ԃ�ɃR���T�[�g�ɏ����ꂽ�B�}�����o�R���T�[�g�ł���B
�y��̓}�����o�A����Ȋy�킳�����܂�m��Ȃ������B����Ȗ؋Ղƌ��������̂��ȁB�R���T�[�g���͒n���̑��������Z���^�[���������q�ǂ����܂߁A�����̐����������B
�X�^�[�g�ŋ������̂́A�����Ȃ�s�A�m���t���u���̈��A�@�d�G���K�[�v�u�`�����_�b�V���@�u�����e�B�v�ƃe���|�����Ȃ��t�ł�ꂽ�B
�u�`�S�C�l�����C�[���@�o�T���T�[�e�v�ňꕔ���I���܂łɘA���V�ȁA�e���݈Ղ��ȂɁA������͂��މ��t�A�}�����o�ƌ����y�킪�t�ł郁���f�B�Ɉ������܂ꂽ�B
����łЂƂ�A�}�����o���t�҂͂��ׂĊy���Ȃ��̈Õ����t�������̂ɂ͋������B
�Õ��ƌ����A���N���O�̃s�A�m���\����V�x���E�X�́u�t�B�������f�B�A�v���������t�H�[���́u�V�`���A�[�i�v���������A�Õ��Œe�����B�����̒��q�Œe����͂��Ȃ̂ɁA�ԈႦ�Ēe���������B���A�ǂ��������Ƃ����ԈႦ���B����̏ォ��u��������e�����Ă��������v�Ɛ}�X�������肢���āA�Ȃ�Ƃ��e�����o��������B
�v���Ƃ͌����A�}�����o�̐搶�̑f���炵���ËL�͂Ɋ��S�����B
�����w���Ă���s�A�m�̐搶���A����������ߑ��Ŕ��t���ꂽ�B�V�Ȃ��x�݂Ȃ����F�S�n�ǂ��e���ꂽ�B���_�I�ɂ����̓I�ɂ�����ǂ��������낤�Ǝv���B
��̓}�����o�R��̋����������B����ɑ傫�Ȋy��}�����o���R��A���t�҂͗���ɍׂ��_�������ĉ���t�ł�B�}�����o���m�������������Ȃ��猩���ȉ��t���w�`�r�o���f�B�́u�l�G�v���u�āv�x�ȂǂT�Ȃ��I������B
�����ɂƂ��ĉ��y�Ƃ͉����낤�B���w�A�N�w�Ƃ͈Ⴄ�]�ւ̏_�炩���h���ɐS�����B
�l�Ԃ͂��낢��Ȋy��ʼn���t�ŁA���R��l�ւ̈���z���Ă���B
����̃R���T�[�g�ł��A���̎����������������C�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�X�E�U�E�R�O
�@�@�@�@�@�@�@���肾���Ł@����t�ł�
���y�͔]��a�炰��B�����o���ĉ̂��̂��̂͂����B���Ƃ����̒��ׂł́A�]�̌������ǂ��Ȃ�B��y�����t����Ƃ����Ƃ����B�������ǂ���ʂ��͂�����Ԃ��Ȃ����B
���̃e���r�����āA���y�������łȂ��t�ł�y�����A�S�n�ǂ����h�����B
�d�������߂ĂU�R����K���n�߂��s�A�m���A���낻��I��肩�ȂƖ����Ă����B
�w�T�O����̃s�A�m�x�����̔��\��͂S�O�l�ȏオ���t�������������B����҂Ȃ̂Ɍb�܂�߂���������Ȃ��B
�������a�C�Ŏ��߂�ꂽ�B���̐搶�������X�ɋ������J���āA�p������l���������������B�݂�ȂP�O�N�P�T�N�Ɩ�����ł����l�����������B�s�A�m�͖��̂��߂ɔ��������̂ł���B
�W�P�ɂȂ��Ďv�������Ȃ�������ɂȂ�A�S�E��p�Ő������x�B�D���ȉ��y���̂������B���A�t�ł�Ɣ]�����炮�B��͂�s�A�m��e�����Ƌv���Ԃ�ɏ��̐搶�̋����֏o���B
�ȑO���t��Œe�����V�x���E�X���w�t�B�������f�B�@�x��e�����B
���̋Ȃ͏c�ɒ������V�A�ƍ�����ڂ��Ă��鍑�t�B�������h���A���x���卑���V�A�ɍU�߂���R���������B���̋Ȃ͔����������f�B�̗���Ƌ��ɁA��R����Ȃ������Ă���B
�ȑO�A�s�A�j�X�g�ٖ��́w�t�B�������f�B�A�x�̉��t�����|���ꂽ�B�͂P�X�R�U�N���܂�Ŏ����Ɠ���81�B
�������A���͂Q�O�O�Q�N�]�쌌�œ|�ꂽ�B�����ĂQ�O�O�R�N���肾���̃s�A�m���t�ŕ��������B�t�B�������h�ݏZ�Ȃ���A���{�ł��u���肾���̉��y��v���Â������I�ȃs�A�j�X�g�ł���B
�����O�A�t�B�������h���獇���c���������A���́w�t�B�������f�B�@�x���e���r�Œ������B������������������R�̉̎��̑f���炵���������B
�������������P�Q���W���́A�V�V�N�O���{���^��p���U�����A�ߌ��̑����m�푈�ɓ˓��������������B
���y�Ƃ����̂́A���̂悤�ɔ]���h�����A���₩�ɁA���炩�ɂ��Ă����̂��B���肾���ł��e�����Ƃ���s�A�j�X�g�Ƌ��ɁA���̋Ȃ𖡂�����B
�W�P�̓������p�҂����̈ӋC���݂����K�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�W�E�P�Q�E�W
�@�@�@�@�@�@�@�@���@�C�A�s�A�m���e����
�@�@�@�@�@�@�@������S�E��p����Q�T�Ԃ��߂��c
�u�A���C�W���O�E�O���C�X�v�Ɠ��̈Â��A�������S�ɂ��݂���f�G�Ȑ�����t�ł��������B
�e�m�[���̎�@�V�_���́A�����n�ɒ������Ă����č��l�ƌ��n�̓��{�l�����Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ���A���Y�t������ĉƒ{�̓_����V�_�̖ڂɂ����A���̂��ƂŌ����������B
���̌㗼�e�͗������c��Ɉ�Ă�ꂽ�B�ǓƂȃh���ꐶ���ŐV�_�͗��e�Ə��Y�t�Ɛ푈�����B
�c��������ߏ��̐l�����̊Ԃŕ]���������V�_�̉́A�V�_������������q�t�͔ނ��w�_�w���ɓ��ꂽ�B���̑��̕��̒��Ŏw���҂���u���̐����g��Ȃ��̂͂��������Ȃ��v�ƌ����A��w���Ƌ߂��Ɂu���Ȃ��̖��邢���͐_�l�Ƃ������܂���̃v���[���g�v�Ɨ�܂���e�m�[���̎�ւ̑����ݏo�����B
�s����ꂽ���X�̋ꂵ�݂�Y��A�_�ɋF���������т��̂����l��́B
�V�_���u�l�̖��ɗ����Ă���ƕ�����Ɓ@���邭�Ȃ��B���͐푈���Ȃ���ΐ��܂�Ă��Ȃ������B�����炱���A��`�咣�����������a�ւ̎v�����̂����������v�ƌ����B
�Ӗڂ̃e�m�[���̎�@�V�_�ׂ��]���̖̂��Ȃł��邱�̋Ȃ����ꌧ�ߔe�s����قʼn̂����B
�E���ɂP�T�Z���`�̏����Ƃ̂���g�A�ƂĂ��w�Ƀs�A�m�������͓͂���Ȃ����낤�Ǝv�����̂ɁA�s�A�m���e�����B�u�A���C�W���O�E�O���C�X�v�����낪���߂郁���f�B���B
�l�X�Ȍ������Q�����߂��d�ˁA�Ƃ��Ƃ��V�̂Ƀ��X����ꂽ�B��p����Q�T�Ԃ��߂�����
�u�قڂӂ��̐������o���Ă��܂��v
�u�Ղ����w���n�r���̃v�����g�x�͂���Ă��܂����A�s�A�m�e���Ă����ł����H�v
�u�G�b�@�W�P�Ńs�A�m�H�@�����A�����B�f�G�ȃ��n�r����v
�u�ŁA�ǂ�ȋȒe���́c�c�B����ȗ͂����ς��̎p���͂��߂�����ǁc�v
�N�ł��A�ӂ��ɐH�ׂĂӂ��ɕ����ē�����O�B�����v���ĕ�炵�Ă���B
���ꂪ�ˑR�u�H�ׂ��Ȃ��v�u�����Ȃ��v�ƂȂ�Ɓc���R�T�ԑO�W�P�̘V�̂Ɂu���̂�����͂P�W�~���̈�������v�Ƃ��������̌������˂��t����ꂽ�B
�㒎�́A�u���̍܂Ń��X�Ȃ��ꂽ�����Ȃ��v����Łu��p�Ȃ�Ă��Ȃ��v�ƌ����������B��������l���̎�p�̌��̂���F�������u���R��p��v�ƁA�ő��ɘb���Ȃ��Ⴉ�����T�O��U�O��̑̌��𗦒��ɘb���Ă��ꂽ�B�����ς��Ղ�����܂��B
��p�͏I������B���ː����ÁA�R������Â͂��Ȃ��B�c���A�Ĕ���h���w�z�������Ö@�x(�T�N��)���n�߂邩�ǂ����A���f�𔗂��Ă���B
���͂R�N�O�ɓ������p�����B�ꖺ�Ƃ��������ɂȂ������Ƃ́A������̈�`�q������ł���̂��H
�u����ꐶ�v�Ƃ������A������������������B���̂��ƂɊ��ӁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�W�E�W�E�S
�@�@�@�@�@�@�@���y�̂�����
�v���Ԃ�Ƀs�A�m���\��ɎQ�������B�Q���҂��悻�P�O�l�A���ď㋉�A�����A�����ɕʂ�āA�T�O�l�߂������o�[�����Ԃ����炵�ĉ��l���̐搶�Ɋw�����B
���喼�_�����𒆐S�ɂ����u�T�O����̃s�A�m�����v�ł́A���_���������͓I�ɍ�ȁA�ҋȂ����Ȃ��L�x�������B�^���Ȏw���ɐ��E�̉��y��A�e�����Ȃ�������B
���ꂪ�P�O�N���P�T�N��������l�������������R�����m��Ȃ��B
�u���͋����̕a�C�ŕ��������A���ꂼ�ꉹ��o�̏��搶���X�ɋ������p�����Ă���B
���\��̃v���O�����́A�A�_����ȁw�T���E�g���E�}�~�[�x����n�܂�A���_������ȁw���̗c�����ɍK�����I�x�Ƒ����B�����Ƃ肵���ȏ�A���̐V�N�ȋP���Ɩ����̍K���ւ̊肢������������B
�`���C�R�t�X�L�[�́w�Ԃ̃����c�x��e���l������A���������̏o�ԂŁA�}���I��ȁw�y���Ȃ�T���^�E���`�A�x��e�����B
�i�|���̐l�X�́w�T���^�E���`�A�x�ƌ������́w�y���Ȃ�T���^�E���`�A�x���w���Ƃ����A�L����������Ă���Ɖ���ɂ������B�M�l���������i�|���`�𗣂�đD�o����Ƃ��́A�X�Ƃ����C�������̂������c�B
�Ō�͔�ѓ���j�����w�n�i�~�Y�L�x���Õ��ŗ͋����e�����B
�A�e�̃v���O�����ɂȂ����B�ҋȂ��ꂽ�w�߂����̊w�Z�x���Ȃ���A�Ȃ��n��o�����i�����ɕ����юႢ����̋C���ŐS���₩�ɂȂ�B
�A�e�̗ǂ��͑�����݂��Ɉӎ����Ȃ���A�Ȃ�\������Ƃ��납�ȂƎv���B
�����o�[�͎Ⴍ�Ȃ��B���̒��łW�O�ΑO��̐l�����l���āA���������̊Ԃɂ��������V�ɂȂ��Ă����B���Ă͂W�O��̎��͔h��y�����l�������̂Ɂc�B
�ҋȂ��o�����y�͂��̐��֗������Ă��܂����B
�u�w��������ǂ��ă����f�B��t�ł�B���͏����Ă��܂��̂Ɂc�B���̖c��Ȏ��Ԃ��l����ƋC�������Ȃ肻���c�v����͍ŋߓǂ{�w���I�Ɖ����x�ɂ������B
�u�Ⴂ�l�ւ̎w���ƈ���ĔN�z�̎������ւ̎w���͒��荇�����Ȃ��ł���v�Ə��̐搶�Ɍ����Ɓu���������A�e��������l������������v�Ǝ����グ����A��܂����肳��ċȂ�t�ł��т𖡂���Ă���B
�m���ɗl�X�ȃ����f�B�ɖ�����āA�S���炮�����͋C������h���Ԃ���B��ꂽ�]�ɂ����h��������A��т�������B���ꂪ���y�̂������Ȃ̂��낤�B
�n�����g���ŁA�e�n�Ɉُ�C�ۂ������ЊQ�����ő呛���̂��܁A�W�܂��ĉ��y�������ł��Ă����́H�@�����̐��E�͐푈�������l�����A�ǂ�ǂ�ɐi�߂Ă���B����ȋC����������B
�������A����Љ�ɂȂ�N����Ⴂ�l�ɖ��f�ɂȂ炸���C�Ől���̍ŏI�͂��˂Ȃ�Ȃ��B�����l����A�����Ƃ��]��������h�����Ȃ���߂��������t��͗ǂ������ƌ�����̂����m��Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�V�E�V�E�P�V
�@�@�@�@�@�@�@�P�O�O��ł��P�T�O��ł��c
�Q�R�N�ԑ������s�A�m�������A���̔��\��łƂ��Ƃ������܂����B
���É����}�n�z�[���̋q�Ȃ͂قږ��ȂŁA�����̔��\��Ƃ͉����Ⴄ���͋C�������B
���t�҂͂T�O�l�߂��Ƃ������������A����͂R�S�l�B�v���O�����ɂ͖��O�Ɖ��t�Ȗڂ��A�Ƒt�A�A�e�ʂɕ��сA����ɍu�t�T�l�̖��O�ƘA�e�����ڂ��Ă����B
�J���`���[�Z���^�[�ӔC�҂���u�����̕a�ōu�����v�̈��A������A���t�͏����̐V��������X�^�[�g�����B
���l�Õ��Œe���l������A�ł��r���ŃX�g�b�v���Ă��܂����Ƃ��������B
�v���O����������̐l�́A����Ƀx�e�����̗��������Œe���Ă����B
���̏o�Ԃ̐l�������オ�����B����Ǖ���̗���ɉ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���搶���q�Ȃ��璼�ڕ���֓o��K�i�������悤�ɁA��Ŏx�����B���ʂɕ����Ȃ��l�𖾓��̂킪�g�Ƃ��v���B
�������A�s�A�m�Ɍ������ƕʐl�̂悤�ɂȂ�A�u�u���[���X�̃����c�v��e���ꂽ�B
���̐l���N���X���ʂŒm��Ȃ��l���������A���ɒu���Ă������B��͂菗�̐搶�ɋq�Ȃ��畑��ֈ����グ�Ė��ꂽ�B
�V���Ă����y���D���ŁA�s�A�m��e��������ꂽ�̂��낤�B�����v���Ɛ��X���������������B
�㔼����Ō�̉��t�܂ł́A���P�O�N�Q�O�N�ƌp�������w�͂����点�����t�����������B�킪�u�t�B�������f�@�v���܂��D�]�Ń��������B
���k�̘A�e�����邱�ƂȂ���A�T�l�̏��̐搶�����X�Ȃ�ς�荇���Ēe���u��A�e�v�̗͋����͌����ɔ��\�����߂��������B
���t��̓r���ŁA�������v�w���o�Ȃ���݂�Ȕ���Ō}�����B
�����܂��̕���ʼnԑ���ꂽ�����́u���ꂩ����ǂ�ǂ�V�����Ȃ���邩��B�W�R�t��H���₢��P�O�O��ł��P�T�O��ł��c�v�̈��A�ɂ݂�ȃh�L�b�Ƃ����B
�����āA�T�l�̏��搶����l��l���A���ꂽ�B
�ƁA����ɁA���搶�����������B�u�������S�z����Ă��܂��B���T�̃��b�X���̗\��ł����c�Ηj���P�O������ł��v���̈��A��������ߕt�����B
�����́u�F�m�ǁv���Ȃ��A�ˑR�̃��b�X����~����邹�Ȃ��܂����ށB
�z�[���͖��邭�Ȃ����B�q�Ȃɂ����ȑO�̃����o�[���搶�������A�܂�@���Ă����B
�Ō�̔��\��ƁA�K���ȂP�T�N�Ԃ̃s�A�m���b�X���͂��̂悤�ɏI�������B
�Q�O�N�ȏ������҂ɉ��y��t�ł��т�^��������ꂽ�l���͑f���炵���B�l������ς���A�C�����炮�B
�Q�R�N�Ԑ��k�������W�R�̐�y�̂��Ƃ����g�ɟ��݂�B�u�I���̂Ȃ����͉̂����Ȃ��v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�T�E�P�O�E�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�N�A���\��W�O��A�����̂͊ȒP������ǁc
�s�A�m���\��͂ӂ��N�P��ł���B���A�N�S������\�������s�A�m����������B�������Ɖߋ��`�ɂȂ��Ă��܂������B
�u�T�O����̃s�A�m�����v�Ƃ����B���y���D���ł��A�d����ƒ�̎���Ńs�A�m��t�ł�]�T���Ȃ������l���Ώۂ̋����������B
�N���V�b�N����{�ɁA�V�����\����^���S�Ȃǂ����L���ҋȍ�Ȃ𑱂��������́A�X�^�[�g�����Q�O�N�O�͌����̉��勳���������B�����Ă��ꂽ�̂́A�X�^�[�g����Q�O�N�ԋx�܂�����́A�N��W�O�߂��̌������������B
�N���X���̘A�e�w���ƌʎw���̑��ɁA�R�����ɂP�����b�X���Ƃ������܂����������B�݂�Ȃ̑O�ł��s�A�m���t��͂R�����ɂP���ŁA�N���̓��}�n�z�[���Ƃ����啑���ł̉��t�������B�ْ��͂��邪�A���K�̐��ʂ��ĖႤ�ꂪ�������̂͏[�����ɂ��Ȃ������B
�U�O�܂œ����āA�U�R����s�A�m�Ɍ������������ł��A���̊Ԃɂ��P�T�N�������B
�u��Ƃ�̒����當���͐��܂��v�ƌ������A�V�O�A�W�O�Ή߂��Ă��A�݂�ȂȂ�������̂��낤�B
�u�{�P�h�~�v�A�u�s�A�m���e�����сv�u�F�����Ƙb�����肨������o�����낱�сv�c��͂艹�y���D���Ȃ̂��B
�ȑO�A�������b�X���̂Ƃ��Ɂu�����ƁA����������K���ė����v�Ǝ���ꂽ���Ƃ�����B
�ʎw���̂��߂ɁA����o�̏��̐搶���T�l����B���̒��̈�l�Ɂu�삦�߂��A�����Ƒ̏d���点�v�Ƌ����Ɍ����Ă����ƁA���k���Ԃ��畷�����B
�����͐��m�ȃs�A�m�w���̂��ƁA�u�����g���Ēe���Ȃ���c�����܂ł��������Ƃ͎v���ĂȂ����ǁc�v�ȂǂȂǁA�����Ȍ�����������͗L���ŁA�݂Ȉ�x���x�͌o�����Ă���B
�������w���̋������b�X�����������A�ŋ߁u���b�X�����X�b�|�J�����v�ƁA���X���ɂ���悤�ɂȂ����B
��N���́u��W�O�t��v�������B���j�̉ԑ��������ɑ��낤�B�ƁA�ϋɓI�ɔ��Ă����l�̂��Ƃɋ������B
�u�����O�ɂW�R�Ő������x�e�����̖��O���A�����́H�ƕ������́v�u��������͂������܂����v�ƌ����Ă��A���̗��K�̓��ɂ܂��u�����́H�v���ꂪ�����āA�u��͂�A�ς�B���j������Ȃ獡���Ȃ��v�Ƃ��̐�y�Ɏ�����A�݂�ȃV���b�N�����B
���͍��N�S���̋������b�X���ŁA�R�Ȃقǎw�������B�w���͓I�m�ł��̂����̈���u�A���[�W���O�E�O���[�X�v��e���Ɓu���̋Ȃ͂ǂ������Ȃ������邩�H�v�ƍl�������A���ׂ�����w���ɖ��������B
���\����A�����u�A���[�W���O�E�O���[�X�v�ɂ��������̕]���ɋ������B
�u�i1�j���̋Ȃ炵���e���Ă���B�i�Q�j��̕\������B�i�R�j�������҂����肾�v
�����́u�����A�������v��������O�������B�a�Ɣ����ȊW����Ȃ̂��낤���H
�N�Ƃ��Ă��A�ق߂���̂͂��ꂵ���B����Ƃ��ǂ蒅�����u���X�g�z���v�����c�B
���̐l�S���̕]���������������A�u�������A���������_���v�ƁA�S���ɂ�����ƕ]���ƌ��_�������Ă����B
���ꂩ��b�����āA�J���`���[�Z���^�[�̒S���҂���u�u�����v�̈��A���������B
�u�Q�O�N������Ă��āA�}�ɕ��ƌ����Ă��c�ƁA�قڑS���̏����t���ӌ����Œ�o����܂����B��u���̔M�ӂ�����A�������b�X���Ȃ��ŁA�P�N�Ԃ����p�����܂��v
������ꂽ���͂ɂ́u���{�l�A���Ƒ��̕��Ƃ��b�������܂����B�P�T�N���Q�O�N�������ė���ꂽ�̂́A���X�Ȃ�ʋ����̗͗ʂƓw�͂������ƍl���܂��v�Ƃ������B
�������A���̌�̘b�������ŁA��N�Ԍp���͎������A�����i�Q�O�P�T�N�j�X�����ƂȂ����B
�u���������ɂ����A���̋������F�m�ǁH�v�c�Ȃ������ɔ���B
���̐S�̒��ŌJ��Ԃ��B�u�l�͘V����B�i���̂��̂��͂Ȃ��B���ƐȂ��c�v���B
�z�[���ł̃��X�g���\��́A���̋Ȃ�e�����B�V�x���E�X��ȁu�t�B�������f�B�A�v���B
�]�o���œ|��ĉE���g�s���ɂȂ����u����̃s�A�j�X�g�v�ٖ���A�����������ɐN�����ꑱ���ċꂵ�t�B�������h�̐l�B�̋�J��z���B
����͔F�m�ǂƐf�f����Ă��܂����������v���Ȃ��ɂȂ���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�T�E�W�E�W
�@�@�@�@�@�@�@�u�A���[�W���O�E�O���C�X�v��������
�@�d���𑲋Ƃ��ĂU�R����n�߂��s�A�m���܂������Ă���B���́u�T�O����̃s�A�m�����v�́A�R�����ɂP��S���̐搶�ȊO�ɉ��喼�_�����̋������b�X��������A���\����R�����ɂP��B
�@����A�������b�X�����u�A���C�W���O�E�O���C�X�v�u�o�b�n�̃��k�G�b�g�v�Ȃǒe�����B
�@�u�A���C�W���O�E�O���C�X�v���A������x�ƒe�����ꂽ�B
�@�e�����ɂ��т��X���������ɁA�u���̋Ȃ͂ǂ������Ȃ��H�v�ƕ�����u���l��̂Ŕ߂����ȁv�Ɠ������B���A�����͓����ɖ������Ȃ������B
�@���ȏ��ɂ͊ȒP�ȉ�����ڂ��Ă���A�u���̋Ȃ͂����ȂȂ̂ɁA�݂�Ȃ����܂�e���Ȃ��v�ƕt�L����Ă����B
�@�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ���A�u�A���C�W���O�E�O���C�X�v�Ƃ������Ȗ��̉��Ɂu���炵�������v�Ƃ���A���{��Ɖp�ꂪ���݂ɉ̎����S���ڂ��Ă����B�L���Ȏ]���̂Əo���B
�@���͒m��Ȃ������B��Ȏ҂͕s���Ȃ���A�쎌�̓W�����E�j���[�g���Ƃ������B
�@�W�����E�j���[�g���͂P�V�Q�T�N�C�M���X���܂�ŁA�u�z��f�Ձv�ŋ����̕x��B�����z��Ƃ��ĝf�v���ꂽ���l�̈����͉ƒ{�ȉ��B���̂��ߗA���D���ł̗ȉq����ԂŁA�A����ɒ����O�Ɋ����ǂ�E���Ǐ�A�h�{�����Ȃǂő��������S�����B
�@�P�V�S�W�N�Q�Q�̂Ƃ��A�D���Ƃ��ĔC���ꂽ�D�����ɑ����A�C�ɓۂ܂ꂻ���ȑD���ŕK���ɐ_�ɋF�����B�D�͊�ՓI�ɗ���E����ꂽ�B
�@�@�c�A���C�W���O�E�O���C�X�@���Ɣ����������ł��낤��
�@�@���̂悤�Ȏ҂܂ł��~���Ă�������
�@�@���݊O�����܂���Ă�������
�@�@�_�͋~���グ�Ă�������A���܂Ō����Ȃ������_�̌b�݂�
�@�@���͌��o�����Ƃ��ł���c
�@�@�@�@�@�c����܂Ő������̊�@��ꂵ�݁A�U�f����������
�@�@�@�@�@�������������̂�
�@�@�@�@�@���ł��Ȃ��_�̌b�݂ł������c
�@�@�c�������@���̐S�Ƒ̂������ʂ�
�@�@���̌��肠�閽���~�ނƂ�
�@�@���̓x�[���ɕ�܂�
�@�@��тƈ��炬�̎�����ɓ����̂��c
�@�@�@�@�A���[�W���O �O���[�X�^�́^�p��A���{�ꎚ�� - YouTube
�@�N���X�`�����ł͂Ȃ����ł��A���̋ȂŒm�������l��̂ɉ̂��鍕�l�z��̋�Y�������ł���B�W�����E�j���[�g���͕w�Ƒ��z�̊�t���d�˂Ėq�t�ɂȂ����B
�@���l�z��f�ՂɊւ�������Ƃɑ���[�������ƁA�͂���^�����_�̈��ւ̊��ӂ����߂��Ă���Ƃ����Ă���B
�@�ŋ߁A�S���̋��R�Ȃ���A�w�Ӗڂ̃e�m�[���̎�V�_�ׂ������u�A���C�W���O�E�O���C�X�v���̂����B������s���̎�(����)�u�����݂����ӂɕς��āv�x�Ƃ��������V���̋L��(�Q�O�P�T�E�T�E�W)�Ɍf�ڂ���Ă����B
�@�V�_�ׂ���͉̎萶���R�T�N�A���܂�͉��ꌧ�A�ČR��n�ɒ������Ă����č��l�ƁA���n�̓��{�l�����Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�B�P�ŗ��e�����������͋A�����A��͍č������̂őc��Ɉ�Ă�ꂽ�B
�@�ő�̕s�K�Ǝv�����̂́A����Ԃ��Ȃ����Y�w�̌��ʼnƒ{�̓_����������Ď����������ƁB
�@�P�S�őc�ꂪ���ɁA���ꂩ��Q�N�o�����Ƃ�����I�Ɏ��ɂ����Ȃ�A��˂ɔ�э������Ƃ����B���A�ʂ�|�����F�l�ɏ�����ꂽ�B
�@���W�I�őc�ꂪ�D���������]���̂����ɂ��A�ߔe�s���̋���ɍs�����B�o�}�����q�t�Ɂu��l�ɂȂ�����A�����J�֍s���ĕ����E���Ă��v�ƌ����������B�q�t�͉������킸�A�����A�����܂𗬂����B
�@���̌�A�q�t�͐V�_���������A�����̐_�w�Z�֓��w�������B
�@�_�w�̕��̒��Ő��̑��̎��Ƃ�����A�w���҂���u���̐����g��Ȃ��̂͂��������Ȃ��v�Ƃ����A�Q�V�ʼn̎�̓�������n�߁A����W�҂�̎x���ȂǂłR�S�ʼn��y��w�ɐi�w�ł����B
�@�Q�O�P�T�N�S���P�X���A����̓ߔe�s������łP�O�O�O�l���閞���̊ϏO��O�ɉ̂����B�����m�푈�����̉����̔ߌ����̂����u���Ƃ����є��v���u�Έ�(������)�v����I����A�ϋq���܂��ʂ������B
�@�P�T�Ȃ��̂������ƁA��������̔���A�w�J�����܂Ȃ����ōĂѕ���ɖ߂�̂����̂��u�A���C�W���O�E�O���C�X�v�������B
�@�V�_�ׂ̂��Ƃ�
�@�u�l�̖��ɗ����Ă���ƕ�����Ɩ��邭�Ȃ���B�����ɗ^����ꂽ�������̂����Đ����������B���ꂪ�n�[���j�[�ƂȂ蕽�a�ɑ����v
�@�u�����͂������̏��ՁA�푈���Ȃ���ΐ��܂�Ă��Ȃ������B�����炱����x�Ə��Ղ𐢊E�Ɏc���Ȃ��悤�A�l���@���A��`�咣�������a�ւ̎v�����̂����������v
�@�����ǂ�ŁA����R�����Œm��������t���[�g�t�҂́A���y�ɂ����̂��Ƃ��v���o�����B
�@�u�w���܂�������x���Ƃɂ͖𗧂��܂���(���Ԃ�)�B����ǂ��w�悭������x���߂ɂ͌������Ȃ����̂ł�(��������)�v
�@���\��̋Ȃ͌��܂肾�B�����Ȃ���u�A���C�W���O�E�O���C�X�v�̂����������������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�P�T�E�T�E�Q�Q
�@�@�@�@�@�@�@�h���`���������̉��y
�@���A��������с@�����y����
�@���̐V���^�C���́A�����ڂŎ���ǂ��Ȃ���a�f�l�Ɏ��X����B
�@�������V���p���̋Ȃ��Ă���ƁA�����Ȃ蕷�����ꂽ���{�̉̂̃����f�B������Ă����B�u��̍~�钬���c�v���̉̂̏o�n�߂̃����f�B���R�`�S��J��Ԃ��Ă���悤�ɕ��������B�v�͂��̂��ƂɈȑO����C�����Ă����ƌ����B
�@�Ȃ��u���z�ȃw�Z����i�S�X�v�ŁA�P�P���R�O�b�قǂ̒����ł���B
�@�V���p�������{�̂��̋Ȃ�^����͂��͂Ȃ��B�u��̍~�钬�v�̍�Ȏ҂��A�L���̐[�����ɂ������V���p���̃����f�B���̂̐����ɂȂ��Ă��܂����B�̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B
�@�q�ǂ��̍����W�I�͂��������A�e���r�͂Ȃ������B�o���R�l�����ӑ吺�ʼn̂����������B
�@���̕n��������A���܂��������̗[���т��ςނƁA�����吺�ʼn̂����B�a�J��̈Â��낾�����B
�@���݂͑S���̈����ł��邪�A�����̂��Ă��肢���������A�w�|��Ŏo���R�l�Ƃ����w�N�őI��ēƏ����������������B
�@�u������̂�����v�u�݂���̉ԍ炭�u�v�Ȃǐ�c���q�A�F�q�o�����̂��Ă����̂ł���B
�@�Љ�l�ɂȂ��Ă���A���ׂ������点�Ę]�����œ��@�����o��������B�������@�����������W�̕a�@�ŁA���҂̒��̉��y�D���̐l�������A����I�Ƀ��R�[�h�R���T�[�g�ŃN���V�b�N���y���y���܂��Ă��ꂽ�B
�@�a�̐S�z�̒��Œ������u�V���p���̌��z�����ȁv�́A�t����̑�D���Ȏv���o�̋ȂɂȂ����B
�@���̍��u�J���v�ƌ������y�̒��t�����A�������Ō��P�炢���y���y���߂��B
�@�w����N���V�b�N�x�`�s�^�ʖڂȖ��Ȉē��`�̒��҂͔���T�ꎁ�ŁA���̂悤�ȕ��͂�����B
�@�u�x�[�g�[���F���́w���x�́A���{�l�ɂƂ��Ă̖Y�N��̃h���`���������v�т����肷��悤�Ȃ��ƂX�Ə������̂́A�u��ʓI�ɁA�N���V�b�N���y�͌��ꂵ���~���������B�����v���Ă���l�������B�R���T�[�g���ł��A�����Ɛ_���ɐ^�ʖڂɉ��y�Ɏ����X����l�����ł��ӂ�Ă���B
�Ȃ��A�N�̐��ɂȂ�Ɠ��{�l���w���x�������Ȃ�̂��v�ƁA�x�[�g�[���F���́u�����ȑ��ԁv�ɂ��ď����Ă���B
�@�u���{�l�ɂƂ��Ẵh���`���������Əd�Ȃ�B�o���g���́w�����F�悱��ȉ��y�ł͂Ȃ��A�����Ɗy�������y��t�ł悤�ł͂Ȃ����x�Ƃ����̐����A�ے��́w����܂ł̎d���̋�J��Y��āA�����̓h���`�������������܂��傤�x�ɏd�Ȃ邩�炾�B�v
�@���҂́u�ܘ_�A���̋Ȃ͐l�ނ̎���Ƃ������ׂ����y���B�w�^���x�ȏ�ɁA�ꕪ�̌����Ȃ��\�����꒮���҂̐S��h���Ԃ�B���y�͂����O�y�͂܂ł͓��ɂ����ł���B
�@�x�[�g�[���F���́A��l�y�͂̓V���[�̎��w����ɂ悹�āx��l�Ԃ̐��ʼn̂킹���ƌ��߂Ă����B�c��������ƑO�̎O�̊y�͂Ƃ̓��ꂪ�Ƃ�Ȃ��Ȃ�B
�@������`�F���ƃR���g���o�X�Ń����f�B���t�ł���B��Ńo���g���ɂ���ĉ̂��郁���f�B�Ɠ��������f�B�ł���B�w�����F��A����ȉ��y�ł͂Ȃ��A�����Ɗy�������y��t�ł悤�ł͂Ȃ����x�v
�����āA���̍����ɂȂ�B
�@�u�w�u���[���X���l�̌��l�ȉ́x�ł́w�l�݂͂Ȏ��ʁB���˂ΊD�Ɖ����x�Ɩ���ς��̂����̂��B�c�Ƃ��낪��������w�w�����˒��́x�̏o�����Ƃ悭�Ǝ��Ă���B�c�����˒��͋��������B�������Ă������Ă��c�Ɖ̂������Ȃ��Ă���v�Ƃ������B
�@����ɂ�����u�h���H���U�\�N���w�����̉́x�͏@���I�Ő��^�ʖڂȋȂ��B���̉̋ȏW�Ō�̑�P�O�Ȃɓ���ƓˑR�w��₱�A�����₱�c�x�̃����f�B���������Ă���v
�@�u�����˒��v�̍�Ȏ҂͒��R�W���ŁA�u��₱�v�͕s���ł��邪�A�u��v�̕������R�W���ł͂Ȃ����ƒ��҂͏����Ă���B����ȕ��͂�ʔ����ǂB
�@���A���R�ɍl���A�y������
�@���y�́A���S�N���̂̉��y�Ȃ̂Ɋy����ŁA���邢�͐l���̈����݂��S�ɟ��ݍ��މ�����������B����̓N���V�b�N�����ł͂Ȃ��B
�������A�����ɓǂ�Œ����镶�������邩�A���˂Ȃ��Ȃ�ɕ�����Ղ����ɂȂ邩�A�Ȃǂƍl���ĕ��͂������B����Ǝ��X���͂�������Ŗ��肪�Ȃ�B����ȂƂ��A�s�A�m��e���ƁA�]�̑S���Ⴄ���삪�����̂��낤�B�����������肷��B���y�̕s�v�c�ȗ͂ł���B����A�Љ�̎��Ԃ���A���y�̎��Ԃɐ�ւ����B
�@�w����N���V�b�N�x�̒��҂������悤�ɁA�ǂ�ȕ���ɂ��A�S���قȂ錩���Ƃ������̂͂���B�ٌ��������āA�قȂ錩��������Ƃ������̈Ӗ������炽�߂čl����B
�����Ƙb�������A���݂��d���Ȃ����v������̂�n��o���B���ꂪ���R�ł���Ȃ��疯��I�ԓx�Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B
�ǂ����̎̂悤�Ɂu���̓������Ȃ��v�Ƌ����ɂЂƂ�悪��̐����������߁A���F�����Ŏ�����ł߂�B���킢���ɂȂ����B
�@�u�T�O����̃s�A�m�v�Ƃ�������������B����S�O�l�ȏ�łR�����ɂP�\�����A�\���ƘA�e�̉��t�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��N���A���}�n�z�[���łW�O��ڂ̔��\��ςB
�@�d���𑲋Ƃ��ĂU�R����Q�����Ă��邪�A�P�O�N������V�O�߂���B�Ȃ��ɂ͂W�O�Ή߂��̐l�����l������B�Õ��Œe���l���B�������ԈႦ��Ƃ����悭���邪�A����҂̂ЂƂ�ł���B
�@�F�m�Ǘ\�h�̃g���[�j���O�ƐS���Ă���B
�@�I����Ă��瓯���N���X�̃����o�[�ƐH������B�u�y�������炱�̏�̂��߂ɗ���݂����v�Ƃ��A�u�ڂ��h�~���v�Ƃ��A�u�v�������ĂЂƂ��炵�ɂȂ����B���̉Ƃ���s�A�m����������B�Ⴂ�l���Z��ł���H�c�������v�ȂǂȂǁA�݂�ȂU�O��V�O��㔼�ł���X�����B����N�����炱���A�����܂ŏo�Ă�����A�����߂邢�܂Ɋ��Ӂv�ƌ��������Ȃ���B
�@���y������A�Љ�̎��Ԃ��y���݁A�����Ƃ���n�낤�B�c�莞�Ԃ����Ȃ����́B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w����N���V�b�N�x���Ҕ���T��(���~�ɐV��)�@�@�Q�O�P�T�E�P�E�Q�X
�@�@�@�@�@�@�@�d��������A�K���ł���
�@�q�ǂ��s�A�m���\��ɍs�����B�ꕔ���w����w����O�̎q�������������A�啔���͏��w���������w�N�ƌ����B�o��҂��悻�V�O�l���̐��̑����ɋ����B
�@���̎q�͑S������ꂽ�h���X�A�݈ߏւɂ��Ă��t�����X�l�`�̂��ł����A���̂�Ƃ�ƖL�����͂ǂ����B
�@����芴�S�����̂͂قڑS���Õ��Œe�����B�q�ǂ������͉��y��̂Ŋo���Ă��܂��̂��낤�B
�@���w���œ�ȃV���p���̃m�N�^�[���u���v��e���q�������B�Ⴂ�e�������K���ŃJ�������\������A���t���I���ƁA����̉�����K���F�B���e���ԑ������o���ĘJ���Ă����B
�@���͂S�N���j�q�A�u���̃����[�N���X�}�X�v�������őI��Œe�����B���w�P�N�̏��̑��̓x�[�g�[���F���́u�ߜƁv��R�y�͂��A��͂�Õ��Œe�����B
�@�ӂ���Ƃ��������ċȂ̐S���̂��Ă����B
�@����A�u�T�O����̃s�A�m�v�����ł́A�Ԃ��Ȃ��N�S������锭�\������Ă���B�N���̓��}�n�z�[���Œe���̂��B
�@���̋����ɎQ�������͎̂d�����I�����U�R�������B���ꂩ��P�S�N���߂����B���k���ߔ������V�O��ɂȂ����B
�@�U�O��Ȃ�܂��o���������w�������B���ꂪ�V�O��㔼�Ƃ��Ȃ�ƈÕ�����ρA�Ƃ݂�Ȃ������B�ł��A�c���d�������Ɋw��ł�͂�Õ��Œe�����B�ԈႦ�Ă������B
�@�����܂Ő��E�̉��y��t�ł��т�����������ꂽ�̂́A��͂��ȕҋȂŁA���Ƃ��N��肽���ɂ��e�������������悤�Ƃ������喼�_������A���y��o�̎Ⴋ�w���҂����̔M�ӂ��낤�B
�@�[�Ă��̉��₩�ȏ��~�̋�A�������V��ł���悤���Ȃ��ƁA���ƎU�����Ȃ���c�ɓ��������ł����B���A�k���̋�ɓˑR����ނ����悤�Ȍ��������_���������B
�@�V�C�\��ʂ�̊��C������Ă���̂��낤�B
�@���_�̏o���́A�܂�ł��̓��̂悤���B�P�Q���U���A�S�܂���o�������N�����B
�@���s�Ɏ������s�̌��A�����̉��\�ō���́u����閧�ی�@�v���Q�c�@�Œʉ߂������B
�@�m�[�x����܂��ӂ��ފw�ҁA�����҂����̔��A���{�ٌ�m��A���{�V���������{�y���N���u�A�����͉f��l��|�p�W�҂ȂǂȂǁA���́u����閧�ی�@�v�̊댯���𗝗R�ɔ��̐����������B
�@�ܘ_�����̂ӂ��̏��������A��R�̓��{�l���������̂ɁB
�@�����܂��ʼnB���A���ł��閧�ɂł��A��̑��Ō��Ƃ����u�����ێ��@�v�Ɠ����댯�Ȗ@���A�u�i�`�X�h�C�c�̂������w�v�������������A���̓��{�̓���傫���������B
�@�ǂ�Ȏ��ɂ��قȂ�ӌ��͂��邾�낤�B�B��A��͂��蓾�Ȃ��B���̖@���͔��̐��ɂ܂�Ŏ����X���Ȃ��B
�@�ǂ��܂Ŕ閧�Ȃ̂������܂��̂܂܁A���R�Ȕ������A����ɐ푈�������Ă͂��܂�Ȃ��B
�@�V�Q�N�O�̂�����ˑR�A�푈���I�ƌ���ꂽ�P�Q���W���A�T�������B���S���l���̖����D��ꂽ�B
�@�@�@�@�@�@���珎���͎��R�������B�����`�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�d�����������₩�ɐ������鐢�������B
�@���s�s�ȋ��s�̌��Ō��߂�ꂽ�閧�ی�@�A�P�Q���U����Y��Ȃ��B
�@�U�O�N���ۂ̂Ƃ��A���s�̌������͓̂����̊ݎA���{�̑c���ł���B���̂��ƂŔ��Ή^�����S���I�ɍ��܂����B
�@�������ō���߂��ɁA�W�P�W�����e���g���Ē�R���Ă���l����������B
�@�������A�p�~�܂ŁA�Ⴂ�l�����Ƌ��ɁA�V�l���o���鎖����낤�B
�Q�O�P�R�E�P�Q�E�P�P
�@�@�@�@�@�@�@�u���̎�͂��ꂢ����Ȃ��v�@�t�W�R�E�w�~���O���R���T�[�g�ɑz��
�@�R���T�[�g�z�[���ł̐����t�͋v���Ԃ肾�����B
�@���t�҂̐l�C�f���āA�������Ȃ̂ɂP�K�͒������A�Q�K���قږ��ȂŁA�R�K�Ȃ����͂�Ƃ肪�������B���t�҂̊炪�����Ȃ��A���p�����������̂��c�O���������B
�@�s�A�m�\���͂��ׂĊy���Ȃ��̈Õ��A�P���ԂS�O���قLj���������M���������B
�@�o�b�n����n�܂��āA���X�g�́u�J���p�l���v�܂łT�ȁA�Ƃ��Ƀ��\���O�X�L�[�́u�W����̊G�v�́A�\�����t�Ƃ��ď��߂Ē������B
�@�l�X�Ɉڂ낤�l���̂Ƃ���A�z�������B�͋����A�D��ɁB�I�͂ɋߕt���ɂ�A����ɂ����炩�ɁA���₩�ɂȂ��Ă������B���̋Ȃ��悻�S�O���Ԃ�e�������t�W�R�A�w�~���O�̕\���͂Ɋ��������B
�@�Ⴍ�͂Ȃ��̂ɁA���̗̑͂ɂ͒E�X�ł���B
�@���́A���@�C�I�����Ƃ̋����A
�@���@�C�I�������A���@�X�R�E���@�b�V���t�Ƃ����u���K���A���܂�̂S�R�A�P�X�W�V�N�p���̃������e�B�{�[�R���N�[���ŗD�����A���E�ő劈�Ă���Ƃ��B�m��Ȃ������B
�@�Ƃ��ɑc���u���K���A�Ŏw���҂Ƃ��Ă����Ă���A�u�R���T�[�g�ɂ͂R���l���̐l������������X�^�[�v�ƐV���Љ�ɂ������B
�@�t�炵���x�[�g�[���F���̃\�i�^�T���u�X�v�����O�\�i�^�v���n�܂�A�����Ȃ蒮�O�������Â��ɂ����B���邢���@�C�I�����̏t�炵�����F�A�����������̃s�A�m���t�W�R�E�w�~���O�Ƃ����ґ��B
�@�Q�Ȗڂ���D�����}�X�l�[���u�^�C�X���ґz�ȁv�A�������B����ȏ���ґ�͂Ȃ��Ǝv�����B
�@�e���݂̂���Ȃ���̑I��́A���炭�t�W�R�E�w�~���O�̍l�������낤�B
�@��N���ɏo�ł��ꂽ�����œǂB
�@�u�N���V�b�N�̐��E�ł́A�Ȃ��N���m��Ȃ��悤�ȋȂ�I�Ԃ́H�@�e���݂������Ċϋq����Ԃ悤�ȋȂʼn��t������Ȃ�����E�E�E�v
�@�u�s�A�j�X�g�͂��ꂢ�Ȏ�����Ă���B���厖�ɂ��Ă��邩��B���̎�̓S�c�S�c�Ƃ����Y�킶��Ȃ��B�����邽�߂ɘJ�������肾����B���܂܂Ō���Ȃ��������ǁA�������Ȃ��ĕa�@�̑|���w���������Ƃ��������v�ƌ����B
�@����̋Ȗڂɂ��郊�X�g�́u�n���K���[�����ȁv�ƁA�u���[���X�́u�n���K���[���ȁv�ɂ��āA�u�Ƃ̂Ȃ��悤�ȕn�����l�����̉��y���������ȁA�����Ƀ��X�g�Ȃe���ȂƂ���ꂽ���A���X�g�͕n�����l�����ɐS������������A�����Ɏ��X���č�����̂�v
�@�ȑO�ǂ����ɂ����������Ƃ��v���o�����B
�@��w���҃o�[���X�^�C���Ɏ莆���o���u���̃s�A�m���ė~�����v�Ƒi�����B
�@�P�X�V�O�N�R�T�ɂȂ�A�E�B�[���Ń��T�C�^�����J���邱�ƂɂȂ����B���ɖ�����������͂��������B����悤�ȗ₽�������������A�q�[�^�[�ɂ��ׂ�ΒY���������Ȃ��āA���M���o�����ׂ������Ă��܂����B�P�����݂Ȃ��玨���������Ȃ��Ȃ������Ƃ�m�����B
�@���t��͎��~�߁A�s�A�j�X�g�@�t�W�R�E�w�~���O�ɐ�]�̓��X���������B
�@�H�ׂ镨���Ȃ��āA�����n�鏒�����̓��X���������B
�@���ꂪ�A�P�X�X�X�N�A�m�g�j�̃h�L�������^���[�ԑg�u�t�W�R�@����s�A�j�X�g�̋O�Ձv���唽�����ĂсA����L���ɂȂ����B�����́u�x���Ȃ��Ă��҂��Ă���v�������ɂȂ����ƌ����B
�@���ł́A�P�ȏI���ƎႢ���@�X�R�E���@�b�V���t���A�t�W�R�E�w�~���O�̎������ė����オ��A���O�ɓ���������B�����Ď��̋Ȃ�e���̐��ɍs���B
�@���y��t�ŁA�l�ւ̈���e���ꂾ�����B
�@�����Y��Ȃ��B�ƂȂ��l�����{�ɂ���R����B�̂���n�����l�����ƖL���Ȑ����̐l���������B
�@�R�E�P�P��k�Ђł��悻�Q���l������D��ꂽ�B���ݏZ���o��ꂸ�A�����̂߂ǂ������Ȃ��l�������P�T���l�B�������̂̕��˔\���S�z�ŁA�Ƒ����ɂȂ��Ă���l�������R�O���l�����邱�Ƃ��B
�@�t�W�R�E�w�~���O�́A�u�������i�܂ꂽ��������B�����Ȑl�ԂȂ�Ă��Ȃ��B���R�̂������v�Ƃ����B
�@�}�l�̂��Ȃ�Ȃ��̂��ƁA�l�ɖ��f�������������ꂽ��B�l�͈�l�ł͐������Ȃ��B�s���S�Ȑl�ԓ��m�A�݂�Ȑl�Ƃ̂����M���W���Ɗ���Đ����Ă���B
�@���ӂ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
�@�t�W�R�E�w�~���O�̉��y�͋�J�l������������A�S�ɟ��݂�B
�@����ŎQ���ł��Ȃ��Ȃ����`�P�b�g���ƁA�F���U���Ă��ꂽ�R���T�[�g�������B
�@��X���߂��A�Q��ڂ̃��b�V���A���[�ō��G����n���S�̃z�[����
�u���Ă��ȉ��y�ɐZ�ꂽ��Ƃ�ƍK���ɁA���ӂ��Ȃ�����l�v�ƌ����Ȃ���F�ƕʂꂽ�B
�Q�O�P�R�E�R�E�X
�@�@�@�@�@�@�@�T�O�N�ƂT�O��ŏI���N
�@�����ƋC�Z�����N�̐��ɁA�P����u�I�C�I�C�v�s�A�m���t�����������B
�@�R�����ɂP�邻��́A�P�N�łS��ɂȂ�B�������N���̓��}�n�z�[���Ƃ����啑��ł̉��t�ł���B�T�O��̔��l���������邩��u�I�C�I�C�k�V���V���l�v�ƌ����Ǝ����邩������Ȃ��ȁB
�@����ł��A�Q���҂̔����ȏ�͂V�O��ȏ�ƌ����邩��ԈႢ�Ƃ������Ȃ��B
�@����̗��e�ɍ��ȉԁX�������A����₩�ȕ���ł���B�҂��Ă���P�O�O�O���~�ȏ�̃O�����h�s�A�m�������璭�߂�B
�@���Z�܂Ńo�c�`���s�A�m���K�����Ƃ��������́A������Ƃ���͋����^�b�`�Ƒ����e���|�Œe���B���̌オ�d���𑲋Ƃ��āA�U�R����n�߂����̏o�Ԃ��B
�@�Ȃ̓g�������́u�Q���̃Z���i�[�f�v�A�O��t�H�[���́u�V�`���A�[�i�v�̈Õ��������ԈႦ���̂ŁA��r�I�ȒP�ȋȂɂ����B�Ȃ�Ƃ��Õ��ŋȂ̕��͋C���o�������H
�@�W�O�߂��āA�^�����ɂȂ������̐l�����X�ƃ����Q�́u�Ԃ̉́v��e�����B
�@���N�Љ�œ����Ă���Ȃ�̒n�ʂ������낤�Ǝv����j�����A�u���̋�����ȁu�X�C���̌��z�v���Õ��Œ�������B���\��̂��߂ɂ݂�ȗ��K��ς�ł����B
�@�`���C�R�t�X�L�[�́u�M�́v��A�^���z�C�U�[�́u��s�i�ȁv�A�����́u���l��́v�A�N�Ȃ̂ɂ݂Ȃ����X�����̂́A�w�Ŕ]���h�����邩��H
�@�܂��܂������Ă���V�O������邢�܂̎���ɁA�����͔�Вn�Ő�̌����Ȃ��s���ŔY�ޔN�����������Ƃ����̂ɁA�������܂߂ă����o�[�͌b�܂�Ă���l�������B
�@�ł��A�V��Љ�ŎႢ�l�����ɖ��f�������Ă͂����Ȃ�����A�撣��V�l�����I
�@����o���҂͂R�T�l�A�\�����t���I���Ǝ��͘A�e�A�Q�l�g�Ńe���|�����킹��̂�����B����ł������I�������B�����B
�@�ƁA�ˑR�d��ɌĂ�ċ������B�\�����ꂽ�̂��B
�@��ɂ́u�{�u���͉��t��T�O��o�����ڕW�ŁA�����B������܂����v�Ƃ���A���̐l�����Ɛ��́A�p������\�͂����͂���̂��낤�ȂƁA�߂����P�R�N�̂Ƃ����v�����B
�@�����A������u�t�����̉��y�ւ̏�M���������B
�@�������ĉ��y��͏I��������A���킽�������N�����I�����I������B
�@���ʂ́A�u���h�R�v���́u���@�ς���v���̉E�X���̕|�������������B����͂����������A�푈�͎E�������A���ꂾ���͐�_���I
�@�����āA���Ղ������ĉғ��Ƃ����_�o�̐�������������˂ƁA�����A�푈�̌��҂̘V�l�͒Ɋ�����B
�@�������o�ώY�ƏȑO���S�V�Q�����e���g���Ĕ��������咣���Ă���l���烁�[�����͂����B�u�������t�����Ńe���g���߂��錠�͂Ƃ̊W�͕ς�邾�낤�v�ƁB
�@���������A���˔\������˂Ȃ�Ȃ��B�q�ǂ������̖������B�����Čo�ς���A��������ׂ����B�S���̓��[�łV���̋c�ȂɂȂ��������}�A�݂�ȂŌ����葱�������B
�@���N�������̏W�����q�ǂ��������J���Ă��ꂽ�B
�@���R�Ȃ���A�T�O�N�ƂT�O���@���ڏo�x�����Ƃ��B�������Ɋ�ڂ��B
�@���ӖY�ꂿ�ᔱ�����肾�B
�@�u���O�o�����������B�����C�ɂȂ�Ȃ�v�ƁA�����Ő��������B
�Q�O�P�Q�E�P�Q�E�R�O
�@�@�@�@�@�@�@���s�A�m�@�܂��s�A�m
�@�u�������́A�s�A�m�͂��[���ƂÂ��Ă��������v�B����ďZ�ދ��s�̑�����莆���͂����B
�@���̉Ă͍��������������A�A�ꍇ�����M���ǁ��]�����������������A�v�������Ȃ��a�@��~�}�Ԃɂ����b�ɂȂ����Ă������B�ꎞ�͈ӎ��s���Ŋ�Ȃ��������A��t�����̌��g�I�Ȍ����Ə��u�A�Ή��������������ƂŁu�^���ǂ������ł��ˁv�Ƃ�����t�̂��ƂΒʂ�A�P�����]��̓��@�ʼn��Ƃ����ʐ��������߂����Ăł���B
�@����Ŏ㒎�̉��l���A�����Ɣ�J�Ń_�E�����O�ɂȂ�u���낻��s�A�m���I���ɂ��悤���ȁv�Ɩ����������B�R�����ԁA�s�A�m�����͂������Ȃ��Ȃ����B
�@�u�����̂悤�Ȏ�ŃX���X���e������̑��Ɛ��ɁA�����Ō��ǂ̕����o������Ȏ�Ȃǖ{���͏o�������Ȃ��v�u�Ⴂ�Ƃ����特�y�D���A���ɃN���V�b�N�͂悭�������B�ł����l����Ƃ������낻����ނ��ׂ��H�v�u���̃s�A�m�͖S���`�ꂪ�����������N�������������ǁA�ЂȐl�`�H�s�A�m�Ȃ炢�����ǁE�E�E�ƌ����ē������o���Ă��ꂽ�B������n�����ƌv���猎���ŕ��������Ď�ɓ��ꂽ�s�A�m�Ȃ̂��v���߂���e���Ȃ����낤�B
�@���ꂱ��l�������������A�ꂵ���Ă������B
�@����ȂƂ��A���s����͂������̎莆�ł���B���̎莆�ɂ͉Ԃ�����Ă�̂��D���Ȃ������ɂƁA�j���W���Ƃ��ڂ��̎킪�����Ă����B�莆�ɂ́u�������ɉ]��ꂽ�悤�ɁA�P���P��̓s�A�m�ɐG���Ă��܂��B�������Ƃ��ł݂�ȂłЂ�����܂��傤�v�Ƃ������B���w�S�N���̂��̑��́A���\��ł̓G�X�e����ȁu���l�`�̖��Ƃ߂��߁v��e�����Ƃ����B
�@���������A���É��̑������w�T�N�Ń��[�c�@���g�́u�s�A�m�\�i�^�P�Q�ԁv��e�����B���̒���o�����ɂ��ĂP�N������ꏏ�ɒe���Ă���B�킪�ƂŒe�����Ȃ̓G���������C�q��Ȃ́u�ނ������v�������B
�@�q�ǂ��͊o����̂������A�����Õ����Ă��܂��B�������́A�R�����ɂP��̔��\��Ɍb�܂�A�P���ɍl���Ă��N�S��A�P�O�N�łS�O����l�O�ʼn��t�����v�Z�ɂȂ�B���\��͂P����x��ł��Ȃ��B�p�����邱�ƁA���ꂾ�������\���Ȃ��B
�@���\��Ƃ����R�N�O�̂ق�ꂢ�̌����v���o���B�L�����ł̔��\��ŁA�ǂ����e���Ȃ�Ɠ�Ȃ̃��X�g��ȁu�n���K���A�������ȂQ�ԁv�ɒ��킵���B���\��ƒe���Õ��܂łł����B
�@�����{�Ԃō��ƉE���I������Ȃ��B��蒼���B�܂������Ń_���B����ł�����̏ォ��u�����P�x������点�Ă��������v�Ɠ����������B����ƒe�����u�n���K���A�������ȁv�������B�u�N���Ɛ}�X�����Ȃ�v���{�̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ��ɂ͂������Ƃ��ŁA���݂��̂悤�Ȏ�ňÕ���������O�ɒe���������A���̕�e���A�����݂�ȂŒe���A����ς�y�����B�������̒a�����ɂ��ꂽ�莆�A�����ɂ́u�s�A�m���Â������������ł��B�݂�ȂŃs�A�m������ł��B������s�A�m���Â��邱�Ƃɂ����Ƃ����āA��������Ǝv���܂��v�ƁA�قƂ�ǂЂ炪�Ȃ̎莆�ɁA�v�킸�ɂ�����A���p���オ�����B
�@����ɁA���낢�덢��Ȃ��Ƃ��N���āA���̒��̎��⎩������肽�����Ƃ����ɂᐶ���Ă���b����Ȃ��Ȃ��Ă����B���ꂩ��̍���Љ�ŁA����ɂȂ��Ă��s�A�m�����̂悤�ɂV�O�A�W�O�ł��A���C�ɉ��y���y���ސ�y�����A����͋M�d�Ȃ��ƂȂ̂����m��Ȃ��B
�@�X�ɁA�����₩�ł������̖ڐ��ŕ�������������B���̂��Ƃ��A�l�b�g�̂g�o�̏[���Ɍq����B��������������u���Ȃ��̕��͂����A������ɖ|�Ă������v�Ƃ������[�����͂������ƂŁA�C���^�[�l�b�g��g�o�̗͂��������܂��ꂽ�����v���o�����B
�@�A�N�Z�X�̑����A�ꍇ���̂g�o�Ƌ��ɁA���̂g�o���u�����߃T�C�g�v�ƌ����ĉ����鋳���ɂ��A�傢�ɗ͂�Ղ����B
�@�F�������w�҂̂r�����A�����̐V���ɏ����Ă����B
�@�u�f�l�̉��y���D�҂ɂƂ��āA�l�O�Ŋy�������t�ł����Ƃ�����A���t�̏o���A�s�o���Ƃ͊W�Ȃ��A����ق��ґ�Ȍo���͂���܂���v�ƁB�u���y�̕s�v�c�A������̕s�v�c�v�Ƒ肷������ŁA���̋@��^����ꂽ�Ƃ����B
�@���̂����������A���悻�P�O�N����킹�Ė�����B�d���𑲋Ƃ��U�R����n�߂��s�A�m�����́A���E�̖��Ȃ�A���喼�_�����̍�ȕҋȂ̋Ȃ��A������o���Ⴂ�搶�������A�N���X���ɂ��邢�͌ʂɎw�����Ă����B�����ĂR�J���ɂP�\�����B������A�Ⴂ������e�����I���e������A�U�O�߂��ď��߂ăs�A�m��e���l���A�^���ɗ��K�ł���B
�@�F�������w�҂r���́u���ׂē��̊��o����b�ɂȂ��Ă��āA����炪�]�̒��̑B��ԂƌĂ�镔���ɒ~�ς���A���ӎ��̋L��������l�Ԃ炵�������Ɍ��т��̂������ł��v�Ƃ������Ă����B�܂�݂�Ȃ������Ă���{�P�h�~�Ƃ��������B
�@�R���̓����{��k�Јȗ��A�ꓬ�����̔�Ў҂������B�ł��A�o���邱�Ƃŗ�܂������A���������Ȃ���A�܂��܂���邱�Ƃ͎R�قǂ���B
�@�����Ő搶�ɁA���̎莆�̂��Ƃ��`���b�Ƙb������u���������v�ƌ����Ă��ꂽ�B
�@�����邱�Ƃ����\�̂Ȃ��҂͍l�����B�u�p������͔͂\�͂��v�ƌ����_���C���}����ɗ�܂���A�s�A�m�͑����Ă݂悤�B
�@���y�̕s�v�c�A�S�̕s�v�c�����邩��B
�Q�O�P�P�N�P�O���P�X��
�@�@�@�@�@�@�@�V���p���u�ԑ��̒��ɉB���ꂽ��C�v�@���P���k�`�F�E�\���G�l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V���p�����a�Q�O�O�N�ɐV���Ȕ���
�@�͂Â悢�@�V���p�����t
�@�Ⴂ���u�J���v�ƌ����A�����l���C�y�ɃR���T�[�g�ŃN���V�b�N���y�ɐe���ރ`�����X���������B���A�Ŗ����̂悤�ɐ����t���������B
���̉āA�v���Ԃ�̃R���T�[�g�ŏo������s�A�j�X�g�y��_���̉��t�́A����ȏ�M�I�ŗ͋����V���p�����������̂��ƁA�����Ɗ����Œ������B
�y��_���͐��X�̏܂���܂��Ă���A���{���\����s�A�j�X�g�̈�l�ł��邪�A�P�X�X�O�N�ɁA��P�Q��V���p���R���N�[���ōŗD�G���t�܂���܂��Ă���B
�X�V�N����A�u���N�`���[�R���T�[�g�v�ŁA���@�C�I���j�X�g�ܓ��݂ǂ�ƁA�S���e�n�̏��w�Z�A�{��w�Z�Ȃǂʼn��t���Ă���B
����́u�V���p���̗��Q�O�P�O�v�Ƃ��āA�k�C�������B�܂ŁA�S�������R���T�[�g�������B
�V���p���́A�@�ׂȊ��o�ƗD��ȏ���Łu�s�A�m�̎��l�v�u���}���h�̃s�A�j�X�g�v�ƌ�����̂��ӂ��ł���B���ꂾ���ł͂Ȃ����Ƃ��A���̖{�̒��ҁ@���@�P���́A���g�s�A�j�X�g�Ƃ��ċ�̓I�Ȑ��X�̎����ŋ����Ă��ꂽ�B
���̈�́A�V���p���̑c���������|�[�����h���������Ƃɂ��ߌ��ł���B
�@�|�[�����h�͖k�Ƀ��V�A�A���Ƀv���C�Z���k�h�C�c�l��ɃI�[�X�g���A�Ƃ����卑�Ɉ͂܂�āA�P�V�V�Q�N�ɑ�ꎟ�����ȗ��A�X�R�N�A�X�T�N�Ƒ�O�������ŁA�|�[�����h�Ƃ������́A����ɖŖS������ꂽ�Ƃ������j������B
�@��R�^���ŗՎ����{������Ă��A��ʎE�l�ō��ƖŖS�Ƃ����ߌ����J��Ԃ���A���̒��ŃV���p���̉��y�����܂ꂽ�B
�M�҂́A�ݓ��̃s�A�j�X�g�Ƃ��ċ�ɂ�̌����Ă��邩��A�ڂ̕t����������Ă����B
�@���҂̕��e�́A���f�����O�̖k���N�ɐ��܂ꂽ�B�ЂƂ�łR�W�x�����z���A�����Ŋw�����҂��Ŋ؍��̑�w���o������A���N�푈�ɂȂ����̂ŁA����������ē����̂�����ŁA��̓��̎R���ɐ��B
�ǂ����Ă������������ē��{�ɗ������A�����ӂ����ѐ��܂�̋��ɋA�邱�Ƃ͂Ȃ��A�c���̎��ɖڂɂ���Ȃ������Ƃ����B
�@���҂̓A�����J�ɍs���A�A���ł��Ȃ������m��Ȃ��Ƃ����ɂȂ����Ƃ��A���̋ꂵ�݂������ł��A�V���p���̐l�����A���������{�Ő����čs�����ƂƏd�Ȃ����Ƃ����B
�@�c����z���V���p��
�@�|�[�����h�̐l�X�́A�c���ɐN���������ւ̒�R�S���A�������̒��ɔR�₵�Ă����B
�c��������˔\�������V���p���́A�P�T�̂Ƃ����V�A�c��̌�O���t�ɏ����ꂽ���A�F�l��������͏o����f��悤�Ɍ����A���͊��߂��̂ŏo������B
����Ȓ��ŕ��G�Ȏv��������悤�ɂȂ����V���p���������B
�P�W�R�O�N�V���Ƀt�����X�v���u���ŁA�|�[�����h�ł����V�A�ɑ����R�^���������ɂȂ�A�Q�O�̃V���p���́A�v��ʂ肱�̂܂܉��y�̂��߂ɁA�I�[�X�g���@�֏o�����Ă����̂������������B
���̂Ƃ��A�F�l����܂��Ă��ꂽ�B�u����������ē������Ƃ��������ɐs�������Ƃł͂Ȃ��B���y�ƂɂƂ��Ă̕���͉��y���v�ƁB
�u���y�������āA�|�[�����h�̔ߌ��𐢊E���ɋ�������̂��v�B�������S�������̂́A�E�B�[���ɍs���V���p���͖����������B
��x�Ƒc���ɋA��Ȃ��̂ł͂Ɩ����Ȃ��獑�𗣂ꂽ�B
�|�[�����h�̐l�X�͓���I�ɂ悭�̂��A�悭�x�邻���ł��邪�A�|���l�[�Y�͒j���I�A�}�Y���J�͐��y�I�ŁA�V���p���͂U�O�Ȃ��܂���}�Y���J����Ȃ��Ă���Ƃ����B
���K�ȁu�v���v�A�|���l�[�Y�u�p�Y�v�A�u�R���v�A�Ƃ�킯�͋����^�b�`�Œe�������K�ȁu�v���v���Ȃ���A�����ŖS������������v�����B��R�^���Ŏ��R�ȑc�����肤�l�X�̐S��������A�͋����Ɉ��|���ꂽ�B
�V���p���́A�����̃V���[�}����A�P�Ή��̃n���K���[�o�g�̃��X�g�ɗ�܂��ꂽ�B�V���[�}���͉B���ꂽ��R���_���������āu�ԑ��̒��ɉB���ꂽ��C�v�ƌ����A���̍˔\�ɂ��Ă��u�V�˂��B���N�E�X�����܂��v�Ɛ��̒��ɐ�`���Ă����ƌ����B
�@�n���K���[���܂�̃��X�g�́A�u�V���p���̃|���l�[�Y���ƁA�^�����������邠����s���Ȃ��̂ɁA�E���A��_�ɗ����������l�Ԃ́A�m�łƂ��ďd�X�����A�Ƃ����悤�Ȍ`�e�ł͕\�����ʂقǂ́A�������v��������v�ƋL���Ă���B
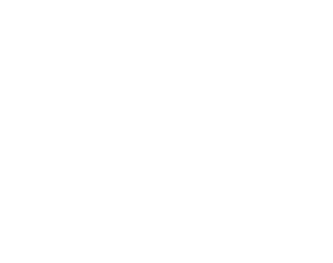
�w�|���l�[�Y�xOp.�T�R�A�p�Y(�P�X�R�U�N�A���M��)�B�o�ł͒x���P�W�S�R�N
���X�g�́A���̋Ȃ��|�[�����h�̈̑傳�̕\���Ƃ��Ă���
�@�V���p���̉��y�́A�h�C�c��p���̐l�X�ɂ͐������ꂽ�������A���I����A����ɉؗ킳����ɐS�����Ă����悤�ł��邪�A���l���̉��y�Ƃ����́A�ނ̎v�z�ƃ|�[�����h�̓y�Ɨ܂��A�V���p���̉��y���`����Ă���Ɗ����Ƃ��Ă����B���̂悤�ɒ��҂͋L���Ă���B
�@�V���p���̕]�`�Ń��X�g�͏����Ă���B
�u�V���p�������x���J��Ԃ����Ƃ����w�U���x�k�|�[�����h��͂y�`�k�W�����ƕ\�L����l�Ƃ�����ɂ́A�j������A���邢�͓ł��ꂽ�ʎ��Ƃ������ׂ��A�������瑞���݂ɂ�����܂ł́A����Ȋ�����܂ނ̂ł���v�ƁB
�@�p���Ŋ��Ă��A�c���ɋA�ꂸ�N���c���������Ă���Ȃ����_�A���߁A�r�����ɔY�݁A���y�̂Ȃ��ɂ������������Ă����B���҂͂����L���Ă���B�ݓ��Ƃ������g�̑��݂ł����q���ɗ����ł��邱�Ƃ��Ǝv���B
�@���t���������Ȃ���ΐH�ׂĂ�����Ȃ������̉��y�ƁA�V���p�����ɉh������߂Ă����C�M���X�ɏo������B�������ӔN�A�a�łP�V�O�Z���`�̐g���ɁA�̏d�S�O�L���O���ɂ₹���V���p���́A���t���I���ƋC�₵�����ɂȂ��āA�x�c�g�ɉ�������Ă����Ƃ����B
�@�ʔ��������̂́A�U�ΔN��̃W�����W���E�T���h�ƂX�N�Ԑ��������ɂ��A������ƂɌo�ϓI�ɂ�������ꂽ�V���p�����A���߂ĉ�����Ƃ��u����ł������ł����H�v�ƌ������G�s�\�[�h�ł���B
�@�v����������͎Q�������Ȃ����͉ƒ�����Ƃ��������̒��ŁA�j���̃W�����W���E�T���h�𖼏��A�Ƃ��ɂ̓X�J�[�g�łȂ��p���^�����p�������Ƃ��������̗��s��Ƃ������B
�@���y�̕s�v�c�ȗ�
�@�l�͗l�X�ȕ�炵�̂Ȃ��ŁA���肠�閽��z���A���y�ɖ�����s�v�c�Ȉ��炬���o����B
�P�O�O�N�o���Ă��A�Q�O�O�N�߂��Ă��A���y�͐����Ă���B
�t���ォ��A�V���p���́u���z�����ȁv�́A��Ԑg�ɟ��݂Ē����������Ȃł���B
�d�n�Z���̂��̋Ȃ́A�n�߂͑����e���|�Ŏ䂫���A�t�̑傢�Ȃ閲�̂悤�Ȃ��̂���������B���ԕ��͂̂т₩�ɁA�������悤�ɃJ���^�[�r���ŁA���R�Ƃ������S�̂悤�Ȃ��̂������������B
�f�l�Ȃ���A�Z���̈��������Y���ŁA�������ƈ��炬�Ɏ������̂������ČJ��Ԃ��������t�������B
����ɁA�u��z�ȂQ�O�ԉd�n�Z���@���v�ł���B�f��u���̃s�A�j�X�g�v���ςė]�v�D���ɂȂ����Ȃ��B
�@�u�V���p�����a�Q�O�O�N�v�͊Ԃ��Ȃ��I���B
���̖{�́A���y�̐V�N�ŁA����ȉ������������悤�ȋC���ɂ��Ă��ꂽ�B
�@�@�@�@�@�@�@�s�A�m�̓��@
�@�k��l�A�Q����
�@�u��ς��B�l���̑�a�@�֓��@�����āv�B�u�����H�@�ނ��H�v�u�~�}�Ԃʼn^�ꂽ�́H�@�a���͉��H�v�@���ǂ��̗F�l�����������܂܁A�u���j�����j���v�ƁA�d�b����Ă��܂����B
�@�a�C�œ��@�����̂̓s�A�m���B�Q�N�ɂP�Ă��钲���ŁA�s�A�m��峂������Ă��邱�Ƃ����������B����͑�ςȂ��Ƃ��������B�L�[�̍������Ă���t�F���g������Ă����B
�@�����̐l��峂̌����������Ă��ꂽ���A�悭�ڂ��Â炳�Ȃ��ƌ����Ȃ��قǏ�����峂ŁA�m���Ƀt�F���g������Ă����B�s�A�m�͖����S�̂Ƃ�����������A�����R�O�N�o�B
�@�������u���Ȃ��ƁA�L�[�����ĂȂ��n���}�[�̕����H���āA�ςȉ������o�Ȃ��Ȃ�B�ꍏ�������ق��������B�Ƌ����ꂽ�悤�Ȋ����������B
�@�u�s�A�m���ւ����܂����H�v�u�������̏I�����߂��̂ɁA�V�����s�A�m�Ȃ�āE�E�E�@����ɁA�����������ꂼ��s�A�m�����邵�ˁv
�@�u�Ƃ���ŁA����̓��@��͂�����ł����H�v
�@�u���m�ɂ͖����킩��܂��A���悻�P�T���~�قǂ��Ǝv���܂��v
�@�����Q���~�ƂP�T���~�A�����A�Ƃ�킯�ސE�҂ɂƂ��Ă͑�����B�ł��A���̂܂ܕ��u����킯�ɂ͂����Ȃ����E�E�E�B�����Ȃ�̂́A�P�Q�O��ɂP��̊����Ƃ��B
�@����̓��@�����́A�l���I�͂̏ے��݂����Ɏv�����B���܂ł��Ⴍ�͂Ȃ���B�������̑̂�����A�����������݂����Ă���ł���H�@���̓{���{���A�ڂ́A�y���ƃp�\�R���A�����Č���ƃ{���{���ł���H
�@���낻��s�A�m���߂���H�@���ߏ����Â��ɂȂ��Ċ��邩����B
�@����Ȑ����������Ă���悤�ȋC�������B�s�A�m���e���Ȃ��āA������������Ƃ́A�ǂށA�����Ƃ������Ԃ��s�A�m�̕��������������ƁB�ł��A���̓����牽���ςȂ̂��B
�@���܂܂ŐV���ǂ�A�����͐H�����ς�ŋ͂��̎��ԃs�A�m�ɐG��B�l�Ԃ̔]�́A�����t�ł�����Ɋm���ɔ�������B�߂����Ƃ��A������������Ƃ��s�v�c�ȗ͂�����B
�@�S�R�Ⴄ�C���ɂȂ��āA���̎d���Ȃ�Ǐ��Ȃ�ɐ�ւ��Ă����B
�@���̂Q�T�ԁA����Ȕ]�̓]�����o�����A�����f�B�ɋQ�����]�ŎU���ɂ��Ă��Ǐ��ɂ��Ă��A��������̋�Ƃ������A���ĐH�ɋQ�����悤�ɁA�����ɋQ���������������B
�@�k��l�A�S�ȈÕ��Œe���ʂ��B�V�N�@�͋����V���p��
�@�H�����I���B���ƂȂ��s�A�m�̂ӂ����J���Ă��܂����B����͖̂̔���A��������Ƃ��������ׂ̍��_�����ԓ���B������Ƃт����萮���T�Q�{���A�������t�F���g��̕��ɕ����ĕ��ԁB�L�[�̐����B
�@�����P��́A���������_���Q�{�ƂR�{�A���݂ɊԊu���Ƃ�Ȃ���V�g���ԁB�[�����ɂ����P�{�������܂��č��v����R�U�{���B�@���ꂪ�����ȂȁB
�@���g�Ȃ��́A�P�Ȃ����ۂ̓��ꕨ�A���h��̑傫�Ȕ��ɉ߂��Ȃ����A���y�Ƃ������̂�n�肾����{���B
���E�̐l�X�̐S�����S�N���̊Ԗ����������鉹�y�Ƃ́A�Ȃ�ƕs�v�c�Ȃ��̂��B
�@�������̊W������B����ƁA�Â��Ƀ����f�B������n�߂��B
�@�V���p���́u�J����v�A���l�W�����W���E�T���h�ƃ}�W�����J���֓]�n�×{�ɍs�����Ƃ��̍�i���B�v�킸���X����B�����Đt����ɖ����Œ������u���z�����ȁv���B
�@����A�s�����V���p���̗[�ׁA�j�����s�A�j�X�g�͂�������l����̒������D�u�ƕ����Ă����B�����āA�����Ȃ�u�p�Y�|���l�[�Y�v��e�����B
�@���̗͋����Ɉ��|���ꂽ�B���̋Ȃ��I�������A����̕Ћ��ɖ߂�}�C�N�Ō��n�߂��B
�@�u�V���p���͂P�V�Ŗ�z�ȂP�X�Ԃ���Ȃ��܂����E�E�E�v�B
�@��l�ʼn�����A��l�Ńs�A�m�Ɍ������B�c���|�[�����h�����V�A�ɐ�̂���p���ցA��x�Ƒc���̓y�͓��܂Ȃ������B
�@�s�A�m�̎��l�Ƃ�����V���p���B���̃V���p�����c�����v���Ȃ́A���t������ɗ͋����Ȃ��Ă����B
�@����ȗ͋����V���p���͏��߂Ē������B�S�āA�y���Ȃ��̈Õ��������B
�@�]���V���p���ɌX�|�����̂��낤�Ǝv�����B�o�𗓂Ɂu�y��_���A�S����s�A�m���n�߁A�P�X�X�O�N�ɃV���p�����ۃs�A�m�E�R���N�[���ōŗD�G���t��܁v�Ƃ������B����ς�ȁB
�@�k�O�l�A�����Ƃ�����
�@峂����̂����₫���������o�����B
�@�u���ꂽ���A�������Ă��܂������ǁA���܂܂ł̂悤�Ƀs�A�m�e���낤���H�v
�@�u�P�O�N�͂悭�e�����������ǁA�ӂ��J���Ȃ��Ȃ�A���ꂽ���̗V�я�ǂ�ǂ₻���v
�@����A���߂��ɍH������̖T��ʂ�����A���������z�C�Ȃ̂ɁA�z�������ĎQ�����B�������牊�V���A�g���b�N�̉��ɂ����肱��ŐQ�Ă���l�������B���̋x�e�ꏊ���Ȃ��E��B
�@�����̂���A���V���߂��ɉƂ��o��B���S�ɂQ�O������Ė��É��w�ɒ����B�w�߂��̎��]�ԗa����ɒu�������]�Ԃł��悻�Q�O������Ɗ����X�ɒ����B
�@�Z�������Ԃɖ������ĉ��ς��Ă��A�E��ɒ�������͊��ł������藬��A�����҂�𔘂��o���ăf�X�N�Ɍ������B���̕����ł͂P�T�N�ԓ��������A�w�ǂ��j���̏o���R�[�X�g�A�����͋͂��ŁA�Ɛg�Œ�N�܂œ����L�����A�E�[�}�������������B
�@�P���̕�Ƃ��ē��������A�Q�Ԗڂ̎q�̂Ƃ��Q�x���Y�̌��������B���̕����ɕς���ĊԂ��Ȃ��ؔ����Y�ɂȂ����B
�@��t�̐f�f�����o���ē]�Α��X�x��ł��܂��A�o�Y�܂ő����������B
�@�u���Y�܂Ȃ���A�N��I�ɂ����Y�߂Ȃ��v�o������߂��o�Y�������B
�@���R�Ȃ���o�Y��́A�S�R���ڂ̎Y��x�ɖ������畜�E�����B�玙�x�E���x�͂��������A���̊Ԗ���������A���Ȃ������B
�@����ƒʏ�̃y�[�X�œ����n�߂������������B
�@�����̐܂ɓ��������ۂ������W�����A�吺�Ō������B
�@�u���I�@�x��Ŏq�ǂ��Y��ŁI�v�A���R�Ƃ����B
�@�ÂɁu���̐E��́A�o���R�[�X�ɏ�����҂������ݐE���������̂����v�ƌ����Ă����B
�@�R�O�N�ȏ�̌������߂��A�����̃����o�[�݂͂ȑސE���Ă��邪�A���X�v�����Ƃ�����B
�@���̐l�������C��������u�������B�u���݂̏��q������ǂ����l���ł����H�v�ƁB
�@�����Ƃ́A������Ƃ͂����������ƂȂ̂��B���܂̌��𐢑�̖��⑧�q�������A�������Ŋ撣���Ă��邾�낤�ȁB
�@���������N�����āA����ƍ��o������Ƃ�^�C���A�|�p�^�C���B
�@�N�z�҂ɃN���V�b�N���y�̊�т��ƁA��ȁA�ҋȂ������鉹�喼�_����
�Ɖ��l���̉��呲�̏��������B
�@���̐l����������A�݂�Ȓe���������B�\�����t�ƘA�e�A�R�J���ɂP��̉��t��A���k�̎��i�͂T�O�Έȏ�ŁB
�@���������������������w�͂̐ςݏd�˂ł���B
�@�����ĕ��͕\���A�Ⴂ�l�����Ɠ��̃Z���X��n�͂͂Ȃ��Ă��A���N�����������҂ɂ��������Ȃ�����������͂��B
�@�����ǂ��\�����邩�A���R�ɑn��o����b�܂ꂽ��Ԃ��A�c�莞�Ԃ����Ȃ��Ȃ��������ɁA�M�d�Ɏv����B
�@�C���^�[�l�b�g�Ƀz�[���y�[�W���J���Ă͂�P�O�N�A���̑�����������ɂȂ����B
�@�d�b�̃x���������B�|�����ςȂ��������F�l���낤�B�����ƁB
�@�ӂƁA���ɋA��A�����ɂ͋���ۂ̍������̖T�ŁA�V�w�l����l�ڂ��肵�Ă����B
�@�ǂ�����́H�@�s�A�m��߂�́H�@������́H
�@
�@�R�T�Ԃ̓��@���Â��I���āA�����̕a�@����s�A�m���މ@���ė����B
�@�����̐l�́A����̓������J�o�����������L���āA�L�[�𗧂Ă�����ׂ���A�����o������L�[�̐���ɘc�݂��Ȃ����ƁA���C�悭��Ƃ����B
�@�Q���ԉ߂����B���Ɩڂ��L�[�ɂ������āu�悵�I�@�����I�@���̏u�Ԃ���Ԃ̊�тł��v�ƁA�Ί�Ō������B
�@�Ί�����ĐS�����܂����B
�@�ߌ�Q���Ԃ́A�p�\�R��������ŏ����A�ǂށB
�@�[�H��́A�s�A�m�e���ň��炩�Ȕ]�ɁA���炩�Ȗ���ɁB
�@�悵�I�@����ōs�����B
�@�@�@�@�@�@�@���グ�Ă����@��̐����E�E�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�t�K�j�X�^���̓y�ɂȂ���
�@���É��̔ɉ؊X�@�h�A�[�ł̂Ȃ��Ŗ�T�O�O�̃L�����h�����P�����B
�@�y���ӂ̉��t�҂��u���グ�Ă����@��̐����E�E�v��t�ł��B
�@�Ђ�����Ȃ��ɎԂ̌�������B
�@�h�̌����_���k�ɂ���L��ɂ́A�P�O�O�l�ȏ�̐l�������W�܂����B�A�t�K�j�X�^���ŎE���ꂽ�ɓ��a�炳�D���������Ƃ������̉̂�S�ɍ��݁A�R�P�̎Ⴂ���𓉂B
�@�Q���҂����Ԃ��������e�̉ԁA�Â��ɗ������������̋��ɟ��ݍ��ށB�����������������Ȃ��B
�@�H�ו����Ȃ��A�n�����A�t�K�j�X�^���A�Ȃ炻�̒n�ŐH�ו�����낤�ƁA�T�N�Ԃ�������ɓ�����A����A�͂�ʂĂ���n�ɐ����ƁA�@�K���ɗp���H��������y�V�����[����̐l�����A���ɂ͂ƂĂ��ł��Ȃ��B
�@���S�ɂȂ�����t�����N���́A���n�ŁA���̂悤�ɒ�����ǂB
�u�ɓ�������E�����̂̓A�t�K���l�ł͂���܂���B�l�Ԃł͂���܂���B����A�t�K�j�X�^����I�ޖ\�͂ł���܂��B���������A�C�X�������k�ł��邱�Ƃ��߈��ł��傤���B���̓L���X�g���k�ł��B
�@���܁A�A�t�K�j�X�^���ł͂T�O�O���l�ȏ�̐l�X���Q��ɒ��ʂ��A�푈�ō߂̂Ȃ��l���������𗎂Ƃ��Ă��܂��B�U�O�N�O�C���{���푈�ō��y���p�ЂɂȂ�A�Q�O�O���̕��m�ƂP�O�O���̎s�������ɁA�A�W�A�̋ߗ����ɂ���ȏ�̎S�Ђ������炵�܂����B
�@���̒n���瓦�����Ȃ��A�t�K�j�X�^���̐l�����Ƌ��ɁA���Ƃ��p�����邱�Ƃ��A�ɓ�����ւ̒Ǔ��ł���A�ߋ��̐푈�Ŏ��l�X�ւ̒����ł��v�B
�@���N�A���É����قʼn���I�������o���ꂽ�B�u���q���̃C���N�h���͈ጛ�v�ƒf�����B
�@�u��s�o�N�_�b�g�͕����P�X�N�ɓ����Ă�����A�A�����J�R���V�[�A�h�A�X���j�h�̗��������͂�W�I�ɑ�����̑|������W�J���A���ۓI�ȕ��͕����̈�Ƃ��Đl���E�����A����j��s�ׂ��s���A��ʎs���ɑ����̋]���҂o�����Ă���n��ł���A�퓬�n��ɊY������v�Ƃ̔F�����������B
�@���̔������A�����ƑS���ɍL�������ƁA�u���q���C���N�h�������~�ߑi�ׂ̉�v�Ƃ��āA�o�X�ō���֍s�����ƒ�Ă��ꂽ�B
�@�������v�w�́A�����܂Ō����Ƃ��Ă��̍ٔ��������A�s���^���Ƃ��ĕK���Ŏ��g�܂ꂽ�l�����̓w�͂ɓ����������B
�@�P�X�U�O�N�̈��۔��̔N�A���̖��É��h�����_�ŃJ���p���������B
�@�O�r�Y�z�̍������ł��тɂȂ����l�����֎x���������B�����̂����łP���~����P�ӂɁA�Ⴉ�����������͊��������B
�@��s��Ԃʼn����Ԃ������ď㋞���A�����������B���H�����ς��ɍL�����āA����Ȃ��ŕ������t�����X�f�����v���o���A�����M���Ȃ����B
�@�����A�N��Ƌ��ɗ������̗͂̂��Ƃ�����A���ɗp��������ŎQ�����~�߂��B
�@�����āA����A�ɓ�����𑗂��ɎQ�������̂ł���B
�@�C���N�h���ƃA�t�K�j�X�^���A����́A�����ĕʂ̂��Ƃł͂Ȃ��B
�@����ǂ��납�A�C���N�Ő퓬�s�ׂɋ��͂������A����ƓP�ނ̎������������q�����A���{�́u�V�e�����[�@�v���������āA�C���h�m�ł̋����ɋ��͂��悤�Ƃ��Ă���A�P�N���������܂肻���ȏ��B
�@�A�����J�̌����ʂ�ɂȂ��āA���̓A�t�K�j�X�^���ւƂȂ肩�˂Ȃ��B
�@�W���[�i���X�g���J���a�����A�������Ō��n�֍s���č�����f��u���˔\�𗁂т�q�ǂ������v�Ɓu�C���N��ꂩ��̍����v�Ƃ����f��ŁA�C���N�̎q�ǂ������������A�N���X�^�[���e�̔j�ЂŁA����ɂȂ��ċꂵ��ł����B
�@����ɁA�ČR�͍��ۖ@�ŋւ����Ă���A�_�o��Ⴢ̃K�X�˂��g�����̂ł͂Ȃ����Ǝv����悤�ȏǏ�ŁA�����Ȃ��Ȃ��Ă���q�B���ʂ����B�f���̔��͂́A�X�Ɗς��҂ɑi���Ă���B
�@�t�Z�C�����U�������ہA�����X�ɉ�œI�ȍU�����d�|�����ɂ�������炸�A�P�����̃r�������͎c�����B�f���ł́A�j�s�����ꂽ�n��ɁA�|�c���ƐΖ��֘A�̃r�������������c�����s���R�ȏ��ʂ�A�A�����J�̖ړI���f�l�ɂ��悭������f���������B
�@�C���N�ɑ�ʔj�킪����ƁA�A�����J���U�ߍ���ł���T�N�A���s�s�Ȑ푈�ŁA��Q�͕��ʂ̏����ɍ~�肩����B�푈�Ƃ͎E�������ł���B
�@���̓A�t�K�j�X�^���ƂȂ�Ȃ����߂ɁA��l�ł͉����ł��Ȃ��Ă��A��s���Ƃ��āA�����m��A�S�����B�X�^�[�g�͂�������B
������Ƃ������Ƃ́A�����������Ƃł͂Ȃ����Ǝv�����B
�@����V�������߂��A�v���Ԃ�ɕv�Ɩ��邭�₢���L���H�ʂ��������B�y���[�H���ƁA��O�I�ȋ��H���֓����āA�r�[���Ŋ��t�����B
�@�u�����ꂳ�܁I�@��C�̂Ƃ��́A�����H�������Ńr�[���Ŋ��t�Ȃ�ĂȂ������Ȃ��v
�@�u�x�z�����̋����A����ł����Ƃ��v��Ȃ������B�Ⴉ�������A���ɂ͊�]�����������E�E�E�v�B
�@�����A�Ђ����猣�g�������������ɁA�قȂ�ӌ��������Đ��}�̐�]�����тɂȂ�A����������_�I�n���A�o�ϓI�ǂ��B
�@���̋�ɂ��܂��Ⴂ�����ɑ̌��ł��Ă悩�����B�{���̂��Ƃ������āA�悩�����B
�@�u���グ�Ă����A��̐����E�E�E�v
�@���X���������f�B�A�j�ł�H��
�@���݂��ݗ��j�����������������B
�@�@�@�@�@�@�@�e���Ȃ������u�t�B�������f�B�A�v
�@�s�A�j�X�g�ٖ�]�[�ǂœ|��A�Q�N���̕K���̃��n�r���ŁA���肾���̉��t�ƂƂ����S�����B�u�a�ɓ|��Ă���A�͂��߂āA���肾���ł��̋Ȃ��e�����Ƃ��A�������܂����v�ƁA���̐l�͒W�X�Ƙb�����B
�@���̐��E�I�s�A�j�X�g�́u���肾���̉��t��v�ŁA�u�t�B�������f�B�@�^�́v���āA�����Ă���s�A�m�����́A�R�J���ɂP�x�̉��t��́A��ɂ��̃V�x���E�X�̋Ȃɂ��悤�ƌ��߂Ă����B
�@���ꂩ��R�J���@�Õ��������B�O���͂��キ�A�㔼�̓t�H���e�ŗ͋����B����Ȏw���ŁA�J��Ԃ����ՂɌ��������B
�@���肾���ł����r�A�m���e���Ȃ��Ȃ�����Y�A���̂��ƂƁA���R�A�������ł���ƒm���Ă���A�]�v���̃s�A�j�X�g�̂�������̂����Ɛ������B
�@�t�B�������h�����V�A�Ɏx�z���ꂽ�����A���̋Ȃ����t�����x�ɖ\�����N���A���t���֎~����邱�Ƃ��������Ƃ����ȁA���̔���������������������ɁA��R�������j���v���Ȃ�����K�𑱂����B
�@�y�X�e�����B�Ə��������B�������A�����͊Â��Ȃ������B�����O�ŁA�����Ȃ�e���l�������P�l���邱�Ƃ�m�����B
�@�����A�����ԑO�A�v���O���������Ă��炾�����B
�@����Ȃ��Ƃ́A�ԈႦ�闝�R�ɂȂ�͂��͂Ȃ��̂ɁA���߂ċ����h�L�h�L�����B�����ƑO�ɒm�肽�������B�ȂǂƁA���_�I�ɂ��炵�Ȃ����ƁA���̏�Ȃ��ł���B
�@�O���͂Ȃ�Ƃ��Ȃ����B���A�t�H���e�ɂȂ��ė͋��������ׂ�������A�ԈႦ���B����Ȃ��ƂłƁA�ȑO���o�������������蒼���A����ƒe�����B���̂Ƃ��̂��Ƃ����ɕ����B���߂��B�~�߂悤�B
�@�����オ���āA�錾�����B�u�������܂��v�B
�@��蒼�����A���߂ĂȂ�ˁB��������̃s�A�m�ł���B
�@�����A���܂̌��������̒��ŁA�s�A�m���e���邾�����ґ̏�Ȃ��B
�@�����Ƃ́A��Ƃ�̒��ł������܂�Ȃ��B����Ƃ��̂�Ƃ�̐������ł���悤�ɂȂ����A�ق�̎b���̂Ƃ��Ȃ̂ɁB
�@�T�O����̃s�A�m�Ƃ����Ă��A�n�߂��̂͂U�O�Ŏd�����~�߂ĂR�N�ゾ�B
�@��b���Ȃ��Ƒʖڂ��Ȃ��B
�@���\��I����A���������݁A�P�[�L��H�ׂȂ���k������b�܂ꂽ�ґl�A����������̐搶�����̔�]����ŁA�@�ԈႦ���l�����ɂ����l������A�u�A�肽���v�Ƃ��������āA�Â��A��]�Ɏ����C�������A�ق�̏��������A�~��ꂽ�B
�@�Ȃ�Ƃ��s�b��Ȃ��u�t�B�������f�B�A�v�ŁA�ٖ�X�A�ꂵ���A�������v���o�̋ȂɂȂ����̂ł���B�@
�Q�O�O�W�N�P�O��
�@�@�@�@�@�@�@�E�肪�����Ȃ�
�@�������߂��B�s�A�m���e���Ȃ��B�E���g�s���̃I���A�����Ⴍ���Ȃ��B
�@��]�̒��ŁA���N��܂Ō��܂��Ă������t����A���X�L�����Z�������B
�@��t�̐f�f�́A�]�[�ǂ������B
�@�g�͓̂����Ȃ����A����ɓ��͂͂����肵�ė��āA�w�Z�𑲋Ƃ����N���甪�N��ɁA�t�B�������h�������y�@�ŋ���
�Ƃ�����������������U��Ԃ�B
�@�t�B�������h���{�̏I�g�|�p�Ƌ��^���Ẳ��t�����́A���E����3000��ȏ�ɂȂ�B
�@�q�ǂ�����͐푈���������Ƃ��l������A���̂悤�ȍK�^�������B�t�B�������h�ʐM�́A�u�ċN�s�\�v�Ɠ��{�ɓ`�����B
�@�I���͎��ȂȂ������B
�@���䖲���œ�N���A�K���Ƀ��n�r���̓��X�𑗂����B�����m������ȉƂ̗F�l�������A����̂��߂̋Ȃ�T���A���X����Ă��ꂽ�B
�@�ԋ{�F���A�ь��A�g�����A���g�ۗY�A�J�쌫��A�m���h�O�����A�N�����ȂǂȂǁE�E�E�B�܂��Ɂu����̃s�A�m�Ȃ̖L��v���ɂȂ����B�L������B
�@�ł��A�܊p����Ă��ꂽ�Ȃ������ԁA�e���C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
�@�Ⴆ�A�V���[�x���g�́u�A���F�E�}���A�v�A������Ȃ��e�����V���[�x���g�̒��ŁA���̋Ȃ̗D���������肾���Œe������A���������ŁB�����v���ƒe���Ȃ������B
�@�t�B�������h�ɓ���A�������y�@�̋����𑱂����I��������ȑ̂ɂȂ��āE�E�E�B
�@�V�x���E�X�́u�t�B�������f�B�A�^�́v��e������A�Е������̎肵�������Ȃ��g���ȉ߂��āA����ς�e���Ȃ��B
�@���������̂��ʂ����Ă悩�����̂��ǂ����A���X�A�Y�ݖ����Ȃ���̃��n�r���������B
�@�O�N�O�A���É����炩��z�[�����u�����̉��y��v���v�悵�Ă��ꂽ�B�N�Ɉ��̌v��ŁA�O�N�ڂ̍���ŏI���B
�@�I���́A�s���R�ȉE�������Ђ�����Ȃ���A�s�A�m������������z�������B����Ȏp�����炯�o�������Ȃ��B�����ȏセ��ȋC���������B
�@�����̃T���g���[�z�[���ł̉��t��O�ɁA�o�b�n�́u�V���R���k�v��e�����B����͕a���畜�A�����Ƃ��A���߂Ēe�����Ȃ������B
�������B
�@�����āA�V�x���E�X�́u�t�B�������f�B�A�^�́v��e���I����āA���������B
�@�ł��A���K�ł͋��������A�T���g���[�z�[���ł͋����Ȃ������B
�@�I���͖��É��ŁA�ԋ{���́u���̂��邵�|�I�b�t�F���g���E���v��e�������B
�@�A�����J��Z�����̐_�b�́A���ׂĂ̐����a���̂Ƃ��A����^���Ă����͕̂��̐_�Ƃ����B
�@���R�̐_��Ɉ�ꂽ���̋ȂƁA���A����Ƃ����߂Ēe�����o�b�n�́u�V���R���k�v�A
�@����ƃV�x���E�X�́u�t�B�������f�B�A�^�́v��e�����B
�@
�@�I���́A�����I��邻�̂Ƃ��܂ŁA�e�������邾�낤�B���肾���ŁB
�\�\�܂����ڂꂻ���������ٖ�������肾���́u�t�B�������f�B�A�^�́v���ā\
�Q�O�O�W�N�V��
�@�@�@�@�@�@�@�s�A�m�͉̂�����
�@�N���̃s�A�m���t��́A��N�ǂ��胄�}�n�z�[���������B
�@�u50����̃s�A�m�v�̔��\��͂R�����ɂP��̂ŁA1�N�͂����Ƃ����Ԃɉ߂���B
�@�e�����Ȃ́A�p�b�t�F���x���́u�J�m���v�A�ʑt�ቹ�̋ȂňÕ��Ɏ肱�������B
�@����ł����Ƃ��Õ����A�����{�ԁA���疜�~������ƌ�����O�����h�s�A�m�̑O�ɍ������B�Ȃɒ����Ă��A�݂�Ȃ����������悤�ɁA�Ԃ�Ԃ�k����Ƃ������Ƃ��Ȃ��A��r�I��Â������B
�@1�A2�A3�ƐS�Ő����A���ՂɎ���̂���B����ƁA�E��̃����f�B�͂������A���肾���ςȉ���e���Ă���B
�@��蒼���B�܂������B����ɂ�����x�A�ł��S�R���߂��B
�@���䂩��q�ȂɌ������āA�v�킸�������B�u������x������点�Ă��������v�ƁB
�@����ƁA�����̐��������ꂽ�B���̂܂܁A�Ȃ̒��ɓ��邱�Ƃ��o�����B
�@�ƂA���āA������^���e�[�v���ƁA�o�����̃~�X��3��łȂ��A4�����B
�@�悭�������܂����e�����������̂��ƁA��Ȃ���70�̐}�X�����ɋ������B
�@���̃e�[�v������������u����ł����߂Ȃ���?�v�u����ł��e����?�v�Ǝ��₵���B
�@���s�̂悤�ɌJ��Ԃ������A���߂�Ƃ������_�͏o�Ȃ������B
�@�ԈႦ��Ƃ����A�w���Ҋ��G�V�̌o���𒆓��V���̋L���œǂB
�@�u���ăI�[�X�g�����A�ŃX�g���r���X�L�[�́w�t�̍ՓT�x���w�������Ƃ��A���ꂽ�Õ��Ȃ̂ɐU��ԈႦ�A�w���̃~�X�x�ƒ��O�Ɏӂ�A���t�ĊJ��ɍĂъԈႦ���B�Õ��p�̊y��������ł��āA���̒������͐ߕ����������Ƃ��B����ł��~�X��F�߂����ƂŌh�ӂƍD��������ꂽ�v�B
�@�����ǂ�ŁA�܂�Ń��x���͈Ⴄ���A�l�ԂƂ��ăz�b�Ƃ����B
�@�w���Ҋ��G�V��2006�N6���ɖS���Ȃ����B�s���̏Ă��ՂŁu�����̕�������ɂȂ낤�v�Ɛ�������鏭�N�A
�@���͂��▭�ŁA�D��ł悭�ǂ�ł����̂Ŏ₵���Ȃ����B
�@����ɁA�|�[�����h�̗D�G�ȃr�A�j�X�g�A�N���X�`�����E�c�B�����}���̃��T�C�^���̂��ƁB
�@�Q�����̃s�A�j�X�g�́A���t��ɓ��{��Ń��b�Z�[�W��ǂB
�@�u���{��30�N�ԉ��t���s�����ƗF��Ɋ��ӂ��܂��v�ƑO�u�����A�����ނ�Ɍ��n�߂��B
�@�u3�N�O�A���{���푈�ɎQ�^�������Ƃ͎c�O�A�E�C�������Ĕ��������Ă���l�����ɁA���ꂩ��̉��t������܂��v�B
�@���ꂩ��e�����V���p���̃\�i�^���ԁu�����v�͑s�₾�����Ƃ����B
�@�u�����̃c�B�����}������͑z�����������s��ȉ��t�������B�Ƃ��ɑ����͔ߒɂȋ��т��ԚL�Ƃ����ׂ����̂������B
�@�{��A�푈�A���A���ׂƉ������l�̊y�͂ɁA�q�Ȃ͑���ۂ݁A�����Ĕ����I�Ȕ���ʼn������B���̓��A�A���R�[���̉����]�n�͂����Ȃ������v�B
�@�����`�����̂́A�������勳���̉��c�֎q���ł���B
�@�u�n���������|�[�����h�ɂ́A�s�A�m�̕��i���Ȃ��A�����Ŏ��肵�Ē��B�����ނɂƂ��āA���E�Ɛ藣���ꂽ���y�Ȃǂ͂��蓾�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�B
�@���̗D�ꂽ�s�A�j�X�g�́A�M�d�ȃ��b�Z�[�W�͖{���ɂ��ꂵ�������B
�@���q�����C���N�ɔh�����ꂽ���ƂɏՌ����Ă��̃��b�Z�[�W�ɂȂ����Ǝv���B
�@�č��͈���I�ɍU�ߓ������C���N�A�u��ʔj��͂Ȃ������v���ƂœD�������Ă���C���N��A����ɒǏ]���Ă�����{�A���@�ᔽ�̎��q���h���ł͂Ȃ����B�s���^���Ƃ������ٔ��ő����Ă���B�S����6000�l���錴�������̍ٔ��ł���B
�@�������A�͌������p���������Ă���B�����̈�l�Ƃ��āA�u�����̂������̂��C�[�W�X�͂��ʂ�v��A���q�̖��É���`�Ɂu��A�@�v�z���Ȃǂ�
�@����? �@���̊Ԃɐ푈�ɂȂ�����?
�@����Ȏ���ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
�@�f���炵�����y�|�p�Ƃ����́A���łs���╶�́A���y�̕s�v�c�ȗ͂����炽�߂čl�����B
�k�Q�O�O�W�E�R�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�l�ԁ@���X�g���|�[���B�`
�@�u���y�Ƃ͐_���^���Ă��ꂽ�̑�Ȋ�Ղł���v�ƌ������A���E�I�`�F���t�҂́A�������X�`�X���t�E���I�|���h���B�`�E���X�g���|�[���B�`��2007�N4��27���ɑ��E�����B
�@����𓉂�ŏo�ł��ꂽ���̖{���A�����q�̃`�F���t�҃C���@�V�L�����ҏW�����B�k�w���X�g���|�[���B�`�x�t�H�Ф2007�N9���l
�@�u���{�ɍs���āA���{�̊F�ɉ����!�v�ƁA2006�N11���A�d�a�������ē��{�ɗ������X�g���|�[���B�`�B
�@1989�N�A�����x�������̕ǂ̑O�Ń`�F����t�ł����X�g���|�[���B�b�`�B
�@�����āA�\�A�M�����1991�N�A���X�N���̃o���P�[�g�ɔ��ōs�����Ƃ��A�����̎g���Ɗ������l�Ԃł���A�c���Ɛ��E���̌b�܂�Ȃ��l�X�̂��߂ɁA�w�͂�ɂ��܂Ȃ��A�l�ԃ��X�g���|�[���B�`�������B
�@�ނ��ǂ��l���A�����ɐ����������A�L�x�Ȏ����ň���ɂ܂Ƃ߂��A�Ҏ҃C���@�V�L���́A�u���X�g���|�[���B�`���A����Ȏ��Ԃ��₵�āA���ڐl��������Ă���A������m�邱�Ƃ��ł����̂́A�M�҂ɂƂ��đ傫�ȓ����������v�Ə����Ă���B
�@���ł��A���悻�T�O�łɂ킽��R�́@�������s���X�g���|�[���B�`������肫�t�ŁA���s�s�ɔ��Q����A�|�p�ƂƂ��ă\�A���ƂƕK���ɓ������Ƃ�́A�X�Ƌ��ɔ����Ă���B
�@�ҏW�́A�S�̂��R���T�[�g�`���Ɏd���ĂāA���j�[�N�ɖ����܂��Ă����B
�Ⴆ�A1�͂����X�g���|�[���B�`�ɕ�����v�������[�h�Ƃ��āA�Ҏҁk�C���@�V�L����ȁl�Ƃ��A2�̓��[�����X�N���k���X�g���|�[���B�`��ȁA�C���@�V�L���ҋȁl�ƋL���A�ʔ����H�v���Ă���B
�@�����́u���X�g���|�[���B�`������肫�v���A3�͌������@�k���X�g���|�[���B�`��ȁl�Ƃ��āA�Ȃ�قǂƎv�킹��B
�@�x�e�u���X�g���|�[���B�`�v�ɂ́u�鑠�́A���ʎʐ^�W�����y���݂��������v�Ƃ������B
�@���̎ʐ^���������̂��B
�@���E�̒��L���ȉ��y�Ƃ��A�ɂ������Ȃ��f�ڂ���Ă���B
�@�V���X�^�R�[���B�`������B�v���R�t�B�G�t������B�I�C�X�g���t���A�P���v������B���q�e���A�X�^�[���A�J�������A�����E�E�E���̑��A���̑��E�E�E
�@���̎ʐ^�W�����ł��A���X�g���|�[���B�`�̉��y�I�����̑��ʂ��A�̑傳��������A���̖{���������b�オ�������Ǝv���B
 �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@
�P�X�W�X�N�x�������̕ǂ̑O�ʼn��t�@�@�@�@�@�@�@�@�P���v�A���j���[�C����
(�ʐ^�̓]�ڂ́A�t�H�Ђ̗�������)
�@�������A���̖{�̉��l�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B
�@���̂�������A���y�Ƃ����|�p�̕��삾���ł��ǂ�Ȃɑ���������Ă����B���E���܂��ɂ��������y�������A�c���Ƒ̐��̂��߂ɁA�l�ԓI��Y�Ƃ̓����Ƃ��Ȃ����B
�@�Ӑ}�I�ɘc�߂�ꂽ���Ƃ̏��ŁA�����͐^����m�邱�Ƃ��o���Ȃ��B���̔ߌ����A��l�̒��l�I���y�Ƃ̕s���̐��_�œ������B
���E�I�`�F���X�g�A���y�Ƃ̃��X�g���|�[���B�`���A�ȃ��B�V�l�t�X�J���Ƌ��ɁA�\�A���ЂD���ꂽ�̂́A1978�N8��19���ł���B
�@���N3��16���̃C�Y���F�X�`�����́u�\�A�M�ō���c������́A�w�\���B�F�g�Љ��`���a���A�M���ЂɊւ���x�\�A�M�@�掵���Ɋ�Â��A�\�A���ЂD���邱�Ƃ����肵���v�ƕ��B
�@�����悤�ȑ̌��ŋꂵ���Ƃ����邪�A���͂����������Ƃ�����ƂȂ�ƁA�z����₷���Y�������낤�B
�@�����A�\�A�M�ō�������c�����ĂɁA���X�g���|�[���B�b�`�v�Ȃ��o�����p������̏��Ȃ́A���̂悤�ɋL���Ă���B
�@�u�����͉��y�Ƃł��B����̐鍐���ꂽ�߂́A�ł����グ�ł��B��ƃ\���W�F�j�[�c�B���������̉Ƃɓ��������Ƃō߂ɂ��ꂽ���Ƃ́A�M�a����Ԃ悭�����m�̂͂��ł��B�R���T�[�g�̒��~�A�C�O�����̋֎~�A���W�I�A�e���r�A�V���G��������̃{�C�R�b�g�ȂǁA���y������Ⴢ����悤�Ƃ��鐔�X�̎��݂��s���܂����B�E�E�E�v
�@�v�w�����āA�Ȃ̓��[�j���M�́A�v�̓X�^�[�����܂�[�j���܂Ƃ����A�\�A���ƍō��̖��_���A���X�N�����y�@�����̈ʂɂ������B
�@�����I�ɂ͖��S�ŁA�V���X�^�R�[���B�`��I�C�X�g���t�Ƃ͈قȂ�A�����ă\�A���Y�}�ɓ��낤�Ƃ͂��Ȃ������B���A�ǂ�ȏ����Ȓ��ł���M�����߂ĉ��t���A�c���̕����̂��߂ɂ�����w�͂������B
�@����Ƃ��A�V���X�^�R�[���B�`���V�������t�Ȃ���Ȃ����B�`�F���t�҂̃��X�g���|�[���B�`�́A�������薣������Đl���ŏ��߂�2���Ԃ�9���ԁA����2���Ԃ́A7���ԗ��K�����B�������č�Ȏ҂̂��߂ɁA�Õ��Œe�����B
�@�V���X�^�R�[���B�`�́A�����̎����M�����Ȃ������Ƃ����B
�@�l���̓]���_�ɂȂ����̂́A�\���W�F�j�[�c�B���Ƃ̏o��ł���B
�@1960�N��A�\���W�F�j�[�c�B���́A�������e���ł̐�����`���������w�C�����E�f�j�[�\���B�`�̈���x�\���A��ƂƂ��ėL���ɂȂ����B
�@���X�g���|�[���B�`�͂�����[���̂悤�ɓǂB�V�삾�����w���a���x�w�����ɂāx�̌��e����ēǂB
�@���T�C�^�����������ɁA���R�A�\���W�F�j�[�c�B�����Z��ł��Ēm�荇�����B���̂��Ƃɗ��j�I�^����������͎̂����������낤���B
�@�\���W�F�j�[�c�B���́A1970�N�m�[�x�����w�܂����^���ꂽ�B���A�{���ł̓\�A��Ɠ�������Ǖ�����A���ׂĂ̎�v���ɍ�i���f�ڂ��邱�Ƃ��ւ���ꂽ�B���X�g���|�[���B�`�͖ق��Ă���ꂸ�A���J���Ȃ���v���ɑ����čR�c�����B
�@���̎莆�͌��\����Ȃ������B���̒��ォ��A���X�g���|�[���B�`�́A���V�A�̓c�ɒ��ł����A���t��w����������Ȃ��Ȃ����B
�\�A�M�����A70�ɂȂ��Ă��A75�ł����C�Ɋ����ނ��A80�̒a�������j���ĂP������ɁA���̐��֗��������B
�@���̖{�ɂ́A���y�E�ł́A���Ȃ�ڂ������X�g���|�[���B�`�̐��U���Ԃ��Ă��āA���y�ɊS�̂���l�ɂ͋����[�����͂ł��邪�A����̓v�������炱���̕M�Ǝv���B
�@���̒��̉��y�Z�p�ɂ��Ă������L�������B
�@���X�g���|�[���B�`�̌��J���b�X��
�@�P�A�����q�������ނ̐^�����Ȃ��悤�ɁA�����̓`�F����e���Ȃ��Ńs�A�m���t�Ŏw�����A������Ă��B���X�N���̕��������ɂ����āA��Ɉ��C���F���g�ŁA����قǂ̍˔\���W�܂�`�F���̎��Ƃ͂ق��ɂȂ������B
�@�Q�A���y�S�̂ɓ����A���̋Ȃ�Y���͂����Ȃ��ƁA�X�R�A�������ɏn�m���邱�Ƃ�v�������B���߂̃��b�X������Õ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���䂱�����A�ŗǂ̎t�ł���Ƃ悭�����Ă����B
�@�R�A�ɒ[�ɒx���e���|�ŃV���[�x���g�́w�A���y�W�I�[�l�E�\�i�^�x���v���e���Ɖ��t�����B���E�܂ł������Ƃ����e���|���A���X�g���|�[���b�`�ɂ͉\�������B�u�Ђ܂��v�ƌĂ�Ă������X�g���|�[���B�`�̉��t�ɂ̓I�[�����������B
wikipedia�@�w���X�e�B�X���t�E���X�g���|�[���B�`�x
�@���̂R�_���A�܂�Ń��x�����Ⴄ�Ƃ͂����A����ȁA�f�l�̃s�A�m�D�����A�R�����ɂP�x�̔��\������Ă�����̌��Ƃ��āA�����ł���M�d�ȃA�h�o�C�X�������B
�@�Ō�ɁA�ӔN�̃��X�g���|�[���B�`�̃G�s�\�[�h���ʔ����B
�@�����A�e�������@�C�I�����t�҂̍Ȃ��ނ̕�����K���ƁA�ނ��z�e���̕����̗�����|�����Ă���B�u�܂��Ȃ����C�h���������肫�ꂢ�ɂ��Ă���܂�����v�Ƃ������Ɂu���C�h����������ė��āA���X�g���|�[���B�`�̓��V�A�̓��ƌ���ꂽ��A���₾��H�v�ƁA���̎咣��f�łƂ��đނ����B
�@�l�ɂ₳�����A�ȂɌ������������l�Ԃ������B
�@�@�@�@�@�@�@���肾���̉��t��
�@�s�A�j�X�g�ٖ�]�쌌�œ|�ꂽ�̂͂Q�O�O�Q�N�A���t�����S�n���N�L�O�̃��T�C�^����S���ōs�Ȃ������N�ł���B�����T�N���߂����B
�@�s�A�m�e���ŁA�E�肪�s���R�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��̃V���b�N�͑z����₷����̂������낤�B
�@�Q�N���̋ꓬ�̓��X�A�Ռ�����s���ɗ�������A���肾���̉��t�Ȃ�e���悤�ɂȂ����B
�@���̃s�A�j�X�g�w�ٖ��E�����̉��y��x�֍s�����B
�@���₩�ȏΊ�ŕ���̃s�A�m�܂ŕ����B�ق�̏��������A�E���������Â銴���ň֎q�ɍ���ƁA�g�ɂ܂Ƃ������̃|�P�b�g����A�ዾ�����o���Ă�����B�����Ēe���n�߂��B
�@�n�߂̐��Ȃ͖k���̌��i���v�킹���B
�@���ꂩ��A���肾���ٖ̊�̂��߂ɐV�������ꂽ���Ȃ���e���B�Ў肾���ō����A�ቹ�ƖZ�������Ղ̏�𑖂点��B�b�������Ă���ڂ�����B�܂�ŗ�����g�����悤�ɉ���瞂�B
�@�v�������瓖�R�ƌ����邪�A�����N�Ώۂ̃s�A�m�����ŁA�K���ɒe���Ă��鎄�̗�����A�]���L���ȉ��ʂ��B
�@�ٖ��Ƃ́A���R�ɂ����N������B
�@���h�ŁA�D�ꂽ�˔\�̎�����͖k���ɓ���A�U�S�N����w���V���L�ɏZ�ށB���̂P�O�N�قǑO����t�B�������h�������y�@�̋����ȂǂƂ߂邪�A���{�Ɩk���T�J���Ɛ��E�łR�O�O�O��ȏ�̃R���T�[�g���s���A�b�c�͂P�O�O���ɂ̂ڂ�B�M���x�����W�߂��̂́A�l����鉉�t�̎����ƌ����Ă���B
�@��Â������y�z�[���̌����ł́u�o�b�n��x�[�g�[���F�����������y�ł͂Ȃ��v�u�͂邩�́A�M���V���ł͉F���̓���𖾂��錮�����y���ƍl�����Ă����Ƃ������A�C���h�ł͌Â����琢�E�͉��łł��Ă���Ƃ����v�z���`�����Ă���v�Ƃ��B
�@���Ȍv�炢�ŁA���̃s�A�j�X�g�́u�X�y�V�����g�[�N�v�����������A�l�X�̐S���Ƃ炦���͉̂��Ȃ̂��B
�@�m�g�j�̃n�C�r�W�������W�u����̃s�A�j�X�g�ٖ��@�ӂ����т����y�v�͉q�������ǒ��܂���܂��A�s�a�r����u��Ղ̃s�A�j�X�g�v�͂O�U�N�̔N�ԃe���r�x�X�g��i�ɑI��Ă���B
�@�ǂ�Ȑl�ł��A�����l���ō��܂��A�������ނ��Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��B
�@�������A���̂܂܂ł͂��Ȃ��B
�@���t�����ĊJ�̈ӗ~�ƍs���ŁA�u������v���Ƃ��܂��ꂽ���炱���A�����̐l�X�̋���������ꂽ�̂��낤�B�ܘ_�A�������̂ЂƂ�ł���B
�@�ŋ߂̐V���ŁA���m���̐��t�y�R���N�[���ŗD���������o�������钆�w���t���A�����g�s���ɂȂ�Ȃ���A�E�肾���Ŏw���ɕ��A�����j���[�X��ǂB
�u����˂��p�͌��������Ȃ����v�ƌ����Ȃ���u���y���D�������A���k�����Ɛڂ���̂���D�����v�ƁB
����ɁA���Ɍ��ł́A��V�I�Ɏ��r�̈ꕔ���������Ă���q�ǂ����A�`����g���ă��@�C�I���������t������g�݂�����Ă���Ƃ����L�����������B
�@�X�ƂV�̏��̎q�́u���ꂢ�ȉ����o��̂��D���B�傫���Ȃ����烔�@�C�I�����̐搶�ɂȂ肽���v�ƌ����A�o�b�n�́u���k�G�b�g�v�ȂǂT�Ȃ��I�����ƕĂ����B
�@��l�Ƃ����t����E�肪�`��ŁA���̑傫�Ȏʐ^�ɏՌ������B
�@�[���̎U���ŁA�����F�̋�ɁA��������L�k����ׂ��悤�ȉ_���������Ƃ��A���R�̔������ɐS���������B�����āA�y�������y���������Ă���B
�@�v���������e�����l�̎��ɉ�A�h���A�߂����Ƃ��ł��܂͂����o�Ȃ��B
�@����ȂƂ��A�S�ɟ��݂鉹�y���Ɨ܂����ڂ��B
�@���y�Ƃ́A���y�̗͂Ƃ́A�s�v�c�Ȃ��̂��Ƃ��炽�߂đz�����B
�@�@�@�@�@�@�@�l���̉��F
�@�u�̂��߃J���^�[�r���v�Ƃ����}���K�����X�ɕ��ςɂȂ�A�e���r�ł̕��f���D�]�������B�{�Ƃ͈Ⴄ�e���r���f�̖��͂́A�h���}�̖ʔ����Ƌ��ɁA�N���V�b�N�̖��Ȃ��A���Ȃ������邱�Ƃ����m��Ȃ��B
�@���������A�v�������ŊςĂ����B�U�̑��́A�s�A�m���K���n�߂Đ��J���A���߂Ă̔��\��Łu���炫�琯�v�Ɓu���悵���̖�v���ԈႦ���ɒe�����Ɗ�B�Ƃ��낪�A�e���r�́u�̂��߃J���^�[�r���v�ł́A�̂��߁k��c�b�l���A�R���N�[���̉��t�̓r���ŁA�X�g�����B���X�L�[�́u�y�g���[�V�J�v����A�}�Ƀe���r�̗����ԑg�̃e�[�}���y��e���Ă��܂��A�R���N�[���̒���͑厸�s�ƂȂ�A�������ݔ߂���ł����B
�@������ς������勃�������Ƃ����B�ꏏ�ɊςĂ����R�̎q�͕s�v�c�����ɁA�˂������ǂ������́H�ƌ������������B�q�ǂ��́A�l�Ƃ��Ă̊����͂ǂ������Ă����̂��A�����[�������B
�@��N�̓��[�c�@���g���a�Q�T�O�N�ŁA�N���V�b�N���y���ɂ킩�Ɍ��C�Â����B�Q�O�O�N���Q�T�O�N���l�X�����߂Ē������y�A�l�̂�����̂Ђ��ɟ��ݍ��݁A�傫�Ȋ�т��A���邢�͐[�������݂̂������h�蓮�����B���y�̕s�v�c�ȗ͂ł���B
�@�k�P�l�A�ǂ݂₷���g�c�G�a�̉��y�]�_
�@���E���҂ɂ����Ċ��������ȉ��y�ƃ��q�e���ɂ��āA�u�f��̃��q�e���v�Ƒ肵�ď����ꂽ�g�c�G�a�̕����ʔ����B
�@�u���q�e���̓s�A�m���|���Ɣߖ�������Ƃ����������B�������P�l�Ńs�A�m�Ɍ������A�Õ��Œe���Ă���Ƃ��A�����̔��q�ɂǖY�ꂵ�Ď��s���邩���킩��Ȃ��B���̋��|���ނ�s�A�j�X�g�̔w���ɒ���t���Ă���̂��������͖Y�ꂪ�����B���⑽���̐l�͂���Ȃ��Ƃ͖��ɂ��v�킸�A������Ƃ̎��|���y����ł���v�B
�@��s�A�j�X�g���u�s�A�m���|���E�E�E�Ɣߖ�������v�Ƃ��������肪�A�ƂĂ��悭�����ł���B����ɂ͗��R������B
�@���y�D���̒����N���吨�A����o�̎Ⴂ�搶��A��ȉƂ��w�����鋳���ɒʂ��Ă���A�������̂ЂƂ肾����B
�@�ߔ������P�O�N�I��A�T�N�ȏ�ʂ��l�������B�I���x�e����������ȃs�A�m�e�������邪�A�U�O��V�O��̐l���A�����̐��ʂ����ŕ\�����悤�ƁA�^���Ƀs�A�m�Ɍ������A�R�����ɂP�x�̊����ʼn��t������Ă���B�N�z�҂��Õ��Œe�����i�́A�����I�ł�������B
�@�v���O�����ɂ����ď��Ԃ�����܂łْ̋��́A�l�ɂ���Ă͐S������яo�������ł���B�V���̐g�ɂ��Ȃ肵��ǂ��A�Ƃ����l�������B
�@���i�A�Ǝ��̂ЂƋ��Łu�����A���ꂩ��s�A�m�̎��Ԃ��v�Ƃ����Ƃ��́A���N�����āA����Ɠ�����Ƃ�ɐS�����炮�B�����ɂ͖������ȂƎv���悤�ȋȂ��A�J��Ԃ��̗��K�Œe����悤�ɂȂ�A�Õ��Œe����ƂȂ�Ɗ�т͔{������B�V�ዾ���������Ԃ��s�v�A���ׂĂ�Y��đt�ł鉹�̂Ȃ��ɓ����čs�����Ƃ��o����B���t��ْ̋����{�P�h�~�ɂȂ�Ǝv���A�S�����������B
�@�u�x�[�g�[���F�����w���x�����������鏭���O�A�S�N�Ԃ��̂������W���͂Ŋ����������w�����~�T�ȁx�͒����ł���B
�@�w���x�͐l�ނ̗��z�̋P�������\�������A�w�����~�T�ȁx�͌����������𗦒��Ɏ��ꂽ��ł̋F��̉��y�ŁA�x�[�g�[���F���͗��z�ƌ����̗�������ڂ𗣂��Ȃ������B�厖�Ȃ̂͂��̎����Ǝv���B
�@���z�̒Nj��A����搉̂͂�������ǁA����P�_����ŗ��z�����ڂɓ��炸�A�ՂQ���Q�˂����邱�Ƃ͓Ƃ�悪��̕�݁A���l�ւ̖��������ɂȂ�₷���B���z�ƐM�O�̐����������ł̍s�����ǂ�ȋ��낵�����ʂނ��́A��펞��Ɏ��������U�X�o�������v�B�g�c�G�a�̉��y�]�͂������[���B
�@�T�O�N�ԏ��������������A�N��X�O�ŋx�M�錾�������B�Ȃ�S�����A�̂̔����Ȃ��Ȃ����悤�ȋC���A�Ƃ����Ȃ��L����ǂB
�@�ޏ����S���Ȃ��āA�ǂ����悤���Ȃ��傫�ȋ��S�ɂł����B�Q�l�ł����Ƃ����P�ԍK���������̂ɁA�����Ȃ���肾�Ƃ�����]���B����̍��ɍs���čȂ�A��߂������Ƃ����B
�@���N�ӋC�������ď����������A�ꍇ���ƁA���̂悤�ɂȂ�����A��͂��]�����낤�B�킩��A�킩��B
�@���̂Ƃ��A�u���疢���������́A���E���ЂƂɌ��Ԃ��́v�Ⴂ���A�悭�̂����������t�b���S�����B
�@���z�����āA���̎����̂��߂ɁA�����Ȃ���t�̏�M�𒍂������X�B
�@�P�X�U�O�N�͓��{�����۔��ŔR�����B���۔�������c���S���œ���s�����J��Ԃ��A�Ǐ������ی��������ŁA�E��Ŏ��ԋx���Ƃ�n��ɂ����������ɓ������B
�@�u����Ղ��Ȃ��v�Ƃ����悤�ȁA���Ƃ̏���������������A�S������A�������ď������Ă����l�����������B���̋c�Ă�����ŋ��s�̌�����A�S������́A�R�c�̓���s�����L����A������ӂ͐l�Ŗ��܂����B
�@�e�n�̏��X���X�X�g�ŎQ�����A�U���P�T���̑S������s���ɂ́A�S���P�P�P�P�Y�A�T�W�O���l�ƁA��O�K�͂̍R�c�^�����W�J���ꂽ�B
�@����́A�����I������āA�푈�̓C���Ƃ����v���A�̌��܂����s���������B
�@��\�̂P�l�Ƃ��ĎQ���������A���̐��P�O���l�̃f���̔M�C���A���܂̐l�����ɑz���o���邾�낤���B�Ⴂ�l�ɂ́A�����炭�u�ւ����̐킢�v���炢�̗��j�����m��Ȃ��B���{�͂܂��n���������B�������A�l�Ƃ��Ă̂�����͂������B
�@�����ŏ������n�������Ƃ́A���H�����ς��ɍL�����Ď���Ȃ��t�����X�f���������B
�@�����̋G�߂ɁA�����āA���Y�}�̐�]�����ƂɂȂ����v�́A�܊p������w�܂ŏo���̂ɂƁA���Ƃ̕���ɑ唽����A�������ꂽ�g�������B
�@�����͂S���̂P�̂V��~�ɁA������x�z�����ŗF�ɂ́A���l�悵�ȃI�{�b�`�����I���z�ƌ���ꂽ�B
�@��]�����P�O�N�A�R�T�łP�O���~�A�P�T�N�߂��Ă��x�z�����̂P�O���~�]�́A������̗F�l�̔N���S�O���~�̂S���̂P�������B
�@���́A�{�[�i�X�t���́A���肵�������������Ȃ��ɂ͐����͂ł��Ȃ������B�{�[�i�X���o��Ƃ����߂��̗X�ǂ֗a����B�b������ƁA�����A�����͂܂�����Ȃ��B�����ɒ����ʒ��ŏ����������������o���B����Ȃ��Ƃ̌J��Ԃ��������B�Ă��A�N�����B
�@�ł��A�n�R�͉��Ƃ��Ȃ������B�Q�l�ɂ͗��z������A�S�ɔR���鉊���������B
�@���̘A�ꍇ���Ƃ̎��ʂȂ�A�g�c�G�a�̐�]�����킩��B
�@�k�Q�l�A�̂���������
�@��������́A�`���C�R�t�X�L�[�̃s�A�m�ȁu�S�G�v�̒��́u�M�́v�ɂ��킹�āA�S�l���̂������悭�̂����Ƃ����B
�@�@�@�@�Ђ������̂Ђ���̂ǂ����͂�̂Ђ�
�@�@�@�@���Â�����Ȃ��͂Ȃ̂�����
�@�u���̂ǂ����t�̓��ɁE�E�E�v����̂ɂ���̂����A���̃g�Z���̐����ɁA�҂����荇�����Ƃ����B
�@�����ЂƂA�}�X�l�[��Ȃ́u�G���W�[�v���D���������̂͗L���Șb�������悤�ŁA�ނ����̎���ꂽ�t�𓉂މ̂��������ƁA�������ƃ��Y���ɂ̂����̐��ɁA���Ȃ������Ă���I�y���I�ȊÂ����邢�g�U��̂����Ɋ���̐^�����̂肤���ďo�Ă��āA�������̂̐S��ł����悤���B
�@�ŋ߁A���t��Œe���ȂƂ��đI�̂��A���́u�M�́v�Ɓu�G���W�[�v�������B�S���̋��R�ł���B
�@�Ȃ������ꂵ���Ȃ��āA��������ɋ������������B
�@���̎��l�́A�P�X�R�S�N�ɐ��܂ꂽ�q���Q�N��ɖS�����A���_�s����ɂȂ����B�w�Ƃł̗���A�����A���e�̎��ƁA�������^���������A�R�O�Ō��j���]��ᇂŋ}�������B
�@�g�c�G�a�͎Ⴂ����A�悭�s�������ɂ����悤�ŁA���̎��l���������́A�����Ŏ����𓉂�ł���҉̂Ƃ����v���Ȃ��Ƃ����B
�@�@�@�@�z���z���A���ꂪ�l�̍����A�k�����l
�@�@�@�@������������
�@�@�@�@�@�@�@���ꂪ�H���̎G���̒��ɁA
�@�@�@�@�@�@�@�����Ă������Ƃ�����A
�@�@�@�@�݂̂���������H�������Ƃ�����A
�@�@�@�@�@�@�@�Ǝv���Ȃ�Ƃ������B
�@�D���ʼn��t�����ȂƁA�˔\�̂��鎍�l�̍D���ȉ̂Ƃ��A���܂��ܓ����������Ƃ����ɉ߂��Ȃ��B�ł��A���̋��R����ԁB���������āA���̓V�˓I���l�Ƌ��ʂ��鉽��������̂����m��Ȃ��ȂǂƁA����ɑz�����邪�A�l���̔߂��݂̊��������������Ă���̂����m��Ȃ��B
�@���l��������́A�l���̋�ɂɋ������悤�ɂȂ�Ȃ���A���̌���Ƌ�Y��n��ʂŐ������A��i�⎩�Ȃ��ɂ����B�����̓|�[�Y�ɂ����Ȃ��B
�@�����̓|�[�Y�ɉ߂��Ȃ��Ƃ��������́A�V�N�Ŗʔ��������B
�@�k�R�l�A���|���ꂽ�@�����t�̔���
�@�����t�ŃT���T�[�e�́u�c�B�S�C�l�����C�[���v�����B
�@���t�҂̐�Z�^���q�́A�N���C�}�b�N�X�ɂ͕G��܂�悤�ȒႢ�p���ŁA�����ȉ���n�肾���A�����̒��O�����|�����B
�@�Ⴂ���A�e���r���Ȃ���������ɁA�l�X�́u�J���v�u���y�F�̉�v�Ƃ��u�J���v�ȂǂŁA�����̂悤�ɐ����t���A�����ŕ����I�~���������B
�@�ꐢ���r�������@�C�I���j�X�g�ҋv�q��ޖ{�^���A�z�K�����q�Ȃǂ��A����ȂɒႢ�p���͂Ȃ������悤�Ɏv�����A�ǂ����낤���B
�@��Z�^���q�́A�c�B�S�C�l�����C�[����e���O�ɁA��Ȏ҂̌Z�A��Z���̍�i�u�L���G�v�Ȃǂ����t�����B�w���҂̎���ɁA���ׂĂ��Ȃ���������̋��n�Œe�����Ɠ����Ă������A�����f�l�ɂ́A�Ί�ł̉��������悭�������āA�l�C�̍������킩�����B
�@��Z��������ɏo�Ĉ��A���������A���܂��܁A�a�������킽���Ɠ����P�O���Q�P���ƒm��A�e���݂��������B
�@�����ĉ��t���ꂽ�̂́A�V���X�^�R�[���B�`�̌����ȑ�T�ԁu�v���v�B���������\�A����A�X�^�[�����̒e�����ł������������A��e���������P�X�R�V�N�ł���B
�@�P�X�R�Q�N�Ɂu���c�F���X�N�S�̃}�N�x�X�v�l�v���A�r�����m�A���̔����|�p�ƂȂǂƁA�O��I�ɔᔻ���ꂽ�B�V�˂Ƃ���ꂽ��ȉƂ́A��ȉƐ����ƉƑ������܂Ŋ�@�ɒ��ʂ����Ƃ����Ă���B
�@�u�v���v�́A�X�^�[����������̔ᔻ�ɉ����ď������A�ЂƂ�̃\�r�G�g�|�p�Ƃ̉Ƃ��ď����グ���A�M���I�Ȓ��O�̎x�����B
�@�����t�Œ����ƁA��Q�y�͂ł̂��ǂ����悤�ȃ��Y���ƁA��R�y�͂̑������Ȑ[�������ȂǁA�������ǓƂ��A�u�v���v�̖������A�Ђ��Ђ��Ƌ��ɔ������B
�@�Ō�̍��炩�ȑ��ۂ̉��A�呾�ۂ̂W�A�ł́A�����ɑł����܂ꂽ�B�̐��A�N���ɑ���Y���̂悤�ɋ����A�\�Ɨ��A��ʐ��̂����ۓI�ȏI�͂������B
�@���������A�����������̒��O�́A�������Ŗ�S�疜�l���̗F�l��e�����A��������E����Ă��邩��A���̋Ȃ̗����̐^�ӂ��킩���Ă����Ƃ������Ă���B
�@�P�X�W�X�N�ɓ��������̎Љ��`�����A�X�P�N�Ƀ\�A�M�������B�V���X�^�R�[���B�`������łP�U�N���߂��Ă����B
�@�ׂ̐Ȃ̕v�́A��S�y�͂̋����킽�鑾�ۂ̉����A�v���ւ̂ق��N�ƁA�����v���ւ̂��˂�Ɠ�d�ɁA�d�ˍ��킹�Ē������ƌ������B����ւ̒��荞�݁A���s�����ۂɂ��ꂽ�o���҂������ƁA�؎���������B
�@�P�T�N�Ԃ̋��Y�}��]�Ɛ������������A�R�O�̂Ƃ��w�����j�Ɉٌ����������B
�@�㋉�̎w���͐E��̗l�X�ȗv�������グ�ē������A���̐��}�̋@�֎��𑝂₷���Ƃ��肪�d�_�ɂȂ��Ă���B������A�@�֎����������₵���Ƃ������Ƃ���ɓ_�������Ă���w���͊Ԉ���Ă���B�Ƃ������̂������B�C�̍�����]���ԂƎ�ȂŘb���������B����͕��h���A�K���ᔽ���ƁA�Q�P���Ԋċւ���A��������B
�@���̍Ȃ͑S���m�炸�A�����̂悤�ɔ��荞�݂̉�c�������Ă���Ǝv������ł����B�T�P�A�Q��������������Ɏ��ɍs���A������ߗނ�͂���B�v�w�Ƃ����ǂ��A�閧�͎��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���g���E��x���ӔC�ҁA�w�����Ƃ��āA�A���[��܂Ŋ����ɒǂ��Ă����B
�@�X�̓}���́A�����Ȑl�Ԃ����������B�������A�g�D�̈���Ƃ��ď@���̂悤�ɁA���ꂪ�S�Ă��ƖӖړI�Ɏw���ɏ]���l�����������B�܂��A�]�킴��Ȃ������B
�@�u���ׂĂ��^���v�Ƃ������Ƃ�����̂ɁA�^���Ă݂čl���邱�Ƃ͑厖�Ȃ̂ɁA���ꂪ�Ȃ������B����莩�����g�������ł������B
�@�����̐E��A�n��Ƃ̖����ɔY�݁A�����_�o�����ǂ����������B�v�͎��Ȕᔻ���Đ�]�����ɕ��A�������A��]�����тɂȂ����̂́A���ꂩ��P�O�N��̂S�O�̂Ƃ��������B
�@���x�͐����ȉ�c�ŁA���ꑽ�����A�����w�����̔ᔻ�������B�������тɂȂ����B
�@�ސE���͖ܘ_�Ȃ��A���C�~��݂P�Œǂ��o���ꂽ�v�́A�u�}���̈ꕪ�v�ŁA�Q�N�Ԏ���Ŗ@����Ɗw�����B
�u�����w�����́A�ᔻ�𗝗R�ɂ�����C�͕s���v�Ɩ��É��n���ٔ����֒�i�����B
�@�����Ȃ��A�ٌ�m�Ȃ��́A�ǓƂȍٔ������������B�N���ƘA��������Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA����ɑg�D�̒��荞�݂������A�U���ɏo�Ă����s���ꂽ�B
�@�����A���w�S�N���̒��j���w�Z����A��B�u�ςȎԂ��~�܂��Ă����v�ƌ����B�v�͗����������ė������A���������яo���ĎԂ܂ő���A�u�N�̖��߂Ō������Ă���̂��I�v�Ɠ{�����B�Ԃ͋}���i�ő��苎�����B
�@�����A���^�ǂŎԂ̃i���o�[�ׂ���A������̓g���^�����ԐE��x���̓}���������B
�@�{�l�ɉ�ɍs���A�g�D�̎w�߂Ƃ͂����A�s���ȍs�ׂɌ��d�R�c�����B
�@����ȓ��X�A�A��鎄�ɂ��A���ӂ̂悤�ɋ��Y�}�n��ψ�������u�Ȃ��ٔ�����߂����Ȃ��I�v�̓{���A�u�i��ψ���ɂT����U�����i���Ă���̂ɂȂ��Ԏ����Ⴆ�Ȃ��̂ł����I�v�̌J��Ԃ��A�Ƃ��ɂ͎q�ǂ������̑O�ŁA�܂̍R�c�d�b�������B
�@���A���É��̊����X�֏o�̂��߁A���]�Ԃ𑖂点��B�r���̗c�t���̕~�n�ɉ����āA���ƐԂ̎R���Ԃ��炫�����Ă����B���̖ڂɟ��݂�V�N�Ȕ������ɂ�����S���Ԃ߂�ꂽ�B���R�ȓ��{�ł悩�����B
�@������Ƃ��x���Ȃ�����B�T���~�����̗F�A���̗F�Ɏ�Ă�肭�肵���؋����Q�N�ԂŁA�W�O���~�ɂ��Ȃ��Ă����B
�@�v�͐e�����F�l�R�l�Ɏ؋���\�����݁A�P�l�͋C�����悭�݂��Ă��ꂽ���A�Q�l�́A�����݂̑���͗F������킷����ƒf��ꂽ�B���̂Ƃ��A��i������߂錈�S�������B�v�̐l���̐��������^�������Ƃ͂Ȃ������B
�@�ǂ�Ȑl�ł��A�l���l�炵�������A�K���ɂȂ�ׂ����B���������Љ�͕s�\�Ȃ̂��낤���B
�@�S�Q�A�����邽�߂ɓ������͊w�K�m�����Ȃ������B
�u�����A�V�����X�^�[�g�ł��B�w�K�m�֗��ĕ����悤�I�v�@�w�Z�̍Z��O�ŕv�w�̃r���z��A�e�L�X�g�͑��w�K�m�ɔ�э��݁A�g�p����\�����ꂽ�B���R�A�`���̍Z������ɋ����������l�����āA�����b�ɂȂ�������ƌ����āA�e�L�X�g�g�p�������Ă���u�����͂Q��������Ȃ�����v�ƃA�h�o�C�X�����Ă��ꂽ�B
�@���̍K�^�ŁA�X�^�[�g����T�O�l�̎q�ǂ������Ă��ꂽ�B
�@���߂̍��́A�x�e�ɂ����Ɖَq���o�����B���A���k�͒蒅���Ȃ������B���̂����K�������ʂ����̂��A���͔h��������������m���A�͂����n�߂��B
�@���N�U�O�l�A���X�N�V�O�l�Ɛ��k�͑����������B����͒c��W���j�@�ƌ�����q�ǂ����������鎞���Ƃ����K�^�Ƃ��d�Ȃ�A�F�����ƁA�����Ɋw�Ԋ�сA�o����y�������݂�Ȃŋ��L�����B
�@���т��]���ɂȂ�A�ō��P�Q�O�l���^���ɕ����A�n�C���x���̍��Z�i�w���ʂ������B
�@�o�C�g�搶�������A�����ސE���č��������B�u�w�͂Â���l�Â���v�Ƃ����{���o���A�m�j���[�X�͂P�O�O���܂Ŕ��s�����B����́A�Ƃ̐l�̈ӌ���Љ���ȂǍڂ��čD�]�������B
�@�u�����̓j���[�X�̓��H�v�u���[�C�v�Ǝq�ǂ������͊�ԁB�P�l�P�l���ǂ����B����ƎЉ�̕����B
�@�u�j���[�X�̓���D���I�����āA���̎��ԕ����Ȃ��Ă�������v�B
�@���̊Ԃɂ��Q�O�N�̌��������ꂽ�B��Ă邱�Ƃ͊y���������B�q�ǂ��D���ɂ̓s�b�^���������B
�@�������ɂȂ�ƁA�v�̂��߂����Ŗڊo�߂����X���I������B�����̖���v���ƃ\�A�̕���Œ��N�܂肪���������S�̓ܓV���A�����Ɛ��ꂽ�B�v�w�Ƃ�����Ȃɑu�₩�ɁA�S���̌��͋v���Ԃ肾�����B
�@��J�������킪�q�����������S�����Ɉ�����B�Ⴂ�����̋�J�͔����Ăł�����Ƃ������A�p�����ʂ��̌������l���ł悩�����B�v�w�Ƃ��A�݂�ׂ����݂̂͂��B���ׂ����Ƃ͂�����B
�@���x�̓C���^�[�l�c�g�Ŏv���̂�����Ԃ�Ƃ����B
�@�L���Ȍ����҂��A���Y�}�̊����ƂŎ��߂��l�͑S���ɕS���l����ƌ��������A�l�c�g�ɊJ�����z�[���y�[�W�͂����P�O�N�o�����B�A�N�Z�X�́A�v�w�ł��悻�S�O�������́A�S����l�͑����̂��낤�B
�@�l���A�I�͂̏�����B
�@���|�I�Ȕ��͂̐����t���āA�g�c�G�a���̂��Ƃ����x���S�����B
�@�u���y�������Ă���ƁA���@�C�I�����̉��ɂ���A�̐��ɂ���A���邢�̓t�����[�g����g�����y�b�g�A�`�F���ɂ�����܂ŁA���ꂢ�ȉ��ł������قǁA���ꂪ�����߂����Ђт��̂͂ǂ������킯���낤�v�B
�@�u���v�@�Q�O�O�U�N�A�g�c�G�a���͕����M�͂���͂����B
�@�@�@�@�@�@�@�V������Ł@�s�A�m�͂�����
�@�g���m�ܗւŁA���E�����ڂ������q�t�B�M���A�X�P�[�g�A�����_���ɋP�������{�̍r��I��A�z�Ƃ�������������ۓI�������B
�@����A���͔h�̑I��̃W�����v�ł̓]�|���������A�l�Ԃْ̋��́A�����ɗ��K���d�˂Ă��A��������ł��낭������邱�Ƃ�������A�s�A�m���t�Ƃ��ʂ�����̂������ċ����[�������B
�@�L���ȃs�A�j�X�g�̃��q�e�����u�s�A�m���|���v�Ɣߖ��グ�鎞���������B���������Ă���͉̂��y�]�_�Ƃ̋g�c�G�a���ł���B�u�����̔��q�ɈÕ����ǖY�ꂵ�āA���s���邩���킩��Ȃ��B���̋��|���ނ�s�A�j�X�g�̔w���ɒ���t���Ă���̂��킽�������͖Y�ꂪ�����v�B
�@�������̃s�A�m���t��́A�قƂ�ǂ�60�Α�̏����ŁA�e���l�͖�40�l�B
�@�t�B�M���A�X�P�[�g��4���A���t��̃s�A�m�Ȃ��A�����������ꂭ�炢�e�������Ȃ̂ɁA�o���҂́u�S������яo�������v�Ƃ��A�u�肪���Ղ̏�łԂ�Ԃ�k����v�Ƃ����B���悻�����͏C�s10�N�̃x�e�����ł���B
�@���̓��A�}�X�l�[��ȁw�G���W�[�x��e�����B�w�����A�߂��������t��!���炵�����͂������ɁE�E�E�E�x�Ɖ̂��A�������y�Ƃ��č��ꂽ���̋Ȃ̃����f�B���ۗ����Ĕ������A������ꂽ�B
�@�J��Ԃ����K���A�Õ��܂ł������A�����{�ԂɂȂ��ċْ������̂��e���|����⑬���Ȃ��Ă���B�f�����w�����Ƃ���ł��ꂩ�������A�Ō�̌����Ȑ����ɏ�����ꂽ�B
�@�����_���X�g�́A�J��Ƀo���@���b�e�B���̂����A�C�^���A�̌��w�g�D�[�����h�b�g�x���Ă��̋Ȃɕς����B����Ȃ���s�v�c�ȉ^���̂悤�Ȃ��̂��������ƌ����Ă����B
�@�O�b�𐔂���̂ɁA�u�����A�c�[�A�X���[�����ł͒Z���̂Łv����ɁA�u�A�C�X�N���[���v�������b�ɂ͒E�X�����B�Ɠ��̗D��ȕ����w�C�i�o�E�A�[�x��n��o���A���_�ɂȂ�Ȃ��̂ɕ������B���ꂪ���E���̐l�X��B�Â��ɂ����B
�@�H�v���A�w�͂��d�ˁA�X�P�[�g������ށB
�@���ꂱ���A�����_���̌����Ǝv�����B
�@�������o���́A�c�����푈�ŁA�邲�Ƌ�P�������B
�@���É������̎��Ƃ֑a�J�����B�e���r���Ȃ�����A�^���ÂȖ��Ɍ������āA�̂���̂��Ă����B
�@���ׂ̂�����A�u�������܂��ˁ[�v�ƖJ�߂Ă��ꂽ�B������A���ӓV������ʼn̂����B�w������̂�����x��w�݂���̉ԍ炭�u�x�B���y�͎₵�����A�����������Ă��ꂽ�B���ꂪ�u�s�A�m��e�������v�̌��_�����m��Ȃ��B
�@�s�A�m�ɗ�ޒ��Ԃ����́A�e�̉������Ȃ���A�����́A���N�̐E�Ɛ����𑲋Ƃ��Ă���A�s�A�m�ɒ��킵�Ă���B�s�A�m�͖����ނ��߂ɂ���B���̓_�����́A�����_���X�g�Ɗ��S��v����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�s�A�j�X�g�@������q�ɂ݂�l�Ԑ�
�@�P�O�N�O�A�a���̃s�A�j�X�g������q�̃��T�C�^���ł��̖{�����B
���ܓǂݒ����āA�����ʂ����������A��������قǂɊ����Ȃ������̂́A�����̖��n���́A���̖{�ɂ͐l�̐S�ɔ���A�������̎��b���ڂ��Ă���B
�@�u�P�v
�@���̂ЂƂ��u�E�r�̏��������̓��m�̋����v�ł���B
�@���{�̃V���p���e�����������ɔF�߂钘�҂́A������̎�p��A�t�������p�B���Ƃ������ǂƍR����܂̕���p�ɂ��߂܂��ʼn��t��f�O���Ă����B
�@����A�A�����J���\����s�A�j�X�g�̈�l���I���E�t���C�V���[���́A�R�V�̂Ƃ��A�����s���̕a�C�ʼnE��̎��R��D���Ă����B
�@��]�Ɠ����Ȃ���s���̐��_�ō���̂��߂ɏ����ꂽ��i���}�X�^�[���A����̃\���X�g�Ƃ��ăJ���o�b�N�����B
�@�M�҂́A�������p��A�Ă��߂��H���������悤�ɂȂ��đ̗͂������������������A�t���C�V���[���Ƃ̋����������オ�����B
�@���t�}�j�m�t�́u�s�A�m�R���`�F���g�Q�ԁv�B�E�r�������������A�����܂ŋꂵ���K���̗��K���d�˂��B�����āA�E�r�̏������ғ��m�̋��������������B
�@�Q�R�O�O�Ȃ̑�z�[���͕S�]��̕⏕�Ȃ܂Ŗ����������ƋL���B���̔ӂ���ق�Ƃ��̍ċN���ł����ƁA��т����s�A�j�X�g�ɂ킽�����S����̔���������B
�@�u�Q�v
�@�u���[���b�p�̐^�����Ƃ͂��₾�v�ƒ����������[���b�p���w�Őg�ɂ����V���p�����t�̐����I�X�^�C���ɋ^��������A���{�l�ɂ����ł��Ȃ��s�A�m���t�̔��ɂ��čl���n�߂��B
�@�����āA�c����������k�C���ƃ|�[�����h�̗��j�ɂ��Ėڂ��������B���̂�����ɁA�V���p���e���Ƃ�����s�A�j�X�g�̗D�ꂽ�i�����������B
�@�k�C���̗��j�͗����̗��j�������ƒ��҂͏����B
�@��Z�����A�C�k�̓J���C�k�_�l�Ƌ��ɕ��a�Ȑ������c��ł������A�a�l�����������Ă��Ă��炱�̒n�͌��ʂ��Ă������B�������͓����A�ȒP�ɁA���{�l�͒P�ꖯ���Ƃ����Ă��邪�A����k�����l��k�C���k�A�C�k�l�̗��j��k��A�P���Ɍ�����Ȃ����Ƃ�����B
�@�V���p�������܂ꂽ�|�[�����h���A�P�W���I�����Ƀv���Z�C���A�I�[�X�g���A�A���V�A�̂R���ɂ���ĕ�������Ă���ߌ��̗��j���͂��܂�B
�@���͂Ŏx�z���悤�Ƃ���҂ƁA�x�z�҂ɗ����������ҁA���̈Ⴂ���ĐS�̒��ŏd�Ȃ�B�M�҂͂P�W����|�[�����h�ŕ�炵���̂ŁA���R���낤�B
�@�V���p���̎���A�l���݂ɂ����ė����l�X�̐⋩�ƌ����Ă������w�v���x��w�،͂��x�̃G�`���[�h�A�X����v�������߂��w�p�Y�|���l�[�Y�x������e�����B
�@�P�X���I�̐������ߌ��̗��j��瞂��M�Œe�����s�A�j�X�g�̐[���A�т������A�s�A�m�̎��l�Ƃ�����V���p���̕ʂ̐l�Ԑ��ɐG�ꂽ�z�����B
�@�k�R�l
�@���Ɨׂ荇�킹�̎q�������̂��w�}�C�E�E�F�C�x
�@�k�C�����_�̏����Ȓ��ɕa��{��w�Z������A�����̏d�x�W�X�g���t�B�[�̎q�ǂ��������w�K���Ă���B
�@���̒��ł����₩�Ȋy��X���J���Ă���l���A�G���L�E�M�^�[��h���������̎{�݂Ɋ����B�ȉ��͔ނ̘b�B
�@�W�X�g���t�B�[�́A�̒��̋ؓ��������Ă����āA�ċz����ƂȂ�A��l�ɂȂ�O�Ɏ���ł��܂��q������B
�@�����łQ�P�Ŏ��N���w�Z�̑̈�قł̃R���T�[�g�ɁA�v�w�����҂��Ă��ꂽ�Ƃ����B�����Ŏ��쎩���̋Ȃ����Ă��ꂽ�B
�@���̃R���T�[�g�̍Ō�ɁA�q�ǂ������S���ł킽�������v�w�̂��߂Ɂw�}�C�E�E�F�C�x���̂��Ă��ꂽ�B�S�Z�ŕS�l���炢�̎q�ǂ����B
�@���N�A���l�����q�ǂ�������ł����B���̎q�ǂ��������s���R�ȁA�܂��Ȃ����ŁB�����������Ă��Ȃ����A���t���悭�킩��Ȃ��̂�����ǁE�E�E�B
�@���̊y��X��͕M�҉�����q�Ɍ�葱�����B
�@�u�ǂ�Ȃɂ��܂��̎肪�̂��Ă��A���́w�}�C�E�E�F�C�x�ɂ͂��Ȃ�Ȃ��B����Ȃɋ������ꂽ�}�C�E�E�F�C�́E�E�E�v
�@���T�C�^���ŖK��Ă��̘b�����M�҂́A���N��A�����Ȃ���Ăє��_�̓y�B�����āA�V���p����e�����Ō�Ɂw�}�C�E�E�F�C�x��e�����B
�@���̓�����P�O�N�߂��o���A�䂭���тɕK���Ō�Ɂw�}�C�E�E�F�C�x��e���B
�@�����ӂ��߁A�ܑ̂������Ȏ҂́A���ꂪ������O�ŁA���ӂ̋C������Y�ꏟ���ł���B�k���̏����Ȓ����畷�����Ă������ȁw�}�C�E�E�F�C�x�B
���̉̐��ɐS���X�����M�҂́A�P�O�N�߂������܂����C�Ŋ���Ă��邾�낤���H
�@���{�T���������̔�Q�ґ���s�A�m�Ō�����ꂽ�j���[�X�͕��������E�E�E�B
�@�����A�S�����߂Ēe���B�w�}�C�E�E�F�C�x���B
�@�@�w���̂��̐��u�������Ƃ͂�������邱�Ɓv�x�@������q��(�C���ЁA�P�X�X�S�N�T��)
�@�@�@�@�@�@�@���y�ނ��Ȃ�
�@�m�g�j�X�y�V�����u�A�V���P�i�[�W�E���R�ւ̃R���T�[�g�v�́A�s�ˎ������̂m�g�j�ŁA�v���Ԃ�ɂ����ԑg�������B
�@�X�^�[�����̋��|��������A�V���X�^�R�[���B�b�`�͌����ȁu�o�[�r�B�E���[���v����Ȃ����B(�P�R�ԕσ��Z����i�P�P�R)
�@�T�̊y�͂���Ȃ邱�̋Ȃ́A��S�y�́u���|�v�Ŗ��炩�ȃX�^�[�����̐��ւ̔ᔻ�X�Ɖ̂����B�u�钆�ɂ����ƃh�A���m�b�N���鉹�B����͑ߕ߁A�č��c�v�����̂��B
�@�����A���t�o�����̂͂P�X�U�Q�N�P�Q�������݂̂ŁA�X�^�[��������̃\�A���ǂɉ��t���֎~���ꂽ�B���ǂɂ��̎������߂ȂǁA�������������Ƃ肪�������B
�@�ԑg�ɂ́A�P�X�X�P�N�\�A�����A���̋ȁu�o�[�r�B�E���[���v���������ɖ߂����̎��Ń��[���b�p���t�������A�s�A�j�X�g�ł���w���҂ł�����A�V���P�i�[�W���o�����Ă����B���̂悤�ȁA���̂��鉹�y�ƂƂ͎v���Ă����Ȃ������B
�@�X�^�[�����̐����ł́A�|�p�������p�����Ă������Ƃ͎��̊o�傪�v�����B
�@�P�X�R�O�N�A���l�̃E���W�~�[���E�}���R�t�X�L�[���s�X�g�����E�����A�Ȍ�A�S����|�p�Ƃ͒��ق�����ꂽ�B
�@�}�N�V���E�S�[���L�[�́A�w��x�ō����I��ƂƂȂ����B�������A�ӔN�X�^�[�����̐����������悤�ƁA���}���E���[������A���h���E�W�C�h�ƌ𗬂��A�閧�x�@�ɓ�����͂܂�A���̂R�N�O�����猵�����Ď����ɂ����ꂽ�B
�@�P�X�R�U�N�ɓ�̎��𐋂��Ă��邪�A�\�A�����ɔ��@���ꂽ�����ŁA�X�^�[�������ނ��E�������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B
�@���̂悤�Ȏ���ɃV���X�^�R�[���B�b�`�������c�ꂽ�̂́A��ՂƂ�������B
�@�A�V���P�i�[�W�͂P�X�R�V�N���܂�A�P�X�U�O�N�Ƀ����h���ɖS�����āA�{�i�I�Ɏw���������n�߂Ă���B
�@�P�X�T�T�N�̃V���p���R���N�[���ł͗��K�ȂU�Ԃ�e�����B����͌�̌�葐�ɂȂ�قǂ̖����t���������A�R���N�[���͂Q�ʂ������B�R�����̃~�P�����W�F���́A�D���𐄂��Ă������A�R���ɔ[���ł����A�R���������ނ����Ƃ����B
�@���͉��y�̐��m���ȂǂȂ����A�Ⴂ���P�N�߂��]�����ŗ×{�����Ƃ��A�N���V�b�N���y���Œ������B
�@�U�O�Ή߂��Ďn�߂��s�A�m�́A�����e�����s�A�m�́A�u�~���v���ڊo�߃R���T�[�g����ŁA�����T�N�ɂȂ�B
�@�Ƃ��ɁA�s�A�m���e���ĉ��ɂȂ�H�Ƃ��v���B���ʂƌ����A�����ނ��ȂƂ����₵���B
�@�ł��A�l���Ă݂�ΐl���ɂ͖��ʂ��v��B���ʂȂ��Ƃ����́A�Ȃ��Ȃ��̂ē���Ŋ�����B������̉��[���A��������A���݂��݂Ƃ�����т����ɂ���ğ��݂킽��B
�@�z�[���y�[�W�Ɂu�������Ȃ閳�ʂ̊�сv�Ƃ������͂��ڂ��A���y�ЂƂ����̋�����{�点����������B�Õ��Œe����悤�ɂȂ�܂ł̎��Ԃ��A�������Ǐ��ɂ��Ă���A�����v��Ȃ��ł��Ȃ��B
�@�V�����Ȃɒ��킷�铖���͂��肵�A�ǂ��ɂ��Ȃ炵���Ȃ�A�Õ��Œe����悤�ɂȂ�Ƃ���Ɗ�тɂȂ�B
�@���E�̖��Ȃɒ��킵�A���키��т����߂Ȃ��̂́A��͂艹�y���D�������炾�낤�B�w�͂��Ēe����悤�ɂȂ�̂�����݁A��������ɂ͍l�����Ȃ���Ƃ�ɋC�t���̂��s�A�m�̂��A�ł���B
�@���b�X���I����A�����N���X�̐l�����Ƃ̌y�H�����Ȃ���̎G�k�́A�l���ꂼ��ɐl��������Ă��閡���o��B
�@������A�Q�l�̐V�l������������A�P�l�͓Ɛg�̂܂ܒ�N�܂œ����āA�ސE���Ă���}���V�����ƃs�A�m���w�����Ēe���n�߂��B
�@�����P�l�͕v�Ɏ��Ȃ�A�q�ǂ��͂��邪�A�V�O�łЂƂ�V�l�p�}���V�����ɓ���A�Җ]�̃s�A�m���K���n�߂��B�����̌��f�͂ɒE�X�����B
�@���̂ނ��Ȃ��̂悤�Ȍ𗬂��y���݂̂ЂƂł���B
�@�S�N���X�ł��悻�T�O�l�B���t���\��͂R�����ɂP��ł��邪�A���Ȃ�̒e������A�����܂ŋ���������l���ْ��̂Ƃ��ł���A���̐V�N�ȕ\���قƂ��鉽��������A����Ӗ��ł͑s�ςł�������B
�@���낢��Ȏ���⎩�g�̌��E�����o���Ď��߂�l�����邪�A��������A���̂Ƃ��܂ł���Ă݂悤�Ǝv���B
�@���\��߂��Ȃ���������A�b�c�ŃV���p���̗��K�ȑ�R�ԁw�ʂ�̋ȁx�����B���t�͋��R�A�A�V���P�i�[�W�������B
�@�A�V���P�i�[�W���t�ł鉹�F�́A�����P���̂b�c�Œ������s�A�j�X�g�̉��t�Ɖ���������Ă���B�f�l�Ȃ�ɂ��ꂪ�킩�����B
�@�\�������R�ŁA���݂��݂Ƃ������S��\���Ȃ���A�t�H���e�֓����͋����A�����ĐÂ��Ȍ��сA�����Ȃ���Ȃ��������f���ɂ�����ɟ��݂Ă���̂��킩�����B
�@���̋Ȃ́A�V���p���Q�O�̍�i�Łu���͂���قǔ������Ȃ����������Ƃ��Ȃ��v�ƒ�q�Ɍ�����Ƃ��B���V�A�ɐ苒���ꂽ�c���|�[�����h�Ɋ�z�����A�J���ɖ�������������Ђ��Ђ���������B�ʂ�Ƃ́A�l�Ƃ̂��ꂾ�����l���Ă������́A�F�������߂��B
�@�P�W�P�O�N���܂�̃V���p���́A�Q�O�̂Ƃ����V�A�ɑ��郏���V�����ق��N�R�ɎQ�����悤�Ƃ����B���̊W�ŃE�B�[���ɋ��h���Ȃ�A�p���ɖS�������B�V���p���̕��̓|�[�����h�v���R���o�āA�M���̉ƒ닳�t�Ƃɂ��Ă����Ƃ������Ƃ��킩�����B
�@�s�A�m�̎��l�Ƃ�����V���p���̎��I�ő@�ׂȍ�i���������A�L���ȃ|���l�[�Y�́w�v���x��w�R���x�Ȃǂ̋Ȃ���������Ƃɓ��S���������B
�@�h�C�c�ɐN�����ꂽ�P�X�S�O�N��̃����V�����ق��N�͒m���Ă��Ă��A���̂P�P�O�N���̂ɁA�N���҃��V�A�ɑ��ă����V�����ق��N�����������Ƃ�m��A�����̔ߌ��Ɛl�Ԃ̋�������z�����B
�@���V�A�̃|�[�����h�ւ̐N�U�A�ƍّ̐����ł̌|�p�Ƃւ̈��́B�����͗D�ꂽ�˔\�̔������ז����������B�������A���̋ꂢ�l���̖��ʂ��A�[�����킢�Ƌ�����l�X�ɗ^����̂ł͂Ȃ���
�@���肷��قǂ̍������A����ł�������ł����Ƒ��������N�A�Ă̏I���ɁA�V���p���ƃV���X�^�R�[���B�b�`�A����ɃA�V���P�i�[�W�A�R�l�������c���Ǝ��R�ւ̔M���z���ɐG�ꂽ�B����̓\�b�Ɣ��ł�H���̂悤�ɁA����₩�ɁA�S�n�悭�����B
�@�������A���\��̓V���p�����A�A�V���P�i�[�W���B
�@���Ȃ�̉�����\���������ƁA��������点���̂ł���B
�@�@�@�@���@�@�@�A�V���P�i�[�W�͂Q�O�O�S�N����m����C�w���҂Ɍ��܂����B
�@�@�@�@Google�����w�V���p���N�\�x�@�@�w�V���p���̐��������x
�@�@�@�@�@�@�@�u���z�ȕ��\�i�^�@�����v�ɑz��
�@�v���Ԃ�̃��T�C�^���ŁA�x�[�g�[���F���́u�����v�����B���V�A�̎��s�A�j�X�g�@�A���N�T���_�[�E�M���f�B���̉��t����u���z�ȕ��\�i�^�v�̑�P�y�̓A�_�[�W���@�\�X�e�k�[�g�́A�Ɠ��̊����������B
�@�P�O�N�قǑO�A�f��u�����̉āv�ŁA���U���������̋Ȃ�e���������I��ʂ��v���o�����B�v�w�Ŏ������̊J���x�ɓo�����̂́A���ɍs�������������A�F���x�m�Ƃ����邱�̎R��ڈ�ɂ��ĉ���֔���Ƃ�m�������炾�����B
�@�m���̓��U���a��قŁA�푈�̂��߂ɓ��e�ƂȂ��ĎU�����Ⴂ���A�P�O�Q�U����m��A��������̈⏑��ǂB���ꂩ������S�N���߂����B
�@�u����܂���������@���ꂩ�玀�ɍs��������Y��Ă��܂��������v�u�K���A���h�ɑ̓�����v���܂��v�B�����̈⏑�͋������߂���B
�@���T�C�^���ňꏏ�������F���A�f��Ɠ����薼�̏�����ǂƂ����̂ŁA�����݂肽�B
�@���̃h�L�������^���[�����A�u�����̉āv�ɂ́A�f��ɂ͂Ȃ��Ռ��I�Ȏ������L����Ă����B����́A���U�o�����ēr���ŕČR�̍U���������ĕs����������A�G���W���s���ň����Ԃ��Ă����������������ӂ���A��֏�Ԃɂ����ꂽ�Ƃ��������ł���B�u���܂��́A���̂����ɂ����Ȃ����̂ł͂Ȃ����v�u�G���W���s���Ɍ��������āA�����c�낤�ƌv�����v�����̎��ӂɁu���肢�ł��B������x�o�������Ă��������v���������͐g�̌������咣���āA�ēx�̌����s���咣�����Ƃ����B�����������̊�h�Ɂu�U�����v�ɂ́A�S�O�l�قǂ����e����Ă����Ƃ����B
�@���́A�����c��A��]���Ȃ���l���𑗂������������̔�b��ǂ�ŁA���̐����A�Ƃ��̌��͎҂́A���̂悤�Ɍ��Ђ�U�肩�����A����̐g�͉������A�����̑P�ӂ݂ɂ���̂��Ǝv�����B
�@�ߍ��C���N�Ől���ɂȂ��ĊJ�����ꂽ�R�l�ƁA���̉Ƒ��ւ́u���ȐӔC�v�升���������悤�Ȃ��̂ŁA�قȂ�ӌ��ւ̈Ӑ}�I�o�b�V���O�ŁA���̃��x�����p���������B�����ĕ|�����Ƃ��Ǝv���Ă����B
�@�u���z�ȕ��\�i�^�v�����̋Ȃ́A�킽���̂�����ɟ��ݍ��ށB
�@�@�@�@�@�@�@��������Ȃ閳�ʣ�̂�낱��
�@�d�������߂��U�O����R�N��A�s�A�m�����ɒʂ��n�߂��B�����͂R�J���ɂP��̉��t��̓��A���̋����̋�������Ȃ�����X�y�C���̌��z���e�����B
�@�I���W�i�����Ɣ��������������͂̋Ȃ������B
�@�����͌�������Ɉ��������āA��N������̉��y�������ō�ȁA�ҋȁA�s�A�m���t�̎w���𑱂���T��A�Ⴂ�w���҂��琬���Ă���B
�@�搶�����̒��J�Ȏw���ɓ�����ׂ��Õ��ł���܂ŗ��K�����B�Õ��Œe����悤�ɂȂ�ƁA������s�A�m���b�X���͑傢�Ȃ閳�ʣ�ƌ����A���K����i�Ɗy�����Ȃ�B
�@�x�[�g�[���F���̢�����̋ȣ���e����l���A�n�߂�����ŁA��r�I�ȒP�ȋȂ��ԈႦ��l���A�݂ȋْ����āA���E�̖��Ȃ�e�����т𖡂�����B�����̂́A���̂قƂ�ǂ��U�A�V�O�Α�ŁA�����Ȏw�������ł��A�\��������Ƃł���B
�@���̓��AO����̓E�F���i�[�̢�̂磂�e�����B
�@O����v�w�͎R�������y���ނ����ǂ�v�w�������B��A���v�X��o�R���ɓˑR�A���ɏP��ꂽ�B���x�P�N�O�̎����ŁA�e���r�̃j���[�X���ς��ȂƁA�l���Ƃ̂悤�ɊςĂ����B
�@�ቺ�ɍL����_�C�A���̉_��˂��j��A���͒n���ĉ�����삯�オ��A�A�b�ƌ����Ԃ��Ȃ��A���v�N�̖���D�����B
�@O������ӎ������������ꖽ�͎�藯�߂��B�P���������@�����a�@�ŁA���_�����S����O����́A�v�̎���m�炳�ꂽ�B
�@���̂̃V���b�N�ŋ������x���A�܂͎~�܂炸�A����Ȃ��邪�������B
�@���̂܂ܕv�̌��ǂ������Ƃ����z����f���Ă��ꂽ�̂́A���ꂩ�琶�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��q�ǂ���������O����͌������B�����āA��l���q�ɐ旧���ꂽ�X�O�����̋`��Ɠ�l�̐������n�܂����B�`��͕ҕ������ӂ����A�������A�Ԉ֎q���K�v�ɂȂ��Ă����B
�@O����́u�������Ƃ����C�������Ȃ���v�Ɨ�܂��A�����P����K���ő������B
�@�Ƃ��Ƃ��������B���܂ł́A�����߂��̑��q�̕�܂ŕ����Ă��Q��ɏo������Ƃ����B
�@�R�J���x�����ŁAO����͋����Ɏp���������B
�@�Ƃ��ɂ͗܂���ŁA���C�Ɍ����ɗ������������Ƃ���O����́A��s�A�m������ĂĂ悩�����B���K����Ƃ��͖��S�ɂȂ�邩��c�c��ƌ����B�����N���X�̎��������t�ɗ�܂��ꂽ�B
�@O���t�ł颖�磂́A�R�̐��X������C�ɁA���R�A�����炫�����Ă��镗�i��z�킹��f���炵�����t�������B
�@�s�A�m���t�͂�����̕\���ł���B
�@�l���̉��F���A�H���ƂƂ��ɂ�����ɟ��݂�B���܂��炭�A�������Ȃ閳�ʂ��y�������Ǝv���B
�@�@�@�@�@�@�@���ɐF������
�@�@�@�@�@�@�@�@��������z����̂��l����t�W�q�E�փ~���O�A��l���͊R�o�裗{�V�Ўi
�@�s�A�j�X�g�@�t�W�q�E�փ~���O�́A�w���E�J���p�l���x���ăt�@���ɂȂ����l�͑����B�������̈�l�ł���B
�@�ޏ��͗c��������V�˂Ƃ���ꑱ�����B����ɂ�������炸�P�X�U�X�N�f�r���[�����܂������O�ɕ��ׂŗ����̒��͂������ǂ�ꐶ�������Ă����B
�@���t������łb�c�������悤�ɂȂ����̂́A���ŋ߁A��̎��ŋA�������P�X�X�X�N�A�m�g�j�ŕ�������Ă���ł���B
�@�\��̂��Ƃ́A�ŋߏo�������@�w�t�W�q�E�փ~���O�^���̗́x�ɂ������B
�@�ǂ�ꐶ�����������A���Ⴊ���������H�ׂĂ���Εa�C�m�炸�������ƌ����B
�@���̖{�ɂ́A���E�I�ȉ��y�ƃJ��������A�o�[���X�^�C���A�N���C�_�[�}���Ƃ̐G�ꍇ�����A�ʐ^����ŋ����[��������Ă���B
�@���ł��A����X�g��u���[���X�́w�n���K���[�����ȁx�́A�Ƃ̂Ȃ��悤�ȕn�����l�����̉��y���������ȂŁA�h�C�c�ɂ���Ƃ�����悭�e�����B��������A���鋳��������ȋȂ�e���ȁI�Ɠ{�����B����A�Ȃ�ł���ȕςȋȂ��A���X�g�͍�Ȃ����̂��Ɠ{���Ă������B
�@�w���y�͔�]�Ƃ̂��߂ɂ���̂ł͂Ȃ��x�Ƒ肵�����̏͂ł́A�����ЂƂ̃G�s�\�[�h���Љ�Ă���B
�@��h�C�c�Ŏ��̒e���s�A�m���Ȃ���d�������Ă�����H���A���ւɏo���Ƃ��A�~���[�W�b�N�A�~���[�W�b�N�ƌ����Ăɂ��ɂ����Ċ��ł��Ă��ꂵ�������B���Ԃ̋Ȃ�e���Ă����̂��������킩��Ȃ��̂ɁA���̃s�A�m���y����Œ����Ă��ꂽ�B���y�݂͂�Ȃ̂��߂ɂ���̂棁B
�@�����Ƀt�W�q�E�w�~���O�̐^����������ƁA�������ɋ��������B
�@��s�A�m�͉��̂ЂƂЂƂɐF������悤�ɒe���B�@�B�̂悤�Ɋ�p�ɐ��m�ɒe�����S�Ȃ̂͌�����Ƃ͂�����L���B������ȃ~�X����ɂ�����A�ǂ��������Ŏ��炵���e��������厖�Ȃ��ƂƂ���������A���x���͂܂�ňႤ���A���Ƃ��Ă���s�A�m���y���ގ��ɂ͗�݂̂��Ƃł���B
�@�����ЂƂ̕\��w�l���͊R�̂ڂ�x�́A�ŋߕ]���́@�{�V�Ўi���w�o�J�̕ǁx�̍Ō�̏͂ɂ������B
�@��l���́A�ƍN�������d�ׂ��ĉ��������s���ǂ��납�A�l���͊R�o�肾�
�@�Љ�I�n�ʂ��o�ϓI����������w�̋����ɂ��āH�@�Ƌ������B
�@��R�o��͋ꂵ������ǁA����オ��Ύ��E�����ꂾ���J����B�������A����オ��̂͑�ςł��B��𗣂�����瘾�̒J��ɂ܂��t���܂ł��B�l���͂����������̂��Ǝv���B������A�N�����Ċy���������B�m�I�J���͏d�ׂ����ƣ
�@���͐��N�O�A�o�R�����O�d���̑吙�J���v�����B
�@�Z���A����Ȃ������F�̐��̔������͓��{��A�������A�d���傫�ȃU�b�N��w�ɁA��ɑł��t����ꂽ���������A����ŕK���ɒ݂͂Ȃ��碂����]�����̌��ꣂ̊Ŕ�����B�[�R�H�J�̐��E�̓J������������]�T���Ȃ��A�u���̖��f�Œ�[���J�ɋz�����܂ꂻ���������B
�@�����ɁA�w�o�J�̕ǁx�Ɓw�t�W�q�E�փ~���O�^���̗́x�̋��ʓ_���݂��B
�@�w�o�J�̕ǁx�̗{�V�Ўi�͢�b���킩��A���邢�͐�̐^����͂����Ƃ����B�ꌳ��`�łȂ���`���咣���Ă���B���̓_�́A�L���X�g������̐_�ƐM�����_���̃t�W�q�E�փ~���O�ƈႤ�_�ł���B
�@�ЂƂ̐_�݂̂�M����A�L���X�g���A�C�X�������A���_�����M�҂��A���E�l���̂R���̂Q�Ƃ����B���{�͎��R�@���̐��E�A���S��(�₨��낸)�̐_�̐��E������A��ΓI�^���͑��݂��Ă��Ȃ��ƁB
�@���͒��N�A�Љ��`�͐l�ނ̗��z�ƁA��������ΓI�^����I�Ȕ��z�����Ă����B���ꂪ�A���X�̎E�l���ӂ��ޔ�l�ԓI�Ȍ����J��Ԃ��A�閧�ɂ����������͂ŁA�V�O�N�]��ŕ��Ă��܂����B������A��ΓI�Ȑ^���ȂǐM���Ȃ��B
�@����Ȃ�̋�J���̌����āA�����͈ꕔ�A�^���čl���镔�������ׂ����Ǝv���悤�ɂȂ����B
�@������A�{�V���̢�Ō�́A�l�Ԃł���������낤�A���������������c���Ă��Ȃ��̂ł́H��ɋ�������̂ł���B
�@�{�V���́A�`���łm�g�j��ᔻ���Ă��O�͐_�l���Ƃ܂Ō����Ă���B
�@������A�q�ρA�����̕����b�g�[��Ȃ�Ă��蓾�Ȃ��ƁB
�@�C���N�푈�����̕����łȂ��A�S�˂����M��������āA�ґ�ȑ����̔ԑg�Ґ������Ă���m�g�j�ɓ�������^��ƁA����|���������Ă���̂́A�������ł͂Ȃ����Ƃ��킩���Ēɉ��ł���B
�@�Q���Ƃ��A�����Ɠǂ߂āA��������܂��B
�@�w�t�W�q�E�w�~���O�^���̗́x(�s�a�r�u���^�j�J�A�Q�O�O�P�N)�B�w�o�J�̕ǁx(�V���ЁA�Q�O�O�R�N)�B
�@�@�@�@�@�@�@�u���b�t�Ƃ����肳��
�@����̖��_�������J����T�O����̃s�A�m������ł����肳��ƒm�荇�����B�ޏ��́A�����̋A��Ɍy�����H�����ɂ������A���炭���@���̂��o�����K��������ꂽ�B
�@���̂��߂ɁA�����̂���h����n���S�Ŗ��É��w�ɏo�Ă���A�܂����S�ɏ��ς��čs���ꂽ�B�������S�𗘗p���鎄�́A�r���܂ňꏏ�ɍs�������B
�@����͂��肷��悤�ȏ����Ăł��K���Ƃ�ꂽ�R�[�X�ŁA�s�A�m���������Ŕ�ꂽ���́A�������S���Ă����B�v�ɐ旧����Ă���A�w���߂��Q�l�̎q�ǂ�����ďグ��ꂽ�ƕ����B�撣��₳��ł���B
�@�ޏ��͂��ƂΕ\�����L���ŁA���邩�����B�����̐܂�Ƀu���b�t�̢���@�C�I�����̉��F��Ƃ���������ɍڂ����Ǝf���A���Гǂ܂��ĂƗ��B�����Ď��̂g�o�ɍڂ������ĖႤ���Ƃɂ����B
�@�����b�c�Œ��������A�������̋ȂƁA���炽�߂ċȂ̑f���炵���ɋ������ꂽ�B
�@����A���s�Ŋw�������𑗂�A�N���V�b�N���܂��������j����ڂ������̋ȍD���ȂP�Ȃ��棂Ɠd�b�Ō����Ă����B
�@�s�A�j�X�g�̃t�W�q�E�փ~���O�������ɏ����Ă���悤�ɁA����y�͂킽�������݂�Ȃ̂��߂ɂ���̂���B
�@�@�@���@�C�I�����̉��F�@�@�@�V��������
�@���̓��A���͉��������O�ɍ��܂�������݂��Ȃ���A�L���̎G�Ђ��������Ă����B���̎��A�����������ςȂ��̃��W�I���痬��Ă������@�C�I�����̉��F�E�E�E�E�B
�@���̉��F�̂��܂�̔������ɁA�G�Ђ����̎���~�߂āA�I���܂ŕ��������Ă��܂����B
�Ȃ��I�������A�������ꂽ��ȎҖ��ƋȖ����}���Ń����������B
�@�u���b�t��ȁ@�@���@�C�I�������t�ȁ@�@�P�ԁ@�@�g�Z��
�@�ȗ����̋Ȃ́A���̐S�̋��菊�̂悤�ɂȂ����B
�@�P�����I���Ăق��Ƃ���ЂƂƂ��A���̋Ȃ��B���x�����Ă��A�ŏ��̊������h��A�K���Ȏv���ɂ܂��B���̂b�c�ɂ͓����u���b�t�̃X�R�b�g�����h���z�Ȃ������Ă���B
�@�A�T�ȏo�����̋Ȃ́A�������[�����̒������܂���Ă���悤�ȍ��o���炨��������B
�@���̋Ȃɂ��ẮA�ȑO�m���̃R���T�[�g�}�X�^�[�����Ă��炵�����i��j���A�Ⴂ�Ƃ��ɁA���߂Ă��̋Ȃ����܁A���̐����̂��܂�̔������ɋ���ł��ꂽ�ƁA���W�I�̑Βk�Řb�����Ă��炵�����A�u���b�t�̉��y�ɂ́A�l�̐S�𖣗�����v�f�������ɂ���̂��낤���B
�@���̂P���̂b�c�́A�{���ɂ悭�������B���̎����Ă���b�c�́A�T���o�g�|���A�b�J���h���t�A���C�v�c�B�q�Q�o���h�n�E�X�nj��y�c�A�w���́A�N���g�}�Y�A�����A�z�K�����q��������̂Q�Ȃ���ꂽ�b�c���A���N���O�ɏo���ꂽ�B������w������y���݂��o�ė���
�@�ȑO���烔�@�C�I�����̉��F�͍D�����������A�u���b�t�̂��̂Q�Ȃ́A���@�C�I�����̎������Ƃ����������F�̕������A�����ɒ������Ă����B���P�l�̎��Ԃ́A�����₩�Ȋy���݂ł���B
�@���ꂩ��N����d�˂�Ƌ��ɁA�����͈̔͂́A���̂�����ƒ���Ɍ����Ă��邾�낤�B���̎��A�Ƃ�̎��Ԃ��ǂ��߂������A�����������Ă̎��̉ۑ�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�������
�@���́A�N�ɂP�x�A�o���Q�l�Ƃ��̘A�ꍇ���łP���̗������Ă����B
�@�Q�N�O�A�����̏h�Ŏo�݂���̍���ЂƂ����w���A�w�悾���������̂ŕ�܂�Ă���̂������B
�@����̎w�A�ǂ��������́H�
�@�����ˁA����ǂ����ģ
�@��ȂɁH�@���傤�Ђ��傤���ģ
�@��ŏ��ɒ܂̌`���c�́B���ꂪ�A�~�ɂȂ��ė₦��Ɣ����Ȃ�A���т�Ēɂ��̂�
�@��N�A�M�B�̂ЂȂт�����ŋv���Ԃ�ɍĉ�A�y�����b�肪�͂��B�݂���̎w�̔������̂��A���E�̂ЂƂ����w�̐�Ɋ�����Ă����B
�@��N�̊����͌����������B���̊����ŏǏi�݁A�ʂ��Ă���a�@�̈�t���碍�������n�߂Ă���B�߂Ɍ����Ăǂ�ǂ�i�s���飂Ɛ������ꂽ�B
�@����̂܂ܐi�߂Α��߂܂Ő�Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ飂Ɛ鍐����A�w�悩��V�~�������Ƃ����B
�@��p�̓��A��������n�߂����납��A�݂���͐q��łȂ��ɂ݂ɂ̂�����������B�_�o�͎w��ɏW�����Ă���A��������̒����ߌ��ɂ��������A���ɂ������N����������B���̓����A���̎��̓������悻�P�T�ԁA�݂���͖�����ނ���Ƃ�ꂽ�B������Őh�����Đ���ɂ����ƍ��ɘb�����B
�@������A��A�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ��a�C�̐��̂ɁA���͂��R�Ƃ����B�����ǂ́A�P���a�̂ЂƂŎw�����S�̂��d���Ȃ�A�r���܂ōL����s���̓�a��B
�@���o���͍����Ɉ炿���N���������A����Ƃ��A�����̒�������݂���ɉ��C�Ȃ��b���ƁA��݂��ɂ����Ăǂ��������ƁH�@�܂�ł킩��Ȃ�����ƌ������B����قnj��N�ŕa�C�m�炸�������B
�@�c������A�ߏ��ɓ������̉̎�Ƃ��Ċ��Ȃ���A���l���̎q�ǂ������Ƀs�A�m�������Ă���搶�������B�e�݂͂���ɂT����s�A�m���K�킹���B�x�e�����炵���A���ǂ��̋C�������I�����y�ɓ����Ă��ꂽ�B�݂���͏����Ȏ�ŁA�P�I�N�^�[�u���L���Ēe�����߂ɁA�����A�e�w�ƂЂƂ����w�̊Ԃ��L����̑������Ă����̂��v���o���B���̉Ƃւ͍����ꏏ�ɂ��Ēʂ����B
�@���[�c�@���g�̢�g���R�s�i�ȣ��A����k�G�b�g��A�x�[�g�[�x���̢�G���[�[�̂��߂ɣ�ȂǁA�L���ȋȂ́A����Ȃ��e����悤�ɂȂ��Ă������B�݂���͉���i�݁A�s�A�m���t�Ƃ��ē������B
�@���N�T���A��c���{�̖@�v�������Ƃ��A�݂���͂����ƌÂ��Ȃ����s�A�m�̂ӂ����J�����B�ЂƂ����w�̐�ɔ�����т��������E�̎�ŁA���Ղ��班�����ꂽ�ʒu���A�ׂ��Ɏw�����Ă����B
�@����́A�����ƃV���p���̈��ɂȂ������z�ȂQ�O�ԁA�d�n�Z����ɈႢ�Ȃ��B
�@���N�O�A�|��ĂP�J���Ő����}�����݂���̕v���D���������B���������̂悤�ȒZ���̐����B
�@�ׂ̕�������A�����Ƃ��̌��i�߂����̖ڂ��܂łڂ₯���B
�@�@�@�@�@�@�@�N���b�V��(������)
�@�f��w�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�x�̒��̉��y�w�G�[�f�����C�X�x�́A��l�̃����f�B�[�Ƃ�����B��N�X���A���K�o�R�����������ɗ當��������ĒT������A�����������x�������ꂩ�����Ă����B�������A�C�ӂ̊X���ȊO�͐l�e���ق�̐��l�A�قƂ�ǖ��l���̂悤�ȓ��́A���Ԕ������ς��Ŗ��邭�P���Ă����B
�@�X�C�X�̍��Ԃł����锒�����ȃG�[�f�����C�X(�ʖ��E�X���L��)��̂́A���̍������Ӗ�����Ƃ��A���̃s�A�m���t��͂��̋Ȃƌ��߂Ă����B
�@�R���̉��t����A�v���O�����P�O�ԖڂɃs�A�m�̑O�ɍ������B���̋Ȃ͔����ɍ��肪�ς��Õ����ɂ��������B�������A�P�J�����O����A�܂�ɂӂ�e�����ȁA���M�������ăs�A�m�Ɍ��������B
�@���t�͂܂��܂��������B
�@�Ȃ���(�t�H���e)�Ɉڂ�Ƃ���ŁA�������ꂽ�B���Ă��Ƃ��B
�@�����܂�������݂܂���A��蒼���܂���ƌ����āA�����ʂ�ł���Ǝv�������A�܂�ł��߁A�Ȃ̉��t���N���b�V�����Ă��܂����B
�@�������ɐ�y��u�t���������ԁB���ʂ́A�S�������Ԃ�Ǝw���d���Ȃ�B�]�Ǝw��̔����ȊW�́A�ْ�������ʂōۗ����A�����͂���Ƃ͏����Ⴄ�B�N���b�V���Ȃ̂��B
�@���t��O�Ƀp���ƃR�[�q�[�Ōy���ЂƂ������ꂽ�Ƃ��A����\��O�ْ̋����ăC���ˣ�Ƃ����F�l��l�ɁA������ˁA�ł��������Ɠ����Ă����ł���B���d�Ԃ̒��ŁA�݂�ȃX�[�c�p�Ŏd���ɏo������̂ɁA���͏��������I�V�������ăs�A�m���t�ɏo������Ȃ�āA����ȍK�����v���Ƃ��肪�������ģ����s�����炻��͎��́A�債�����ƂȂ���B�傫�Ȃ��ƌ������̂͒N�Ȃ̂��B
�@�\�����t�ɑ����ĘA�e�Łw���L�̃^���S�x��e�����B����ƃ��Y��������Ȃ��āA��h���꣎��ɁA���P�O��������Q�l�ŕK���ɒe�������A�A�e�͉��Ƃ��T�}�ɂȂ��������m��Ȃ��B�����ŁA�]�̒��̓^���S�ł����ς����������ƂɋC�t�����B
�@���M���X�ŗD��ɗ��S��e���\�肾�������A�G�[�f�����C�X�͂������ǂ��납�A���������c�ɎU��ʂĂ��B�l���͂��A�����N���邩�킩��Ȃ��B
�@������t��ł́A�Ⴂ�u�t���e���x�[�g�[���F���́w�����x�̔��́A���k���t�ŏ^���ꂽ�w���ϗ��s�A�m�ȏW�x�A�w��̐瑐�x�A�w�Ȃ��������̉́x�A���邢�͂����g���Ŋ���l�́w���̉́x�ȂǁA�T�N���V�N���������㋉�N���X�̐l�̉��t�́A�ƂĂ��T�O��U�O��̎w�����Ƃ͎v���Ȃ������Ȃ��̂������B
�@�����Ђ�����A���t��I����҂݂̂̂����Ȏ����������ɂ����̂ł���B
�@���������Ȃ��J��Ԃ��������ꑱ�����v���A����U�N�Ԏg�����p�\�R�����ˑR�N���b�V�����đ呛�������B����t�ǂ��������H�����S�ɃN���b�V�����������H�
�@�ސE��́A���j������茤���̃z�[���y�[�W�������b��̕v�͢�{�ǂݏo������ǂ�ȉ��y���a�f�l����ƁA�����\���ȃ_���i�l�ł��邪�A�N���b�V�����M�����Ȃ��l�q�������B
�@���̖�͔��ʂāA���������s�A�m���b�X���̋C�͂Ȃ��A�e���r�̉f��w�j�͂炢��@�Ђ���q���S�x�ŁA�R�O�N�߂����O�̎�X�����Ђ���Ɣ�������������ɍĉ�A����ƕ���S���߂����悤�ȋC�������B
�@�@�@�@�@�@�@�s�A�m�͉̂�
�@�L������ْ͋���������߂Ă���B��₱������w���A�s�A�m�̌��Ղ��������B�u�T�O����̃s�A�m�v���t��ł́A�킪�U�R�̒x���f�r���[�́A���ȁw���X�N�̗[���x�������B
�@�v���O���������ċ������B�o���҂͖�T�O�l�A����Ȃɂ����y���D���ŁA���������łȂ��������e���Ă݂��������N���������ƂɁB
�@�ō���͂W�Q�̒j���ŁA���|�c�@���g�́w�g���R�E�}�|�`�x��e���A�Ƃ�͂V�O�Α�̏����Łw���V�A��舤�����߂āx�������ɉ��t�����B�[�����K�����͂��Ȃ̂ɁA�|�����ƃ~�X������l�������A���ꂪ�ƂĂ������������ƁA�u���O�v�������Ă����B
�@���ܓ��{�ɂ͂U�W�V�����тɃs�A�m������A���̂����S�T�O���䂪�����Ă���ƌo�钡�̒��ׂɂ���B
�@�킪�Ƃ̃s�A�m���~���P�O�N�A�����S�̕n�R����ɋ`�ꂪ�������o���Ă���A���[���Ŕ��������̂��B�܂��Ɂu�~���s�A�m�A���ڊo�߃R���T�[�g�v�ł���B
�@�����̃����o�|�͑S���Ȃ肽�Ă̂T�O��ŁA�u����̓t�@�̉��ƒ��ӂ����ƃp�j�b�N�ɂȂ�v�Ƃ��u���ł킩���Ă��A�w�������ɂ����Ȃ��v�u�e�������i������̂��y�����v�ȂǂƁA���X�����𗬂���B�u�Ƃ̌��́A�����w���ȁx���Ă����Ƃ肵�Ă���v�ƌ����A�u�����Ȃs�A�m���n�܂�ƁA���������Ɖāw�E�E�H�[�x�Ƃ����o���Ċ��ł���v�ƌ��t�����˕Ԃ�B�u�d�������̐l�����A�������Ō��������������v�Ƃ�������j��������B
�@�ǂ�Ȉ̂��l�ł���b�́w���傤����x����e�������B�݂�ȃv���C�h�Ȃǐ�������āA�K���̒���ɂȂ�B�u����Ȃ��������ȁw���傤����x���߂Ē������v�B�����A�����Ɍ��Ă�������Ƃ��̍��]�ł���B���̐搶�ɂ����Ȃ�������������ꂽ�B
�@���N�̋������ŁA�����A����������玟�̓R���ƁA���������Ɏ��ɓ������Ă����B���ꂪ�̂ɐ��݂��Ă��܂����̂��낤�B�����āA���܂܂ʼn䗬�Œe���āA�����C���ɂȂ��Ă��������ƊϔO�����B�Ȃ̃R�����g�Ɂu�̂��܂��傤�v�Ƃ������̂��A�u���̋��ނ͐��y�ƌ��p���ȁv�Ƌ����Ȋ��Ⴂ�������B
�@�l���̔ӏH�ɁA����Ɨ^����ꂽ��Ƃ�̂ЂƂƂ��A���������Ȃ̂悤�ɂ����u���y���y���܂Ȃ�������v�B�������\���Ȃ����āA�u���������v�s�A�m�̍����ɗ������������B
�@�u�s�A�m�͉̂��v�̂��B�Ȃ̂����낪�e����悤���i���悤�B
�@�]�ɒ��������w���g�����߂��A�ߍ��A�����̓{�P�i�s���~�܂����C�z������B
�@���ߏ�����A���y���t�́w�M��x���������Ă���B�ߕӑ����h�~�̂��߁A�T�b�V�͂�����ƕ߂āA�����A���b�X���J�n���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�d�w�s
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����G�b�Z�C���Ԃ����֍s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�q�̃z�[���y�[�W�ɖ߂�
