�w���v���_���j�x�Ɋւ����c�k��Y�u���Ȕᔻ���v
��c�E�s�j����Ɓu���Ȕᔻ���v���\�����̈ꎟ�����W(�Q)
(�{�n�쐬�E�ҏW)
�@�k�ڎ��l
�@�@�@�P�A�{�n�R�����g
�@�@�@�Q�A��c�k��Y�u���Ȕᔻ���v(�S��)
�@�@�@�R�A�w���v���_���j�x(����)
�@�@�@�@�@�@��O�ё�́A���Z�����̗��_���(�S��)
�@�@�@�S�A�w���{���Y�}�̘Z�\�N�x(����)
�@�@�@�@�@�@��c�E�s�j����Ɓu���Ȕᔻ���v���\�����Ƃ̊֘A��(����)
�@�@�@�T�A�w���{���Y�}�̎��\�N�E�N�\�x�i�����j
�@�@�@�@�@�@���[���R�~���j�Y���ւ̋}�ڋ߂Ƌt����f�[�^��P�X�V�T�N�`�W�T�N
�@�@�@�U�A�R�̋��Y�}�ɂ��Democratic
Centralism�����o��
�@(�֘A�t�@�C��)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����MENU�ɖ߂�
�@�@�@�@�w�Ǔ��E��c�k��Y�@���̗��j�I���߁x�}������]�o���Ɍ����鑽�d�l�i��
�@�@�@�@�w�u���v���_���j�v�Ɋւ���s�j�N�O�u���Ȕᔻ���v�x�ꎟ�����W�i�P�j
�@�@�@�@�Γ������w��c�s�j�u���v���_���j�v�o�Ōo�܁x�莆�R�ʂƏ��]
�@�@�@�@�w��c�k��Y���ψ����̑��d�l�i���x��c�E�s�j���⎖���̐^��
�@�@�@�@�w�s�j�N�O�̋{�{�����ᔻ�x�k�閧�l��c�E�s�j���⎖���̐^��
�@�@�@�@�w�j�̑S�ʉ���ɂ�����s�j�N�O�̎l�ʑ��x�\�����v�_�҂Ƃ����v�z�E���_�I�o��
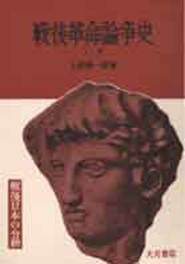
���ҏ�c�k��Y�̂݁A�㉺���E�e�R�T�O�~
�@�P�A�{�n�R�����g
�@���P�{�{�����́A���̇��Q�E�R����Ɓu���Ȕᔻ���v���\�����ɂ���āA�}�������������������Ɯ����̍ő�����������悤�Ƃ����B�����āA��C��������E��������E�����ψ��S���Ƃ����g�b�v���x������ꋓ�ɋt������������ł����C���E�^�[�Q�b�g(��v�W�I)�ɂ����̂́A�Z�퓯��ł͂Ȃ��ANo.�R�̏�c�k��Y�̕��������ƍl������B�u���Ȕᔻ���v�́w�O�q�x�f�ڏ������A�s�j�E��c�Ƃ������ɂ����̂́A��̓}���n�ʂ̕���������ψ����ŏゾ��������ɂ����Ȃ��B
�@���{���Y�}�����[���E�W���|�l�R�~���j�Y���ւ̋}�ڋ������t�����������ŁA�{�{�������ŏ�����_�����̂́A�u���Ȕᔻ���v�̌��J�������B�Ȃ��Ȃ�A�Q�l�̍��₾���ł́A������ɂ����̂����A��C��������ō\���������Q�E�R����ψ���ȊO�ɕ�����Ȃ�����ł���B�Q�l�́u���Ȕᔻ���v���A���_���w�O�q�x���S�����\���邱�Ƃ����A���́w�O�q�x��K���ǂޒ��������S���\�l�E�}�{���Ζ����W�O�O�l�ɂ������������������ő��ɂȂ�d�g�݂������B
�@�������A���������̓�������邽�߂ɂ́A�Q�l�̢���Ȕᔻ������e�͂���ȊO�ɁA���N���s�́w���{���Y�}�̘Z�\�N�x(�P�X�W�Q�N)�̊֘A���A���{���Y�}�̃��[���R�~���j�Y���ւ̋}�ڋ߂Ƃ�������̗��E�E�t����̌o�߃f�[�^�A�C�^���A�E�t�����X�E�X�y�C�����Y�}��Democratic Centralism�����̌o�߃f�[�^�A�c���x�v��������w�ғ}���ɂ�閯��W�����ᔻ�̓����𑍍��I�ɂƂ炦�A���̒��ŁA���̓���ʒu�Â��邱�Ƃ��K�v�ł��낤�B
�@���̎�������������A�Ȃ��d�v�Ȃ̂��B����́A�����A�{�{�����ɂ���t����N�[�f�^�[���������Ă��Ȃ���A���{���Y�}�́A���[���R�~���j�Y���̓����A�����E�}�������ɂ���āA�������`�I��Democratic
Centralism�Ƃ����ƍߓI�g�D���������S�ɕ������A�����`���}�ɓ]�����Ă����ɂ������Ȃ�����ł���B���{��`���ɂ����āA�B�ꐶ���c���Ă��郌�[�j���^���Y�}�Ƃ����������I�ȑ����͂Ȃ��Ȃ��Ă�������ł���B����ɁA�����z�I�Љ��`�̐��������v���j�̂�p�����邱�Ƃɂ���āA���}�h�̋��Y�}�ɂ�������x���S�������A���}�h�Ƃ̑I�����͋�������сA����I�Ȑ��������������̓I�ȓW�]���J���Ă����Ɗm�M���邩��ł���B
�@�t���s�̂��߂��S�A���l�������ɂ����āA���̏�c�E�s�j����Ɓu���Ȕᔻ���v���\�����́A�����L�[�|�C���g�ɂȂ�B����́A�}�����g�b�v���ɂ�����t�������ł���B����ɂ������A�i�P�j�w�ғ}���E�o�ŊW�}����ւ̃l�I�E�}���l���A�i�Q�j�����`���w�����O���[�v�A���a�ψ���O���[�v�E�������O���[�v�Ƃ������Y�}�n��O�c�̃O���[�v�}����ւ̏l���A�i�R�j����@���x���}����ւ̏l���Ȃǂ́A���ԋ@�փ��x���ł��Ȃ��A���ׂ���b�g�D���x���̓}���ɂ�������l���������BDemocratic Centralism�́A���S�ȏ�Ӊ��B�̑g�D�����ɕώ����Ă���B�t����̎��_�ł́A���łɁA�{�{���I���h�E���߃O���[�v�̐��ɂȂ��Ă����B����āA���̂悤�ȑ̎��̑g�D�ɂ����ẮA�܂��A�g�b�v�𐧈����A�ォ��t������Ƃ����N�[�f�^�[����������A�{�{�����ɂƂ��āA�L�[�|�C���g�ɂȂ����B
�@��c�E�s�j�Z��̢���Ȕᔻ������e�ɋ��ʂ���̂́A����W�����̋K������ł���B���R��`�A���U��`�A���h��`�Ƃ́A����W�����������E�E�K���ᔽ�����ł���B�{�{�����́A�Q�l�̎��Ȕᔻ�_����ʂ��A�}���������S���\�l�Ɠ}�{���Ζ����W�O�O�l�ɂ������āA����W�����̋K�������炷��悤�A��E����҂͍��₾�Ƃ��鋺���Ɯ������������B
�@�����^�C�~���O�́A���[���R�~���j�Y���R�}��Democratic Centralism�������w�����A�ᔻ�I�Ȍ��������J�n���Ă��鎞���A�����āA���{���Y�}���̊w�ғ}����o�ŘJ�A�W�}�������ɑ����̃��[���R�~���j�Y���^���ҁ�����W�����ᔻ�҂��o�����Ă��������ƈ�v���Ă���B�P�X�V�W�N�����̓c���x�v���w��i���v���Ƒ����I�Љ��`�x(�匎���X)�́A���̃W�������̒����Ƃ��āA���ٓI�ȏd�ł��d�˂Ă����B�}�������s�̎G���w���E���������x�́A�����̂悤�ɁA���{���̃��[���R�~���j�Y�����}�̘_����|��E�f�ڂ��Ă����B����́A�}�{�����ɂ��A���[���R�~���j�Y���̓����x���E�Љ�҂��A��c�k��Y�����łȂ��A�����h�Ƃ��đ䓪���A�ꈬ��́u���܂���v�u���V��v����Ȃ�ō����͎Ҏ��I���h���͂��A���q�̌Ղɂ��鐨�����������B�}���������A�����̕����E�L���������ēǂނ悤�ɂȂ����B
�@�������u���A�X�^�[������`�ҁE�{�{�����Ǝ��I���h�E���߃O���[�v��́A�}�{�����ŁA�����オ�����B�ނ̍d����������W�����̋K�������H���́A�u���܂���v�u���V��v�����̉����ȑԓx�ɂ���ďے������悤�ɁA�ÏL���}�̎����y�������悤�ɂȂ��Ă����B�{�{�����Ɣނւ̖ӏ]�I�����h�́A�}�{�����ɂ����āA���|�������̍ō����͕ێ��O���[�v�ɂȂ�A���Ԃ͏����h�ɓ]�����������B
�@�܂��A���Y�}�n��O�c�̃O���[�v���ł��A�}�S�̂̃��[���R�~���j�Y���x���Ƃ������͋C�̒��ŁA�{�{���I���h�́A�����h�ɂȂ��Ă����B���[���R�~���j�Y���̂��܈�̎w���́A�X�^�[�����̃x���g���_��S�ʋ��₷�邾���łȂ��A���̌��̗��_�I�����ł������[�j���̐����̗D�ʐ����_�����ے肷�邱�Ƃ������B���[�j���́A�v���^���ɂ����鐭���E���}�����̗D�ʐ�����ʓI�E�ߓx�ɋ����������Ƃ����B�ނ́A���̓����Ƃ��āA�i�P�j������v���^������ɂ�����{���V�F���B�L�A���Y�}�̗D�ʐ��A�i�Q�j�����ƕ��w�Ƃ̊W�ɂ����鋤�Y�}�̎w�����m���A�i�R�j���Y�}�n��O�c�̂ɂ������鋤�Y�}�̐�ΓI�w�����l�����咣�����B
�@���[���R�~���j�Y���́A�}���N�X�E���[�j���̃v�����^���A�ƍٗ��_�̕����ADemocratic Centralism�̑g�D�����̕��������łȂ��A���[�j���̂��̗��_������ʓI�Ȍ���Ƃ��Ĕᔻ���n�߂��B�����āA���Y�}�Ƒ�O�c�̂Ƃ̊W�́A���[�j���^����E�炵�āA�Γ������̊W�ɓ]�����ׂ��Ǝ咣�����B���{�ɂ����閯���`���w�����O���[�v�A���a�ψ���O���[�v�A�������O���[�v�A���̑��O���[�v�́A���ꂼ��̕���ɂ��������̌�����A�{�{�����̃X�^�[������`�I�x���g���_�̉����t���ɂ������āA���������Ɣᔻ�����߁A�ނ̑�O�c�̂ɂ������銱�E�l������w�߂��痣�E���A�}��������̎���E�����w����ڎw���悤�ɂȂ��Ă����B
�@�ނ́A�X�^�[������`�I�l�����Ƃ��āA�Z�S���ȍ~�A�ނ�ᔻ�����ʂ̓}�����}���O�r������}���ƍ��𐋍s���Ă����B���{���Y�}���A���[���R�~���j�Y���̎w���Ɠ������ADemocratic Centralism���������悤�ɂȂ�����A�ނ̔ƍ߂ɂ�������ᔻ�����o���邾���łȂ��A�t���V�`���t�ɂ��X�^�[�����ᔻ�Ɠ������Ԃ���������댯���������B���ƌ��͂��������}���N�X��`�O�q�}�ɂ�����ō����͎҂́A�����ȂׂāA�\�����̌������֎�����p���ɂ������A���̓��ʂł͎��Ȃ̒n�ʕۑS�ɋ��X�Ƃ���A���S�ȉ��a�҂ł���B�}�����h�����̌o�����L�x�ł���A���̒��ŁA�����h�]���̔߈���������Ă����{�{�����́A���[���R�~���j�Y���Ƃ̊W�A������x������}����������A�����������I���h���A�����h�ɓ]�����A���x�͔ނ炪�r�˂����댯���@�m�����B
�@�����ŁA�ނ́A���{���Y�}���t����N�[�f�^�[�����f�����B����́A�����h�E�ё�̒D�������̐������������B�����A���[���E�W���|�l�R�~���j�Y��������t����̎�����A�N�[�f�^�[�Ɩ��t���鍪���́A�R����B
�@�k�����P�l�A�{�{�����́A����W�����̌������E�����w������̋t����������@�Ƃ��āA�ʏ�̓}�����_�ɂ���đ����h�̐����������i���Ӑ}�I�ɔr�������B�ނ疯��W���������E��Ηi��̏����h�́A�S�A���l�������ŁA�u����W�����ᔻ�ҁv�u��O�c�̎��������q�v�u���}���q�v�r�˂�����S�A���̈��L�����y�[�����A�w�Ԋ��x�w�O�q�x�w�����]�_�x�w���啶�w�x�Ƃ����}����`������t�����p���A�\�͓I�ɔᔻ�E�٘_�҂��l�����������g�����B�������A�P�X�V�W�N����W�T�N�܂ŁA�W�N�Ԃ��̃L�����y�[�����Ԓ��A�ނ�́A���b�e����t�����}�������⓯���҂ɂ������āA�@�֏e�̏e�e�̂悤�ɁA�����܂Ȃ��A���Z�̘_���E�L���˂��������B
�@���̔ᔻ�_���E�L���̓��e�́A���������b�e���\���Ɏ~�܂炸�A����Ƃ������k�ُp���g���A�E�\�A�����W�̘c��������߂����x���ɂȂ��Ă����B�ނ炪��p�����k�ُp�̈��́A����̎咣�E�_�����Ӑ}�I���P���Ȃ��Ă����āA������Ō��I�E���b�e���\��I�ᔻ���������Ƃ�������ł���B�w�Ԋ��x�����ǂ܂Ȃ��}�������́A��ʂ̈���I�����L�ۂ݂ɂ��邵���Ȃ��A���f�����ׂē}�����Ɉˑ����A����I�v�l��r�������^�C�v�ɉ�������Ă������B
�@�k�����Q�l�A�}���������S���\�l�E�}�{���Ζ����W�O�O�l���ɂ����āA�����I�ȏ����h�ɓ]�����������ō����͎Ҏ��I���h���A�����Ȏ�@�ŁA�}�������ɑ��H�����[���R�~���j�Y���h������W�����ᔻ�h��e�����A���₵�A�u���Ȕᔻ���v���������������ł���B���̍�����ANo.�Q�E�R���Q�U�N�O�̖��������������Ɏ��M�E�o�ł��A�P�W�N�O��No.�P����łɂ����������̓��e�E�o�ōs�ׂ����E�K���ᔽ�������Ƃ���A�ٗl�Ȉْ[�R��ٔ��܂����̍s�ׂ������B����ɂ́A�Ăё����h���͂�D���Ԃ����߂ɁA�����S�������\���A�������߂ɂ���Ƃ������㏈�Y�̂悤�Ȏ�����g�����B
�@�����{���Y�}�j��A�폜���Ҍl�ɂ������āA�}���������f�ߓI�����\�����P�[�X�͂�����ł�����B�������A�Q�l�̂悤�Ȍ`�ŁA�g�b�v���x���̌l�ɁA�Q�U�N�O�́g���h�Ɋւ��颎��Ȕᔻ������������A���̑S�������\������Ƃ����ٗl�Ȍ`���͈�x���Ȃ��B�}�j��A�O�㖢���̏o�����ł���B����́A�܂��ɁA�����h�ɓ]�����������t����N�[�f�^�[�h���A�ǐ����n�ɂ����œ|�Ώێ��ɂ������āA����E���J���Y�������Ƃ������鐫������@�E�ƍߍs���ł���B�����ɁA���̎����́A��������\������No.�P�̈ٗl�ȐS������h�]���̋��|�ƕ������킹�̂����܂����S�����A���Ԃ�G�̂悤�ɕ����яオ�点����̂ɂȂ��Ă���B
�@�k�����R�l�A�}�������ɂ�����D�����������łȂ��A��b�g�D�}���ɂ�������S�A���l�������ɂ���āA�w�ғ}���A�o�ŘJ�A�W�}���A�R�̑�O�c�̃O���[�v�}���A����@���x���E���E���x���}�������ɂ������������Ɯ����Ƃ����S�A���L�����y�[����ʂ��A���{���Y�}�S�}�ɂ�����{�{�����̑����h���ЂƐ�ΓI���͂��Ċm�������@���g�����B
�@�����̌o�߂́A�����I�ȏ����h�E�{�{�����ɂ��D���̓}���N�[�f�^�[�ƋK��ł���B�N�[�f�^�[��@�ɂ���āA�œ|���ׂ������h�Ƃ́A(�P)����W�����������E�����w���̓}�������A����ёS�}���̐��́A(�Q)���Y�}�n��O�c�̂ɂ����郌�[�j���̈�ʓI�Ȑ����̗D�ʐ����_�E�X�^�[�����̃x���g���_�̔ے�Ɠ}��������̎���E�������w�����鐨�͂������B�������A�����h�Ƃ����Ă��A�X���ŁA���A���͋C�I�ȃ��x���Ɏ~�܂��Ă����B����ɂ������āA�{�{�����̍ō��w���Ҏ��I���h�E���߃O���[�v�́A�Ӑ}�I�ɍ��ꂽ���łȕ��h�������B�������̂���ɂ́A�ڂɂ͖ځA���ɂ͎��A���h�ɂ͕��h�ŗ��������������Ȃ��B���͋C�I�ȑ����h���A�����h�̍ō��w���Ҏ��I���h�ɑR�����镪�h�̌����ɓ����̂ɂ��ẮADemocratic Centralism�ƕ��h�֎~�K��Ƃ��������������[�j���̎������A�����̓��{���Y�}���ł͋��������B
�@�P�X�V�O�E�W�O�N�㓖���̃��[���b�p�ɂ́A�n�����̃\�A�E�����P�O�J���̂��ׂĂ���]�I��Ɋׂ��Ă���Ƃ������ʂɗ��ꍞ�݁A�X�^�[�����̂S�O�O�O���l�l���ƍ߃f�[�^����i�ƍ����ɖ\�I������ԂɂȂ��Ă����B�����̔F���́A���[���R�~���j�Y�����}���Ɏ~�܂炸�A�����S�̂����L���郌�x���ɂȂ��Ă����B��������A���[���R�~���j�Y���ɂ����郌�[�j���̎������A�ɂ݁A�ᔻ����A�قǂ��������Ă����B����́A���{���Y�}���Ɠ��{�����̃��x���ƑΏ̓I�������B
�@�ނ̋t����N�[�f�^�[�������ɐ��������������ŁA���{���Y�}�́A�Q�P���I�ɂȂ��Ă��A���{��`���ɂ����āADemocratic Centralism�Ƃ����}�������`��}���E�j��g�D���������B��̐��}�Ƃ��āA�����c��邱�ƂɂȂ����B�������A���̔��ʁA�P�X�W�O�N���s�[�N�Ƃ��āA�}���͂o�g�m(�}��P�E�Ԋ������{��H�E���j��N)�́A����Ȍ��Q�V�N�����A���~�߂̂Ȃ������𑱂��邱�ƂɂȂ����B�W�N�Ԃɋy�ԁA�{�{�����̋t����N�[�f�^�[�ƂS�A���l�������L�����y�[���́A�}���Ő������Ă��A���{�����E�L���҂ɂ������Č�������^���A�����Ȑ��}���_�����ɂ����鐭�}���ۗ��̃g�b�v�ƂȂ��Ă���B����ɂ��A�o�g�m�̂��ׂĂ̎w�W�Ō��葱���邱�ƂɂȂ����B�ނ̋t����N�[�f�^�[�́A�}�O�ɂ������ċt���ʂݏo���Ƃ�������ȁA���邢�́A���������R�Ȍ����������炵���B
�@�@�@�@�w���{���Y�}�̓}���́A���̌����l�����x�P�X�W�O�N���s�[�N�Ƃ���Q�R�N�Ԃ̓}���͌���
�@��c�k��Y����Ȕᔻ���
�@�{�{�������A�ᔻ�E�٘_�҂�}���O�r����������́A�����Q�ł���B(�P)���f�I�����I�𗬂����ւ��Ă��閯��W�����Ɉᔽ���A�����@�ցE�זE���z���āA�}�����ᔻ�E�{�{�ᔻ�̕��h�����A�Q�l���h�E�R�l���h�����������Ƃ����˂������A�i�Q�j����Ƃ�����e�[�}��}�����̘g�ɉ������߁A���肩���āA�ނ��R�⊯�Ƃ��ē}�����ƒf�肵���e�[�}��}�O�ɂ����������Ƃł����グ�邱�Ƃł���B
�@��c�k��Y�́A�u���Ȕᔻ���v�ɂ����āA�ő�̌�肪�A�}������}�O�̏o�ŕ��ɂ����������Ƃ�������W�����ᔽ�������ƁA���ȋK�肵�Ă���B����́A�w���v���_���j�x�̓��e�E�o�łƂ�����̓I�s�ׂɂ��Č���A�{�{�����̏퓅��i�Ƃ��Ă��k�ُp�̉����t���ł���B
�@���������A�Q�̃t�@�C���ɓ]�ڂ����A��Q�O����̃X�^�[�����ᔻ�߂��鍑�ۗ��_����i�s�j���M�j�ƍ������_����̓���(��c���M)�A���̑��̊e�́E�i���j��ǂ�ł��A���{���Y�}���R�܂ނƂ��Ă��A�����S�̂́A�u�}�����v�̔��e���z���Ă���B�����́A�����̓��{�̘_�d�A�w�������_�x�w���E�Ȃǂ́x�e�G���⍶���w�c�S�̂����_�����e�[�}�������B���ꂪ�}�����łȂ������ƂȂ�A�{�{�������k�ق��A�Q�l�́u���Ȕᔻ���v�̘_�����A���ꂩ�����B
�@���̃t�@�C����(�{�n�쐬�E�ҏW)�Ƃ����Ӗ��́A�u���Ȕᔻ���v���A���������́k�ڎ��l�������̂��A���̔��f�ŁA�k���ڎ��l�Ƃ��ď����o�������A�܂��A�����̂��������������ɂ������Ƃł���B(�`���)�́A�����}�������B�������A�����ɂ��ẮA��ؒ����E���M�E�폜�Ȃǂ����Ă��Ȃ��B
�@�w���v���_���j�x��O�ё�́A���Z�����̗��_���(�S��)
�@���̖{���ƂƂ��ɁA�P�S�́i���j�����Ă��A���̃e�[�}���A�}�����ƒf�肷��̂́A���S�Ȍ��ł���A�{�{�����̂ł����グ����ł���B�s�j�E��c�炪�A��͍��ۗ��_����A�Z���������_����S���M���A���_�������V�[���́A�Q�U�ƂQ�X�ŁA�܂������������Z��̘A�g��i�Ƃ��āA�قق��܂������̂�����B�����A���̖{���E�i���j���e�́A�Γ����ς�T�l������������c��Ȏ����A���_���e�̃������Ȃ���A���̔N��ƒm���ł͓��ꏑ���Ȃ��������x���ɂ���B�����Ƃ��A�_�����e�ɂ́A�X�^�[�����ᔻ���ゾ���ɁA�]���̊Â����ʐ�������B����āA���̖ʂɊւ���u���Ȕᔻ���v���e�ɂ́A�[���ł���B
�@�w���{���Y�}�̘Z�\�N�x���A��c�E�s�j����Ɓu���Ȕᔻ���v���\�����Ƃ̊֘A��(����)
�@��c�E�s�j�u���Ȕᔻ���v�́A�}�����ٖ̕�(�u�Ԋ��咣�v)�ɂ��A�w���{���Y�}�̘Z�\�N�x�o�łɍ��킹�āA�Z�킪�A����I�ɔ��Ȃ��A���\�������ƂɂȂ��Ă���B�������A����́A�c���x�v���ᔻ�L�����y�[���ƘA����������W�����̈������߁E�K���������j�̈�A����сA���[���R�~���j�Y����Democratic Centralism�����X���Ƃ̐≏�Ƃ����t����H���̈�ł��邱�Ƃ͖����ł��낤�B
�@�w���{���Y�}�̎��\�N�E�N�\�x���A���[���R�~���j�Y���ւ̋}�ڋ߂Ƌt����f�[�^��P�X�V�T�`�W�T�N
�@�C�^���A�E�t�����X�E�X�y�C�����Y�}��Democratic Centralism�����o��
�@�����́A�N�\�I�f�[�^�ł���B�������i�{�n���j�ɏ��������A�{�{�����̉s���k�o�́A���[���R�~���j�Y���ɋ}�ڋ߂����A���̑���̉�k�E���ݖK���ʂ��āA���[���b�p�̂��ׂĂ̋��Y�}���ADemocratic Centralism��������A�}���N�X�E���[�j����`�Ƃ��f�₵�A�Љ���`���}�ɓ]�����Ă���������k�������B�ނ́A�X�^�[������`�҂Ƃ��āA���{���Y�}�̍ō����͎҂Ƃ��āA���{���Y�}�����邩�A����Ƃ��A�X�^�[�����ᔻ�̂悤�ɁA�������}�S�̂���ᔻ�E�ӔC�Nj������̂ł͂Ȃ����Ƃ������|�ɑł��k�����B
�@�t����̌��f�́A���X�Ɍ`������Ă������B���̌��ӂ́A���{�ɂ�����ŏ��̌��ꂪ�A�i�{�n���j�ɂ��钆��O�O�����̍���E�����Ɠc���x�v�������ᔻ�̑�L�����y�[���ł���B���ۊW�ɂ����郈�[���b�p�R�}�Ƃ̐≏�̌���́A�P�X�V�W�N�ȍ~�A�����R�~���j�P�E���������Ƃ�����k���ʂ̔��\�`�������Ȃ��Ȃ������Ƃł���B
�@�Q�A��c�k��Y�u���Ȕᔻ���v(�S��)�@�w�O�q�P�X�W�R�N�W�����x�f��
�@�w���v���_���j�x�ɂ��Ă̔��ȁ\�u�Z�\�N�j�v�ɏƂ炵�ā\
�@�k���ڎ��l
�@�@�@��A���_�I���e�A�Ƃ��ɐ��Z��`�I�]��
�@�@�@��A�o�ł��ꎩ�̂����ŁA���h��`�I����
�@�@�@�O�A���U��`�A���h��`�A���R��`�̌��
�@�}�n���Z�\���N���L�O���č�N�����s���ꂽ�w���{���Y�}�̘Z�\�N�x�́A�}���O�ɑ傫�Ȕ�������тÂ��Ă���B
�@�Ƃ��ɐ��̓}�j�ɂ��ẮA�V�����ڍׂȑ����I���q�������Ȃ�ꂽ���́w�Z�\�N�j�x�̔��\���@��ɁA���́A�͂��߂ē}�̒��������ɑI�o���ꂽ������(���Z�l�N�\�ꌎ)�̂�����ő[�u���Ƃ������̒����w���v���_���j�x�i�匎���X�A�㊪�͈��ܘZ�N�\���A�����͌��N�ꌎ���j�ɂ��āA���̖��_�ƌ��Ƃ��A���߂Ă����炩�ɂ��Ă��������B
�@�Ƃ����̂́A���̒��삪�A���̐�Ō���A���̓}�j��v���^���̗��_�j���Ƃ�グ���_�]�ȂǂɎ��Ɉ��p����邱�Ƃ����������A��������肤�邩��ł���B�܂��ŋ߁A���̒���̂Ȃ��̏��q���A������咣�̍������Ɏ����o���ꂽ������܂�Ă���B��Z�N�O�̒����ł͂��������A��ő[�u���K�v���������̏��̂����������炩�ɂ��Ă������Ƃ́A���݊�����ψ����Ƃ����E�ӂɂ��鎄�̉ʂ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ӔC�A�{���͂����Ƒ����ʂ����Ă����ׂ��ł������ӔC�ł���Ǝv���B
�@�@�@��A���_�I���e�A�Ƃ��ɐ��Z��`�I�]��
�@�������́A�����̒����̓}�g�D�ɑ����Ċ������Ă������A�O��ڂ̌��j�̗×{���𗘗p���āA�匎���X�́w�o�������{�̕��́x�̂Ȃ��̈���Ƃ��Ă��̖{���������B�S�|�J�A�̏��L�����Ă�����̏�c����Y(�s�j�N�O)�Ƃ����_���A�ނ��S��\��͂̂����l�͂S���M���������́A�u�͂������v�łӂ�Ă��邪�A�����܂ł��Ȃ��ŏI�ӔC�͎��ɂ���B
�@�u�푈���ォ����ܘZ�N���ɂ�����܂ł̓��{�}���N�X��`�̗��_�j���A���炽�߂čĐ����������v�i�͂������j�Ƃ��Ă̂��̗��_�I���e�ɂ��ẮA�攪��}���i���Z��N�����j�̍j�̍̑��̂̂��A��c�A�s�j�������w�}���N�X��`�ƌ���C�f�I���M�[�x(�匎���X�A�Z�O�N�\����)�̏�E�������ꂼ��̏��_�ŁA���ȓ_�������炩�ɂ������Ƃ�����B��c�́A�����Ƃ̕Ό��Ƃ̓����ɂ����邠���܂����A���_�����ɂ����邫�т����}�h���̎コ�Ƃ�����̎v�z�I��_�ɂ��āA�s�j�́A�Љ��`�v���Ƃ����헪��̌�������n�A����I���v�̗��_�Ɛ�p�ɂ��Ă̈�ʐ��A��̐���ł̓����̔c���Ƃ����O�̗��_�I��_�ɂ��Ăׂ̂��B
�@�������w���{���Y�}�̘Z�\�N�x���\���@�ɁA����A���߂ēǂ݂Ȃ����Ă݂�ƁA�w���v���_���j�x�Ŏ����W�J�������O��̕��͂�W�]�ɂ��Ă��A���̌�̎l���̈ꐢ�I�ɂ킽�錻���̗��j�̔��W�A���{���Y�}��擪�Ƃ������{�̊v�V���͂̓����̑O�i���̂��̂ɂ���āA���т����ᔻ�ƌ���������ꂽ�����̖����ӂ���ł������Ƃ��A���R�̂��Ƃł͂��邪�A�ɂ��܂łɂ悭�킩�����B
�@��A�O�������Ă����A���{���Y�}�́u�Z�S���v�i���܌ܔN�����j�A�\�A���Y�}���\����(�ܘZ�N��)�̒���ȂǂƂ����S���������Ȃ��悤�ȁA���a�����ւ̊y�ϓI�W�]�A�\�A�A�����Ƃ��̓}�ɂ�������ߑ�]���Ɗ��҂�����A���{�Љ�}�̔��������`�ⓝ�����̓W�]�ɂ��Ă̊Â��]���ȂǂȂǂ�����B
�@�Ȃɂ����傫�Ȗ��́A��O�A���̓��{���Y�}�̓}�����̗��j�I�Ӌ`�A���_�������ӂ��߂����̐ϋɓI�����ɂ������鐸�Z��`�I�]����������(��P���)�Ƃ������ł���B
�@�w���{���Y�}�̘Z�\�N�x�́A���Ƃ��ΓN�e�[�[�ⓖ���̓��������ɂ���]���A���邢�͐��̑�l��A��܉�A��Z��}���̕]���ɂ݂���悤�ɁA�����ɂӂ��܂�Ă�����_����ɂ��Ă͑�_�Ȏ��ȕ��͓I�w�E�������Ȃ��Ȃ�����A����炪�ʂ������ϋɓI�����Ɨ��j�I�Ӌ`�Ƃ��A�����ɂ��ƂÂ��Ė��m�ɕ]������ԓx����ʂ��Ă���B
�@�Ƃ��낪���́w���v���_���j�x�́A���_�I��_����j��̌��Ǝ����l�������̂��w�E����̂ɋ}�ŁA���̌��ʁA�S�̂Ƃ��ē}�����Ɠ}�j�Z��`�I�ɂ݂���(��Q���)�����������Ă���B���Ƃ��ΐ�O�̓}�ɂ��Ă��A�ێR���j�̐푈�ӔC�_�Ɋ֘A���āu���퓬����g�D�����Ȃ��������Y�}�̐����w���̐ӔC�v��₤�i�㊪�A����y�[�W�j���͂�����A���ČR��̉��Ɂu�����̊��S�ȓƗ��v������������Z��}���ɂ��Ă��A���̈Ӌ`��]�����A���铬����g�D���錈�ӂ��������w�����́u�コ�Ɖ��a�v���w�E�������́i�㊪�A�l�܃y�[�W�j������B���������ł��A���̎��s�̎�ȐӔC����{���Y�}�̑��̃Z�N�g��`�ɋ��߂ĎЉ�}�̔��������`�ɂ݂Ȃ��Ƃ����X���̕��͂������ɂ���̂��A�������Z��`�I���z�̂�����(��R���)�ł���B
�@�w�_���j�x�̏��u�����{�v���_���̍Č����v�̂Ȃ��́u���ۓI�Ȑ����ɂ������āA�Ƃ��������{�̌����ɂ���������{�}���N�X��`�̑傫�ȗ���������͑����]�n�̂Ȃ������ł��낤�v�Ƃ��A�u�^���̑O�i�ɔ�r���āA����Ɨ��_�̗���������͂��킾���Ă���Ƃ��킴������Ȃ��v�Ƃ������͂ɑN���ɂ��߂���Ă���悤�ɁA�����̎��́A���_�̕������j��ɂ����ꂽ��_����Ǝ����l�������̂��w�E���邱�Ƃɂ���āA���̓}�j���A�S�̂Ƃ��Ă͎��s�ƌ�T�̘A���Ƃ݂Ȃ��A���{�̋��Y��`�^���𗧂�������̓T�^�Ƃ��Ă������������Ƃ���j�ςɗ����Ă����B
�@�����ɂ́A�Ⴉ�������̖��n���Ɨ��_�I�����������������Ƃ�F�߂�������Ȃ��B�������A���d�v�Ȃ��Ƃ́A���������j�ς́A��O�A���̓}�j�̕]���Ƃ��Č���Ă��������łȂ��A�}�j�̍̑��Ƃ��̌�̓��{���Y�}�́A���_�I�A���H�I�O�i���A�܂����������ł��Ȃ����̂ł��������Ƃł���B
�@�@�@��A�o�ł��ꎩ�̂����ŁA���h��`�I����
�@���������j�ςɂ��������������́A�����̎����A�}�I���n�ɗ��Ă��A���h�I���n�ɗ����Ă���(��S���)�Ƃ����A���[�����ƌ��т��Ă����Ǝv���B
�@���̈Ӗ��ł́A�w�}���N�X��`�ƌ���C�f�I���M�[�x�㊪�́u���_�@�Z�S����̎v�z�����̋��P�v�łׂ̂����̔��Ȃ́A����߂ĕs�\���Ȃ��̂ł������B����͂����ς�u�������̎v�z�����ɂ͒��Ԕh�I��_������v��Ă����i�㊪�A��y�[�W�j�_�ɂނ����Ă������A���̔��Ȃ����Ȃ��u���Ԕh�I�v�A���ȕٌ�I�Ȃ��̂ɂƂǂ܂��Ă����B�w���v���_���j�x�Ƃ�������̂����Ƃ��{���I�Ȗ��_�́A���̎��M���̂��A��������h��`�I����̎Y���ł�����(��T���)�Ƃ����_�ɂ���B
�@���Ȃ킿�A�w���v���_���j�x���M�̂����Ƃ��傫�Ȍ��́A��\�N�O�̎��̔��Ȃ��܂��ӂ��Ɏ���Ȃ������_�A�}�O�̏o�ŕ��ŁA�}�j��_�]���A�܁Z�N���̑�����j�̖��̓��c�ɎQ�����A�e�����������悤�Ƃ����A���̌�����ԓx(��U���)�ɂ������B
�@���̖{�������ꂽ�����́A�u�Z�S���v�̗��N�̈��ܘZ�N�̌㔼�ŁA�}���Ō܁Z�N���̑����A�j�̖��̓��c���i�s���͂��߂Ă��������ł������B�w�Z�\�N�j�x���Ђ��Ƃ��ƁA�ܘZ�N�l���̘Z�����Łu�܁Z�N���̑S�ʓI�ȉ𖾂̓w�͂̕K�v�v���w�E����A�㌎�̔������Łu�掵��}���̊J�Â����肵�v�A�\�ꌎ�̋㒆���ŁA�u�}�����̂��߁A�w�j�́x�w�K��x�̊e�ψ���ƂƂ��Ɂw�܁Z�N�Ȍ�̓}�����̒����x�̈ψ����ݗ����邱�Ƃ�����v���Ă���(��l���y�[�W)�B
�@�u�}�͑��āv���̑����ꂽ�̂͗����N�㌎�̑�\�l��g�咆���ψ����ł���A�u�܁Z�N���ɂ��āv�Ƃ��������������̑����ꂽ�̂͌��N�\���̑�\�܉�g�咆���ψ�������(��܈�y�[�W�A��l��y�[�W)����A����ȑO�ɏ����ꂽ���̒����̂Ȃ��̍j�̖��A�܁Z�N���ɂ��Ă̕��́A���q�A�咣�ɁA���̌�̑S�}�I���B�_����݂āA���Ȃ��Ȃ���E������ӂ���ł��邱�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B
�@���Ƃ��w�_���j�x�́A�w�Z�\�N�j�x���u���}�j��̍ő�̌��v�Ƃ������c�h�ɂ��}�����ψ���̉�̂Ƃ������ɂ��Ă��A�����ᔻ�����A�u��}��`�v�Ƃ������m�Ȍ������Ƃ邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��B�t�ɓ����c�̌��������u������Œ艻���������v�i�㊪�A��Z��y�[�W�j�Ƃ��A�����I�}�������A���Ȃ킿�u�Ւ��w�����Ɍ��W���āA�������ߓx����}�������ɂ���Ē��ς̕��̑��̎w�����̌��𐳂��ׂ��ł������v�i���A��Z�O�y�[�W�j�Ə����Ă���B
�@�������A���������s���m�ȏ��q�A������咣�̈�ЂƂ��A�����w�E���邱�Ƃ��A���̉ʂ����ׂ��ӔC�ł͂Ȃ��B�������ӂ��ގ��Ȃ̎咣���A�}�̖���W�����ɂ��ƂÂ��A���o�I�K���ɂ��������āA�����ׂ̂����ǂ����Ƃ����A���{���Y�}���̊�{�ɂ�����邱�Ƃ������A���S���ł������B
�@�����ψ���́A���ܘZ�N�Z���̎������ŁA�j�̖��̑S�}���c�̕K�v���݂Ƃ߁A�\�ꌎ�̋㒆���Łu�j�̓��c�ɂ������Ă̗��ӎ����v�Ƃ������j���̑����Ă���i�w�Z�\�N�j�x�A��܁Z�y�[�W�j�B�����Ď��������c�Ȍ�w�O�q�x�ōj�̖��ɂ���l�_�����f�ڂ��͂��߁A���N���ł͍j�̖��̓��W�������Ȃ��A���N�㌎������ʂ̓��_�b�Ƃ��Ắw�c���ƑO�i�x���W�܂Ŕ��s���āA�u����W�����ɂ��ƂÂ����o�I�K������S�}���c�v(��܈�y�[�W)���g�D����Ă������B
�@�Ƃ��낪�A���͓}���ł���Ȃ���A�w�c���x��w�O�i�x�ɂ́A�P�т��_�����o���邱�ƂȂ��A�����͂₭�w���v���_���j�x�������グ�A�}�O�ŏo�ł��邱�Ƃɂ���āA�܁Z�N���̑����ƍj�̖��̓��c�ɎQ������A��萳�m�ɂ����Ήe����^���悤�Ƃ���ԓx���Ƃ����B�ܘZ�N�\�ꌎ�\�ܓ��̓��t�����u�͂������v�ɂ́A���̈Ӑ}�����R�Ƃׂ̂��Ă���B
�@�@�u�����ł����{�v���̌��Ƃ����ɂ��ẮA�����炭���͂��߂ĂƂ����Ă悢�L�͂ȓ��c�������Ȃ��悤�Ƃ��Ă��鎞�ɁA���N�Ԃ̐��_���̑������o���邱�Ƃɂ��Ă��A���낢��Ȕᔻ�����邩������Ȃ��B���������̎����A����̐i�H���߂邽�߂̍L�͂ȓ��c�ɂ������鎄�̎Q�������Ӗ����邱�ƂƂȂ�A�܂���������̌��ׂɂ�������炸���̓��c�̎Q�l�����Ƃ��ď����ł��𗧂�����Ƃ����Ȃ�A�]�O�̎��тł���v
�@�����̓}�̏�����ׂĂ݂�ƁA���̒������o�ł������Ǝ��̂����(��V���)�ł������B
�@�����A�}�����ψ���́A�W�c�w���Ɩ����`���������Ȃ�����A�}�������R��`�A���U��`�ɂ������邱�Ƃ��悭���܂��߂Ă����i�Z�������c�c���ܘZ�N�l���j�B�㒆���i�ܘZ�N�\�ꌎ�j�́u�j�̓��c�ɂ������Ă̗��ӎ����v�́A���̂悤�Ɍ��肵�Ă����B
�@�@�u�j�̂ɂ��Ă̈ӌ��́A�l�ł���Ƌ@�ւł���Ƃɂ�����炸�A�����ψ���ɏW������v
�@�@�u�j�̖��̓��c�����̂��ׂĂ̓}�����̓��c�Ƃ��Ȃ����A�K��Œ�߂��Ă���}���W��┭��c�A�}�̊��s���œ��c�����v
�@�_���u���Y��`�҂̎��R�ƋK���v�i�u�A�J�n�^�v�A�ܘZ�N�\��\�����j�́A�u���_����ѐ���̕���ŁA�}�̒c���Ɠ���ɂƂ��ėL�Q�Ș_�c���ꕔ�̓��u�ɂ���ē}�O�ւ����o����Ă��邱�Ɓv�Ȃǂ�ᔻ���A�t�����ꓝ���ψ���c���̘_���u���R��`�ɔ����������}�������W�����悤�v�i�u�A�J�n�^�v���N�l���ܓ��j�́A��̓I�Ȏ���Ƃ��āA�����}�̎w���@�ւ̍\�����������l�тƂ̖��Ƃ��āA���v�����u�ق��́w�_���^���̔��ȁx�̏o�ŁA���䏺�v�́w�������_�x���k��ł̓}�ᔻ���Ƃ肠���āA���т������̌����w�E���Ă���B
�@����ɏ�C������́u�j�̖��̓��c�ɂ��āv�i���N�Z���\�����j�́A�����s�ψ���́w���{�v���̐V�������x�ƁA�}���ɂ��w���{���Y�}�j�̖�蕶���W�x�̔��s���A�㒆������ɔ��������̂ł��邱�Ǝw�E���A�S�}�ɖ���W�����ɂ��ƂÂ��j�̓��c��i���Ă���B
�@�����̂����̕��j�A���肩��݂Ă��A�܁Z�N���ƍj�̖��ɂ��āA�l�I�ȑ����ƌl�I�����Ƃ��A�����͂₭�}�O�̏o�ŕ��Œ�o�������̒����w���v���_���j�x�́A�}�K������炸�A�}�̌���ɔ����āA���R��`�A���U��`�ɑ��������̂ł��邱�Ƃ͖����ł�����(��W���)�Ǝv���B
�@�@�@�O�A���U��`�A���h��`�A���R��`�̌��
�@���́A�}�K������o�I�Ɏ��`�����������}���Ƃ��āA�j�̖��ɂ��Ĉӌ�������A�w�O�q�x��w�c���ƑO�i�x�ɘ_�����o���ׂ��ł��������A���̌����͏\�ɕۏႳ��Ă����B�Ƃ��낪���͂��������ԓx���Ƃ炸�A�}�O�ŁA�j�̖��A�܁Z�N��������ɘ_���钘����o�ł���ԓx���Ƃ�A���������ꂪ�}�K����}����Ɉᔽ���Ă��邱�Ƃ��ӎ����Ă��Ȃ������B���������ԓx���Ƃ����̂́A�����̍������ɂ����鎄�̎v�z�I�Ɍ���������B
�@������U��`(��X���)�ł���B
�@�����Ō܁Z�N���ɂ����鎄�̊����ɂ��킵���ӂ�����͂Ȃ����A�u�Z�S���v�O�ォ�Ȃ�̊��ԁA���́A������A���̗��_�I�X��������̓}���O���[�v�̂Ȃ��ɂ����B�匎���X�́w�o���@�����{�̕��́x���A���̃O���[�v�̊��ɂ����̂ŁA�j�̓��c�����ӎ���������̗��_�I�������\�����o�Ŋ��ł��������B���̃O���[�v�̂Ȃ��ɂ́A�����炩�ɕ��U��`���������B
�@�����Ђ낭�݂�ꂽ�����������U��`�́A�e�Ղɕ��h��`�ɓ]���A���W����d��Ȋ댯�������Ă������A�����㕪�h��`�ɂ�������������B���̂��Ƃ́A�قƂ�ǂ����}�����ɑ��菜�����ꂽ�A���̃O���[�v�̂��̌�ɂ���āA�����ŏؖ�����Ă���B
�@����������R��`(��P�O���)�ł���B
�@�����̎��́A�܁Z�N��肩��u�Z�S���v�ɂ�����o���A�����ăt���V�`���t�閧�ɂ��X�^�[�����ᔻ�ɂ���āA�ˋ�������͎̂����̎v�l�����Ȃ��A�}��}�̎w���҂ւ̖��ᔻ�I�Ǐ]�͂����������܂��ƐS�ɐ����悤�ɂȂ��Ă����B���̐S�I��Ԃ͕��U��`�A���h��`�ƌ�������(��P�P���)�A�}�̌���ɂ��Ă��A������Ȃ�������ɂ��₷���X�����͂��ł����B
�@�w�_���j�x�̂Ȃ��̂��̈�߂́A���̊댯�����߂��Ă����B
�@�u������������������̌������A�}���N�X��`���_�̉ߋ��̏����ׂɂ��Ă͈٘_������Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ��ŋߐ��N�Ԃ̗��_�Ƃ̂���ɂ��ẮA�P�ӂƓ}�h���̌��ʂƂ͂����A�������������⋤�Y�}�̌�����d�A�����ɂ�������q���Ȋ��o�Ƒn���I�ȕ��͂������A�����I���ɂ��Ă͐��k�Ș_����W�J���邱�Ƃ͂ł��Ă��A�����Ƃ�����I�Ȗ��ɂ��Ă͒Njy���݂����炠����߂������������a�Ȍ�p�w�ғI�ԓx�ɂ��������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�l���q�̖��͂���ɃX�^�[�����l�������Ă̖��ł͂Ȃ��A���{�ł͂����ƈ�ʓI�ɁA���Y�}�̎w���I��������юw���I���_�ɂ������閳�ᔻ�ȒǏ]�̌X���Ƃ��ĂƂ肠���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i�㊪�A�l�y�[�W�j
�@�������}�̌���A���j�ɂ��Ă��A��������H���A���ꂪ�����ɍ��v���Ă��邩�ǂ������A�^���Ɍ��A���͂��邱�Ƃ́A���̌���������Ȃ����}�@�ւƂ��̍\�����͂������̂��ƁA�}�����_�Ƃ����łȂ��A���ׂĂ̓}���ɂƂ��āA�`���I�Ȃ��Ƃł���B�������A���̍ۂ̈ӌ��̒�o�́A�}�K��ɂ��ƂÂ��A����W�����̑g�D�����ɂ��ƂÂ��Ă����Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�}�́A����W�����̑S�I�Ȕ����ɂ���Ă̂݁A��萳�����F���ɓ��B�����邩��ł���B
�@�Ƃ��낪��Ɉ��������̏��q�́A�}�����_�ƌl���A�}�̌������j���u���v�Ɗ����A�݂Ȃ����Ƃ��A�ނ��댈�����j���d�Ȃ��ŁA�}�����}�O���Ȃǂɂ�����炸�A���R�ƗE�C�����Ď����\���ׂ��ł��邩�̂悤�Ȋ܈ӂ��ӂ���ł���B�W�c�I������d�A�}�̑g�D���������Ȃ���A�ӌ����������Ƃ̏d�v���́A���y����Ă��Ȃ��B���y����Ȃ������łȂ��A�����g�����R��`�A���U��`�̌X���A������̕��h��`�ɐ[�����������Ă�������(��P�Q���)�́A���̏��S�̂����߂��Ă���B
�@�������A���_�I�Ȍ����̎��R�́A�ő���ɕۏႳ���Ȃ�Ȃ����A�}�̔��W�̏����Ƃ��Ă̓}�������`�͏\���ɑ��d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�}�����_�Ƃ̌����̎��R�́A���Ӑ[��������K�v�Ƃ��鑽���̖�肪�悱������Ă��邪�A����ɂ�������炸�}�K��ɂ��߂��ꂽ����W���g�D�����ɂ��ƂÂ��}�����_�Ƃ̎��o�I�K���̌���́A�ǂ�ȏꍇ�ł��A�ő���Ɏ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���O�Z�N�ɂ���Ԏ��̓}�������ӂ肩�����Ă݂āA���̖{�����������̎��́A�݂����玩�o���Ă͂��Ȃ��������A���Ȃ�댯�Ȓn�_�ɗ����Ă��������ł������Ǝv���B�����A�}���Ƃ��Ă̋O�����ӂ݂͂������Ɋ������Â��낱�Ƃ��ł����̂́A���ۓ������͂��߂Ƃ���}�Ɠ��{�̋ΘJ�l���̓����̗��j�I�ȑO�i�̂Ȃ��ŁA�V���������̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��ł������炾�����B
�@���_�̖ʂł��A���{�̍��ƓI�]���̖�肻�̑��ɂ��āA�܂��܂�������ԓx���Ƃ�Ɏ��������̃O���[�v�Ƃ̑Η����Ђ낪��A�����̘_��������������Ȃ��Ȃ��Ă������o�߂��������B�������Ď��́A�攪��}���O�A�j�̑��Ă����\���ꂽ�Ƃ��A������x�����闝�_�I���n�ɗ����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă������A�܂����̃O���[�v�̏��Ȃ���ʐl�тƂ̓}����̗�������A����W�����̑g�D�����̏d�v�������������Ɋ�����悤�ɂȂ��Ă����B
�@���̈ꕶ�𑐂���̂́A�Â������ނ��������������߂ł͂Ȃ��B���O����傫�ȓ]���_�ɗ����A���̗��_�Ɛ���̎���I�A�n���I�Ȕ��W�����߂��A�}�S�̂����̕���ł��d�v�ȑO�i���Ȃ��Ƃ����鍡���A�}�����_�Ƃ̌����̎��R�Ƃ��̑O��Ƃ��Ă̖���W�����̑g�D�����Ƃ̊W���A���߂Ė��Ƃ������Ⴊ�A��A�O���܂�Ă��邩��ł�����B
�@���́A�����g�̌o������A�}�����_�Ƃ��A�g�D���������}�I�ϋɐ��������ƂƁA�}�S�̂̐����I�A�����I�O�i�ɐϋɓI�ɍv�����邱�Ƃ��A���͕s����̂̂��̂ł��邱�Ƃ�Ɋ����Ă���A���̈ꕶ�����̂��Ƃ̈�̋��P�Ƃ��Ė𗧂��Ƃ�����Ă���B
�i�������E���������낤���}������ψ����j
�@�R�A�w���v���_���j�x(����)
�@��O�ё�́A���Z�����̗��_����@(�S��)
�@�k���ڎ��l�@�����o�D�Q�P�P�`�Q�R�P
�@�@�@�P�A���Z����Ɠ��{���Y�}
�@�@�@�Q�A�J�_�h�̊���
�@�@�@�R�A�ЁE���̓���ɂ���
�@�@�@�S�A���{�鍑��`�̕���
�@�@�@�T�A���j�̖��
�@�@�@�U�A���{�}���N�X��`�̔ᔻ
�@�@�@�V�A�_�Ɩ��
�@�@�@�W�A(��)�P�S��
�@�P�A���Z����Ɠ��{���Y�}
�@�ȏ��͂ɂ킽���āA���Z����E���S���𒆐S�Ƃ��鍑�ۓI�ȃ}���N�X��`���_�̓������Љ���̂́A�{���̉ۑ�ł���킪���̊v�����_�ɂ������Ă��A���ꂪ����I�e�����y�ڂ����邩��ɂق��Ȃ�Ȃ��B���Z�����̓��{�̃}���N�X��`���_����́A���ۗ��_����̐V�������W�̏�������āA���Ȃ̗��_�̌��Ɣ��W�̐V����������ӂ݂����B����������͌܁Z�N����܌ܔN�܂ł̎����̂悤�Ȓ����I�W�J�ł͂��肦�Ȃ������B�Ƃ����͍̂���́A���Ă̍��ۓI�w���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�e���̃}���N�X��`�ɂ������鎩��I�Ȕ��W�̋����v�������̒�N���̂��̂̂Ȃ��ɂӂ��܂�Ă�������ł���B
�@���������āA���܂łƂ��ɖ��ᔻ�I�ȒǏ]�̌X���ɂ������肪�������������ɂ킪���̃}���N�X��`�̐V�i�K�͂������ĕ��R�ȓ��ł͂Ȃ������B����͎��Ȕᔻ�₽�߂炢�A�����Ⓘ�ق��Ƃ��Ȃ����A��ɂ̑����ߒ���K�v�Ƃ��A���O���̃}���N�X��`�̂悤�Ȉꋓ�ɉ����͂Ȃ��ꂽ���ς��������ɒ悷�邱�Ƃ��ł����A�܂���N���ꂽ������̐������ێ�̒i�K���ւāA�悤�₭�V�����ٓ����݂��͂��߂Ă����B�ȉ����̏͂ł́A����J���Ԃ̗��_����̓������T�ς��邱�ƂƂ������B
�@�܂����{���Y�}�����ψ���͑��Z����̈�J���̂̂��ܒ����̌��c�Ƃ��āw�\�������Y�}���Z����ɂ��āx�i�w�A�J�n�^�x�ܘZ�N�O����l�����j�Ƃ��������\�������A���e�͑��Z����̏����_�̗v��ƘZ�S���̐������̍Ċm�F�ɂƂǂ܂�A�Ƃ��ɐϋɓI�ȓ��e�������̂ł͂Ȃ������B�}�̋@�֎�����ł̓��_���܂��ӎ��I�ɂ͊J�n���ꂸ�A�O�͂ł݂��悤�ȏ��O���̋��Y�}���݂��������Ȕ����Ƃ������邵���ΏƂ��݂��Ă����B
�@�l���ɂ͘Z�������J����A�Z�S���̊�{���j�ɂ��ƂÂ��}�̔C���ɂ��Ă̕Ɗe����̊������j�Ă����\���ꂽ���A��͂�܂����Z����̐��ʂ͋�̓I�ɂ͂Ƃ肢����Ă��Ȃ������B�悤�₭���c���J�n���ꂽ�̂̓t���V�`���t�u�閧�v�����\�ɂȂ����̂��̘Z��������ŁA�������̌��c�w�Ɨ��A�����`�̂��߂̉�������r��̎�̖��ɂ��āx���Q�@�I�����[�̒��O�ɔ��\����A�V�j�̖̂��̈�߁u���{�̉���Ɩ���I�ϊv���A���a�̎�i�ɂ���ĒB��������ƍl����̂͂܂������ł���v�Ƃ��������̉����̕K�v���݂Ƃ߁A�T���t�����V�X�R�u�a��c�Ȍ�̏�̕ω��ɂ���āA�c��������āu�����`�I�������{�v����������\���Ȃ�тɎЉ��`�ւ̕��a�I�ڍs�̉\�������܂�Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���ł������i���P�j�B
�@���̌��c�͎��{��`�����̋��Y�}�̕��a�I�ڍs�̑ԓx�\���ɂȂ���āA�v���̕��a�I���W��ے肵�Ă�������܂ł̕��j��]���������̂ł��������A���P�ƍu�a�ɂ�����܂ł̎��N�Ԃɂ��āA�A�����J�鍑��`�̌R���𗝗R�Ƃ��āu����������Ă̊v���̉\���v��ے肵�Ă����_�́A�̂��ɂ�����ȓ}�����c�̑ΏۂƂȂ����B
�@���������c���A��̖����c���Ȃ�������{�v���̒��S�I�����ڕW�Ƃ��Ė���������哝��������b�Ƃ�����}�h�ɂ���č\�������u�Ɨ��E���a�E�����`�̂��߂̐��{�v�̕��a�I�Ȏ������������A���̐��{�̔C���Ƃ��āu�����̖����`�I���x�ƌ����̊m���A���������̈���v�Ȃ�тɁu�T���t�����V�X�R���E���Ĉ��S�ۏ���E���čs������̉����������͔p���v�������A���̐��{���I�ǓI�ɂ͓��{�̓Ɨ��a�I�ɂ����Ƃ肤�邵�A���ŎЉ��`�ւ̕��a�I�ڍs�̏o���_�ƂȂ邱�Ƃ��w�E�������Ƃ́A�܂��T���ɂ����Ȃ��Ƃ��Ă����{�v���̐����H���ɂ��Ă̐����������������̑O�ɖ��炩�ɂ��A����ɏ��Ȃ��Ƃ����_�I�Ȑ����H���̂����ł͎Љ�}�E�J�_�}�Ƃ̊v���ɂ����钷���I�ȋ��͊W���͂��߂ĉ\�ɂ������̂ŁA���ɏd�v�ȈӋ`�������̂ł������B
�@���{�}���N�X��`�̐V�������_�I�O�i�́A����Ȍケ�̎��������c���_�@�Ƃ��āA���ۗ��_����̐��ʂ�ێ悵�Ȃ��炵�����ɊJ�n����Ă����B
�@�Q�A�J�_�h�̊���
�@�E�̂悤�Ȏ���ɂ���āA���Z������߂��铢�_�͂܂����Y�}�̊O���ŁA��Ɂw�������_�x�w���E�x�̓�̑����G���̎���Ŋ����ɓW�J����Ă����A���������̓��_�̂Ȃ��ł́A���l���̗�O���̂����Ē��ق�����Ă������Y��`���_�Ƃ̂����ɁA�]���X�^�[������`����ѓ��{���Y�}�����т����ᔻ���Â��Ă����R��ρE�����Y���擪�Ƃ���J�_�h���_�Ƃ��ꂹ���Ɍ����Ȑi�o���݂��A������Ș_�w���͂������Ƃ��傫�ȓ����ł������B
�@�܂����Z����S�ʂ������������̂Ƃ��ẮA�����Y�̘_���w�Љ��`�̌Â����ĐV�������́x�i�w���E�x�܌����j���A���̏����_�̂����A�v���̕��a�I���W�̉\���E���a�����E���{��`�̌��͂��قڏ��F���āA�����ꂽ����������Ȃ����B���̂Ȃ��Ō��₪���{���Y�}�́u�V�j�́v�̉�����v�����A���{�Љ�}�́u�c���`�v�I�Ό������܂��߂����Ƃ͎��X�ɓK�����������咣�ł������B�������ꂪ�A���݂̎������ꎟ����̎�������ސ����āu���ΓI������v�ƋK�肵�����Ƃ́A�u���ړI�Ɋv���I�ȏ����̂��Ƃɂ���Ƃ͍l���ȂƂ��Ƃ��������Ƃ��Ă��s���m�ł���B���Ƃ��Ήp�E���̃X�G�Y�N������Ƃ��Ă݂Ă����݂��������āu���ΓI������v�ł͂Ȃ����ƂΗ�����Ă���B
�@���̂ق����̑S�ʓI�������������̂Ƃ��ẮA�w�t���V�`���t�E�~�R����������ǂ�Łx�i�w�������_�x�l�����j�A���k��w���͉����x�i�w���E�x�܌����j�A�w�X�^�[�����ᔻ�Ȍ�x(�w���E�x�Z����)�A���c����E�C�ꌒ�O�̘_�]�Ɠ��_�w�\�A�̕ϖe�x�i�w���E�x�������j�Ȃǂ����邪�A��������W���[�i���X�e�B�b�N�Ȋp�x����Ƃ肠����ꂽ����I�E�[�֓I�L���������A���̐��m�ȈӖ���T��o���A���Ƃ߂悤�Ƃ����w�͂��}���N�X��`���_�ƂƎЉ���`�I���邢�͂��̂ق��̐����w�ҁE�Љ�w�҂����Ƃɂ���ċ��ʂȍL��ł����Ȃ�ꂽ�Ƃ����ϋɓI���ۂ������ꂽ���ɂ́A�傫�Ȑ��ʂ݂͂��Ȃ������B�Ƃ͂����A�����̋L���ɂ͓��{�̘_�d�����Z������v���Ċ��}���A�V��������̒a������v���ė\�����Ă������悭�\������Ă����B
�@�R�A�ЁE���̓���ɂ���
�@�悤�₭�Z�����납��A���{�̘_�d�ɂ����Z����̏����_����b�Ƃ��āA���{�ɌŗL�̏�����Ǝ��ɒNj����Ă������Ƃ���_����������͂��߂�B�ȉ��A�e�[�}�ʂɂ��̒Nj��̂����܂��ȓW�]���܂Ƃ߂Ă��������B
�@�܂����̃e�[�}�́A���Y��`�ƎЉ��`�A���������Ă܂����Y�}�ƎЉ�}�Ƃ̐V�����W�ɂ��Ă̖��ł���B���̖����ŏ��ɐ��ʂ��炤���Ƃ߂��̂��R����ł���B
�@�R��͂܂��Z���_�]�w�\�A�͂ǂ��ς������x�i�w�������_�x�l�����j�ŁA�����u�\�A�̐��������ɐV�����n����z�����Ėc�����邱�Ƃɂɂ���ĎЉ��`�̐��E���`�������v�����͏I��������A�u�Љ��`�̐��E�́A�\�A�̐����c�����邱�Ƃɂ���Ăł͂Ȃ��A�ق����Ǝ��̓��ŎЉ��`�Ɉڍs���������A����I�ɁA�������ٖ��ɘA�g�������̍��X�̊ԂɎ��{��`�I�ȍ��ۊW�Ƃ͂��������Љ��`�I�ȐV�������ۊW��n�������W�����邱�Ƃɂ���Č`������Ă䂭���̂Ƃ݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���݂܂��\�A�̐��ɏ]�����Ă���q���������A����Ɏ��含�������A�\�A�Ƃ̊Ԃɐ���ȎЉ��`�I�ȍ��ۊW��������������ɐi�ނ��̂Ǝv����v���ƁA���̂��ƂƊ֘A���ĉI�]�Ȑ܂͂����Ă��R�~���t�H�����͉�̂���ċ��Y�}�ƎЉ�}�C���^�i�V���i���̏��}�h������V�������ۓI�@�ւ��n�݂��������߂Â����Ƃ��\�z�����Ǝw�E�����B�p��ɍ����͂��邪�A�����Ƃ��Ă͑쌩�Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̐V�����C���^�i�V���i���ւ̓W�]�̈�̗��Â��Ƃ��āA�R��ς��ҏW�l�ɖ�����˂Ă���w�Љ��`�x�l�����̓��[�S�̗��_�ƃ����z���B�`�́w�V�����C���^�i�V���i���x�̒��ڂ��Ă��邪�A���̂Ȃ��Ń����z���B�`�́A���ۑg�D�̖��́A���łɎЉ��`�����ƌQ���`������Ă��鍡���ł́A�J���^�������͊l���̏�������ɂƂǂ܂��Ă��������Ƃ͂��������ӂ��ɒ�N����˂Ȃ�ʂ��ƁA�R�~���t�H���������C���^�i�V���i�����A�V��������ɌÂ��`���������悤�Ƃ������v�Ȏ��݂ł��������ƁA���ݕK�v�ȋ��͌`�Ԃ͎Љ��`�ւ̓��̑��l������b�Ƃ��Ȃ���u�Љ��`�����̂��߂ɐ키������g�D��g�D�^����}���ӂ��ނ����Ƃ���I�ȍL�͂ȘA���v�ł��邱�Ƃ��咣���Ă����B�R��̓W�]�͎�̌�T�����ӂ��߂Ăقڂ���ƈ�v���Ă����̂ł���B
�@���̖��́A���k��w�v�V���}�x�i�R��ρE������q�E�Ώ�Ǖ��E�����O�j�i�w���E�܌����x�̂ȁ[���ł����������킵���W�J����A���Z����ł͉ߋ��̐l���������Ƃ������āA�u�Љ���`���}���ꎩ�g�̑��ݗ��R��ϋɓI�ɔF�߂āA���ꂪ�Љ��`�v�����s�̈�̎�v�Ȑ��͂ƂȂ肤��v�Ƃ��ꂽ�Ƃ݂��A���ǎ�`�E�C����`�Ƃ͂͂������ʂ���˂Ȃ�ʂ��ƁA���̎Љ���`�Ƌ��Y��`�Ƃ̓������̋C�^�͍��㐢�E�I�ɋN���Ă���Ɨ\�z����邱�Ƃ��m�F���A����ɓ��{�̊v�V���}�̍s���̓�����߂��鏔�����A�Љ�}�Ƌ��Y�}�̌��ׁA���}�̊K���I��Ղ̎コ�Ɩc��ȏ��u�����ԑw�������{�̎Љ�\���Ƃ̊֘A�A�_���w�̊l���A�����̐����S���̓����A��吭�}�ƎЋ����}�ȂǁA���܂ł��܂�Nj����ꂽ���Ƃ̂Ȃ��V������̓I�Ȗ�肪�Ђ낭�����̑ΏۂƂ��ꂽ�B�����łӂ��ꂽ�����͍����萳�m�ȉȊw�I������K�v�Ƃ�����̂ł���B
�@���̊ԃC�M���X�J���}���h�̗��_���f�E�c�E�g�E�R�[���̘_���w�ʂ��Ĉ�����悷�ׂ������Љ���`�҂Ƌ��Y��`�x�i�w���E�x�������j���Љ��āA���Ȃ�̔�������B�R�[���͎l�������Ɂu�Љ��`�Ƌ��Y��`�Ƃ̂������ɉ��狤�ʓ_���Ȃ����Ƃ�f������v�Ƃ����s������̋��ۂɂ���ă\���F�g�̐����]���ɂ��������Љ��`�C���^�[���s�ǂ̐��������A���Y��`�ƎЉ���`�͏d�v�ȓ_�ɂ����ĈقȂ��Ă͂��邪�A���Ȃ��Ƃ��l�̓_�A���Ȃ킿�A(�P)���Y��i�̎Љ�I���L�̎����A(�Q)�l���̂��߂̕������Ƃ̎����A(�R)�s�J�����̈�|�A(�S)�J���ҊK���̎w���͂̏��F�ɂ����Ă͈ӌ�����v���Ă��邱�ƁA�Љ��`�C���^�[���咣���Ă���c���`�Ɩ\�͎�`�̖������I�Η��͖��Ӗ��ł��邱�Ƃ�����A�Љ���`�̗��ꂩ����Z����̈Ӌ`��F�߂āA���Y��`�҂ƎЉ���`�҂Ƃ��u���{��`�ƒ鍑��`�Ɣ����v�ƂɑR���铝���z������������߂Â�����Ǝ咣�����̂ł���B
�@��̍��k��w�c���`�Ɗv�V���}�x�i�s���d�l�A�u��`�Y�A���ԓc����A�H�m�ܘY�j�i�w�������_�x�Z�����j�A�w���{�ɂ�����Љ���`�Ƌ��Y��`�x�i�ɓ��D���E���c�t�v�E�u��`�Y�E���ؐ����E�����T�O�j�i�w���E�������x�́A�O�҂͏��I���搧���̂Ȃ��Ŏ������ꂽ�Ћ��̓���s������b�Ƃ��������I���_�A��҂̓R�[���_�����o���_�Ƃ��ē��{�v���̐헪�_�ɂ�����_�I���_�����ł��������A�����I�ɂ����_�I�ɂ����{�ł͎ЁE���E�J�̎O�̊v�V���}�̍s���̓��ꂪ���낢��Ȗ����ӂ��݂Ȃ�������n�����邱�Ƃ𗦒��Ɏ��������ł������B
�@���ƂɌ�҂̓��_�̂Ȃ��ŁA(�P)���ʂ̓����̎�ڕW�̈�������Ɨ��ɂ��邱�ƁA(�Q)�Љ�}�͓Ɨ��ƎЉ��`�Ƃ��ɒB�����ׂ����̂Ƃ��A���Y�}�͂܂������`�������ĎЉ��`�ւƂ��邿�����͂��邪�A���H�I�ɂ͑ΓƐ莑�{�����Ƃ����_�ł͎O�}�Ƃ�����ł��邱�Ƃ̓�_�����炽�߂čĔF�����ꂽ���Ƃ͏��Ȃ���ʎ��n�ł������B�����̈�A�̐��}�����̎Q��������k��ł́A���݂̓���̂��߂̎�ȏ�Q�́A�Љ�}�́u���Y�}�Ƃ͈�����悷��v�Ƃ����ԓx�ɂ��邪�A����͐�O����̊�łȉE���Љ���`�̔������_�ƁA������͋��Y�}�̂���̌�T�̔��f�Ƃ��āA��Ƃ��ĘJ���^���̉ߒ��Ő����j�I�Ɍ`������Ă������Y�}�s�M�_�Ƃ̌��ł��邱�ƁA���Y�}�ɂ������Ă����Ƃ��]�܂ꂽ���̂͊v���̕��a�I���W�ɂ��Ă̑ԓx�̖��m���ƕ��j�̈�ѐ��ł��邱�ƂȂǂ����炩�ɂ��ꂽ�B�O�q�������Y�}�̎��������c�͂����̗v�]�̈�ɂ����������̂Ƃ������Ƃ��ł���B
�@���ŎR��ς���̎��Ȃ̃e�[�}����j�I�ɒNj������͍�w���ێ�`�̐V�����ۑ�|�Љ��`�^���̐������̂��߂Ɂx�i�w���E�x�������j�����\���ꂽ�B�R��́A��O�̑��C���^�[�E��O�C���^�[�̕���̗��j�I���Ȃ������Ȃ��A���Z����ɂ���āu�\�A�̑����ӔC��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������ւ̏�Q�͂Ƃ菜����v���ۃv�����N���A�[�g�̓���̐V������]�����܂�Ă����Ƃׁ̂A���̌��Ƃ����Ƃ��āu�����ŏ����ɍl������C���^�i�V���i���́A���łɎЉ��`�����̎�������Ă��鍑�X�̓}�A���{��`���ɂ�����}�A�A���n�I�ȏ�ԁA�܂��͂���������Ԃ���V���ɉ�����ꂽ�������i�n��̓}�Ƃ����A�ق��������̂��Ƃɂ���O�̃O���[�v�̎Љ��`���}���e��������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł����āA����͉ߋ��̂ǂ̃C���^�i�V���i�������A�͂邩�ɕ��G�ȓ��e�ƕ��G�Ȗ��������̂ł����āA���������Ēe�͐��̂���g�D��K�v�Ƃ��邱�Ƃɂ��Ȃ�v�Ƃׂ̂��B
�@�R��̂��̘_���́A�V�C���^�i�V���i���̒Ƃ����������̂����A���̊�̓g���A�b�e�B�́u�������S�̐��v�̗��_�Ǝ�����������������߂��Ă���Ɠ����ɁA���{���Y�}�̑n���Q���҂ł���Ȃ��炻�̌�ʌ̕���������Ă����R�삶����̌o�����ɂȂ��āA��O�̓��{�̊v���^���̍ĕ]�����������Ȃ����Ƃ��鍡��̈Ӑ}���������������Ƃ��ł��A�d�v�Ȗ����o�����_���ł������B
�@���̌�w�Љ��`�x���N�L�O���́A�قƂ�ǎ��ʂ̑唼�����₵�ĎR��ς������ގЉ��`�^���j�̍��k����f�ڂ������A���̂Ȃ��ŎR��́A���Y�}������咣����Ă��������̔���_�����Ȃ���A�J�_�h�Ƌ��Y�}���}���N�X��`�^���̂Ȃ��̓�̗���Ƃ��ĂƂ炦�A�g�D�_����헪�_�ɂ܂ł�����L�͂ȕ��͂������Ȃ��ė��҂̑���𖾂炩�ɂ��A���{�̎Љ��`�^���j�̓Ǝ��̓W�J�����݂Ă���B�R��̕]���̐��ۂɂ͑����̖�肪�c����Ă��邪�A��O�̃v�����N���A�^���j�̖{�i�I�Č��������łɓ����ɂ̂ڂ��Ă��邱�Ƃɂ��ẮA�^���������]�n�͂Ȃ��B
�@�Ћ��̓���s���̖��ɂ��ẮA�w�O�q�x����̃A���P�[�g�w���Y�}�ƎЉ�}�̋��́x�͏d�v�Ȉʒu�����߂�B�����ɂ��߂��ꂽ�����Ȉӌ��́A�O�r�̏����������ɔF�߂�������̂ł������B��������ɘJ�_�}�̎Љ�}�ւ̍��������肳�ꂽ���Ƃ́A�Ћ����}�̊W�Ɏ�̕ω��������炵���B�J�_�}�̓��}�́A��ʎЉ�}���̓��ꐨ�͂����߂�ƂƂ��Ɉ�ʐ����t������ӂ����ѐV�����Ӗ��������Ă�����吭�}���̕��������߂邱�Ƃɂ���ĎЋ��̓������̎�������������\�����������Ă���B�J�_�}�̍����������Ȃ�����N�ꌎ�̎Љ�}������̓]�@�Ƃ��āA�Ћ����}�̊W�͂܂����̋ǖʂɂ͂�����̂ƍl�����悤�B
�@�S�A���{�鍑��`����
�@���{�鍑��`�����̖��ɂ��čŏ��ɓ��_����т������̂́A�l�N���A�R����`���������ɂ��Ę_�w���͂��Ă����L�c�l�Y�ł������i�w���{�鍑��`�͕��������邩�c��̖���N�Ƃ��āx�\�w�O�q�x�܌����j�B�L�c�́A�h�C�c���Y�}�̍j�̓I�錾���ˋ������h�C�c�鍑��`�����̎����̌o�ϓI�ߒ����A�����Q���E�N�`���X�L�[�̒����ɂ���Ă��Ȃ肭�킵���Љ���̂��A���{�鍑��`�̕����ߒ��͂��A�h�C�c�̂悤�ɂ��łɌ����ɕ��������Ƃ́u���}�Ȍ��_���������̂͂�����ł���v�Ƃ����Ȃ�����A�H�����Y�����ُ̈�ȑ����A���Y�̏W���ƓƐ�̂̋����A���i�A�o�Ǝ��{�A�o�̑���Ȃǂ̎w�W����u���ʁA�M�҂́A���{�o�ς̌���ɁA�A���n�o�ϓI�v�f�ƂȂ��ŁA����������鍑��`���W���O�ʂɂłĂ��邱�Ƃ��݂Ƃ߂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��v�Ƃ��āA���������̕K�v����т����A�u����Z�N�̌o�ωߒ����w�]���ČR���x�Ƃ����Œ艻���ꂽ�����ŊD�F�ɂʂ�Ԃ���̐��x���J�x�̗��_�v�i��̓I�ɂ͂��́w��g�u���x(���T)���͂��߂Ƃ��Ĉ�ʓI�ł��������_�������Ǝv����j�̑��}�ȍ������K�v�ł���Ǝ咣�����B
�@�L�c�̖���o�ƂȂ��ŁA�鍑��`�����̐����I�ߒ��𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ������݂���㐴�ɂ���Ă����Ȃ�ꂽ�i�w���R���t�@�x�\�w�������_�x�Z�����j�B���͔��R���t���u�A�����J�ɏ]�����Ȃ�����鍑��`�I���������Ƃ߂Ă���v��ʐ������������{�Ƃ��A�g�c�h���A�����J�鍑��`�́u���{�ɂ�����ԓ��v�Ƃ��ē����Â��A���{�̓Ɛ莑�{�́u�܂��鍑��`�I�������Ȃ��Ƃ���Ƃ����ɂ͂قlj������A���łɂ��̌X�����Ă���A����́A�������W����ł��낤�v�Ƙ_�����B
�@�E�ɒ�o���ꂽ���p����A���{�̃A�����J�鍑��`�̏]�����̕]���A����ɂ͌���鍑��`�̓����Ƃ�����肪�ӂ����ь����̑ΏۂƂȂ��Ă����͓̂��R�ł���B�w�������_�x�i�������j�̓��W�w���ĊW�̍Č����x�ƁA�w���E�i��Z�����j�̓��_�w����鍑��`�x�i�L��L�߁E�s���d�l�E�����L���D�ΐ쎠�E���a�����j�͂��ꂼ��̂����ł��̖��W�����悤�Ƃ������̂ł���B
�@��҂́A���[�j���́u�鍑��`�_�v�̕��͂��A�l���N���ւ������̏�ɂ����āA�ǂ̂悤�ȏC���Ȃ����͐V�����K���K�v�Ƃ��邩�Ƃ����e�[�}��Njy�������_�ŁA�o�Ȏ҂̖L�x�Ȗ��ӎ��ɂ���Ă��܂��܂Ȗ�肪�E���������Ă������A���̐߂̎��ɊW����e�[�}�ł́A���a���������h�C�c�Ɠ��{���͂�����Ɓu�Ɛ肪�x�z����o�ς́A�Ƃ���Ȃ������鍑��`�ł���v�ƒf��������������Ƃ����ڂ��ꂽ�B�܂��s���d�l�͋���Ȏ��{��`���ɂ��㏭���{��`���́u�]�����̖��́A�鍑��`�̐V���������`�Ԃ̖��Ƃ��āA�������������Ƌ������ׂ��_�v���Ƃׂ̂Ă���B�����I�ɂ��o�ϓI�ɂ��A���{�́u�]���v�\���̗��_�I�𖾂͓��{�鍑��`�����̖��̏œ_�Ƃ��āA�������Ƃ��ً}�̔C���ƂȂ��Ă���B
�@�T�A���j�̖��
�@���R�Ύ���́w���a�j�x�ɂ��������T�䏟��Y����o�����^��ɒ[�����_���́A�������_�@�Ƃ��ĐV�����W�J�����߂��A���̂Ȃ�������j�̂��Ȃ荪�{�I�ȍĕ]���ɂ��ĐϋɓI�ȗ��_�������Ȃ������R�Ύ��̓�̘_�������ݏo���ꂽ�i�w����j�����̖��_�x�|�w�������_�x�Z�����A�w���j���ǂ��Ƃ邩�x�\�w���E�������x�B
�@���R�͑��̘_���ł́A��O�̗��j�����Ƃ��Ă͂������A�Z�S���̌��c�ɂ����āA�����̋��Y�}�̗���ƁA���j�I�ɉ\�ȕϊv�̃R�[�X�ɗ��u����ׂ��O�q�̗���v�Ƃ���ʂ��A���҂̍������w���a�j�x�̂Ȃ��ɂ��������Ƃ����Ȕᔻ���A����j�����̋q�ϐ��͌�҂ɐ��������r���邱�Ƃɂ���Đ�������Ƃׁ̂A�w���a�j�x�̉Ȋw�I���Ȕᔻ�̏œ_�Ƃ��Đ�O�̋��Y�}�̐헪�����p�������o���͂������Ă����u�コ�Ɨc���v�̋�̓I�Ȏ��ɂƂ肩���邱�Ƃ�錾�����B
�@���R�͂��̂悤�Ȕ��Ȃ̂����ɗ����āA�܂����_���Ő��j�ɂ��Ă̏d�v�Ȏ��Ȕᔻ�������������B
�@(�P)�@�u���剻�̎����v�̐ϋɓI�Ӌ`�\�\�u����R�K��v�̃A���`�e�[�[�Ƃ��Ă̐��Z��`�ɂ�������ʂ��߂ɂ́A���̗��j�I�����Ƃ��Ă̍����̉�������̎��̂�T��˂Ȃ�ʁB���̎��̂Ƃ��ĉ��R�͓����鍑��`�I���v�͈͓̔��ł��A���{�̖��剻�����������߂���̗��j�I���������݂������ۏ�̏��v���ƁA�v���I��ł͂Ȃ��������A����Ɂu�ߎ������v���������݂������������Ƃ̓�����������B
�@(�Q)�@���@�̐ϋɓI�Ӌ`�\�\�����������剻�̎����ɐ��肳�ꂽ�V���@�́A�鍑��`�I�v���̔��f�ɂ�������炸�A�{���I�ɂ͔��t�@�b�V�������j�̂Ƃ��Ắu�|�c�_���錾�̉����Ƃ��ė������ׂ����i�v�������Ă����B�Ȍケ�̌��@�ɏ����ꂽ�����I���R�̓��e�́A�����̗͂œ����Ƃ��č������̎蒆�ɂ���B
�@�i�R�j�@���a�^���̗��_�\�\�����̐����ɂ����钆�S�I�ڕW�́A�����̂��ׂĂ������ĎЉ��`�����{��`���̖��ł͂Ȃ��A���a�Ɩ����`���������邽�߂́u�Љ��`���Ǝ��{��`���̕��a�����v�̎����ɂ������B���{�̕��a�^���̖ڕW���܂������ɂ���A��̐��x���Ƃ�������������炭��s���ƍ���������Ă��Ă���O�ł͂Ȃ������B
�@�ȏ�̎O�_�̎��Ȕᔻ����A���R�́A�V���@�̐����͒鍑��`����̈�ł���Ƃ���]���̃}���N�X��`�I���ꂩ��o�Ă�����̂͐�p�I��i�Ƃ��Ă̌��@�i�쓬���ł����Ȃ������Ƃ��A���͌��@�i��́u���ۓI�ɂ͕��a�����̎����Ɋ�^���A�����I�ɂ͖����`���������邽�߂̓��{�̐����ۑ�̏œ_�v�ł���ƌ��_�����B����̗��_�͐����{�́u�y�n���v��J�����@�Ȃǂ̏d�v�ȏ��[�u�̐i���I�v�f�������v�Ƃ����\���F�g���m�w���咣�̎��Ȕᔻ������Ɉ���i�߂āA���̏��݂̈�̏œ_��������o�������̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@�܂��܌��̗������ł́A�܈�N�ȗ��A���j���ɂ������閯����`�I�J���p�j�A�ɂ���Ă��Ȃ�̍������Ђ��������������ɂ������āA�˂��܂�����ɂ���ċ��Y�}�ɑ�������j�w�҂̐ӔC�����������Ȃ��A�Ε�c���̎��Ȕᔻ�����\���ꂽ�i���ё�͒��P�R�Q�Ɓj�B����͐��j�̕]���ɂ��傫���Ȃ���ׂ����̂ł���B
�@���j�͂������č��A���Ȃ荪�{�I�ɏ������߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ��Ă��Ă���B���̉���ő傫���E�ɗh��A�R�~���t�H�����_�]�ʼnE���Ό������Ȕᔻ���ē��ɑ傫�����ɗh��A���Z����ł�����x�ɍ��Ό������Ȕᔻ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��������{�}���N�X��`�́A�����N�����Ă݂��сA���̏o���_���Ȋw�I�Ɍ��Ȃ����K�v�ɔ����Ă���̂ł���B
�@�U�A���{�}���N�X��`�̔ᔻ
�@�Z�S���E���Z����E�t���V�`���t�u�閧�v�Ƌ��Y��`�Ƌ��Y�}���߂���d���肪���̈�N�ԂЂ��Â��ċN�������߁A�킪���̃W���[�i���Y���ł͋��Y��`�ᔻ����{���Y�}�ᔻ���ӎ��I�ɂƂ肠������X�������܂�A���̃e�[�}���������_���⒘���������������ꂽ(�U)�B
�@�Ȃ��ł��A�����Ƃ����s�������̂͑����̓��{���Y�}�̋ɍ��`����`�̌�T�������W���[�i���X�e�B�b�N�Ȕᔻ�ŁA���L���̒��������̑�\�I�Ȃ��̂ł����i7�j�B����̋��Y�}�ᔻ�́A�}�O����̎����ɂ��ƂÂ������Ȕᔻ�Ƃ��Ă̐ϋɓI�Ӌ`������������A���{���Y�}�̐��̗��j���A��ʓI�Ɍ�T�̘A���Ƃ��ĕ`���������_�ɂ����āA���_���ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��댯�Ȑ��Z��`�ޕ�قƂ��Ă̖������͂������̂ł������B
�@��ʓI�ɂ����Ă��A��T���Ƃ��ɑ傫�Ȃ��̂ł������ꍇ�ɂ́A���̍����͗e�Ղɋt�̋ɒ[�̐��Z��`�ɂ�������₷���B�������ꂽ��T�̐����Ɣ͈͂𐳊m�Ɍ�����߁A���̊��Ԃɓ}���B��������{�I�Ȑ����̕]���Ƌٖ��Ɍ��т��Ă��̔�d��������߂邱�Ƃ́A�����Ƃ��o�����鋤�Y��`�҂ł������܂Â��₷������ȉۑ�ł���B���{���Y�}�̋ɍ��`����`�̌�T�̔ᔻ���A�����̗��j�I�������炫��͂Ȃ���A���܂����̊��Ԃł����}�������Ȃ��Ă����Ɨ����߂������鍑��`�̉p�Y�I�ȓ����A�����`��i�삵�A�ΘJ�҂̐�������i�삷�邽�߂̂˂�Â悢���퓬���A������x�܂ōL�͂ȑw�����W���������a�i�쓬���Ȃǂ̏����ʂ����Ă�������Ȃ�A�ᔻ���̂��̂��s���m�Ȃ��̂ɓ]��������肩�A�������ɊK���G�𗘂���������ʂ����̂ƂȂ炴������Ȃ��̂ł���B
�@���Ƃ����֓���Y�́w�����{�J���^���j�x�i�ܘZ�N���E�㌎���j�́A�J���^���j�Ƃ������G�ȉۑ�����Y�}�̌�����w���Ƃ�����{�I�ϓ_�Ő����������̂ŁA�����������Z��`�I�X���̈�Y���ł������B�܂���O���̃}���N�X��`��V�����ϓ_���琮�����悤�Ƃ���J�삪���R�O���ɂ���đ����Ŕ��\���ꂽ���A����������{�}���N�X��`�̗��j���u�_�R���_�v�̏����̗��j�Ƃ��ĕ`����������ώ�`�I�Ȃ��̂ɑ��Ă����i8�j�B
�@�����̋��Y��`�ᔻ�̂Ȃ��Ŗ��J��̕���ɓƎ��̃��X���ӂ���ĐV���������o���Ă������̂́A�T�䏟��Y�E�ێR���j�E����E�v����E�ߌ��r����ł������B�}���N�X��`�Ƃ͕ʂ̗���ɗ������̐l�X�̔ᔻ�ɋ��ʂ��Ă��������́A�}���N�X��`�̔ᔻ���A���̗��_�̕��@�_��A���邢�͗��_�̂ɂȂ���Ƃ��ċ��Y��`�҂̔F�����@��A���z���@�̌��ׂ͂��邱�Ƃɂ���ĉʂ����Ƃ������Ƃł���B�������������͂��̔ᔻ�Ɉ��̐��ʂƌ��E�Ƃ��Ƃ��ɂ���������̂ł��������Ƃ͌��₷�������ł��낤�B
�@�T��͂܂����w�I��@����g���Đ�O�̓}�j����ڂ��Ȃ���A���{���Y�}�̎v�l���@�̓����I���ׂƂ��āA���ɁA���{�ŗL�̍����I�`���E���K�E���i����{�ŗL�̏������ɂ��Ắu���{�̓������̂��̂���̔��z�v�̌��@�A���ɁA���{�̒m���l�ɓ��L�́u�O���ӏ]�v��`�A��O�ɁA���{�l�I���i�̂�����Ƃ��Ắu�ɒ[�Ȍ��Ȑ��Ɛ���������`�v�u���l���f�ɂ����閳�ނ̐��}���v�Ȃǂ��A���{���Y�}�̃Z�N�g��`�ƌ�����`�̐S���I�����Ƃ��Ďw�E���A����ɋ�̓I�ɎR��C�Y���̍ĕ]�����͂��߂Ƃ��Đ�p���ɂ��邢�����̋^�������o�����B
�@�ێR�̘J��́A���Z����̃e�[�}���ꎩ�̂̒Nj��͂��炭�����āu�X�^�[�����ᔻ���߂���e�����Y�}�̘_�c��f�ނƂ��āA�����̐����ߒ��ɑ���}���N�X��`�҂̎v�l���@�ɓ��������Ă�����̖��_���w�E�v���A�u�R�~���j�X�g���ˋ�����}���N�X��`�̎v�l�@�ɂ������ꂽ����������́g���R���h��v���v���悤�Ƃ������̂ł������B
�@����́A�R���~���j�X�g�̎v�l�@�̂Ȃ��ɁA�l���q�̍����_�c�Ɍ�����悤�ɗ��j�I�E��̓I���������A���Ɍ����ɂ����̂ڂ��Ă��܂��u�k�y�@�I�_���v�A����Ƃ͋t�Ɂu���ɂ��̐��̂�\�I�����v�Ƃ����悤�ɖ{���ړI���炷�ׂĂ𗬏o�����Ę_����u�{�������I�v�l�v�A���_�ƃe�[�[�d���邠�܂�ɐ����S���̔��ʂ̔F�������ۂ��Ă��܂��u������`�v�A���ׂĂ����{��`���x��Љ��`���x�ɊҌ����Ă��܂��u���̐��Ҍ���`�v�Ȃǂ̌ŗL�̔�Ȋw�I�v�l�X�����ӂ��܂�Ă��邱�Ƃ��A���킵���w�E�����B
�@���́A�O�f�w���a�j�x����㐴�E��ؐ��l�́w���{�ߑ�j�x�ɂ͂�����u�����ߒ��v�i�|���e�B�J���E�v���Z�X�j�A�܂�c��O���́E���͏W�c�E���}�E�c��E���{�Ȃǂ̏��W�c�̕��G�ȑ��݊W�������āu����v�������Ȃ���u���̓I�ȗ����I�ȏz�̉ߒ��v���قƂ�Ǖ`���Ă��炸�A����́u���{�̃}���N�X��`�҂̌���j�����Ɍ����Ă���d�v�ȃ|�C���g�v�ł������瑽���́u�ƒf�v�����܂����̂Ɣᔻ�����B�������Ă���͗��j�w�҂̔C���Ƃ��āA�u�����ߒ��v�̋�̓I���͂ƕ��s���āA�o�ύ\���E���{�\���̌����A�����I�G���[�g�̐����I�s���l���E�v�z�\���̎��ؓI���́A�u���㐭���ɂ������O�̗��_�I�c���v�Ȃǂ��K�v���Ƃ��A�u�����Ɛ��I�ȃ����Y�v���Ƃ�т������B
�@�v��E�ߌ��́u���{���Y�}�̎v�z�v�������ꂽ�n�ӂɂ���ĕ��͂��A���{�̗B���_�͂��̓��L�̗��j�I�����̂��߂Ƀ}���N�X��`����Ƃ��āu��㈓I���@�v�ɂ���Ă̂ݎ��A���̌��ʁu�����̍ו��ɂ킽���Ắv�����F�����������u��ǓI�B���_�v�Ƃ��Ă̐��i�������A�������u�ُؖ@�I�B���_�v�ɂ܂Ő������Ă��Ȃ��Ɣᔻ�����B�����ē��{���Y�}�̍���̉ۑ�Ƃ��āA���_���u���؉\�̗̈�i�e�X�^�r���e�B�[�E�]�[���j�ɂЂ����ǂ��āv���̐��ۂ�������Ƃ����\�͂�g�ɂ��邱�Ƃ�v�������B
�@�����̐l�X�̓��{�}���N�X��`�ɂ������鐽���Ȕᔻ�́A����̃}���N�X��`�ɂ�����Ă���ꕔ�̔ے�I���ۂ��A�}���N�X��`�̗��_�̌n�ɓ��݂��Ă���{���I���ׂł��邩�̂悤�ɂ��������ނ�������Ƃ��Ă��A�����ɐ[���Ȕ��Ȃ𔗂���̂ł������B����̓��{�}���N�X��`���A���̑n���I�����ɂ���āA�ǂꂾ�����_�I�L�����Ǝw�����Ƃ��Ƃ���ǂ��Ă����邩���A���͂����̐l�X�̔ᔻ�̗L�����������肷�邱�ƂƂȂ�ł��낤�B
�@�V�A�_�Ɩ��
�@���͂ł��ӂꂽ�悤�ɁA���Z�����A�}�����c�̑O�i�̌��ʁA�\���F�g���m�w���咣���A���{�́u�y�n���v�v�́u�i���I�v�f�v���������Ƃ����Ȕᔻ�������Ƃ������āA�Z�S����A�u�����̐w�c�ɂ�������̈ӌ��A�}�b�N�̔_�n���v�͂ǂ�ȏd��ȕω��������炳�Ȃ������Ƃ����ӌ��ƁA�}�b�N�̔_�n���v�ɂ���Ă킪���̔_���ɂ͕����I�c�����͊�{�I�ɂ͂Ȃ��Ȃ����Ƃ����ӌ��́A�Ƃ��Ɍ���Ă����v�Ƃ�������^���Y�Ȃǂ̐ܒ��I�����͒n���A������u���۔h�v�̌������������������Ƃ���ʓI�ɔF�߂��Ă����B
�@���Y�}�̘Z����(�l��)�����肵���e����̊������j�̂����A�w���ʂ̔_���^���̕��j�x(�w�O�q�x�Վ������w���{���Y�}�̔C���ƕ��j�x)�́A�_�n���v�̌��ʁA�n��I�y�n���L���r������āu�_���I�y�n���L�v���g�傳��A�u�_���͐V���ɃA�����J��̎x�z�ƓƐ莑�{�̎��D�ɂ�������v���𒆐S�Ƃ��āv�����Ă���A�y�n���v�̔C���͂Ȃ��c����Ă���Ƃ͂����A���ʂ̓����̏d�_�͐ŋ������E���i�����E�c�_���������Ȃǂɂ��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�y�n���v��y�n�Ǘ��g���̕]���A�^���̑g�D�_���p�_�Ȃǂɂ��Ȃ�̑���͂���ɂ��Ă��A���̕��j�̊�{�v�z���A���͂ł������퓌�����̕��j�Ɗ�{�I�ɂ͓�������̂��̂ƂȂ��Ă��邱�Ƃɑ����̗]�n�͂Ȃ����̂ł������B
�@����ɔ������i�㌎�j�́u�V�j�́v�̔_�����̋K��̍Č����Ɖ������N���A�Z�����̕��j�Ăɂ��ƂÂ��_�ƁE�_�����̗��_�I���c��S�}�ɂ�т������B
�@�Ȃ��A�Z�����̕��j�Ăɂ��ẮA���j���ꔪ�Z�x�́u�R�y���j�N�X�I�]��v���Ƃ����ɂ�������炸�A�ߋ��̐���ɂ��Ă̎��Ȕᔻ���ړI�ӎ��I�ɒ�N����Ă��炸�A���̌��ʏ퓌�̓����̌o�����Ȋw�I�ɐێ悳��Ă��炸�A�����̐�p�A�g�D�̌`�ԂȂǂɂ����ĕs�\���ȓ_���c���Ă��邱�Ƃ�ᔻ���A�������̖����o�����V��F���̔ᔻ�����\����Ă���i�w�_���^�����j�i�āj�ւ̔ᔻ�x�\�w�O�q�x��Z�����ꍆ�j�B
�@����ɂ��̎����ɂ͔_�Ɨ��_�̊�b����ɂ����āA�͂₭���������̘_���_����N���ꂽ�B
�@�i�P�j�@�_���̊K�w�敪�̍Č����\�\���̖��͂܂�����Ύ��ɂ���Ē�o���ꂽ�i�w���{�_���̊K���K��̊�{���x�\�_���^��������ҁw�V�����_���^���x�ܘZ�N���������ځj�B����́A���݂̓y�n���L�̊�{�`�Ԃ͕����n�_���I�y�n���L�ł͂Ȃ��u�_���I�y�n���L�v�ł���A�_���o�ς́u�����i���Y�v�Ƃ��Đ������Ă���A���W�͒��ړI���Y�W�ł̎��D����u���ʉߒ��ł̓Ɛ莑�{�܂��͍��Ƃɂ�������W�v�Ƃ��Ă�����Ă��邱�Ƃ��܂��m�F�����̂��A�]����ʓI�������K�w�敪�_�A�x�_�E���_�E�n�_�E�ٔ_�Ƃ����悤�ȋ敪�́A���������_���̌���ɂ��Ă͂܂�ʃh�O�}�ƂȂ��Ă���Ǝ咣�����B
�@����̓h�C�c�̃G���X�i�[�́u�ΘJ�_���K���v�Ƃ������_�Ɏ肪��������߂Ɛ莑�{�̒��ړI���D�ɑS�_�������炳��Ă��邩����A���{�_���́u�ЂƂ̊K���A�ΘJ�I���K�����`������v�Ƃ��A���{�̔_�ƒ��J���̓���Ȑ��i���狌���̌ÓT�I�ȁu�n�_�E�ٔ_�v�K��͂��Ă͂܂炸�A�܂����{�̕n�_�o�c�̎��R�o�ϓI���i���炢���āA�u�Ɛ莑�{�ƋΘJ�_���̊K���Η��̂Ȃ��ŕn�_�w���������Ƃ��v���I�ȃG�l���M�[�����Ƃ����]���̗��_�������邱�Ƃ͂ނ��������Ƃ���߂đ傽��Ș_�������Ȃ����B
�@�������Ĉ���́A���{�̋ΘJ�_���̕����ߒ��́A�T�^�I�ȃu���W���A���ƃv�����N���A���ł͂Ȃ��A��ʓI�ɂ́u���u���W���A�I�o�c�ɒ�����܂܂ł̕x�T���v�Ƃ�������X���ƁA�u�G�������U�I�Ȕ_�ƊO���J���ɂȂ���n�����v�Ƃ��������X���Ƃł���A�o���Ƃ����Ɛ�̔_���^���̂��ǂ���ƂȂ�Ƃ������_���݂��т��Ă���B
�@���̌��_�́A�퓌�ł̒������H�I�o���̐T�d�ȗ��_���ł����������ɁA�]���̗��_�ƍ��{�I�ɑΗ������V���_�Ƃ��č���̔_�Ɨ��_�̕���ɂ������̘_���̑ΏۂƂȂ���̂Ǝv����B
�@���v���E��ؐ��E����v祏�w�_���^���̔��ȁx�i��ꌎ���j�̂�����ؐ��̏������u��́E����̔_���^���v�́A�ߋ��̉^���̃Z�N�g�I�X���̔��ȂƂ����_�ł͈���Ɠ����o���_�ɗ����Ȃ���A�u���_�w�v�����鍑��`�ƓƐ莑�{�̎��D�Ƃ����u�_���Ƃ��Ă̖������W���I�ɂ����Ă���v���A���Y�}�́u���{��`�I�ȓƗ����c�_���̌o�c���P�̗v�����x�������シ�ׂ��ł���Ƃ����V���������\���Ă���B���̌����ɂ��Ă͈�����������ɁA�S�ΘJ�_���K���̗v���𒆔_�v���ɂ킢�������A���̌��ʂƂ��ĈˑR�Ƃ��āu�n�_�ˋ��_�v���G�������Ă�����̂Ƃ��Ĕᔻ�����i�_���^��������ҁw�Ɛ莑�{�Ƃ��������_���^���x�\�ܘZ�N����\�̑�Z�́j�B
�@����Ɂw�ϊv���ɂ�����n����e�x�i�R�c�����Y�ҁA�܌ܔN�x�y�n���x�j�w��̕\�ܘZ�N�㌎���j�ŁA�]���̎��Ȃ̔_�Ɨ��_�̈ꉞ�̎��Ȕᔻ�������Ȃ�����㐴�����A���ݓy�n���߂��铬������i�ɂ��肼���Ă����Ƃ��Ă��u�y�n���͂�����Ƃ��Ė����`�v���̉ۑ�����̍���ɉ�������āv����A�u�n�_�Ȃ������v���w�̓y�n�~���̖����v�����u���R�Ȕ_���I�y�n���L���������i�K�I�����v�ł���Ǝ咣���Ă��邱�Ƃ��݂Ă��A�����ɂ�����_�Ɨ��_��̑Η������Ȃ��ό`����ɂЂ���ł��邱�Ƃ��킩��B
�@�i�Q�j�@�y�n���L�̋K���\�\�_�n���v�ɂ��ω��̖{���ɂ��āA�����̘_���ɂÂ��ĉ��v��̎���_�I�y�n���L�̐��i�K�肪���炽�߂Ė��ɂȂ��Ă���B�ژ_�͂͂Ԃ����u�_���I�y�n���L�v�i����j�A�u�����_�I�y�n���L�v�i�I���S���w�_�Ɩ�����x�j�A�u��{�I���i�͒n��I�y�n���L�v�i���r��V�j(9)���ǂ̑��Η����錩�������łɂ�����Ă���B�w�Ƃ�킯�ϊv���ɂ�����n����e�x���R�c�����Y���y�n���x�j�w��̓��c�̌��_�Ƃ��Ă��̂悤�ɂׂ̂����Ƃ́A����u�������_�ҁv�̐V�����L�͂Ș_���Ƃ��ēK�p����邩������Ȃ��B
�@�@�u�L������ɁA�����̔_�n���v�ɂ����Ă͔������I�A�n��I�y�n���L�́A�Ɛ莑�{�ɂ��_�Ɗ�@�̉����Ƃ��āA�ɂ߂đ�Ђɉ�̍ĕ҂���͂�������Ղ����|���ꂽ�̂ł͂Ȃ������B���������Ă܂��A���v��ɂ�����y�n���L�̐��i���A�����I�y�n���L�̉�̂��琬�����鎩�R�Ȕ_���I�y�n���L�A�܂��͕����n�I�y�n���L�̊T�O���Ȃ��ė����邱�Ƃ����Ȃ��B�v�i�����l�O��y�[�W�j
�@�i�R�j�@�������̌��Ƃ����\�\���������_�̓]���ƂƂ��ɁA���i�K�ɂ�����u���Y�̋������v����{�_�Ƃ̋ߑ㉻�����������߁A�u�����̎Љ��`�I�_�Ƃ��w��������́v�Ƃ��ĕ]�����悤�Ƃ��錩�������܂ꂽ(�P�O)�B����ɂ������Ă͑O�L�_���^��������́v����Ύ��E�V��F���炪�S�ʓI�ɔ��ᔻ�������Ȃ��Ă���i�O�f�w�Ɛ莑�{�Ƃ��������_���^���x�j�B
�@�ȏ�̂ق��ɁA�l�������`�_�ɂ���(�P�P)�A���Q���_�ƌi�C�z�̔��Ȃɂ���(�P�Q)�A�}���N�X��`�N�w�̔��Ȃɂ���(�P�R)�A�Ȃ�тɎЉ��`�̔��W�@���̉�(�P�S)�Ȃǂ̘_���������Ȃ��Ă��邪�A�����̖������ׂĘ_���̌��������Ă��Ƃ��ꂽ�Ƃ����i�K�ŁA���܂łׂ̂Ă��������ɂ��ĂƓ��l�ɁA���{�v���_���̌��i�K�́A�{�i�I�W�J������Ɏc���Ă���Ƃ����ׂ��ł��낤�B
�@�W�A(��)�P�S��
�i1�j�@�w�A�J�n�^�x�ɂ��ܘZ�N�Z����Z�����������w�\�������Y�}���Z����̏����x���A�ڂ���͂��߁A�w�O�q�x�ɂ����E�㌎���Ɂw�\�������Y�}���Z����E���c�̊w�K�v�j�x���f�ڂ��ꂽ�B
�i2�j(3)(4)�@�C�M���X�A�h�C�c�̃f�[�^�ɂ��A�ȗ�
�i5�j�@�o�όR�����̉ߑ�]���ɂ������čŏ��ɔᔻ�����킦���̂��䋂����́w�z�ɂ�����Ɛ�@���x�i�w���E�o�ϕ]�_�x�ܘZ�N�㌎���j�ł��邪�A����ɂÂ������c�t�g���A�u���{�o�όR�����̒���v�̍Č�������A���̒���́u����܂�ł���A�s�������ł���v�ƌ��_���Ă���i�w�o�ϕ]�_�x���N�ꌎ�j�B
�@�i6�j�@���̂������_�������ӂ��ޑ�\�I�Ȃ��̂�������ƁA���W�w���{���Y�}�̐V�W�]�x�i�w�m���x�Z�����j�A�����Y�w���{���Y�}��]���x�i�w�Љ��`�x�������\�w�Љ��`�\�Â����ĐV�������́x�����j�A�w�\�A�̕ϖe�Ƌ��Y��`�̏����x�i�w�������_�x�Վ������j�A���c����w�X�^�[�����ᔻ���ǂ��Ƃ邩�x�i�w���E�x�������j�A�T�䏟��Y�w�v���̓������߂����ā\����j�̎��̉ۑ�(�l)�x�i�w�������_�x��Z�����j�A�ێR���j�w�X�^�[�����ᔻ�̔ᔻ�x�i�w���E�x��ꌎ���j�A����w����j�̏d���Ɛ[���x�i�w���E�x����j�A�v����E�ߌ��r��w������{�̎v�z�x�i�ܘZ�N��ꌎ���j�B
�i7�j�@���L��w���w�҂̊v�����s�́x�i�ܘZ�N�l�����j�A�w�����V�c���x�i�ܘZ�N�ꁛ�����j�A�w��X�؋��Y�}�͓k�}���x�i�w���|�t�H�x�ܘZ�N��ꌎ���j�A����ɗނ�����̂Ƃ����O�Y�Ƃ��w���Y�}�x�@�i�ܘZ�N��ꌎ���j�Ȃǂ�����B�Ȃ��A���̋��Y�}�j�Ɏ�ނ��������ɂ��E�c���w����}���̍����x�A�������w�����ꂴ���́x�A���Y�����w�זE�����x�A���B���w���{�̓~�x�Ȃǂ�����B�ق��ɐV���L�҂݂̂����Y�}�j�Ƃ������㊰���w���{���Y�}�x�i�ܘZ�N����j���o�ł��ꂽ�B
�@�i8�j�@���R�O���w���{�}���N�X��`�j�x�i�؏��X�ܘZ�N�l�����j�A�w���{���{��`�_���̌��i�K�x�i�؏��X�ܘZ�N����j�B
�i9�j�@���r�́A�_�n���v��́u����_�I�y�n���L�v���u��ʂɂ����Ēn��I�y�n���L�̑Η����Łv�ł��邪�A�������āu���R�Ȕ_���I�y�n���L�v�ł͂Ȃ��Ƃ�����ʐ��i�������Ă���A�Ȃ��u��{�I���i�v�́u�n��I�y�n���L�v�ł���Ƃ��i�w�_�n���v�Ɠy�n���L�̐��i�x�\�w�ϊv���ɂ�����n����e�x�����j�A�ʂ̘_���ł́u�y�n���L�̒n��I��_���I�`�ԁv�Ƃ��ł���(�w���ɂ�����y�n���L�̊�{�I���_�x�\�w�o�ϕ]�_�x�ܘZ�N���)�B
�i10�j�@���Ƃ����������w�_�n���v�ƊK���W�̕ω��x�i�w�O�q�x�ܘZ�N�������㍆�j�A�{��ܘY�w�_�n���v�ƒ��쌧�ɂ�����_�Ƃ̎��{��`�I���W�x�i�w�O�q�x�ܘZ�N����O���j�B
�i11�j�@�w����Љ��`�u���x�i���m�o�ϐV��Њ��j��܊�����ё�Z���Ɍf�ڂ��ꂽ�ҏW�ψ���̎��Ȕᔻ�A��X����Y�w�Љ��`�I���ۋ��͂̓]��_�x�i�w�o�ϕ]�_�x���N�ꌎ���j�B
�@�i12�j�@���c���v�w�}���N�X��`�o�ϕ��͂̐V�������W�\���i�C�z�_���x�i�w�A�J�n�^�x�ܘZ�N��ꌎ��l�E��܁E�������j�A�䋂����w���i�C�z�̌����x�i���{�]�_�V�ЌܘZ�N����j�B
(13)�@���k��w�}���N�X��`�͂ǂ����W����̂��x�i�ÍݗR�d�E�v����E�ߌ��r��A�w�������_�x�ܘZ�N�����Վ��������j�A�w���{�̃}���N�X��`�x�i����A�w�������_�x�ܘZ�N����j�A�O�Y�Ƃ��w���̒����������Ă���x�i�w�����@�ܘZ�N�܌����j�B
�i14�j�@�w����Љ��`�u���x�@�i�S�Z���A���m�o�ϐV��Њ��j�A�w�Љ��`�u���x�i�S�����A�͏o���[���j�B
�@�S�A�w���{���Y�}�̘Z�\�N�x(����)
�@�k���ڎ��l�@��c�E�s�j����Ɓu���Ȕᔻ���v���\�����Ƃ̊֘A������
�@�@�@�P�A�Z�S����̓}�����A�P�X�T�U�N�`�T�W�N
�@�@�@�Q�A��V������ɂ�����}����T�̋��P�A�P�X�T�W�N
�@�@�@�R�A����W�����ᔻ�҂����A�c���x�v���ᔻ�A�P�X�V�W�N
�@�P�A�Z�S����̓}�����A�P�X�T�U�N�`�T�W�N(�o�D�P�S�V�E�P�S�W)
�@�܂��A�܁Z�N���̎���Ƌɍ��`����`�̌��̐[�������͂����肷��ɂ�A�}���ɂ����R��`�A���U��`�A�l��`�A�s�k��`�A���Z��`�̌X���⒪���������炵�������ꂽ�B�ߋ��̌��ւ̔ᔻ�̎��R�Ƃ������ƂŁA�}�����͓}�g�D�̓����œ��c�E��������Ƃ�����������͂���A�}�̖���W�����⎩�o�I�K��������X���́A�}���O�ɂ��܂��܂̌`�ł����ꂽ�B�܁Z�N���ɂ��ē}�������J�Â�����c�A�W��ł��A�������̑��̒n���̉�c�ł��A�Q���҂��ӔC�̏��݂̋�����v�����āA��c����������ꍇ�����Ȃ��Ȃ������B����ɁA���̊ԁA�s���Ȕ��⏈���Ȃǂ������ď����A���邢�͓}�̏�Ԃɐ�]�I�ɂȂ��ė��}����}�������Ȃ��Ȃ������B��ł����x���i�זE�j���������݂�ꂽ�B
�@�܂��A�u�Z�S���v�ł���ꂽ�����ψ��̈���ł���u�c�d�j�A�Ŗ�x�N�炪�A�}�̕���̎����ɁA�}�����̂����œ}�̊����Ƃ��Ă�邷���Ƃ̂ł��Ȃ����s�ׂ������Ȃ��Ă������Ƃ������炩�ɂȂ����B�u�c�́A�}�̒�����������܂��ɔC����������ē��S���A���S�̗��R�������I�ӌ��̑���ɂ��邩�̂悤�ɂ�����Ĕ��}���h��g�D���A�}�̂����������킾�Ă��B�}�����́A�u�c���������A���̍����ӂ����B�Ŗ���}�̒��������ۂ��A�G�ΓI�ԓx���Ƃ������ߏ��������B
�@�Q�A��V������ɂ�����}����T�̋��P�A�P�X�T�W�N(�o�D�P�T�T�E�P�T�U)
�@���́A�����̂Ȃ��ŁA���܁Z�N�̓}�̕���Ƃ��̌�̎��Ԃɂ��āA�ڍׂȑ����������Ȃ��A�}����̒��ځA�ő�̌������A�����̐����Ǒ����ɂ��A�K��ɂ��ƂÂ��Ȃ��w���I�����̔r���H��ƒ����ψ���̈���I�ȉ�̂ɂ��������Ƃ��w�E���A���̕s�K�ȕ���̌o������A���̌܂̋��P���Ђ��������B
�@�i1�j�@�����Ȃ鎖�Ԃɍۉ�Ă��}�̓���ƒc���A�Ƃ��ɒ����ψ���̓���ƒc�����܂��邱�Ƃ����A�}���̑��`�I�ȔC���ł��邱�ƁB
�@(�Q)�@���̂��߂ɁA�ƕ����I�l���S�w�����K�������鎩�R��`�A���U��`�����т����r���A�����Ȃ�ꍇ�ɂ��K������炵�A�K�肳��Ă�����̑��̓}��c�����I�ɂЂ炫�A����W�����ƏW�c�w���̌�������ʂ����ƁB
�@�i�R�j�@�����ψ�������̒c���ƂƂ��ɁA�����ƒn���g�D�Ƃ̒c���̂��߂ɍőP�̓w�͂��͂炤���ƁB
�@�i�S�j�@�}�̕���O�c�̂̐���Ȕ��W��j���ɂ����o���ɂ����āA�����Ȃ�ꍇ�ɂ��}�̓�������}�O�ɂ����������A�����}���ʼn�������w�͂��������ƁB
�@(�T)�@�}�̎v�z���݂Ɨ��_���y�����镗������|���A�}������擪�ɑS�}���A�}���N�X�E���[�j����`���_�̊w�K��g�D���A�}�̐����I�A���_�I���������コ���邽�߂ɓw�͂��邱�ƁB
�@���͂܂��A��O�G�ɋ������ē}�Ɛi���I�l�m�𗠐�A��㒷���ɂ킽���ē}�������̔ƍߓI�������Â��Ă����ɓ����̏������m�F�����B
�@�R�A����W�����ᔻ�҂����A�c���x�v���ᔻ�A�P�X�V�W�N�i�o�D�S�O�P�j
�@���̊ԁA�ѓc�]�����𗘗p���������U���̂Ȃ��ŁA���{���Y�}������W�����ɂ������������A�����Ɉ�̂˂炢���߂�`�ł����Ȃ��Ă������ƂƂ��֘A���āA���łɑ�\�l��}���ł��w�E����Ă����_�d�Ȃǂ̈ꕔ�_�҂ɂ�閯��W�����_���A�����ł��Ȃ��ے�I�������͂����Ă����B�����́A���{���Y�}�̖���W�������A�ߑ㐭�}�Ȃ瓖�R�́A�����Ƃ������ꂽ�g�D�I�����̈�ł���A�O�q�}�Ƃ��ĕs���̂��̂ł��邱�Ƃ��Ȃ�痝�������A����W������ᔻ������A���h��h���̎�����̗e�F�ɂȂ���悤�K�������߂邱�Ƃ��咣������A�s���ł͏����������ɏ]���Ƃ��Ă����̓}�̕��j�ɂ�������ᔻ�̎��R��ۏႷ��̂�����I���}�Ƃ��Ă�����܂����Ǝ咣����Ȃǂ̌X���������Ă����B
�@�����ɂ������ẮA�s�j�N�O�u�Ȋw�I�Љ��`���w������`�x���v�i�w�O�q�x����N�ꌎ���j�A�u�O�q�}�̑g�D���Ɠc�����_�v�i�����Z�N�O�����j�A������Y�u�O�q�}�̑g�D�����̐����v�i�u�Ԋ��v�]�_���W�Ŏ����N�\�ꌎ�������j���͂��߁A�����̗��_�I�J�삪�[���ᔻ�I�𖾂������Ȃ����B
�@�����ł́A����W�����ᔻ�҂����̋c�_���A���{���Y�}�̖���W�����_���܁��N�ԑ���ӂ��ނ킪�}�̒ɋ�̌o���̂Ȃ����炤�݂����ꂽ���{�ɂ�����Ȋw�I�Љ��`�̉^���̗��_�Ǝ��H�̓��B�_���Ƃ������Ƃ��݂��ɁA�������ꂱ��̊O���̗����ɂ��ē}�̑g�D�_��ᔻ���Ă��邱���A���V�A�v���̉ߒ��ł��낢��Ȏ����Ƀ��[�j�����ׂ̂����t�A�Ƃ��Ƀ��V�A�̉Ȋw�I�Љ��`�̒��������u���W���A�I�����ƈ�̓}�̂Ȃ��ɘA�����Ă�������Ƀ��[�j�����������u�ᔻ�̎��R�ƍs���̓���v�Ƃ���������A���̂܂܂��܂̋��Y�}�̊�ɂ��邱�Ƃɂ���āA�킪�}�����u���W���A�I�������ӂ��ދ�������I�ȓ}�ɂЂ����ǂ��c�_�ł��邱�ƁA���Y�}���̖����`��_����̂ɁA�������{�̎Љ�ɂ����閯���`�̖��Ǝ����㍬�����A�����͍��Ƃ̂Ȃ������Љ��]��ł���̂�����A�����̉^���̑g�D�������Љ�Ɠ��������ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����o�N�[�j�����̋c�_�ƂȂ��Ă��邱�ƂȂǂ��A�[���ڍׂɉ𖾂����B�����̗��_�I���ʂ́A���E�̋��Y��`�^���ɂƂ��Ă����I�Ӗ��������̂ł������B
�@�T�A�w���{���Y�}�̎��\�N�E�N�\�x�i�����j
�@�@�@�@���[���R�~���j�Y���ւ̋}�ڋ߂Ƌt����f�[�^�A�P�X�V�T�N�`�W�T�N
�@�@�@�@�C�^���A�A�t�����X�A�X�y�C���R���Y�}�Ƃ̊W
�@�P�X�V�T�N
�@�X�E�Q�O���`�Q�W�@�C�^���A���Y�}��\�c(�A���t���h�E���C�N�����w������)�������A�X�E�Q�Q�`24�}��\�c(�c���E����x�v��C������ψ�)�Ɖ�k�A�X�E�Q�X�����R�~���j�P�\
�@�P�O�E�P�Q�`�P�X�@�t�����X���Y�}��\�c(�c���|�[���E�����������Lj�)�������A�P�O�E�P�R�`�P�S�A�P�W�}��\�c(�c���E����x�v��C������ψ�)�Ɖ�k�A�P�O�E�Q�O�����R�~���j�P�\
�@�P�P�E�P�T�@�t�����X�A�C�^���A�����Y�}�A���R�̖��Ȃǂŋ����錾
�@12�E�P�S�@�X�y�C���E�C�^���A�����Y�}���ẪX�y�C���l���Ƃ̍��ۘA�яW��(���[�})�ɐ���x�v��C������ψ��炪�o��
�@�P�X�V�U�N
�@2�E�S�`�W�@�t�����X���Y�}�������ɓ}��\�c(�c���E�������d��C������ψ�)���o��
�@3�E�Q�V�`�R�P�@�X�y�C�����Y�}��\�c(�c���E�J���������L��)�����A3�E�Q�W�`�Q�X�}��\�c(�c���E�{�{�ψ���)�Ɖ�k�A�R�E�R�P���������\
�@�S�E�S�`�P�O�@�t�����X���Y�}�}���V�F���L�������A�S�E�T�{�{�ψ����ƃ}���V�F���L������k�A�S�E�P�O���������\
�@�S�E�Q�V�@�s�j�N�O�_���u�Ȋw�I�Љ��`�Ǝ������\�}���N�X�E�G���Q���X�����v�́u�Ԋ��v�A�ڊJ�n(�`�T�E�W)
�@�U�E�Q�X�`�R�O�@���[���b�p���Y�}�E�J���ғ}��c(�x������)
�@7�E�Q�W�`�R�O�@���O��Վ��}���A�u�����v���A�u���R�Ɩ����`�̐錾�v�Ȃǂ��̑�
�@�@(�{�n��)�A�R�}���܂ރ��[���b�p�̂��ׂĂ̋��Y�}���A�V�O�N��ɁA�v�����^���A�ƍٗ��_�͌�肾�����ƁA���R�Ƃ��̕����錾�������ƂƂ̊֘A(�H)�B���{���Y�}�����́A���������A�v�����^���A�ƍف��v�����^���A�[�g�̎������J���ҊK���̌��͂Ɩ��ύX���āA�B���E�������B�u���R�Ɩ����`�̐錾�v�́A���[���E�W���|�l�R�~���j�Y�����ے�������e�ƂȂ����B
�@�w�ғ}������O�O�D�y�w�@��w�����́A�s�j�u�����v�_���ɂ������āA�����܂Łu�ƍفv�Ƃ����ꂪ�������Ƃ���w�p�_���\�����B����ɂ������āA���{���Y�}�́A���̘_���E�������킹�āA�u�}������}�O�ɂ����������v�K���ᔽ�Ƃ��āA�ނ����₵�A���������B
�@�P�X�V�V�N
�@�P�E�P�O�`�P�X�@�}��\�c(�c���E�s�j���L�ǒ�)�A�C�^���A�K��A�P�E�P�O�`�P�P�C�^���A���Y�}��\�c(�c���E�W�F�����g�K�E�L�A�������e�w������)�Ɖ�k�A�P�E�Q�O���������\
�@�@(�{�n��)�A���̂悤�������R�~���j�P�A���������̔��\�́A�P�X�V�V�N���Ō�ł���B�Ȍ�A���̋����`���͂Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@�R�E�Q�`�R�@�C�^���A�A�t�����X�A�X�y�C���O�}���L���̉�k(�}�h���[�h)�A�����������\
�@�P�P�E�V�@������Y�_���u�O�q�}�̑g�D�����̐����v���u�Ԋ��v�]�_���W�łɌf��
�@�@(�{�n��)�A���̘_���́A�}�����ɂ���P��ڂ̊w�ғ}���E�c���x�v���ᔻ�������B�ނ́A�P�X�V�U�N�V���A�u�����[���v�ɁA�t�����X���Y�}�̃f�����F���W�F���_���Љ���R�����L���w���܂��܂ȁu�X���v���}�����ŋ������錠���x�\�����B����ɂ������āA�}�����́A�ނ��ʂɓ}���ᔻ�E�l��������B�ނ��A���̎�����̍���ɋ������Ȃ��̂ŁA�}�����́A���̓��e�ɂ�������u������Y�v���̔ᔻ�_���\�����B�u������Y�v�Ƃ́A�����v�A��c�k��Y��S�l�������M�̃y���l�[���ł���B���̌���A�P�X�V�V�N�A�ނ́A�G���_���w��i���v���ƑO�q�}�g�D�_�x���f�ڂ����B�����ŁA�ނ́A���[���R�~���j�Y���̗��_���e�A�X��������ɏڂ����A�m��I�ɏЉ���B
�@�P�X�V�W�N
�@�S�E�P�X�`�Q�R�@�X�y�C�����Y�}��X����ɓ}��\�c(�c���E�^�J�t����C������ψ�)���o��
�@�P�Q�E�T�@�w�O�q�x����N�ꌎ���ɕs�j�N�O�_���u�Ȋw�I�Љ��`���w������`�x���\�c�����_�̔ᔻ�I�����v���\(����W�����_�Ȃ�)
�@�@(�{�n��)�A����́A��Q��ڂ̓c���x�v���ᔻ�������B�ނ��A�P�X�V�W�N�R���A��L�G���_�����܂߂��w��i���v���Ƒ����I�Љ��`�x(�匎���X)���o�ł����s�ׂƒ������e�ɂ�������A�c���x�v���ᔻ��L�����y�[���̊J�n�ł���B����́A�����ɁA���{���Y�}�ɂ�郆�[���R�~���j�Y���ᔻ�A�Ƃ��ɁA�C�^���A�A�t�����X�A�X�y�C���R���Y�}��Democratic Centralism�����������������ɂ�������S�ʔے�Ƃ������i�����������Ă����B
�@�P�X�V�X�N
�@�R�E�R�O�`�S�E�R�@�C�^���A���Y�}���܉���ɓ}��\�c(�c���E���ψ���)���o��
�@5�E9�`�P�R�@�t�����X���Y�}���O����ɓ}��\�c(�c���E���㕛�ψ���)���o��
�@�P�X�W�P�N
�@�V�E�Q�W�`�W�E�P�@�X�y�C�����Y�}���Z����ɓ}��\�c(�c���E����x�v���ψ���)���o��
�@�P�Q�E�Q�X�@�C�^���A���Y�}�A�u�\���v���Ɏn�܂����Љ��`�v�́u���i�͂������͂������v�Ƃ̌��c���\
�@�P�X�W�Q�N
�@�P�E�R�P�`2�E�P�V�@���ψ����A���A�ɁA�m���E�F�[�A�f���}�[�N��K��B�Q�E�R�`�V�t�����X���Y�}���l����ɏo�ȁA�Q�E�P�O�C�^���A���Y�}�x�������O�G�����L���Ɖ�k�A�������\�������Ȃ�
�@�P�Q�E�X�@�{�{�c���A�w���{���Y�}�̘Z�\�N�x�\�A�P�Q�E�Q�T�P�s�{�̏��Ŕ��s
�@�@(�{�n��)�A���̓��e�ɂ́A�i�P�j�Z�S���ォ��P�X�T�W�N�O��ɂ�����A����W��������̈�E�Ƃ��Ă̎��R��`�E���U��`�ᔻ�A���h�����ᔻ�ƁA�i�Q�j�P�X�V�W�N�O��ɂ����閯��W�����ᔻ�҂����ւ̔��ᔻ���������B���̗��҂��A����W������Ηi��̃e�[�}�Ō��������̂��A��̏�c�E�s�j����Ɓu���Ȕᔻ���v���\�����ł���B��c�E�s�j����́A�P�Q���܂ł̊Ԃɍs���A�u��l�̔��Ȃ��튲�œ��c����A���F���ꂽ�͍̂�N(�W�Q�N)�\�v(��Ԋ��咣��W�R�E�X�E�Q�T)�ł������B���ꂩ��W�J����A�����ψ���́A�w�O�q�x�W�R�N�W�����ŁA��c�E�s�j����Ȕᔻ��������\�����B
�@�P�X�W�R�N
�@1�E�S�`�P�P�@�X�y�C�����Y�}��\�c(�c���E�J���������s�ψ�)�����A�P�E�T�A�W�A�P�O�{�{�c���Ɖ�k�A�P�E�P�P�X�y�C�����Y�}�Ƃ���k�ɂ��Ă̐V�����\
�@�Q�E�Q�V�`�R�E�P�P�@�}��\�c(�c���E����x�v���ψ���)�A�ɋ��Y�}���o�Ȃ̂��߃C�^���A��K��
�@�P�X�W�S�N
�@�Q�E�Q�X�@�C�^���A���Y�}�̃x�������O�G�����L���A�X�y�C�����Y�}�ւ̘A�т�\��
�@�R�E�V�@���A�X�y�C�����Y�}�A���}�W���W�̋�������
�@�W�E�Q�T�`�Q�X�@�t�����X���Y�}��\�c(�c���E�}�N�V���E�O�����b�c�����Lj��E���L)�������A�W�E�Q�V�}��\�c(�c���E���ؗm���ۈψ���ӔC��)����k
�@�P�X�W�T�N
�@�Q�E�P�S�`�P�W�@�}��\�c(�c���E���ؗm��C������ψ�)�A�t�����X���Y�}���܉���ɏo�ȁA�Q�E�P�Q�C�^���A���Y�}�̃A���b�T���h���E�i�b�^���L�������k
�@�X�E�P�T�`�Q�S�@�}��\�c(�c���E���q���L�ǒ�)�A�C�^���A���Y�}�̃A���b�T���h���E�i�b�^���L�����
�@�U�A�R�̋��Y�}�ɂ��Democratic Centralism�����o��
�@�@�@�@�R�~���e�����^���Y��`�^���̃��[���b�p�ɂ�����I��
�@�C�^���A���Y�}�\�\��]��
�@��㎵�Z�N�A�}���Łu�v�����^���A�ƍفv�̗p�����������B
�@��㔪��N�A�u�\���v���Ɏn�܂����Љ��`�v�́u���i�͂������͂������v�Ƃ̌��c���\
�@��㔪�Z�N�A�u���̂��т��ƂɌ��肳��鑽���h�̗���Ƃ͈قȂ闧������R����`�ɂ����Ă��ێ����A�咣���錠���v�̋K����s���B
�@��㔪��N�A��\������A�����`�I�����W������������A���h�֎~�K����폜�����B
�@�����N�A���\����A��������}�ɓ]�������B���N�\�A�����h�����Y��`�Č��}�����������B
�@����Z�N�A���I���Œ������h�A���������a�������B��������}���D�ꁓ�A���Y��`�Č��}���D�Z���̓��[���ŁA�u�I���[�u�̖v�S�̂ł́A�O���c�Ȃ��l�������B
�@���㎵�N�A����}���ɂ�����}�����͘Z�\�����l�ŁA���̂��������}�����D�܁����߂�B
�@�t�����X���Y�}�\�\�����`�I�����W��������
�@��㎵�Z�N�A���\�����Ţ�v�����^���A�ƍ٣���_����������B
�@��㔪�ܔN�A���\�܉�����A�}�O�}�X�R�~�ł̔ᔻ�I�ӌ����\���K������Ȃ��Ȃ�B
�@����l�N�A���\������ŁA�����`�I�����W��������������B�^����O�Z�l�A���Ό\��l�A�����l�\�l�l�Ƃ����̌����ʂ������B
�@����Z�N�A���\�����ŁA�u�~���^�V�I���v�i�ω��j����A�}���v��}��B�@�֎��u���}�j�e�v�́A���풼��͎l�Z�����������B�������A�Z�\�N�ォ�甪�\�N��܂ŁA�\�ܖ����A���㎵�N�ł́A�Z�����A��Z�Z��N�͎l���ܐ畔�Ɍ������Ă���B
�@��Z�Z�Z�N�O���A��O�Z����ŁA��w�̉��v��i�߂邽�߂ɁA���̃e�L�X�g�����肵�A����ւ̓}���̈ӌ��\���͎O���l�ȏ�ɏ�����B
�@��Z�Z��N�Z���A���I�����[���́A�l�D��ꁓ�ł���A����͈��㎵�N���I�����[����.�����̔����Ɍ��������B�t�����X���@�c�Ȃ́A�O�܋c�Ȃ���A���c�ȂɌ������B�����̌��ʂ́A�u���y�����v�̉e�����������Ƃ͂����A�t�����X���Y�}�j��ő�̔s�k�������B
�@��Z�Z�O�N�l���A��O�\�����ŁA�}�j�㏉�߂đΈĂ���o����A�l�\�܁��̎x�����B�}���v�h���嗬�����A���͓�h�ŁA�}���v�ւً̈c��o�h�ł���B�}�����́A��㎵��N���\�Z���l�A����Z�N��\�����l�A��Z�Z�O�N�\�O���l�ւƁA��т����}�����ނ𑱂��Ă���B
�@�X�y�C�����Y�}�\�\�R����
�@��㔪�O�N�A�e�\�h�A�J�������h�A���[���R�~���j�Y����}�������`�̓O�ꉻ�ɂ܂Ő[�������邱�Ƃ��咣����V����h�ɎO�����
�@��㔪��N�A���̌�̍Č������̒��őI���u���b�N�Ƃ��Ă̓��ꍶ������������B���̔N�̑��I���œ��ꍶ���͋�D��O�����l�������B����O�N���I���ł͋�D�����l�������B
�@�����N�A�����`�I�����W��������������B
�@��Z�Z�Z�N�O���A���I���ŁA���ꍶ���͈���Z�N�̓�\��c�Ȃ��甪�c�ȂɌ�ށA��s�����B
�ȏ��@�@����MENU�ɖ߂�
�@(�֘A�t�@�C��)
�@�@�@�@�w�Ǔ��E��c�k��Y�@���̗��j�I���߁x�}������]�o���Ɍ����鑽�d�l�i��
�@�@�@�@�w�u���v���_���j�v�Ɋւ���s�j�N�O�u���Ȕᔻ���v�x�ꎟ�����W�i�P�j
�@�@�@�@�Γ������w��c�s�j�u���v���_���j�v�o�Ōo�܁x�莆�R�ʂƏ��]
�@�@�@�@�w��c�k��Y���ψ����̑��d�l�i���x��c�E�s�j���⎖���̐^��
�@�@�@�@�w�s�j�N�O�̋{�{�����ᔻ�x�k�閧�l��c�E�s�j���⎖���̐^��
�@�@�@�@�w�j�̑S�ʉ���ɂ�����s�j�N�O�̎l�ʑ��x�\�����v�_�҂Ƃ����v�z�E���_�I�o��