
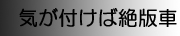
やっぱ2ストでしょ!
フォーゲル(QB50)
フォーゲルのクラッチを交換する
初稿:2006.5.22(作業日:2006.5.4)
※私、まったくの「ど素人」なので、用語の使い方とかパーツの名前とか間違って使っている可能性があります。ウソは書いていないつもりですけど、書いてあることを鵜呑みにしないでください。
我が家へフォーゲルがやって来た時のオドメータは、およそ13,000km。新車時からどの時点でどの程度のエンジンに換装されたのかはわかりませんが、私が乗るようになってから(スプロケットを替えてから)、クラッチの滑りが感じられるようになりました。
そこで冬の間にクラッチを交換しようとパーツを買っていたんですが、寒いガレージで作業したくないという甘えが出まして、十三墓峠の雪も消えたゴールデンウィークの最中、バイク通勤を再開しようか、という数日前になってようやく作業に取りかかりました。
今回新品で用意したパーツは、クランクケースカバーのガスケットとクラッチのフリクションプレート。クラッチプレート(金属性のやつ)はまだ持つだろう、ということで今回は交換を見送り。
各々の部品番号は次のとおり。
| クランクケースカバーガスケット | 3MT-15451-00 | 数量1 |
| フリクションプレート | 4EU-16321-00 | 数量3 |
※これはGT/GR系エンジン用のパーツナンバーです。ポッケ/フォーゲル用ではありませんので、ご注意を。しかも、パーツナンバーは突然変わってしまうことがあります。明日には役に立たなくなるかも。
 | ガスケットとフリクションプレート |
フリクションプレートの番号が4EUで始まっていますから、TZR50Rと共通部品です。っていうか、TZMも一緒。TZM用のフリクションプレートなら在庫してたのに。ただ、GT/GRはプレート3枚なんですが、TZR/TZMは4枚必要です。まあ、二十年以上を経たエンジンの、大事なパーツが共通部品として現在でも使用されているというのは非常にありがたいことで、メーカーさんにはいつまでも部品を供給していただきたいなあ、と切に願っております。
さて、実際の作業です。作業そのものは至って簡単。ど素人の私でもトラブルなく交換できました。
まずはエンジンを暖気して、ミッションオイルを抜きやすくします。
オイルが温まった頃を見計らって、エンジン下のドレンよりミッションオイルを抜きます。
 |
画像中央の大きなボルトがミッションオイルを
抜くためのドレンボルト。 |
オイルが抜けきったところでエンジン右側のクランクケースカバーを外します。カバー前方にあるオイルポンプカバーを外す必要はありません。が、オイルポンプに繋がっているワイヤーとパイプは結構邪魔な存在です。これが抜けたりしないように注意。また、カバーのネジが固着している時は無理に回そうとせず(何故かネジの頭が軟らかくてなめやすい)、浸透剤やショックドライバーを使って慎重に外してください。外す時にネジの頭をなめますと、組み付ける時にネジにトルクが掛からなくなってしまいます。
 | クランクケースカバーを開けたところ。 |
コンプレッションスプリングを留めている4本のボルトを外し、プレッシャープレートを外しますと、お目当てのクラッチプレートが出現します。フリクションプレートとクラッチプレートが交互に並んでいます。これを全部外します。
 |
外したパーツ。
あれ?クッションリグが2本しかないぞ。
サービスマニュアルの絵には3本あるのに。
しかも相当劣化している。次回は全部交換ですね。 |
 |
フリクションプレートの
新品(上)と使い古しの比較。
新品でも山はこの程度。 |
外した時の逆の手順でパーツを組み込みます。念のため順番を。
奥から、クッションリング→フリクションプレート→クラッチプレート→クッションリング→フリクションプレート→クラッチプレート→クッションリング→フリクションプレート、です。
プレッシャープレートを組み込んで、はい、完成。じゃなくて、クランクケースカバーを組み付けて完成、ですね。
 |
ガスケットを折り曲げたり傷つけたりしないように
クランクケースカバーを組み付けます。 |
大事なことを忘れていました。ドレンボルトをしっかり締めたことを確認してからミッションオイルを入れなければ。サービスマニュアルではヤマハギヤオイル10W30が指定となっていますが、粘度さえ合えば4サイクル用オイルなら何だっていいようですので、CARAに使ったエンジンオイルの残りを注入。ただし、エンジンオイルとミッション/クラッチオイルに求められる性能は異なるものがありますので、「何だっていい」を真に受けてミッション壊さないようにしてください。私もたまたま手持ちのオイルがなくて、やむなく使ったオイルですので。
オイルの指定注入量は500ccで許容範囲は+50cc、−0ccです。つまり、550ccまでは入れてもいいけど、500cc未満ではまずい、ということですね。
最後にクラッチケーブルの遊びを調整します。(ここから先は画像がありません。手がオイルまみれになったので。)
まずはプッシュロッドのクリアランスを調整します。左ジェネレーターカバーの「YAMAHA」のロゴの右側に小さな突起があります。この突起の中にクリアランスを調整するスクリューがあります。その前に、クラッチワイヤーのアジャストボルトを緩めて、遊びを大きくしておきます。
ジェネレーターカバーを外し(下の画像で解るとおり、チェンジペダルを先に外さないとカバーは外れません)、アジャストスクリューを留めているボルトを緩め、スクリューが固くなる位置まで締め込みます。が、どこまで行っても固くなりません。おかしいなあ。ようやく固くなった位置では、ボルトが締まらないくらいスクリューが奥へ入ってしまいました。その位置でクラッチレバーを握っても、クラッチが切れている感じがしません。一体どうなっているんだ、と、チェンジペダルケースカバーを外してみたところ、クラッチワイヤーの動きをプッシュロッドへ伝えるカムがチェーンのオイルや埃でドロドロ。アジャストスクリューの先がプッシュロッドの頭にうまくヒットしていませんでした。で、ここら辺を入念に掃除。カム周りが綺麗になったところで再度調整。今度はうまく行きました。スクリューを締め込んで固くなった位置から1/4回転戻して調整終了。最後にクラッチレバーの遊びをアジャストボルトで調整します。
 |
ジェネレーターカバーの右側の小さな突起の中に
アジャストスクリューがあります。
調整前にチェンジペダルケースカバーの裏側を
掃除した方がいいです。っていうか、掃除必須。 |
とりあえず交換後のインプレッション。交換前の微妙に滑っている感じはなくなりました。ただ、ギア抜けが結構起こるようになりました。これは多分、ミッションオイルに原因があると思われます。近いうちにTZRのミッションオイルを交換しなければいけないので、その時に合わせてまともなオイルに交換することにしよう。
さて、クラッチはいつまで持ってくれるのだろうか。現在のオドメーター約14,500km。
![]()
![]()






