ドストエフスキー読書日誌から「死の家の記録」(1/3)
【作品の背景と内容】
ドストエフスキーは、一八四七年春頃から社会主義の思想家ペトラシェフスキーのサークルに参加した。そのため、サークルの同志とともにロシア官憲に逮捕された(ペトラシェフスキー事件)。銃殺刑を宣告されて、刑場で刑が執行される直前に「恩赦」が言い渡され(このように受刑者を極限状態に追い込むのは、当時のロシアの思想犯への「見せしめ」である)、シベリア流刑となった。監獄へ向かう途中、慈悲深い婦人たちに一冊の聖書を贈られ、それを、刑期中、唯一つ持ち込むことが許された書物として胸に抱いて、四年間、オムスクの監獄で服役することになる。その際の獄中での経験と見聞を記録したのが「死の家の記録」である。ただし、この記録は、検閲を逃れるため、ある貴族の徒刑囚の手記(フィクション)という形をとっている。
この作品に物語性はなく、監獄の内部の様子と日常生活、若干の出来事、囚人たちの身の上話の数々、囚人たちの人間性についてのドストエフスキーの観察といった事柄から成り立っている。(工藤精一郎・訳(新潮文庫)による)
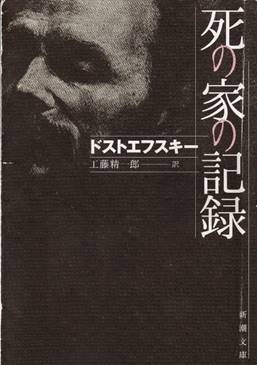
【様々な人間類型観察】
「死の家の記録」は、暗澹たる作品ではあるが、読後、二つのことが強く印象に残った。一つは、囚人たちの人間性について観察したことを語るドストエフスキーの活き活きした語り口である。この作品の中には、後年の「悪霊」や「カラマーゾフの兄弟」に登場する人物を彷彿とさせるような人間も含め、様々な人間類型が登場するが、その中でも、(一)人間離れした強靭な肉体や精神を持った人物、(二)純粋で優しい青年、(三)狡猾で卑怯な貴族の囚人、が印象的である。小川榮太郎[1]氏の共感に満ちた美しい表現も借りつつ、それらの人物を紹介しよう。
【強靭な野人たち】
まず、ドストエフスキーは、人間離れした屈強な肉体や精神力を持つ人間たちに目を見張る。「目の前に人間大の化け物のような大蜘蛛を見ているような」ガージンという殺人犯や、「逃亡兵あがりの札つきの強盗」オルロフのような人物が紹介される。彼はとりわけオルロフの異常な豪胆さに驚嘆している。過酷な鞭打ちの刑を執行されて「背中はすっかり腫れあがって血が滲み、紫色になって」意識朦朧とした状態で囚人たちの大部屋に運ばれてきたオルロフは、あくる日にはすっかり意識を回復させた。ドストエフスキーは言う:−
私は絶対の自信をもって言い切れるが、私の生涯を通じて、彼ほどの強い鉄のような性格を持った男に一度も会ったことがない。…(中略)…明らかに気力が肉体をすっかり抑えていた。このような人間は自分をどこまでも抑制することができ、あらゆる苦しみや刑罰をものともせず、世の何物をも恐れていないことは明らかだった…[2]
この後もしばらく、オルロフに対する驚嘆と畏敬の言葉が連ねられている。それはまさしく、「犯罪者の描写ではなく、或る強靭な人格への全きオマージュに他ならない」[3]のだ。犯した罪に相当する苛酷な罰を受けることによって、こうした強靭な精神の持ち主たちの魂には、健全な浄化が生じている。ドストエフスキーはそう感じたようである。それを敷衍して、小川榮太郎氏は、次のように述べる:−
それにしても、そもそも人間は何故罪に陥り、そしてその罪障のために「臓腑がひきちぎれる」ほど「叩きのめされ」なければならないのか(近藤注:何百回もの鞭打ちのような苛酷な罰を受けなければならないのか、の意)。…(中略)…それは、健全なものだ。彼らは、己の罪と卑劣をはっきりと知っている。知っているがゆゑに、彼らを支えているのは、例えば「外見上、驚かない」という強者のモラルを生きることだけなのである。強がってゐなければ、彼らは、外側から容赦なく襲ひかかる侮蔑と、内側から来る自尊心の崩壊に、耐へられない。
モーゼの十戒に決定的に牴触した人たちだ。が、現代人にしばしば見受けられる、罪の意識のかけらすらない自己正当化といふ心の病気は、ただ一人を除けば(近藤注:後述の貴族出の囚人Aのことを指す)、ここには見られない。精神の不在は、見られない。寧ろ、裏返された健全な道徳が、ここにはある。[4]
【心優しい青年】
獄内には、囚人とはいえ、心素直で純真な若者もいた。例えばダッタン人の若者、アレイの純真さにドストエフスキーは入獄すぐに気づき、二人は仲良くなった。ロシア語の読み書きができないアレイに、ドストエフスキーは聖書を教科書にして教えてやっていた。こうした場面を読むと、この暗澹たる獄内で、そこだけ陽光が差し込んでいる様に感じられる。ドストエフスキーは、「どこに、いまごろはいるだろう、私の善良な、可愛い、可愛いアレイ!」[5]と幾度となくアレイを思い出している。小川氏は次のように表現する:−
さうかと思へば、ダッタン人の青年アレイを描く時のドストエフスキーは、殆ど夢中になって恋人を描写するかのようだ。[6]
【冷笑主義に凝り固まった貴族:現代の写し鏡】
ドストエフスキーは獄中で、純真なアレイと正反対に「根性の腐った卑怯な貴族出の」囚人Aと出会う。Aは、監獄監督官である少佐のスパイ役を務め、囚人たちの動静を少佐に密告していた。Aは、自分の欲望を満たすために、多くの人を欺き人の命を売ったりした罪で十年のシベリア流刑となっているが、罪の意識のかけらも無く「徒刑囚になったからには、卑劣なことをしても構わないし、恥ずかしくもないわけだ」と、自己を正当化していた。ドストエフスキーはAを嫌悪してこう述べる:−
これは人間の肉体的な一面が、内的にいかなる規準にも、いかなる法則にも抑えられない場合、どこまで堕落し得るものであるか、ということの一例である。そして、彼のいつもせせら笑っているような薄笑いを見ることが、わたしにはどれほど忌まわしかったことか。…(中略)…そのうえ彼が、抜け目なく小利口で、美男子で、少しは教養もあり、それに才能もあったことを考えていただきたい。ああいやだ、社会にこんな人間がいるくらいなら、火事でもあった方がまだましだ。疫病や飢餓の方がまだいい![7]
小川氏は、ドストエフスキーの時代よりさらに信仰や道徳に無関心になった現代には、貴族Aのような冷笑主義の「成功者」がはびこっていると、次のように述べるが、私も満腔から共感する。曰く:−
堕落した貴族『A…フ』は、スタヴローギン(近藤注:小説「悪霊」の主人公)とは違ひ、真っ直ぐ現代の病理にまで直進する。合理主義、人権イデオロギー、経済原則、快楽至上主義などに、信仰と良心の問題を還元しようとする近代原理そのものが、「内部になんらの規準、なんらの法則にも抑制されなかった場合」の社会全体への応用であるのは明白であろう。事実、良心といふ内面の声を喪った現代社会といふ「牢獄」の中で、私たちは、何と悲しいまでに、オルロフやアレイよりも、『A…フ』にこそ似てしまったことだらう。魂の問題を引き受けない人間論や政治経済論が溢れ返ってゐることだらう。[8]
(次回へ続く)