ドストエフスキー読書日誌から「死の家の記録」(2/3)
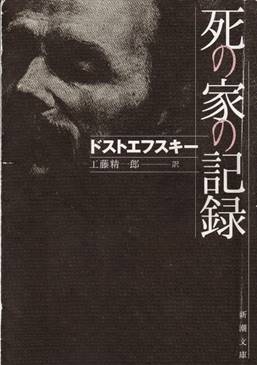
(前回からの続き)
【庶民体験から得たもの】
さて、「死の家の記録」を読んで印象に残ったことの二つ目は、ドストエフスキーの「庶民体験」である。彼は、ロシアの庶民が貴族階級や上流階級の人間とは決して心を許して親しくなることはないという冷厳な現実をいやというほど思い知らされたが、しかしまた、庶民は貴族階級や上流階級の人間が失っている美徳を備えているのを心に沁みて感じたのだった。
このような生身の民衆と直接長期間に亘って触れ合う経験は、他のロシアの文豪はしていない。同時代のトルストイもツルゲーネフも、文豪たちはみな「貴族」「旦那」の立場からしか庶民と触れ合うことはなかった。この経験は、ドストエフスキーの後の創作に決定的な影響をもたらした。「罪と罰」「白痴」「悪霊」「未成年」「カラマーゾフの兄弟」といった傑作群に登場する人物の異様な心の屈折や強靭さや人間表現の奥深さには、この経験が色濃く反映されている。
ドストエフスキーが庶民階級と貴族・上流階級との「心の断絶」の根深さを痛感させられる経験は、随所に描かれている。例えばこんな調子である:−
…新しく監獄に来た者がすべて、来て二時間後には、…(中略)…みんなと顔なじみになり、そしてみんなが彼を仲間と考える。ところが、旦那とか、貴族となると、そうはいかない。たとえどんなに正直で、善良で、聡明であっても、何年もの間、みんなによってたかって憎悪され、軽蔑されなければならないのである。理解されないし、何よりも――信じられない。彼はみんなの友だちでもないし、仲間でもない。…(中略)…この疎外がときに囚人たちの側から全く悪意なしに、ただ無意識になされることがある。おれたちの仲間の人間じゃない、というただそれだけである。[1](傍点はドストエフスキー)
獄内で「旦那」として疎外されていたドストエフスキーだが、彼は庶民の美徳を見出した経験も様々語っている。例えば、獄内で囚人たちによる素人芝居が演じられる場面がある。芝居が始まるとき、皆が、「わたし(ドストエフスキー)に芝居をほめてもらいたいと思って、卑屈な気持ちなど少しも持たずに、わたしを一番いい席へ通した」[2]のである。ドストエフスキーは鋭敏に、囚人たちには(つまりはロシアの民衆には)公正な判断と自分たちの価値に対する正しい感情が存在することに気づく。曰く:−
「おまえに一番いい席をやるのは、…(中略)…芝居ってものを尊敬しているからだ。だから、客の区別はおれたちが自分でやらなきゃならねえんだ。」こうした考えには真の高潔な誇りが、どれほどこもっているか!それは金銭に対する尊敬ではない。自分自身に対する尊敬である。[3]
わが国の民衆の最も高い、そして最も鮮明な特徴――それは公正の感情とその渇望である。…(中略)…上っ面の借り物の皮をひん剥いて、本当の中味をもう少し注意して、もう少し近づいて、いっさいの偏見を捨てて観察しさえすれば、――見る目のある者は、民衆の中に予想もしなかったようなものを見出すはずである。わが国の賢人たちが民衆に教え得ることは少ない。私は確信をもって断言するが――その逆である。賢人たちの方こそ、まだまだ民衆に学ばなければならないことが多いのである。[4]
(次回へ続く)