ドストエフスキー読書日誌から「死の家の記録」(3/3)
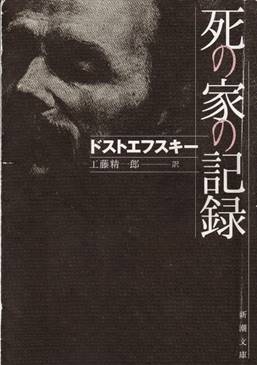
(前回からの続き)
【信仰の蘇生】
四年間の獄中経験からドストエフスキーが得たもので、「死の家の記録」に明確に描かれていない重要なものがある。それは、ドストエフスキーの内なる変化、すなわち「炎で焼き鍛えられた鋼のような信仰の蘇生」である。
ペトラシェフスキー事件以前のドストエフスキーは、空想的社会主義に共感を抱く、正義感の強い若きインテリ、典型的なロシアの良心的インテリゲンチャであった。唯物史観は人を無神論者に仕立て上げる。社会主義のような無神論的ヒューマニズムは、社会的不平等や不条理が現世に存在することを以て神を否定し、社会制度の改革で不平等や不条理を解決しようとする思想である。無神論的ヒューマニズムは、神を人間に置き換えるが、神なき人間中心主義、敬虔な心を喪失した人間中心主義は奢り高ぶり、「何でも許される」というニヒリズム(虚無主義)に容易に転落する。そして「何でも許される」ニヒリズムは、政治的には権謀術数の末に少数エリートによる非人間的な独裁体制に向かう。そのことは、滅亡したソ連や現在の中共の共産主義の運命を振り返れば明らかである。しかしドストエフスキーの当時において、無神論的ヒューマニズムや社会主義は、神への信仰に代わる魅力ある思想であり、多くの若者を引き付けたのである。ドストエフスキーもまた「時代の子」であった。無神論的心情、神の存在を疑う気持ちは、生涯ドストエフスキーから消えなかった。
だが、苦役と孤独の獄中生活で、様々な囚人たちの人間模様を見聞するうちに、ドストエフスキーは、人間は無神論的ヒューマニズムが想定するような合理的存在ではないことを悟らざるを得なかった。同時に彼は「流刑生活の言語を絶する辛い体験を通して、苦悩による自己浄化について確信した。[1]」そして苦悩が自己浄化をもたらしたのは、獄中に持ち込んだ聖書の熟読によってであった。苦悩の浄火をくぐり抜け、「炎で焼き鍛えられた鋼のような信仰の蘇生」を経たドストエフスキーの目には、無神論的ヒューマニズムの限界は明らかだった。かくして彼の心の内には、「神の否定者」と「神を渇望する者」とが葛藤するようになる。
懲役の終わった年に、ドストエフスキーはある婦人に宛てた手紙でこう書いている:-
わたし自身が経験し、それを感じぬいたから申し上げるのですが、そうした瞬間に「干からびた草」のように信仰を渇望し、それを見出すのは、もともと不幸の中でこそ真実が明らかになるからなのです。
自分自身のことを申すなら、わたしは世紀の子であり、今日に至るまで、いや、棺の蓋が閉ざされる時まで(わたしにはそれがわかっているのです)、不信と懐疑の子です。信じたいというこの渇望が、どれほど恐ろしい苦しみに値したか、また現に値しているかわからないほどですが、反対の論拠が多くなればなるほど、ますますその渇望は強くなるのです。
それでも神は時折は、わたしがまったく安らかな気持ちでいられるような瞬間を授けて下さいます。そんな時わたしは人を愛し、他人からも愛されるのを見出しますし、まさにそういう瞬間にわたしは自己の内に信仰のシンボルを作り上げたのですが、そこではわたしにとってすべてが明快で、神聖なのです。そのシンボルとは極めて簡単なもので、こうなのです。つまり、キリスト以上に美しい、深い、共感できる、合理的な、男性的な、完璧なものは何一つ存在しない、いや、存在しないだけではく、熱烈な愛を込めて言うなら、存在するはずもない、ということを信じるのです。
それだけではなく、仮に誰かが、キリストは真理の外にあることをわたしに証明し、また、キリストが真理の外にあることが実際であったとしても、わたしとしては、真理と共にあるよりもキリストと共にとどまる方が望ましいでしょう。[2]
後のドストエフスキーの作品群では、彼自身の内なる「神の否定者」(不信と懐疑の子、神に対し反対の論拠を与えようとする衝動)と「神の肯定者」(信仰を渇望する者、キリストが真理の外にあっても共にとどまる者)とが鋭く対立する。それは、まさしくドストエフスキーの耐え難い心の葛藤を象徴しているのだ。
「白痴」のイポリット、「悪霊」のスタヴローギン、「罪と罰」のラスコーリニコフ、「カラマーゾフの兄弟」の次男イワンは、ドストエフスキーの内なる「無信仰と懐疑の子」を仮託された人物たちである。一方、「白痴」のムイシュキン公爵、「悪霊」のチホン僧正、「カラマーゾフの兄弟」の三男アリョーシャやゾシマ長老は、ドストエフスキーの内なる「信仰を渇望する者」を仮託された人物たちである。
* * *
いよいよ出獄する最後の場面を「そうだ、さようなら! 自由、新しい生活、死よりの復活…何という素晴らしい瞬間であろう!」と結んだドストエフスキーの生活は、その後も穏やかなものではなかった。が、「死の家の記録」に描かれた経験は、確かに、後のドストエフスキーの傑作群を生み出す母体となったのである。
令和二(二〇二〇)年四月三日