|
真夜中の脳みそ
詩集「半熟卵」(Update:2001.
9.16.)
コラム「午前3時の天気予報」(Update:2004.
8.21.)
AIBO日記(Update:2003.11. 3.)
アルバム(Update:2003.1.31.)
「紺野」とは?(Update:2004.
8.21.)
Links(Update:2002.10.20.)
更新ログ(Update:2004. 8.21.)
Mail Me !
|
第19回 「奥村土牛」氏の作品に触れて
私は絵を鑑賞するのが好きである。洋画、日本画、版画、油彩、水彩等々特に対象を問わず、ではあるが、まったく無目的に漫然と観ているわけでもない。しかし、自分自身で「これは好き」と思ったものであればなんでもかんでも観るようにはしている。よって、ルネッサンス以前の宗教画から現代アートまでできるだけ幅広く観ている。できるだけ見聞を広く持っていたい、できるだけ偏らずにいたい、すばらしいものを少しでもたくさん見知っておきたい、という欲求がある。でも思い直してみると、洋画よりも日本画を観る機会が少なかったような気がしている。
私が日本画家として名前を知っているのは、東山魁夷氏、横山大観氏、上村松園氏、上村松篁氏ぐらいなものであった。ここでとりあげる奥村土牛氏(「とぎゅう」と読む)に関しては、文化勲章を授与された方でありながら、日本美術院名誉理事長となられた方でありながら、私はまったく知らなかった。自分の見聞の狭さをつくづく感じる(今思い起こすと美術の教科書に実はしかり載っていたのではないかと思ってしまうような、まさに近代日本画の「巨星」なのである)。知らなかった自分が実にお恥ずかしい。
自分自身不思議で仕方がないのであるが、たまたま勤労感謝の日を含む連休に、長野県内を無目的に車を走らせていると「奥村土牛記念美術館」という看板が目に入り、なんとなく入ってみようという気になってついふらりと寄ってみることにした(山が基本的に好きなのでけっこう山方面に無目的に車を走らせることはままある。そこに温泉でもあれば言うことなし、である。嗚呼、日本人だなぁ)。そこで初めて日本画家、奥村土牛氏を知ったのであった。まさに「偶然」である(このときの私の思考:「奥村土牛記念美術館」→「奥村土牛」って誰だろう→名前からして日本画っぽいな→これだけ大きな看板が出ている、しかも「記念」ということは実は有名な人なのではないだろうか→なぜこのようなところに美術館が→ゆかりのとか生まれのとかそういうものだろう→日本画はあまり観てないなぁ→観ておこうか、通り過ぎようか→時間に余裕はあるし、寄ってみよう)。
「奥村土牛記念美術館」には奥村氏の素描が150点ほど収蔵されている(全て本人からの寄贈)。洋画で見られる油彩と日本画では完成形は色感や質感がかなり異なるが、素描の段階ではあまり洋画と日本画と違いはないんだな、と少し素っ頓狂なことを思ってしまった。日本画家としてかなりの名声を持っておられた方なので、素描であっても充分に鑑賞に耐え得るものである。その画力には感服せざるを得ない。素描といっても線だけのものから彩色が施されたものまで実に多彩である。
「描きたいと思った対象なら、人物、風景、動物、花鳥、なんでも失敗をおそれずぶつかっていきたい。無難なことをやっていては、明日という日は訪れて来ない、毎日そう考えるようになっていた。」とは生前の氏の言葉であるが、まさにその通り実践されていたようで、描かれてある対象は身近な風景から、僧侶、花、鳥、魚、城等々さまざまである。とにかくところかまわずスケッチしていたらしい。1990年、101歳になって病に倒れても精力的に描き続けた(しかしこの年に亡くなられている)。
私はこのコレクションの中の「梅」、「牡丹」、「文楽やぐらお七」の3点が気に入った。「梅」は1968年のもので、春霞の中にくっきりとした枝振りの梅の樹にぽつぽつと清らかな紅が映える。構図といい、色といい、実にすばらしい。「牡丹」については収蔵作品中8点ほどあるが、私はこの中で1946年のものが一番よいできであると思う。1977年のものも線や色に円熟した柔らか味があってよいのだが、57歳のときのまだ若々しい輝きを持つ線と色。50年以上前の作品であるので紙の朽ち方も味を出している。「文楽やぐらお七」は1980年、91歳の作品だ。人形の面のくっきりした線と髪や紅の着物の柔らかな線。この対照がしばらく私を釘付けにした。
全てにおいて格調高く、清新な作品の数々。めぐり合わせの偶然に感謝すると共に、すばらしい作品に触れた充足感が残った。
自分自身は毎日無難なことだけを繰り返してはいないか、かつて(10年前)の自分自身が忌み嫌った漫然と過ごすだけの日常を自分は送ってはいないか、明日という日の訪れを自らが切り開いていく気概があるのか、氏の言葉は重く、深い。
「奥村土牛記念美術館」は長野県八千穂村にある。JR小海線八千穂駅のすぐ近くだ。奥村氏が第二次世界大戦戦時中に疎開していたおりに住んでいた黒沢合名会社会館離れがほとんどそのまま美術館となっている。窓のガラスを見て昔通った木造校舎の小学校を思い出した。ガラスを成型する技術がまだ高くなかったころの薄い、あまり厚さが均一でない、小さな板で窓枠の中に棧があるそんな窓に郷愁を感じた。もし、通りかかることがあればふらりと寄ってみてほしい。
自分自身、こういった地方の美術館をふらりと寄ってみるという、ある種の楽しみを知ってしまったようだ。
(1998.11.29.)
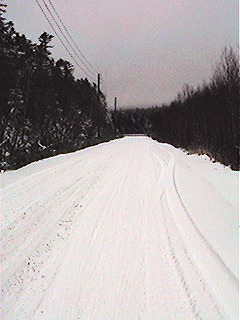
Prev  Next Next
| 