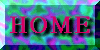
1/8/00記
ダイビングの器材って、一度買うとなかなか買い替えたりしないものだと思う。しかも、買ったのはきっと初心者だった頃で、その当時の商品知識(競合メーカー間の比較等)は今ほど判断力を持ったものではなくて、結構言われるままに買った人も多いのではないだろうか?私の場合は、レギは講習で使ったのと同じ物を、スタビはイントラの勧めで決定した。値段は判断材料になかった。この私が?と思われるでしょうが、当時は米ドルが\240もしていた時代だったので、国産のアブナイ器材(今でこそ、それなりの実績があるが、当時は国産は安かろう悪かろうと言われていた)を買う位なら、どうせローンを組んじゃうので、高いのでもしょうがないと思わされた。また、当時はダイバー人口も現在の比ではないので、量産効果も出なく高くてアタリマエという世界だった。上記為替レートだけから考えても、単純に現在の2倍以上の値段だったことは容易に推定できますよね。初めて器材を購入する客は、自分で基準になるものが無いので、買った機材が良いのか悪いのか判断することすらできないのだ。悪くは無い、と言うことはあっても、YYY社のより良いよ、などという評価自体不可能なのだ。そうすると、初めての器材を購入するに当たって気を付けなければならないのは、「評判の悪いメーカーの物は買わない」ということだけにならないか?安かろう悪かろうでも、機能が多少劣っていても、壊れなければ「こんなものだ」と思えるのではないだろうか。一生使える物だから良い物をと勧める店員は、ここまで考えてモノを言ってるとはとうてい思えない。ちなみに一生は使えないことは歴史が示している。数十年後に渡って保守部品をキープしてくれるという約束になっている物は別だが、ユーザーなんてバージョンアップとか仕様変更という言い訳で旧製品のサポートを受けられなくなると手も足も出ないものだ。無償でバージョンアップなりをやってくれればいいのだが、そういうことは稀だ。
自分の器材だから、使うにつれて慣れてくるから、使いやすいなあと勘違いしたままずーっと使ってたりする。たまに自前の器材が不調だとか、何かの機会に、レンタル器材を使って初めて、他機種の使い勝手に触れられるというものだろう。特にレギュレータは吸ってみないと分からないし、吸っても良く分からないことも多い。普通のレギュレーター使用者で、喉の渇きを訴えない人がシャーウッドの最近のレギを試してもありがたみを感じないが、一旦シャーウッドを使ってしまうと他のレギに戻れない的な要素もあり、なかなか複雑である。シブイ、軽いも相対的な言葉だから、自分のレギに慣れていれば、シブイ奴でも決して悪いということはないのだろう。BCは、結構レギなんかよりもバリエーションがあり、戸惑うことがある。タンクの固定の仕方だけじゃなくってベルトの位置、バックルの型式などは随分違うこともあり、セッティングやプレダイブチェックの時に自分の器材をさっさと背負ったら、バディーの器材がどうなって装着されているのかを見ておくのは良い勉強になる。本当にレスキューしなきゃいけなくなった時、溺者のBCを脱がせるのに手間取ってしまうことの無いように。ひとつひとつ完璧に覚えるのは意味もないけど、パターンがいくつかあるので、それを知っておくことは重要だ。水中での安定性とか姿勢の云々についてはレギと同じで、中性浮力の取れない初心者が評価できる項目でも無い。まして、外観からだけでは何も判断できない。
[このページトップに戻る][おやじのひとりごとの目次に戻る]
1/9/00記
今や自由競争の激化で色んなメーカーが色んなラインアップを揃えてきている。自分は器材を買い替える予定が無いから関心が無いと言われればそれまでかも知れないが、色んなメーカーの色んな器材、小物などなど、たまには入ったことのないショップにでも入って物色してみるのも楽しいものだ(時間があれば...)。スクーバ器材の歴史ってそんなに長い訳じゃないで、今の形で完成の域にあるとは思えない。面白いものを色々メーカーには期待したい。でも、試
しに使ってみる機会がダイビングプロショップで働く人以外の一般のダイバーにはほとんど無いことの方が問題だとも思う。
器材メーカーの営業担当の方へ!新製品の売り込みにプロショップ巡りも良いけど、IOPとか大瀬崎みたいな場所で無償貸し出しでモニターさせたり(アンケートに答えると「その器材」が抽選でもいいから貰えたりなんかすると最高)して、もっと一般ダイバーのフィールドテスト/フィードバックを増やしてちょうだい。店の店頭に飾ってあったって、いくらカッコ良くても、自分に合うフィンかどうかなんて、やっぱり使ってみないと分からない。評判が良くても、使ってみたことの無い物は、そもそも購入検討の対象に挙がってこないのだ。「今使っている***って取り敢えず問題無く使えている。」こういう状況の購買層に対して、新製品の***ってこんなに良いですよ、と訴えても、買い替え需要として売れることはないだろう。試してみる機会があり、良さが体感でき納得出来た時、人は初めてそれを「欲しい」と思うのではないか?そして、それを買った人だけが「買ってよかった」と感じ、xxxの***は良いよ、と広まる。営業努力とは価格面だけではないはず!一旦、海に浸けてしまった器材は新品として販売できなくなることは理解できるが、どうせなら多くの試着/試用希望者に実際に使って良さを実感できる機会を提供することのほうが、メーカーとしての責務を果たすという観点からも有意義なアプローチだと考える。広告費に多大な金を費やすよりも遥かにユーザーにとってありがたい。
[このページトップに戻る][おやじのひとりごとの目次に戻る]
3/7/00記
反省しきり。撮りっ放し、現像しっ放し、マウントすればまだ良い方。最近全然時間をかけられない。やっと、それでも気まぐれで人の真似をして紙焼きを試みた。10年以上前にはコダックのダイレクトプリントが1枚\135位でLサイズだったと記憶している。
フジはCBプリントを試したことはあるが、キャビネサイズ以上だし、発色はすんごく良いものの、試しに紙焼きしてたら海行きどころじゃなくなる。ということで、試しにLサイズでRPを頼んでみた。1枚税込みで\100を切る。昔のコダックは詐欺のような仕上がりでしかなかったのでここまで紙焼きしようという意欲を無くしたままだった。あるいは現在ではフジのRP並なのかも知れないが、という位、「フジクロームRPプリント」は期待以上だった。まあ、期待が10年以上前の詐欺レベルでは、誉めてることにはならないだろうが。ログブックにハサミでトリミングして貼り付けるという用途としては十分すぎると思った。35mm原版ではピントのチェックも厳しいので、取り敢えずLサイズで焼いてみて、もし良かったら次のプロセス(CBプリントかCD-ROMへのファイル化)へ移行できるじゃないか。
実は、後者に魅力を感じているのです。私のパソコンでは、最新のOSが走らないので、フイルムスキャナーを買っても、トラブルの恐れが大(あるいはそもそも動かないかも)なのです。そこで、一応CD-ROMは4倍速のがあるので、写真屋でスライドから画像ファイルに変換してもらえば、これまで未踏の「HP上の写真公開」ができるじゃないか!ということで一応盛り上がりを見せたのですが、結局、写真の整理が先だ!先月のスリーブもそろそろハサミを入れてマウントしなきゃとか、...やっぱり時間が無い!さてこの先どうなることやら。乞うご期待。なんて、このままだったりするのかなあ?
[このページトップに戻る][おやじのひとりごとの目次に戻る]
3/21/00記
ウミウシは綺麗なのがいるので、はまっているダイバーも多い。でもアメフラシはグロいだけなので嫌いという声も多い。同じなかまなのに、サイズがデカイと嫌われてしまうという要素がある。オオモンイザリウオも30cm位の奴で黒かったりすると「かわいくない」となる。話を戻すと、沿岸に生息するウミウシの仲間も、スクーバダイバーの発見によって新種がどんどん記録されているという。2ヶ月連続でウミウシを見たので、ウミウシ写真専用セットアップを組んでみたくなってきた。ウミウシは動きが少ないので、当てチョンができる。NIKONOS-Vの機動性にSea & Seaのマクロリング+YS30なんていうのが理想。接写用の枠先5mmという固定焦点で撮ることになるので、一度露出を決めておきさえすれば、何も考えずに当てチョンだ。ストロボの向きも固定できれば最高だ。トウシマコケギンポもタツノオトシゴもこれでいける。1眼レフでサージに耐えながらピント合わせをするより遥かに良い。シャッターチャンスには絶対の強みである。取り敢えず手持ちの機材では余分のYS30が無いので、YS60でやってみよう。撮影時に余裕があれば、シャッタースピードもバルブを使った超スローでバックの色出し(これからの味噌汁シーズンのあの濃い緑色がうまく出せれば最高:昔、中村宏治さんの大瀬崎での写真にすごく良い色のがあった)にもこだわれる。うーん、また2台持ち込みか!?それにしても最近ワイドは、やらなくなってしまったなあ、撮りたい絵が無いという感性渇ききった悲しい状態だ。亜熱帯から熱帯に最近行ってないからかもしれない。でも単なるサンゴ礁のカラフル熱帯魚ウジョウジョも食傷気味だし。一番いけないのは、人の(プロの)写真を見てない(雑誌を見てない)ので、そういう刺激を受けてないことが問題なのだ。ちゃんと立ち読みしなければ...本屋さんごめんなさい。
[このページトップに戻る][おやじのひとりごとの目次に戻る]
8/28/00記
多分オープンウォーターなどのエントリーレベルの講習で、タンク材質の見分け方は習わないのではないか、と思い書いてみることにした。ある程度の経験者には常識。と、なめてかかって、ブリーフィングの時に「ここのタンクはスティールですから、アルミタンクでウエイト調整してある人は1kg位ウエイト減らした方がいいですよ」と言うのを忘れたりする(した!=反省)。だから、ガイドやリーダーがタンク材質の話をしなかったら、自分でチェックしてウエイト調整しましょう!というお話。
もったいぶったが、ポイントはタンクブーツと呼ばれる底の部分の黄色や黒のプラスティックやゴム製の物がついているかどうかである。タンクブーツが付いていたら、スティール製のタンクである。アルミタンクは底が平らなので、自立する。スティール製の場合、底が丸いので(知ってた?)、自立できず、ブーツが必要となる。
何故、材質が違うと形が違うか?スティール(マンガン鋼)製は、丈夫だが加工しにくいので、鋼管の一端を赤熱状態で鍛接して丸い底部(平らなのは作りにくい)を形成し、反対側も赤熱状態で肩部および口金部に仕上げられるのだ。この製法はマンネスマン法と呼ばれている。一方、アルミニウム合金製は加工しやすいので、金属塊をプレスによって平らな底付きの円筒形に絞って成形される。こちらはエルハルト法と呼ばれる。どちらも高圧ガス保安法では継目なし容器という分類である。
後半の部分は、知らない人も多いだろう。強度は上述の通りスティールの方が強い。同じ体積のボンベ(タンク)なら、アルミの方が分厚く作られるため、大きくなるのだ。体積(容積)は、タンクの肩部に刻印されているV10.0等という表示を見てVolume(内容積)のVが10.0Lなのだと知れる。但しこの決まりは高圧ガス保安法によるものなので、外国のタンクは違うのだ。
ついでに外国では、空気のタンクの色を1/2以上をねずみ色にしろ!という規制がないので、赤やら黄色のタンクがあるのだ。日本では勝手に色を塗ったりして使ったら違法となる。
[このページトップに戻る][おやじのひとりごとの目次に戻る]