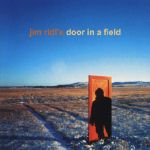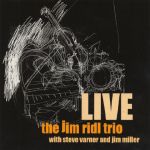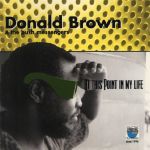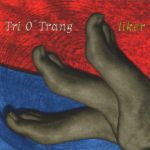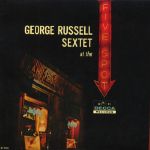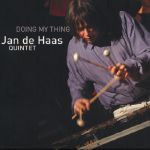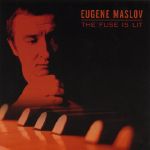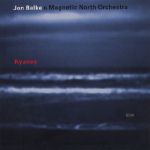 |
JON BALKE&MAGNETIC NORTH ORCHESTRAの
2001年録音のアルバム。
オーケストラと名乗りつつも構成は7人です。って、少なっ。
 手元の1993年の「FURTHER/(ECM)」ってアルバムを見ると 手元の1993年の「FURTHER/(ECM)」ってアルバムを見ると
11人いましたから更にシェイプアップされたのでしょうか?(笑)
PER JORGENSEN(TP,VO),MORTEN HALLE(SAX,FL),
ARVE HENRIKSEN(TP),SVANTE HENRYSON(CELLO),
JON BALKE(PF,KEY),ANDERS JORMIN(B),
AUDUN KLEIVE(DS)と云うちょっとイビツな編成です。
ですから、普通のオーケストラサウンドとは全く異なります。
トランペットこそ2本ありますが、他は全部バラバラの編成。
コンボ演奏なら別に普通の事ですが、オーケストラとしては異様です。
「FUTHER」のトランペット×2+サックス×2+弦楽三重奏の構成と比べると
そもそものアレンジの方向性が全然違う事に気付きます。
全曲に渡って、切れ目らしい切れ目は1、2箇所しかなく、
一体どの楽器が鳴っているのかわからない微妙な音の積み重なり。
そして、各楽器が離合集散をしながら、少しづつ表情を変えていきます。
思うに、これほどi-tuneのビジュアライザーの似合うアルバムはないでしょう(笑)。
(2004.4.18) |


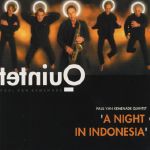

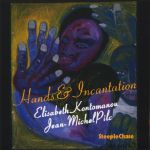
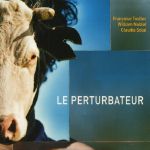

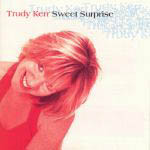
 以前blogに書いた記憶のある
以前blogに書いた記憶のある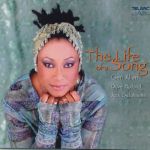

 他にも「02/(FINLANDIA RECORDS)」って
他にも「02/(FINLANDIA RECORDS)」って

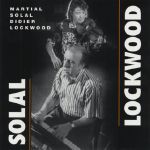
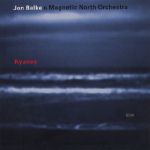
 手元の1993年の「FURTHER/(ECM)」ってアルバムを見ると
手元の1993年の「FURTHER/(ECM)」ってアルバムを見ると