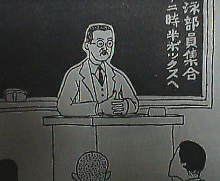入学まで−−昭和20年春の特殊事情
昭和20年は敗戦を目前にした年であっただけに、三高入学の段取りでも特殊な年で三高の歴史の上でも特筆すべきものがある。保存していた連絡文書もかなり風化してきたので、ここに記録して留めておく。
1月31日付で入学許可書が発送されたが、例年なら「直ちに」されるはずの入学手続きも3月31日迄でよく、入学式も追って通知すると書かれていた。同時に「入学者心得」、「注意」も送られた。「入学者心得」には、3月31日迄にしなければならないことが、注に示したようにいくつか書かれていたが、殊に入学金はその日までに納入しないと入学許可取り消しということであった。しかし、手元にある私の領収証書の日付は5月2日になっている。5月31日付の領収証は前期分授業料50円、報国団入団費10円と報国団費前期分7円50銭のものであり(物価水準の目安として書くと、当時私たち中学生の動員の報酬は一ヶ月30円で、一般勤労者から強制徴用された徴用工で月収80円程度であった。従って授業料前期50円というのは現在の水準で15万円程度というところだろう。絹織物関係の会社に勤めていた父はもはや会社自身が休業状態にあり給料も半失業者同様であったから、この50円の工面さえなかなか大変だったと思う。帽子は正規のものとの連絡が来ていたから、熊野を少し上がったところにあった山本帽子店に米だったか小豆だったかを算段して制帽を求めに行ってくれた父を思うと今更ながら篤い感謝の気持ちがこみ上げてくる。入学式に何を着ていったかの記憶はないが、制服も売っていなかったかと思う。その後、私は妹に助けてもらって家にあった大きな木綿の風呂敷を真っ黒に染め、これをわたしの体型に合わせて型紙を作り、それに合わせて裁断し、自分でミシンで服に仕立てた。あまりにも体型に合わせたものだから着てみるとすごく窮屈だったが、これを着て登校した思い出がある。)、授業料領収書が「昭和20年度学校特別会計」「経常」「直轄諸学校」「諸収入」という分類になっているのに報国団関係は「昭和十九年度」となっているのは少々首を傾げたくなる。報国団費7円50銭は納入通知書(発行日付は書かれていない)によると、7月から9月までの3ヶ月分である。入学式通知は5月22日付で本人と父兄のそれぞれに送られ、昭和20年7月1日午前8時から行われた。