 「真鍋先祖系圖」(真鍋島の真鍋総本家)
「真鍋先祖系圖」(真鍋島の真鍋総本家) 「真鍋先祖系圖」(真鍋島の真鍋総本家)
「真鍋先祖系圖」(真鍋島の真鍋総本家)
<真鍋先祖系図の解釈>
御裳濯川十揖「真鍋先祖発掘(上巻)」大塚秀男著・真鍋頼行発行より
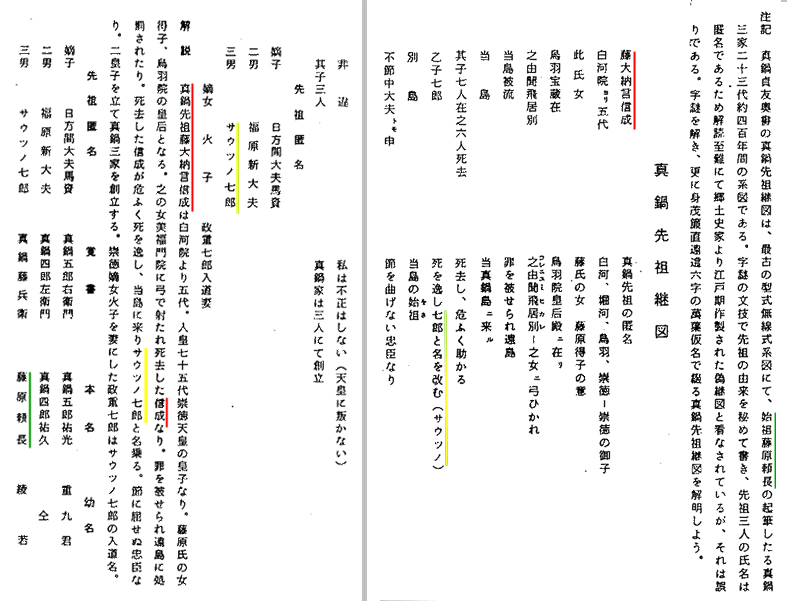
藤原信成は真鍋先祖の匿名である。頼長は保元の乱の後も30数年生きており、真鍋家継図も頼長が起筆した、となっている。いささか突拍子もない解釈だが、保元物語に、頼長は「神矢に当たったのかと思われた」と書かれており、これが神のご加護で助かったことを暗示している、としている。 事実はどうだったのだろうか。すぐに死んだのか、あるいは、ほほをつらぬかれただけで命は助かり、矢傷でゆがんだ顔をかくしていたため、「関面(=冠面)殿」と呼ばれていたのか。
実際は、保元の乱で敗れ讃岐に配流となった崇徳院が、配流先の直島にて双子をもうけた。この 二人の皇子重九君と、同じく保元の乱で敗れた藤原頼長の三氏にて真鍋家を創立した。(配流の 身であるため、皇子出産を伏せた。また、頼長も保元の乱で流れ矢に当たり戦死したことになっ
ているため、匿名とした。)
| 屋 号 | 現在当主 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三 家 | 五庁殿 | (いっちょんど) | 重九君 | |
| 四文殿 | (よもんどけ) | 重九君 | ||
| 関面殿 | (かんめんどの) | 頼長 | ||
| 七 家 | 元家殿 | (もとえ) | 元平 | |
| 神十殿 | (かんじうけ) | 大塚 | ||
| 神五殿 | (かんごけ) | 大塚 | ||
| 大屋殿 | (おうやけ) | 上原 | ||
| 九弁殿 | (きうべん) | 岩野 | ||
| ます千殿 | (ますせんけ) | 三宅 | ||
| とし殿 | (とし) | 小西 | ||
| 根の家他 | 源根 | |||
| 三根 | ||||
| 五根 | ||||
| 久平 | ||||
この著書の内容はおもしろいが、矛盾もある。保元の乱では、平氏も源氏も一族が2つに別れて対立した。特に平氏では清盛が頼長側とは対立している。この著書では、牛若丸の生い立ちの謎にまでせまり、源平合戦で頼長は源氏方に味方し、清盛を敵視しているように書かれている。しかし、「平家物語」でも「源平盛衰記」でも真鍋氏は平氏方についている。清盛没後とはいえ、源平合戦の平氏はまさに清盛方である。この辺の解釈が書かれていない。
歴史上の頼長の生死はもうひとつすっきりしない。本当に保元の乱の後も頼長が生きていて、自筆の書が残っているなら、日本の歴史のためにも是非公開して頂ければ、と思うのだが・・・・・。
この著者によると、歴史の表舞台に表せない崇徳上皇・頼長の境遇を、西行法師がその歌の裏にかくして表現しているとしている。そこまで言われるとその信憑性に疑問を持ちたくなるが、いろは歌(イロハニホヘト・・・)は、冤罪を訴える「咎なくて死す」という言葉を折り込んだ暗号文であるという説もあるぐらいだから、西行の歌に裏の意味があっても不思議ではないのかもしれない。
さらに時代が下ると、真鍋総本家は福山藩に弾圧され、悲惨な目にあった、と書かれている。
この著書には驚くような内容がいっぱい書かれていて興味深いが、この下巻は出版されているのだろうか?
↓
下巻を見つけるのに長い期間かかったが、やっと、御裳濯川十一揖「真鍋先祖発掘(下巻)」大塚秀男著・真鍋頼行発行を発見しました(参考資料)。 上巻の内容とはかなり趣が異なり、「いろは歌」、「義経記」、「保元物語」、「平家物語」、「源平盛衰記」、「梁塵秘抄」、「宇治拾遺物語」、「今昔物語」、「打聞集」、「春日権現験記絵」の各文書と頼長・真鍋島を結びつけようとするものである。
上巻も奇異な内容だが、下巻も理解し難い内容となっている。