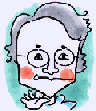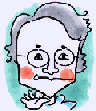フレッツ光ネクスト・ファミリー・ハイスピードタイプを使って、家庭のLANをインターネットにつないできたが、最近(2016年の秋)、biglobeのプレミアムサービスというオプションを使い始めた。ファミリー・ハイスピードタイプの接続速度は最大200Mbpsだが、プレミアムサービスは最大1Gbpsと言っている。biglobeからは、他にも、最大1Gbpsのオプションとして、v6プラスも提供されているし、NTT東日本からは、ギガファミリー・スマートタイプ/ギガラインタイプが提供されている。ここまで、「ギガ」が並ぶと、利用者は何を頼りに選択したものか悩んでしまう。ここでは、まず、biglobeのプレミアムサービスと、v6プラスについて書いてみたい。次に、これらが使っているMAP-Eという技術について紹介し、最後に、NTT東日本のギガファミリーと、これらの「最大1Gbps」サービスについて回る「ギガ対応」のWifiルータについても触れる。
・biglobeプレミアムサービスとv6プラスの違いは何か (MAP-E)
biglobeのインターネット接続オプションである、プレミアムサービスの提供が始まって数か月経過したが(2016年12月現在)、今のところ、時間帯によらず400Mbps前後でインターネット接続ができている。これは、接続速度計測サイトのspeedtest.netを使用して測定した数字であるが、最大1Gbpsのサービスを使ってるユーザーが、ネットで報告している数字と比較すれば高速な方である。(PCをイーサネットケーブルでルータに接続して測定。)このオプションを使う前は、フレッツ光ファミリータイプ(IPv4のPPPoEで最大200Mbps)を使用していて、混雑時には1Mbpsも出ない状況を経験しているので、今のところ改善効果は出ている。一方で、毎月800円の有料オプションであるプレミアムサービスは、同様に最大1Gbpsながら、追加料金が不要なv6プラスに対して、価格差に見合うメリットがはっきり見えないところがある。
v6プラスと、プレミアムサービスの共通点は、MAP-Eという方式を使ってIPv4パケットにIPv6のヘッダを付け、NTTのNGN(フレッツ光の利用者が接続する、NTT東西のローカルなネットワーク)を通すという点だ。一方、異なるのは、ユーザー側でMAP-Eを処理する装置が、NTTからレンタルされている光回線終端装置(ONU)なのか(v6プラス)、biglobeが貸し出すWifi付きルータなのか(プレミアムサービス)という点だ。また、v6プラスでは、IPv4のPPPoE接続機能が停止されるという違いもある。プレミアムサービスではONUの設定を変えないので、ONUに直接パソコンをつなげば、IPv4のPPPoEの通信を使うこともできる。なお、v6プラスとプレミアムサービスは、いずれも、IPv6グローバルアドレスを使うという技術的な理由から併用できないので、これらをリアルタイムで切り替えて通信速度を比較することはできない。
v6プラスは、フレッツ光の利用者にIPv6通信を提供しているJPNE(日本ネットワークイネイブラー株式会社)のサービスである。biglobe、nifty、ASAHIネットなどのプロバイダは、JPNEを使ってIPv6インターネット接続サービスを提供しているので、v6プラスのオプションを持っている。逆に、JPNEを使っていないプロバイダの利用者は、v6プラスは利用できない。JPNEの様なプロバイダはVNE(Virtual Network Enabler)と呼ばれ、自社のIPv6ネットワークをNGNに直結する権利を持っている。VNEはJPNEを入れて3社に限定されていたが、2012年に16社まで増やすことが決まり、2016年にbiglobeもVNEとして認可された。これによって、biglobeは、自社のIPv6ネットワークを、NGNの出入り口(POI:point of interface)に接続して、v6オプションと同じサービスを提供できるようなった。多分、これがプレミアムサービスだと推測するが、技術情報が開示されていないので、間違っているかもしれない。
JPNEの提供するv6プラスは、NGNの機能を使って、NTTのONUに内蔵されたホームゲートウェイ(HGW)というルータに、MAP-Eのプログラムをダウンロードして実現している。つまり、利用者は新たに専用のルータを買う必要はない。ただし、ONUにHGWが内蔵されていることが前提なので、フレッツ光の利用者であっても、このサービスを利用できない場合がある。サービスの利用条件に「ひかり電話」という言葉が出てくるのは、ひかり電話を使っている加入者のONUには、HGWが内蔵されているからである。一方の、biglobeプレミアムサービスは、ONUのHGWを使用せずに、biglobeからレンタルされるルータに、MAP-E機能を搭載している。
接続速度に差を生む要因は2つある。1つは、MAP-Eを処理するルータのスループットの違い。MAP-Eは、IPv4のIPアドレスとポート番号を変換するNAPT処理に加えて、IPv4パケットごとに、ヘッダー部分にIPv6パケットを追加・除去する処理をするので、ルータへの負荷は高い。ONU内蔵のHGWと、レンタルされたルータの間で、処理能力に差があれば、接続速度に差が発生する。2つ目は、NGNとプロバイダの接続点の違い。JPNEが提供するv6プラスの通信は、必ず、NGNの出口でJPNEのネットワークへのインタフェースを通る。v6プラスはJPNEと契約している複数のプロバイダが共用するので、biglobe以外の利用者の通信も、同じインタフェースを流れることになり、他のプロバイダの利用者が増えれば通信速度が制限される。一方、プレミアムサービスの方は、biglobeが自前のインタフェースをNGNに繋いでいるのであれば、他のプロバイダの利用者数に影響されることはない。しかし、上に書いたように、biglobeから情報が開示されていないので想像の域を出ない。
プレミアムサービスの技術的な情報が取れないので、だらだら推測を書いてしまったが、結局のところ、月々800円の明確な差はWifiの速度差程度しかない。ONUにオプションのPCカードを差して実現するWifi機能より、biglobeからレンタルされるルータに内蔵されたWiFiの方が高性能ではある。もっとも、これは、すでにIEEE802.11acを実装した高速なWifiルータを使っている人には関係が無いことだ。結論として、複数の利用者がストリーミングビデオを見るとか、インターネット接続した4K対応テレビでVOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスを使っているヘビーユーザーでもなければ、まずは、追加料金の無いv6プラスを試してみるのが良いかもしれない。付け加えると、ひかり電話に加入していない人にとっては、プレミアムサービスは、ひかり電話に加入せずにMAP-Eが使える手段でもある。
・プロバイダがMAP-Eを使う理由 (NAPT+IPv4アドレスの共有)
v6プラスもプレミアムサービスもMAP-Eを使っている。ここでは、IPv4アドレスを節約するためにMAP-Eを使う意味について書きたい。MAP-Eは、家庭のIPv4通信を、IPv6でNGNを通して、IPv4のインターネットに繋ぐ技術である。具体的には、家庭のルータが、IPv4のパケットの頭にIPv6のヘッダ部を追加してNGNに送り出し、受け取ったプロバイダのルータでIPv6のヘッダを剥がして、IPv4のパケットを復元する。ここで、IPv6ヘッダ内の送信元アドレスも、IPv4ヘッダの中に入った送信元アドレスも、家庭のルータに割り当てられたグローバルアドレスが使われる。NGN内のルータは、IPv4とIPv6のいずれも通すことができるが、あえてIPv6で通す理由は、NGNからプロバイダのネットに直結できる他に、IPv6アドレスに情報を載せるMAP-Eの機能を使うためでもある様だ。
IP通信は、通信元と接続先の間をIPアドレスと言う数字列と、ポートというインタフェース窓口番号を使ってつないでいる。NAPT(Network Address Port Translation)が使われる前は、インターネットに接続する端末の数だけのIPアドレスが必要だった。IPv6が考案された理由は、IPv4では32ビット長のアドレスだったのを、128ビットまで拡張して、対応できる端末数を劇的に増やすことだった。したがって、インターネットの全ての端末やサーバーがIPv6に対応していれば、MAP-Eを使う必要もないが、現実はIPv4しか対応しないサーバーもあるので、IPv6のみを利用することは難しい。そういうわけで、ネット対応の端末が増える一方で、限られたIPv4アドレスで、いかに多くの端末をつなぐかが、プロバイダの悩みになる。MAP-Eは、IPv4パケットを転送する以外に、こうした問題を解決する手段にもなっている。
長くプロバイダが使ってきたIPv4のPPPoE接続でも、NAPTという技術で、複数の端末からの通信を一つのIPv4アドレスに束ねる機能を使っている。家庭内の端末は、それぞれが異なるローカルアドレス(家庭内でしか使えないIPアドレス)を持っているが、ルータはPPPoEというパイプを通し、ISPから配られる一つのグローバルアドレス(インターネットで使えるIPアドレス)で通信を行っている。アドレスは一つだが、ポート番号は16ビットあるので、予約されていないで自由に使える番号も潤沢にある。これを使って、複数の端末の通信を一つのIPアドレスに束ねるのがNAPTである。しかし、これだけでは一つの利用者が、一つのグローバルIPv4アドレスを占有することになるので、MAP-Eでは、さらに、一つのグローバルIPv4アドレスを複数の利用者で共有し、それぞれの利用者に異なるポート番号の範囲を指定することも可能にしている。実際に、biglobeのプレミアムサービスで、どのようにMAP-Eが使われているか見てみる。
プレミアムサービスかv6プラスを使っているLANにパソコンを繋いで、Windowsのコマンドプロンプトを起動する。このプロンプトから、
ipconfig /all
というコマンドを入力する。全てのイーサネットアダプタの、パラメータが表示されるが、一番初めの「ローカル エリア接続」に注目する。IPv6のIPアドレスに関連した情報としては、「IPv6 アドレス」「一時IPv6 アドレス」「リンクローカル IPv6アドレス」の3つがある。また、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーの項目にも、128ビットのIPv6アドレスが表示されているはずだ。リンクローカル IPv6アドレスは、PC自身が設定した、LANの中だけで有効なアドレスで、ゲートウェイもルータのリンクローカルアドレスになっている。ルータのリンクローカルアドレスは、fe80で始まる64ビットプレフィックスに、MACアドレスの途中に0xfffeを挟んだ64ビットを付加している。Windowsの場合は、デフォルトでランダムな数字列を使うので、MACアドレスは入っていない。末尾に足された%と数字は、端末のイーサネットアダプタに対応している。
「IPv6 アドレス」は、ルータからDHCPv6で割り当てられたグローバルアドレスで、ルータが上位64ビットのプレフィックスにランダムな下位64ビットを足して作成している。「一時 IPv6 アドレス」の方はPCなどの端末が、下位64ビットをランダムに作成している。このアドレスはインターネット接続に使われるので、インターネットからの攻撃を避けるために定期的に変更される。二つのアドレスを見ると、上位(左側)の64bit分が共通になっている。これが、プレフィックスという部分で、HGWごとに固有の値になっている。プレフィックスは、NGN上のルータから、HGWを通して家庭のルータに配布される。v6プラスならPCが直接HGWから受け取る。HGWとルータは、プレフィックスに自分のMACアドレスを元に生成した下位64ビットを足して、グローバルアドレスにする。このように、全ビットをDHCPv6で設定する管理方法をステートフルと言い、HGWやルータの様に、下位16ビットをMACアドレスから自動生成する管理方法をステートレスと言う。セキュリティは、ステートフルの方が高いと言われている。
「IPv6 アドレス」の上位64ビットのプレフィックスが、240bで始まっている場合、これはJPNEの管理下にあるプレフィックスである。実際は26ビットまでが範囲なので、240b::/26と表現される。このことから、このアドレスは、JPNEに預けたbiglobeの割り当て分から配布されていることが分かる。27から40ビットまでは、HGWに割り当てられた固有のアドレスである。これに続く41から56ビット目は、MAP-Eで使われる情報で、EAビットと呼ばれる。例えば、EAビットが16進数の0x1014である場合、最初の10hはIPv4のグローバルアドレスの下位バイト、14hは使えるポート範囲を示している。10hは十進数の16なので、グローバルアドレスのプレフィックスが、123.123.123/24であれば、このHGW/ルータに割り当てられたグローバルアドレスは、123.123.123.16となる。ポートについては、ポートオフセットが4ビットであれば、16進数の0xX14Y(Xは1〜f、Yは0〜fの16進数)がポートの範囲になる。例えば、0x1140〜0x114f, 0x2140〜0x214fという具合に割り当て範囲が決まる。最初の4ビットがゼロの範囲は予約されていて使えない。この例では、123.123.123.16アドレスの15x16=240ポート分が割り当てられる。
HGWから与えられたグローバルアドレスのプレフィクスからIPv4アドレスと、ポート範囲を読むには、EAビットの長さや、グローバルIPv4アドレスのプレフィックス(上の例で123.123.123の部分)、ポートオフセット(上の例では4ビット)などが必要だが、これらは、NGNのルータからDHCPv6で配布される。このように、MAP-Eを使うと、EAビットの下位バイトで同一IPアドレスのポートを分割できるので、おなじグローバルIPv4アドレスを複数の利用者に割り当てることができる。1アドレスを1人が占有していたIPv4のPPPoEに比べて、最大16倍の利用者を接続できることになる。そうはいっても、IPv6のアドレス空間に比べれば利用者可能な数は限られるので、インターネット側のサーバーがIPv6に対応するまでという位置づけではある。
・NTT東のフレッツ光ネクスト・ギガファミリーとは何か (PPPoE IPv4)
ギガファミリー・スマートタイプも最大1Gbpsの接続サービスで、ファミリー・ハイスピードタイプの高速版という位置づけにある。ちなみに、ギガファミリー・スマートタイプに対して、ギガラインタイプという選択肢もがある。これはルータにWifi機能がついていないというだけの差だ。既に、Wifiルータを使っているのでいらない人向けのサービスらしい。
ギガファミリー・スマートタイプを契約すると、ホームゲートウェイというルータが送られてくる。v6プラスの説明で、ONUに内蔵されたホームゲートウェイという言葉を使ったが、このサービスではONUと分離した説明になっている。もっとも、実際は、ONUも内蔵されたPR-500というホームゲートウェイと、ONUが内蔵されていないRT-500/RS-500というホームゲートウェイが提供される。ONUが内蔵されていない機種は、既にONUを導入済みの加入者向けだろう。「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ レンタル機器仕様」というwebページの情報によると、レンタルされるPR-500/RT-500は2.4GHzのWifi機能が入っていない機種の様だが、PCカードを入れて追加できる様だ。5GHzと2.4GHzは同時に使えるので、両方あれば、ルータと同じ階の部屋なら5GHz、別の階で使うならは2.4GHzと使い分けて、通信速度の低下を避けることもできる。ちなみに、2.4GHzの方が障害物によって減衰しにくい。
興味は、どのような方法で1Gbps通信をしているかだが、「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ 提供条件」というWebページには、「インターネットプロトコル(IPv4)は、PPPoEとなります」とあるので、PPPoEを使ってプロバイダとIPv4の通信をしているようだ。MAP-Eは、IPアドレスや、ポートの設定を細かくできるが、NTTの装置を使って利用者のルータに、それぞれ固有の情報を配布する必要がある。一方のPPPoEは、利用者にはプロバイダに対応したPPPoEのアカウント情報だけ知らせればよいし、PPPoEの終端装置で復元したIPv4パケットの扱いはプロバイダに任せればよいので、複数のプロバイダが共有する形態としては適している。ただ、基本は、ハイスピードタイプと同じ仕組みで、ホームゲートウェイが1Gbpsに対応しただけなので、利用者が増えると、最大200MbpsのPPPoE接続と同じ状況になるかもしれない。
光ネクスト・ギガファミリーについてまとめれば、これまでのPPPoE(最大200Mbps)を最大1Gbpsに高速化したバージョンのようである。少なくともbiglobeの加入者には、同じ最大1Gbpsのv6プラスという追加料金無料の選択肢があるので、あえてギガファミリーを使う理由はない。ギガファミリーを使う必要があるのは、上に書いたJPNEを使用しないので、v6プラス相当のサービスを提供していないプロバイダの利用者、ということだろう。
・ギガビット対応Wifiを過大評価してはいけない
プレミアムサービスやギガファミリー・スマートタイプについてくるギガビット対応Wifiだが、これに、あまり期待してはいけないと思う。ギガビット対応と言っているのは、5GHz帯のIEEE802.11acが使えることを指している。Wifiルータの仕様を見ると、80MHzで最大1.3Gbpsなどと書かれている。IEEE802.11acでは、3つの技術で高速化している。1つはチャンネルを束ねた高速化。80MHzというのは、.11nでチャンネル当たり40MHzだったバンド幅を、80MHzに広げて高速化している。2つ目は、QAMと言って、同じ周波数の電波で位相と強度の組み合わせを増やす技術。.11nの64QAMから.11acでは256QAMに組み合わせを増やすことで、速度を3割くらい速くしている。3つ目は、MIMOという方式だ。これは、同じ周波数だが、複数のアンテナを使うことでアンテナの数だけ通信経路を増やすという技術だ。1.3Gbpsの速さを出すには、これらをフルに使わなくてはいけない。すなわち、3対のアンテナで、80MHzのバンド幅で、256QAMという3つが同時に使える必要がある。そもそも端末側は、これらの技術に対応できているだろうか。
少なくとも、1.3Gbpsを利用できるには、使うパソコンやスマホが.11acに対応していなくてはいけない。しかし、対応していても、電波状態が悪くて40MHzで通信していれば600Mbpsに遅くなる。さらに、アンテナが1つしかない端末は、200Mbpsの通信速度になる。また、アンテナが3本あっても、同じLANを複数の端末で使えば、通信速度は割り勘で遅くなる。これからも、1.3Gbpsというのが、限定された条件でのことだということが分かる。さらに言えば、これは規格値なので、実際に使用するとこれよりも遅くなる。プレミアムサービスで届いたルータWG1810HPを使い、.11acに対応したiPhone7とインターネットの間の接続速度をspeedtest.netで測定したところでも、ピークでも180Mbps、実用で80Mbps程度だ。そもそも、インターネットとの接続が1Gbpsもいかないのに、1.3Gbpsを期待する必要があるだろうか。インターネットから送られてくる4Kテレビの映像を、無線LAN経由で見たとしても、転送速度は25Mbpsあれば足りる。そう考えると、100Mbps程度であっても、安定してつながることが大事で、ピーク速度の1Gbpsにこだわる理由は無いように思う。
・ボトルネックはどこにあるのか
最大200MbpsのPPPoE(IPv4)を1Mbpsまで遅くしてしまうボトルネックはどこにあるのあろう。最大1GbpsのPPPoE(IPv4)やv6プランに変えただけで改善するとすれば、GE-PONの1Gbps光アクセス網にはなくて、光を電気に変えた後の経路にあるのだろう。さらに、NGNの中のフレッツ速度計測サイトでは、最大200Mbpsの契約なら、NGNの出口まで、リミッタがかかる200Mbpsで通っていることが確認できる。すると、NGNからプロバイダのネットワークへの出口にボトルネックがあると考えるべきだろう。NGNからいくつかある出口の帯域を、どれくらい広げるかはプロバイダの財布次第だ。v6プラスの評判やbiglobeのプレミアムサービスの接続速度を見ると、biglobeは、最大200MbpsのPPPoE接続よりも、IPv6経由で直接通信するv6プラスやプレミアムサービスに投資を向けているように思う。そうであれば、利用者も、そちらのサービスを使った方が不満はないだろう。
この先、光アクセス系をボトルネックにするのは、長い時間一定のデータが流れる映像サービスだろう。ただ、GE-PONにぶら下がっている32家庭で、4Kテレビを同時に見たとしても、25Mbpsの32倍で800Mbpsである。実際は、32分岐を全部占有しているわけでもないので、まだ、数MBのファイルをダウンロードする余裕はあるし、アップロードの方は別の波長を使うので、下りの信号に圧迫されることもない。つまりは、さらに8Kテレビのコンテンツが配信されるまでは、GE-PONで充分足りる。NTTは、アクセス系の10G-PON化については、家庭へのインターネット接続だけでは、投資回収できないのか、ビジネス用途や、携帯電話網の通信を通す構想を持っているようだ。フレッツ光の利用者は、しばらくは最大1Gbpsのサービスを使うことになるだろうが、プロバイダが、ちゃんと信頼性や安定性を維持してくれれば、実用上の問題は出ないだろう。