宮本顕治の「五全協」前、スターリンへの“屈服”
自己保身目的による党史偽造歪曲犯罪の基礎データ
(宮地作成・編集−「解説」のみ加筆・改定)
〔目次〕
『朝鮮戦争と武装闘争責任論の盲点』資料の解説(宮地) (「解説」のみ加筆・改定)
1、『戦争責任論の盲点』と『朝鮮戦争と武装闘争責任論の盲点』との関係
2、1951年2月23日四全協から、1951年10月16日五全協
3、五全協から、1953年7月27日朝鮮戦争休戦協定成立 武装闘争データ(表1〜3)
〔資料1〕、不破哲三『四全協から五全協』(抜粋)
〔資料2〕、小山弘健『コミンフォルム判決による大分派闘争の終結』(全文)
〔資料3〕、亀山幸三『五全協にいたる経過』(全文)
〔資料4〕、宮本・蔵原2人『宮本分派の解散宣言』(抜粋)
〔資料5〕、第7回大会報告『四全協から五全協』(抜粋)
〔資料6〕、宮本顕治『五全協から六全協』(抜粋)
〔資料7〕、不破哲三『六全協の準備』(抜粋)
(関連ファイル) 健一MENUに戻る
『朝鮮戦争と武装闘争責任論の盲点』朝鮮“侵略戦争”に「参戦」した統一回復日本共産党
『嘘つき顕治の真っ青な真実』屈服後、五全協武装闘争共産党で中央活動をした証拠
『シベリア抑留に関する日本共産党問題』ソ連から108億円以上の資金援助
石田雄 『「戦争責任論の盲点」の一背景』
吉田四郎『50年分裂から六全協まで』主流派幹部インタビュー
藤井冠次『北京機関と自由日本放送』人民艦隊の記述も
川口孝夫『私と白鳥事件』 中野徹三『白鳥事件』の添付
れんだいこ『日本共産党戦後党史の研究』 『51年当時』 『52年当時』 『55年当時』
『点在党員組織隔離報復措置』『日本共産党との裁判第4部』
〔小目次〕
1、『戦争責任論の盲点』と『朝鮮戦争と「武装闘争責任論」の盲点』との関係
2、1951年2月23日四全協から、1951年10月16日五全協
3、五全協から、1953年7月27日朝鮮戦争休戦協定成立 武装闘争データ(表1〜3)
これは、別ファイル『朝鮮戦争と武装闘争責任論の盲点』の基礎データとなる(資料篇と解説)である。宮本顕治と日本共産党は、1967年以降、今日まで一貫して、「(現在の)わが党は、武装闘争になんの関係もなく、責任もない。なぜなら、それは、党分裂時の一方の側である徳田・野坂分派がやったことだからである。よって、武装闘争の具体的実態について、そのデータや総括を公表すべき義務はない」としてきた。
具体的な言動証拠は、大須事件被告人永田末男が、公判陳述において3つを明記した。
第一、一九六七(昭和四十二)年七月「朝日ジャーナル」誌記者とのインタビューの中で宮本書記長は次のように語った。「極左冒険主義の路線は、以上の党の分裂状態からみれば、党中央委員会の正式な決定でなかったことも明白です。当時、分裂状態にあった日本の党の方で指導的な援助をもとめたということはあるにしても、ソ連共産党と中国共産党が、当時の党の分裂問題にかんして、四全協決議を一方的に支持して、それに批判的な側を非難したり、あるいは極左冒険主義の路線の設定にあたって、これに積極的に介入したということも、今日では明白です。」(「赤旗」一九六七・七・二八第二面掲載)と。
第二、一九六八年六月二十九日には、参議院選挙を前にしたNHK東京12チャンネルの選挙番組「各党にきく」に出席し、臆面もなく次のように述べたのである。「いわゆる『火炎ビン事件』というのは、これはよくいろいろなときにもち出されるのですが、あのとき、共産党は実際はマッカーサーの弾圧のなかで指導部が分裂していて、統一した中央委員会でああいう方針をきめたわけではないのです。ですから、党の決定にはないわけです。一部が当時そういう、いわば極左冒険主義をやったので、それは正しくなかったといって党はこれを批判しています。したがって党が正規にああいう方針をとったことはなかったのです」(「赤旗」一九六八・七・一付三面掲載)。
第三、一九六九年一二月二八日、毎日新聞での、テレビ司会者前田武彦氏との対談である。その後も彼は、機会あるごとに同様の言明をしている。そこで滑稽なのは、宮本が火炎ビンの投擲が「ひじょうに大きな印象をあたえて、共産党自体が、ひじょうになにか物騒なものだせいう印象をまだのこしている」と陳弁これつとめた。それに対し、前田氏から逆に、「しかし、火炎ビンを民家にぶっつけたり、なんでもない人を殺傷したりとかいうようなことは、なんにもなかったわけでしょう」と指摘、反問、いや、むしろたしなめられて、「そうなんです」と渋々認めていることである。(「赤旗」日曜版一九六九・一二・二八抵載)(「前衛」一九七〇・・三〇五号三二三頁)
この科学的社会主義式言い分は、詭弁であり、明白なウソである。なぜなら、下記や資料7つにあるように、
(1)、宮本顕治は、「宮本らは分派」というスターリン裁定に屈服し、それぞれの反徳田4分派組織とともに「宮本分派」を解散した。彼は、五全協前に、志田重男・主流派に他国際派中央委員6人とともに自己批判書を提出し、主流派に復党したからである。これにより、党分裂はなくなり、五全協共産党から統一回復をした。五全協以降は、統一回復共産党であって、徳田・野坂分派共産党ではない。
(2)、武装闘争実践データは、四全協〜五全協期間に起きていない。その実践は、下記(表1、2)データにあるように、すべて統一回復の五全協共産党が指令し、遂行した。よって、武装闘争は、スターリンへの屈服=宮本分派解散・自己批判書提出・主流派復党をした宮本顕治を含む五全協武装闘争共産党が行ったものであり、党分裂時の一方の側である徳田・野坂分派がやったことというのは、宮本が得意とする真っ赤なウソだった。
その結果、宮本言動の犯罪性は二重の面を持った。
〔犯罪性1〕、宮本顕治の自己保身目的による党史偽造歪曲犯罪
1967年以前、宮本顕治は、武装闘争責任の有無について、なんの発言もしていなかった。なぜ、五全協武装闘争共産党の15年後になってから、このような党史偽造歪曲犯罪をする必要が生じたのか。
(1)、そこには、五全協武装闘争共産党への宮本顕治の参加・関与レベル疑惑に関し、何らかの弁明をせざるをえないという1967年当時の政治的背景があった。宮本顕治の五全協武装闘争共産党への関与レベル疑惑が、五全協共産党からの東京第1区立候補者になった事実も合わせて、一挙に高まったからである。
『宮本を党史偽造歪曲犯罪に追い込んだ国際的国内的政治要因4つ』
(2)、さらには、スターリンへの屈服後、五全協武装闘争共産党で自分が中央活動をした証拠を全面否定し、抹殺するだけでなく、「汚れた手」ではないとウソ・詭弁をつく自己保身の犯罪動機が根底にある。これらの証拠については、別ファイルで検証した。
『嘘つき顕治の真っ青な真実』屈服後、五全協武装闘争共産党で中央活動をした証拠
〔犯罪性2〕、1952年武装闘争の騒擾事件裁判15年目における敵前逃亡犯罪
1967年とは、1952年武装闘争の3大騒擾事件公判が15年後でも継続中だった。犯罪という意味は、宮本言動が大須事件のみに騒擾罪を成立させる上での共産党側・宮本顕治による副次的原因=敵前逃亡犯罪になったからである。
大須事件被告150人は、警察・検察の騒擾罪でっち上げの国家権力という敵の犯罪とたたかっていた最中だった。宮本顕治の敵前逃亡とは、この言動により、被告・弁護団・家族たち全員を、現在の共産党・宮本体制から切り離し、関係ないとし、見捨て、見殺しにした犯罪行為を指す。これについて、大須事件被告団長を宮本顕治の報復により解任された永田末男は、裁判書面において、痛烈に宮本顕治の言動を批判した。
大須事件元被告酒井博は、宮本言動の性質を敵前逃亡犯罪と規定し、繰り返し批判してきた。私は、大須事件について、酒井博に何度も直接取材したが、(1)公判経過と、(2)その裏側における共産党・宮本対応を検証するにつけ、彼が規定した敵前逃亡犯罪という宮本犯罪の性質への認識が一致した。
大須事件被告人永田末男『第一審最終意見陳述・控訴趣意書における宮本顕治批判』
元被告酒井博『証言 名古屋大須事件』宮本言動の性質=敵前逃亡犯罪
『1967年からの党史偽造歪曲犯罪による敵前逃亡犯罪』前衛党最高権力者の人間性
彼の敵前逃亡犯罪がどのような内容・経緯だったの詳細は、別ファイル『大須事件第5部』で検証した。それは、大須事件に騒擾罪を成立させる上で、副次的要因とはいえ、重大な宮本犯罪結果を引き起こした。
第5部『騒擾罪成立の原因(2)=法廷内外体制の欠陥』敵前逃亡犯罪の内容・経緯
ただし、宮本言動がウソであることを論証するには、いくつかの基礎データを確認しておく必要がある。このファイルは、詭弁、ウソを分析する前提となる7つの資料と、その解説を載せた。〔資料〕中の赤太字は、私が付けた。
1、『戦争責任論の盲点』と『朝鮮戦争と武装闘争責任論の盲点』との関係
宮本顕治・日本共産党は、丸山眞男『戦争責任論の盲点』にたいし、1994年第20回大会前後で、異様なまでの「丸山批判キャンペーン」13回を行なった。この資料篇と解説テーマは、丸山眞男が批判した日本共産党の結果責任たなあげ体質と共通するものを含んでいるので、丸山論文の題名の一部を借りた。というのも、丸山眞男が、その小論を書いた直接の動機は、彼も体験した「メーデー事件」で、(1)皇居前広場突入を指令・指揮し、流血の惨事を引き起こさせた日本共産党の無責任さ=突入方針にたいする結果責任をとらないこと、(2)指導部の突入方針とその誤りについての総括を公表しないこと、(3)その根底にある武装闘争全体の結果責任のたなあげ体質にたいする批判だった。丸山眞男の真意については、石田雄東大名誉教授が『「戦争責任論の盲点」の一背景』で書いている。
このファイル題名の『宮本顕治のスターリンへの“屈服”』とは、1951年10月初旬、宮本顕治が行なった(1)スターリンに直接名指し規定された宮本分派(統一会議・宮本系)の組織解散、(2)志田宛の宮本自己批判書提出と、(3)それによる主流派・臨中への復党の行動を指す。このテーマで、彼の主流派・臨中復党が、五全協の前か、それとも後なのかが、なぜ重要になるのか。それは、実際的な武装闘争実践が、〔資料1〕『不破哲三証言』にあるように、五全協から始まったからである。
武装闘争開始前に、彼が主流派・臨中復党をしていたことが証明されれば、上記のような科学的社会主義式言い分は、詭弁・ウソであることが明白になるからである。それは、宮本顕治による自己保身目的の党史偽造歪曲犯罪を証明することになるからである。宮本自己批判書は公表されていない。その存否について、議論になってきた。その存在と3回書き直し事実を〔資料3〕で、当時の国際派中央委員亀山幸三が証言している。
彼の言動は、党史偽造歪曲という党内犯罪に留まらない犯罪結果をもたらした。3大騒擾事件において、名古屋・大須事件だけが騒擾罪とされた。その基本原因は、警察・検察の騒擾罪でっち上げ犯罪による。ただ、その副次的原因として、大須事件公判15年目における彼の自己保身犯罪のマイナス影響がきわめて大きかった。この詳細は別ファイルで検証した。
『騒擾罪成立の原因(2)=法廷内外体制の欠陥』 『第5部・資料編』
ファイル副題の『盲点』とは、戦争責任論と武装闘争責任論の2つに共通する、(1)日本共産党が結果責任をとらないこと、(2)きちんとした具体的総括をして、(3)その実態データを公表するということへの無責任体質のことを意味する。〔目次〕資料の題名は私がつけた。その「正式題名」は、資料冒頭に書いた。なお、このテーマについては、『シベリア抑留に関する日本共産党問題』の「ソ連から108億円以上の資金援助」でも分析してある。
2、1951年2月23日四全協から、1951年10月16日五全協
この期間は、臨時中央委員会(主流派・臨中)と排斥された7人の中央委員との、明白な組織分裂時期だった。1950年6・6追放の翌日の主流派・臨中結成、非合法機関化、北京機関設立は、すべてモスクワの指令による予定の行動であったことを、現日本共産党・不破哲三が、〔資料1〕で証言している。6月25日、ソ連・中国共産党、朝鮮労働党が仕組んだ、社会主義3カ国と前衛党による朝鮮“侵略”戦争が勃発した。モスクワ指令は、それに勝利するために、朝鮮戦争後方兵站補給基地日本において、日本共産党をして後方基地武力かく乱戦争に加担させる作戦の一環だった。ソ連崩壊までの米ソ冷戦期間中において、米ソの代理戦争は、いくつもある。しかし、朝鮮戦争は、事実上の直接対決をした唯一の“熱い戦争”だった。
そこにおける後方基地武力かく乱は、クラウセヴィッツの『戦争論』をひも解くまでもなく、完璧な戦争行為である。軍事方針・武装闘争を、極左冒険主義というイデオロギー問題レベルだけでとらえると誤りを犯す。それを、4つの共産党・労働党ぐるみの東アジア“侵略”戦争行動と位置づけるかどうかで、このテーマの理解度がまるで異なる。日本共産党は、第二次世界大戦後、発達した資本主義国共産党の内で、唯一の社会主義国家・共産党が行なう侵略戦争に加担したマルクス主義政党となった。
もちろん、朝鮮戦争には、マッカーサーの陰謀の側面がある。しかし、それによって、4党ぐるみの“侵略”戦争という本質を否定することはできない。
朝鮮戦争勃発の8カ月後、“侵略戦争”を継続しているソ連・中国共産党は、北京機関・主流派・臨中に四全協開催の指令をした。その会議は、日本に中国革命方式を機械的に適用する「劉少奇テーゼ」に基づく植民地型軍事方針を決定した。しかし、その内容が抽象的であり、五全協以前に、具体的な武装闘争事件は、いっさい発生していない。
この期間中で、重大なことは、1951年4〜5月、モスクワにおける、「宮本らは分派としたスターリン裁定」である。その内容と性格、および絶大な影響は、〔資料1〜5〕で載せた。スターリンの意図は、明らかである。それは、後方基地武力かく乱戦争作戦を遂行する上で、その中核となる日本共産党の組織分裂を即時中止させ、NKVDスパイ野坂参三を指導部トップとする組織統一を回復させることだった。人民艦隊密航日本共産党員の北京機関を抱えている中国共産党・毛沢東も同じ意図だった。これらも、不破哲三が、〔資料1〕で認めた。
その四全協から五全協までの経過分析が、〔資料1〜5〕までである。徳田・野坂主流派・臨中に対抗するグループは、いわゆる国際派メンバーである。国際派といっても、もともと統一した組織ではなく、主流派・臨中設立後、5つの反徳田分派になっていた。ところが、反徳田5分派は、「宮本らは分派としたスターリン裁定」に出会うと、瞬時に腰砕けになった。宮本分派(統一会議・宮本系)を含めて、1951年6月から10月初旬にかけて、5分派すべてが、分派組織解散宣言を出し、主流派・臨中に自己批判書を提出した。そして、スターリンが直接、認知した正規の日本共産党徳田・野坂中央委員会に復党した。さらに、五全協の「51年綱領」と軍事方針を承認した。この詳細な経過は、小山弘健が、〔資料2〕で分析した。
それら5分派の自己批判内容には、さまざまなレベルがある。(1)スターリン信奉による心からの服従、あるいは、(2)偉大なスターリンと絶賛してきた宮本顕治の二枚舌的屈服=“宮本式偽装転向”、さらには、(3)当時の日本共産党の基本的体質であったコミンフォルムへの盲従性の結果など、いろいろある。しかし、そのいずれにしても、反徳田5分派の組織解散と主流派・臨中復帰によって、五全協前に、日本共産党の組織分裂はなくなり、ともかく党組織統一が回復した。自己批判レベルの違いを、亀山幸三が、〔資料3〕で分析している。
他6人の国際派中央委員と比べ、宮本顕治が、なぜ、スターリンの「宮本らは分派」という名指し裁定に、もろくも屈服したのか。その思想的心情的背景には、2つがある。
(1)、彼は、スターリン執筆が証明されているコミンフォルム批判を真っ先に受け入れ、賛同した。そして、占領下の平和革命という野坂理論から、暴力革命=武装闘争路線への即時転換を強烈に主張した。コミンフォルム批判の本質は、38度線付近で硬直状態に陥った朝鮮侵略戦争への日本共産党軍の「参戦」命令=後方兵站補給基地日本における武力撹乱戦争への秘密決起指令だった。当初、コミンフォルム批判に抵抗した所感派中央委員28人・80%にたいし、国際派中央委員7人・20%の中でも、宮本顕治こそスターリン秘密指令を無条件に遂行しようとした国際的指令盲従派の中心指導者だった。
(2)、その屈服の根底には、彼の異様なまでのスターリン崇拝心情がある。そのレベルは、シベリア抑留をされた日本国民の利益の上に、スターリン擁護を置くという反国民的なスターリン賛美信仰があった。それは、別ファイルのシベリア抑留記をめぐる彼の露骨なスターリン賛美言動に典型的に表れている。
『宮本顕治の異様なスターリン崇拝』高杉一郎抑留記『極光のかげに』批判の態度
宮本顕治・日本共産党が、1955年7月六全協で初めて党統一回復になったと宣伝するのは、真っ赤なウソで、自己保身目的の党史偽造歪曲犯罪である。その結果、日本共産党員だけでなく、左翼・有権者・マスコミのほとんどか騙された。現在も、なお騙され続けている。日本共産党80年史上、自己保身目的に基づくこれほど大掛かりな党史偽造歪曲犯罪を成功させたのは、宮本顕治以外にはいないであろう。
3、1951年10月16日五全協から、1953年7月27日朝鮮戦争休戦協定成立
(組織統一回復共産党の武装闘争期間1年9カ月間と実践データ)
1951年10月初旬、宮本分派(統一会議・宮本系)の組織解散と、宮本自己批判書の志田宛提出でもって、反徳田5分派はすべて解散した。それによって、日本共産党は、スターリン指令による後方基地武力かく乱戦争作戦を遂行する上での組織統一回復をした。これについては、『第7回大会政治報告』が、〔資料5〕のように、「第5回全国協議会は、ともかくも一本化された党の会議であった」と、明確に規定している。ただし、精神的な団結の回復は、別問題で、まだ解決していない。
現日本共産党・不破哲三も〔資料7〕で認めているように、五全協の方針・内容とともに、開催も、スターリン指令によるものだった。五全協は、(1)スターリンが直接作成した「51年綱領」を決定した。(2)同時に、ソ連・中国共産党が指示した朝鮮戦争の日本における軍事作戦方針をそのまま受け入れて、軍事方針を決定し、朝鮮戦争支援の武装闘争を直ちに展開した。(3)それには、日本人共産党員とともに、当時まだ日本共産党籍であった在日朝鮮人共産党員が、祖国解放戦争として、武装闘争の先頭に立った。
この軍事方針・武装闘争の実態は、抽象的な極左冒険主義というイデオロギー規定で隠蔽できるものではない。ただ、今回の〔資料篇〕では、これらの日本共産党が行なった朝鮮戦争分担行動内容のデータ(表)だけを載せた。その詳細は、別ファイル『「武装闘争責任論」の盲点』で書いた。
1953年3月5日、朝鮮戦争の指導実権を100%発揮していたスターリンが死去した。そして、1953年7月27日、朝鮮戦争休戦協定が成立した。その日で、日本共産党の武装闘争事件も、見事なまでに“ぴたりと休戦”した。これには、当然、ソ連・中国共産党の武装闘争停止指令があったと思われるが、それについての具体的証言・証拠文書は、まだ公表されていない。しかし、(1)7月27日時点における休戦協定成立と、(2)日本共産党の武装闘争完全停止という不思議な一致事実は、武装闘争が、後方基地武力かく乱戦争作戦行動=日本共産党の朝鮮戦争加担行為であったことを、ほぼ完璧に立証するデータの一つとなる。武装闘争期間は、1年9カ月間にわたった。
日本共産党は武装闘争データの公表を一貫して拒絶してきた。全国的な後方基地武力かく乱戦争行動データを載せているのは、現時点で、警察庁警備局『回想・戦後主要左翼事件』(警察庁警備局、1967年、絶版)だけである。よって、以下の諸(表)は、それを、私(宮地)の独自判断で、分類・抽出した。
(表1) 後方基地武力かく乱・戦争行動の項目別・時期別表
|
事件項目 (注) |
四全協〜 五全協前 |
五全協〜 休戦協定日 |
休戦協定 〜53年末 |
総件数 |
|
1、警察署等襲撃(火炎ビン、暴行、脅迫、拳銃強奪) 2、警察官殺害(印藤巡査1951.12.26、白鳥警部1952.1.21) 3、検察官・税務署・裁判所等官公庁襲撃(火炎ビン、暴行) 4、米軍基地、米軍キャンプ、米軍人・車輌襲撃 5、デモ、駅周辺(メーデー、吹田、大須と新宿事件を含む) 6、暴行、傷害 7、学生事件(ポポロ事件、東大事件、早大事件を含む) 8、在日朝鮮人事件、祖防隊・民戦と民団との紛争 9、山村・農村事件 10、その他(上記に該当しないもの、内容不明なもの) |
2 1 1 |
95 2 48 11 20 8 15 19 9 23 |
1 5 2 3 |
96 2 48 11 29 13 11 23 10 27 |
|
総件数 |
4 |
250 |
11 |
265 |
(表2) 武器使用指令(Z活動)による朝鮮戦争行動の項目別・時期別表
|
武器使用項目 (注) |
四全協〜 五全協前 |
五全協〜 休戦協定日 |
休戦協定 〜53年末 |
総件数 |
|
1、拳銃使用・射殺(白鳥警部1952.1.21) 2、警官拳銃強奪 3、火炎ビン投てき(全体の本数不明、不法所持1件を含む) 4、ラムネ弾、カーバイト弾、催涙ビン、硫酸ビン投てき 5、爆破事件(ダイナマイト詐取1・計画2・未遂5件を含む) 6、放火事件(未遂1件、容疑1件を含む) |
|
1 6 35 6 16 7 |
|
1 6 35 6 16 7 |
|
総件数 |
0 |
71 |
0 |
71 |
(表)の説明をする。本来は、統一回復五全協が行なった武力かく乱戦争実態を、六全協日本共産党が、これらのデータを公表すべきだった。しかし、NKVDスパイ野坂参三と指導部復帰者宮本顕治ら2人は、ソ連共産党フルシチョフ、スースロフと中国共産党毛沢東、劉少奇らが出した「具体的総括・データ公表を禁止する」との指令に屈服し、(1)“上っ面”の極左冒険主義というイデオロギー総括だけにとどめ、(2)武装闘争の具体的内容・指令系統・実践データを、隠蔽した。そして、(3)今日に至るまで、完全な沈黙を続けている。
このデータは、『戦後主要左翼事件・回想』(警察庁警備局発行、1968年)に載っている数字である。そこには、昭和27年、28年の左翼関係事件府県別一覧、その1〜4が265件載っている。総件数を、(表1)の10項目、(表2)の6項目に、私の判断で分類した。(表2)件数は、すべて(表1)に含まれており、そこから武器使用指令(Z活動)だけをピックアップした内容である。この『回想』は、283ページあり、これだけの件数を載せた文献は他に出版されていない。もちろん、警察庁警備局側データである以上、警察側の主観・意図を持った内容であり、そのまま客観的資料と受け取ることはできない。しかし、五全協日本共産党による武装闘争指令とその実行内容を反映していることも否定できない。
(表1) 後方基地武力かく乱戦争行動の攻撃対象には、特徴がある。米軍基地、米軍キャンプ、米軍人・車輌襲撃件数は、11件/265件で、4%だけである。それにたいして、警察署等襲撃(火炎ビン、暴行、脅迫、拳銃強奪)、警察官殺害(印藤巡査1951.12.26、白鳥警部1952.1.21)、検察官・税務署・裁判所等官公庁襲撃(火炎ビン、暴行)件数は、145件/265件あり、55%を占めた。このデータ件数比率からは、次の判断が成り立つ。ソ中両党の日本共産党「軍」にたいする後方基地武力かく乱攻撃命令対象が、米軍基地・軍需輸送の直接破壊ではなく、後方基地日本全体の治安武力かく乱にあったのではないか。
(表2) 使用武器の大部分は、火炎ビンだった。ただ、使用総本数について、『回想』も明記していない。『戦後事件史』(警察文化協会、1982年)という、1232ページの警察発行の大著がある。そこでは、1952年6月25日、吹田事件翌日の新宿駅事件について、次の記述をした。「朝鮮動乱二周年目の二十五日、夕方から新宿の東京スケートリンクで行われた国際平和記念大会に集った約二千五百名が、散会後の九時四十分ごろ新宿駅付近にくり出し、警戒中の約千名の警官と衝突、例によって硫酸ビン、火炎ビンを投げつけて大乱闘となり、検挙者三十名、警官隊の負傷者二十名、新聞記者、カメラマンの負傷者三名を出した。投げられた火炎ビンはこれまでの事件では一番多く総数五十本以上で、投げ方も非常に正確であった」(378)。この本数を見ると、使用火炎ビン総数は、火炎ビン投てき件数35件で、数百本と推計される。
ただし、休戦協定成立と同時の日本共産党の武装闘争完全停止といっても、ソ連・中国共産党は、軍事方針廃棄の指令を出さなかった。日本における暴力革命路線を堅持させる指令だった。日本共産党は、2党の指示に従って、火炎ビン事件、警察署・警察官襲撃事件について完全に停止したが、暴力革命のための軍事委員会・中核自衛隊・山村工作隊活動を、武装闘争抜きで継続した。スースロフ指令によって、それらの軍事組織解体を決定したのは、六全協1カ月前の1955年6月28日である。
そこで、武装闘争責任論のテーマが問題になる。宮本顕治・不破哲三・志位和夫の論旨は、上記の内容で一貫している。責任論を検討する上で、組織統一回復・日本共産党の朝鮮戦争加担行為における、(1)指導部責任と、(2)復帰したが指導部から排除されたままの一党員(元指導部)責任とを区別する必要がある。
(1)、“スターリン認知”徳田・野坂中央委員会、および五全協選出中央委員個々人は、1年9カ月間の朝鮮戦争加担行為にたいして、完全な武装闘争責任を負っている。
(2)、宮本・蔵原・亀山幸三ら第6回大会選出中央委員7人・20%は、その期間、復帰したが指導部から排除されたままの一党員(元指導部)だった。主流派・臨中設立時に、排斥された7人中、袴田里見は、もっとも早く、モスクワで、スターリンに屈服し、北京機関指導部に“転向”したので、彼を除く6人は、組織統一回復共産党のたんなる一党員だった。よって、宮本顕治には、(1)の武装闘争指導部責任はない。
ただし、彼が自己批判書提出・復帰後、五全協武装闘争共産党の中央レベルで活動した証拠が出てきた。それは別ファイルで詳細に検証した。これらから見ても、「(現在の)わが党は、武装闘争になんの関係もなく、責任もない。なぜなら、それは、党分裂時の一方の側である徳田・野坂分派がやったことだからである」というのは、宮本式詭弁・ウソである。
『嘘つき顕治の真っ青な真実』屈服後、五全協武装闘争共産党で中央活動をした証拠
(3)、ましてや、六全協は、〔資料7〕で、不破哲三も完全に認めているように、スースロフと中国共産党指令を受けて、宮本顕治らとともに、武装闘争指導部責任を100%負っている五全協選出中央委員と袴田を、中央委員として選出した。死去した徳田球一と除名した伊藤律以外の、100%武装闘争責任中央委員のほぼ全員を選んだ。それは、宮本顕治の“スースロフへの屈服”とNKVDスパイ野坂参三との妥協の産物だった。それによって、彼個人も、六全協以降、野坂・宮本体制のトップとして武装闘争指導部責任を100%継承したことになる。彼は、その屈服・妥協の見返りとして、野坂・宮本トップ体制の党内権力を、ようやく手に入れた。

(1)、五全協で統一を回復した日本共産党が分担した朝鮮侵略戦争加担の戦争行為期間は、
1951年10月16日五全協軍事方針の実践開始から、1953年7月27日朝鮮戦争休戦協定
成立までの1年9カ月間である。
(2)、宮本顕治は、“分派組織”統一会議・宮本系のスターリン指令解散をし、宮本自己批判書
を志田宛に提出した。その直後からの「点在党員組織隔離報復措置」継続期間は、1951年
10月初旬宮本のスターリンへの“屈服”から、1955年3月15日スースロフ指令による野坂・
志田との妥協で宮本が五全協党中央指導部員に復活するまでの3年5カ月間である。
(3)、宮本は、その間、統一を回復した日本共産党に復帰しているが、「所属党組織もなく」、
隔離報復を受けて、宮本百合子全集の解説を執筆していた。よって、彼には、武装闘争遂行
に関して、統一中央役員としての指導部責任はない。しかし、五全協武装闘争共産党の中央
レベルの活動を1955年3月15日以降した。よって、武装闘争共産党の中央責任がある。
(4)、六全協は、死去した徳田球一と除名した伊藤律以外で、武装闘争指導部責任を100%
負う主流派・臨中・五全協側中央委員のほぼ全員を再選した。それにより、野坂・宮本体制の
トップとして、宮本顕治は、武装闘争指導部責任を100%継承したのである。
現在の党が、そのメンバーを全員含んでいる以上、「武装闘争は分裂した一方がやった
ことであり、(現在の)党にはなんの責任もない」というのは、宮本式大ウソ・詭弁である。
(表3) 六全協で、宮本顕治は武装闘争責任を100%継承
|
党役職 |
武装闘争指導部責任・個人責任 |
直接責任なし・復帰党員責任 |
比率 |
|
中央委員 |
野坂、志田、紺野、西沢、椎野、春日(正)、岡田、松本(一三)、竹中、河田 |
宮本、志賀、春日(庄)、袴田、蔵原 |
10対5 |
|
中央委員候補 |
米原、水野、伊井、鈴木、吉田 |
5対0 |
|
|
常任幹部会 |
野坂、志田、紺野、西沢、袴田 |
宮本「常任幹部会責任者」、志賀 |
5対2 |
|
書記局 |
野坂「第1書記」、志田、紺野。竹中追加 |
宮本。春日(庄)追加 |
4対2 |
|
統制委員会 |
春日(正)「統制委員会議長」、松本(惣) |
蔵原、岩本 |
2対2 |
|
排除中央役員 |
伊藤律除名。(伊藤系)長谷川、松本三益、伊藤憲一、保坂宏明、岩田、小林、木村三郎 |
神山、中西、亀山、西川 |
(8対4) |
|
総体 |
伊藤律系を排除した上での、武装闘争指導部責任・個人責任者の全員を継承 |
4人を排除した上での、旧反徳田5派との「手打ち」 |
この(表)は、小山弘健『戦後日本共産党史』(芳賀書店、1966年、絶版)の第4章1、六全協の成果と限界(P.183)の記述を、私(宮地)が(表)として作成したものである。その一部を引用する。
「発表された中央の機構は、政治局と書記長制が廃止されて、かわりに中央委員会常任幹部会と第一書記制が採用された。スターリンの死後、フルシチョフが集団指導を強調してソ連共産党に創始した一方式を、そのまま『右へならえ』式に、日本の指導体制に採用したものだった。((表)人事記述個所を中略)。みぎのような中央人事は、全体としてみると、旧徳田主流派が若干の優位をたもちつつ、旧統一会議系国際派とのバランスをはかってくみたてられていた。それは、六全協までのはなしあいの主体が、伊藤派をのぞいた旧主流派と神山・中西・亀山・西川らをのぞいた旧反対派との二つであったことを、あきらかにしていた。この事実は、下部における大衆的討議を一さいぬきにしたこととあいまって、六全協の限界と弱点を、はっきりばくろしていた」。
宮本顕治は、文化部関係人事で、宮本百合子らの宮本顕治崇拝者を抜擢し、一方で、強い宮本批判を持っていた原泉ら築地の文化人、中野重治支持者らを排除した。
1953年7月27日休戦協定成立と日本共産党への武装闘争完全停止指令の2年後、ソ連共産党スースロフと中国共産党は、日本共産党に六全協開催を命令した。ソ中両党従属下の日本共産党は、正式に日本における後方基地武力かく乱戦争作戦に終止符を打った。そして、分担した日本における朝鮮戦争行為を、2党の指示どおりに、日本共産党だけの「極左冒険主義」とだけイデオロギー規定した。ただし、2党は、日本共産党が軍事方針内容、武装闘争実態のデータ公表と具体的総括をすることにたいして、禁止命令を出した。さらに、スースロフは、NKVDスパイ野坂参三をトップと任命し、その名称もソ連共産党の衛星国となった東欧共産党・労働者党型と同じく、「第一書記」と命名した。2党の総括禁止・反対指令の存在も、不破哲三が、〔資料7〕で証言している。
宮本顕治は、2党の指令、武装闘争の総括・公表禁止命令、NKVDスパイとトップを組むという人事指定などの“談合、裏取引き条件”をすべて認めて、党指導部トップに復帰した。それ以降、現在に至るまで、宮本・不破・志位とも、軍事方針・武装闘争実態やデータについて、抽象的な文言以外、何一つ公表していない。そして、上記の言い分に固執している。
その言い分の論拠となるものは、党組織分裂期間の宮本式規定である。その内容は次である。1950年6・6追放翌日の主流派・臨中設立、非合法機関化以降、1955年7月27日六全協まで、5年間2カ月間の党組織分裂期間が続いた。党組織統一回復は、五全協からではなく、六全協からである。この宮本式規定が正しいのか、真っ赤なウソ・詭弁かどうかが、『盲点』となる。
宮本・不破・志位の言い分が論理的に成立する可能性が一つだけある。それは、宮本顕治特有の党規約だけに一面的に依拠した形式論理である。その思考・詭弁スタイルを検討する。ただし、以下の宮本主張内容は、私が、『日本共産党の五〇年問題資料文献集全4巻』(新日本出版社、1957年)、宮本顕治『五〇年問題の問題点から』(新日本出版社、1988年)における膨大な宮本論文、発言などを読んだ上で、その根底に潜む、彼の深層心理と本音を、私なりに抽出したものである。
〔宮本式形式論理・詭弁1〕、諸会議の党規約上正当性の有無
1947年12月21日の第6回大会は、党規約上、正規の会議であった。
しかし、1950年6月7日の主流派・臨中設立・国内非合法機関、北京機関などは、スターリン、毛沢東の指令によるものとはいえ、第6回大会規約から逸脱した誤りであり、反党的規律違反である。また、全国協議会は、第6回大会規約にもなんらその規定がない以上、四全協・五全協とも、党規約違反の会議である。それは、誤りというにとどまらず、会議の存在と諸決定自体も、党規約上認められない。
第6回大会以降で、党規約上正規の会議は、1958年7月23日の第7回大会のみである。その10年7カ月間に発生した軍事方針・武装闘争の実態、北京機関が日本国内に指令したことは、すべて第6回大会党規約に違反している。よって、第7回大会以後の現在のわが党は、1年9カ月間の軍事方針・武装闘争内容にたいして、また、その間に発生した諸事件や伊藤律27年間中国幽閉問題などに、なんの関係もなく、責任もない。コメントする必要も、義務もない。
〔宮本式形式論理・詭弁2〕、分派問題と党規約との関係
その間、第6回大会規約を正しく堅持していたのは、私(宮本)と蔵原2人の中央委員のみである。なぜなら、(1)徳田・野坂らは、規約を守っていた正規の中央委員会(2人)にたいする分派であり、そちらに所属した中央委員数28人・80%や分派側党員数90%の圧倒的多さに関係なく、徳田・野坂分派と呼ぶのが正しいからである。また、(2)排斥された中央委員7人の内、宮本・蔵原2人以外の5人は、方針・行動ともに極左分派に陥った。よって、その5人も、極左的な規律違反を犯した以上、正規の中央委員会を代表しえないからである。
(1)徳田・野坂らが規約違反の反党的分派を結成し、(2)7人中5人が規約違反の極左的分派に転落したからには、正規の第6回大会中央委員会は、私(宮本)が体現している。私たち2人(宮本顕治と蔵原)こそ、「我輩は“党”である」と宣言できる、第6回大会党規約上の正統性を保持している中央委員会そのものである。
〔宮本式形式論理・詭弁3〕、統一会議・宮本系結成、解散と六全協
私(宮本)は、蔵原と2人で、統一会議・宮本系を結成した。徳田・野坂分派28人と極左分派5人とが、先に党規約違反を犯して、党組織を分裂させた以上、私が、やむなく対抗組織を作ったことは、党規約上許される。それは、レーニンが、ロシア社会民主党内において、メンシェヴィキ分派に対抗して、当初、少数派のボリシェヴィキ分派を結成したことが、正当であったことと同じである。
ただし、スターリンの「宮本は分派」という裁定によって、統一会議・宮本系の組織解散をし、自己批判書を提出した。また、規約上正当でない六全協では、スースロフの指令によって、徳田・野坂分派および極左分派とも妥協した。しかし、これは、主流派・臨中以降5年間の組織分裂を止め、わが党の統一と団結回復のためにしたことであって、なんらやましいことはない。
〔宮本式形式論理・詭弁4〕、現在のわが党と軍事方針・武装闘争との関係
第6回大会規約から見て、第7回大会以降における現在の、わが党は、規約違反の徳田・野坂分派が行なった五全協の軍事方針・武装闘争などの、いかなる行動・事件にたいして、なんの関係もなく、責任もないのは当然である。その具体的総括や武装闘争データをいまさら公表する義務もない。なぜなら、「六全協・秘密付帯決議」で、それらの誤った方針を「廃棄する」と秘密に決定しているからである。廃棄・削除した武装闘争データやファイルを、ごみ箱あさりによって、回復させよ、とでも要求するのか。
たしかに、六全協前後において、武装闘争の具体的総括とデータを公表し、その指導部個人責任を明らかにすべきという意見がかなり出た。しかし、野坂・宮本指導部トップの一人となった私には、そもそも武装闘争指導部の個人責任はまったくない。「点在党員組織隔離報復措置」を受けていた私個人に、現書記長として、武装闘争指導の自己批判をせよ、とでも言うのか。たしかに徳田・野坂分派指導部に武装闘争の個人責任は存在する。しかし、六全協後の党は、党の統一と団結を回復させることが最優先課題である。その当時の誤りをほじくりかえすことは、団結回復にマイナスとなるだけである。それを要求するのは、打撃主義・清算主義の思想である。
これらの宮本式形式論理を、(1)正当性があるとして認めるのか、それとも、(2)彼特有の詭弁・ウソとするのかで、以下の〔資料1〜7〕の読み方が、まったく異なる。
(注)、これは、不破哲三『日本共産党にたいする干渉と内通の記録、ソ連共産党秘密文書から・下』(新日本出版社、1993年)の第十部「干渉主義の戦後の起点」における「党中央委員会の解体、党の分裂と極左冒険主義」の内、『四全協から五全協』に関する個所(P.322〜326)の抜粋である。
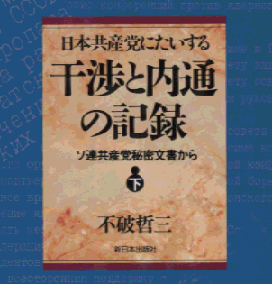
―――――――――――――――――――――――――――――――
「北京機関」と中国流「武闘」方針のもちこみ
実際、党の統一を破壊した徳田派は、朝鮮戦争下の日本に、日本の情勢をまったく無視した、外国じこみの極左冒険主義の方針をもちこみ、日本人民の闘争にかつてない悲劇的な事態をうみだし、拡大したのです。極左冒険主義のもちこみが、日本で問題になったのは、このときがはじめてでした。一九五〇年六月の徳田派の一方的な地下潜行は、この分派の主要な幹部が中国に亡命する国外脱出計画に連動してゆきました。八月末には徳田が、九月には野坂が、あいついで中国に亡命し、北京に分派の指導機関をつくりました。これが、いわゆる「北京機関」です。「北京機関」は、最初からソ連共産党や中国共産党に財政的にもまるがかえにされた「機関」で、これが、徳田派の最高機関となりました。(P.322)
彼らは、ソ連や中国の党指導部の直接の指揮下に、彼らにつながる国内の諸組織を指導し、中国の武装闘争をまねた極左的な「軍事闘争」方式を強引にもちこみました。この極左冒険主義の方針は、日本の革命運動、民主運動に大混乱をひきおこし、簡単にはいやすことのできない深刻な損失をもたらしました。
五一年二月の徳田派「四全協」
徳田派は、この方針を系統的な形でまとめあげた「軍事方針」を、翌五一年二月、「第四回党全国協議会」と称する全国会議で決定しました。これは、党規約になんの根拠もない、不法な会議でした。(P.323)
スターリンが参加したモスクワ会議
一九五一年の四月、徳田、野坂、西沢隆二ら「北京機関」の代表者たちは、モスクワによばれました。そこで、「日本共産党の綱領」(いわゆる「五一年綱領」)と、「四全協」での方針をより“精密化”した「軍事方針」などの作成にあたりました。この作業は、スターリンの直接の指示と監督のもとにおこなわれました。スターリンが参加した会議も、数回にわたってひらかれ、中国共産党の王稼祥対外連絡部長も参加しました。
とくに「五一年綱領」は、スターリン自身が筆をとってしあげたものでした。「軍事方針」も、スターリンが、朝鮮戟争の「勝利」の展望と結びつけて問題提起をし、それにもとづいてつくられたものでした。
これらの文書の作成が終わった段階で、五一年五月に、最後の会議がおこなわれました。そこには、ソ連側からはスターリンを中心に、マレンコフ、ベリヤ、モロトフという当時の政治局の中心人物、中国側からは対外連絡部長の王稼祥が出席し、日本側からは、「北京機関」の代表である徳田、野坂、西沢の三人とともに、全国統一委員会に属していた袴田が出席しました。(P.325)
「五一年綱領」と新「軍事方針」
この会議で確認された「軍事方針」も、「四全協」での「軍事方針」をさらに発展させたものでした。「四全協」の「軍事方針」は、武装闘争の一般的な方向をうちだしはしたものの、その中身はまだ抽象的で不十分だとされたのです。こんどの「軍事方針」は、スターリンが最初に基本的な問題点を指示し、それにそって日本側でつくった案を、ソ連側で最終的に手をいれるという形で、仕上げられました。これも、スターリンが提起し、スターリンの指示と参加のもとにつくられた、スターリン的な方針で、「四全協」の方針とくらべて、武装闘争や武装組織づくり(「中核自衛隊」、山村に武装闘争のための根拠地をつくる「山村工作隊」など)にいっそう本格的に、いっそう大規模にとりくもうとするものでした。(P.326)
〔資料2〕、小山弘健『コミンフォルム判決による大分派闘争の終結』(全文)
(注)、これは、小山弘健『戦後日本共産党史』(芳賀書房、1966年、絶版)の第二章「大分派闘争の展開、1950〜1951年」における第8節「コミンフォルム判決による大分派闘争の終結」(全文、P.122〜129)である。
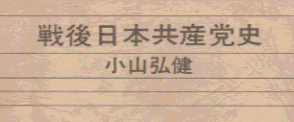
―――――――――――――――――――――――――――――――
第8節 コミンフォルム判決による大分派闘争の終結(全文)
反対派の中心たる統一会議の分裂、関西派や春日・亀山の中央への統一申しいれとなるにおよんで、全国ビューローとしては、なんらかこれへの態度をあきらかにせねばならなくなった。それで、八月中旬に全国統一会議の全国代表者会議をひらき、統一方針の根本的検討をおこなうことを、全国の反対派によびかけた。宮本派は、そこで関西派や春日(庄)派の屈服方針と対決し、できれば党統一についての自派の主張を全体の決議にまでもっていき、ゆるんだ統一会議の全国組織をかためなおそうとかんがえた。このため、長文の全国代表者会議への報告草案をつくりにかかった。ところが、事態は突如一変した。八月一三日に、山田ら関西地方統一委員会は、無条件復帰交渉の前提として自派組織の解消を決議したが、その翌一四日に、決定的な報道が「モスクワ放送」としてはいってきたのである。その内容は、八月一二日付のコミンフォルム機関紙『恒久平和と人民民主主義のために』が、二月の四全協における徳田派の一方的な「分派主義者にたいする闘争にかんする決議」をはっきりと支持し、分派活動は日米反動を利するだけだからあくまでこの決議をまもりぬけとアピールしているという、おどろくべきものだった。
このコミンフォルムの判決は、反対派の全グループにとって青天のへきれきであり、致命的一げきだった。これよりまえ、中央委員少数派は、徳田・野坂ら主流派の指導分子が、占領軍当局と日本政府の追及をのがれて、日本を脱出したことを知っていた。徳田らは北京その他の国際友党勢力に援助と協力を依頼し、同時に党内闘争にかんして自派に有利な工作をおこない、国際的支持をえようとはかるものとおもわれたから、これとの対抗上、宮本・春日・袴田・蔵原・亀山らが話しあった末、自分らの立場を訴えるため、一九五〇年の暮にまず袴田を中国に先発させたのだった。それでいま、コミンフォルム機関紙がはっきりと主流派支持の声明を出したことは、党内闘争の双方の代表の意見をきいたうえで、北京よりむしろモスクワ(スターリン)の線がこれに判決を下したものと想像されたわけである。とにかく、これによって、もはや論議の余地はなくなった。八月一六日、関西地方統一委は、無条件復帰による党統一の完了の決議をおこなった(「コミンフォルム論評にかんする決議」)。予定した全国代表者会議はかたちだけのものとなり、一八日には、関東地方統一会議指導部が主流指導下の各機関への折衝開始と全組織の解消を決定した(「党統一にかんするコミンフォルム論評とわれわれの態度」)。反対派の屈服による分派闘争の終結は、時期の問題となった。
他方、コミンフォルム判決で勝利を確認された主流派は、八月一九〜二一日の三日間にわたり、東京都内でひみつに第二〇回中央委員会をひらいた。第一九中総いらい一年四カ月ぶりの、しかも四全協とおなじく完全に徳田派だけで一方的にもった規約無視の中央委員会だった。徳田ら海外にわたった以外の地下指導幹部に、椎野や志賀もこれに参加したものとみられた。この会議では、「党の統一にかんする決議」など五つの決議が採択され、四全協で採択された改正「党規約草案」も承認された。党統一にかんする決議は、徳田主流派が絶対に正しかったという前提にたち、反対派にたいして復帰の団体交渉とか集団的復党の方式を一さい拒否、てってい的な自己批判と分派にたいする闘争をちかうことを条件とする「無条件屈服」のみちだけをみとめた。この党統一にかんするものをふくめて、五つの決議は、九月六日付『内外評論』(第二巻第一八号・通巻第二七号、または『健康法』第二七号)にすべて発表された。
重大なのは、この会議が、党の実さいの指導の中心が非公然指導部におかれるべきこと、非公然中央こそ全党唯一の指導機関たらねばならぬことを確認したうえ、まえの五〇年テーゼ草案の処理に一言もふれずに、突然「日本共産党の当面の要求―新しい綱領(草案)」なるものを提出し、これを全党の討議にふすると決定したことだった。のちに(中ソ論争がおこってから)あきらかにされたところでは、前記のように日本から北京に密行し、さらに、モスクワに行った徳田・野坂らが、スターリンに日本の党内問題についての裁定を乞い、さらにこのあたらしい綱領の作成をも乞うて、かれらの立会いの下にスターリンみずから筆をくわえたのであった(一九六四年四月一八日「日本共産党中委にあてたソ連共産党中委の書簡」)。しかし、この当時、新綱領草案がなぜ旧徳田テーゼにかわって突然提出きれてきたのか、どのような順序でどのような機関で作成されたのか、一般には全然知らきれず、党内でもたんに、「権威」のある国際組織の協力ないし指示のもとにつくられたことが示唆されただけだった。会議のあと、これは特別のあつかいでもって公然面の全党機関に提示された。
かくて一年余にわたる党史上空前の分裂抗争は、組織的には全反対派の主流派への無条件屈服というかたちでの復帰、思想的には新綱領のもとへの全党の理論的統一というかたちでの収束によって、はっきりとかたがつけられた。八月二三日付『内外評論』(第二巻第一七号・通巻第二六号、または『健康法』第二六号)は、海外で袴田が書いたとみられる「私は分派と一切の関係を断ち、分派根絶のために闘争する」という自己批判文を、八月九日付「同志袴田里見の自己批判について」という主流がわの前がきをつけて掲載した。袴田は前述のように、宮本以下反対派中央委員たちの先発として、自分や反対派と徳田派との対立について国外の「権威」の判定をあおぐために、日本をはなれていた。だからかれが無条件で屈服してしまった事実は、あらためて、モスクワでのスターリンの裁定が主流派を是とし国際派を「分派」として断罪したこと、その結果がさきのコミンフォルムの四全協対分派決議の支持となり、さらに新綱領となってあらわれたこと、等を確認させたのである(後年に、スターリンの前で徳田と袴田が論争し、スターリンの一かつで袴田が自己批判書を書いたことが明らかにされた)。
こうして、八月下旬から九、一〇月へかけて、反対派の各グループがなだれをうって解体していった。もっとも強硬に徳田派の粉砕をさけんでいた国際主義者団は、もっともはやく復帰の方針をさだめて、八月二三日付主流派・臨中への「申入書」で、「自己の分派を一切の痕跡を断つまで解消させる」決意をのべ、主流派・臨中がそのために「心からの援助を与えられんことを切にお願い」した。九月には、「団結派」が解散大会をひらき、そこでの報告「党統一の勝利的発展とわれわれの態度」において、「論評」に支持された主流派・臨中の基本的ただしさと反対派のまちがいを無条件にみとめ、四全協と主流派・臨中を承認し、みずからのグループ解体と無条件的復帰申しいれとを確認した。また八月には、春日庄次郎が秋月二郎の名義で、「私の自己批判―本当に党と革命に忠実であるために」「××同志諸君へ自己批判書を書きおえて」の二つの文書を書いた。一〇月、統一会議の指導部は「党の団結のために」を声明、そこで自分らの主観的意図にもかかわらず「日米反動に利する結果となった」ことをみとめ、げん重な自己批判とともに「ここにわれわれの組織を解散するものである」と宣言した。この年四月、津々良・西川らを中心に労働組合運動での反対派組織として結成され、その後活動をひろげつつあった全統会議(全国労働組合統一情報委員会)も、一〇月五日の第四回代表者会議で、国際批判に順応して解消することを決議した。
こうして、春日派・宮本派、関西や中国やその他の統一会議系地方組織、国際主義者団・団結派・神山グループなど、いずれも組織の解散をおこない、個々に自己批判のうえで復帰を申しいれるという方法をとった。すべてがみずからを「分派」とみとめ、自分ら分派のあやまりをみとめ、その完全な敗北を承認したのである。中央指導部がわは、かれらにたいして、復帰条件として、新綱領と四全協規約の承認・分派としておかしたあやまちの告白と謝罪、克服と清算を、容しゃなく要求した。ただ反対派のなかでも、まだ一部の分子(新日本文学会、その他)は中央への屈服をがえんじなかった。だがかれらの反対派としての力は、武井昭夫・安東仁兵衛らの全学連グループなどのほかは、その後ほとんど実さいに発揮できなかった。この武井らの抵抗も、翌五二年三月の全学連第一回拡大中央委までしかつづかなかった。
とにかく、党の分裂抗争は、不正常なかたちで突然に終止符をうたれた。コミンフォルムの一匿名論文をきっかけにはじまった大分裂は、中共からの勧告で大きくゆれ、さいごにまたコミンフォルム(スターリンの意思を表示した)の一片の判定によって、あっけなくうちきられた。ここに一貫してみられる特徴は、全党および全党員の思想性のよわさであり、自主性の欠如であり、大衆的組織力の不足であり、実践的基盤のぜい弱さであった。軍事占領への認識や独立問題の意義を外国からの批判でさとるということ自体が、すでに思想の自立性をうしなっている証拠だったが、こうした内的弱点への反省の欠如は、このあと全党あげてスターリンや北京の権威にたいする隷従主義に埋没し没入してしまう結果となってしまった。このため、反対派の徳田派との闘いの正当さも抹消きれた。
なにより問題なのは、最初のコミンフォルム(スターリン)論評が形式的にまちがっていたところへ、さいごのコミンフォルム判定が、形式でも内容でもまったくまちがっていたという事実だった。分裂とその後の統一阻止の最大の発意者、責任者は徳田書記長であり、その連帯責任者はかれと結びつく中委多数派とそのグループであった。かれら徳田派閥分子の専断的行動・規約無視・家父長的支配などに、主要な分裂原因があったのである。これとたたかううえで、中委少数派と反対派分子の態度も、すべて正しいとはいえなかった。しかし分裂をひきおこし、その後の統一の再三の機会をぶちこわした徳田派の政治責任は、どんな口実や代償をもつてしてもさしひきできないものであった。ところがコミンフォルムは、ここへ、一国の党内問題に直接介人するというあやまりと、きらに両者の正否に不当な判断を下すというあやまりと、二重のあやまりをもちこんだ。この二度目の判決が、最初の論評で党分裂の動因をあたえたことへのあと始末だったとみることができるとしても、コミンフォルムがすでに一年余にわたる深刻化した党内闘争に外部から直接介入して一方のがわに加担したことは、本来的にまちがった行為だった。しかもその判決内容がまちがっているとすれば、これを弁護しうる余地はまったくないのである。
このようなコミンフォルム=スターリンの誤りにもかかわらず、日本共産党を圧倒的に支配するスターリン権威主義の力は、反主流派を無条件屈服に追いやった。もっとも強硬だった野田派から、宮本・袴田・春日・神山・亀山・中西らのすべてが、国際権威の威力に無条件に支配されて、コミンフォルム判決に一言の反対も異存もなく、一方的に自分らのあやまりを認め、規約違反の歴然たる主流に復帰をねがうというさんたんたる状態となったのである。このようなまちがった国際的判決と、それのまちがったうけいれからなされた「統一」が、順調に完了するはずがなかった。その後主流派の一方的独裁化と反対派の屈服による無力化が一般化していき、ついには主流派指導下に全党あげての極左冒険主義への突入となるのである。
ところで、過去一年半にわたる分派闘争は、このとき全体として占領軍や政府からの直接の攻げきの激化と加重して、深刻な打げきを党と大衆にあたえた。外からの圧迫と内からの相克の重奏のもとに、党はてってい的によわめられ、革命勢力は大はばに後退した。とくに分派闘争の同志あい食むせいさんなありかたは、多くの大衆団体・労農組織に直接これがもちこまれたため、いたるところ恐るべき破壊作用をおよぼした。産別会議とその傘下労働組合、日本農民組合の各地支部、全学連、学生社会科学連合会、民主主義科学者協会、婦人民主クラブ、新日本文学会、歴史学研究会、帰還者同盟、平和ようご日本委員会、日ソ親善協会、新劇グループ、その他党員グループや党細胞が有力な指導力を発揮した多くの大衆団休に、苛烈で非人間的な、ときには低劣と卑劣さにみちた分派闘争のどろじあいがもちこまれた。党と大衆団体の区別は無視きれ、党内闘争をそのまま大衆のなかにもちこみ、反対者を大衆団体から放逐するなど、あらゆるまちがった処置がとられた。このため、戦後誠実な党員の努力と力量で維持され発展してきた多くの大衆団体が、めちゃくちゃに撹乱され破かいされ、運動全体としてはかりしれない害毒をおよぼした。
分派闘争の非人間的な実相は、敗戦後理想と情熱をもって党に参加してきた多くの若い純心な党員たち、誠実で有能な勤労者党員たちに、むざんな打撃をあたえ、かれらの多くを失意と絶望のなかにおいやった。大なり小なり、肉体的精神的にぎせいをはらわせられ、党にたいするかれらの信頼はグラつき、共産主義や革命運動そのものへの疑惑すらいだかせるにいたった。多くの学生・青年分子が、生涯二度と回復しえない精神の深傷を負って、永久に党からはなれていった。それだけでなく、分派闘争は、党周辺の多くの先進分子・同調分子にも党への深刻な不信をよびおこし、かれらを急速に党からはなれさせた。終戦後の熱心な活動によってえた影きょう力は、ここに大きく減退した。
党内闘争に全エネルギーをうばわれて、党はこの時期、日本の大衆が当面した多くの問題に、十分の力を注ぐことができなかった。朝鮮戦争のぼっ発から講和会議の準備にいたる重大な転換期に、党はいたずらに内争にエネルギーを消耗し、相克と憎悪につかれはて、大衆闘争を組織することも有効な政治指導をしめすこともできなかった。前年の不当なレッド・パージはじめ、占領軍と官憲のたえまないだん圧迫及があったとはいえ、こうした内争は党の大衆にもつ好きょうを根底からおしつぶしたのである。一七〇万をこえる強大さをほこった産別会議が、この五一年末一きょに三万数千名の弱小勢力に転落したほか、党外郭の多くの大衆団体がその基盤をうしなった。これらすべての事実にたいして、主流派・反対派をとわず全党員が、それぞれの地位と役割におうじて責任を問われねばならない。
(注)、これは、亀山幸三『戦後日本共産党の二重帳簿』(現代評論社、1978年、絶版)の第4章「四全協とあいつぐ自己批判」の内、第3節「椎野自己批判から五全協にいたる経過」全文(P.152〜160)である。彼は、主流派・臨中によって排斥された第6回大会選出中央委員・国際派7人中の一人であり、第7回大会でも中央委員になった。第8回大会の綱領問題と選挙方針問題で、党中央と意見が対立し、1961年末除名された。この文献は、7人中では、蔵原以外に、もっとも宮本顕治と近い関係にあった中央委員の証言である。下記の「経過表」は、私(宮地)が、内容を変えずに、算用数字表に直した。

―――――――――――――――――――――――――――――――
椎野自己批判から五全協にいたる経過
8・14コミンフォルム論評の放送から五全協にいたる経過表
|
月 |
日 |
事項 |
|
8 |
14 16 18 19 中旬 |
モスクワ放送が8・10付コミンフォルム機関紙に「四全協、分派に関する決議」掲載を放送(国際批判) 全国統一会議系の全国代表者会議(埼玉会議)開かる(宮本派) 関東統一会議指導部、モスクワ放送を受け入れ、組織解消を声明(宮本派) 党中央部(所感派)第20回中央委員会開く、「新綱領」提示と「党統一の決議」 袴田自己批判を主流派・臨中側公表す(所感派) |
|
9 |
4 8 上旬 |
椎野ら一九名に公職追放、逮捕令出る。岩田英一、細川嘉六、山辺健太郎ら逮捕 サンフランシスコ平和条約、日米安保条約調印 春日庄次郎自己批判を公表、復帰承認(春日派) |
|
10 |
上旬 16 中旬 22 |
宮本ら「党の団結のために」発表。宮本、自己批判を三回書き直し、復帰承認される。蔵原も同じ(宮本派) 五全協、新綱領、新中央委員決定、伊藤律政治局より落ちる(所感派) この頃、亀山自己批判公表、復帰承認される(亀山派) 主流派・臨中議長に小松雄一郎を指名、部員、塚田大願、梶田茂穂を届け出る(所感派) |
この表のように、春日派、宮本派、所感派・主流派・臨中派の三者三様に、たくさんの文書が、みだれとぶ中で、突如として八月一四日のモスクワ放送は主流派・臨中側の四全協決議「分派主義者にたいする闘争にかんする決議を全面的に支持する」という、コミンフォルム機関紙の内容を放送した。要するに「分派は誤っている、直ちに自己批判して党中央の下に復帰せよ」というのである。もっともあわてたのは、もちろん宮本派=全国統一会議=全国ビューローであった。一八〇度の方向転換が必要になったからである。彼らはそれまでは春日派内部にも自分らの仲間を送り込み、主流派・臨中との折衝をひそかに調べて、それと競合する形で主流派・臨中側と交渉を進めていたが、こんどはそれがきかない。全国代表者会議(埼玉会議と呼ばれている)も直ちに組織解消の方向を決定した。
ところが、ここで意外なことに、春日派にも大異変が起こった。所感派と無条件復帰、統一の話し合いが九分通り決定していた(実際には全部合意していた。だから関統委議長・山田六左衛門は合意事項を全国ビューローに提案したのである)。春日らは、八・一四放送が出ると一挙に、非常にはげしい、徹底的な自己批判の立場にかわったのである。それはまったく一方的に「われわれだけが全部誤りであった、自己批判して復帰する」というコースであった。私は連絡を受けてすぐ大阪へゆき、春日のアジトで彼の自己批判書を見せられたとき、彼の激変に非常におどろき、ついで勃然とした怒りがこみ上げてきた(このとき、私も自分の自己批判の大綱を書いて持参した)。それははや八月も終わるころであった。志賀や袴田の自己批判にあれほど批判的であった春日が同じようなボーズ・ザンゲに陥ることは私にはどうしても容認出来なかった。要旨は次の通り。「私らの属した分派の誤りと有害性はもはや明白である」に始まり、「われわれの誤りは単に組織上においてのみならず、思想、政治、戦術その他、党活動の全面に及ぶものである」とし「一九五〇年一月のコミン論評とそれにたいする政治的所感―その時点で所感に反撃したのは正しかったが、そもそもその反対した当初から自分の心の中には若干の分派主義があった。あの誤れる志賀意見書にたいしてもその分派的反幹部的気勢に援助を与えた」というものである。要するに初めから自分らに分派意識があり、それから分派行動が始まったというものである。このような考え方は、たとえ春日個人の心の奥にそういうものがあったとしても、下部で何百人、何千人の同志が春日や私らとともに、所感派・主流派・臨中の党破壊の行動に抵抗して闘っている、その階級的、愛党的精神を根底から否認するものであった。春日自己批判はいわば悪魔の前に罪の許しを乞うようなもので、とうてい私らの良心が許容出来るものではなかった。春日自己批判の中には、「こういう自己批判はわれわれの良心が許さないといぅものもあるだろう、その良心云々こそ、分派的良心である」と書いている。私はこういう他人の腹の内を見すかしたような先取り批判にたいして、彼の心の中に強い非同志的感覚が横たわっているのを見出し慄然とした。
春日の自己批判は明らかに一種の自虐趣味まで含まれるボーズ・ザンゲであり、ある意味では徹底した個人主義、ニヒリズムであった。志賀、袴田らのそれは他人に責任転嫁をはかる利己的な、いわば汚い自己批判であったが春日のそれは、その利己主義がないために、いっそう誤りの深いものであった。私はいつかはこれらをまとめて公開し、追いつめられた共産主義者のきわめて非現実的な、また、きわめて観念論的精神構造を分析したいと思っている。こういうボーズ・ザンゲ、復帰のコースをかりに「Aコース」としよう。
宮本派のほうはどうか。彼は全国代表者会議を招集し、政治組織方針をきめ、いっそう強固な分派組織をつくろうとしていた矢先だから、八・一四によって内部は文字通りてんやわんやになったそして全国代表者会議どころでなく結局は「自己批判して復帰しよう」というのが大勢をしめた。ここでも大別して次の三通りになった(この点は安東仁兵衛の『日本共産党私記』に委しく出ている)。
第一は「やはりわれわれが根本的に誤っていた、自己批判して復帰しよう」とするもの、すなわちこの場合にも、われわれが全面的に、徹底的に誤っていたとするもの(不破哲三、現在、共産党書記局長がその先頭であった)と、もう一つは、われわれは負けたのだから仕方がない、自己批判して帰ろうとするもの(力石定一ら)の二通りがあった。これらはだいたいのところ「Aコース」またはそれに近いものといえる。
第二は、われわれは部分的には間違っていても、基本的には正しかった。したがって、根本的にわるかったという自己批判は出来ない、それで復帰出来ないとすれば、それも仕方がない、というものであって武井昭夫たちの主張で、これはごく少数であった。それをかりに「Cコース」としよう。
第三は、われわれの現実は分派である。内外情勢はこの状態を許さないほど切迫している。そのことは明白だから、われわれが自己批判出来るところだけ、自己批判して、復帰しよう、とするものでこれをかりに「Bコース」としよう。
宮本派のみならず、いずれの派であろうと、コースはだいたいこの三通りしかないのは当然である。宮本派でも日本帰還者同盟(土居祐信、高山秀夫ら)はだいたいAコース、新日本文学会の党員はおおむねCコース(中野重治の場合はよくわからない)、中国地方委員会と全学連系の党員は、およそBコースだが、そのいずれの集団にもA、B、Cの三通りに内部は分解していった。
ところで宮本自身はどうであったか。彼自身は、当時の文献をいっさい隠しているので、十分明らかでない。彼が自己批判をして復帰したことは明白な事実だが、その内容はいまもって明らかにされていない。彼がCコース=「基本的な自己批判はない、復帰しなくてもよい」というのではなかった。結局は何回か書き直しを命ぜられて、それにしたがったのだから、Aコースか、それにごく近いもので復帰することが出来たはずである。
さて、宮本の本音はどうか。資料集第三分冊一九三頁に「党の団結のために(一〇月)」なる文書が載っている。それには編者(宮本のこと)注として「この声明は五一年十月、中央委員会の機能の回復等を主張して共同していた中央委員たち(要するに宮本と蔵原だけ)が発したものである」と書かれている。この声明の内容は明らかにBコースである。いわく、「統一した党の中に別組織をつくることは分派となり、明らかに誤りであるが、分裂状態におかれた場合には、統一のための組織的手段もまた止むを得ないと信じてきた。しかしわれわれのその主観的意図にもかかわらず、党の分裂を克服出来ず、分裂状態の継続は客観的に日米反動に利する結果になった。この点についてわれわれは厳重に自己批判する。それを教訓とすることを決意し、ここにわれわれの組織を解散するものである」と、なかなか立派なものである。これは明らかにBコースである。それが認められて復帰したとすれば、私などとも同じであり、何もいうことはない。ところがこの文書は当時どこに出されたものか、誰も知らないし、また筆者の署名もない。宮本と蔵原の二人か、せいぜいそのほか数人の間で回し読みされたぐらいで、いわゆる国際派党員はほとんど誰も見ていないしろものである。こういう文書を“発した”などと注釈をつけて資料集に載せる宮本が如何に自分の面子と無謬性を守ろうとしていたかを示して余りあるものといえよう。
しかも宮本の本音はこのBコースではなく、実際はCコースであったことは明白である。宮本は当時もいまも自分がいささかでも誤りを犯したなどとは全然考えていない。当時、国際派党員の間で「官本はどうしてもモスコーへいって、黒白をつけるといっている。船が手に入らなければ、タライの舟にのってでもゆくといっている」という風評が広く伝えられた。私は「その話はデマだ。むしろ、国際派内部を牽制する謀略で、宮本が自分を取りつくろうためにすぎない。彼は実際は何が何んでも復帰コースをとるはずだ。そして、下部の同志にはそういうデマによって『自己批判すべきところは正直に自己批判して復帰する』という党員としてのあたりまえの線(Bコース)を崩そうとしているのだ」と一笑に付していた。これは単なるエピソードではなく、当時、ある機関紙に掲載されたものである。いわゆる宮本のタライ舟による日本海横断論である。
のちに彼自身が書いた「経過の概要」(これも公表はされていない。私はこれを神山茂夫から入手した)によれば、次のようになっている。「八・一四放送後、別項の声明(資料集(3)参照)を発し、中央委員の指導体制を解体す、この間、期限つきで、自己批判の提出を……これに応ず。また、経過措置として主流派・臨中側との交渉、地方組織の統合その他に他の諸同志とともにあたる」と。
ここには、はっきりと「自己批判の提出を……(求められ)……これに応ず」(括弧内は筆者)となっている。また、私がずっとあとに宮本から直接聞いたところでは「三度書き直しを命ぜられた」という。その通りであったと思う。いずれにしても簡単な、前記の「党の団結のために」なる文書ぐらいの線で復帰出来たのではなかったことは明らかである。宮本は八・一四のあとすぐに、大急ぎで全国統一会読を解消し、ついで下部の統一と復帰などはすべて他人まかせにして、自分のことだけに専念した。神山とも前日まで緊密であったが、すぐ連絡を切ってしまった。宮本派はほとんどすべてバラバラになった。もしも宮本がBコースならば、論理の必然として、宮本派の内部がバラバラになることはあり得ないはずである。宮本が三回も書き直して、非常にボーズ・ザンゲに近い自己批判を提出し、それがみとめられた段階でようやく復帰したことは間違いない(なお、このさい、宮本と蔵原、中野重治が同一歩調であったと思う)。そして宮本自己批判は杉本文雄の手を経て志田重男の懐に入ったことは明白である。椎野はそれを見たことがないという。この頃は所感派の中ですでに志田のへゲモニーが確立されていたらしい。ところで、宮本がいくら隠しても、自己批判を出したことは明白である(これを立証する証拠もあるが、それはあとで、五〇年間題の総括論争のときにふれることにする)。しかるに宮本はそのことを、その当時もいまも、ひた隠しに隠しつづけているところに、彼の政治的、思想的誤謬の根が横たわっている。嘘は次の嘘をつくり、さらに大きな虚妄につながってゆく。ともあれ宮本は、かなりAコース(ボーズ・ザンゲ)に近い自己批判を書いて復帰した。もっとも彼が自己批判を書くのは非常に苦しかったに違いない、というのは、彼の本音は「Cコース」であり、建て前は「Bコース」であり、現実に書いたか、書かされたものは「Aコース」に近いものであったからである。それゆえに、それは本質的に虚偽の自己批判であるから、人に見せられるようなしろものではない。宮本がひた隠しにするのもわからぬではないが、共産党の指導者の態度としては、まったくいただけないことはもはや多言を要しないであろう。
(注)、この正式題名は、『党の団結のために』声明(『日本共産党五〇年問題資料文献集3』P.193)である。文末にあるように、「1951年10月」となっているが、日付は書かれていない。また、声明署名者はなく、宛先もない。しかし、『日本共産党の七十年』では、これを宮本顕治の『声明』と認め、10月初旬=五全協前と時期確定した。
この文書にたいして、亀山幸三は、上記のように解釈した。「資料集第三分冊一九三頁に『党の団結のために(一〇月)』なる文書が載っている。それには編者(宮本のこと)注として『この声明は五一年十月、中央委員会の機能の回復等を主張して共同していた中央委員たち(要するに宮本と蔵原だけ)が発したものである』と書かれている。この声明の内容は明らかにBコースである。ところがこの文書は当時どこに出されたものか、誰も知らないし、また筆者の署名もない。宮本と蔵原の二人か、せいぜいそのほか数人の間で回し読みされたぐらいで、いわゆる国際派党員はほとんど誰も見ていないしろものである。こういう文書を“発した”などと注釈をつけて資料集に載せる宮本が如何に自分の面子と無謬性を守ろうとしていたかを示して余りあるものといえよう。」
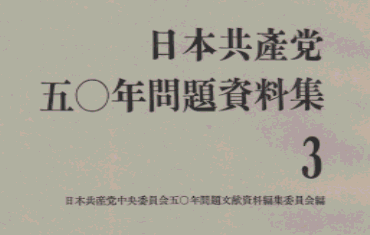
――――――――――――――――――――――――――――――――
党の団結のために
先に八月十日付「恒久平和と人民民主主義のために」にのせられた論評に接し、その趣旨を実践にうつすという根本態度を、われわれは、直ちに決定した。この見地からすべての同志が正しく確信と情熱をもって行動するために、統一のための実践的措置を進めるとともに、討議が行われてきた。
それは、われわれが、過去一ケ年にわたって次のような確信にもとづいて行動したからである。
志賀意見書を中心とする一部極左分派の盲動があったとはいえ、十九中総における中央委員会と全党の「一致団結」という、感激的決議の直後の政治局所感を支持した同志の分派活動、さらに六・六弾圧に際してそれらの人々による所感に反対した党中央諸同志の排除、そのための事実上の中央委員会の分裂と解体、それに反対したり、五〇年テーゼ草案に批判的意見を有する個人ならびに、諸組織に対する組織的大量処分が行われ、党は事実上大きな分裂状態におちいった。われわれは、この分裂混乱を克服するため、時として若干の逸脱があったとはいえ、基本的には十八中総の決議や中央委員会の団結そのものに反対するような、極左分派組織とは明確な一線を画し、一切の分派の解消、党中央の団結とその周囲への全党の団結を目標として闘ってきた。統一した党の中に別の組織をつくることは分派組織となり、明らかに誤りであるが、分裂状態におかれた場合には、統一のための組織的手段もまた止むをえないものであると信じてきた。
しかし、われわれのそのような主観的意図にもかかわらず、党の分裂を早急に克服できず、分裂状態の継続は客観的に日米反動に利する結果となった。この点についてわれわれは厳重に自己批判するとともに、今後ともに批判と自己批判によってこの問題についての卒直な検討を深め、それを教訓とすることを決意し、ここにわれわれの組織を解散するものである。
(後略)
(編注、この声明は一九五一年十月、中央委員会の機能の回復等を主張して共同していた中央委員たちが発したものである))
(注)、これは、『第七回党大会、中央委員会の政治報告から』(一九五八年七月二十三日)の「第六回党大会以後の諸問題」の抜粋である。掲載は、『日本共産党五〇年問題資料文献集4(別冊)』「日本共産党の五〇年問題について」(P.20〜32)にある。ここでは、五全協を、明白に「ともかくも一本化された党の会議であった」と認定した。
―――――――――――――――――――――――――――――――
『第七回党大会、中央委員会の政治報告』の「一九五〇年から六全協までの活動」から抜粋(P.26)
二つの組織が公然と対立抗争する党の分裂状態は、大衆の不信と批判をうけ、党勢力は急速に減退した。
このような事態のもとで、四全協指導部の間に従来からの戦略や指導上の誤りが自己批判されはじめた。これらのことが分裂した双方のなかに統一への機運をつくりだし、両者の統一のための話し合いもすすんでいった。八月十四日のモスクワ放送を契機として、全国統一会議の結成を準備していた中央委員たちは下部組織を解体して、主流派・臨中のもとに統一する方向にすすんだ。
だが、四全協指導部は、これらの組織に属していた人びとに、分派としての自己批判を要求し、そのため復帰も順調に進まなかった。このような態度は基本的には六全協にいたるまで克服されず、党内問題の解決をおくらせる主要な原因となった。
一九五一年十月にひらかれた第五回全国協議会も、党の分裂状態を実質的に解決していない状態のなかでひらかれたもので不正常なものであることをまぬがれなかったが、ともかくも一本化された党の会議であった。
(注)、これも、『日本共産党五〇年問題資料文献集4(別冊)』「日本共産党の五〇年問題について」(P.20〜32)にある。『日本共産党五〇年問題資料文献集1〜3』の出版は、1957年で、「日本共産党中央委員会五〇年問題文献資料編集委員会編」という正規の委員会作成である。ところが、『五〇年問題資料文献集4(別冊)』だけは、1981年出版で、著者日本共産党となっているだけである。よって、この別冊内容は、宮本顕治が編集したものとなる。
その別冊に『「私の五〇年史から」1975年―五〇年の党分裂のころ』を載せた。以下は、その抜粋(P.191〜192)である。下記の組織解散日付は、五全協前の1951年10月初旬であることを、現日本共産党が認めている。
―――――――――――――――――――――――――――――――
「私の五〇年史から」―五〇年の党分裂のころ
一九五〇年一月のコミンフォルムの批判は、反帝闘争を重視するという積極的な内容の面を持っていたが、そのやり方は明らかに大国主義的であった。しかし、私をふくめ当時の党指導部の者は、コミンテルン時代の名残りから、まだコミンフォルムやソ連共産党などに対する事大主義を脱していなかった。同時に、当時の党の指導の家父長的非科学的な弱点、欠陥に気づき苦しんでいた者が少なくなかった。
(中略)
六月二十五日には、朝鮮戦争が始まった。弾圧は、この戦争の先ぶれだった。この間、百合子は一九五一年一月に突然の病気で急逝した。
私はマッカーサーの追放以後、中央委員会の機能回復を求めて統一委員会をつくって活動し、全国の党組織のかなりがこの方向に立った。一九五一年八月、コミンフォルム機関紙は、徳田に率いられた側の党組織がその「軍事方針」を決めた「四全協」で統一委員会側を攻撃した決議をのせた。モスクワ放送と「人民日報」などがこれを報道した。これらは、分裂した一方への公然とした支持を意味した。私たちは活動を中止し、結局組織を解散した。当時まだ私たちは、コミンフォルムの批判―ソ連共産党や中国共産党の批判を不可抗力視する傾向をまぬがれていなかった。私は、不本意だが、この状態で活動を続けても道理は通らないだろうと考えざるをえなかった。しかし、極左冒険主義の失敗は、次第に誰の目にも明らかになっていった。一九五三年の総選挙では、共産党の支持票は以前の六分の一の六十五万票に低落した。
そのころ、私は河出書房の『宮本百合子全集』の解説を書いた。私は党機関とのつながりはなかったが、『人民文学』や『新日本文学』に現われたセクト主義があまりにひどいので、一評論家としてその批判を精力的に書いた。それらを、『批判者の批判』上下二巻として出版した。
翌一九五五年のある日、顔を知った使いの者が来て、志田重男らが会いたいと告げた。彼は先の分裂以後地下活動に入り、徳田に一番近い一人と思われていた人物だった。その日、自動車をたびたび乗り換えて、郊外の大きな家に行った。志田のほか西沢隆二らがいた。徳田は北京で死んだ、極左冒険主義は誤りだった。伊藤律はこれこれの経過で不純分子であることが判明した―彼らはこう言って、「六全協」(第六回全国協議会)の計画を提案した。
(『宮本顕治現代論3 救国と革新をめざして』新日本出版社、一九七五年、所収)
(注)、これは、〔資料1〕とは別のデータである。不破哲三『日本共産党にたいする干渉と内通の記録、ソ連共産党秘密文書から・下』(新日本出版社、1993年)の第十部「干渉主義の戦後の起点」における「自主独立への道」の内、『六全協の準備』に関する個所(P.361〜364)の抜粋である。
――――――――――――――――――――――――――――――――
モスクワでの「六全協」の準備
こうして、「六全協」の準備がはじまりました。
「六全協」の決議案の作成は、モスクワでおこなわれました。五三年末、徳田死後の体制や方針の相談のために、紺野与次郎、河田賢治、宮本太郎らが日本から中国に渡り、「北京機関」の指導部にくわわりました。五四年春、ソ連共産党の指導部からよばれて、野坂、西沢(隆)、紺野、河田、宮本(太)らがモスクワにむかいました。問題は、「六全協」での方針転換の準備でした。五一年以来、モスクワにとどめられていた袴田も、部分的にこれにくわわりました。ソ連側の中心は、スースロフとポノマリョフで、のちに六〇年代の対日干渉にしばしば名前がでてくるコヴィジェンコなども、顔をだしています。「六全協」決議案はソ連側主導でつくられました。この決議案に、「五一年綱領は正しかった」という文句をいれることを頑強に主張したのも、スースロフなどソ連側でした。
国内では、徳田派の国内での中枢にいた志田重男が宮本氏に会い、「極左冒険主義もやめる」「徳田への個人家父長制もやめる」(当時、徳田の北京での死はまだ公表されていませんでした)「従来の党の弊風は全部改める」の三条件をしめして、党の統一の回復と運動の転換についての協議をもちかけました。(P.361)
モスクワの策略
また、ソ連共産党指導部は、統一を回復した日本共産党が、五〇年問題の全面的な総括をおこなうことに、つよく反対しました。この問題では、フルシチョフや劉少奇が直接のりだして、ソ連と中国の党の意向を日本共産党の代表団に伝えました。これも、五〇年問題の総括が、スターリンやソ連共産党の干渉にたいする批判をふくむものとなること、また彼らが支持した徳田派の誤りがうきぼりにされ、今後の対日本共産党工作の障害になることなどを、恐れてのことだったにちがいありません。
彼らの策略の最大のものは、戦後ただちに野坂にヒモをつけて、五〇年間題での介入の最大のテコとしたように、日本共産党の指導部のなかに、ふたたびモスクワのヒモのついた人物を配置して、ソ連共産党指導部が希望する線を日本共産党がすすむように、内部から働かせることでした。
この内通者の一人は、いうまでもなく野坂でした。それにくわえて、モスクワが確保したあらたな内通者は、袴田でした。袴田は、ソ連共産党の圧力のもと、五一年五月のモスクワでの会議で徳田派に降伏してから、三年間、モスクワにとどまっていましたが、「六全協」決議案を準備した五四年のモスクワの会議のあと、北京にきて、「北京機関」の代表者の一人となりました。(P.363〜364)
以上 健一MENUに戻る
(関連ファイル)
『朝鮮戦争と武装闘争責任論の盲点』朝鮮“侵略戦争”に「参戦」した統一回復日本共産党
『嘘つき顕治の真っ青な真実』屈服後、五全協武装闘争共産党で中央活動をした証拠
『シベリア抑留に関する日本共産党問題』の「ソ連から108億円以上の資金援助」
石田雄 『「戦争責任論の盲点」の一背景』
吉田四郎『50年分裂から六全協まで』主流派幹部インタビュー
藤井冠次『北京機関と自由日本放送』人民艦隊の記述も
川口孝夫『私と白鳥事件』 中野徹三『白鳥事件』の添付
れんだいこ『日本共産党戦後党史の研究』 『51年当時』 『52年当時』 『55年当時』
『点在党員組織隔離報復措置』『日本共産党との裁判第4部』