|
|
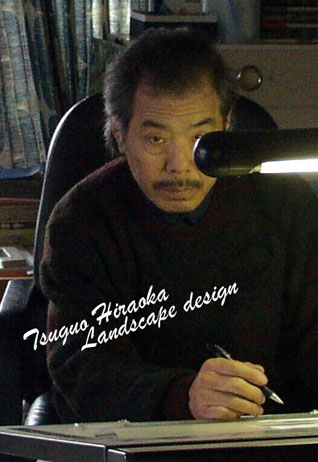 |
 |
水琴屈を仕掛けた鉢飾(蹲踞)
The mechanism which makes the sound of a koto was carried out. The vessel of a stone which a hand washes.(It crouches and a hand is washed.)
|
|
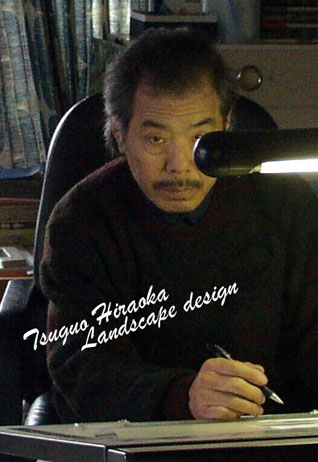 |
 |
水琴屈を仕掛けた鉢飾(蹲踞)
The mechanism which makes the sound of a koto was carried out. The vessel of a stone which a hand washes.(It crouches and a hand is washed.)
庭職人の独り言
「技」(庭師に関わる道具と機械)
“入門”
私は庭作りに関わる一職人 昭和10年生まれで小中学校卒業後高校は定時制に入学 同時に親が営む庭職人の世界に入門した
私の家業の創業者は親父でその子である兄と私は二人兄弟で時代背景(昭和26年に入門)から明治生まれの親父は封建的で親父の意志に逆らうことはできなかった 従って有無もなく親父の意図のまま誘導されるがまま私達兄弟は庭職人の道を歩まざるを得なかった
“機械”
要は機械の開発進歩で仕事の能率向上は図れていることには異論のないところだが職人の技術は低下している 職人と言われた人が 私を含め機械を使うようになった
さて機械の導入と言えば 私の職業の造園が一番遅れているであろうと考えるが 然しどの職種においても移動運搬手段の自動車(機械)が大きく巾を占めてきた ・・・・余談だがそれに因む違和感に お坊さん(僧侶)が衣 草履履きにヘルメット姿でバイクは滑稽に見えた 「バイクで走っているお坊さんごめんなさい」・・・・・
私の事業所においても今 自動車は便利で能率向上は否めない 今の一般社会情勢の流に合せ歩むには不可欠な存在ではあることは承知しつつも何か私の脳裏には“違う”“狂っている”という赤信号が出ている
今更自動車のない時代を忍んでみてもどうにもならないことだが自動車に憧れた懐かしい時代もありそれが実現した そして今や珍しくもない当たり前の最低レベルの時勢の流れの定番でもある
3人が1日6万円(24時間)かかった運搬が自動車を使うと1人で2時間でこなせる 例えば人手間を1人(8時間労働)2万円と仮定して人力運搬と自動車を金額に換算すると3人で6万円(24時間)それが5千円(2時間)で済み 経費として自動車の消耗費 ガソリン代その他諸々を含めても7千円もあれば十分 従って8.5分の1で済むことになる そのメリットが施主 業者共に生ずるから納得してしまうのが現状である でも過去において3人1日かかっていても施主は納得していた それが8.5分の1で出来て只回転が速くなっただけで両者共に損益勘定からしてどちらも特に益があるとは思えない 只一般社会の流に合わせているのみであり常識の変遷にすぎない
“道具”
道具と言えば「感こつ」道具を通して身体に伝わってくる感覚とか音 例えば槌を使うとき打ち下ろす強度timing(タイミング)
職人と言えば即「わざ」あらゆる職種様々な場でその人(職人)でないと出来ない「わざ」があり その職人の技術によって作り上げられたものに大きな物からミクロ的なものまでとってもこのページには並べきれない作品(造作物)がある 「わざ」には臨場感がある 道具を使い身体でものを創る 又その道具すら自分で作る
それが機械によってその職人達がだんだん影を潜めていく そのなか拘り職人が僅かながら伝統的に継承されてきた技術を受け継いでいる この現状は嘆かわしく見るに忍びないものがある
石を割ったり欠いたりするにも道具と機械では能率はかなりの差がある そこで私が特に述べたいことは道具での仕事はその道具を使える技術者がいなければならない
“庭師”
私の職業は施主に何を提供しているのかな?また施主は何を求めているのかな? と考えたとき間欠なく脳に閃く言葉は「安らぎ」「癒し」ではないのか?
改めて考えても「安らぎ」「癒し」のために汗かき命を削っているといえる
そこで軌道を「技」(道具と機械)に戻すと親子三人が片道20km程ある道のりを ダイハチ車(道具)を引っ張って松の木一本をまるまる一日がかりで材料屋に買いにいったことが普通で それがつい昨日のように思うが自動車(機械)なら一人が2時間有れば悠々とこなせる仕事である
この差は一体何になんだろうか?と時に独り言のように呟いている
そこで心の豊かさからすればどちらに軍配が上がるのだろう? 今は今成と思えばそれまでだが 私には現状をどうすることも出来ないと頭では理解しているものの この先この調子で進化して行くと思えば非常に心配だ?
庭作りに石の吊り上げ移動に使う道具 これが実にシンプルでカシヤ 手巻きウインチ チェンブロック私が入門当時使われていた道具だ これは機械と言えば機械だろうがanalog(アナログ)的で今に比べれば物の差ではない
一方機械の方はオペレーターが必要だ
技術者とオペレーターを比較したとき一人前になる年期といえば 例えば石を割り仕事で道具を使ってする場合は先ず石割道具が使える迄には最低でも3年の年期を必要とする
機械の場合はオペレーターが種類によって異なるが使うその機械の取扱い説明書を読むだけで使えるようになる(中には多少の講習を受けなければならないものもあるが)
何か味気ない「技」のいらない時代になってきている 操作方法を教えるだけでかなりの仕事が出来る
私がこれから述べようとすることは読者の方の中には「古い」と言う方もいるでしょう でも私は古いものを全て排除していいものかと最新の進化で得たパソコンを使いながら昔を忍んでいる
「技」を持っている人の仕事を眺めていると不思議に思えてくる年期の入った人の仕事を見ているとまるでマジックを見ているようで時間の経つのが分からない程見入ってしまうことがある
設計を書くにしても今パソコンで(VectorWorks)を使えばリアルに現物に近い絵が描ける
そんな時代に手書きの設計は?と思われる方もおおいでしょうが 私は手書きの設計で通したいと思っています 手書きにしても一本の線を定規を使って引く線とフリーペンで引く線では味わいが違う
私はプロです だから今の時代に即した施工方法でないと依頼者に受け入れてもらえないからおおむね概ね今なりの方法工事は進めています
でも行程の中で適材適所で「技」が必要な仕事がある 先述したように造園は機械の導入が一番遅れているのが幸いしてかまだまだ「技」を生かす仕事は残っている 「技」がないとできない仕事もある が今の従業員に「技」を教えるには大変である
第一習う側にその姿勢がない そして指導者も少ない 「技」を厳しく修得した人とそうでない人を年代で分けるとすればこれは一般によく言われる事ですが 終戦を境に戦前戦後生まれで人類の変遷があったといえる
厳しく「技」に拘ったのはやはり戦前生まれである 反論はあろうと思うが戦後生まれの人は人類が違うといっても言い過ぎではないだろう