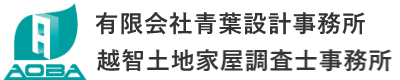よくある質問
土地家屋調査士へのよくある質問をまとめました。
法務局に地積測量図があるからといって境界が明らかであるとは限りません。
作成年月日が古い地積測量図は辺長や面積しか記載されておらず現地での復元が困難な為、新たに立会いを行い境界を確定する必要がある場合があります。
簡易な計算ツールを用意しましたので、条件にあわせて入力してみてください。あくまで概算ですので、正式な見積もりは直接依頼ください。
新築の住宅であれば、居宅として認定できる状態になっていれば、完全に完成していなくても表題登記の申請は可能です。当事務所では風呂・トイレ・キッチンが設置したら、申請可能ですとお伝えしております。
申請して表題登記が完了するまでに概ね1週間ほどかかりますので、ローン設定の日にちが決まっている場合はお早めにご相談ください。
新築の建物の場合は、法務局に申請して概ね1週間ほどで完了します。
亡くなった親などが建物を建てて表題登記をしていなかった場合の表題登記は、少し長くなる傾向にあります。建物の図面が無いことも多く、また相続の関係資料を揃える必要もあり、トータル的に長くかかりますので、売却等を予定されている場合は早めにご相談ください。
表題登記は申請義務があるため、登記しなければ罰則があります。しかし、買い主が売却後すぐに解体される場合は、表題登記をしてしまうと、解体後に滅失登記をする必要も出てくるため、表題登記せずに売却されたらどうですかとアドバイスしています。
「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させる制度です。それなりの要件があります。申請すれば国が引き取ってくれるわけではありません。
詳しくは法務省WEBサイトをご確認ください。
相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であることが絶対条件です。例えば自分で購入した土地がいらなくなったからといって、この制度は使えません。
以下の場合は申請が出来ませんので、例えば(1)Aであれば建物を解体して更地にする必要があります。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
上記(1)を全てクリアしたとしても、(2)不承認事項に当たる場合は承認されないことがあるため、やはり最初に法務局で帰属制度を使うことが可能かどうかの当たりをつけてから、ことを進めたほうが良いでしょう。
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
まずは、最寄りの所轄法務局で「このような土地があるのだけど帰属制度は使えますか?」と問い合わせてください。それが一番確実で、最初の第一歩です。
2025年時点で、相続土地国庫帰属制度の申請代行を出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士となっています。しかし、この3種の資格者では、境界について測量したりすることが出来ません。土地の境界などを決めるためには、調査士が現地で測量を行ったり、仮杭を入れたりする作業を行う必要が出てくる場合もあると思われます。
3業種の知り合いがおられない場合は、ご紹介することも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
土地家屋調査士の出番です。ただし、境界を調べたけど、帰属制度が使えなかったということもありえますので、まずは所轄の法務局で確認してください。
土地上に建物がある場合は、国庫帰属制度の申請が出来ません。従って建物を解体する必要がありますが、解体したら建物の滅失登記が必要となります。
境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地も申請が出来ません。境界については、法務局の公図だけでは判断することが困難な場合があります。土地の位置や範囲などが不明な場合は、土地家屋調査士の出番となります。