HAMK "THE STORY OF A FLOWERFIELD"
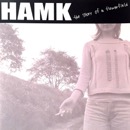 "エモ"という言葉に少し懐疑的な私でさえ、日本産のHAMKによるこのアルバムを聴いてしまえば、"エモ"の存在を認めざるを得ません。それほど、心に強く響く作品です。アルバムの冒頭を飾る1曲目"Don’t
Leave
Me"から、感情がぶつけられたような遣る瀬無いメロディが心に突き刺さり、その瞬間から引き込まれてしまいます。まさにエモーショナルそのもので、涙腺にグッとくるような、胸がきゅ〜んと締め付けられる感覚が広がります。特に3曲目"The
Rain"のように、スピード感を抑えた曲であっても、内側から湧き上がる熱い感情がしっかりと伝わってきて、聴くたびにドキドキしてしまいます。こうした曲が生み出す感覚は、まさに希有で、簡単には出会えないエモーショナルな体験です。2005年にリリースされたこの1stアルバム、個人的には2ndよりもこちらの方が断然オススメです。強く心に響く何かを感じることができるこの作品を、ぜひ聴いてほしいと思います。
"エモ"という言葉に少し懐疑的な私でさえ、日本産のHAMKによるこのアルバムを聴いてしまえば、"エモ"の存在を認めざるを得ません。それほど、心に強く響く作品です。アルバムの冒頭を飾る1曲目"Don’t
Leave
Me"から、感情がぶつけられたような遣る瀬無いメロディが心に突き刺さり、その瞬間から引き込まれてしまいます。まさにエモーショナルそのもので、涙腺にグッとくるような、胸がきゅ〜んと締め付けられる感覚が広がります。特に3曲目"The
Rain"のように、スピード感を抑えた曲であっても、内側から湧き上がる熱い感情がしっかりと伝わってきて、聴くたびにドキドキしてしまいます。こうした曲が生み出す感覚は、まさに希有で、簡単には出会えないエモーショナルな体験です。2005年にリリースされたこの1stアルバム、個人的には2ndよりもこちらの方が断然オススメです。強く心に響く何かを感じることができるこの作品を、ぜひ聴いてほしいと思います。
PALE "ANOTHER SMART MOVE"
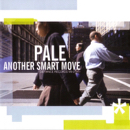 このドイツ産のPALEによる作品はジャンルとしてはエモに分類されるのでしょうか。確かに、WATERSLIDEさんの指摘どおり、曲によってはSTARMARKETを彷彿とさせる歌いっぷりがあります。また、PROMISE
RINGやGET UP
KIDSに通じる疾走感があり、暗めの雰囲気の中に繊細ながらも力強いメロディが光る、そんな作品です。特に、2曲目"Some
Scenes May Last"から3曲目"Six Shining Minutes At The
Airport"への流れは圧巻。静から動へと移り変わる展開がドラマティックで、聴くたびに心が揺さぶられます。この鬱屈した世界を少しでも前向きに生き抜くために、こうした音が必要なのだと実感させられます。1999年にDefiance
Recordsからリリースされた3rdアルバムですが、いわゆる「ドイツっぽさ」はあまり感じられません。やはりこの手の音を追うならば、ドイツとスウェーデンのシーンには常にアンテナを張っておくべきですね。
このドイツ産のPALEによる作品はジャンルとしてはエモに分類されるのでしょうか。確かに、WATERSLIDEさんの指摘どおり、曲によってはSTARMARKETを彷彿とさせる歌いっぷりがあります。また、PROMISE
RINGやGET UP
KIDSに通じる疾走感があり、暗めの雰囲気の中に繊細ながらも力強いメロディが光る、そんな作品です。特に、2曲目"Some
Scenes May Last"から3曲目"Six Shining Minutes At The
Airport"への流れは圧巻。静から動へと移り変わる展開がドラマティックで、聴くたびに心が揺さぶられます。この鬱屈した世界を少しでも前向きに生き抜くために、こうした音が必要なのだと実感させられます。1999年にDefiance
Recordsからリリースされた3rdアルバムですが、いわゆる「ドイツっぽさ」はあまり感じられません。やはりこの手の音を追うならば、ドイツとスウェーデンのシーンには常にアンテナを張っておくべきですね。
GUNMOLL "ANGER MANAGEMENT IN FOUR CHORDS OR LESS"
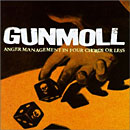 NO
IDEAレコードのバンド、ゲインズビル産のGUNMOLLによる1stアルバム(2001年リリース)。これはもう、期待を裏切らない熱量全開の名作です。しわがれたダミ声が、哀愁たっぷりに、全身全霊で歌い上げる様はまさに圧巻。JAWBREAKERの初期をもっと速くしたような感触もあれば、LEATHERFACE、HOT
WATER MUSIC、さらには同時期に活躍したGRABASS
CHARLESTONSあたりを彷彿とさせる部分もあります。とにかく、オープニングから一気に引き込まれる展開の良さ。そして、おしっこがちびるほどの名曲とも言うべき"Say
Goodbye"をはじめとした、アルバム前半のタイトな流れはもう最高の一言。疾走感と感情がぶつかり合うようなサウンドに、痺れながらの大疾走。聴いていて拳を握りしめたくなる瞬間の連続です。そして、蛇足ながらも個人的に衝撃だったのが、GUNMOLLがかつて京都のライブハウスMOJOに来ていたこと。まさか、近所で彼らがライブをしていたなんて...知らなかったとはいえ、実に悔しい。
NO
IDEAレコードのバンド、ゲインズビル産のGUNMOLLによる1stアルバム(2001年リリース)。これはもう、期待を裏切らない熱量全開の名作です。しわがれたダミ声が、哀愁たっぷりに、全身全霊で歌い上げる様はまさに圧巻。JAWBREAKERの初期をもっと速くしたような感触もあれば、LEATHERFACE、HOT
WATER MUSIC、さらには同時期に活躍したGRABASS
CHARLESTONSあたりを彷彿とさせる部分もあります。とにかく、オープニングから一気に引き込まれる展開の良さ。そして、おしっこがちびるほどの名曲とも言うべき"Say
Goodbye"をはじめとした、アルバム前半のタイトな流れはもう最高の一言。疾走感と感情がぶつかり合うようなサウンドに、痺れながらの大疾走。聴いていて拳を握りしめたくなる瞬間の連続です。そして、蛇足ながらも個人的に衝撃だったのが、GUNMOLLがかつて京都のライブハウスMOJOに来ていたこと。まさか、近所で彼らがライブをしていたなんて...知らなかったとはいえ、実に悔しい。
DYNAMITE BOY "SOMEWHERE IN AMERICA"
 2001年にFearless
Recordsからリリースされたテキサス産のDYNAMITE
BOYによる3rdアルバム。メロコアらしいノリの良い楽曲が詰め込まれており、聴いていると自然と体が動いてしまうような軽快さがあります。スピード感で言えば、1stの方が上かもしれませんが、1stが初期衝動的な勢いで突っ走る作品だったのに対し、この3rdは、各曲が練り込まれており、アルバム全体としても非常に完成度が高い仕上がりになっています。サウンド自体は異なりますが、その疾走感とキャッチーさは、FACE
TO FACEやGREEN
DAYを彷彿とさせるものがあります。そして、個人的に強く推したいのが、女性ゲストボーカルをフィーチャーした3曲目"No
Way
Out"。曲が持つ哀愁とポップさが絶妙に絡み合い、アルバムの中でも特に際立つ存在となっています。ちなみに、次作となる4thアルバムでは、少し大人の雰囲気が出てしまっていますが、これまたFACE
TO FACEの3rdが好きな人にはお薦めできる内容です。
2001年にFearless
Recordsからリリースされたテキサス産のDYNAMITE
BOYによる3rdアルバム。メロコアらしいノリの良い楽曲が詰め込まれており、聴いていると自然と体が動いてしまうような軽快さがあります。スピード感で言えば、1stの方が上かもしれませんが、1stが初期衝動的な勢いで突っ走る作品だったのに対し、この3rdは、各曲が練り込まれており、アルバム全体としても非常に完成度が高い仕上がりになっています。サウンド自体は異なりますが、その疾走感とキャッチーさは、FACE
TO FACEやGREEN
DAYを彷彿とさせるものがあります。そして、個人的に強く推したいのが、女性ゲストボーカルをフィーチャーした3曲目"No
Way
Out"。曲が持つ哀愁とポップさが絶妙に絡み合い、アルバムの中でも特に際立つ存在となっています。ちなみに、次作となる4thアルバムでは、少し大人の雰囲気が出てしまっていますが、これまたFACE
TO FACEの3rdが好きな人にはお薦めできる内容です。
GREY AREA "GREY AREA"
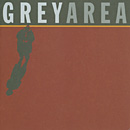 JUNCTION
18と同じく、一聴するとメロコアと分類されそうなサウンドですが、これはしっかりと「メロディック・ハードコア」として紹介したい。このニューヨーク産のバンドGREY
AREAの背景には、WARZONEをはじめとするNYハードコアシーンがあるため、どこか一本芯の通った力強さが感じられ、軽薄な雰囲気が一切ありません。FACE
TO
FACEのような疾走感とフックの効いたメロディを求めている人には、かなり刺さるのではないでしょうか。特に、1曲目"Right
Now!"から炸裂するハイトーンで伸びやかなボーカルは、爽快感抜群。聴いていて思わず拳を突き上げたくなるような衝動を掻き立てます。中古市場を少し探せば、数百円でゲットできるかもしれませんので、迷わず手に取ることをおすすめします。1998年にVictory
Recordsからリリースされた1stアルバム。ちなみに2ndアルバム"FANBELT
ALGEBRA"ではボーカルが変わっていますが、意外と良いです。
JUNCTION
18と同じく、一聴するとメロコアと分類されそうなサウンドですが、これはしっかりと「メロディック・ハードコア」として紹介したい。このニューヨーク産のバンドGREY
AREAの背景には、WARZONEをはじめとするNYハードコアシーンがあるため、どこか一本芯の通った力強さが感じられ、軽薄な雰囲気が一切ありません。FACE
TO
FACEのような疾走感とフックの効いたメロディを求めている人には、かなり刺さるのではないでしょうか。特に、1曲目"Right
Now!"から炸裂するハイトーンで伸びやかなボーカルは、爽快感抜群。聴いていて思わず拳を突き上げたくなるような衝動を掻き立てます。中古市場を少し探せば、数百円でゲットできるかもしれませんので、迷わず手に取ることをおすすめします。1998年にVictory
Recordsからリリースされた1stアルバム。ちなみに2ndアルバム"FANBELT
ALGEBRA"ではボーカルが変わっていますが、意外と良いです。
OSKER "IDLE WILL KILL"
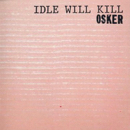 2001年にリリースされたロサンゼルス産のOSKERによる2ndアルバム。Epitaphからのリリースではありますが、いわゆる典型的な「Epitaphサウンド」には当てはまらず、メロコア的な印象はほとんどありません。むしろ、この作品に詰め込まれているのは、歌い上げるようなボーカルが紡ぎ出す、巧みな旋律とうら悲しさ。メロディが前面に押し出された楽曲が続き、その熱量と感情表現の豊かさには圧倒されます。特に4曲目の"Contention"は、まさに涙腺を刺激する名曲。アコースティックギター一本でも成立しそうなほど、ボーカルの力が際立っていて、聴いているうちに心をぐっと掴まれてしまいます。エモーショナルでありながらも、決して押し付けがましくなく、じわじわと染み込んでくるような音が魅力的です。ちなみに、1stアルバム"TREATMENT
5"は、もう少しスピード感があり、荒削りな「若気の至り」的な作品になっています。
2001年にリリースされたロサンゼルス産のOSKERによる2ndアルバム。Epitaphからのリリースではありますが、いわゆる典型的な「Epitaphサウンド」には当てはまらず、メロコア的な印象はほとんどありません。むしろ、この作品に詰め込まれているのは、歌い上げるようなボーカルが紡ぎ出す、巧みな旋律とうら悲しさ。メロディが前面に押し出された楽曲が続き、その熱量と感情表現の豊かさには圧倒されます。特に4曲目の"Contention"は、まさに涙腺を刺激する名曲。アコースティックギター一本でも成立しそうなほど、ボーカルの力が際立っていて、聴いているうちに心をぐっと掴まれてしまいます。エモーショナルでありながらも、決して押し付けがましくなく、じわじわと染み込んでくるような音が魅力的です。ちなみに、1stアルバム"TREATMENT
5"は、もう少しスピード感があり、荒削りな「若気の至り」的な作品になっています。
HÜSKER DÜ "NEW DAY RISING"
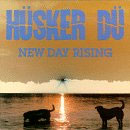 DAG
NASTYと並び、メロディック・ハードコア史において決して避けて通れない、まさに教科書的な存在。それが、ミネアポリス産のHÜSKER
DÜです。個人的なベストソングはミニアルバム"METAL
CIRCUS"に収録されている、恐ろしいほどの名曲"Real
World"です(なお、このミニアルバムには、LIFETIMEがカバーしたことで知られる"It’s Not Funny
Anymore"も収録されているので、未聴の方はぜひ)。しかし、アルバム全体の完成度という点では、この3rdアルバムだと思います。SST
Recordsからリリースされた1985年の本作は、単なるハードコアの枠を超え、破壊的な激しさと美しさが見事に融合した名作となっています。大好きな"Celebrated
Summer"や"Books About
UFOs"など、バラエティ豊かで、感情を揺さぶる楽曲が満載。荒々しい轟音の中に、どこまでも切なく、そして力強いメロディが溶け込んでいて、まさに唯一無二のサウンドです。これが1985年のリリースとは信じられないほどの完成度。メロディック・ハードコアの原点のひとつとも言える彼らの才能が、これでもかというほど詰め込まれた一枚です。
DAG
NASTYと並び、メロディック・ハードコア史において決して避けて通れない、まさに教科書的な存在。それが、ミネアポリス産のHÜSKER
DÜです。個人的なベストソングはミニアルバム"METAL
CIRCUS"に収録されている、恐ろしいほどの名曲"Real
World"です(なお、このミニアルバムには、LIFETIMEがカバーしたことで知られる"It’s Not Funny
Anymore"も収録されているので、未聴の方はぜひ)。しかし、アルバム全体の完成度という点では、この3rdアルバムだと思います。SST
Recordsからリリースされた1985年の本作は、単なるハードコアの枠を超え、破壊的な激しさと美しさが見事に融合した名作となっています。大好きな"Celebrated
Summer"や"Books About
UFOs"など、バラエティ豊かで、感情を揺さぶる楽曲が満載。荒々しい轟音の中に、どこまでも切なく、そして力強いメロディが溶け込んでいて、まさに唯一無二のサウンドです。これが1985年のリリースとは信じられないほどの完成度。メロディック・ハードコアの原点のひとつとも言える彼らの才能が、これでもかというほど詰め込まれた一枚です。
PEGBOY "STRONG REACTION"
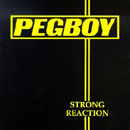 言わずと知れたメロディック・ハードコアのオリジネーターの一つであるNAKED
RAYGUNのメンバーが在籍するPEGBOY。シカゴ産メロディックの代表作として、その名を語らずにはいられない、まさにいぶし銀のような1stアルバムです。1991年にQuarterstick
Recordsからリリースされ、その後のシーンに多大な影響を与えた一枚で、おっさんの哀愁がこれでもかと漂う、渋くて熱い名作。全編にわたり、ハードな勢いとメロディックなうら悲しさが絶妙なバランスで同居しており、"Strong
Reaction"、"Field Of Darkness"、"My
Youth"といった楽曲の数々は、何度聴いても胸を締めつけられます。CD版には、これまた超名作の12インチEP"THREE-CHORD
MONTE"がボーナストラックとして全曲収録されています。1990年代前半の哀愁メロディックが好きな方には間違いなくジャストフィットする教科書的存在な古典的名作であります。
言わずと知れたメロディック・ハードコアのオリジネーターの一つであるNAKED
RAYGUNのメンバーが在籍するPEGBOY。シカゴ産メロディックの代表作として、その名を語らずにはいられない、まさにいぶし銀のような1stアルバムです。1991年にQuarterstick
Recordsからリリースされ、その後のシーンに多大な影響を与えた一枚で、おっさんの哀愁がこれでもかと漂う、渋くて熱い名作。全編にわたり、ハードな勢いとメロディックなうら悲しさが絶妙なバランスで同居しており、"Strong
Reaction"、"Field Of Darkness"、"My
Youth"といった楽曲の数々は、何度聴いても胸を締めつけられます。CD版には、これまた超名作の12インチEP"THREE-CHORD
MONTE"がボーナストラックとして全曲収録されています。1990年代前半の哀愁メロディックが好きな方には間違いなくジャストフィットする教科書的存在な古典的名作であります。
KIDSNACK "FIRST STEPS"
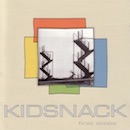 青さ全開のハイトーン・ボーカルが響き渡り、WALKERに匹敵するようなヘタレだけど甘くて哀調を帯びたメロディがこれでもかと詰め込まれたテネシー産のKIDSNACKによる1stアルバム。聴いていると、なんとなく女性に相手にされなさそうで(※完全なる想像です)、悶々とした鬱屈した日々を過ごす若者の心の叫びが聞こえてくるようです。そんなセンチメンタルな世界観の中に、ふとSAMIAMを彷彿とさせるドラマチックで感傷的なフレーズが差し込まれるのがたまりません。疾走感のあるサウンドですが、単なるスピード勝負ではなく、楽曲全体にエモーショナルな響きがあるのがこのバンドの個性でしょう。"Just
For A
Day"や"Goodwill"といった心ときめくキャッチーな名曲が散りばめられた、まさに青春の葛藤を音にしたような良作。2001年リリース。メロディックパンクが好きな人なら、この瑞々しい1枚をぜひ聴いていただきたい。
青さ全開のハイトーン・ボーカルが響き渡り、WALKERに匹敵するようなヘタレだけど甘くて哀調を帯びたメロディがこれでもかと詰め込まれたテネシー産のKIDSNACKによる1stアルバム。聴いていると、なんとなく女性に相手にされなさそうで(※完全なる想像です)、悶々とした鬱屈した日々を過ごす若者の心の叫びが聞こえてくるようです。そんなセンチメンタルな世界観の中に、ふとSAMIAMを彷彿とさせるドラマチックで感傷的なフレーズが差し込まれるのがたまりません。疾走感のあるサウンドですが、単なるスピード勝負ではなく、楽曲全体にエモーショナルな響きがあるのがこのバンドの個性でしょう。"Just
For A
Day"や"Goodwill"といった心ときめくキャッチーな名曲が散りばめられた、まさに青春の葛藤を音にしたような良作。2001年リリース。メロディックパンクが好きな人なら、この瑞々しい1枚をぜひ聴いていただきたい。
WRONG LIFE "EARLY WORKINGS OF AN IDEA"
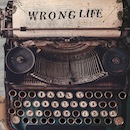 2020年と2021年にリリースされたシングル曲に、未発表曲を2曲加えて編まれたWRONG
LIFEによる編集盤。2022年にLast Exit
Musicからリリースされました。フロントマンは元MURDERBURGERSのボーカル&ギターということで、当然ながらその後期作品の雰囲気を色濃く感じます。3回目に聴いたとき、曲の展開や空気感からMEGA
CITY
FOURに似ているなと思ったのですが、すでにWaterslideさんのレビューにそう書かれていました(もしかしたら、無意識に記憶の片隅に残っていただけかもしれません)。どの曲も丁寧に作り込まれており、聴けば聴くほど心に染みるメロディが溢れています。UKらしい名状しがたい不安感を抱えて鬱屈した気持ちを抱えつつも、それでも前を向いて歩こうとする希望と意志が詰まった楽曲たちは、聴くたびに胸に迫ってきます。なお、2023年にリリースされた1stアルバムも素晴らしい仕上がりです。
2020年と2021年にリリースされたシングル曲に、未発表曲を2曲加えて編まれたWRONG
LIFEによる編集盤。2022年にLast Exit
Musicからリリースされました。フロントマンは元MURDERBURGERSのボーカル&ギターということで、当然ながらその後期作品の雰囲気を色濃く感じます。3回目に聴いたとき、曲の展開や空気感からMEGA
CITY
FOURに似ているなと思ったのですが、すでにWaterslideさんのレビューにそう書かれていました(もしかしたら、無意識に記憶の片隅に残っていただけかもしれません)。どの曲も丁寧に作り込まれており、聴けば聴くほど心に染みるメロディが溢れています。UKらしい名状しがたい不安感を抱えて鬱屈した気持ちを抱えつつも、それでも前を向いて歩こうとする希望と意志が詰まった楽曲たちは、聴くたびに胸に迫ってきます。なお、2023年にリリースされた1stアルバムも素晴らしい仕上がりです。
SOUTHPAW "THE GOD IS SOUTHPAW"
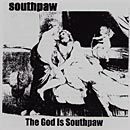 こちらはSOUTHPORTではなく、SOUTHPAWです。かつて3rdアルバム"TRAJECTORIES"を手に取ったものの、エモ寄りの雰囲気がどうにも自分の琴線には触れず、正直スルーしていました。しかし、2007年にFIXING
A
HOLEが初期シングルなどをまとめた全22曲入りの編集盤をリリースしたという情報をネットで発見。半信半疑ながら、イチかバチかで購入してみました。そして再生ボタンを押した瞬間、思いました。「なんで今まで聴いてこなかったんだ…!」だと。期待を裏切らない王道UKメロディックのノリで、HOOTON
3 CARにも通じる疾走感と哀愁がたっぷり詰まっており、聴いていて自然と胸が熱くなります。2nd
EPの曲の出来の良さは言わずもがなですが、特に8曲目”Casanova”から12曲目”Nextdoor”にかけての未発表EP音源の素晴らしさには驚愕。なぜ当時リリースされなかったのか、本当に謎すぎます。
こちらはSOUTHPORTではなく、SOUTHPAWです。かつて3rdアルバム"TRAJECTORIES"を手に取ったものの、エモ寄りの雰囲気がどうにも自分の琴線には触れず、正直スルーしていました。しかし、2007年にFIXING
A
HOLEが初期シングルなどをまとめた全22曲入りの編集盤をリリースしたという情報をネットで発見。半信半疑ながら、イチかバチかで購入してみました。そして再生ボタンを押した瞬間、思いました。「なんで今まで聴いてこなかったんだ…!」だと。期待を裏切らない王道UKメロディックのノリで、HOOTON
3 CARにも通じる疾走感と哀愁がたっぷり詰まっており、聴いていて自然と胸が熱くなります。2nd
EPの曲の出来の良さは言わずもがなですが、特に8曲目”Casanova”から12曲目”Nextdoor”にかけての未発表EP音源の素晴らしさには驚愕。なぜ当時リリースされなかったのか、本当に謎すぎます。
DOUGHBOYS "HOME AGAIN"
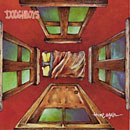 物悲しいメロディが胸を打つ、カナダが誇る名バンドDOUGHBOYSの2ndアルバム。1989年にRestless
Recordsからリリースされた本作は、メロディックパンク史において欠かせない傑作のひとつです。もし「メロディックパンクの教科書」がこの世に存在するとしたら、このアルバムが載っていない本をレジに持っていく必要はないでしょう。後にALL
SYSTEMS GO!でも活躍するJohn Kastnerが在籍し、さらにALLのBill StevensonとStephan
Egertonがプロデュースを手がけていることからも、その音の完成度の高さはお墨付き。個性的なボーカルの声質に少しクセを感じる人もいるかもしれませんが、そんなことは気にせず聴き込んでみてほしい。そこには涙腺を刺激する美しいメロディ、突き抜ける爽快感、そして絶妙なポップセンスが詰め込まれています。特に2曲目"No
Way"、3曲目"I Won’t Write You a Letter"などが私好みです。「DOLL
メロディック狂必聴ディスクUS編」紹介ディスク。
物悲しいメロディが胸を打つ、カナダが誇る名バンドDOUGHBOYSの2ndアルバム。1989年にRestless
Recordsからリリースされた本作は、メロディックパンク史において欠かせない傑作のひとつです。もし「メロディックパンクの教科書」がこの世に存在するとしたら、このアルバムが載っていない本をレジに持っていく必要はないでしょう。後にALL
SYSTEMS GO!でも活躍するJohn Kastnerが在籍し、さらにALLのBill StevensonとStephan
Egertonがプロデュースを手がけていることからも、その音の完成度の高さはお墨付き。個性的なボーカルの声質に少しクセを感じる人もいるかもしれませんが、そんなことは気にせず聴き込んでみてほしい。そこには涙腺を刺激する美しいメロディ、突き抜ける爽快感、そして絶妙なポップセンスが詰め込まれています。特に2曲目"No
Way"、3曲目"I Won’t Write You a Letter"などが私好みです。「DOLL
メロディック狂必聴ディスクUS編」紹介ディスク。
PETROGRAD "ASSORTED LULLABIES"
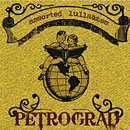 ルクセンブルクのポリティカル・メロディックバンドPETROGRADが残した楽曲をまとめた編集盤CD。2009年にSP
Recordsからリリースされた本作は、まさに「闘うメロディックパンク」の良作です。まず耳を引くのが、光るメロディと男女ボーカルの絡み。それぞれの声が交差することで、楽曲に奥行きが生まれ、ただのポリティカルパンクに終わらない独特の魅力を持っています。そして、歌詞の内容や楽曲の雰囲気から、私の頭には真っ先に我が愛するハードコアバンドCONFLICTが浮かびました。もちろん、破壊力で比べたら爆弾と爆竹くらいの差ではあるものの、彼らの意志やスタンスには確かな共通点を感じます。彼らもまた、音楽を通してメッセージを届けようとしているのです。話は変わりますが、ここを訪れるような方々の中でCONFLICTを聴いている人は少ないかもしれませんが、もし未体験であれば、ぜひ一度手に取って聞いてみてほしいです。(番外編
PART3のHARDCORE編で紹介してます。)。
ルクセンブルクのポリティカル・メロディックバンドPETROGRADが残した楽曲をまとめた編集盤CD。2009年にSP
Recordsからリリースされた本作は、まさに「闘うメロディックパンク」の良作です。まず耳を引くのが、光るメロディと男女ボーカルの絡み。それぞれの声が交差することで、楽曲に奥行きが生まれ、ただのポリティカルパンクに終わらない独特の魅力を持っています。そして、歌詞の内容や楽曲の雰囲気から、私の頭には真っ先に我が愛するハードコアバンドCONFLICTが浮かびました。もちろん、破壊力で比べたら爆弾と爆竹くらいの差ではあるものの、彼らの意志やスタンスには確かな共通点を感じます。彼らもまた、音楽を通してメッセージを届けようとしているのです。話は変わりますが、ここを訪れるような方々の中でCONFLICTを聴いている人は少ないかもしれませんが、もし未体験であれば、ぜひ一度手に取って聞いてみてほしいです。(番外編
PART3のHARDCORE編で紹介してます。)。
UNWELCOME GUESTS "WAVERING"
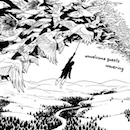 アメリカ・バッファロー産、2011年にDirt Cult
RecordsなどからリリースされたUNWELCOME
GUESTSの2ndアルバム。これはもう、余計な装飾を排した、シンプルに格好良い作品です。派手さはないものの、じわじわと心に染み込んでくるフォーキーな情緒と、哀愁を帯びたしゃがれ声の響きが何とも言えず心地よいです。ダイブやモッシュが似合う音ではありません。各曲のイントロの作り方が非常に巧みで、それぞれの楽曲が独立して際立っているのがポイントです。超名曲と叫ぶような一曲があるわけではないものの全体としての流れがしっかり構築されており、アルバム単位で聴くことで真価を発揮するタイプの作品だと思います。切ないけれど、決して沈み込むわけではなく、聴いた後には顔を上げて前を向けるような不思議な力を持った一枚。こういう音には、やはりウイスキーがよく合う。グラスを傾けながら、じっくりと味わいたいアルバムです。
アメリカ・バッファロー産、2011年にDirt Cult
RecordsなどからリリースされたUNWELCOME
GUESTSの2ndアルバム。これはもう、余計な装飾を排した、シンプルに格好良い作品です。派手さはないものの、じわじわと心に染み込んでくるフォーキーな情緒と、哀愁を帯びたしゃがれ声の響きが何とも言えず心地よいです。ダイブやモッシュが似合う音ではありません。各曲のイントロの作り方が非常に巧みで、それぞれの楽曲が独立して際立っているのがポイントです。超名曲と叫ぶような一曲があるわけではないものの全体としての流れがしっかり構築されており、アルバム単位で聴くことで真価を発揮するタイプの作品だと思います。切ないけれど、決して沈み込むわけではなく、聴いた後には顔を上げて前を向けるような不思議な力を持った一枚。こういう音には、やはりウイスキーがよく合う。グラスを傾けながら、じっくりと味わいたいアルバムです。
DRAPES "SILENT WAR..."
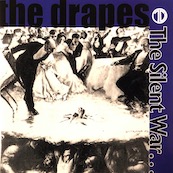 1997年にOnefoot
Recordsからリリースされたオレゴン産のDRAPESによる2ndアルバム。この作品、まさにWaterslideさんがおっしゃるとおり、前のめりに突っ込んでいくドラムに、ボーカルとギターが仕方がなく引きずられるようについていく独特の疾走感が魅力的です。スピード感はあるのに、いわゆるメロコア的な軽快さとは違う空気をまとっているのが面白いところ。5曲目の"Blame"あたりはもう、まさに大好物と言える仕上がりです。そしてアルバム全体の構成も練られていて、途中でパッヘルベルの「カノン」のインストを挟んだりと、単調にならない工夫が施されているのも好印象。LAGWAGONの流れを感じさせつつも、どこか違う雰囲気を持っているなと思っていたら、ふとNAVELが頭をよぎる瞬間も。…いや、違いましたね(笑)。ちなみにラストの"Taken
By Surprise"は、同郷のレジェンドPOISON IDEAの"FEEL THE
DARKNESS"に収録された楽曲のカバー。ただ、ジャケットのクレジット表記が間違っているような…?
1997年にOnefoot
Recordsからリリースされたオレゴン産のDRAPESによる2ndアルバム。この作品、まさにWaterslideさんがおっしゃるとおり、前のめりに突っ込んでいくドラムに、ボーカルとギターが仕方がなく引きずられるようについていく独特の疾走感が魅力的です。スピード感はあるのに、いわゆるメロコア的な軽快さとは違う空気をまとっているのが面白いところ。5曲目の"Blame"あたりはもう、まさに大好物と言える仕上がりです。そしてアルバム全体の構成も練られていて、途中でパッヘルベルの「カノン」のインストを挟んだりと、単調にならない工夫が施されているのも好印象。LAGWAGONの流れを感じさせつつも、どこか違う雰囲気を持っているなと思っていたら、ふとNAVELが頭をよぎる瞬間も。…いや、違いましたね(笑)。ちなみにラストの"Taken
By Surprise"は、同郷のレジェンドPOISON IDEAの"FEEL THE
DARKNESS"に収録された楽曲のカバー。ただ、ジャケットのクレジット表記が間違っているような…?
MENSAKA "LAS CANCIONES QUE NO QUERÍAS ESCUCHAR"
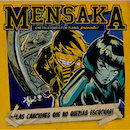 スペインのポップパンクが大好きなものの、どのバンドも似た雰囲気になりがちなので、新しく紹介するのは控えよう…と毎回思ってしまうのですが、このMENSAKAはスペイン産ではなくアルゼンチン産。だったら話は別ですね。紹介せずにはいられません。アルゼンチン訛りがあるのかもしれませんが、正直、私の鈍感な耳ではスペインとの違いを判別することはできません。ただ、そんなことはどうでもよくなるほど、このアルバムには心を打つメロディがあります。さらっと聴けばシンプルに思えますが、各曲のサビの掴みが絶妙で、最初から最後まで飽きさせない構成になっています。まるで計算され尽くしたかのような完成度の高さ。それでいて、漂う遣る瀬無さが胸に刺さるのです。2016年リリースの本作は、アルゼンチンのメロディック・ポップパンクの中でも光るものを持った作品であります。
スペインのポップパンクが大好きなものの、どのバンドも似た雰囲気になりがちなので、新しく紹介するのは控えよう…と毎回思ってしまうのですが、このMENSAKAはスペイン産ではなくアルゼンチン産。だったら話は別ですね。紹介せずにはいられません。アルゼンチン訛りがあるのかもしれませんが、正直、私の鈍感な耳ではスペインとの違いを判別することはできません。ただ、そんなことはどうでもよくなるほど、このアルバムには心を打つメロディがあります。さらっと聴けばシンプルに思えますが、各曲のサビの掴みが絶妙で、最初から最後まで飽きさせない構成になっています。まるで計算され尽くしたかのような完成度の高さ。それでいて、漂う遣る瀬無さが胸に刺さるのです。2016年リリースの本作は、アルゼンチンのメロディック・ポップパンクの中でも光るものを持った作品であります。
CORN FLAKES "CHILDISH"
 売り文句によると、「スペインの伝説的なメロディック・バンドによる名盤」とのことですが、正直、私はこれまでノーマークでした。1992年にBcoreからリリースされたCORN
FLAKESによる2ndアルバム。聴いてみると、なるほど、これは確かに語り継がれるべき一枚かもしれません。メロディはDOUGHBOYSを彷彿とさせ、疾走感はFACE
TO
FACE、そしてひねくれたALLのエッセンスを少し加えたような印象。でも、そこに水を少し足して薄めたような感覚があるのも事実です。しかし、このスピード感でこれほどまでに哀愁を詰め込むセンスは見事。気がつけば最後まで一気に聴き通してしまいます。また、歌詞が英語のためか、よくあるスペインのポップパンク特有の陽気さやクセの強さはあまり感じられません。今どきの音ではないかもしれませんが、この時代ならではの空気感と、勢いと、青臭さが詰まった痛快な作品です。「DOLL
メロディック狂必聴ディスクUK&ヨーロッパ編」にも紹介された一枚。
売り文句によると、「スペインの伝説的なメロディック・バンドによる名盤」とのことですが、正直、私はこれまでノーマークでした。1992年にBcoreからリリースされたCORN
FLAKESによる2ndアルバム。聴いてみると、なるほど、これは確かに語り継がれるべき一枚かもしれません。メロディはDOUGHBOYSを彷彿とさせ、疾走感はFACE
TO
FACE、そしてひねくれたALLのエッセンスを少し加えたような印象。でも、そこに水を少し足して薄めたような感覚があるのも事実です。しかし、このスピード感でこれほどまでに哀愁を詰め込むセンスは見事。気がつけば最後まで一気に聴き通してしまいます。また、歌詞が英語のためか、よくあるスペインのポップパンク特有の陽気さやクセの強さはあまり感じられません。今どきの音ではないかもしれませんが、この時代ならではの空気感と、勢いと、青臭さが詰まった痛快な作品です。「DOLL
メロディック狂必聴ディスクUK&ヨーロッパ編」にも紹介された一枚。
FIFTH HOUR HERO "NOT REVENGE... JUST A VICIOUS CRUSH"
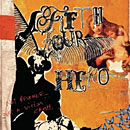 カナダ・ケベック出身のメロディック・バンド、FIFTH HOUR
HEROによる2006年の傑作2ndアルバム(No Idea
Recordsよりリリース)。哀愁と力強さが見事に絡み合う、男女ツインボーカルが最大の魅力です。特に掛け合いのパートが炸裂すると、もう最高に気分が盛り上がります。どの曲もキャッチーでありながら渋さが滲み出ており、TILTあたりが好きなら間違いなくハマるはずです(ちょっと毛色は違いますが…)。そして個人的に思い出深いのが、2006年11月28日・京都での来日ライブ。ごく普通の雰囲気のGenevieve嬢が、ギターを弾きながら熱唱する姿に思わず胸キュンしてしまいました。さらに、おっさんの方のギターにはJAWBREAKER、BROADWAYS、FIFTEENのステッカーがベタベタ貼ってありましたよ。なお、このアルバムのCDに隠しトラックとして収録されている"Wrong
Hit / Wrong
Answer"が圧倒的な超名曲。あまりの良さに涙腺崩壊レベルですが、どうやら誤って収録してしまったらしいです(NAVELのTomiさん情報、本来はTHIS
IS MY FISTとのSplit EPに収録されてます)。
カナダ・ケベック出身のメロディック・バンド、FIFTH HOUR
HEROによる2006年の傑作2ndアルバム(No Idea
Recordsよりリリース)。哀愁と力強さが見事に絡み合う、男女ツインボーカルが最大の魅力です。特に掛け合いのパートが炸裂すると、もう最高に気分が盛り上がります。どの曲もキャッチーでありながら渋さが滲み出ており、TILTあたりが好きなら間違いなくハマるはずです(ちょっと毛色は違いますが…)。そして個人的に思い出深いのが、2006年11月28日・京都での来日ライブ。ごく普通の雰囲気のGenevieve嬢が、ギターを弾きながら熱唱する姿に思わず胸キュンしてしまいました。さらに、おっさんの方のギターにはJAWBREAKER、BROADWAYS、FIFTEENのステッカーがベタベタ貼ってありましたよ。なお、このアルバムのCDに隠しトラックとして収録されている"Wrong
Hit / Wrong
Answer"が圧倒的な超名曲。あまりの良さに涙腺崩壊レベルですが、どうやら誤って収録してしまったらしいです(NAVELのTomiさん情報、本来はTHIS
IS MY FISTとのSplit EPに収録されてます)。
PARKWAY WRETCH "HOMESICK"
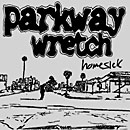 通販でよく見かける危険なキーワード、CRIMPSHRINE、FIFTEEN直系。それに釣られて何度痛い目を見てきたことでしょう。大抵は、FIFTEENとは似ても似つかない音で、せいぜいAaron
Cometbusが関わったSHOTWELLやBLANK
FIGHTを思わせるようなものばかり…。そんな中で迎えた2006年リリースの本作。これはついにCRIMPSHRINE、FIFTEEN直系認定マークを与えて良いかもしれません。もちろん、あの偉大な師匠に及ぶものではないのですが、スピード感を武器にしながらも、その雰囲気をしっかりと醸し出している点は間違いなく光るものがあります。特に"Superhero"のカッコ良さには心が震えました。疾走感に乗せて放たれるメロディは、どこか哀愁を帯びていて、まさにFIFTEENの影を垣間見せてくれる一曲です。もちろん、楽曲の完成度自体は師匠に遠く及ばないかもしれませんが、それでもあの空気感に触れることができるというだけで、このバンドの存在は貴重です。
通販でよく見かける危険なキーワード、CRIMPSHRINE、FIFTEEN直系。それに釣られて何度痛い目を見てきたことでしょう。大抵は、FIFTEENとは似ても似つかない音で、せいぜいAaron
Cometbusが関わったSHOTWELLやBLANK
FIGHTを思わせるようなものばかり…。そんな中で迎えた2006年リリースの本作。これはついにCRIMPSHRINE、FIFTEEN直系認定マークを与えて良いかもしれません。もちろん、あの偉大な師匠に及ぶものではないのですが、スピード感を武器にしながらも、その雰囲気をしっかりと醸し出している点は間違いなく光るものがあります。特に"Superhero"のカッコ良さには心が震えました。疾走感に乗せて放たれるメロディは、どこか哀愁を帯びていて、まさにFIFTEENの影を垣間見せてくれる一曲です。もちろん、楽曲の完成度自体は師匠に遠く及ばないかもしれませんが、それでもあの空気感に触れることができるというだけで、このバンドの存在は貴重です。
ARMCHAIR MARTIAN "MONSTERS ALWAYS SCREAM"
 コロラド産のARMCHAIR
MARTIANのこの作品は、JAWBREAKERやHÜSKER
DÜの影を感じさせつつも、土臭いカントリー要素を程よくブレンドした独特な仕上がりになっています。ちょっとかすれた声と物悲しいメロディが心を掴んで離しません。特に2曲目の"Crestfallen"は、まさにおしっこちびり級の大名曲と言っても過言ではありません。哀愁と激情が交錯するメロディラインに引き込まれ、心の奥底を揺さぶられるような感覚を味わえます。私は以前、2001年リリースの再発CD(14曲入り)を聴いていたのですが、念願叶って1998年リリースのオリジナル10インチレコードを入手することができました。オリジナル盤は、ジャケットデザインが異なるだけでなく、ボーナス曲が4曲削られたことで、より凝縮された印象を受けます。ちなみに、元ALLのChad
Priceがベースプレイヤーとして4曲にクレジットされているのもファンには嬉しいポイントです。Joey
Capeが運営するMy Recordsからリリースされました。
コロラド産のARMCHAIR
MARTIANのこの作品は、JAWBREAKERやHÜSKER
DÜの影を感じさせつつも、土臭いカントリー要素を程よくブレンドした独特な仕上がりになっています。ちょっとかすれた声と物悲しいメロディが心を掴んで離しません。特に2曲目の"Crestfallen"は、まさにおしっこちびり級の大名曲と言っても過言ではありません。哀愁と激情が交錯するメロディラインに引き込まれ、心の奥底を揺さぶられるような感覚を味わえます。私は以前、2001年リリースの再発CD(14曲入り)を聴いていたのですが、念願叶って1998年リリースのオリジナル10インチレコードを入手することができました。オリジナル盤は、ジャケットデザインが異なるだけでなく、ボーナス曲が4曲削られたことで、より凝縮された印象を受けます。ちなみに、元ALLのChad
Priceがベースプレイヤーとして4曲にクレジットされているのもファンには嬉しいポイントです。Joey
Capeが運営するMy Recordsからリリースされました。
疲れた〜。ブログで頻繁にディスクレビューしている人ってとっても偉いです。
【MY BEST 161〜180に進む】
【MY BEST 121〜140に戻る】
【FIFTEENとLEATHERFACEが好きだ!に戻る】
【姉妹ページ海外旅行記 小市民の気弱な旅へ】