TRAVOLTAS "ENDLESS SUMMER"
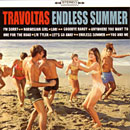 この音そしてこのジャケットから想像できないオランダ産。この2002年にRadio Blast
RecordingsなどからリリースされたTRAVOLTASによる3rdアルバムはBEACH
BOYSやRAMONESからの影響があるサーフ・ポップ・パンクです。確かにそれらを聴き、影響を受けたうえでやっているのでしょうが、とはいえ巷のバンドとは頭一つ飛び抜けている曲の美しさとハーモニーが際立っているからこそ広く世界で評価されているのだと思います。1曲目"One
For The Road"を聴くだけで分かります。やっぱり世界は広い。SONIC SURF CITYやYUM
YUMS等がお好きな方は間違いなく大丈夫なのでは。で、8曲目"Lori"を聴いているとなぜかTHE HOUSE OF
LOVEと似ているかなと思いましたが、はい、皆さんにはどうでもいいことですね。ちなみにプレミアが付いていて、傑作とされている2ndアルバム"MODERN
WORLD"については個人的には定価以上のお金を出してまで買うほどでもないと思います。
この音そしてこのジャケットから想像できないオランダ産。この2002年にRadio Blast
RecordingsなどからリリースされたTRAVOLTASによる3rdアルバムはBEACH
BOYSやRAMONESからの影響があるサーフ・ポップ・パンクです。確かにそれらを聴き、影響を受けたうえでやっているのでしょうが、とはいえ巷のバンドとは頭一つ飛び抜けている曲の美しさとハーモニーが際立っているからこそ広く世界で評価されているのだと思います。1曲目"One
For The Road"を聴くだけで分かります。やっぱり世界は広い。SONIC SURF CITYやYUM
YUMS等がお好きな方は間違いなく大丈夫なのでは。で、8曲目"Lori"を聴いているとなぜかTHE HOUSE OF
LOVEと似ているかなと思いましたが、はい、皆さんにはどうでもいいことですね。ちなみにプレミアが付いていて、傑作とされている2ndアルバム"MODERN
WORLD"については個人的には定価以上のお金を出してまで買うほどでもないと思います。
THE HEXTALLS "CALL IT A COMEBACK"
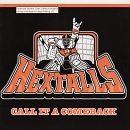 カナダ産のTHE
HEXTALLSによる2008年リリースの3rdアルバム。正直なところ、この作品に特別な個性を感じるかと言えば、そうではないかもしれません。彼ら自身もおそらく、独自性を追求するよりも純粋に楽しく演奏することに重きを置いているのでしょう。その音楽性は、いわゆるERGS!やTEENAGE
BOTTLEROCKET系のポップ・パンク。耳にすっと馴染む親しみやすさがあって、どこかで聴いたような感覚も否めません。だけど、それがどうしたって話です。だって、このアルバムは一貫して、胸が張り裂けそうなポップさをメガ盛りにした良曲の宝庫なのですから。例えば、"On
the Third Day, Axl
Rose"など、聴いていて思わず笑みがこぼれるほどキャッチーで楽しい曲たちが次々と溢れ出してきます。テンポよく進んでいく楽曲群の中に、時折見せる哀愁がまた心地よくてたまりません。
カナダ産のTHE
HEXTALLSによる2008年リリースの3rdアルバム。正直なところ、この作品に特別な個性を感じるかと言えば、そうではないかもしれません。彼ら自身もおそらく、独自性を追求するよりも純粋に楽しく演奏することに重きを置いているのでしょう。その音楽性は、いわゆるERGS!やTEENAGE
BOTTLEROCKET系のポップ・パンク。耳にすっと馴染む親しみやすさがあって、どこかで聴いたような感覚も否めません。だけど、それがどうしたって話です。だって、このアルバムは一貫して、胸が張り裂けそうなポップさをメガ盛りにした良曲の宝庫なのですから。例えば、"On
the Third Day, Axl
Rose"など、聴いていて思わず笑みがこぼれるほどキャッチーで楽しい曲たちが次々と溢れ出してきます。テンポよく進んでいく楽曲群の中に、時折見せる哀愁がまた心地よくてたまりません。
VAGINASORE JR "VAGINASORE JR"
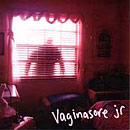 フロリダ産のVAGINASORE JRによる2006年の1stアルバム。A.D.D.
Recordsからのリリースです。まずバンド名からしてなんとも挑発的な響きがありますが、この作品の魅力は、哀愁漂うメロディ展開と疾走感の絶妙な組み合わせにあります。ラフで熱いボーカルと、それを支えるバックコーラスが涙と鼻水を流しながら叫んでいるかのような(勝手な想像です...)熱量を感じさせてくれます。OFF
WITH THEIR
HEADSをもう少し柔らかくしたような音でありながら、内に秘めた寂寞感や焦燥感が伝わってくるのです。10曲をわずか21分で駆け抜けるテンポ感も素晴らしく、特に後半に収録されている名曲"Rules"は、熱いメロディが胸に強く突き刺さります。彼らのエネルギーとセンスが見事に詰め込まれた一曲です。ちなみに2ndアルバムの"THIS
HERE PENINSULA"もちょっと爽やかになっているものの根本は変わっておらず、おすすめであります。
フロリダ産のVAGINASORE JRによる2006年の1stアルバム。A.D.D.
Recordsからのリリースです。まずバンド名からしてなんとも挑発的な響きがありますが、この作品の魅力は、哀愁漂うメロディ展開と疾走感の絶妙な組み合わせにあります。ラフで熱いボーカルと、それを支えるバックコーラスが涙と鼻水を流しながら叫んでいるかのような(勝手な想像です...)熱量を感じさせてくれます。OFF
WITH THEIR
HEADSをもう少し柔らかくしたような音でありながら、内に秘めた寂寞感や焦燥感が伝わってくるのです。10曲をわずか21分で駆け抜けるテンポ感も素晴らしく、特に後半に収録されている名曲"Rules"は、熱いメロディが胸に強く突き刺さります。彼らのエネルギーとセンスが見事に詰め込まれた一曲です。ちなみに2ndアルバムの"THIS
HERE PENINSULA"もちょっと爽やかになっているものの根本は変わっておらず、おすすめであります。
ANOTHER FINE MESS "MILLION SMILES"
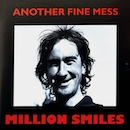 個人的には有名VA"The Best Punk Rock In England, Man"での収録曲"Fab
66"でしか知らなかったバンドANOTHER FINE
MESS。そもそもその曲自体の印象が薄いし、本作品に収録されている涙を誘う超名曲である1曲目"Smile"なんかを収録してくれていたのなら、前からがっつり注目していたのでしょうが…。個人的には再評価できたのは、FIXING
A HOLE
RECORDSさんが本作及びその他盛り沢山の2枚組編集盤CDをリリースしていただいたおかげなのですが、あまりに良すぎて後日このオリジナルアルバムCDを入手した経緯があります。ダイナミックレンジが狭いせいか、今時感がない昔のUKメロディックの音で、曲自体には抑揚があるものの、なぜか地味というかキラキラしていないのが、妙に心地良い。勘違いかも知れませんが、彼らはJAMが好きなのではと思うようなフレーズが何箇所かでチラホラと聴こえてきます。まぁWACTなんかのショボいポップパンクがお好きなら手に取って頂ければと思います。1992年にリリースされた唯一のアルバム。
個人的には有名VA"The Best Punk Rock In England, Man"での収録曲"Fab
66"でしか知らなかったバンドANOTHER FINE
MESS。そもそもその曲自体の印象が薄いし、本作品に収録されている涙を誘う超名曲である1曲目"Smile"なんかを収録してくれていたのなら、前からがっつり注目していたのでしょうが…。個人的には再評価できたのは、FIXING
A HOLE
RECORDSさんが本作及びその他盛り沢山の2枚組編集盤CDをリリースしていただいたおかげなのですが、あまりに良すぎて後日このオリジナルアルバムCDを入手した経緯があります。ダイナミックレンジが狭いせいか、今時感がない昔のUKメロディックの音で、曲自体には抑揚があるものの、なぜか地味というかキラキラしていないのが、妙に心地良い。勘違いかも知れませんが、彼らはJAMが好きなのではと思うようなフレーズが何箇所かでチラホラと聴こえてきます。まぁWACTなんかのショボいポップパンクがお好きなら手に取って頂ければと思います。1992年にリリースされた唯一のアルバム。
STOLEN BIKES RIDE FASTER "NOTHING HAS CHANGED"
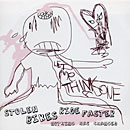 最初にイタリア産のSTOLEN BIKES RIDE
FASTERが2006年にリリースしたこのアルバムを聴いたときは、正直なところ感情があまり揺さぶられませんでした。でも、ある日、音量を上げて再生してみたときに、自分はこの作品をちゃんと聴いてあげられていなかった、と気付いたのです。激しいだみ声でバタバタと勢いだけで突っ走っているだけかと思いきや、実はエモーショナルなメロディと疾走感が見事に同居しているじゃないですか。特に名曲"Eyesblinder"は、荒削りな演奏の中にもキラリと光るグッドメロディがしっかりと埋め込まれていて、物悲しさがじんわりと胸に染み渡ってきました。例えるのが難しいバンドですが、あえて言うならLEATHERFACEとMILES
APARTを足して2で割ったら壮大になりすぎるので、あえて3で割ったような感じでしょうか?無骨でラフな雰囲気の中にも繊細な美しさがしっかりと感じられるところが、彼らの魅力だと思います。
最初にイタリア産のSTOLEN BIKES RIDE
FASTERが2006年にリリースしたこのアルバムを聴いたときは、正直なところ感情があまり揺さぶられませんでした。でも、ある日、音量を上げて再生してみたときに、自分はこの作品をちゃんと聴いてあげられていなかった、と気付いたのです。激しいだみ声でバタバタと勢いだけで突っ走っているだけかと思いきや、実はエモーショナルなメロディと疾走感が見事に同居しているじゃないですか。特に名曲"Eyesblinder"は、荒削りな演奏の中にもキラリと光るグッドメロディがしっかりと埋め込まれていて、物悲しさがじんわりと胸に染み渡ってきました。例えるのが難しいバンドですが、あえて言うならLEATHERFACEとMILES
APARTを足して2で割ったら壮大になりすぎるので、あえて3で割ったような感じでしょうか?無骨でラフな雰囲気の中にも繊細な美しさがしっかりと感じられるところが、彼らの魅力だと思います。
ANTI-ANTI "HOORAY FOR EVERYTHING"
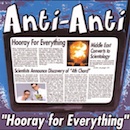 フロリダ産とはいえ、このANTI-ANTIのCDから感じられるのは、ゴリゴリの熱さや重厚さとは対極にある青くて甘酸っぱい疾走感です。まさに1990年代後期のポップパンク好きに突き刺さる音。2003年にFastmusicからリリースされたこのアルバムは、CLETUSやWALKERを思わせつつも、その哀愁を少し和らげた軽快さと爽やかさが特徴的です。Web上では評価が低かったり語られていない感じですが、それでもこのアルバムを無視してしまうのはもったいないと思います。特に、4曲目の"I
Want You Back"から5曲目の"It’s Gotta Suck to be a
Girl"へと流れる展開は、本当に気分を高揚させてくれるとともに勢いに乗って駆け抜ける感じが心地良いです。Discogsを見てみると、過去の作品と同じ曲名が多いことから編集盤扱いの可能性もありますが、それでも十分に楽しめる内容です。
フロリダ産とはいえ、このANTI-ANTIのCDから感じられるのは、ゴリゴリの熱さや重厚さとは対極にある青くて甘酸っぱい疾走感です。まさに1990年代後期のポップパンク好きに突き刺さる音。2003年にFastmusicからリリースされたこのアルバムは、CLETUSやWALKERを思わせつつも、その哀愁を少し和らげた軽快さと爽やかさが特徴的です。Web上では評価が低かったり語られていない感じですが、それでもこのアルバムを無視してしまうのはもったいないと思います。特に、4曲目の"I
Want You Back"から5曲目の"It’s Gotta Suck to be a
Girl"へと流れる展開は、本当に気分を高揚させてくれるとともに勢いに乗って駆け抜ける感じが心地良いです。Discogsを見てみると、過去の作品と同じ曲名が多いことから編集盤扱いの可能性もありますが、それでも十分に楽しめる内容です。
THE TATTLE TALES "HEARTS IN TUNE"
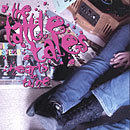 ニューヨーク産のTHE TATTLE
TALESが2006年にリリースした1stアルバムは、伸びやかで爽やかなボーカルとポップなメロディが何よりも魅力的な一枚。ジャンルとしてはパワーポップと呼ぶのがしっくりくるかもしれません。このアルバムに流れるのは、心温まるような甘酸っぱさと開放感で、まるでアメリカのカラフルで甘いお菓子を頬張るような幸福感を味わえます。それは古くはBEACH
BOYSから、WEEZER、ERGS、UNLOVABLES、LOCAL
BOYSといった名だたるバンドたちが持っていたポップの魔法をしっかりと受け継いでいる証拠でもあると思います。特に1曲目の”Lucky
Girl”。このシンセが効果的に使われた楽曲は、アルバムのスタートにふさわしいキラキラとしたエネルギーに満ちています。気分が沈んでいる時でも、この曲を聴けば自然と笑顔になってしまうようなポジティブな力を感じさせてくれます。
ニューヨーク産のTHE TATTLE
TALESが2006年にリリースした1stアルバムは、伸びやかで爽やかなボーカルとポップなメロディが何よりも魅力的な一枚。ジャンルとしてはパワーポップと呼ぶのがしっくりくるかもしれません。このアルバムに流れるのは、心温まるような甘酸っぱさと開放感で、まるでアメリカのカラフルで甘いお菓子を頬張るような幸福感を味わえます。それは古くはBEACH
BOYSから、WEEZER、ERGS、UNLOVABLES、LOCAL
BOYSといった名だたるバンドたちが持っていたポップの魔法をしっかりと受け継いでいる証拠でもあると思います。特に1曲目の”Lucky
Girl”。このシンセが効果的に使われた楽曲は、アルバムのスタートにふさわしいキラキラとしたエネルギーに満ちています。気分が沈んでいる時でも、この曲を聴けば自然と笑顔になってしまうようなポジティブな力を感じさせてくれます。
THE PETTYFORDS "ALOHA MEANS GOODBYE"
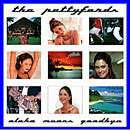 「アロハ」という言葉や「ムラカミ」なんてメンバーがいたりすることからして、まさにハワイ産かと思わせるTHE
PETTYFORDSの唯一のアルバム。2000年に天下のWhoa Oh
Recordsからリリースされたこの作品、一見しょぼめのポップパンクに思えるけれど、聴けば聴くほど不思議な味わいが増していく一枚です。聴き始めは、SKIMMERやWALKERをさらにゆるくしたような、どこか頼りないサウンドに感じられるかもしれません。でも、しばらくするとSICKOにも通じるような軽快さとシンプルな楽しさが顔をのぞかせます。おもちゃのような軽やかなボーカルの声質がとにかくユニークで耳に残るとともに、音全体がハワイのゆるくて暖かい風を感じさせながらも、どこかほろ苦さを含んでいるところがまた魅力的です。特にお気に入りなのが、2曲目の”Kids
And Parents
Alike”。この曲の緩やかで親しみやすいメロディは、まるで夕暮れ時のビーチでのんびりと過ごしているような気分にさせてくれます。
「アロハ」という言葉や「ムラカミ」なんてメンバーがいたりすることからして、まさにハワイ産かと思わせるTHE
PETTYFORDSの唯一のアルバム。2000年に天下のWhoa Oh
Recordsからリリースされたこの作品、一見しょぼめのポップパンクに思えるけれど、聴けば聴くほど不思議な味わいが増していく一枚です。聴き始めは、SKIMMERやWALKERをさらにゆるくしたような、どこか頼りないサウンドに感じられるかもしれません。でも、しばらくするとSICKOにも通じるような軽快さとシンプルな楽しさが顔をのぞかせます。おもちゃのような軽やかなボーカルの声質がとにかくユニークで耳に残るとともに、音全体がハワイのゆるくて暖かい風を感じさせながらも、どこかほろ苦さを含んでいるところがまた魅力的です。特にお気に入りなのが、2曲目の”Kids
And Parents
Alike”。この曲の緩やかで親しみやすいメロディは、まるで夕暮れ時のビーチでのんびりと過ごしているような気分にさせてくれます。
THE REAL DANGER "MAKING ENEMIES"
 THE REAL
DANGERはオランダ産のポップパンクバンドで、本作は2010年にShield
Recordingsからリリースされた2ndアルバム。オランダのバンドを紹介するのは珍しいと思いきや、そういえば以前にTRAVOLTASも取り上げていましたね。確かに海外のWebサイトで紹介されているようにDESCENDENTS/ALL、ERGSを足して、FACE
TO
FACEのスパイスを振りかけて4で割ったような感じです。各バンドの雰囲気にそっくりな曲もありますが、うまく自分たちのスタイルに溶け込ませているのが好印象です。ということで、個性は傍において、アルバム全体のクオリティの高さには感心です。各曲がしっかりと作り込まれていて、聴き進めるうちにこのバンドの持つエネルギーとメロディセンスに引き込まれていきます。そして、SUPERCHUNKに敬意を払った直球のカバー曲"Skip
Steps 1&3"に感激です。
THE REAL
DANGERはオランダ産のポップパンクバンドで、本作は2010年にShield
Recordingsからリリースされた2ndアルバム。オランダのバンドを紹介するのは珍しいと思いきや、そういえば以前にTRAVOLTASも取り上げていましたね。確かに海外のWebサイトで紹介されているようにDESCENDENTS/ALL、ERGSを足して、FACE
TO
FACEのスパイスを振りかけて4で割ったような感じです。各バンドの雰囲気にそっくりな曲もありますが、うまく自分たちのスタイルに溶け込ませているのが好印象です。ということで、個性は傍において、アルバム全体のクオリティの高さには感心です。各曲がしっかりと作り込まれていて、聴き進めるうちにこのバンドの持つエネルギーとメロディセンスに引き込まれていきます。そして、SUPERCHUNKに敬意を払った直球のカバー曲"Skip
Steps 1&3"に感激です。
DOWN AND OUTS "FRIDAY NIGHTS MONDAY MORNINGS"
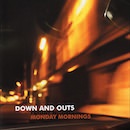 DOWN AND
OUTSは、GRAMPUS EIGHTのMark
Magillがギター&ボーカルであると紹介されているバンドであり、本作は2ndアルバム(2007年リリース)。でも「あのGRAMPUS
EIGHTね。なるほど、ふむふむ。」と納得される方は日本にどのくらい存在するのでしょう?ちなみにそのバンド名はあの名古屋の某チームからだそうです。で、本作品。イギリスならではの物悲しいながらも、盛り上がる曲をぶちこんだ逸品であります。どこのサイトでもポップパンクとOiなどのストリート・パンクの融合という感じで紹介されており、確かなその通りなのですが、でも5曲目"Anchors
Away"なんか、それだけでは語りきれない味わい深いまさに泣きのUKメロディックそのものな名曲だと思います。CLASH好きなんかもイケるかも。2018年7月の京都でのスタジオライブ行きましたが全曲キャッチーで良かったです。
DOWN AND
OUTSは、GRAMPUS EIGHTのMark
Magillがギター&ボーカルであると紹介されているバンドであり、本作は2ndアルバム(2007年リリース)。でも「あのGRAMPUS
EIGHTね。なるほど、ふむふむ。」と納得される方は日本にどのくらい存在するのでしょう?ちなみにそのバンド名はあの名古屋の某チームからだそうです。で、本作品。イギリスならではの物悲しいながらも、盛り上がる曲をぶちこんだ逸品であります。どこのサイトでもポップパンクとOiなどのストリート・パンクの融合という感じで紹介されており、確かなその通りなのですが、でも5曲目"Anchors
Away"なんか、それだけでは語りきれない味わい深いまさに泣きのUKメロディックそのものな名曲だと思います。CLASH好きなんかもイケるかも。2018年7月の京都でのスタジオライブ行きましたが全曲キャッチーで良かったです。
BLUELINE MEDIC "THE APOLOGY WARS"
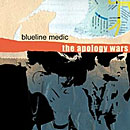 BLUELINE
MEDICのこの1stアルバムは、2001年にFueled By
Ramenからのリリース。プロデュースを担当したのは、あのJAWBOX等のJ.
Robbins。もはや説明不要の大御所による手腕が光る作品です。とはいえ、BLUELINE
MEDIC自体もただの新人バンドではありません。メンバーにはオーストラリアの名バンドCAUSTIC
SODA(最高!)での経験を持つ者も含まれており、ベテランならではの渋みと深みをたっぷり感じさせてくれます。このアルバムの魅力は何といっても感情のこもった緻密な演奏と、美しくも感傷的なメロディにあります。後期JAWBREAKERや渋めのALKALINE
TRIOを好む人には、確実に響くのではないでしょうか。特に印象的なのは、3曲目の"Making The Nouveau
Riche"や4曲目の"At Least We Had The War"。感情がじわりと染み渡ってくるような名曲です。
BLUELINE
MEDICのこの1stアルバムは、2001年にFueled By
Ramenからのリリース。プロデュースを担当したのは、あのJAWBOX等のJ.
Robbins。もはや説明不要の大御所による手腕が光る作品です。とはいえ、BLUELINE
MEDIC自体もただの新人バンドではありません。メンバーにはオーストラリアの名バンドCAUSTIC
SODA(最高!)での経験を持つ者も含まれており、ベテランならではの渋みと深みをたっぷり感じさせてくれます。このアルバムの魅力は何といっても感情のこもった緻密な演奏と、美しくも感傷的なメロディにあります。後期JAWBREAKERや渋めのALKALINE
TRIOを好む人には、確実に響くのではないでしょうか。特に印象的なのは、3曲目の"Making The Nouveau
Riche"や4曲目の"At Least We Had The War"。感情がじわりと染み渡ってくるような名曲です。
THE STEINWAYS "GORILLA MARKETING"
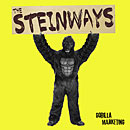 ニューヨーク産のTHE STEINWAYSによるこの2ndアルバムは、2008年にCold Feet
Recordsからリリースされた一枚です。実を言うと、彼らの1stアルバム"MISSED THE
BOAT"は私には全く響いてきませんでした。しかし、この2ndアルバムにはいい意味で裏切られました。巷では「1stを軽く超えた」との評判がありましたが、「あの1stを超えたって言われてもなぁ…」と半信半疑で購入してみたところ、これが見事にヒット。個人的には1stとは別物と考えても良いくらい、数段上の完成度を感じました。荒削りながらも、ポップパンクとしての勢いと甘酸っぱさが絶妙にブレンドされており、前作とは比べものにならないほどキャッチーで魅力的な作品に仕上がっています。バンドとしての個性という点では課題が残っているかもしれませんが、それを補って余りある勢いと爽快感が感じられる作品です。
ニューヨーク産のTHE STEINWAYSによるこの2ndアルバムは、2008年にCold Feet
Recordsからリリースされた一枚です。実を言うと、彼らの1stアルバム"MISSED THE
BOAT"は私には全く響いてきませんでした。しかし、この2ndアルバムにはいい意味で裏切られました。巷では「1stを軽く超えた」との評判がありましたが、「あの1stを超えたって言われてもなぁ…」と半信半疑で購入してみたところ、これが見事にヒット。個人的には1stとは別物と考えても良いくらい、数段上の完成度を感じました。荒削りながらも、ポップパンクとしての勢いと甘酸っぱさが絶妙にブレンドされており、前作とは比べものにならないほどキャッチーで魅力的な作品に仕上がっています。バンドとしての個性という点では課題が残っているかもしれませんが、それを補って余りある勢いと爽快感が感じられる作品です。
VIBEKE SAUGESTAD "THE WORLD FAMOUS HAT TRICK"
 心が荒んで晴れないとき、優しさと温もりに包まれるような癒しを求めるなら、このアルバムはまさに最適です。あの偉大なパワーポップ・バンドYUM
YUMSでオルガンを担当していたVIBEKE
SAUGESTADが2007年にリリースしたソロ作品。これが彼女の3rdアルバムであり(LPはScreaming
Appleからリリース)、ノルウェー産のポップマジックが詰まった一枚。まだ聴いたことがない人のために例えるなら、BLONDIEをさらにキュートで甘酸っぱい方向に振り切ったようなサウンド、と言えば伝わるでしょうか。1曲目の"He’s
Peculiar"からして、甘美でキャッチーなメロディが心に飛び込んできます。バックを支えるのはYUM
YUMSのメンバーたちですから、そのメロディの心地よさの威力は間違いありません。特に9曲目の"Stupid"は、PRETENDERSの名曲"Kid"を思い起こさせる哀愁が胸を締めつけます。
心が荒んで晴れないとき、優しさと温もりに包まれるような癒しを求めるなら、このアルバムはまさに最適です。あの偉大なパワーポップ・バンドYUM
YUMSでオルガンを担当していたVIBEKE
SAUGESTADが2007年にリリースしたソロ作品。これが彼女の3rdアルバムであり(LPはScreaming
Appleからリリース)、ノルウェー産のポップマジックが詰まった一枚。まだ聴いたことがない人のために例えるなら、BLONDIEをさらにキュートで甘酸っぱい方向に振り切ったようなサウンド、と言えば伝わるでしょうか。1曲目の"He’s
Peculiar"からして、甘美でキャッチーなメロディが心に飛び込んできます。バックを支えるのはYUM
YUMSのメンバーたちですから、そのメロディの心地よさの威力は間違いありません。特に9曲目の"Stupid"は、PRETENDERSの名曲"Kid"を思い起こさせる哀愁が胸を締めつけます。
BACKWOOD CREATURES "LIVING LEGENDS"
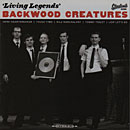 BACKWOOD
CREATURESは、ドイツ・ケルン産のポップパンク・バンドで、この2ndアルバムは2003年にStardumb
Recordsからリリースされました。ちなみに、ケルンといえば京都市の姉妹都市ですが、このアルバムからはまったくと言っていいほどドイツっぽさは感じません。むしろ、アメリカの1990年代ポップパンクの流れをしっかりと受け継いでいて、METHADONESやQUEERSを足して割ったようなRAMONESリスペクトのポップパンクといったところでしょうか。特に7曲目の"Dance’til
Dawn"は、うきうきとしたリズムとメロディが最高に気持ちよく、思わず体が動き出してしまうような仕上がりです。さらに、ボーカルの声質がPEAWEESやDEVIL
DOGSといったガレージパンク的なロックンロール魂を感じさせる点も大きな魅力です。ちょっとざらついた質感が楽曲に奥行きを与え、爽やかなだけでは終わらない味わいを生み出しています。アルバムタイトルの「生きた伝説」という言葉は大げさかもしれませんが気持ち良いです。
BACKWOOD
CREATURESは、ドイツ・ケルン産のポップパンク・バンドで、この2ndアルバムは2003年にStardumb
Recordsからリリースされました。ちなみに、ケルンといえば京都市の姉妹都市ですが、このアルバムからはまったくと言っていいほどドイツっぽさは感じません。むしろ、アメリカの1990年代ポップパンクの流れをしっかりと受け継いでいて、METHADONESやQUEERSを足して割ったようなRAMONESリスペクトのポップパンクといったところでしょうか。特に7曲目の"Dance’til
Dawn"は、うきうきとしたリズムとメロディが最高に気持ちよく、思わず体が動き出してしまうような仕上がりです。さらに、ボーカルの声質がPEAWEESやDEVIL
DOGSといったガレージパンク的なロックンロール魂を感じさせる点も大きな魅力です。ちょっとざらついた質感が楽曲に奥行きを与え、爽やかなだけでは終わらない味わいを生み出しています。アルバムタイトルの「生きた伝説」という言葉は大げさかもしれませんが気持ち良いです。
SHONBEN "1999"
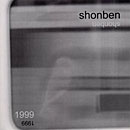 SHONBENというバンド名を見たときに、思わず「日本語?」と思いましたが、やはり「小便」からきているんですね。このバンドは、元BROCCOLIのベースであるScott
Stewart(こちらではギターを担当?)と、ドラムのGraeme
Gilmourが短期間在籍したプロジェクトだそうです。2003年にNewest Industry
Recordsからリリースされた唯一のアルバム編集盤。BROCCOLIという名を聞くだけで胸が高鳴るUKメロディックファンにとっては、思わず手に取ってしまいたくなる一枚ではないでしょうか。最初に聴いたときは、地味で陰気で、疾走感にも欠けるように感じました。しかし、ふともう一度大音量で聴いてみると、凡庸だと思っていた曲が、美しいメロディへと脳内で変換されていき、気づけばその音楽に癒されている自分がいました。音の印象としては、BROCCOLIとAPPLEORCHARDの中間的なサウンドといった感じでしょうか。特に2曲目の"Souvenirs"は、まさにその良さを象徴する一曲だと思います。
SHONBENというバンド名を見たときに、思わず「日本語?」と思いましたが、やはり「小便」からきているんですね。このバンドは、元BROCCOLIのベースであるScott
Stewart(こちらではギターを担当?)と、ドラムのGraeme
Gilmourが短期間在籍したプロジェクトだそうです。2003年にNewest Industry
Recordsからリリースされた唯一のアルバム編集盤。BROCCOLIという名を聞くだけで胸が高鳴るUKメロディックファンにとっては、思わず手に取ってしまいたくなる一枚ではないでしょうか。最初に聴いたときは、地味で陰気で、疾走感にも欠けるように感じました。しかし、ふともう一度大音量で聴いてみると、凡庸だと思っていた曲が、美しいメロディへと脳内で変換されていき、気づけばその音楽に癒されている自分がいました。音の印象としては、BROCCOLIとAPPLEORCHARDの中間的なサウンドといった感じでしょうか。特に2曲目の"Souvenirs"は、まさにその良さを象徴する一曲だと思います。
THE POPSTERS "OUR BITES BRING YOU BACK"
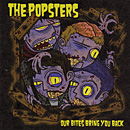 イタリアのメロディックといえば、MILES
APART。ガレージシーンならPEAWEES。そして、ポップパンクの代表格として名前を挙げるなら、このPOPSTERSになるのでしょうか。2008年にリリースされた3rdアルバムは、そんなイタリアから届けられた一品です。イタリア産のアルバムはそれ程、所有していないのですが、どれも意外とステレオタイプ的なラテンな明るい感じがせず、青くて切ない作品が多いですよね。本作もポップパンクの王道とも言える爽快なメロディと、時折見せるうら寂しさが絶妙に組み合わさっており、シンプルながらも普遍的な魅力があります。最後の曲である"Promise"なんかは、甘酸っぱくて特にその良さが際立っています。なお、MYSPACEによると、彼らが影響を受けたバンドとして名前を挙げているのはRAMONESやFACE
TO FACE。なるほど。
イタリアのメロディックといえば、MILES
APART。ガレージシーンならPEAWEES。そして、ポップパンクの代表格として名前を挙げるなら、このPOPSTERSになるのでしょうか。2008年にリリースされた3rdアルバムは、そんなイタリアから届けられた一品です。イタリア産のアルバムはそれ程、所有していないのですが、どれも意外とステレオタイプ的なラテンな明るい感じがせず、青くて切ない作品が多いですよね。本作もポップパンクの王道とも言える爽快なメロディと、時折見せるうら寂しさが絶妙に組み合わさっており、シンプルながらも普遍的な魅力があります。最後の曲である"Promise"なんかは、甘酸っぱくて特にその良さが際立っています。なお、MYSPACEによると、彼らが影響を受けたバンドとして名前を挙げているのはRAMONESやFACE
TO FACE。なるほど。
LOVEJUNK "TRIBULATIONS"
 LOVEJUNKは、あのPERFECT
DAZEなどのメンバーによって結成されたバンドであり、この1stアルバムは、2001年に名門Crackle
Recordsからリリースされています。2ndアルバム"AMSTRADIVARIUS"も悪くはないのですが(録音自体はこちらの方が古いとのこと)、どうも印象が薄いというのが正直なところ。やはりこの1stアルバムの方に魅力を感じます。何と言っても、名曲"Jealous"をはじめとするキャッチーでポップな楽曲がこのアルバムの魅力を際立たせています。疾走感のあるテンポに、悲哀を帯びたボーカル、そしてザクザクとしたギターのコンビネーションが最高です。
各曲が非常に高水準でまとめられているため、これをハズレだと感じるUKメロディック・ファンはほとんどいないのではないでしょうか。少なくとも、歴史的に重要な存在であるPERFECT
DAZEよりも、まずはこちらを手に入れるべきだと思います。
LOVEJUNKは、あのPERFECT
DAZEなどのメンバーによって結成されたバンドであり、この1stアルバムは、2001年に名門Crackle
Recordsからリリースされています。2ndアルバム"AMSTRADIVARIUS"も悪くはないのですが(録音自体はこちらの方が古いとのこと)、どうも印象が薄いというのが正直なところ。やはりこの1stアルバムの方に魅力を感じます。何と言っても、名曲"Jealous"をはじめとするキャッチーでポップな楽曲がこのアルバムの魅力を際立たせています。疾走感のあるテンポに、悲哀を帯びたボーカル、そしてザクザクとしたギターのコンビネーションが最高です。
各曲が非常に高水準でまとめられているため、これをハズレだと感じるUKメロディック・ファンはほとんどいないのではないでしょうか。少なくとも、歴史的に重要な存在であるPERFECT
DAZEよりも、まずはこちらを手に入れるべきだと思います。
DOCTOR BISON "DEWHURSTS-THE MUSICAL"
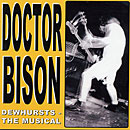 DOCTOR
BISONの唯一のこのアルバムは、1998年にMother Stoat Recording
Co.からのリリース。元ABS、LEATHERFACEのおっさんたちが織り成すこの作品は、派手さこそないものの、熟練の渋みと味わい深さで勝負する仕上がりとなっています。全8曲で35分というコンパクトな内容ですが、そこに詰まった濃密な世界観は聴きごたえ十分。バンジョーらしきアコースティックな曲も収録されており、個性的な音作りが耳に心地よく響きます。元ABSのBaz
Oldfieldが曲を書いているらしく、彼の伸びやかで渋さも兼ね備えたボーカルが全体を引っ張ってくれています。中でも2曲目の"Delusion
Of Grace"は隠れた名曲と言えるでしょう。そして忘れてはならないのが、元LEATHERFACEのDickie
Hammond兄貴が曲中で泣かせるギターのフレーズは、聴く者を強烈に引き込む力を持っています。
DOCTOR
BISONの唯一のこのアルバムは、1998年にMother Stoat Recording
Co.からのリリース。元ABS、LEATHERFACEのおっさんたちが織り成すこの作品は、派手さこそないものの、熟練の渋みと味わい深さで勝負する仕上がりとなっています。全8曲で35分というコンパクトな内容ですが、そこに詰まった濃密な世界観は聴きごたえ十分。バンジョーらしきアコースティックな曲も収録されており、個性的な音作りが耳に心地よく響きます。元ABSのBaz
Oldfieldが曲を書いているらしく、彼の伸びやかで渋さも兼ね備えたボーカルが全体を引っ張ってくれています。中でも2曲目の"Delusion
Of Grace"は隠れた名曲と言えるでしょう。そして忘れてはならないのが、元LEATHERFACEのDickie
Hammond兄貴が曲中で泣かせるギターのフレーズは、聴く者を強烈に引き込む力を持っています。
SHADES APART "SHADES APART"
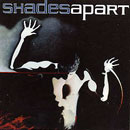 DAG
NASTYがお好きな方にはぜひおすすめしたい、SHADES
APARTのセルフタイトル1stアルバム。メロディックの静かなる古典的名盤。1988年にWishingwell
Recordsからリリースされた本作は、派手さを抑えたクールで渋いメロディック・サウンドの名作であります。Webで検索してもほとんど無視されているバンドですが、このアルバムの完成度は想像以上に高く、長年にわたって心に残り続ける力を持っています。個人的には、メロディック界の大御所的ポジションにいてもおかしくない存在だと密かに思っております。1曲目の"On
The Inside"は、イントロの時点でもう掴まれてしまいますし、4曲目の"Dark
Days"は、あまりにも切なくて、胸の深部にまで響く名曲です。そして、1994年にCDとして再発された際に、大阪の名店TIME
BOMB
RECORDSで猛烈にプッシュされていたのも懐かしい記憶。ちなみに、後にリリースされた1993年のアルバム"NEON"から入るのは、できれば避けた方がよろしいかと…。「DOLL
メロディック狂必聴ディスクUS編」紹介ディスク。
DAG
NASTYがお好きな方にはぜひおすすめしたい、SHADES
APARTのセルフタイトル1stアルバム。メロディックの静かなる古典的名盤。1988年にWishingwell
Recordsからリリースされた本作は、派手さを抑えたクールで渋いメロディック・サウンドの名作であります。Webで検索してもほとんど無視されているバンドですが、このアルバムの完成度は想像以上に高く、長年にわたって心に残り続ける力を持っています。個人的には、メロディック界の大御所的ポジションにいてもおかしくない存在だと密かに思っております。1曲目の"On
The Inside"は、イントロの時点でもう掴まれてしまいますし、4曲目の"Dark
Days"は、あまりにも切なくて、胸の深部にまで響く名曲です。そして、1994年にCDとして再発された際に、大阪の名店TIME
BOMB
RECORDSで猛烈にプッシュされていたのも懐かしい記憶。ちなみに、後にリリースされた1993年のアルバム"NEON"から入るのは、できれば避けた方がよろしいかと…。「DOLL
メロディック狂必聴ディスクUS編」紹介ディスク。
SCARPER! "EVERY TURN"
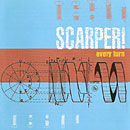 SCARPER!によるこの作品を紹介するかどうか、実はずいぶん長い間迷っておりました。でも結局、世間で人気のLATTERMAN系より、こちらの方が断然好きなんだから仕方ないと、自分の中で吹っ切れて、こうしてご紹介させていただく次第です。2000年にBoss
TuneageからリリースされたUKメロディックバンドによる1stアルバム。ホーンを取り入れたサウンドが特徴的なのですが、いわゆるスカパンク的な軽さではなく、どこか物悲しさと哀愁が滲むメロディック・パンクであるところが最大の魅力です。1曲目の"Invitation
Elsewhere"から、その世界観はしっかりと伝わってきます。そしてアルバムのハイライトとも言えるのが、11曲目の"Eight
Million Ways To
Die"。聴いていると、なぜか胸の奥がじんわりと熱くなり、私の場合は少年時代に観たテレビの金曜ロードショーのテーマ曲がふと頭をよぎるほどの、懐かしさに包まれます。決して完璧なアルバムとは言えませんが、いつもと少し違うテイストのバンドを求めている方に、ぜひ一度手に取っていただきたい一枚となっております。
SCARPER!によるこの作品を紹介するかどうか、実はずいぶん長い間迷っておりました。でも結局、世間で人気のLATTERMAN系より、こちらの方が断然好きなんだから仕方ないと、自分の中で吹っ切れて、こうしてご紹介させていただく次第です。2000年にBoss
TuneageからリリースされたUKメロディックバンドによる1stアルバム。ホーンを取り入れたサウンドが特徴的なのですが、いわゆるスカパンク的な軽さではなく、どこか物悲しさと哀愁が滲むメロディック・パンクであるところが最大の魅力です。1曲目の"Invitation
Elsewhere"から、その世界観はしっかりと伝わってきます。そしてアルバムのハイライトとも言えるのが、11曲目の"Eight
Million Ways To
Die"。聴いていると、なぜか胸の奥がじんわりと熱くなり、私の場合は少年時代に観たテレビの金曜ロードショーのテーマ曲がふと頭をよぎるほどの、懐かしさに包まれます。決して完璧なアルバムとは言えませんが、いつもと少し違うテイストのバンドを求めている方に、ぜひ一度手に取っていただきたい一枚となっております。
【MY BEST 261〜280に進む】
【MY BEST 221〜240に戻る】
【FIFTEENとLEATHERFACEが好きだ!に戻る】
【姉妹ページ海外旅行記 小市民の気弱な旅へ】