65 FILM SHOW "BREATHING WILL BE ASSISTED"
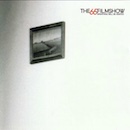 バージニア産の65 FILM
SHOWによる2000年作の唯一のアルバム。Waterslideさんのレビューに惹かれてCDを購入したものの、なぜか既に同じCDを持っていたという思い入れのある(?)作品。ジャンル的にはエモに一歩踏み入れているかも知れませんが、難しさや重たさはなく、耳馴染みがよいので私自身としてはメロディックパンクな作品扱いとしております。言ってみれば、GARDEN
VARIETYなぐらいの聴きやすさであります。2曲目"When The Canvas Turns
Black"など、スケール豊かなメロディが盛り込まれていてどれも水準以上の良い曲を揃えておりますが、水準をぶっ飛ばした極上曲を1曲だけでも入れられなかったのが、世間的に地味な扱いとなってしまっている結果なのかもしれません。ちなみにSCARIESやALLI
WITH AN IをリリースしていたLaw Of Inertiaからです。
バージニア産の65 FILM
SHOWによる2000年作の唯一のアルバム。Waterslideさんのレビューに惹かれてCDを購入したものの、なぜか既に同じCDを持っていたという思い入れのある(?)作品。ジャンル的にはエモに一歩踏み入れているかも知れませんが、難しさや重たさはなく、耳馴染みがよいので私自身としてはメロディックパンクな作品扱いとしております。言ってみれば、GARDEN
VARIETYなぐらいの聴きやすさであります。2曲目"When The Canvas Turns
Black"など、スケール豊かなメロディが盛り込まれていてどれも水準以上の良い曲を揃えておりますが、水準をぶっ飛ばした極上曲を1曲だけでも入れられなかったのが、世間的に地味な扱いとなってしまっている結果なのかもしれません。ちなみにSCARIESやALLI
WITH AN IをリリースしていたLaw Of Inertiaからです。
HAKAN "HAKAN MANIFESTO"
 イタリア産のパワーポップ・パンクバンド、HAKANによる4thアルバム。1960〜70年代のポップスやロックの香りが漂うメロディーに、ガレージな音作りが絶妙に融合しています。「ガレージ」と聞くと敬遠される方もいらっしゃるかもしれませんが、ここではあくまでスパイスのような役割を果たしており、作品全体の魅力を引き立てております。一度耳を傾けていただければ、その良さが伝わるのではないでしょうか。
気のせいかもしれませんが、ふとした瞬間にDavid
Bowieのような雰囲気が脳裏をよぎりました。どの曲もアップビートで心地よく、ツボを押さえた展開が続きます。特に10曲目"Jas
Is Moving To Town"ではBUZZCOCKSを思わせる展開もあり、終始、飽きのこない構成となっております。
過去の作品もいくつか聴いてみましたが、個人的にはどうもフィットせずこの4thが最も心に響きました。哀愁がにじむメロディーラインがとても印象的で、他のアルバムとは一線を画す完成度を感じます。2022年リリース。
イタリア産のパワーポップ・パンクバンド、HAKANによる4thアルバム。1960〜70年代のポップスやロックの香りが漂うメロディーに、ガレージな音作りが絶妙に融合しています。「ガレージ」と聞くと敬遠される方もいらっしゃるかもしれませんが、ここではあくまでスパイスのような役割を果たしており、作品全体の魅力を引き立てております。一度耳を傾けていただければ、その良さが伝わるのではないでしょうか。
気のせいかもしれませんが、ふとした瞬間にDavid
Bowieのような雰囲気が脳裏をよぎりました。どの曲もアップビートで心地よく、ツボを押さえた展開が続きます。特に10曲目"Jas
Is Moving To Town"ではBUZZCOCKSを思わせる展開もあり、終始、飽きのこない構成となっております。
過去の作品もいくつか聴いてみましたが、個人的にはどうもフィットせずこの4thが最も心に響きました。哀愁がにじむメロディーラインがとても印象的で、他のアルバムとは一線を画す完成度を感じます。2022年リリース。
FRIDAY STAR "DEFENCELESS"
 FRIDAY
STARによる唯一のアルバム"DEFENCELESS"は曲の美しさという点では、STARMARKETを思い起こさせるほどの逸品だと思います。どこか歌いまわしにも通じるものがあり、ふと似た空気を感じてしまいます。また、イタリア産ということもあってか、MILES
APART(EVERSOR)の影響も受けているのではないかと想像してしまいます。ただ、彼らと比較すると、より親しみやすくメジャー感のある音作りが印象的です。惜しいのは、ボーナストラックの2曲を除いても11曲で46分という長さで後半までこちら側が辛抱できなくなってくること。もし10曲で35分ほどにまとめていたら、さらに高い評価につながったのではないかと感じます。作り手としてはおそらく出てきたアイデアをアルバムに詰め込みたいという衝動を抑えられなかったのかもしれませんが…。とはいえ、メロディーの素晴らしさは揺るぎませんし、全体としてはしっかりと“良盤”と呼べる作品です。2003年作で、日本盤もリリースされているようです。
FRIDAY
STARによる唯一のアルバム"DEFENCELESS"は曲の美しさという点では、STARMARKETを思い起こさせるほどの逸品だと思います。どこか歌いまわしにも通じるものがあり、ふと似た空気を感じてしまいます。また、イタリア産ということもあってか、MILES
APART(EVERSOR)の影響も受けているのではないかと想像してしまいます。ただ、彼らと比較すると、より親しみやすくメジャー感のある音作りが印象的です。惜しいのは、ボーナストラックの2曲を除いても11曲で46分という長さで後半までこちら側が辛抱できなくなってくること。もし10曲で35分ほどにまとめていたら、さらに高い評価につながったのではないかと感じます。作り手としてはおそらく出てきたアイデアをアルバムに詰め込みたいという衝動を抑えられなかったのかもしれませんが…。とはいえ、メロディーの素晴らしさは揺るぎませんし、全体としてはしっかりと“良盤”と呼べる作品です。2003年作で、日本盤もリリースされているようです。
BACK TO NORMAL "MONEY & HEALTH"
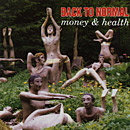 BACK TO
NORMALによる、唯一のオリジナル・アルバムとなる本作は、1995年にフィンランドでひっそりとリリースされました。まず目に飛び込んでくるのが、思わず「どうしてこうなった…」と首をかしげてしまうジャケットのセンス。この作品が生まれたのは、ちょうどRANDYやNO
FUN AT
ALLといったスウェーデン勢が勢いに乗っていた1990年代中期。隣国フィンランドで生み落とされたこのアルバムには、スウェーデン勢とはまたひと味違う、少し素朴で、少し泥臭い、でもそれがたまらなく魅力的なメロディック・パンクのエッセンスが詰まっています。彼らによると影響を受けたのはALLやSNUFF、初期BAD
RELIGIONとのことですが、やはりどこか北欧らしさが加わっており、全体的に地味ながらも、胸にじわじわと染み込んでくる不思議な魅力があります。特に2曲目の"Remember"は、適度なスピード感に加えてキャッチーで切ないメロディ展開が光る名曲です。
BACK TO
NORMALによる、唯一のオリジナル・アルバムとなる本作は、1995年にフィンランドでひっそりとリリースされました。まず目に飛び込んでくるのが、思わず「どうしてこうなった…」と首をかしげてしまうジャケットのセンス。この作品が生まれたのは、ちょうどRANDYやNO
FUN AT
ALLといったスウェーデン勢が勢いに乗っていた1990年代中期。隣国フィンランドで生み落とされたこのアルバムには、スウェーデン勢とはまたひと味違う、少し素朴で、少し泥臭い、でもそれがたまらなく魅力的なメロディック・パンクのエッセンスが詰まっています。彼らによると影響を受けたのはALLやSNUFF、初期BAD
RELIGIONとのことですが、やはりどこか北欧らしさが加わっており、全体的に地味ながらも、胸にじわじわと染み込んでくる不思議な魅力があります。特に2曲目の"Remember"は、適度なスピード感に加えてキャッチーで切ないメロディ展開が光る名曲です。
THE GLORY HOLES "THE GLORY HOLES"
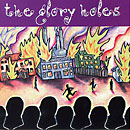 うわー、吃驚しました。このTHE GLORY
HOLES、海外も含めて検索しても引っかかってこない。完全に無視されております(EMPTYから出ている同名バンドもあるみたいです)。グーグル検索で引っかかるのは大人のおもちゃばっかしだし。こういったことを避けるためにもバンド名と同じタイトルのアルバムは出さない方がよいかと...。カリフォルニア産で1994年にLethal
Recordsからリリースされたということぐらいで何も書けない。確かに派手さがないけど、メロディックでかなりいい曲書いています。レーベルメイトにONE
HIT WONDERやFIELD
DAYなんかがいて音の傾向はそれなりに似ている気がしますがアルバムの完成度はこちらが上。そんなに捨て曲ないと思うんだけどなー。中古で数百円で売られていたら、是非とも買ってやってください。4曲目"Circus
Sideshow"や8曲目"Roseland"なんかは、感傷的で涙うるうるの大名曲だと思います。
うわー、吃驚しました。このTHE GLORY
HOLES、海外も含めて検索しても引っかかってこない。完全に無視されております(EMPTYから出ている同名バンドもあるみたいです)。グーグル検索で引っかかるのは大人のおもちゃばっかしだし。こういったことを避けるためにもバンド名と同じタイトルのアルバムは出さない方がよいかと...。カリフォルニア産で1994年にLethal
Recordsからリリースされたということぐらいで何も書けない。確かに派手さがないけど、メロディックでかなりいい曲書いています。レーベルメイトにONE
HIT WONDERやFIELD
DAYなんかがいて音の傾向はそれなりに似ている気がしますがアルバムの完成度はこちらが上。そんなに捨て曲ないと思うんだけどなー。中古で数百円で売られていたら、是非とも買ってやってください。4曲目"Circus
Sideshow"や8曲目"Roseland"なんかは、感傷的で涙うるうるの大名曲だと思います。
DEAD MECHANICAL "MEDIUM NOISE"
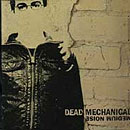 ボルティモア産のDEAD
MECHANICALによるこの1stアルバムは、2007年にリリースされた熱量高めのメロディック・パンク作品。本作では、個人的にも大好きなCHARLIE
BROWN GETS A VALENTINEのフロントマンLucas
Carscaddenがボーカル&ギターを担当しています。前述のバンドに見られるような甘さや叙情性よりも、本作ではざらついた質感とだみ声のボーカルが支配的。荒削りで直球勝負のサウンドながら、まるでスピードを増したJAWBREAKERのような熱さと不器用さが同居していて、聴いていて心が揺さぶられます。特に印象的なのが3曲目"Messy
Apartment"で、ブチキレ寸前のエネルギーが噴き出しており、めちゃくちゃ格好良いです。また、トランペットを交えたアコースティック・ナンバーや、ドラムがボーカルを務める曲(これがまた染みる…)など、バリエーションも豊かで、アルバム全体を通して飽きさせない構成となっております。ちなみに2nd"ADDICT
RHYTHMS"もクオリティー落ちてませんよ。
ボルティモア産のDEAD
MECHANICALによるこの1stアルバムは、2007年にリリースされた熱量高めのメロディック・パンク作品。本作では、個人的にも大好きなCHARLIE
BROWN GETS A VALENTINEのフロントマンLucas
Carscaddenがボーカル&ギターを担当しています。前述のバンドに見られるような甘さや叙情性よりも、本作ではざらついた質感とだみ声のボーカルが支配的。荒削りで直球勝負のサウンドながら、まるでスピードを増したJAWBREAKERのような熱さと不器用さが同居していて、聴いていて心が揺さぶられます。特に印象的なのが3曲目"Messy
Apartment"で、ブチキレ寸前のエネルギーが噴き出しており、めちゃくちゃ格好良いです。また、トランペットを交えたアコースティック・ナンバーや、ドラムがボーカルを務める曲(これがまた染みる…)など、バリエーションも豊かで、アルバム全体を通して飽きさせない構成となっております。ちなみに2nd"ADDICT
RHYTHMS"もクオリティー落ちてませんよ。
MUCH THE SAME "QUITTERS NEVER WIN"
 シカゴ産のバンド、MUCH THE SAMEによる1stアルバムは、2003年にA-F
Recordsからリリースされた高速なメロディック・パンクの名盤。ジャンル的には、いわゆる「高速メロコア」に分類されると思いますが、その中でも本作は哀愁とシリアスな感情の温度がしっかりと伝わってくる、非常に心に残る一枚となっています。私はこのジャンルにはどちらかというと深く入り込めずにいたのですが、そんな中でもこの作品には自然と引き込まれてしまいました。NO
USE FOR A
NAMEに加速装置をつけたような音ですが、個人的に、このジャンルでありがちな「全部同じに聞こえる」問題を、メロディーに感情の起伏を乗せて各曲にそれぞれの色を持たせることによって見事に回避してくれています。なお、オリジナルはCDオンリーのリリースでしたが、2020年に待望のアナログ盤が再発されています。
シカゴ産のバンド、MUCH THE SAMEによる1stアルバムは、2003年にA-F
Recordsからリリースされた高速なメロディック・パンクの名盤。ジャンル的には、いわゆる「高速メロコア」に分類されると思いますが、その中でも本作は哀愁とシリアスな感情の温度がしっかりと伝わってくる、非常に心に残る一枚となっています。私はこのジャンルにはどちらかというと深く入り込めずにいたのですが、そんな中でもこの作品には自然と引き込まれてしまいました。NO
USE FOR A
NAMEに加速装置をつけたような音ですが、個人的に、このジャンルでありがちな「全部同じに聞こえる」問題を、メロディーに感情の起伏を乗せて各曲にそれぞれの色を持たせることによって見事に回避してくれています。なお、オリジナルはCDオンリーのリリースでしたが、2020年に待望のアナログ盤が再発されています。
PAINTED THIN "STILL THEY DIE OF HEARTBREAK"
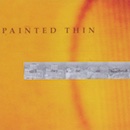 カナダ・ウィニペグ産のPAINTED THINによる1997年にEndearing
Recordsからリリースされた2ndアルバム(全7曲入りなのでミニアルバムと言っていいのかも)。音の印象としては、UKメロディックの繊細さに、同郷ウィニペグのBONADUCESやSCARIESあたりの青くて切ない空気感を掛け合わせたような、哀愁エモーショナルなポップパンクといった趣きです。少し頼りないながらも胸を打つハイトーンボーカルが、心に静かに刺さってきます。1st"Small
Acts of Love and
Rebellion"よりも、メロディと構成の完成度が明らかに高いです。特にハイライトとなる5曲目、The
WeakerthansのJohn K. Samsonによる名曲"Story You Have Heard
Before"は、静かに、けれど確実に胸を締めつける感動の一曲。淡々とした演奏と語りかけるような歌声が、言いようのない寂しさと優しさを残してくれます。わたしゃこの曲で泣けますよ。ちなみに解散後、メンバーはそれぞれThe
WeakerthansやSixty Storiesといったバンドへと歩みを進めることになります。
カナダ・ウィニペグ産のPAINTED THINによる1997年にEndearing
Recordsからリリースされた2ndアルバム(全7曲入りなのでミニアルバムと言っていいのかも)。音の印象としては、UKメロディックの繊細さに、同郷ウィニペグのBONADUCESやSCARIESあたりの青くて切ない空気感を掛け合わせたような、哀愁エモーショナルなポップパンクといった趣きです。少し頼りないながらも胸を打つハイトーンボーカルが、心に静かに刺さってきます。1st"Small
Acts of Love and
Rebellion"よりも、メロディと構成の完成度が明らかに高いです。特にハイライトとなる5曲目、The
WeakerthansのJohn K. Samsonによる名曲"Story You Have Heard
Before"は、静かに、けれど確実に胸を締めつける感動の一曲。淡々とした演奏と語りかけるような歌声が、言いようのない寂しさと優しさを残してくれます。わたしゃこの曲で泣けますよ。ちなみに解散後、メンバーはそれぞれThe
WeakerthansやSixty Storiesといったバンドへと歩みを進めることになります。
LOCAL BOYS "WHATTHECLOCKMAN"
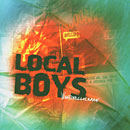 LOCAL BOYSによる2005年リリースの1stアルバム。スウェーデンのAurora
Musicからリリースされた本作は、まさにパンクとパワーポップの中間をゆく甘美な傑作。繊細で胸を打つメロディと、まるでハチミツのようにとろける甘いボーカルが印象的。特にタイトルでもある"Local
Boys"などのキラーチューンでは、磨き抜かれたメロディワークが炸裂しており、聴き惚れてしまいます。この「甘さ」が最大の魅力であると同時に、人によっては「くどい」と感じる可能性もあるかもしれません。けれど、心がすり減るような毎日の中で、少しの優しさや甘さを求めてしまうとき、この作品はその気持ちをすっと包んでくれるような存在になってくれるはずです。ガチガチのハードコアや激情系ばかり聴いていると、ふと息が詰まりそうになる瞬間があります。そんな時に、このスウェーデン産の糖分たっぷりなメロディは、心にしみる栄養補給になってくれるのではないでしょうか。
LOCAL BOYSによる2005年リリースの1stアルバム。スウェーデンのAurora
Musicからリリースされた本作は、まさにパンクとパワーポップの中間をゆく甘美な傑作。繊細で胸を打つメロディと、まるでハチミツのようにとろける甘いボーカルが印象的。特にタイトルでもある"Local
Boys"などのキラーチューンでは、磨き抜かれたメロディワークが炸裂しており、聴き惚れてしまいます。この「甘さ」が最大の魅力であると同時に、人によっては「くどい」と感じる可能性もあるかもしれません。けれど、心がすり減るような毎日の中で、少しの優しさや甘さを求めてしまうとき、この作品はその気持ちをすっと包んでくれるような存在になってくれるはずです。ガチガチのハードコアや激情系ばかり聴いていると、ふと息が詰まりそうになる瞬間があります。そんな時に、このスウェーデン産の糖分たっぷりなメロディは、心にしみる栄養補給になってくれるのではないでしょうか。
THE ARRIVALS "GOODBYE NEW WORLD"
 シカゴ産のバンド、THE ARRIVALSが2000年にThick
Recordsからリリースした1stアルバム。オリジナルはCDのみ。Webサイトなどでは、地元シカゴの先輩格であるPEGBOYの影響を受けているとされていますが、実際に耳を傾けてみると、DILLINGER
FOURのような渋みを帯びたメロディック・パンクや、どこかOiパンクの哀愁を帯びたスピリットまでも感じ取ることができます。タフで直情的なのに、どこかほろ苦さがある音は、一筋縄ではいかない奥深さがあります。特にアルバム前半の完成度は圧巻で、3曲目"Bottle
Song"から4曲目"Last Lullaby"、5曲目"Chinese New
Year"への流れは、まさに胸が熱くなるような展開。熱量と悲哀が絶妙に交差する展開の連続に、思わず心を持っていかれてしまいます。正直、このまま最後まで突っ走ってくれていたら、自分の中ではBest
20入り確実だったのにと思うぐらい、後半のトーンダウンがなんとも惜しく感じてしまいます。
シカゴ産のバンド、THE ARRIVALSが2000年にThick
Recordsからリリースした1stアルバム。オリジナルはCDのみ。Webサイトなどでは、地元シカゴの先輩格であるPEGBOYの影響を受けているとされていますが、実際に耳を傾けてみると、DILLINGER
FOURのような渋みを帯びたメロディック・パンクや、どこかOiパンクの哀愁を帯びたスピリットまでも感じ取ることができます。タフで直情的なのに、どこかほろ苦さがある音は、一筋縄ではいかない奥深さがあります。特にアルバム前半の完成度は圧巻で、3曲目"Bottle
Song"から4曲目"Last Lullaby"、5曲目"Chinese New
Year"への流れは、まさに胸が熱くなるような展開。熱量と悲哀が絶妙に交差する展開の連続に、思わず心を持っていかれてしまいます。正直、このまま最後まで突っ走ってくれていたら、自分の中ではBest
20入り確実だったのにと思うぐらい、後半のトーンダウンがなんとも惜しく感じてしまいます。
EVERREADY "FAIR PLAY"
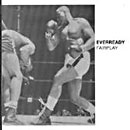 EVERREADYのこの1stアルバム、とっても久しぶりに聴いたんですが、なぜか結構はまりました。珠玉の1曲があるわけではありませんが、平均点以上の曲が散りばめられて流れが心地よく、こんなに良かったかなーという印象を受けちゃいました。音域の幅がなさそうなボーカルに味があります。楽曲自体はJON
COUGAR CONCENTRATION
CAMPをもっとキャッチーにポップにした感じで、侮れなくて、"Change"や"Fairplay"など良い曲を書いています。Discogs情報を見ると1992年録音で最初はカセットテープのみリリースで1996年にCDがLiquid
Meatからリリースされています。やはり昔っぽいチープな作りですが、内容自体は悪く無いです。完全無視されているようなので、ちょっとひねくれた人はどうぞお試しください。なお、LPはジャケットのデザインが異なります(かなりヒドい。なぜCDと同じにしなかったのだろう)。
EVERREADYのこの1stアルバム、とっても久しぶりに聴いたんですが、なぜか結構はまりました。珠玉の1曲があるわけではありませんが、平均点以上の曲が散りばめられて流れが心地よく、こんなに良かったかなーという印象を受けちゃいました。音域の幅がなさそうなボーカルに味があります。楽曲自体はJON
COUGAR CONCENTRATION
CAMPをもっとキャッチーにポップにした感じで、侮れなくて、"Change"や"Fairplay"など良い曲を書いています。Discogs情報を見ると1992年録音で最初はカセットテープのみリリースで1996年にCDがLiquid
Meatからリリースされています。やはり昔っぽいチープな作りですが、内容自体は悪く無いです。完全無視されているようなので、ちょっとひねくれた人はどうぞお試しください。なお、LPはジャケットのデザインが異なります(かなりヒドい。なぜCDと同じにしなかったのだろう)。
SCREECHING WEASEL "MY BRAIN HURTS"
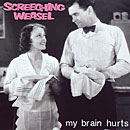 ラモーンなポップ・パンクの古典的傑作とされているシカゴ産のSCREECHING
WEASELによる3rdアルバム(1991年にLookout!
Recordsからリリース)。私はこれまた名作とされている4th"WIGGLE"よりも個人的にはポップ好きという視点からみると、こちらの3rdの方が好みであります。一気に流れるように最後の大名曲のタイトル曲まで辿りつきます。フロントマンBen
Weaselは、我が愛するCRIMPSHRINEに少し関わっているようで(ツアーで臨時的にベースやドラムをしているらしい)、またLOOKOUT!のCRIMPSHIRINEのページのバイオグラフィーをBENが書いており、「イーストベイの魂で最高のバンド」と賛辞をおくっております。これだけでも最高!
で、このアルバム、なぜ再発のジャケットでは気色悪い擬人的な昆虫ジャケットになったのか?大人の事情か?
ラモーンなポップ・パンクの古典的傑作とされているシカゴ産のSCREECHING
WEASELによる3rdアルバム(1991年にLookout!
Recordsからリリース)。私はこれまた名作とされている4th"WIGGLE"よりも個人的にはポップ好きという視点からみると、こちらの3rdの方が好みであります。一気に流れるように最後の大名曲のタイトル曲まで辿りつきます。フロントマンBen
Weaselは、我が愛するCRIMPSHRINEに少し関わっているようで(ツアーで臨時的にベースやドラムをしているらしい)、またLOOKOUT!のCRIMPSHIRINEのページのバイオグラフィーをBENが書いており、「イーストベイの魂で最高のバンド」と賛辞をおくっております。これだけでも最高!
で、このアルバム、なぜ再発のジャケットでは気色悪い擬人的な昆虫ジャケットになったのか?大人の事情か?
CHINESE TELEPHONES "CHINESE TELEPHONES"
 ミルウォーキー産のバンド、CHINESE TELEPHONESによる唯一のフルアルバム。2007年にIt’s Alive
Recordsからリリースされた本作は、まさに一瞬の閃光のように現れては消えてしまった存在です。決して一本調子にはならず、随所にポップでエモーショナルなメロディが顔をのぞかせてくれる、そのちらっと泣かせるフレーズに触れた瞬間、心の奥で何かがふっと緩むような感覚が出てきます。QUEERSやTEENAGE
BOTTLEROCKETといったポップ・パンク好きはもちろん、DILLINGER FOURやOFF WITH THEIR
HEADSのような渋めのメロディック・パンク愛好家にまで刺さるこの許容力の広さも特筆すべきポイントだと思います。そして忘れてはならないのが、壁に掲げたくなるジャケットのセンスの良さ。LPで持ってこそ真価が発揮されるようなアルバムではないでしょうか。
ミルウォーキー産のバンド、CHINESE TELEPHONESによる唯一のフルアルバム。2007年にIt’s Alive
Recordsからリリースされた本作は、まさに一瞬の閃光のように現れては消えてしまった存在です。決して一本調子にはならず、随所にポップでエモーショナルなメロディが顔をのぞかせてくれる、そのちらっと泣かせるフレーズに触れた瞬間、心の奥で何かがふっと緩むような感覚が出てきます。QUEERSやTEENAGE
BOTTLEROCKETといったポップ・パンク好きはもちろん、DILLINGER FOURやOFF WITH THEIR
HEADSのような渋めのメロディック・パンク愛好家にまで刺さるこの許容力の広さも特筆すべきポイントだと思います。そして忘れてはならないのが、壁に掲げたくなるジャケットのセンスの良さ。LPで持ってこそ真価が発揮されるようなアルバムではないでしょうか。
TURTLEHEAD "BACK SLAPPING PRAISE FROM BACK STABBING MEN"
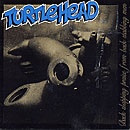 1996年にリリースされたTURTLEHEADによる1stアルバム。長らくアメリカのバンドだと勘違いしておりましたが、実はスコットランド産でした。作品はスウェーデンの名門Bad
Taste
Recordsからリリースされており、そのせいかサウンドにはUKメロディックの雰囲気に加え、スウェーデンっぽい流麗なメロディラインとスピード感がなんとなく溶け込んでいます。特に曲の構成は練り込まれており、キャッチーでありながらも、聴き進めるごとにじわじわとクセになるような仕掛けが感じられます。今の耳で聴くと音作りには少し時代を感じる部分もあるかもしれませんが、9曲目の"Home"などに代表されるように、しっかりと胸を打つメロディが宿っていて、忘れがたい魅力を放っています。中古屋でひっそりと激安で並んでいるような存在かもしれませんが、見つけた時は心の中でガッツポーズを決めて購入してほしい一枚です。バンド名だけでスルーしてしまうには、あまりにも惜しい作品です。
1996年にリリースされたTURTLEHEADによる1stアルバム。長らくアメリカのバンドだと勘違いしておりましたが、実はスコットランド産でした。作品はスウェーデンの名門Bad
Taste
Recordsからリリースされており、そのせいかサウンドにはUKメロディックの雰囲気に加え、スウェーデンっぽい流麗なメロディラインとスピード感がなんとなく溶け込んでいます。特に曲の構成は練り込まれており、キャッチーでありながらも、聴き進めるごとにじわじわとクセになるような仕掛けが感じられます。今の耳で聴くと音作りには少し時代を感じる部分もあるかもしれませんが、9曲目の"Home"などに代表されるように、しっかりと胸を打つメロディが宿っていて、忘れがたい魅力を放っています。中古屋でひっそりと激安で並んでいるような存在かもしれませんが、見つけた時は心の中でガッツポーズを決めて購入してほしい一枚です。バンド名だけでスルーしてしまうには、あまりにも惜しい作品です。
ANTI-FLAG "THE TERROR STATE"
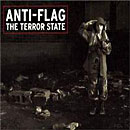 2003年にFat Wreck
Chordsからリリースされた、ピッツバーグ産のANTI-FLAGによる通算5枚目のアルバム。世に溢れるメロコアな作品の中にあっても、単にキャッチーで速いだけではない、緊迫感と重みを湛えた音が、聴き手の胸にじわりと突き刺さるのです。ふとした瞬間に垣間見える社会への怒りや不条理に対する痛烈な視線が、このバンドの芯の部分をしっかりと支えています。特に7曲目"You
Can Kill The Protester, But You Can’t Kill The
Protest"は、タイトルからして強烈ですが、そのメッセージ性の高さと、メロディの熱量が見事に同居した名曲です。音の質感としては、DILLINGER
FOURを少しポップ寄りにしたような感触とも言えるでしょうか。曲ごとのフックも効いていて、全体を通して飽きさせない構成もまた秀逸です。正直なところ、後にボーカルに残念な話題がありましたが、それを差し引いても、この作品に込められたエネルギーと誠実さは揺るぎないと思います。
2003年にFat Wreck
Chordsからリリースされた、ピッツバーグ産のANTI-FLAGによる通算5枚目のアルバム。世に溢れるメロコアな作品の中にあっても、単にキャッチーで速いだけではない、緊迫感と重みを湛えた音が、聴き手の胸にじわりと突き刺さるのです。ふとした瞬間に垣間見える社会への怒りや不条理に対する痛烈な視線が、このバンドの芯の部分をしっかりと支えています。特に7曲目"You
Can Kill The Protester, But You Can’t Kill The
Protest"は、タイトルからして強烈ですが、そのメッセージ性の高さと、メロディの熱量が見事に同居した名曲です。音の質感としては、DILLINGER
FOURを少しポップ寄りにしたような感触とも言えるでしょうか。曲ごとのフックも効いていて、全体を通して飽きさせない構成もまた秀逸です。正直なところ、後にボーカルに残念な話題がありましたが、それを差し引いても、この作品に込められたエネルギーと誠実さは揺るぎないと思います。
CARBONA "TAITO NÃO ENGOLE FICHAS"
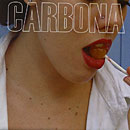 2003年にリリースされた、ブラジル発のラモーン・パンクバンドCARBONAによる6thアルバム。その音は想像通り、SCREECHING
WEASELを彷彿とさせるようなストレートで軽快なポップパンク。「だったらSCREECHING
WEASELを聴けばいいじゃないか」という声もあるかもしれませんが、このバンドならではの魅力は、やはりポルトガル語の響きにあると思います。特に"Meu
Primeiro
All-star"をはじめとする曲では、シンプルな構成の中に不意に胸が締めつけられる瞬間があります。ラモーンパンク特有のマシンガンのような勢いのなかで、それがふと顔を覗かせるからこそ、よりいっそう心に残ります。スペインの偉大なラモーンパンクバンドたちとも共鳴するような、南米らしい陽気さと哀愁のブレンド。もちろん、このジャンルに馴染みのない方には「どれも同じに聞こえる」という危険性はありますが、ぜひ一度体感してみてください。
2003年にリリースされた、ブラジル発のラモーン・パンクバンドCARBONAによる6thアルバム。その音は想像通り、SCREECHING
WEASELを彷彿とさせるようなストレートで軽快なポップパンク。「だったらSCREECHING
WEASELを聴けばいいじゃないか」という声もあるかもしれませんが、このバンドならではの魅力は、やはりポルトガル語の響きにあると思います。特に"Meu
Primeiro
All-star"をはじめとする曲では、シンプルな構成の中に不意に胸が締めつけられる瞬間があります。ラモーンパンク特有のマシンガンのような勢いのなかで、それがふと顔を覗かせるからこそ、よりいっそう心に残ります。スペインの偉大なラモーンパンクバンドたちとも共鳴するような、南米らしい陽気さと哀愁のブレンド。もちろん、このジャンルに馴染みのない方には「どれも同じに聞こえる」という危険性はありますが、ぜひ一度体感してみてください。
THE CONNIE DUNGS "ETERNAL BAD LUCK CHARM"
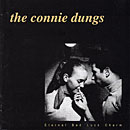 解散してしまったケンタッキー産のTHE CONNIE
DUNGSによる、2000年リリースの4thアルバム。このオリジナルのアルバムは、Mutant
PopからのCDのみのリリースで、バンドの成長が色濃く反映されています。初期作品では、SCREECHING
WEASELやBEATNIK
TERMITESに影響を受けたようなチープで元気なラモーン・ポップパンクを演奏していた彼らですが、特に4曲目"Fearful
Symmetry"などを聴くと、その変化が顕著でここではJAWBREAKERのようなエモーショナルで胸を打つメロディを取り入れようとした跡が感じられ、バンドが最後の力を振り絞って新しい方向性を模索していたことが伺えます。こうした中途半端にも見える試みが、実は唯一無二の個性を生んでいるところに魅力があるのかもしれません。アルバム全体に散りばめられた、可愛らしい声に隠された哀愁や繊細さが、より一層深みを与えています。
解散してしまったケンタッキー産のTHE CONNIE
DUNGSによる、2000年リリースの4thアルバム。このオリジナルのアルバムは、Mutant
PopからのCDのみのリリースで、バンドの成長が色濃く反映されています。初期作品では、SCREECHING
WEASELやBEATNIK
TERMITESに影響を受けたようなチープで元気なラモーン・ポップパンクを演奏していた彼らですが、特に4曲目"Fearful
Symmetry"などを聴くと、その変化が顕著でここではJAWBREAKERのようなエモーショナルで胸を打つメロディを取り入れようとした跡が感じられ、バンドが最後の力を振り絞って新しい方向性を模索していたことが伺えます。こうした中途半端にも見える試みが、実は唯一無二の個性を生んでいるところに魅力があるのかもしれません。アルバム全体に散りばめられた、可愛らしい声に隠された哀愁や繊細さが、より一層深みを与えています。
THE MEASURE(SA) "HISTORICAL FICTION"
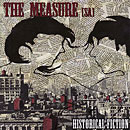 ニュージャージー産のTHE MEASURE(SA)による1stアルバム、2006年にTeam Science RecordsからCD、Don
Giovanni
RecordsからLPとしてリリースされています。アルバム全体に漂うラフでメロディックな音は、まさにアメリカンな感じがあります。DISCOUNTやFIFTH
HOUR
HEROといったバンドに感じる雰囲気にフォークっぽいエッセンスが取り入れられている感じ。各曲は、水準以上のクオリティで、しっかりとしたメロディラインが展開されており、曲ごとにメリハリが感じられ、巧みに作り上げられています。ただし、アルバムを通して聞いてみると、決定的に心をつかまれるような極上の1曲が見当たらないため、個人的にはBest200圏外という位置づけにしてしまいました。それでも、特に6曲目の"Autonomously"や12曲目の"It’s
Me Or The Marlboro
Man"なんかはとても胸に迫るとても良い曲なので、個人的には、全曲、女性ボーカルをメインにした方がより良かったのではと思っています。
ニュージャージー産のTHE MEASURE(SA)による1stアルバム、2006年にTeam Science RecordsからCD、Don
Giovanni
RecordsからLPとしてリリースされています。アルバム全体に漂うラフでメロディックな音は、まさにアメリカンな感じがあります。DISCOUNTやFIFTH
HOUR
HEROといったバンドに感じる雰囲気にフォークっぽいエッセンスが取り入れられている感じ。各曲は、水準以上のクオリティで、しっかりとしたメロディラインが展開されており、曲ごとにメリハリが感じられ、巧みに作り上げられています。ただし、アルバムを通して聞いてみると、決定的に心をつかまれるような極上の1曲が見当たらないため、個人的にはBest200圏外という位置づけにしてしまいました。それでも、特に6曲目の"Autonomously"や12曲目の"It’s
Me Or The Marlboro
Man"なんかはとても胸に迫るとても良い曲なので、個人的には、全曲、女性ボーカルをメインにした方がより良かったのではと思っています。
HDQ "SOUL FINDER"
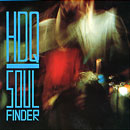 HDQは、Dickie HammondとAndrew
LaingがLEATHERFACEと掛け持ちで活動していたバンドで、本作品は1990年にFull
Circleからリリースされた4thアルバム。このアルバムは、当時DOLLで別宮さんによる絶賛レビューが記載されて、それをきっかけに手に取った思い出があります。再発されて、手に入りやすくなったこともあり、その素晴らしいサウンドに触れやすくなったことは喜ばしいことです。アルバムの1曲目、"Wise
Up"から感じ取れる音は、まさにUKメロディックパンクの中でもUSのDAG
NASTYからの影響を強く感じさせます。HDQは、UKメロディックの歴史においても非常に重要な位置を占めるバンドで、彼らの音楽は時を経ても色あせませんが、メロディックパンク学科に入学したい若いキッズたちは、まずDAG
NASTYという師匠筋のバンドをしっかりと予習しておくことをおすすめします。「DOLL
メロディック狂必聴ディスクUK&ヨーロッパ編」紹介ディスク。
HDQは、Dickie HammondとAndrew
LaingがLEATHERFACEと掛け持ちで活動していたバンドで、本作品は1990年にFull
Circleからリリースされた4thアルバム。このアルバムは、当時DOLLで別宮さんによる絶賛レビューが記載されて、それをきっかけに手に取った思い出があります。再発されて、手に入りやすくなったこともあり、その素晴らしいサウンドに触れやすくなったことは喜ばしいことです。アルバムの1曲目、"Wise
Up"から感じ取れる音は、まさにUKメロディックパンクの中でもUSのDAG
NASTYからの影響を強く感じさせます。HDQは、UKメロディックの歴史においても非常に重要な位置を占めるバンドで、彼らの音楽は時を経ても色あせませんが、メロディックパンク学科に入学したい若いキッズたちは、まずDAG
NASTYという師匠筋のバンドをしっかりと予習しておくことをおすすめします。「DOLL
メロディック狂必聴ディスクUK&ヨーロッパ編」紹介ディスク。
WALTER ELF "DIE ANGST DES TORMANNS BEIM ELFMETER "
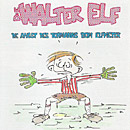 WALTER ELFは後にKICK JONESESとして知られるようになるバンドで、本作品は1988年にWe Bite
Recordsからリリースされた2ndアルバムです。KICK JONESESには名曲"If There Was A
God"がありますが、アルバム全体を通して聴き込むには少し疲れてしまうこともある中、個人的には、KICK
JONESESよりもこのWALTER
ELFの方が圧倒的にお気に入りです。このアルバムでは、ホーンセクションなどのアレンジが巧みに使われており、バラエティ豊かな展開が魅力的です。そのため、アルバム全体を通して飽きが来ることなく、一気に聴き進めることができます。もしこの音楽がUKバンドなら少し古臭さを感じるかもしれませんが、このWALTER
ELFは不思議とその古さを感じさせず、むしろ新鮮で力強い印象を受けます。ドイツのバンドらしい独特の感覚があり、NOISE
ANNOYSのファンならきっと楽しめるアルバムだと思います。
WALTER ELFは後にKICK JONESESとして知られるようになるバンドで、本作品は1988年にWe Bite
Recordsからリリースされた2ndアルバムです。KICK JONESESには名曲"If There Was A
God"がありますが、アルバム全体を通して聴き込むには少し疲れてしまうこともある中、個人的には、KICK
JONESESよりもこのWALTER
ELFの方が圧倒的にお気に入りです。このアルバムでは、ホーンセクションなどのアレンジが巧みに使われており、バラエティ豊かな展開が魅力的です。そのため、アルバム全体を通して飽きが来ることなく、一気に聴き進めることができます。もしこの音楽がUKバンドなら少し古臭さを感じるかもしれませんが、このWALTER
ELFは不思議とその古さを感じさせず、むしろ新鮮で力強い印象を受けます。ドイツのバンドらしい独特の感覚があり、NOISE
ANNOYSのファンならきっと楽しめるアルバムだと思います。
【 その他のMELODIC A-C に進む】
【 MY BEST 261〜280 に戻る】
【 FIFTEENとLEATHERFACEが好きだ! に戻る】
【姉妹ページ 海外旅行記 小市民の気弱な旅 へ】